

NHK講座第12回は「カメラマンの現場から」をテーマに、NHK放送技術局 制作技術センター番組制作技術部でロケデスクを務めておられる石原徹也さんを講師にお迎えした。入局後、ドキュメンタリー一筋でカメラマン人生を送ってきた石原さんだからこそわかる現場での立ち回り、そして、撮影から番組が構成されるまでを、生の声と動きで伝えてくださった。
石原さんは、現在は番組制作技術部のロケデスク(=番組企画の提案を受けて、主にロケーション等のマッチングを行う仕事)を務めているものの、それまでは現場一筋のカメラマンだった。大学時代は、カメラの“カ”の字も知らない学生生活を送っていたそうだ。石原さんは理系で、大学時代は研究に没頭していたものの、自分の研究には未来を見出すことができないと思いながら過ごしていたそうだ。そんな石原さんがNHKを志したきっかけは、いたって単純だった。マスコミ業界を志望する友人からマスコミに関する情報を色々とキャッチするなか、カメラマンならば色々なところに行けて、色々な人に会えるかなという漠然とした気持ちが生まれNHKを受験したそうだ。
入局後は放送技術局番組制作センターの撮影として主にVロケ(=ビデオロケーション)を担当した。この時もこれといった目標を持っていなかったと石原さんは言う。しかし、配属先の先輩にあたる服部康夫カメラマンが手がけた『ドキュメントにっぽん 心で闘う120秒』という、剣道を題材としたドキュメンタリーを見たときに、「自分はこの世界で勝負していこう」という感情を抱くようになったそうだ。
やがて、自分の憧れだった服部カメラマンから、ある番組の特集の仕事をもらうことになる。その番組が、『プロフェッショナル 仕事の流儀』(2008年1月2日放送)だった。しかも、取材対象者は、メジャーリーガーのイチロー選手。当時を振り返り、石原さんは、日本を代表する偉大な野球選手と時間を共に過ごすことに対して、喜びと同じくらいに恐怖を感じていたと語った。
そこから講義は、この番組の撮影に関することを中心に展開された。ドキュメンタリーは対象者の日常と非日常の両面をカメラに収める。これが、基本的に非日常しかカメラに収めないドキュメンタリー以外の番組との違いだ。今回の撮影は、スタッフ3名がイチロー選手に同行し、密着取材を敢行した。スタジアムでは、ディレクター・カメラマン・音声の3名がイチロー選手にすべての照準を合わせている。NHKでは通常、スポーツ中継には7名程度のスタッフが動員されている。その点を考えると、非常に少数で行われているのがドキュメンタリーだ。自宅では、2名のスタッフ(ディレクター・カメラマン)がイチロー選手とその家族に密着している。自宅では、ディレクターが音声スタッフの役割も兼務していたそうだ。自宅での撮影では、何を撮るかという打ち合わせは一切なかった。しかし、石原さんの中で、「今のイチローがあるのは、家族の支えがあるから」と仮定し、家庭での温かさを撮るということだけは決めていたという。
「カメラマンは指示を待ち、その通りに動くだけではだめなんです」と石原さんは言う。これには三つの理由がある。一つは、ディレクターが横で指示をしたら、ディレクターの声が入ってしまうからだ。二つ目は、ディレクターは横にはいるがカメラマンが今、何を撮影しているのか実際にはわからないからだ。そして、もう一つは、ドキュメンタリーの撮影ではいつ何が起こるかわからないからである。つまり、カメラマンは、常に自身の五感を最大限に活用し、総動員させなければならないのだ。そのような状況下では、ただ単に指示を待っているだけでは、作品のクオリティに影響を及ぼす可能性もあるということだ。「カメラマンは常に主体的である必要がある。主体的に撮っていかないといけない。そうでなければ、オペレーターと何も変わらない」と石原さんは強く語っていた。
この時、石原さんが自宅での撮影で狙っていたのは、「鈴木一朗」という、一人の男の家庭での温かさであった。それは、スタジアムでの阿修羅のような厳しい面持ちでいる「イチロー」とは対照的で、優しい面持ちの「鈴木一朗」である。この姿を垣間見ることのできる要素は三つあった。一つは、毎日必ず食べるという奥さんのカレー。二つ目は、愛犬の一弓(いっきゅう)。そして、最後は、それらが生み出す笑顔である。中でも、愛犬の一弓が撮影のキーポイントになると仮定していた石原さんは、一弓の動きを熱心に観察しながら、撮影に挑んでいたそうだ。
さらに石原さんは、カメラマンに大切な要素として、「被写体との心の距離を早い段階で縮めておくことも重要だ」と語る。実際に、この撮影においては、初めの1週間くらいはほとんどカメラも持たずに、毎日イチロー選手と一緒にご飯を食べたりとか、球場に行く車に乗らせてもらったりとかして、専門的な野球の話をしないということに努めたそうだ。全く素性の分からない人間に撮られることは、被写体にとって気分のいいものではない。自分を知ってもらい、単純に仲良くなる必要がある。そして、被写体のこと、主人公のことを心の底から撮りたいという真心をみせることが必要、と石原さんは言う。結果的に、70日間の密着取材になっただけではなく、イチロー選手サイドから一度も取材拒否がないという素晴らしい環境を形成することが出来たそうだ。
講義は、番組のクライマックスへと話が進む。取材を行ったシーズンは、「過去の自分を捨てて新しい感覚を得た」と語るイチロー選手が首位打者争いに挑んでいた。番組では、その姿が描かれている。石原さんは当時を振り返り、「撮影スタッフとしては、過去の自分を捨てて新しい感覚を得た、その果実が首位打者というタイトルであった、という流れがベストシナリオであると考えていた」と述べた。しかし、実際には、3試合を残して、打率は2位。9月29日のゲームに挑むイチローは、「このゲームで3本ヒットを打たなければ、闘いは終わる」と一言話し、スタジアムの中に入っていった。ここで、石原さんたちは、今日が最後の日だと定めた。石原さんは、「番組制作のスタッフとしてではなく、一人の人間として、ベストシナリオ以外は想像したくはなかった。どちらの側に立ったとしても首位打者を獲得してほしかった」と言う。しかし結果は、第四打席で凡退に終わり、このゲームでの三安打は絶望的となった。そして、イチローが守備に就いて、他の外野手とキャッチボールをしている際にボールを落とした。石原さんは、この何気ない動作を「70日の取材の中で唯一の違和感」と評した。そのあと、ゲーム中にイチローが眼に涙を浮かべる姿を何度もとらえる事ができた。石原さんは、「凡退に終わった時は、僕自身も番組はどうなるのかなと思ったりして、カメラを回すのをやめようかとも考えました。でも、スタジアム内においても、常に打席だけではなく、何気ない仕草まで細かく撮影していたからこそ、あのようなシーンをとらえることができた」と語る。
最後に石原さんは、ドキュメンタリー番組の考え方について話してくださった。「ドキュメンタリーは決して取材対象者を崇めるための作品ではない」と石原さんは強く述べる。崇めるだけでは、遠い存在になってしまい、誰からも共感はしてもらえない。むしろ、その人の等身大を描くことで、番組を観た人の人生に何かしらの影響を及ぼせる作品になればと思いながら作っている。そして、石原さんは、この取材を通じて、絶望した時こそが勝負だと気づかされたそうだ。「絶望が目の前に訪れた時に、そこで崩れるのではなく、もう一度立ち上がって自らを奮い立たせることが大事なのだと気づかされた」と受講生にメッセージを残してくれた。
1996年入局。以来16年間ドキュメンタリー撮影一筋で活躍してきたが、2011年6月に現場をいったん離れロケデスクに就任、現在に至る。代表作品はNHKスペシャル「原爆の絵~市民が残すヒロシマの記録~」(カナダ・バンフテレビ祭部門最優秀賞受賞)、プロフェッショナル「イチロースペシャル~知られざる闘いの記録~」など。
![]()
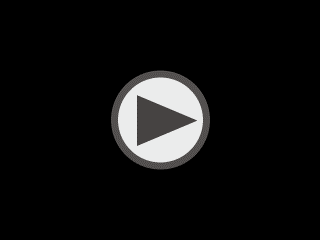


ドキュメンタリーの面白さは、人々のイメージと妄想で作られた虚像の被写体が、等身大の一人の人間として映し出されるところにあると思っている。その作品を制作する過程の中で、ドラマなどと違い、テクニックだけで通用するものではなく、1対1で対峙することで求められるコミュニケーションの大切さを強く感じることのできる講義であった。そして、このコミュニケーションは日常生活においても十分還元できる要素だ。ソーシャル化が進む今日の社会において、改めて、多様な側面から考えさせられる内容だった。
(山田裕規)

