- TOP>
- 図書館について>
- デジタル版展示『知識人の自己形成』>
- 第3部 中学校時代
第3部 中学校時代
旧制の中学校は1872(明治5)年の学制によって創設された中等教育機関。1881(明治14)年に男子の学校とされた。1886(明治19)年の中学校令によって5年制の尋常中学校となったが、1899(明治32)年に中学校に復した。その際、男子に必要な「高等普通教育」を授けることが目的とされた。旧制中学校の多くは戦後の学制改革によって新制高等学校となり、現在に至っている。
旧制の学校系統は、尋常小学校卒業後に初等後教育機関(高等小学校や実業補習学校などの青年学校系統)と中等教育機関に分岐する複線構造をとっていたが、中学校は中等教育機関の中でも高等教育機関に至る上でもっとも正統的なルートとして位置づけられており、学歴取得による社会的上昇を目ざす男子にとって第一の進学目標となった。進学熱の上昇を受けて旧制中学校の数と生徒数は大正期に急拡大し、1920(大正9)年に4万7千人あまりだった入学者数は、丸山眞男が進学する前年の1925(大正14)年には7万5千人弱となった。それでも同学年男子の10%ほどに過ぎない。1919(大正8)年には、中学校を4年間で修了して高等学校に進学できる「四修」という制度が導入されている。
丸山眞男と加藤周一が進学した東京府立第一中学校(通称「一中」)は1878(明治11)年に開学した東京府第一中学の後身にあたり、第一高等学校進学者を多く輩出した名門校。丸山在学中の1929(昭和4)年に東京市麹町区西日比谷町から麹町区永田町に移転した(1932年まで府立高等学校と同居)。1948(昭和23)年に新制の東京都立第一高等学校となり、1950(昭和25)年に東京都立日比谷高等学校に改称した。
第1章 非模範生 ─ 中学校時代の丸山眞男
(1)反抗

〈『東京府立第一中学校創立五十年史』1929年〉
丸山眞男は小学校時代の終わりに7年制の武蔵高等学校を受験するも不合格となり、1926(大正15)年4月、東京府立第一中学校に入学する。一中は軍人の子弟が多い四中などと比べると「リベラル」だったが、「典型的に生意気な都会っ子」「プラス優等生」気質で、丸山は自己嫌悪に陥った。また、一中には学校の方針に従順な優等生グループ、不良グループ、不良というほどではないが学校の方針に反感を持つ反正統派という三種類の学生たちがいた。丸山自身はこのうち反正統派にシンパシーを感じていたが、不良グループの生徒(楠原)とも親交があった。この点は兄鐵雄の影響もあったようである。
ぼくは、亡くなった兄貴に非常に感謝しているのです。もし兄貴なかりせば、ある意味でぼくは非常に平凡な、府立一中のあんまり秀才でもないけれども、模範生だったかもしれない。それが拗ねてしまって、一中に対しても反抗し、校風に対しても反抗した。兄貴の影響で、悪いことは全部兄貴に教わった。その悪いことは探偵小説をはじめとして、みんな人生にとって非常にプラスになっています。
『定本 丸山眞男回顧談』上
一中の同級生には神谷源兵衛、塙作楽(岩波書店編集者)、松本武四郎(医学者)、松浪信三郎(哲学研究者)、小田村寅二郎(右翼活動家、日本思想に関する編著がある)、林基(渡辺基、日本史学者)などがいた(肩書はいずれも後年のもの)。
塾をサボって映画館に通う生活は小学校時代と変わらなかったため、4年次のときの第一高等学校受験には失敗してしまう。伯父の井上亀六はわざわざやってきて、「落ちてよかった。秀才じゃないほうがいいんだ。秀才が日本を毒した」と慰めたという。合格組が抜けた5年次は落ちこぼれとして過ごしたが、反面、受験勉強からも解放されて自由な学校生活を満喫することができた。
(2)教師

一中での授業に興味をそそられるものは少なかったが、東恩納寛淳の東洋史は、暗記に終始したそれまでの授業と異なり、中国史を世界史との連関で教えられ、感銘を受けた。寛淳のリベラルな人柄にも惹かれている。
小学生のときに唱歌が得意だった丸山は、高名な作曲家でもあった一中教師・梁田
(3)読書・映画

(H・ブレノン監督、弁士徳川夢声)
一中在学中は読書の対象が児童文学から文学作品へと移っていった。入学時は『少年倶楽部』や佐藤紅緑の「あゝ玉杯に花うけて」(1927~28年)を愛読していたが、やがて『世界文学全集』などに触れはじめた。学生の必須読書であった夏目漱石などは『漱石全集』を中学校時代にあらかた読破してしまった。ほかの生徒と異なる点があるとすれば、兄の影響で読みはじめた『新青年』であろう。小酒井不木や江戸川乱歩の探偵小説を皮切りに、ポーやコナン・ドイルなど英米文学のおもしろさに目覚め、『アッシャー家の崩壊』『ザ・ブラック・キャット』『シャーロックホームズの冒険』を原文で読みはじめた。3年次(1928年)には『グリーン家殺人事件』の原書を買って徹夜で読むほどに傾倒した。しかし母に見つかり、『新青年』は没収されてしまった。
読書と並行して小学校時代から続いていたのが映画趣味である。一中の入学祝いに高級映画館の「武蔵野館」で鑑賞した『ボー・ジェスト』(H・ブレノン監督、弁士徳川夢声)は丸山に深い感銘を与えた。徳川夢声の名調子は、サイレント映画末期の弁士の中で異彩を放っていた。丸山は埴谷雄高との対談で次のように回想している。
サイレントの末期には、世界的にもドイツの表現派とか、凄いのがあったけども、あれがまた日本へはいってくると、徳川夢声なんていう天才がいてね。『カリガリ博士』などは、夢声の説明と離れてはぼくのなかにないんだね。……夢声がはじめて、シンクロナイゼイションといったらいいか、本当に画面と合ったリアルなセリフでしゃべるやり方をはじめた。……『ボー・ジェスト』は何回も映画化されたけど、ぼくは最初のサイレントのがいちばんいいと思うね。……いちばんはじめに、昔だから長い字幕が出るでしょ。それを夢声が淡々と訳してゆく、……「さりながら兄弟の間の愛情は星のごとく常に燦然たる光を放つのであります」。そこから話が始まるんだ。そういうのを、まだニキビも出ない中学一年生がきいてね、ああ男女間の愛は、なるほど月のごとく満ちる時もあり、欠ける時もあるんだなってことを、そこで教わるわけだね(笑)。
「文学と学問」
丸山は徳川夢声と「武蔵野館」について、「映画の「芸術性」をはじめて私に感得させた恩人であるだけでなく、「西洋音楽」に私を親しませてくれた点でも、日比谷野外大音楽堂における海軍軍楽隊の演奏と並ぶ魂の教師であった」と回想している。しかし、「武蔵野館」の入場料は高く、学生が頻繁に通えるような場所ではなかった。代わりに丸山が足しげく通ったのが「芝園館」である。
中学校時代、丸山は授業を「エスケープ」して「芝園館」に通いつめた。特にジャネット=ゲイナーにご執心だった。しかしあるとき、「芝園館」の半券が母に見つかり、塾をサボって映画館に通っているのがバレてしまい、「兄さんはもうしょうがないと思っている。あんただけは信用しとった」と萩の訛り交じりに叱られてしまった。
一方、映画に比べると戯曲に対する関心は薄かった。『日本戯曲全集』を耽読し、3年次の頃には同人誌に戯曲を書きもしたが、本格的に演劇を観はじめたのは大学時代のことだった。
映画をはじめとする文化は、時代の変化と無関係ではありえなかった。そして、満洲事変前の中学校時代にひととおり当時の文化に触れていたために、徐々に風向きが変わっていったその後の世の中を相対化して捉える視点を丸山はもつことができたのである。
中学生時代は、ちょうど宝塚と松竹少女歌劇と両方でレビューがはじまって、並んで一斉に足を上げるダンスとか、『モン・パリ』〔1927年初上演〕なんていう、一種のミュージカルが流行りだしたころでした。満州事変前の爛熟した、大正デモクラシーの続きじゃないですか。思想的にいうと高等学校に入ったときから反動に入るのですけれども、中学時代から、昭和のはじめの最も爛熟した、頽廃も含んだ文化を一応、経験しえたことがよかったと思うのです。だから、新劇なんかも含めて、だんだん時局に適応していく過程が、よく観ているだけに、ずっとたどれるわけです。
『丸山眞男回顧談』上
(4)社会的関心
丸山が中学生1年次の冬、大正から昭和への改元が行われた。昭和の初期は景気の後退期にあたり、1927(昭和2)年に起きた金融恐慌のあおりを受けて、いとこの清は郷里松代からの進学を断念した。丸山は農村の疲弊を具体的な経験として実感したのである。
1928(昭和3)年2月に実施された第1回男子普通選挙の際には、立候補した菊池寛の演説を聞きに行った。当然、治安警察法により未成年は入れないはずだが、サバを読んで首尾よく入ることに成功した。演説会では菊池のほか、小島政二郎、横光利一、久米正雄の応援演説を聞いている。社会民衆党の立場を説明する菊池の軽やかな弁舌に感心したという。
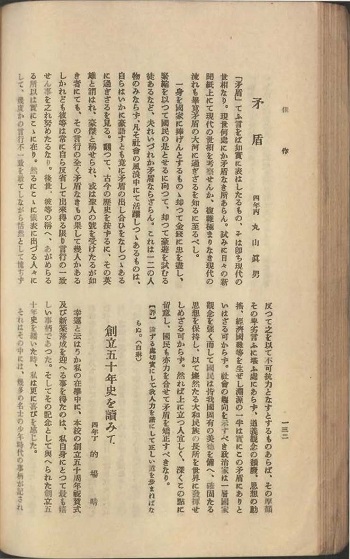
〈国立教育政策研究所教育図書館所蔵〉
この年には日本政治史上の大事件が次々と発生している。その中で、丸山に大きな衝撃を与えたのが1928年6月に起こった張作霖爆殺事件と、8月に持ち上がったパリ不戦条約問題である。張作霖爆殺事件では天皇の発言が結果として田中義一内閣の総辞職につながったが、父が「天皇さんエライ!」とほめている姿を目にしている。また、パリ不戦条約については条文中の「各自ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言ス」という文言が日本の国体に反するとして、批准に反対するキャンペーンが行われた。政教社の社主であった井上亀六はもちろんのこと、父幹治も「田中内閣が困るのが面白いから、やる」といって『日本及日本人』誌上でこのキャンペーンに加担した。丸山は父のこうした態度に、一種の「マキャベリズム」を感じ取っている。
この頃の丸山は、中学生のことゆえ特段の思想的立場をとっていなかった。4年次の頃に国語の授業で出された論題「現代世相の一面を論ず」に対して、「矛盾、これ
(5)文章修行
中学校時代は、丸山の文才が花開きはじめた時期でもあった。1年生の頃、江島への遠足の光景をつづった作文「広島遠足 一年丁」が『学友会雑誌』第93号に掲載されたのを皮切りに、初夏の風景をつづった「夏来る」(第95号)、世相を批判した前述の「矛盾」などの作文を生んだ。さらに文芸方面にも手を伸ばし、英詩を『学友会雑誌』に掲載したり("Ononotofu and the Frog"『学友会雑誌』第101号)、非正統派グループで作った同人誌に戯曲を書いたりした。丸山の文章は周囲にも認められ、5年次の軍事教練では配属将校の永沢少佐から「従軍記者」に任じられ、御殿場での教練の様子を記録している(「富士裾野発火演習記事」『学友会雑誌』第102号)。これには母セイは大喜びだったという。また、作詞した歌を学校に寄贈した。丸山の文才は開花の時期を迎えていたが、その方向性は未だ定まっていなかったといえよう。
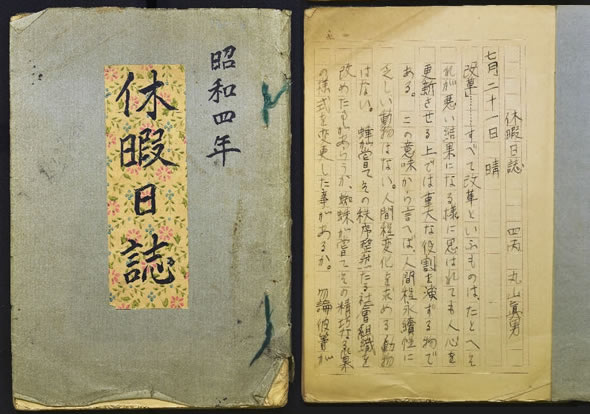
〈丸山文庫資料番号341-6〉
第2章 空白五年 ─ 中学校時代の加藤周一
(1)はみ出し組
1931(昭和6)年4月、11歳の加藤は東京府立第一中学校(現東京都立日比谷高等学校)に入学する。当時の府立第一中学校は国会議事堂近くの永田町にあり、学校に通うには、渋谷で市電青山線に乗り、平河町5丁目で下車した。第一中学校は自由主義的な校風ともいわれるが、一方「詰込学校」とか「規則学校」ともいわれ、勉学にも規則にも厳しいものがあった。第一高等学校へ多くの卒業生を送ることで知られていた。いわばその受験予備校的な性格が強かった。

小学校の受験教育は「職人芸的」であり、加藤はまだ年少だったからか、受験教育に疑問を抱かなかった。しかし、中学校の「工業的な技術と組織」をもった受験教育に、加藤は強い疑問を覚えた。それは個性がない大量規格品を産みだす教育だったからである。どんな有名進学校にも受験体制になじまない「はみ出し組」が必ずいる。「はみ出し組」は、あるいは受験勉強に邁進しない、あるいは校則などを無視する、あるいは運動や趣味に没頭する、あるいは女性に関心が高い「軟派」になる、といった型がある。いずれにしても学校の教育方針に反抗する態度の表れである。彼らは校内の「少数派」である。加藤はまたしても少数派に属することになった。
教育を「人格と人格の接触」とのちに定義する加藤だが、教師とのあいだにも、友人とのあいだにも「人格と人格の接触」を得られなかった。部活にも参加せず、ひたすら自宅と学校の行き帰りの日々を送った。反抗を貫く態度は徹底していて、親しい教師が見つからなかっただけではなく、親しい友人関係も築けなかった。同級生には、のちに哲学者になる矢内原伊作(矢内原忠雄の長男)、同じく『エコノミスト』編集長になる山本進、同じく自然科学系編集者となる高坂知英がいたが、加藤は同級生であったことさえ認識していない。校内には『学友会雑誌』があり、文筆好みの生徒たちが寄稿しているが(丸山眞男も寄稿した)、加藤はついに一度も同誌に寄稿することはなかった。
卒業アルバムを見ると、どこを探しても加藤が写っていない。クラスごとの集合写真にも姿は見えない。撮影時に欠席すると、普通は丸窓で脇に載るものだが、それさえない。おそらく卒業アルバムに自分の写真が載ることさえ拒んだのだろうと推測する。
孤独な5年間を過ごしたに違いない。『羊の歌』では、中学校生活を人生唯一の「空白五年」と名づけた。
(2)例外ネギ先生
「空白五年」にあって、加藤が心動かされたことが皆無ではなかった。それは「ネギ」とあだ名される図画の高城次郎先生(『羊の歌』では高木先生となっている)が「監督なしの試験」を実施したときのことである。生徒たちに「教育の目的は、不正をしようと思えばできるところで、不正をしない人間をつくることだ。その方が試験の成績よりもどれほど大切かわからない」といい、要するに「ノーブレス・オブリージュnoblesse oblige」を求めたのである(これも当時の東京府立一中が標榜していた徳である)。しかし、その目論見はものの見事に失敗し、試験の不正が行われた。ネギ先生は落胆して生徒たちに語りかける。「諸君は私の信頼を裏切ったばかりではなく、正直に試験を受けた諸君の仲間を裏切った」と沈んだ声が教室内に響いた。加藤はこのときのネギ先生の言葉を「ほとんどことばどおりにおぼえています」と書く。加藤はこの不正に加わらなかったが、ネギ先生の言葉は深く心に刻まれたのである。
「平河町の中学校では私は多くの教師に出会った。その大部分は有能な専門家であり、また何人かは好ましい人物であったにちがいない。しかし誰からも ─ おそらくあの瞬間の高城先生を例外として ─ 趣味の上でも、人格の上でも、あるいは話が大げさになるが、世界観の上でも、私はほとんど全く何らの影響をうけなかった」と述懐するのである。
(3)読書と映画

府立一中では、ひとりの先生ともひとりの友だちとも、親しく交われなかったが、加藤の中学校時代がまったくの「空白」であったわけではない。その「空白」を埋めるように、加藤が関心を示し、癒されたものが三つあった。加藤が関心を示したのは、ひとつは読書であり、ひとつが映画であり、もうひとつは夕陽である。

読書については、ふたつが加藤の心を射た。ひとつは詩歌集である。両親ともに詩歌を好んだこともあり、加藤が小学生で『万葉集』を開いてみたことはすでにいった。中学生時代には、与謝野晶子『みだれ髪』や正岡子規『竹之里歌』を読んだ。「牧水にも夢中になった」。さらに『万葉集』の歌のいくつかを覚えた。その後も加藤にとって『万葉集』は大きな意味をもち「詩とは何かを考えるときに、藤村・晩翠を考えず、またいかなる外国の詩人のことも考えず、まず何よりも「万葉」の歌人たちを思いうかべる」とまで書いた。
もうひとつは芥川龍之介である。「馬鹿ねえ」が口癖のおしゃまな幼友だちだった山田千穂子が「馬鹿ねえ、芥川龍之介を知らないの?」といって貸してくれた一冊を読んで、たちまち芥川に魅了された。小遣いをためて渋谷の古本屋で全集10巻を購入して(その全集は立命館大学「加藤周一文庫」に所蔵されるが、第7巻は欠本)、全巻を読破した。なかでも加藤が感銘を受けたのは『侏儒の言葉』だった。『侏儒の言葉』について、加藤は次のように述べる。
学校でも、家庭でも、世間でも、それまで神聖とされていた価値のすべてが、眼のまえで、芥川の一撃のもとに忽ち崩れおちた。それまでの英雄はただの人間に変り、愛国心は利己主義に、絶対服従は無責任に、美徳は臆病か無知に変った。私は同じ社会現象に、新聞や中学校や世間の全体がほどこしていた解釈とは、全く反対の解釈をほどこすことができるという可能性に、眼をみはり、よろこびのあまりほとんど手の舞い足の踏むところを知らなかった。
『羊の歌』「反抗の兆」
加藤が生涯続けた社会的政治的な批評は、『侏儒の言葉』によって促されたに違いない。また加藤は次のようにも総括する。
芥川龍之介のなかに、私が読みとったのは、反軍国主義・日本歴史の偶像破壊・道徳談義への反抗・大勢に順応しない批判的精神であったようだ。吉野作造を通じてではなく、芥川龍之介を通じて、いわゆる「大正デモクラシー」の遺産を受けとったともいえるだろう。
「読書の想い出」
もうひとつの埋め合わせの映画は、中学時代、両親はひとりで映画館に行くことを禁じていたので、必ずしも回数が多かったとはいえないが、それでもいくつかの映画を見ている。
その頃、東和商事会社の輸入していた活動写真のなかでは、七月一四日の晩に、貧しい恋人たちが出会ったり、別れたりしていた。またロシアの大公が、国際会議の古都で、夜遅く町娘を馬車に乗せて走りまわるかと思えば、中部欧洲の麦畑のなかでは、まだ有名にならない大作曲家が、美しい娘と戯れていた。霧の深い英国の都では、警察の眼を自由自在にくらます神出鬼没の怪盗が、売春婦に裏切られ、貧しい者が互に援けあわなくては世も末だと呟きながら、召捕られてゆく。
『羊の歌』「反抗の兆」
この文章から加藤が見たといえる映画は『会議は踊る』(監督エリック・シャレル、1931)、『未完成交響楽』(監督ヴィリ・フォルスト、1933)、『三文オペラ』(監督G・P・パプスト、1931)などであろう。
(4)夕陽を眺める

宮益商店街振興組合(小林總一郎氏撮影)提供
加藤が中学生のときに住んだのは美竹町の2階家である。1階は診療所となっていて、2階の南西角の部屋は父信一の書斎であった。学校から帰った加藤は、その父親の書斎に入り込んでは、夕食までの時を過ごした。西窓からは、遠く富士山までが見渡せた。夕暮れどきに空の色が刻々と色を変えてゆくのを眺めることを日課とした。
5年間の間、西の空の夕暮れを眺めることは、雨の日を除いて、私のほとんど欠かしたことのない日課であった。5年間に私の感覚がうけとったすべてのもののなかで、いちばん美しく、おそらくいちばん深く私を養ったものは、道玄坂の上の西の空であったかもしれない。
『羊の歌』「美竹町の家」
(5)飛び級試験に失敗

襟に5年生を意味する「V」が付けられている
加藤は受験勉強本位の生活には没頭できずにいた。小学生のときには「受験勉強が自分の本業」だと思えたのだが、中学生となるとそうはいかない。しかも、文学に興味を抱きはじめ、「中学校の第四学年に達したときの私は、小説好きの女友だちから借りることのできる本はすべて読みつくしていたし、美竹町の自分の家ばかりでなく、祖父の家にあった内外の小説を読み漁ることにも熱中していたのである。高等学校の入学試験〔飛び級試験 ─ 引用者註〕は近づいていた。しかしその準備のために必要最低限以上の時間を使おうという気は全くなかった」。
こうして第4学年の末に飛び級試験を受けたが不合格となる。試験に失敗して、入学試験の存外に手強いことを知り、第5学年の1年を中学校に通わなければならないことにはうんざりとした。当時、府立第一中学校から第一高等学校に飛び級で行く生徒は50人ほどいた。したがって、加藤のなかにも屈辱感や焦燥感もあっただろうと思われる。しかし、そういう感覚についてはほとんど触れずに淡々と描かれる。それは超越していたからか、超越できなく、むしろ一言も触れたくない気持ちが強かったか、はたしてどちらだろうか。
(6)夏の追分
1936(昭和11)年の冬、第5学年の終わりには第一高等学校の再度の入学試験がやってくる。父信一は次の試験には何としても合格しないとならないと考えたのだろうか。夏季休暇に加藤と妹を信濃追分の油屋旅館に逗留させた。追分油屋旅館は、高等文官試験などを受ける予定の学生が受験勉強のために逗留する旅館として知られていた。それに刺激を受けて、加藤も受験勉強に励むように計らったのだろう。油屋旅館を紹介したのは、父信一の患者であった風間道太郎だったと思われる。
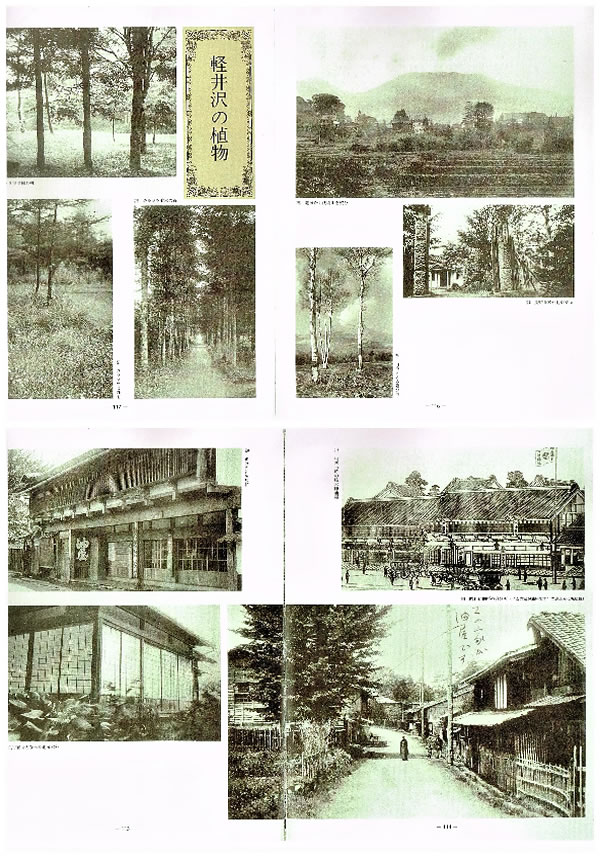
下:油屋旅館:「油屋旅館と文化磁場油やの歴史」
https://aburaya-project.com/history/
ところが、追分は、加藤が生涯の盟友である中村真一郎(1918―1997)や、のちに詩人となる建築科の学生だった立原道造や、詩人・作家として活動をしていた堀辰雄と知己を得る場所になった。これ以降、晩年に至るまで、夏季には追分で過ごす習慣をもった。その契機となったのは、1935(昭和10)年の夏に過ごした追分の体験であった。
(7)2.26事件の衝撃

加藤が第一中学校を卒業する一カ月ほど前の1936(昭和11)年2月26日に、いわゆる「2.26事件」が起きた。皇道派青年将校たちが、統制派軍人や対米協調路線を採る政治家を襲った事件である。2.26事件は、加藤の政治に対する態度を決定づけるほどの大事件だった。
皇道派の指導者である真崎甚三郎や荒木貞夫はクーデタを支持し、陸軍大臣の告示もクーデタを容認するものであった。ところが、昭和天皇の「占拠部隊」の撤収命令が下ると、事態は一変する。統制派の力が強い陸軍首脳部もクーデタ部隊を「反乱部隊」として、これを鎮圧する方向に転換した。
反乱を起こしたクーデタ部隊は「国賊」とされ、一挙に瓦解してゆく。この一連の経過を見て、加藤は政治というものの恐ろしさを知る。
もともと大言壮語を嫌い、徒党を組んで行動することができなかった加藤は、2.26事件によって、「政治」を好まない、という態度がつくられたともいえるだろう。しかし、同時に、「「政治」はこちらから近づかなければ、向うから迫って来る何ものかである」という認識をもった。このふたつの認識のあいだにあって、たえず政治といかなる態度で向き合ってゆくかを考え続けた。それは安保闘争のときにも、九条の会のときにも、加藤は考え続けたうえで、みずからの態度を決めているのである。
