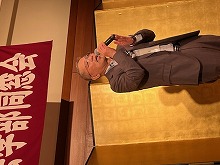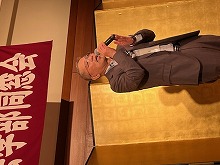令和6年6月23日(日)、ホテルグランヴィア京都の竹取の間において、2024年度立命館大学法学部同窓会総会が行われ、4年ぶりの完全対面で約100人の参加者で開催されました。
総会では仲谷善雄総長に来賓挨拶をいただき、議長である平林幸子会長が議事進行を務めました。また、総合司会を青谷知栄美財務委員長が務め、2023年度活動報告並びに決算及び監査報告、そして2024年度の活動計画・予算案説明が承認されました。2024年度役員案も承認され、濱川登幹事長による第3号議案学習支援基金の使途変更も承認されました。
総会を終え、引き続き講演会が開催されました。
本年は 立命館大学文学部教授の山崎有恒先生による「中川小十郎と西園寺公望を繋いだ絆 --- 立命館大学創立への道 ---」をテーマにご講演いただきました。
先生は日本近代政治史がご専門で、「立命館学園100年史」の編纂事業に参加されるなど、学園史研究の最前線に立ってこられました。
これらの研究により、日本の政党政治史では「最後の元老」といわれる西園寺公望と立命館の関係、創立者 中川小十郎との「出会い」から終生にわたる「深い交わり」等、それまではわからなかった「謎」が徐々に解明されてきたということです。
中川小十郎は1866年(慶応2年)に丹波馬時村(現在の亀岡市)の郷士(武家出身者が後に農民となり非常時には国事に奔走する)の家に生まれ、その親族には有力者が多かったとそうです。同時期、旧幕府軍と新政府軍が京都で戦い、新政府軍の総督に西園寺公望が任命され、馬路村の郷士達もそれに従軍していました。1868年新政府軍が勝利し、明治時代が始まり、京都に凱旋した西園寺は自邸内に「立命館」という漢学の私塾を開設します。「立命館」に学んだ馬路村出身者の一人、小十郎の叔父「謙二郎」は後に西園寺と共に東京に留学して西洋の学問を収めます。
「致遠館(ちえんかん)」(今の小学校)で漢学者の校長から漢文を学んでいた小十郎はその素質を見抜いた叔父の謙二郎が父を説得し、東京留学が認められます。
13歳で謙二郎の家に下宿した小十郎は12年後に帝国大学に入学し、法学と経済学を学びます。そして卒業後は恩師の木下廣次の紹介で文部省に入省します。そこで文部大臣として赴任してきた西園寺公望と出会い、大臣秘書官に抜擢され、京都に赴き京都帝国大学の創立を命ぜられます。木下廣次と西園寺公望は共にパリ大学に留学していた同窓生でした。
民衆の教育が足りなかったゆえに「パリコンミューン」事件が発生したことを学んだ二人の日本にも教育を充実する必要がある、との認識は小十郎にも共有されました。
そして、木下に可愛がられ、謙二郎にも影響を受けた小十郎を西園寺は大切にしました。
しかし、少数の選ばれた者だけの「京都帝国大学」だけでは足りないと考えた小十郎は京都帝国大学の創立3年後に「中等教育」の場としての「京都法政学校(後の立命館)」を創立したのです。「立命館」の創立が自分の人生にとって一番重要な仕事であったと語っていた小十郎。立命館創設者の知られざるその人柄や背景など、貴重なお話を伺うことが出来ました。
その後の懇親会では、宮脇正晴法学部長による乾杯の後、法学部125周年記念事業企画委員長である德川信治先生による来年度の記念事業進捗状況の発表が行われ、現役学生の応援団による演舞、ファイトオンステージで大いに盛り上がり、濱川幹事長による中締めでお開きとなりました。参加された皆様には、恩師や同級生と旧交を温める楽しいひと時を過ごしていただけたようで、閉会後も話は尽きず、名残惜しそうに会場を後にしていらっしゃいました。
また来年、さらに多くの皆様と衣笠キャンパスで交流できますよう、幹事一同楽しみにしております。ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。
広報担当幹事 宮西徳明・古角博子