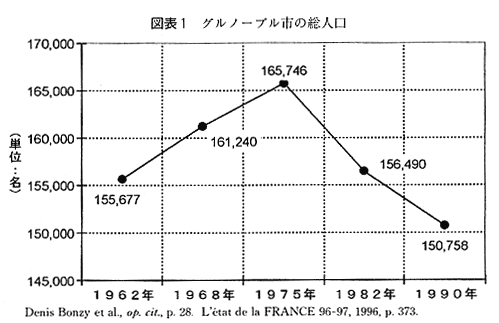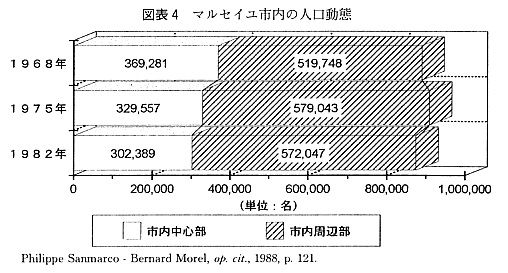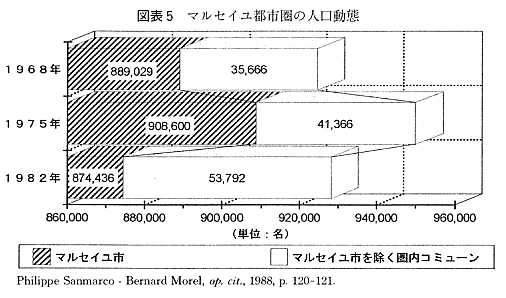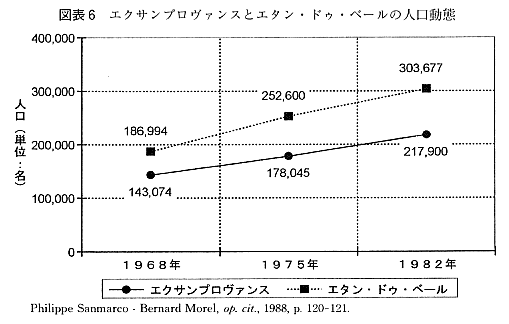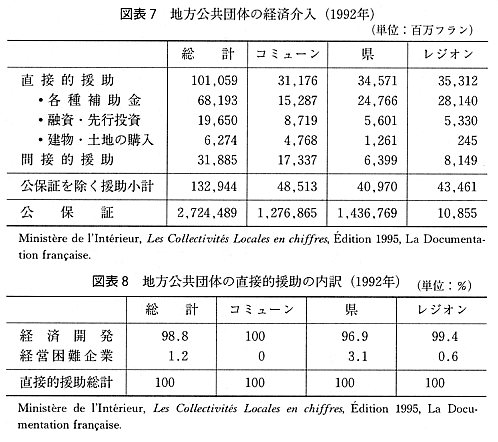|
�́@���@�߁@��
���́@�@�����헪�Ƃ��Ẵ��W�I�����v
�@�@���߁@�@�h�S�[���̃��W�I�����v�ɂ������̖ڕW
�@�@���߁@�@���h�S�[���I�����N���u�̕����I�Q���f���N���V�[�_
�@�@��O�߁@�@�~�b�e�����̐����l���헪�ɂ�����n���������v�̌���
���́@�@�����헪�Ƃ��ẴR�~���[�����v
�@�@���߁@�@�W�X�J�[���f�X�^���헪�ɂ�����R�~���[�����v�̈ʒu
�@�@���߁@�@����I���v�\�z�̒�o
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|�M�V���[���ψ�����|
�@�@��O�߁@�@�W�X�J�[���f�X�^���헪�̍��� �@�@�@�@�@�@�@�@(�ȏ��Z����)
��O�́@�@�O���m�[�u���s�ɂ����镪���^�����̐���̌`���|�n�斯���`���v�̌����|
�@�@���߁@�@�s�s�\���ƏZ���Q���^�s�s����
�@�@���߁@�@�����̉��v�^����GAM�^��
�@�@��O�߁@�@�����E�Q���@�����v�ɂ�����n�斯���`�̈ʒu
��l�́@�@�}���Z�C���s�ɂ����镪���^�����̐���̌`���|�R�~���[���s�����R�����v�̌����|
�@�@���߁@�@�s�s�̐l�����ԂƘp�ݒn��o�ύ\��
�@�@���߁@�@�n�搭���̓W�J�Ɠ]��
�@�@��O�߁@�@�h�D�t�F�[���̒n���������v��
�ށ@�@���@�@�� (�ȏ�{��)
�@
��O�́@�@�O���m�[�u���s�ɂ����镪���^�����̐���̌`��
�|�n�斯���`���v�̌����|
���߁@�@�s�s�\���ƏZ���Q���^�s�s����
��ꍀ�@�@�O���m�[�u���s�̓s�s�\��
�@�@�O���m�[�u���̒n�搭���ɂ��Č�������O��Ƃ��āA�����ł͂܂��A���̓s�s�R�~���[���̓s�s�\��(1)�ɂ��Ă݂Ă��������B�����A�t�����X�̂Ȃ��ł���\�I�Ȑ�[�H�Ɠs�s�̈�ɐ�������O���m�[�u���́A���������W���������Ȋw�Z�p�Ƃ���ɔ����s�s���ł̐l���}���A����ɂ���ɑ����A�Z���Q��������ɓ��ꂽ�s�s�v��̐��i�ɂ���ē����Â�����B�O���m�[�u���Ƃ��̎��Ӑl�����W�n��̔��W�́A�H�Ɛ��Y�̔��W���݂���㐢�I���炷�łɊJ�n�����Ƃ����邪�A����E���ȑO�ɂ́A���͔��d�A�A���~�j�E���A�Z�����g�����A�����A�������H�ƂȂǂ���͎Y�ƂƂ��A���́A�@�B�E�d�C�E�Ȋw�̕���ւƂ��̏d�_���ڍs�����A����Ɏ��Z�N��ɂ́A���q�́E�d�q�H�w�E�T�C�o�l�e�B�N�X�̕���ł̔��W���������B���������Y�Ƃ̔��W�́A�O������̐l�������Ƃ��Č��ꂽ�B���l�Z�N�ɂ͈�Z������ł������O���m�[�u���s�̐l���́A����Z�N���_�ň�ܖ����ܔ���(�O��̃R�~���[������Ȃ�O���m�[�u���s�s���ł͎l�Z���l���O�O��)�ƂȂ��Ă���(2)�A�s�s���ł݂���[�k�E�A���v�E���W�I�����ł̓������Ɏ������ʂł���(�C�[�[�������ł͑��ʂ̌������ݒn)�B�}�\1���疾�炩�Ȃ悤�ɁA���܁Z�N�ォ��Z�Z�N��ɂ����āA�O���m�[�u���s�ł͋}���Ȑl���̑�����o������B
�@�@�����������܁Z�N��ȍ~�ɂ�����O���m�[�u���s�̐l���}���́A�s�s����U�����A���̃R���g���[�����s�\�Ȑ����ɂ܂ŒB�����B�����āA�u�K�v�s���̎s���{�݁E�s�s���u(�S�~�����{�݁A�������A�w�Z�E�E)�v�́A�s�s�v��̂Ȃ��܂܁u�댯�Ȃ܂łɕs���������(3)�v�Ɋׂ����B���Z�ܔN�Ɏn�܂�f���u�h�D�s���́A���������s�s���ւ̑Ή���ƖڑO�ɔ������~�G�I�����s�b�N���̏������ɂ����߂�ׂ��A�u����o�ώЉ�J���v��v�Ɏ��g�ނ��ƂɂȂ�B�������A�f���u�h�D�s�����g�̍l���ɂ��A�����͎s���ɂƂ��āu��{�I�ȖڕW�v�ł͂Ȃ������Ƃ����B�܂�A���̍����s�����ڎw�����̂́A�u�n����Ƃ╶���c�̂̊����Ƃ����̎x���������āA�p���I�ȑΘb�������Ȃ��A���w���Ԓc�́x�Ƃ̋��͂�ʂ��āA�Z���Ɋւ�����̌���̗��āE����ߒ��ւ̏Z�����g�̎Q�����\�ɂ��邱�Ɓv�ɂ������̂ł���(4)�B�����������g�݂��A��q�̂悤�ɁA�u�O���m�[�u�������v�Ƃ��Ēm����Z���Q���^�s�s����̎�@�J���ւƌ������邱�ƂɂȂ�B
��@�@�f���u�h�D�s���̓W�J
�@�@(1)�@�@���x���E�f���u�h�D
�@�@���q�͌����Z���^�[�̃G���W�j�A�ł������f���u�h�D�́A�{�i�I�Ȑ����������AGAM�̑�\�����o�[�Ƃ��ĊJ�n����B���Z�ܔN�ɂ�����O���m�[�u���s�̃R�~���[���c��I���ł́A���̑g�D�̃����o�[�Ƃ��ĎЉ�}�ⓝ��Љ�}�Ƌ������A���������߂�B�������ăf���u�h�D�́A�O���m�[�u���s�̐V�������[���ɏA�C�������A���͂ɂ����Ċ��ɏq�ׂ��悤�ɁA���O�N�ɂ͎Љ�}�ɓ��}���A�����c��I���ł��������č���c�������E����Ɏ���B�����N�̑I���ł͋��Y�}���Q�����A�O�I���ʂ��������A���O�N�̃R�~���[���c��I���ł́A�ꔪ�N�������f���u�h�D�����s���ɂ��Ȃ肪�����͂��߁A���a���A��(RPR)�̃J���j�����Ƀ��[���̍���D����B����Ȍ��ʂł͂��邪�A�������x���ł̓~�b�e������哝�̂Ƃ��鍶���������������A�f���u�h�D�͎���̎��H�����Ȃ�̓_�Ő����������Ƃ�����h�D�t�F�[���@�ĂɎЉ�}�c���Ƃ��Ď^���������A���N�̃R�~���[���c��I���ł̓J���j�����ɔs�k���ARPR�̎s�������������̂ł������B�������āA�������������{�Ɉڂ����n���������v�́A�O���m�[�u���ɂ����ẮA�S�[���X�g�����ɂ����H���ꂽ�̂ł���B
�@�@���̔w�i�ɂ́A��x�ɂ킽��Ζ��V���b�N�̉e�����甲���o�����ꂸ�ɂ������[���b�p�o�ς̖��ƁA����ɔ����O���m�[�u���s�S�̂̒���Ƃ�����肪�������Ɛ��������B������������̌X���́A�����X���ɂ������l�����A���ܔN���甪��N�̊ԂɌ����Ɍ����������Ƃɂ�����Ă���(�}�\1�Q��(5))�B�����āA�}�\2��������炩�Ȃ悤�ɁA�O���l�̑����ɂ͕ω����Ȃ��A�S�̂ɐ�߂�䗦�͈�ꥎl��(��㎵�ܔN)������(��㔪��N)�ւƍ��܂����A���̓���ɂ����ẮA�쉢�����o�g�҂̔䗦�����������ŁA�A���W�F���A�₻�̑��̏����o�g�҂̔䗦�����܂��Ă���(6)�B�����������ۂ́A�s���̓��퐶���ɂ����ẮA���ƕs���Ƃ��Ď~�߂���B�]���āA�����s���́A�u�ٗp�E�����E���v�Ƃ����O�̎w�W�ɂ����Ď��s�����Ƃ݂Ȃ���A�Ƃ�킯�A�ٗp�ƍ����ɂ����ẮA���̎Ⴂ����(�J���j����)�̕����A�s�����v�ւ̋�̓I�p�[�X�y�N�e�B���������Ă���Ƃ݂��Ă����Ƃ���(7)�B
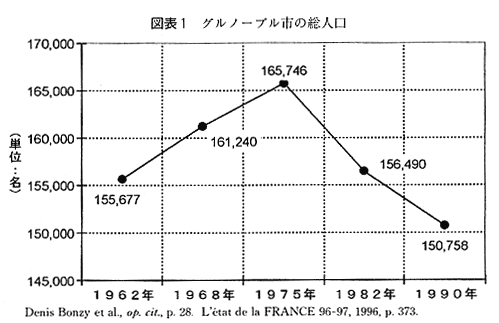

�@
�@�@(2)�@�@�f���u�h�D�̐V�����s�s����
�@�@�f���u�h�D�́A�l���̋}���̂Ȃ��ŃO���m�[�u���ɑ̌n�������s�s�v��̕K�v����Ɋ����A�s�s���̊w�ۓI�����Ɩ��m�ȓs�s�헪���s���̊Ď��ƎQ������Ղɂ��Đ��i���悤�ƍl�����B�ނ́A�l���̖c���ɂ��u�Ȃ�䂫�܂����ɂ��Ă����̂ł͏Z���̑��̂��x������Ȃ��v�Ȃ������̓s�s�ɂ́A�u�Љ�W�Ȃ�тɏZ���Ɗ��̊W�̐V�����̌n�v���K�v�ł���Ƃ��āu�V�����s�s����v���\�z���邪�A�����ɁA�u�s�s���W�ɑ���s���Q���v�̕K�v�����A�s���S���҂Ƃ��Ď��o���Ă����̂ł���B���̍\�z�́A�u�o�ϓI�E�Љ�I�E��ԓI�ϓ_�ɂ����c���v�ƌ��т����邱�ƂŁA�u�s�s�v��v�������������A��������F�����A���̎��{���ē��邱�Ɓv�ɂ���u�s�s�v����Ёi���W�����X�E�f�����o�j�X���j�v�̑n��(���Z�Z�N)�Ƃ��āA�܂��������ꂽ(8)�B�܂�A�]���A���z�Ƃ⌚�Z�p�҂݂̂ɂ��S���Ă����s�s�v��́A�Љ�w�ҁE�o�ϊw�ҁE���v�w�҂Ȃǂ���������w�ۓI���������߂��Ă������A���̂Ȃ��ŁA�s�s�̒P�Ȃ�ʓI�g��Ƃ͋�ʂ����u�s�s�̔��W�v�Ƃ����l���������m�������悤�ɂȂ�A�s�s�����ɂ�����Љ�I�E�o�ϓI�K�w������}������s�s�헪�Ƃ��āu���������̍\�z�v���K�v�ƂȂ�B�������āA���Ɗ������玩�������s�s�̌o�όv����R���g���[���ł���n���̌��I�@�ւ��d�v�������߂邱�ƂɂȂ����B���Ƃ���̎����Ƃ����_�ŁA�����ɂ͍����u�������v���݂Ƃ߂��邪�A�f���u�h�D�͓����Ɏ��̓_�������Ƃ��Ă��Ȃ������B���Ȃ킿�A�����������������A�u�s�s�g�p��(���s��)�̊Ď��ƎQ���Ƃ����A�͂�����\�����ꂽ�ӎu�ɂ���ĕ��t���ۂ���Ă��Ȃ�������A�ł��댯�ȋZ�p��`�Ɋׂ鋰��(9)�v������A�ƁB�������Ĕނ́A�O���m�[�u���ɂ�����s���Q���̋�̉����J�n����B
�@�@�f���u�h�D�́A�s���Q���̖ړI���u�����`�̎��H�ɓ���I������^���A�s�s����̎����ƃO���m�[�u���̓s�s������ʂ��ĐV�����s�s���������݂��邱�ƂɊ�^���A�l�ƏW�c������̉^���̎x�z�҂ɂȂ邱��(10)�v�ɂ���Ƃ������A����̓I�ɂ́A�s�s�����̑Ώۂƒ�Ă��ꂽ������ɂ��Ďs���Ƃ̊Ԃɘ_���ƑΌ�����N���邱�ƂŊ�����`�I�Ȕ���J��`���������A�s�s�����̎�v�c�̂ɔ����̋@���^���邱�ƂŁA���{��`���L�̓s�s���݂ɂ����鎄�I�̐��ɑR���悤�Ƃ����̂ł���(11)�B�������A����ɒ��ڂ��ׂ��_�������B���Ȃ킿�A�u�s�s�S�̂̍\�����̗��v����邽�߂̍\���v�������A���̂��߂ɑg�D���ꂽ�u�A���́v�Ƃ��āA�����ł́u�J���e�B�G�A��(Unions
de Quartier)�v���z�肳��Ă����_�ł���(12)�A���̎�v�ȔC�����A���ǃT�C�h����Ȃ�������(�����J)����b�ɁA�Z���̗l�X�ȎQ���`�Ԃ���苭�͂Ȃ��̂Ƃ��Ď������邱�Ƃɂ���Ƃ���Ă����_�ł���(13)�B�����āA���ꂱ�����u�O���m�[�u�������v�Ƃ���Z���Q���^�s�s����̒��S�������\�����Ă����B
�@�@���̃J���e�B�G�A���́A�����A�O���m�[�u���S�̂�ԗ����鐨���Ŋe���ɐݗ�����Ă���A���Z�Z�N��Z����O���ɂ́A�����̘A���g�D�Ƃ��āu�J���e�B�G�A���A���ψ���(Comite�L
de Liaison des Unions de Quartier)�v���ݗ�����A���N�̎l���ɐ����Ɍ��\����Ă���(14)�B�f���u�h�D�s���̒a���́A���̋���(����јA���ψ���)���A�O���m�[�u���s���S�̂̂Ȃ��Łu���x���v����邱�Ƃ��Ӗ����Ă����B�f���u�h�D�s�����A�s�c��c���ɑ���R���g���[�����Ƃ��āA���́u���ԏ��c�́v�������ʒu�Â��Ă������Ƃ͂��łɏq�ׂ��B�����ŁA���̘A���ψ���́A���̎s���̒a�����u����Ӗ��ł͌��͂̊l���v�ƈʒu�Â��Ȃ�����A�����I�����̖����d�Ȃ������߂ɁA�s���ɑ��ēƗ������X�^���X���ǂ̂悤�ɂ��Ċm�ۂ��Ă����̂��A���̓_�ɂ��Ă��̌�����Ȃ�̋c�_���d�˂��Ƃ����(15)�B����ɁA�s�s���ɂ���Ď䂫�N�����ꂽ�u�V�����R�~���j�P�[�V�����̗l���v���J���e�B�G�P�ʂł̗v���W��`���ɕω���^���A�l�X�ȗv�����������s���������Љ�c�̂����X�Ɛݗ������Ă����Ȃ��ŁA�J���e�B�G�A���ɂƂ��Ă��A����̑��݈Ӌ`�����߂Ė��m�����ׂ��i�K�����łɈ�㎵�Z�N��ɖK��Ă���(16)�B
�@�@�O���m�[�u���s�ɂ�����V�����Z���Q���^�s�s����̎�@�́A���̂悤�ɁA�f���u�h�D�s���̂��ƂŔ��W�𐋂����B�܂�A�s���ǂ��ϋɓI�ɏ����J�������߂����ŁA�J���e�B�G�Z���g�D�͎���𒇉�҂Ƃ��ē���I�ȏZ���Q���`�Ԃ�͍����Ă������A�����͂܂��ɒn�斯���`�̈�Ƃ��Ă����߂�ꂽ���H�ł������B���������J���e�B�G����Ƃ���s�s����̓Ǝ������́A��㔪��N�ɐݗ����ꂽ�u�J���e�B�G�̎Љ�I���W�̂��߂̑S���ψ���v(�̎���@��)�ɂ����Ă���Ɍ������������A��㔪�O�N�ɂ́A���̈ψ����f���u�h�D����ւ̃��|�[�g�w�A���T���u���@�@�s�s�̍Đ��x����o�����Ɏ���(17)�B�������A���̂悤�Ȓn�斯���`�̔��W���A�~�b�e�����������ɂ����镪���E�Q���@�����v�ɂ��̂܂܌��������킯�ł͂Ȃ��B�����ɂ́A��㔪��N�ɐ��������~�b�e�����V���������R��������Ȃ������̘_����Љ�}���̎��������(���̓_�ɂ��ẮA�{�͑�O�߂ɂ����ďڏq����)�B�܂������ɁA��㎵�Z�N��ɂ�����O���m�[�u���s���ƃJ���e�B�G�g�D���A������̉ۑ�ɒ��ʂ��Ă����_�ɂ��Ă��݂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿�A�J���e�B�G�g�D���s�����ɐڋ߂������邱�ƂŁA�s�������D�ʂɗ����ďZ���g�D���哱�E�ĕҐ�������A�����̑g�D����������ꂽ�c�̂Ƃ݂Ȃ��悤�ɂȂ�X�����ǂ̂悤�ɉ�����邩�Ƃ������ł���B����́A�n�惌�x���ɂ����錠�̖͂��A���邢�͖����`�̖��ł���ȏ�A��萭���I�Ȏ��_����̉������K�v�Ƃ����B���̖���_���邽�߂ɂ́A�f���u�h�D�s�����x����^���̂Ƃ��Ă�GAM�����グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�߂����߁A�ȉ��AGAM�𒆐S�Ƃ����O���m�[�u���s�ɂ����鎩���̉��v�^���̗��O�ƌ����ɂ��Č������Ă����B
���߁@�@�����̉��v�^����GAM�^��
�@�@��㎵�Z�N��̃t�����X�ł́A�S���e�n�Ō`������Ă���GAM�^���ɂ���āA�s���Q���𗝔O�Ƃ��鎩���̉��v�^�����W�J����Ă����B�Ȃ��ł��A���̃f���u�h�D��������O���m�[�u��GAM���A�ł��傫�Ȑ��ʂ��グ���Ƃ�����B�����AGAM�̎����̉��v�^�����t�����X�����ɗ^�����C���p�N�g�ɂ��ẮAA�E�}�r���[�AJ�E�����_���A�K�[���B�b�e��̌����҂����ɂ���Ďw�E����Ă���(18)�B�}�r���[�́AGAM�^�����u�Q���f���N���V�[�̗��O���������v�Ƃ��A�u���̔����́A��㎵�Z�N��ɂ�����d�v�ȍs�����|�[�g(�y�C���t�B�b�g�A�M�V���[���A�I�x�[��)�ɔF�߂���v�Əq�ׂĂ���B�ɂ�������炸�AGAM�^���̑��݂ɂ��āA���{�ł͈ӊO�ɒm���Ă��Ȃ��B�����ł́A��������v������Q���f���N���V�[�^���Ƃ��Ă�GAM�^���̊�����咣�ɂ��Č����������邱�ƂŁA���̉^���̐�i���𖾂炩�ɂ���ƂƂ��ɁA�~�b�e�����������ɂ����镪���E�Q���@�����v�̂Ȃ��Œn�斯���`�̋����Ƃ����ۑ肪�A�܂��ɉۑ�Ƃ��ĔF������Ȃ�����A�����čŗD��Ƃ���Ȃ��������ƂɊӂ݁A���̉^�����t�����X�̕����ɂ����Ă͈��̌��E������������Ȃ������_�ɂ��Ă����炩�ɂ��Ă����B
��ꍀ�@�@GAM�^���̌`��
�@�@GAM�^���́A�S���̓s�s�Ɍ`�����ꂽ�����̉��v�^���ł���B�K�[���B�b�e�́A�����GAM�^���ɎQ�������l�X�����̂悤�ɗތ^������B���Ȃ킿�A�ނ�́A���ɂ́A���������Z����n�������̂̉^�c�ɖ������ł����A���ɂ́A���������n��I�����ɑ���������}�̑Ώ��@�ɂ��s�M������Ă���l�X�ł���A�ƁB���������w�i����AGAM�́A�u�ނ�̃R�~���j�e�B�[�����ʂ����̓I�����ɂ��Č������A�ނ炪�l������C�f�I���M�[�I�Ńv���O�}�e�B�b�N�Ȃ�����ׂ���������Ă��邽�߁A��}�h�I��b�Ɋ�Â��s���̓�������Ă��v�Ƃ����(19)�B��������GAM�^���̌`���v���Z�X�̓�����T�^�I�Ɏ������̂��A���Z�l�N�ɐݗ����ꂽ�O���m�[�u��GAM�̎���ł���B��q�̂悤�ɁA�O���m�[�u���́A��[�Y�Ɠs�s�Ƃ��Ă̓���Ȕ��W�𐋂������Ƃ���A�u����������A�O���m�[�u�����ԗL���ɂ��Ă������q�͌����Z���^�[�␅�͔��d���Ƃ������n�C�e�N�Y�Ƃœ������߂ɂ���Ă����~�h���E�N���X�̐l�X�v�ɂ���āA�l���������ۂ������N�����ꂽ�B���������s�s�ɂ�����Y�Ƃ̔��W�Ɛl���̑����ɁA�܂��ŏ��Ɍ��E���������̂́A�����ݔ��ł������Ƃ�����B���Ȃ킿�A��ʐ��т�H��̑����Ɍ������������ێ��ł����A�A�p���g�}���̏�w�K�ł͐������g���Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ԃɗ����������̂ł���B�l�X�̕s���s���͂��̂����Ă�����������Ă������A�ނ�O���m�[�u���ɗ������Ă����~�h���E�N���X�̐l�X�́A�n���ȍs����Љ�{�̌���ɊÂ�悤�Ȃ������̐l�X�ł͂Ȃ������B�ނ�́A���̖��ɂ��ĕ��͂�����������A�s���ɂւƕ����A�ނ炪���ʂ��������������邽�߂ɓ������̂ł���(20)�B
�@�@�O���m�[�u���̎���Ɏ������悤�ȁA�Y�Ɖ���l�������ɔ����s�s���̔����ƁA�����������̉����������s�������̍��g�́A�s�s�^�Љ�ւ̒n��Љ�̕ϗe�v���Z�X�ł���Ƃ����Ă悢�B�]���āAGAM�^���Ƃ́A�܂��ɁA���������t�����X�n��Љ�̕ϗe�ɕt�������n�搭���\���̒n�k�ϓ���̌�����A��̐����I�E�Љ�I���ۂł������Ǝ~�߂邱�Ƃ��ł���B
��@�@�O���m�[�u��GAM�̊����Ɛ����ڕW
�@�@�����A�ł��傫�ȉe���͂������O���m�[�u���s�Ƃ�����Ƃ�܂�������(Meylan)�A�T�����e�O���[��(Saint�|E�Lgre�Mve)�A���E�g�����V��(La
Tronche)�̊e�R�~���[������Ȃ�O���m�[�u���s�s����GAM�^���́A�W�X�J�[���f�X�^�����������̊�Ջ����헪�����s�Ɉڂ�����㎵�܁[�����N�̎����ɁA�n�搭���̎��H��o���ɗ��r���������̉��v�̕��������u�n�斯���`�v�Ƃ��Ē莮�����Ă������B�O���m�[�u��GAM���n�搭���̎��H��o���̂Ȃ��Ŋm�����������̉��v�Ɋւ��l�X�ȖڕW�́A�ނ�̊�����wGAM�A���t�H���}�V�I��(21)�x�ɂ����ĕ\������Ă��������A�Ⴆ�A��㎵�ܔN��ꌎ���s�̑�O�Z���́u�����̌����̕����n��Z�N�^�[�ɂ���ĕ��L���ꂽ��̐������͂�ڎw����(22)�v���A�܂��A�R�~���[���c��I��(��㎵���N�O��)�ɐ�삯�Ĉ�㎵�Z�N��ɔ��s���ꂽ��O�ꍆ�́u�n�斯���`�V���Ȓ��p�_��ڎw����(23)�v���A����ɁA��㎵���N�܌����s�̑�O�́u�R�~���[�������̒n�斯���`�̂��߂̐V���Ȉ�i�K(24)�v���A���ꂼ����Ƃ��Ă���B�ނ�̎�v�ȊS�́A��т��āA�R�~���[�����ǂ̂��Ƃɂ��錠�����ǂ̂悤�ɕ������A�s���ɕ��z���Ă����̂��Ɍ������Ă������A�ނ�̎����̉��v�����m�ȑO�i�𐋂����̂́A�W�X�J�[���f�X�^�����n�����x���v��}��Ƃ���n�����]�Ƃ�������̎x�����B�헪����̉����͂��߂��A�܂��ɂ��̎����ł������B�O���m�[�u��GAM�������̉��v�̐����ڕW���ǂ̂悤�ɔ��W�����A�ǂ̂悤�Ȓn�搭���\�����v�\�z���̂��̎���Ɏc���Ă������̂��B���̎����́wGAM�A���t�H���}�V�I���x�𒆐S�ɁA���ڍׂɌ������Ă������Ƃɂ���B
�@�@(1)�@�@�����̌����̕����|�V���������̉^�c�X�^�C���̊m���|
�@�@�O���m�[�u��GAM�́A���Z�ܔN�ȍ~�A�V���������̉^�c�X�^�C�����m�����ꂽ���Ƃ��������āA�ȉ��̂悤�ɏq�ׂ�(25)�B���Ȃ킿�A�u���͂��s���̎�Ɏ��߂��̂�(26)�v���A���Z�ܔN�ɊJ�Â��ꂽGAM�̑���S�����ɂ����Đݒ肳�ꂽ�e�[�}�ł��邪�A�܂��A���Z�ܔN�Ƃ����N�́A�R�~���[�������j�ɂ����Ĉ�̓]�@�ƂȂ��Ă���A����́A���̔N�Ɏ��{���ꂽ�R�~���[���c��I���ŃO���m�[�u���̍������S�[���X�g�ɏ�����������ł͂Ȃ��āA�O���m�[�u���Ƃ�����s�s�s���ɐV���ȉ^�c�X�^�C�����m�����ꂽ����ł���A�ƁB����ȗ��A�t�����X�̃R�~���[�������̈�ő����̕ω����F�߂���Ƃ���A����͖��炩�ɁA�]�����[���������������Ă����l�X�Ȍ������A�Ăъ��p����悤�ɂȂ������Ƃł���A�]���āAGAM�̊����Ƃ́A�R�~���[���c��ɋc���𑗂荞��ŁA�e�R�~���[���̎����̓��ǃu���H���[���j��D�邱�Ƃɂ���Ɣނ�͎咣����B
�@�@�t�����X�������W�������Ƃ�Â������A�f���N���V�[�͂��蓾�Ȃ��B�����f������ނ�́A�s�������͂���ɂ���Ȃ�A�ӔC�̖�肪���ĉ��̂ł���A�����ɂ͓��R�A�Z�p�ʂ�����ʂł̎��s�ȂǗl�X�ȃ��X�N�����Ƃ����o���Ă����B����䂦�A�t�����X�ɂ����钆���W���I�Ȑ����E�s���\���̎��Ԃ������яオ���Ă���B���Ȃ킿�A�ӔC�҂����ꂼ�ꎩ��̐ӔC��邽�߁A�㋉�@�ւ̔�Ƃ����P�̉��ɐ��荞��ł���u����s���~�b�h�v�������ɂ͑��݂��Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA���͂ƐӔC�Ƃ�����̊W�m�ɂ�����ŁA����͐����E�s���\���̓y����ł߂Ă����K�v�����邪�A�����������ɁA�ӔC�͐l�X�ɂ���ĕ��L����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɣނ�͎咣����B�Ƃ����̂��A�㋉�@�ւ���̂�����d������l�Ŏ~�߂����҂ȂǁA��l�����Ȃ�����ł���B�s���~�b�h�^���������Ƒg�D�̐����I�����Ɋӂ݂�Ȃ�A�R�~���[���i�K�ɂ����Ă��A�ˑR�Ƃ��āA�����W�����ւ̗U�f�������c���Ă���Ƃ����_�ɒ��ӂ��Ă����K�v������B
�@�@�c�_�́A�J���e�B�G����ւƓW�J����B�����āA�ނ�͂����BGAM�́A���Z�ܔN����ш�㎵��N�̃R�~���[���c��c���I���ɂ��������Ƃ��āA�Z��(�Ƃ�킯�Z�����\����s���c�̃J���e�B�G�A��)�ƑΘb����ӎv�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����A�ƁB����́A�ނ�GAM���A�J���e�B�G�A����s���̑��݂Ƃ݂Ă��邩��ɑ��Ȃ�Ȃ����A�ނ�́A�J���e�B�G�A�����A��葽���̏Z������������ōs���ׂ��ł��邵�A�R�~���[�����ǂ���̊�������A�l�X�Ȑ����I�l����������s������(�J���e�B�G�ł̊����́A�����ł͂Ȃ��ƍl����s�����܂�)���ӌ�����������ʂȏ�ƂȂ�ׂ��ł���Ǝ咣����B�������A�R�~���[�����ǂƂ��āA�����J���e�B�G�A���ɑ��Ēł���A�����āA���ׂ��B��̉����́A�ނ�̘b�Ɏ����X���A�d��Ɏ~�߁A�ނ�ƈӌ����Ԃ��������Ƃł���Ƃ����_�ɂ��Ċm�F���Ȃ����B
�@�@���悻�l�K�͂̃R�~���[���Ȃ�A�n���c���Ǝs�������Ƃ̑Θb���\�ł���Ƃ̍l������A���̋K�͂�����O���m�[�u���ɂ����ẮA�R�~���[���ƃJ���e�B�G�̒��Ԓi�K�Ƃ��āu�Z�N�^�[�v���n�݂���A�e�Z�N�^�[�Ɂu�Z�N�^�[�ψ���v���ݒu���ꂽ�B���̈ψ���ɂ͏Z�����c�̒P�ʂƂ����@�\�����҂���A�����A�n�݂��ꂽ�����A���̈ψ���Z���̈ӌ��W��I�������ʂ������Ɣނ�GAM�͕]������B�����āA�O���m�[�u���s���ǂ́A�l�X�ȑ��_(�Ƃ�킯�A��v)�Ɋւ��Đ�����������O�ɁA�����Z�N�^�[�ɑ��ӌ������߂邱�Ƃ��m�F����B�ނ�́A�����������g�݂�ʂ����A�n���c���Ǝs�������Ƃ̑Θb���A�s���ɂ�錠�͂̒D�����������Ȃ����ƂȂ�Ƃ̊m�M���A�����Ɏ������̂������B
�@�@(2)�@�@�u�n�斯���`�v�̒莮��
�@�@�O���m�[�u��GAM�́A�R�~���[���c��I��(��㎵���N�O��)�����A�u�n�斯���`�A��̗D��I�ڕW�v�Ƒ肷�鐭��j�̂��߁A�wGAM�A���t�H���}�V�I���x��O�ꍆ�Ɍf�ڂ���(27)�B�����ɒ�o���ꂽ�ނ�́u�n�斯���`�v�_�́A���āwGAM�A���t�H���}�V�I���x��O�Z���ŖG��I�ɏq�ׂ��u�����̌����̕����v�Ƃ����V���������̉^�c�X�^�C���̎��_������ۂ���A���g�[�^���Ȏ����̉��v�̂�������w���������̂ł���B
�@�@�����ł́A�u�n�斯���`�v�̖ڕW���A���̘Z�_�Ő�������Ă���B
�@�@�@�@�@�����̌����̕���
�@�@�A�@�@���c�̂�W�c�I��Ԃ̊g����Ƃ����Љ�I�����̍l��
�@�@�B�@�@�n����̕�����
�@�@�C�@�@�����������Ɛ�������
�@�@�D�@�@�����J�ƏZ�����c
�@�@�E�@�@����I�����̓��ǂ����ׂĂ̒i�K��
�����Z�̉ۑ�ɂ��āA�O���m�[�u��GAM�͂ǂ̂悤�ɍl���Ă����̂��B�ȉ��A�T���I�ɐ������Ă������B
�@�@�@�����̌����̕���
�@�@GAM�́A�s���Q����ڕW�Ƃ���Ȃ��ŁA�����̌����̕��L��ڎw���Ă����B�R�~���[���c��c���̌������s������юs���c�̂Ƃ̊Ԃŕ��L�����Ƃ��ẮA�R�~���[���ƃJ���e�B�G���z�肳���B�R�~���[���c��́A�s����s���c�̂ɑ��Č��ГI�ȑԓx���Ƃ��Ă��Ȃ������璍�ӂ��K�v������AGAM�Ƃ��ẮA�s�������̌���s���c�̂̓Ǝ�����F�߂�悤�Ȍ_��I���W�̍\�z��ڎw���B
�A�@�@���c�̂�W�c�I��Ԃ̊g����Ƃ����Љ�I�����̍l��
�@�@�s�����c�̂�W�c�I��Ԃ������Ɋg�債���邱�ƂɊӂ݂āAGAM�Ƃ��ẮA���̓�_�ɂ��Ċm�F���Ă����K�v������ƍl����B���Ȃ킿�A���ɂ́A�Љ�W�c�̂�����g�D�`��(�ړI�̖��m�Ȏs�����c�́i�A�\�V�@�V�H���j�A���قǓ`���̂Ȃ��u�R���́i�R���g���E�v���H���[���j�v�Ȃ�)�̍l���ł���B�����āA���ɂ́A�������I�ȎЉ��(�w�Z�A�s��Ȃ�)�Ǝ����I�ȎЉ��(�V�Z��Ȃ�)�Ƃ��c�܂���Ԃւ̔z���ł���B
�@�@���������Љ�I�������l�����邱�ƂȂ��ɁA�n����̕������͎������Ȃ��B
�B�@�@�n����̕�����
�@�@���]�Ƒ̐��̊��ɂ���n��Љ�̊K�����I�g�D�Ґ���]��������ɂ́A�����̍���������Ƃ�F�����Ȃ�����AGAM�́A�n����̕��������A���{�\�ȗ̈悩�琄���i�߂Ă����K�v������ƍl����B
�@�@�܂��́A�R�~���[���̊e���ǃ��x���̏ꍇ�ł���B���̏ꍇ�A�n����̕������́A�������̖��������������Ƃɂ���ĕ����I�ɂ͐������\�ł���B�������A���̂悤�ȍs���I�E���I�������́A���ꎩ�̂����ꐭ���I�ȑI���̑ΏۂȂ̂ł͂Ȃ��B����Ƃ͔��ɁA�����ł������������A�Ⴆ�A�J���e�B�G�i�K�ɂ�����ӌ��\����i�����o������A�s�����c�̊Ԃ�Z���ƃR�~���[���@�ւƂ̊Ԃ̒����⋦�͂W��������A�s�����c�̂ƒn���c�������Ƃ̑Θb�ƁA�s�����c�̂ɂ��s�����ǂւ̖K���Q���Ƃ������I�œ���I�Ȃ��̂Ƃ����肷��_�@�ƂȂ��Ă���̂��B
�@�@�����ł́A����Ǝ��s�̃��x���̏ꍇ�ł���B���̏ꍇ�A�n����̕������́A�Z�N�^�[�i�K�ɂ�����V�����@��(���ʑI���Ɋ�Â��đI�o���ꂽ�����I��\��)�̑n�݂��Ӗ�����B����́A�s�s�s���E�Y�ƁE�o�ς̊e����ɂ����錠�͏W���̑傫�ȗ���Ɏx�z����Ă���A���������W�����́A���̕K�R�I�A���Ƃ��āA���X�ɋ��܂���ݏo�����ƂɂȂ�B
�@�@�����I�ŎQ���I�ȐV�����@�\�����邱�Ƃɂ���āA�s���͎Љ�I�ӔC���\�S�ɕ��S����悤�ɂȂ�B���͂�Ȃ��ӔC�͑��݂��Ȃ����A����̎Љ�I�i�K(�ߗ����́A�J���e�B�G�A�Z�N�^�[�A�R�~���[���Ȃ�)�ɂ����鐭���I�I������Ȃ����͂����݂��Ȃ��̂ł���B
�C�@�@�����������Ɛ�������
�@�@GAM�́A�Z�����g�ɂ��A�����������̊Ǘ��^�c�Ƒ��i������ɐ��i�������ƍl����B�J���e�B�G(���邢�́A�R�~���[��)�̃��x���ɂ����鐶���������̑��i���A�J���e�B�G�ɂ����鐶���̌���ƍ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�������A�����������́A���������コ�����ŁA�d�v�ȕ��@�̈�ł���B
�@�@�R�~���[���c��́A�Ǝ��̎Љ�E��������W������Ǝ��̎�@�����K�v�����邪�A���l�ɁA�����I�s�����c�̂ƁA���ǂɂ���Đݒu���ꂽ�R�~���[�����@�ւƂ̂����Ȃ鍬���������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�D�@�@�����J�ƏZ�����c
�@�@�e�l�́A����Ɋւ��S�Ă̎����ɂ��āA�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂��AGAM�̍l�����ł���B�������A���鐭��₻����߂���I�����𖾂炩�ɂ��邽�߂ɃR�~���[���c����\����������\�́A���Ƃ��A�����̂̎{��Ɋւ���ᔻ�I���͂��������ꍇ�ł��A�ǂ����Ă�����̗���ɕ��Ă��܂��B�]���āA��O�ҋ@�ւ�ݗ��E�琬���邱�Ƃɂ��A�n�������̈ȊO�̏��������i���s�������̂��̂ɂ���悤�A�Z�����c�̏��ۏႵ�Ă����K�v������B
�E�@�@����I�����̓��ǂ����ׂĂ̒i�K��
�@�@�n�挠�͂������悤�Ƃ���ӎv�́A�|���āA�����J�ƁA�S�Ă̒i�K(�J���e�B�G�A�Z�N�^�[�A�R�~���[���A�s�s���Ȃ�)�̊Ԃł̒�����v������B�t�����X�̒����W���V�X�e���Ƃ͔��ɁA���̂悤�Ȓn��̕����I�g�D�Ґ��̂��Ƃł́A���l�Ȉӌ��̕\���𑣐i���A�]���āA�����̌����̕��L�������I��Ղ̏�ɐ����邱�ƂɂȂ�B�܂��A�������������I�g�D�Ґ��́A�l�X�ȃR���t���N�g(�C�f�I���M�[�ԁA�����Q��)�W�����邱�ƂɂȂ�B�����̃R���t���N�g�́A�����̋ɒ[�ȃC���[�W�ő�����̂ł͂Ȃ��A�ނ���A�����I�ł��邱�Ƃ̌����f���N���V�[�̎��H�ɑ���ϋɓI�v���ƌ��Ȃ��ׂ��ł���B���ہAGAM�ɂƂ��Ė{���ɏd�v�Ȃ̂́A�R�~���[���̉��ʒi�K(�J���e�B�G)����R�~���[���̏�ʒi�K(�s�s��)�܂ŁA�����Ƀf���N���e�B�b�N�Ȏ����̓��ǁi�u���H���[���j�̎��H�������i�߂邱�ƂȂ̂ł���B
�@�@�����ł����n�斯���`���A�����^�Љ�̐��n��O��Ƃ����Q�������`(�����I�Q���f���N���V�[)�ł���Ƃ���Ȃ�A�~�b�e�����������ɂ����镪���E�Q���@�����v�̂Ȃ��Œn�斯���`���ǂ̂悤�Ɉʒu�Â����Ă����̂��́A�ɂ߂ċ����[���_�ł���B����́A�n�斯���`�̉^������@���x���v�ւƂ����A��㎵�Z�N��ƈ�㔪�Z�N��Ƃ̘A�����̖��Ƒ����������Ƃ��\�ł���B���������ۂ̂Ƃ���A��㔪��N�̒n���������v�́A�]���̒����W���I�ȍ��Ƃ̘g�g�݂��A�ǂ̒��x���̂������̂��B���̓_�ŁA�Ⴆ�A�}�r���[�́A��㔪��N�@���u������̞B�����v�ݏo�����Əq�ׂĂ���悤�ɁA��炩�ߊϓI�ȕ]���������Ă���B�Ƃ����̂��A���̉��v�̎�v�ȖڕW���A�K�X�g���E�h�D�t�F�[���ɂ���Ė��炩�ɂ��ꂽ���W�b�N�ɏ]���A�u�n���c�������Ɍ��͂�^����v���Ƃɂ��������Ƃ͔ۂ߂��A���������[�n�����]�Ƃ̑R���ɂ����āA�n��̏����R���g�傷�邱�ƂɎ�Ⴊ������Ă�������ł���(28)�B
�@�@�߂����߂���ŁA�t�����X�̐����I�E�s���I�����̂Ȃ��ŁA�n�斯���`���ǂ̂悤�Ȉʒu���߂Ă����̂��A�����āA�~�b�e�����̕����E�Q���@�����v�ɂ����āA�n�斯���`�����̉ۑ肪�ǂ̂悤�Ɉʒu�Â����Ă����̂��ɂ��Č������Ă������Ƃɂ���B
��O�߁@�@�����E�Q���@�����v�ɂ�����n�斯���`�̈ʒu
��ꍀ�@�@�����I�Q���f���N���V�[�^���̐�i��
�@�@�~�b�e���������̕����E�Q���@�����v�ɂ�����n�斯���`�̈ʒu��_����ɂ�����A�n�斯���`���߂����㎵�Z�N��ƈ�㔪�Z�N��̘A�����ɂ��Č������Ă������Ƃ́A�d�v�ł���B�}�r���[�́A�n���������v�ɐ�s���āA�u�n��̐����E�s���P�ʂɂ����镪�����̍l�����v�A��萳�m�ɂ́A�u�n�挠�͂Ǝs�����ڋ߂��͂��邱�Ƃɂ���āA�n��Z�����玩���̂̏����ɂ��Č�����������Ƃ��ł���Ƃ���Q�������`�v�̍l���������݂������Ƃ��w�E����B���Ȃ킿�A�������ƎQ���f���N���V�[�̍l���������т����u���̂悤�Ȓn�斯���`�̊v�V�I�p�[�X�y�N�e�B���́A�w�t�H���X�E���B�[���x�_�b�ƂƂ��ɏo������V�����C�f�I���M�[�I�������ݏo���A����Ɉ�㎵�Z�N��ɂ́A�̌n�����ꂽ���܂��܂Ȓ�Ă��쐬����GAM�^���ݏo�����̂ł���A�����̒�Ă͂₪�āA�����N���u��n���������v�ɐ悾���Ē�o���ꂽ�d�v�s�����|�[�g�ɂ���ċ��L����邱�ƂɂȂ����v�̂ł���B�����āA�����̃C�f�I���M�[�̊g��́A�u�A�\�V�G�[�e�B���ȉ^���̔��W�ƕ������āv����A���������^���͂Ƃ�킯�u����҂Ƃ��Ă̖�����Ɛ肵�A�Z���̏��v���m�����邽�߂̔}��҂����F����A�n��I�����Q��i�삷�鏔�c�́v�Ƃ������������Ƃ��Ĕ��W�����B�����ɁA�����̓��ǂ̑��ɂ��A�������̉��v�̐����Ⴊ����A�}�r���[�́A���̈��Ƃ��ăO���m�[�u���ɂ�����u�J���e�B�G�A���v�̎��H�������Ă���B�����̎��H�̂Ȃ��ň�܂ꂽ�v�z�́A��㎵���N���㔪�O�N�̃R�~���[���c��I���őI�o���ꂽ�V�����R�~���[���c��c�������ɂ���Čp������邱�ƂɂȂ�(29)�B
�@�@���̂悤�ɁA��㔪�Z�N��̕����E�Q���@�����v�ɐ旧��㎵�Z�N��̃t�����X�ɂ́A�u�n���c���ƒn��Z���̊Ԃ��s�����c�́i�A�\�V�@�V�H���j�������V�����f���N���V�[���̋�̉��v���m�F�����̂ł���A�u�����ł́A�s�����c�̂��R�~���[���哝�̐��ւ̑R�����͂Ƃ��ė��������v���ƂɂȂ�(30)�B�����āA�{�͂ɂ����Ă݂Ă����悤�ɁA�O���m�[�u��GAM�́A�f���u�h�D��擪�Ɏ����̉��v�^����g�D���A�O���m�[�u���s��������S�����A�u�n�斯���`�v��������̗��O�Ƃ��鎩���̉��v�^����W�J�����B�����_�����w�E�����悤�ɁACJM���A�����p�~�_�������A���W�I���i�K�ɂ�����v�扻�̐��i���\�z�����J���I�e�N�m�N���[�g����(�Ƃ�킯DATAR)�ƁA�t�����X���Ƃ̋ߑ㉻�_���u������_�ɂ����čl�����̋��L���݂��(31)�A�L�扻�E�������E�������Ǝs���Q���^�f���N���V�[�����т������_�u���̉��v�\�z���N�������ƂƔ�r����ƁAGAM�^���̓����́A�n��ɍ������������`�̎��H�ɂ��傫�ȊS���������Ă���_�ɂ���B
�@�@�����̉��v��ʂ��ēƎ��́u�V���������̉^�c����(32)�v���J�����A�n�斯���`�Ƃ����s�s�s���̃f���N���V�[�`�Ԃ��m���������Ƃ́A������`���咣���Ă���_�ɂ����āA���ꎩ�́A�t�����X�̒����W���V�X�e���ɑ���^�̃I���^�i�e�B�����o������̂ł������B�}�h�����n���c���ƃO���m�[�u���s���Ƃ̑Θb�����́A����̓Ǝ������咣����s�s�^�^������������̓��B�_�ł��������A�s�s�^�Љ�̐����ɔ����n�搭���\���̕ϓ���̌�������̂ł������B�����ɂ́A�����^�Љ�̐��n���i�s���Ă����ƌ����Ă悢�ł��낤�B�܂��A�������x���ł͖�}�̒n�ʂɊÂĂ��������̍������͂ɂƂ��āA�h�S�[���A�|���s�h�D�[�A�W�X�J�[���f�X�^���̊e�����𒆉��W����`�ƌ��т��Ĕᔻ���邱�ƂƁA�s�s�R�~���[���ɂ�����Ǝ��̐�����s�\�͂��ؖ����邱�Ƃ́A���̐������������Ă����ɈႢ�Ȃ��B���Ȃ킿�A�n���������v�ɂ���Ď����I�Ȑ��s�������R�~���[���ɗ^������Ȃ�A�����s���ɂ͂��̌������������\�͂��\�����邱�Ƃ��ؖ������̂ł���B�{�e�ł́A�ނ炪�J�������u�����̉^�c�����v���A��㎵�Z�N��ɓs�s�R�~���[���̂��ƂŌ`�����ꂽ�u�����^�����̐���v�̈�ތ^�Ƒ����A���ꂪ�A�~�b�e�����������ɂ����镪���E�Q���@�����v�́u�����i�v�̈�ƂȂ����ƍl������̂ł���B
��@�@�t�����X�^�n�斯���`
�@�@��q�̂悤�ɁA�~�b�e�����������ɂ����镪���E�Q���@�����v�ɂ����Ēn�斯���`�̋����Ƃ����ۑ肪�A�ŏd�_�ۑ�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ȃ������Ƃ���ߊϘ_���L�͂ł������Ƃ��Ă��A���̌������߂����ẮA�ނ���A�u�Q���v�ɑ������t�����X�I�����̑��݂��w�E���邱�Ƃ��\�ł���B�]���Ă����́A�܂��A�����W�����Ƃ̓T�^�Ƃ݂Ȃ����t�����X�ɂ����āA�n�斯���`���ǂ̂悤�Ɉʒu�Â����Ă����̂��ɂ��Č��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�@�}�r���[�́A�n�斯���`�Ƃ͕ʂɁA�u�n��̏����R�v�Ƃ����l��������O���a���̏������甭�W�𐋂����_���w�E���Ă���B�Ƃ����̂��A���ƃR�~���[���̎��R���Ɋւ���ꔪ����N�ƈꔪ���l�N�̓�̗��@���A�n��̏����R�̐i�W�ɏd�v�Ȗ������ʂ���������ł���B�n��̏����R�Ƃ����l�����́A��c�������`�ƌ��т����Ƃɂ��A�n��Z���̕��ʑI���ɂ���Ēn��̑�\�҂�I�o����d�g�݂�o�ꂳ�������A�����ɁA���̂��Ƃ́A�n�����]�Ƃ̐�������ۏ�����̂ƂȂ����B�܂��ɁA�����ŏq�ׂ���̗��@�̐����́A���a��`��M��u�V�����Љ�K�w�v�Ȃ����u���R��`�C�f�I���M�[���܂Ƃ������a��`�I���]�Ƃ����v���n��̑�\�҂̒n�ʂ��l������u���]�Ƃ����̋��a���v�̏o���ƋO����ɂ�����̂ł�����(33)�B�������A���������n��̏����R�̐i�W���A���ƑS�̂Ɋւ�铝���@�\�̕ύX(�����[�n���W�̍ĕҐ�)��B������ɂ͎���Ȃ������B�����ɂ́A�u�t�����X�̐����E�s���V�X�e���̑g�D�Ґ��Ɋւ��āA��v������߂������`�I�������̎c���v������������ł���B�����āA�u�w�P��ɂ��ĕs���̋��a���x�ɂ�����f���N���V�[�́A���Ƃ̑�\�҂����ɂ�鍑�ƃ��x���ł̌��͂̍s�g�݂̂Ɋւ����́v�ł���A�u���̃f���N���V�[�́A�������͂̐�L���v�ł������B���������t�����X�����W���V�X�e�����~���ƂȂ��āA�u�f���N���V�[�͒n�惌�x���ɓK�p���ꂸ�A�����̈�������āA�n�������c�̂͌��m���̌��Ђ̂��ƂŒP�Ȃ�s���P�ʂƂ���Ă���v�̂ł���(34)�B
�@�@�������āA���Ɗ����ƒn�����]�ƂƂ̑R��(�������a���Ɩ��]�Ƃ����̋��a��)�������яオ��킯�ł��邪�A�}�r���[�ɂ��A�n���̑g�D�@�\�����]�ƌ��͂ɂ���Ďx�z����Ă���ȏ�A�t�����X�����W���V�X�e���̞~������n��V�X�e������������Ƃ��Ă��A����͎��ۂ̂Ƃ���u�n�斯���`�̔��W�Ɠ���̂��̂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����B�m���ɁA�n���̑g�D�@�\�́A��c�������`�̏��K���ɑ����ĉ^�c����邪�A�������A���̑�c�������`�̂��Ƃł́A�u�s���ɂ͑�\�҂��w�����邱�Ƃ͂ł��Ă��A�s�s(cite�L)������\�͂������Ȃ��v�̂ł���B�}�r���[�́A���������t�����X�^�n�斯���`���u�s���Ȃ�(�n��)�����`�v�ƌĂԁB�܂��ɂ������������̂��ƂŁA��l���a�����@����ё�܋��a�����@�́A�n��̏����R���K�肵�����A�����Ď��{����邱�Ƃ��Ȃ��B���̘g�g�݂́A���Ȃ��Ƃ���㔪��N�̒n���������v�܂Ōp�����邱�ƂɂȂ�(35)�B
��O���@�@�����I�Q���f���N���V�[�^���̌��E��
�@�@GAM�ȂLj�㎵�Z�N��̓s�s�R�~���[���ɂ����đ傫�����W�𐋂��������I�Q���f���N���V�[�^���́A�����̉��v��ʂ��ēƎ��́u�V���������̉^�c�����v���J�������_�ł́A�Љ�}�n�s�s�R�~���[���̐����\�͂��ؖ��������A�n���������v��̃R�~���[����������Ƃ����_�ł́A���̐�i�������Ă����Ƃ�����B�������A����������㎵�Z�N��̉^�����A��㔪�Z�N��ɂ�����@�����ߒ��ƘA�����Ă��邩�ۂ��́A�ʂ̎����̖��ł���B�~�b�e�����̕����E�Q���@�����v���A���[�������̌��͂��������A���]�Ƃ�������������A�s����r������Ƃ����\�z�����Ȃ������֓W�J�����Ƃ��A���̉��v�ɂ�����n�斯���`�����̉ۑ肪�y�����ꂽ���Ƃւ̋^�O�̐��������邱�ƂɂȂ邪�A�}���I���E�p�I���b�e�B�́A���̗��R�����̂悤�ɐ�������B���Ȃ킿�A�u��㎵�Z�N�㖖�܂Œn���������v���̒��S�ɒn�斯���`�v�����������Ƃ��Ă��A���̉��v�̌��ߒ��A�Ƃ�킯�A��㔪��N�ƈ�㔪�O�N�ɂ����āA�n�斯���`�v���͂قƂ�Ǒ��݂��Ă��Ȃ�����(36)�v�ƁB
�@�@���Ƃ��A�h�D�t�F�[���@�Ă̂Ȃ��ɂ́A�s���Q���̐��x���ɂ��Ē�߂���������荞�܂�Ă��Ȃ������ȏ�A�����������Ԃ��������邱�Ƃ͎��ɓ��R�̂��Ƃł��邪�A���̓y��͂���ȑO�ɐ��ݏo����Ă����B���Ȃ킿�A��q�́A�W�X�J�[���f�X�^���������Œ�o���ꂽ��㎵���N�́u�n�������c�̐ӔC�������i�@�āv�̐R�c�ߒ��́A�u�Ƃ�킯�A���E�c�������ɂƂ��āA�n�������֘A���@�̂Ȃ��ŎQ���͖@���x�������ׂ��łȂ����A���͂������������A�n�斯���`�̏������\�����������ƂɂȂ�Ƃ�������������@��ɂȂ����v�̂ł���B�]���āA�h�D�t�F�[���@�Ă̐R�c�ߒ�(�����c��̑��lj�)�ɂ����Ė������c���[���[����o�����C����(�u���@���ɂ���āA�n�搢�E�ւ̎s���Q�����i���߂�v)�����̌�c��ɂ����ċc�_����Ȃ�������A��q�̃O���m�[�u���s���ŎЉ�}����c�������E���郆�x���E�f���u�h�D���A��㔪��N�㌎�A�ގ��g����\�߂�u�Љ��`�E���a��`�S���c���A��(FNESR)�v�̖��O�Œ�o�����s���Q���Ɋւ��鑐�Ă��A���̌��،�������Ȃ������Ƃ��Ă��A����͂��ׂČ��E�c�������̊ԂŊm�����ꂽ�R���Z���T�X�Ɋ�Â����̂ł��������ƂɂȂ�B���������ƒn�����]�ƂƂ̑R���ɂ����Ēn�����������_�c���ꂽ��㔪��[����N�̎����A�t�����\���E�~�b�e�����ƃ��x���E�f���u�h�D�Ƃ̊Ԃɂ́A��{�̋��E����������Ă����B�p�I���b�e�B�́A�s���Q�����i�@����̓����ɃX�g�b�v�����������{�l�Ƃ��āA�~�b�e�����̖��O�������A��㔪��N�̑哝�̑I���ɂ�����~�b�e�����̏��������炩�ɂ��Ă��邱�Ƃ́A�u���(la
seconde gauche)�Ɣނ炪�����Ă�����ӎ��ɑ����̏���(37)�v�ł���Əq�ׂĂ���B�������A�t�����X�ɂ�����n�斯���`�̔��W�́A��㔪��N�ŏI�������킯�ł͂Ȃ��B�Ƃ����̂��A��㎵�Z�N��̉^���́A��q�̈����N�@���ҁu�n�斯���`�v�ւƂ���Ίu����`���Ă��邩��ł���(38)�B
�@�@�Ƃ�����A���������ƒn�����]�ƂƂ̑R��(�n��̏����R�̐���)�ɂ����đ�������n���������v�̌����́A�f���u�h�D�̃O���m�[�u���s�ł͂Ȃ��A�K�X�g���E�h�D�t�F�[���̃}���Z�C���s�ɂ���Ƃ�����B�͂����߁A��㎵�Z�N��ɔ��W�𐋂���}���Z�C���s�̐V�����s�s�s���̉^�c��@�ƁA���̎s���h�D�t�F�[�����Ƃ����n���������v�����̂��߂̍s���ɂ��Ė��炩�ɂ��Ă����B
(1)�@�@�O���m�[�u���̓s�s�\���Ǝs���j�Ɋւ��ẮA���ɐٍe�u�~�b�e�����������ɂ�����w�n�斯���`�x�̌`���v(�w�����ٖ@�w�x���㎵�N�x��ꍆ)�̑��͂ɂ����đf�`���Ă���B
(2)�@�@L'etat de la FRANCE 96-97, collab. CRE�LDOC�Ge�Ld. sous la dir. de
Serge Cordellier, E�Llisabeth Poisson. -8e e�Ld. �|Paris�FLa
Decouberte, 1996, p. 373.
(3)�@�@���x�[���E�f���u�h�D�u�O���m�[�u���ɂ�����s�s����Ǝs���Q���v�A�w��g�u���E����s�s����x�ʊ��E���E�̓s�s����(��g���X�A��㎵�O�N)�A���l�ŁB
(4)�@�@���O�A���ܕŁB
(5)�@�@���������O���m�[�u���ɂ�����l���̌����́A�ꔪ���Z�N�ȗ����߂Ă̏o�����ł���Ƃ����BDenis Bonzy et al., Grenoble,
Didier Richard, 1988., p. 36.
(6)�@�@ibid., p. 35.
(7)�@�@���c���u�t�����X�s�s�̕������ƏZ���g�D�|�O���m�[�u���s�𒆐S�Ɂ|�v(�R�c�E�����Ғ��w����E�����̎Љ�_�x�A�Ŗ��o������A����O�N)�A���ŁB
(8)�@�@���x�[���E�f���u�h�D�A�O�f�_���A���ܕŁB
(9)�@�@���O�A���Z�ŁB
(10)�@�@���O�A���ܕŁB
(11)�@�@���O�A���Z�ŁB
(12)�@�@���O�A����ŁB�����}��Ƃ��āA�u(�s����)�ӔC�҂Ǝs���A�������͂Ƃ��܂��܂ȎЉ�c�́A���ꂼ��̊ԂɁA�ٖ��ȊW�v�̑n�o�����҂���Ă����Ƃ���(�����)�B
(13)�@�@���O�A���l�ŁB
(14)�@�@�����ł́A���Y�ψ���́uCLUQ�̗��j�Ҏ[�O���[�v�v���A�����N�ɒ�o�����wCLUQ�̎O�Z�N�j�x���Q�l�ɂȂ�BGroupe
de Travail sur l'Historique du C.L.U.Q.,�hTrente Annees du C.L.U.Q.,
Assemble�Le ge�Lne�Lrale du 16 mai 1991, Comite�L de Liaison des Unions
de Quartier de Grenoble, (Association Loi de 1991), p. 5.
(15)�@�@ibid., p. 6-7.
(16)�@�@���x�[���E�f���u�h�D�A�O�f�_���A���Z�ŁB
(17)�@�@Hubert Dubedout, Ensemble, ferair la ville, rapport au Premier
ministre du Pre�Lsident de la Commission nationale pour le de�Lveloppement
social des quartiers, La Documentation Francaise, 1983.
(18)�@�@Albert Mabileau, op. cit., 1994, p. 128-129. Jacques Rondin, op.
cit., p. 45-47. Peter Alexis Gourevitch, op. cit., p. 165-168. �K�[���B�b�e��GAM�ɂ��Č��y���Ă��邱�Ƃ́A���łɖ�n�F�ꎁ�ɂ���ďЉ��Ă���B��n�F��A�O�f�_���A��㔪�O�N�A��Z�Z�ŁB
(19)�@�@Peter Alexis Gourevitch, op. cit., 1980, p. 166.
(20)�@�@ibid., p. 165.
(21)�@�@Groupe d'Action Municipale, G.A.M. INFORMATIONS. �����̎����́A��������A�O���m�[�u��GAM����сu�O���m�[�u���Z��A���A�����c��(CLUQ)�v�Ŋ�������Ă���t�����\���E�I���[����(Francois
Hollard)�����Ă������������̂ł���B
(22)�@�@G.A.M. INFORMATIONS, N�K 30 - Novembre 1975,�hPartager le Pouvoir�FPour
un pouvoir politique de secteurs.
(23)�@�@G.A.M. INFORMATIONS, N�K 31 - De�Lcembre 1976,�hDe�Lmocratie locale�FPour
de nouveaux relais.
(24)�@�@G.A.M. INFORMATIONS, N�K 32 - Mars 1977,�hMunicipales�Fune nouvelle
e�Ltape pour la de�Lmocratie locale.
(25)�@�@G.A.M. INFORMATIONS, N�K 30.
(26)�@�@���̃e�[�}�́ARendre le pouvoir aux citoyens? �ƕ\�����ꂽ�B
(27)�@�@G.A.M. INFORMATIONS, N�K 31.
(28)�@�@Albert Mabileau,�hA la recherche de la de�Lmocratie locale. Le repre�Lsentant
et le citoyen, Centre de recherches administratices politiques et sociales
de Lille (CRAPS), Centre universitaire de recherches administratives
politiques de Picardie (CURAPP), La democratie locale�Frepre�Lsentation,
participation et espace public, PUF, 1999, p. 64-65.
(29)�@�@ibid., p. 65.
(30)�@�@ibid., p. 65. �Ȃ��A�����ŏq�ׂ��Ă���u�R�~���[���哝�̐��v�Ƃ́A���[���̓R�~���[���c����ɂ�����ݑI�ɂ���đI�o����邪(���ۂɂ́A�R�~���[���c��I���̍ہA�ł����[�̑����������҃��X�g�̕M���҂����[���ƂȂ�)�A���[���ɏA�C�������_�ŁA�c���̐M���̔@������Ɨ����āA���܂��܂Ȍ������l������Ƃ����A���s���x�ɑ���}�r���[�̔ᔻ�I�ď̂ł���B���̓_�ɂ��ẮA�}�r���[�̎��̘_�����Q�ƁBAlbert
Mabileau,�hDe la Monarchie Municipale a�M la Francaise, Pouvoirs, n�K 73,
La De�Lmocratie Municipale, Seuil, 1995.
(31)�@�@Jacques Rondin, op. cit., p. 37-41.
(32)�@�@ibid., p. 46.
(33)�@�@Albert Mabileau, op. cit., 1999, p. 63-64.
(34)�@�@ibid., p. 64.
(35)�@�@ibid., p. 64.
(36)�@�@Marion Paoletti,�hLa de�Lmocratie locale francaise. Spe�Lcificite�L
et alignement, CRAPS, CURAPP, op. cit., 1999, p. 53.
(37)�@�@ibid., p. 53-54.
(38)�@�@���́u�u����`�v�̗��R�𖾂炩�ɂ��邽�߂ɂ́A�����E�Q���@�����v��̒n�搭���\���̓����Ɋւ��錟�����d�v�ł���B���̓_�ɂ��ẮA���̏��_�ɂ����Ď�̌��������������Ƃ�����B�ٍe�u�~�b�e�����������ɂ�����w�n�斯���`�x�̌`���v(�w�����ٖ@�w�x���㎵�N�x��ꍆ)�B
��l�́@�@�}���Z�C���s�ɂ����镪���^�����̐���̌`��
�|�R�~���[���s�����R�����v�̌����|
���߁@�@�s�s�̐l�����ԂƘp�ݒn��o�ύ\��
�@�@�}���Z�C���́A�p���E�������ƕ��ԃt�����X�O��s�s�̈�ŁA���W�I���̓v�����@���X�E�R�[�g�_�W���[���ɑ����A���̓u�V���E�f���E���[�k�ɑ�����A�n���C�ɖʂ����앧�ő�̓s�s�R�~���[���ł���B��㎵�Z�N��㔼�A���̓s�s�R�~���[���Ői�߂�ꂽ�V��������ɂ��Č������邽�߁A�����ł͂܂��A���̓s�s�̐l������n��o�ϖ��ɂ��Ă݂Ă������Ƃɂ���B
��ꍀ�@�@�}���Z�C���̐l�����
�@�@PH�E�T���}���R��B�E�������́A��㔪�ܔN�Ɍ������ꂽ�����w�}���Z�C���x�ɂ����āA�u�}���Z�C���̌o�ϓI�E�Љ�I�E�����I�W�J��������錮�́A�����̎��_�ł́A���܋�N�����㎵�ܔN�܂łɂ��̓s�s���o�������l�������ɂ���v�Əq�ׁA�Ƃ�킯�}���Z�C�������ɂ�����l�����ە��͂̏d�v������������B�Ƃ����̂��A�u�}���Z�C�����L��������̈�́A���̓s�s�������I�ɍx�O�i�o�����D�[�j���������A�p�����ꖜ�w�N�^�[���A���������l��w�N�^�[���ɑ��A�}���Z�C�����O��w�N�^�[�����̍L��ȗ̈��L���Ă���_�v�ɂ���A�}���Z�C���́u���S�s�s�ł���Ɠ����Ɏ��Ӓn��v�ł�����A�u���S�s�s�̏����ɒ��ʂ���Ɠ����ɁA���Ӓn��̏����ɂ����ʂ���v�Ƃ��������悤�ɁA���̐l���������A�}���Z�C���ɌŗL�̎��I�ɐV�������������炵������ł���(1)�B
�@�@�T���}���R�ƃ������̕��͂��Ƃ��Ȃ���A�}���Z�C���̐l�����ɂ��āA����̓I�Ȑ��l�ł݂Ă�����(2)�B
�@�@(1)�@�@�l������(���l�[���ܔN)
�@�@�܂��}���Z�C���̑��l���̕ω����݂Ă݂�ƁA���Z�Z�N������Z���N�̊ԂɁA��l���Ƃ����}���ȑ����������Ă��邱�Ƃ�������B���ɁA���Z���N�����㎵�ܔN�܂ł̊Ԃ̐l���̑���́A��疼�ƒᒲ�ł���B�������A���̎����A���̓s�s�ł͌����ݐl�������������Ă������Ƃ��l�����(�p���ł͎O�Z���l���A�������ł͎������l���A�{���h�[�ł͎l���l��l��)�A�}���Z�C���̐l���͊g��X���ɂ������ƌ����邵�A�}���Z�C���s���ӂ̒n����܂߂čl����Ȃ�A���̎������l���̊g��X���͑����Ă����̂ł���B���Ȃ킿�A���̓V�I�^��N�t�H���^�x���[���܂ŁA���̓\�Z�b�g�܂ŁA�����Ėk�̓J�u���G�܂ł́A�O�Z�̃R�~���[�����܂ރ}���Z�C���n��́A���Z���N�����㎵�ܔN�܂ŁA���̐l������Z������l�����Z��l�ɂ����̂ł���B
�@�@�܂��A�}���Z�C���n�悪������Ă���n���I��������A�O���l�̗����̋K�͂��A�l���̕ω��Ƃ��Č���Ă���B����E����A���ܔ��N����܂ŁA�}���Z�C���ւ̈ږ��҂͋ɂ߂Ēᒲ�ɐ��ڂ����B���̌����́A�C�^���A����̈ږ������̂тȂ��������ƂƁA�k�A�t���J�n�悩��̈ږ������������ᗎ�������Ƃɂ������B���Ɉ��ܔ��N�����㎵�ܔN�܂ŁA�}���Z�C���n��̘J���͎��v�ɉ����邩�����ŁA�k�A�t���J����̈ږ��̗��ꂪ����������B���܌ܔN���_�ŁA�}���Z�C���ɏZ�ޖk�A�t���J�o�g�҂��O���l�S�̂̈�܁����߂Ă�����(�l��������Z�疼)�A��㎵�ܔN�ɂ͘Z�Z�����߂�Ɏ�����(������甪�Z�Z�����A�A���W�F���A�l�O���l�疼���܂ގl���O�疼)�B��㎵�ܔN���_�ɂ�����O���l������甪�Z�Z���ɁA����Ƀt�����X���Ђ��擾�����l�X(�C�^���A�n�A�X�y�C���n�A�����ĂƂ�킯�A�����J�n)�Z���O�疼��������ƁA���̓����A�}���Z�C���ɂ͈�O���l�甪�Z�Z�����̊O���l(�O���o�g��)�����Z���Ă������ƂɂȂ�B�ނ�}���Z�C���ɋ��Z����ږ��ɂ��āA���Љ�w�I�ȃJ�e�S���[�ɕ��ނ���ƁA�ȉ��̂悤�ɐ����ł���B�܂��A�j������݂�ƁA�j�������ɑ��ď����l�O���ƂȂ��Ă���A�t�����X�̑��̒n��ɔ�ׂāA���̒n��̈ږ����u�Ƒ��P�ʁv�ŋ��Z���Ă���Ƃ̐��������藧�B���̂��Ƃ́A��܍Έȉ��̎�N�l���Ɍ����B���Ȃ킿�A��㎵�ܔN�����A�t�����X�l�S�̂ɐ�߂��܍Έȉ��̐l���̊�������Z���ɂ����Ȃ��̂ɑ��A�O���l�̂���͓����߂Ă����̂ł���B

�@�@(2)�@�@�}���Z�C���s�̍r�p
�@�@���Z���N�ȍ~�A��㎵�ܔN�܂ŁA���̊g��X���ɂ������Ƃ͂����A�ᒲ�ɐ��ڂ����}���Z�C���̐l�����Ԃ́A��㎵�ܔN�ȍ~�����X���ւƓ]����B���Ȃ킿�A��㎵�ܔN�����㔪��N�܂ł̎��N�ԂɁA�O���O�疼���܂�̐l���̌������݂�ꂽ�̂ł���B����́A�l�������������ꖜ������̎��R����y���ɏ���A�l���l��܌܈ꖼ���̐l�����o�����������߂ł���B�����āA���̎l���l�Ƃ����l�����o�҂̐����A��Z���l���܂�̐l�������Ґ��ɂ���đ��E���ꂽ���̂ł���A���悻��l�|��ܖ��l���̐l�X���}���Z�C���𗣂ꂽ���ƂɂȂ�(��㎵�ܔN���_�̐l���̈ꎵ���߂������o���A��㔪��N���_�̐l���̈�O�����O������̗�����)�B��㎵�Z�N��̃}���Z�C���ɁA�]���̌X������傫����E����悤�ȃ}���Z�C���s�s�\���̍ĕ҂����������Ƃ������A���������l�����Ԃ̑傫�ȕϓ��́A�}���Z�C�������E�o�ς̍\����W�J�ߒ��ɂ��܂��܂ȕω��������炵�����̂ƍl������B�m���ɁA�l������(��㎵�ܔN�ȍ~)���߂��邱���̌��ۂ́A���̑�s�s�ɂ����ʂ��ĔF�߂��錻�ۂł͂���B�������A���Z�Z�N�エ��ш�㎵�Z�N��̓�Z�N�ԂɃ}���Z�C���o�ς��o��������@���f���o���Ă���_�ŁA�Ƃ�킯�d�v�ł���B
�@�@��㔪��N���_�̃}���Z�C���ɂ�����Z�܍Έȏ�̍���҂́A�S�̂̈�ܥ�܁����߂����A���Έȉ��̎�N�w�͓�ܥ�����ƁA���ɏ��Ȃ��B���̂��Ƃ́A�}���Z�C���̏A�Ɛl�����A���̒n��Ɣ�ׂď��Ȃ����ƂƊ֘A���Ă���B���Ȃ킿�A��㔪��N���_�̃t�����X�S�̂ɂ�����A�Ɛl�����l�O��O���ł������̂ɑ��A�}���Z�C���ł͎O�㥌܁��Ɏ~�܂��Ă����̂ł���B�܂��A��㔪��N�̎��Ɨ��ɂ��Ă݂�ƁA�}���Z�C���͈�l��ƍ������l�������Ă���(�j���̓���ł݂�ƁA�j�������悻����l�ň�O��A���������悻���l�Z�Z�l�ň�ܥ�����ƂȂ��Ă���)�B����ɁA�K�w�\������}���Z�C���n��o�ς̍\�����݂邱�Ƃ��\�ł���B��㔪��N�̒����́A�}���Z�C���̌o�ς��A���܂��O���Y�Ƃ̔��W�i�K�ɍ����|�����Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B���Ȃ킿�A�}���Z�C���́A�N�������҂ƁA�u���[�J���[�w(�A�Ɛl���̓�l��)�ƁA�z���C�g�J���[�w(�O�l��Z��)����Ȃ�ΘJ�҂����̂܂��Ȃ̂ł���A�㋉�Ǘ��E�͔�r�I�����ŋ㥁Z���ƂȂ��Ă���B
�@�@�u�����̃}���Z�C���̕��i�́A���Z�Z�N��͂��߂̂���Ƃ͑S���Ƃ����Ă悢�قǗގ������Ƃ��낪�Ȃ�(3)�v�Əq�ׂāA�T���}���R�ƃ������́A�}���Z�C���s���̐l�����Ԃɂ��Č����������Ă���(�}�\3�E�}�\4�Q��)�B����ɂ��A���l�N�����A�}���Z�C���ɂ͎O�̓s�s����悪���݂����B���Ȃ킿�A���S��(��悩�玵��܂�)�ƁA����ɗאڂ��锪�您��ш�Z��̂Ȃ��̃J���e�B�G������ł���A�����3�̓s�s�����̐l�����x�͍����A��w�N�^�[���������Z�Z�l�𐔂���Ƃ��낪�قƂ�ǂŁA���S���ł͈�w�N�^�[��������l�Z�Z�l���W�Z���Ă���Ƃ��������B�����̑ɂɂ́A���R�ی��悪����A�܂��Ɏ��R�ɂ���Ă���ꂽ���E�����Ȃ��}���Z�C���s�̊O���̂قڑS�Ă����͂ޔ�s�s����悪����B�s�s�����Ɣ�s�s�����̊Ԃɂ́A���悩���Z��܂ł́u���Ӂv�I���Z��Ԃ�����B���̎��Ӌ��́A���l�N�����A���قǂ̐l�����x�ł͂Ȃ�������(��w�N�^�[��������܁Z�l)�A��Z�N��A���͈̏�ς��A�H�Ɖ����i�߂��A�l�����x����w�N�^�[��������܁Z�l�����Z�Z�l�قǂɂȂ��Ă���B
�@�@�}���Z�C���s���̐l�����Ԃɂ��Ă����A�s�s��������ӕ��ւ̈ړ�����{�I�����ł��邪�A��㎵�ܔN�܂Œ��S���ɂ����Ă����F�߂��Ȃ��������̌X�����A����ȍ~�}���Z�C���S�̂ɔF�߂���悤�ɂȂ��Ă���B���S���̐l���́A�}�\4�ɂ��������悤�ɁA���Z���N�ŎO�Z������l�A��㎵�ܔN�ŎO���܌��l�A�㔪��N�ŎO�Z�����O����l�ƂȂ��Ă���A���N�Ԃœ���l�A��l�N�ԂŘZ������l���̐l�����������������ƂɂȂ�(��l�N�Ԃňꔪ���̐l����)�B�Ȃ��ɂ́A���Z���N�����̐l���̓�ꁓ�ȏ�������Ă���s���������(���A�O��A����)�B���ɁA���Z���N�����㎵�ܔN�܂ł̎��N�Ԃɂ�������Ӌ��̐l���́A�����������������Ă��邪�A��㎵�ܔN�ȍ~�A�Ăь����X���ɓ]���Ă���B�����āA���������l�����Ԃ́A��q����悤�ɁA�}���Z�C���n��o�ς̊�@�Ɩ��ڂɌ��т��Ă����B
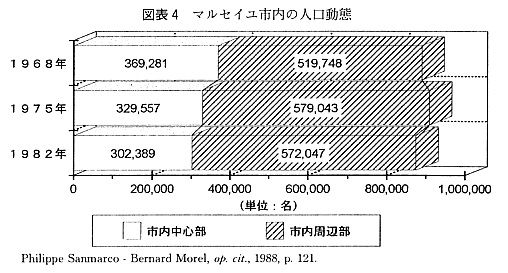
�@�@(3)�@�@�u��}���Z�C�����v�̌`��
�@�@���������l�����Ԃ̋}���ȕϓ��̔w�i�Ƃ��ẮA�}���Z�C���s���̐l�����x�����܂�A�n������������Ȃ��ŁA���̎��Ӓn��ւ̐l���ړ����l������B�s�s���̋�ԓI�E�̈�I�g���ʂ��āA�u��}���Z�C�����v�ƌĂԂׂ���Ԃ���㎵�Z�N��㔼�Ɍ`�����ꂽ�Ƃ���Ȃ�A�����ɂ̓}���Z�C���s���̂��������������e�����Ă����ƍl������B�������A�s�s���̊g�医�ۂ����̎����܂ł��ꍞ���Ƃ́A���̓s�s�Ƃ̔�r�ɂ����Ĉ��̍l�����K�v�ł���B���̓_�ŁA�}���Z�C���̓����ƌ�����v���́A���̗̈�I�K�͂̑傫���ɂ������B
�@�@���Ƃ��A���́u��}���Z�C�����v�ƌĂ���Ԃ���`�I�ɒ�`���邱�Ƃɂ́A�����̍������B�Ƃ͂����A�u�o�ϓI�_�C�i�~�N�X���l�����邱�Ƃ��ł��K���ł���v�Ƃ���T���}���R�ƃ������̕��͂ɏ]���Ȃ�A����͎���̃R�~���[�����ۂ��鎟�̌܂̋��(zones)����Ȃ�Ƃ����(�J�b�R���̓R�~���[���̐�)�B
�y���S�s�s�z�@�}���Z�C���s�s��(6)
�y����I�E�⊮�I�Z���^�[�z�A�I�o�j���[���E�V�I�^(8)�@�@�B�G�N�T���v�����@���X�i15�j�@�C�G�^���E�h�D�E�x�[���i27�j
�y�c���n�сz�D�G�N�T���v�����@���X�̓c���n�сi16�j
�����āA���Z��N�ƈ�㔪��N�̔�r�ł݂�ƁA���́u��}���Z�C�����v�S�̂ɐ�߂�}���Z�C���s���l���́A���Z������ܘZ��܁��ւƒጸ���A�t�ɁA�l���l�ȏ�̓s�s�̐��́A�܂�����ւƑ��債�Ă���(�}���Z�C���A�G�N�X�A�I�o�j���A�T�����A�}���e�B�O�̌ܓs�s�ɉ����āA���E�V�I�^�A�C�X�g���A�|�[���h�D�u�[�A�~���}�A���B�g���[���A�}���j���[�j���̘Z�s�s)�B
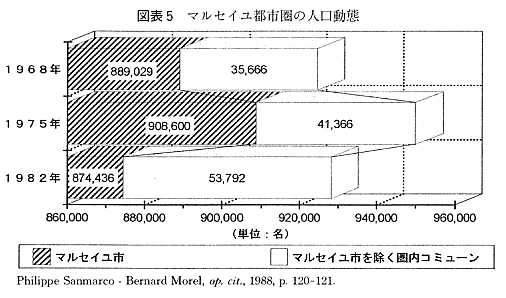
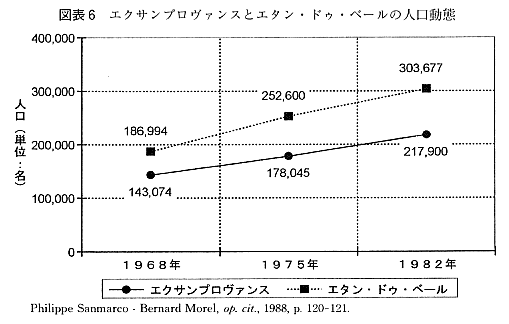
�@�@�u�@�}���Z�C���s�s���v�ɂ��Ă݂�ƁA�}�\5�ɂ��������悤�ɁA�}���Z�C���s���������ӃR�~���[���̐l���́A���Z���N�����㔪��N�܂ł̈�l�N�ԂŁA�܁Z�����܂�̐L�т������Ă���B���̈�l�N�Ԃɂ�����ꖜ������Z�l�Ƃ����l���̑���̂����A�ꖜ�Z���O���l(��O��l��)���O������̗����ɂ���Đ�߂��Ă���B�}���Z�C���ƑΏƓI�ȓ����������Ă���̂��A�u�B�G�N�T���v�����@���X�v����сu�D�G�N�T���v�����@���X�̓c���n�сv�ł���(���v�ŎO��̃R�~���[������Ȃ�)�B�}�\6�ɂ��������悤�ɁA�l���̐L�ї����A���Z���N����̎��N�Ԃœ��l���A��l�N�ԂŌܓ�O���ɂ��y�ԁB���̒��ɂ́A�l�����O�{���������R�~���[��������B�������ł����̕ω��������Ȃ̂́A�G�N�T���v�����@���X�s�ł���B���Z���N����̎��N�Ԃɓ��l���܂�l�����g�債�A�Â����N�Ԃɂ��ꖜ���l���܂�l�����g�債�Ă���B���̌��ۂ́A�G�N�X���ӂ́u�c���s�s���v���ۂƕ��s���Đ��N���Ă���_���d�v�ł���A���̓c���s�s�����ۂ́A�G�N�X���痣���قǎ�܂��Ă������̂́A�}���Z�C���̓����Ɣ�r����Ȃ�A�G�N�T���v�����@���X�s�Ƃ��̎��ӂŋN�����Ă��邱�̈�A�̐l�����ۂ́A��}���Z�C�����S�̂̂Ȃ��ł��A�ł����ڂ��ׂ������ł���B�܂��A�}���Z�C���̓����Ɉʒu����u�A�I�o�j���[���E�V�I�^�v�́A���Z���N�����㎵�ܔN�܂ł̎��N�Ԃł��悻�ꖜ����l�A�Â����N�Ԃł��悻�ꖜ�l�A�l���傳���Ă���B���̋��ɂ�����l�����Ԃ̓����́A�u�c���s�s��(rurbanisation)�v���ۂ����m�Ɍ���Ă���_�ɂ���B����ɁA�u�C�G�^���E�h�D�E�x�[���v�ł��A�G�N�T���v�����@���X�̎���Ɠ��l�A�啝�Ȑl���̑��傪�m�F�����B���Ȃ킿�A���Z���N����̎��N�Ԃœ�Z��A��l�N�ԂŘZ��l�����̐l����������݂Ă���̂ł���B
�@�@�}���Z�C���s�����͂ނ������Ӓn��ɂ́A���鎞�ɂ͑ΏƓI�Ƃ������邳�܂��܂ȓ������F�߂�����̂́A�ł��d�v�Ȃ��Ƃ́A���܂₱�̎��Ӓn��ɘZ�Z������l��㖼���̐l�X����炵�Ă��邱�Ƃł���A���̐����́A�l���̔����l���l�ȏ�̃R�~���[���ɏZ��ł���Ƃ�����A��l���ܐ�O�Z�Z�l����Ȃ邱�́u��}���Z�C�����v�S�̂̎l�O�����߂Ă���B�ȏ�݂Ă����A�u��}���Z�C�����v�̌`�����A�}���Z�C���n��o�ς̍\������ъ�@�Ƃǂ̂悤�Ɋ֘A���Ă����̂��B�ȉ��A���̓_�ɂ��Ă݂Ă����B
��@�@�}���Z�C���n��o�ς̍\���Ɗ�@
�@�@�T���}���R�ƃ������́A��㔪���N�Ɍ������ꂽ�����ɂ����āA�}���Z�C�����̂��Ɍo�����邱�ƂɂȂ鐭���I��@�̍���ɂ́A����E���Ȍ�A���̒n��̌o�ς�h�邪��3�̌o�ϓI��@������Ƃ���B���Ȃ킿�A���Ɉ��܁Z�[�Z�Z�N��ɂ�����u�`�p�Y�Ƃ̊�@�v�ł���A���Ɉ�㎵�Z�N��ɂ�����u���Ӓn��Ƃ̒f��̊�@�v�ł���A��O�Ɉ�㎵�܁[���ܔN�ɂ�����u�t�H�[�f�B�Y���̊�@�v�ł���B�����Ɏ����ꂽ�O�̂����A���̊�@�Ƒ��̊�@�́A�}���Z�C���n��o�ς̍\���I�������яオ�点����̂ł������B�����āA��O�̊�@�́A���̎��Ԃ̐[�����ɂ����āA�}���Z�C���s���ǂ̌o�ω�������v�����邱�ƂɂȂ����B
�@�@�����O�̊�@�Ƃ͂����Ȃ���̂��B�����ɂ��āA�ȉ��A�ȒP�ɐ����������Ă���(4)�B
�@�@(1)�@�@�`�p�Y�ƃV�X�e���̊�@
�@�@�t�����X���{��`�́A�x�T�҂ɂ������ꂽ�V�X�e�����Ƃ��Ă������Ƃ���A��Z�N�ȏ�ɂ킽���ċߑ㉻��i�߂Ă����A�����J���{��`�Ɣ�r����ƁA����E���ȑO�̂Ƃ���ł��łɑ傫���x����Ƃ��Ă����B���B�V�[�̐��ւ̋��́i�R���{���V�H��)�ɂ���ĐM�������Ă��Ă����t�����X�̃u���W�����W�[�́A����E��풼��A�Y�Ɣ��W���߂�����K�͐���̍���𐄐i���A�]���̕��j���ꔪ�Z�x�]�������Ă������B�������č��肳�ꂽ�u�V�����o�ϐ���v���A���M�����V�I����`�҂����Ȃ�u�t�H�[�f�B�Y���v�ƌĂԂł��낤���A����͎�Ɏ��̎O�̕���ɗ��r������̂ł������B
�@�@�@�@�@�@�B���ƃe�[���[��`���Ɋ�Â������Y�������ڎw���V�����J���g�D(���������J���̉Ȋw�I�g�D���Ƃ������@�́A�J���|�X�g�̓O�ꂵ����剻�Ɋ�Â��Ă���)�B
�@�@�A�@�@���Y���̌���Ƃ͔��ɁA�V���Ȏs��E�̘H�̒T���B
�@�@�B�@�@���{�~�ϑ̐��ɂ����钲���҂Ƃ��Ă̍��Ƃ̑S�ʓI����B
�܂��A���������V�����o�ϐ���́A���̂悤�Ȍ܂̌��ۂƂ��Č���Ă����B
�@�@�@�@�@���{�̏W�����ߒ�(���̖ڕW�́A���Y������헪�ɂ����ĊO���o�ς���̗������ő�������o�����Ƃɂ�����)�B
�@�@�A�@�@���A�����̒����A�Љ�̍\�z�A�����Ă���ʓI�ɂ͕������ƂɊ�Â��J�g�W�̏C���B
�@�@�B�@�@���X�Ɋg�債���鍑�Ƃ̎����I�ȉ���B
�@�@�C�@�@�����𑣐i���A������v���ێ�����̂��߂̐M�p�̔��W�B
�@�@�D�@�@�D�������������V���ȎY�Ƌ�Ԃ̑n�݂𑣐i���邽�߂̍��y��������B
�����̌��ۂ́A�T���āA�}���Z�C���n��o�ς��x�z���Ă����`�p�Y�Ƃ̓`���ƑΗ�������̂ł������B����䂦�A�{���h�[�A�g�D�[���[�Y�A���[�A���Ƃ������t�����X�̓s�s���t�H�[�h��`�I�ߑ㉻�ɂ���Ĉ��̐��ʂ��グ�Ă����ɂ��ւ�炸�A�}���Z�C���́A���̂�����̎����܂ŁA�Y�Ɖ��̑傫�ȗ��ꂩ��x����Ƃ��Ă����̂ł���B���̓_�ɂ��āA�T���}���R�ƃ������́A��{�I�ɓ�̗��R������Ƃ���B���Ȃ킿�A���ɂ́A�}���Z�C���ł́A�]���A���̊C�`�𒆐S�Ƃ������Ղ⏤�i���ʂɂ���Ēn��o�ς�ɉh�����Ă������Ƃ���A�����A�����������ՁE���ʒ��S�̒n��o�ς��c�������Ƃ����_�ł���B���ɂ́A�l���̗���(�A���v�X�n���̔_��������̗�����k�A�t���J����̃t�����X�l�̋A��)�ɂ���āA��O���Y�Ƃ⌚�Ƃɂ����鑽���̌ٗp�A����ɁA�����J�������ݏo���ꂽ�_�ł���B������̗��R�ɂ���āA�}���Z�C���́A�u���������o�ςɊ�Â���̓s�s�ƂȂ����v�Ƃ����(5)�B���̂��Ƃ́A����E����A�q�g�E���m�E�J�l�̗��������J�n���ꂽ���̎����ɁA�}���Z�C���n��o�ς����͊O���ɑ�����̎Y�Ƌ�Ԃ���邱�Ƃ��Ӗ������B�]���āA��Ɏw�E�����}���Z�C���ɂ�������̌o�ϓI��@�́A�H�Ɛ��Y����ւ̓����X�����キ�A�����ς�J�����Ԃ̉���(�}���N�X�o�ϊw�ł�����ΓI��]���l���Y)���痘���������o���A�n�������グ����ł����ړI�ȗ�����Nj����悤�Ƃ���Ȃ��ŁA�T���ċZ�p�I�ߑ㉻�ɔے�I�Ȓ�����Ƃ𒆐S�Ƃ���狌�I�n��o�ς̑��ʂ�����ɋ��߂��Ƃ�����B
�@�@�������A�}���Z�C���̒n��o�ς́A�}���Z�C���s�̎��Ӓn������܂߂����L��ȓs�s���Ƃ��đ�����Ȃ�A�Y�Ƃ̋ߑ㉻��}���ŕK�v�ƂȂ�A�������̍D��������ݓI�ɔ����Ă����B���Ȃ킿�A�L��Ȕ��L�n�A���R�ȘJ���́A�ǎ��̎s��A�����āA�n���C�ɊJ����A�����͂�����A�f�Ղɋ��łȊ�Ղ���A�Ζ��̔��~�ɓ������ꂽ�`�p�����݂����̂ł���B�t�H�[�h��`�I���{��`�́A���Ƌ@��(�Ƃ�킯DATAR)����x���A�܂����ɂ̓G�^���E�h�D�E�x�[�����ӂɂ����H�ƒn�т̔��W���A���ɂ͓�k��(���B�g���[��)���ӂɂ��鏔���_�̔��W���A�����đ�O�ɂ͓�����(�G�N�T���v�����@���X)�̔��W�𐄂��i�߂Ă������̂ł���B
�@�@(2)�@�@�f��̊�@
�@�@���̂悤�ɁA��㎵�Z�N��A�o�ϊw�I���_����u��}���Z�C�����v�Ƃ�����I�F�����������悤�ɂȂ����܂��ɂ��̍��A�}���Z�C���Ƃ��̎��Ӓn��Ƃ̂��܂��܂Ȓf�₪���炩�ƂȂ����B���ꂪ�A�}���Z�C���n��o�ςɂ�������̊�@����N���邱�ƂɂȂ�B�܂�A��}���Z�C�������ɎY�Ƃ̋��_���������A����炪����I�ł�����͂ނ��둊�݂ɋ����I�ȊW�����X�ɍ\�z���Ă������̂ł���B
�@�@���Z�Z�N��̃t�����X�ɂ����Ď��{���ꂽ���y��������́A���m�̂悤�ɁADATAR����Ƃ���S�[���X���헪�̈�ł��邪�A��}���Z�C�������ߑ㉻�𐄂��i�߂Ă����ׂ������Ώےn��Ƃ���A���̒n���т��u���Ӂv����u���S�v�ւƈڍs�����邱�Ƃ��ڕW�Ƃ��ꂽ(�Ƃ�킯�A�u�t�H�X�ՊC�H�ƒn�сv�v��)�B�����̐���́A�}���Z�C���s�̎��Ӓn�悪���S���x���ւƋߑ�I���W�𐋂�������ł͐��������Ƃ����邪�A�}���Z�C���s�������Ӄ��x���̂܂܂Ɏ~�܂��Ă�������ł͎��s�ɏI������B���̂悤�ɁA�}���Z�C���n���т̃t�H�[�h��`�I���W�́A�s���S�ȏɂ������B�Ⴆ�A�{���h�[�s�s���ɂ�����ߑ㉻�v���Z�X���A���ӓs�s�ƒ��S�s�s�Ƃœ����i�s���A���[���b�p�S�̂̎��{��`�I���W����݂�Ύ��Ӓn��ɑ�����A�L�e�[�k���A�Ăш�̎Y�Ƌ��_�Ƃ��Ē��S������Ă������B���̓_�Ŕ�r����Ȃ�A�}���Z�C���͑S�����̎���ł���B���Ȃ킿�A�}���Z�C���n��ɂ�����ߑ㉻�v���Z�X�́A���ʓI�Ƀ}���Z�C���s�Ɠs�s�����������Ă��܂����̂ł���B�}���Z�C���s���Ƃ�܂����Ӓn�悪�傫�Ȕ��W�������Ă����̂ɑ��A�}���Z�C���s�́A���ă}���Z�C����ɉh�����Ă����`���Y�ƂƂ����s���m�ȃV�F���^�[�ɂ������܂��Ă��܂����B�v����ɁA���Z�܁[���ܔN�̊ԁA��}���Z�C�����ł́A���S�ł���}���Z�C���s�������Ӊ���������A���̎��ӕ��͒��S�����ꂽ�ƌ������Ƃ��ł���B
�@�@���������A�}���Z�C���s���ɂ����邳�тꂽ�Y�Ƌ�Ԃƃ}���Z�C�����Ӓn��Ɍ`�����ꂽ�V�����Y�Ƌ�ԂƂ̒f��́A���ՁE���ʂɈˑ����Ă����`�p�Y�ƃV�X�e���̊�@������ɑ����������B�������A�����̊�@�́A�}���Z�C���n��o�ς��]�����������Ă����\���I��_���������̂ł��邾���ɁA������邱�Ƃ͂���߂č���ł���ƍl������B���̓_�ɂ��āA�T���}���R�ƃ������͎��̂悤�Ȋ���̗��R����Ă���(6)�B
�@�@���̗��R�́A�u��d�̎Y�ƕ����v�����݂������Ƃł���B�`�p�Y�ƃV�X�e���̊�@�́A�u�����v�̂悤�Ȃ��̂ɂ���ă}���Z�C�����x�z���Ă�����̃��W�b�N��j���B���Ȃ킿�A�}���Z�C���̊O�ɑ��݂��A�`�����u�U��������́v�Ƃ��āA�܂��A�p�����牟������ꂽ���̂Ƃ��āA����ɂ́A�}���Z�C���̎Љ�\���Ƃ͗��������Ȃ����̂Ƃ��Č��ꂽ�A����߂ĈقȂ�������`�Ԃ��Ƃ鎑�{��`�ɑ��A�]���A�}���Z�C���Ǝ��̃��W�b�N�͂���߂Ċ����ŗ͋����R�͂������Ă����B�]���āA�}���Z�C���Y�Ƃ��ꎩ�̂Ƃ��ẮA�ߑ㉻�̑傫�ȗ���ɑg�ݍ��܂��X�����قƂ�ǑттĂ��Ȃ������̂ł���B
�@�@���̗��R�́A�u�n���I�Ȃ��́v�ł���B�}���Z�C���Ǝ��ӂ̐V�����H�ƒn�тƂ��u�˒n�тɂ���Ċu�Ă��Z�L�����[�g���̒n���I�f�₪�A�}���Z�C���ƐV�����Y�Ƌ��_�����ԏ�ŏd��ȏ�Q�ƂȂ��Ă����B��̋�Ԃ��قȂ��̎Y�ƕ����Ɠ�̏Z���ӎ��őΗ����Ă����Ƃ����B���������n���w�I���n���Ƃ邱�Ƃɂ���āA�}���Z�C���Ǝ��Ӓn��Ƃ̊Ԃ̃��W�b�N��s���l���ɍ��ق����o�����Ƃ��Ă��A����ŏ\���Ƃ͌����Ȃ��B�����A���̌��ۂ������炵���ł��d�v�ȋA���̈�́A�}���Z�C���̎��Ӓn�悪�A���炪���Ȃ��Ƃ��n���C�̈ꕔ�ł���Ƃ������Ƃ����ۂ����_�ɂ���B�܂�A�t�H�X�ՊC�H�ƒn�тƃG�^���E�h�D�E�x�[���́A�}���Z�C���ɔ�������n���C�I�E�쉢�I���i����������A���[���b�p�̂��k���̒n��ƌ��т������߂悤�Ƃ����̂ł���B
�@�@��O�̗��R�́A�`�p�Y�ƒn�тƋߗגn�悪���݂��ꂽ���A�}���Z�C���͖��\�L�̐l��������ɂ���A���������l���̑���ɂ���āA���̌o�ϓI���ނ��B�����ꂽ�Ƃ����_�ł���B�}���Z�C���s�́A�Z��̌��݂⏤�Ƃ���ё�O���Y�Ƃɂ�����ٗp�̑n�o��v������A���������l�������ɖڂ�D��ꂽ���߂ɁA���̓s�s�ɏP�������낤�Ƃ��Ă������܂��܂Ȍo�ϓI��@��F�m�ł��Ȃ������B�v����ɁA�u�l���̗������A���z�ݏo���Ă����v�̂ł���(7)�B�m���ɁA��O���Y�Ƃ͑��݂��Ă������A���̋}���Ȕ��W����Ղɂ��āA�}���Z�C���́A��v�s�s�n��Ƃ��Ă̖��������҂���Ă����B�������A�}���Z�C���ɂ������O���Y�Ƃ̌ٗp���A���n���̔�r�I�ꎞ�I�Ȃ��̂ŁA�_�C�i�~�b�N�ȐV�����Y�Ə�����̔��W�ƌ��т��Ă���ƌ������́A�ނ���l�������ƌ��т��Ă���ƌ������Ƃ́A�����ł��Ȃ����̂ł���B
�@�@(3)�@�@�t�H�[�f�B�Y���̊�@�Ǝ��Ɩ��
�@�@��q�̂悤�ɁA�`�p�`�p�V�X�e���̊�@�ƃ}���Z�C���̌�w�n�ɂ�����L��Ȏ��Ӓn��Ƃ̒f��Ƃ�����̌o�ϓI��@���o�������}���Z�C���n��o�ς́A��㎵�܁[��㔪�ܔN�Ƀt�H�[�f�B�Y���̊�@�Ƃ�����O�̊�@���o������B���̊�@�́A��q����悤�ɁA��㎵�O�N�̃I�C���E�V���b�N�ɒ[������̂ł��邪�A�}���Z�C���n��o�ςɑ����Ƃ̑���Ƃ�������߂Đ[���Ȗ���˂����A���ʂƂ��āA�}���Z�C���s���ǂɂ��o�ω�������v������Ƃ���ƂȂ�B
�@�@���܁Z�N��㔼�ȍ~�Ƃ����A�t�����X��܋��a���̐����Ǝ����I�ɏd�Ȃ荇���t�����X�̍��x�o�ϐ����́A���Y���̌p���I�Ȍ���ɂ�����̊g��ɂ���āA����ɐ����𑝂��Ă����B�����������Y���̌p���I����̔w��ɂ́A���Ɖ������e�[���[��`�I�J���g�D�̍\�z�Ǝ��{�~�ς̍��x�����������B�����ŘJ���҂����́A���������Ɛ��Y���̓������s�I�㏸��ʂ��ď���̊g����ێ����A����ɂ��J�g�Ԃɂ�������̗͊W���m�������B���̃V�X�e���S�̂́A�J������A�S�Y�ƈꗥ�X���C�h���Œ����(SMIC)�A�Љ�ۏ�ȂǂƓ��l�A���I���@�ւ��p�C�v���ƂȂ��āA���Ƃ̔���Ă����B���̈Ӗ��ŁA�������������l���̌��ʂ��p������������́A�Ȃɂ����܂��J�����Y�������コ���邱�Ƃł���Ƃ�����B
�@�@��i���{��`�����̂����������x�����Ƀu���[�L���������v���Ƃ��āA��㎵�O�N�̑�ꎟ�Ζ��V���b�N���w�E����̂���ʓI�ł��邪�A�T���}���R�ƃ������́A����ȑO������Ɂu������i�����o�ςɂ����鐶�Y������̌����E��~���m�F����Ă����v�Ƃ���(8)�B�ނ�ɂ��A�������������E��~�̌����́A���܂��܂ȃe�N�m���W�[�̔��W�ɓK���ł��Ȃ��������ƁA�����āA�J����������ނ��邱�Ƃ�J���҂����ۂ������Ƃɂ������Ƃ����B�]���āA�t�H�[�h��`�I�����́A���Y���̌�����p�������Ă����Ƃ�������߂č���ȉۑ�ɒ��ʂ��Ă������ƂɂȂ�B���������ۑ�ɂɒ��ʂ�����i�����̎��{��`�́A���̂悤�ȓ�d�̐헪�����s�Ɉڂ����B
�@�@�@�@�@�V�����e�N�m���W�[�̊J���B����ɂ��A��i�����̎��{��`�ɌŗL�̏�����(���Y���̂���Ȃ����ƐV���Ȏs��̊m��)�̍����B
�@�@�A�@�@�u�Y�Ƃ̒n��ړ]�v�����̊g��B���Ȃ킿�A��J���n��ɂ�����J���҂̌ٗp(�l����̗}��)�ƁA����ɂ�鐶�Y���̌���B
���̂悤�ɁA���Y���̌p���I����Ƃ������ɒ��ʂ�����i�����̎��{��`�́A�]���t�H�[�h��`�ɂ���Ē�������Ă�����Ԃ���ޔ�������������A���ɖ͍����Ă����̂ł���B�����āA��㎵�O�N�ɂ����̍��X�̎��{��`�����������I�C���E�V���b�N�́A�e�N�m���W�[�ɂ��ߑ㉻�헪�ɍČ����𔗂���̂ƂȂ����B���Ȃ킿�A��ƉƂ����́A�����̑唼���Y�����Ɏx������p�ɂ��ĂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ����̂ł���B�܂��ɂ��̂��Ƃ��A�C���t���[�V�����̐i�s������ɋ��߁A���������̉��A�Y�ƍ\���̍č\�z�͏d��ȍ���ɒ��ʂ����B�t�����l�̒ጸ�ɗR�����闘���̒ጸ�́A�����̎Y�Ƃ̐��Y�͂�ቺ�����A�����𐧌���������ɓ������B�����ɁA��ƉƂ����́A�J���҂̑��ɂ��܂��܂Ȋ������v���F�߂��Ă���]���̘J�g�W�̌��������͂������B���̌��ʁA���������������i�ƘJ���҂���̌����v���Ƃ������͂́A�l����̗}���ɂ���ĕ⊮�\�Ȓn��ւ̊�ƈړ]�����������Ă������ƂɂȂ�B�������A���������n���ւ̎Y�ƈړ]�̒n���K�͉��́A���������Ăя㏸������ɂ͎���Ȃ������B�C���t���[�V�����́A�ꎞ�I�ɗ}�����ꂽ���̂́A��蔲�{�I�ȎY�ƍ\���̍č\�z���K�v�Ƃ��ꂽ�B�]���āA����������Ƃ́A������w���͂̌��ނΑO��Ƃ��Ȃ���A���Ɨ��̒������㏸���Ƃ����A����߂č���̑������ÂƂȂ����B
�@�@����������i���{��`���������������t�H�[�h��`�̊�@�́A�}���Z�C���n��o�ςɂƂ��ẮA�[���ȑ�O�̊�@�ł������B����́A�T���}���R�ƃ������ɂ��A�u��d�̈Ӗ��Ń}���Z�C���ɑŌ���^������̂ł������v�Ƃ�����(9)�B���Ȃ킿�A���̑�O�̊�@�́A����ŁA�n��Y�ƃl�b�g���[�N�̐Ǝ㐫��I�悳���A�}���Z�C���n��o�ς̖{�����Ȃ��Ă������K�͊�Ƃɂ���߂Đ[���Ȏ��Ԃ��o���������B�����ł��̊�@�́A�t�H�[�h��`�I�ߑ㉻�헪�ɐϋɓI�Ɋ֗^���Ă���������ɏd��ȑŌ���^�����̂ł���B�Ō���������Ƃ��āA���Ƃ��A�D���C���Ƃ�G�^���E�h�D�E�x�[�����ӂɊm������Ă����V��������(�Ζ����w�A�S�|�A����|)�����Ă͂܂�B�����āA���̋A���́A�\���I�ő����̏ꍇ�����Ԃɂ킽��A�Ƃ�킯���������Ɩ��Ƃ��Č��ꂽ�B���Ɩ��́A�}���Z�C���n��o�ςɂ�����`���I����ɏP�����������B
���߁@�@�n�搭���̓W�J�Ɠ]��
�@�@�T���}���R�ƃ������́A�h�D�t�F�[���̂��ƂŐi�߂�ꂽ�}���Z�C���s���ǂ̐���̖ڕW���A�u����ɑΏ����邱��(faire face)�v�ɂ������Əq�ׂĂ���(10)�B�h�D�t�F�[���́A���炪���[���E�ɏA�������O�N�����̎s�̍��������P���A�{�ݐ����̒x�ꂽ��ŊJ���A�l���̑�ʗ����ɑ��Ă��܂��܂Ȏ{����u�����̂ł���B�������A�������������ڕW���B������Ȃ���������A�}���Z�C���́A��㎵�Z�N��̒��Ոȍ~�A�܂��V���Ȗ��̏o���ɔY�܂���邱�ƂɂȂ�B���Ȃ킿�A���̓s�s�̌o�ϓI�E�Љ�I�E�����I�\���ɓ��݂��邳�܂��܂ȕ����f���A���Y��������ł���B���̓_�ŁA��㎵�Z�N��㔼�̃}���Z�C���́A�n�������ƒn���s���̗̈�ɂ����Ă��A�d��ȓ]���_�ɂ����Ă����Ƃ�����B�����ł́A�}���Z�C���s���Ƃ��Ẵh�D�t�F�[���Ɍ��āA�ނ̍s���ӔC�҂Ƃ��Ă̎�r�����łȂ��A�ނ̐�����@����ѐ�����Ղɂ��Ė��炩�ɂ��Ă����B
��ꍀ�@�@�h�D�t�F�[���̐����I�o���|�앧���܂�̑喼�]�Ɓ|
�@�@�啨�����ƂƂ��ẴK�X�g���E�h�D�t�F�[�������яオ�点�邽�߁A�܂��ނ̐����I�o���ɂ��Ċm�F��(11)�Ă������B
�@�@��z���������I�w���͂�N�����甭�������ނ̐����ƂƂ��Ă̗��z�́A�ꎞ���r�₦�邱�ƂȂ��т��ꂽ�B����͂܂��ɁA�앧�̑喼�]�ƂƌĂԂɂӂ��킵����l�̐����Ƃ̐������܂��̂��̂ł������B���̂��Ƃ́A�h�D�t�F�[�����A�Љ��`�̐����w���҂Ƃ��āA���O�N�����㔪�Z�N�܂ŎO�O�N�Ԃɂ킽��}���Z�C���̎s���߂��ق��A�����̑�b�o����������Ă���B
�@�@���������łɁA���W�X�^���X�^���̂Ȃ��ŁA�Љ��`�^���̎w���҂Ƃ��Ă̓��p�������Ă����B�ނ́A����Z�N�㌎��l���A�n���C�ɋ߂��G���[��(He�Lrault)�̃}���V�����O(Marsillargue)�ɐ��܂�A���e�̉e������A�v���e�X�^���e�B�Y���Ƌ��a��`�I�`���̂Ȃ��ŏ��N����𑗂����Ƃ�����B�G�N�T���v�����@���X��w�@�w���ɐi�w�����ނ́A�����A�w�����������ɂ��A���̑g�D�҂Ƃ��Ă̔\�͂��������B���O�l�N��ꌎ�ɁA�}���Z�C���ł̎O�N�Ԃɂ킽�錤�C���Ԃ��I���A�ٌ�m�ƂȂ����ނ́A��ɁA���������Ɋ��������̂ł������B
�@�@�h�D�t�F�[���̖{�i�I�Ȑ��������́A���O�Z�N���ɊJ�n���ꂽ�ƍl������(������Z��)�B�ނ́A���O�O�N�ASFIO�ɉ������A�g�D���ł͍s������̂�����ɂ��ČJ��Ԃ�����N�������A���ۖ��Ɋւ��ẮA�����ȃu�����h�̗�����Ƃ����B����E��킪�u������ƁA�t�����X���̈�l�Ƃ��ăA���v�X����֑���ꂽ�h�D�t�F�[���ł��������A�t�����X���i�`�X�E�h�C�c�ɔs�k����ƁA�ނ͂����������W�X�^���X�^���ւƐg��]���Ă����B�ނ́A�_�j�G���E�}�C�G(Daniel
Mayer)�ɂ��Љ��`�^���̍\�z����������ȂǁA���̂Ƃ����łɁA���t�����X���\����Љ��`�����ƂƂ��āA���̑����ݏo���Ă����B�������A�Љ��`�҂Ƃ��Ă̔ނ��A���W�X�^���X�^���ɉ�����Ă������Ƃ́A�����ĕ��R�ȓ��̂�łȂ������B�ނ́A�����̃��W�X�^���X�^���������Ă����A���}�ɑ����ȋ^�S�ɒ��ʂ����̂ł���B�����āA���l�O�N��ꌎ�A�悤�₭�ނ́A�Љ��`�҂̕����W�c�����W�X�^���X����^���ւƌ��W������̂ɐ�������B�܂��A�n�������̋@�֎��w���X�|���[���x���}���Z�C���őn�������ނ́A�t�����X�쐼���ł̊����ɏ]�����A�Љ�}�����g�D�̎w���҂Ƃ��ă}���Z�C���̉���ɐs�͂��邱�ƂɂȂ�B
�@�@����E��풼��̈��l�ܔN�܌������A�h�D�t�F�[���́A�S���v�Ń}���Z�C���s�c��̋c���ɑI�o���ꂽ���̂́A�Љ�}���͂���ނ������߁A���N��Z������A���̐E�������Ă���B�����̎Љ�}�́A���͂�L�������������Y�}�Ƌْ��W�ɂ��������肩(12)�A�Љ�}�����ɂ��H�����߂��錵�����Η�������Ă����B�����Ŕނ́A���W�X�^���X�^���������Ƃ��鏔�����������J���Ҏ哱�̐V�����Љ�}�����B���ǁASFIO�̎��s�ψ���́A���̔z���ɂ��郌�W�X�^���X�^���g�D�����U�������B���l�ܔN��Z�������ɁA���@����c�����SFIO�c�����X�g�̕M���ɑI�o����Ĉȗ��A�h�D�t�F�[���́A�I���A�����c��c���ɍđI����Â��邱�ƂɂȂ�(���ܔ��N���̂���)�B�������āA��l���a������������ƁA�h�D�t�F�[���́A�������̑�b�E(13)���C����ȂǁA�t�����X���E�̃��[�_�[�I������S���悤�ɂȂ�B�w�v�����@���T���x�����t�����X�쓌���ő�̓������ɉ����グ�A���܁Z�N�ɂ́A����ĕ҂��哱���������Ă����u�u�V���E�f���E���[�k���A���v�̏��L���ɑI�o���ꂽ�B�ނ́A���O�N�A�Љ�}�����łȂ��A�����h�E�l�����a�^��(MRP)�E�}�i�h�Ȃǂ̒������}�h�̎x�����āA�}���Z�C���̎s���ɑI���B����ȍ~�A���܋�N�A���Z�ܔN�A��㎵��N�̊e�R�~���[���c��I���ɂ����āA�ނ́A�����̎x���ɂ���čđI���ꂽ�B�������A��q�̂悤�ɁA��㎵���N�̑I���ł͎Љ�}�n���}�h�̎w���҂Ƃ��Ďs���ɍđI�����B�h�D�t�F�[���ɂƂ��čŌ�̃R�~���[���c��I���ƂȂ�����㔪�O�N�ł́A���[�ʼnE�����͂��啝�ɖ��i�������߁A�ނ́A�����A���̃��X�g�̕M���҂ƂȂ邱�ƂŁA���Ƃ��s���̍����m�ۂ����̂������B
�@�@�������x���ɂ����鐭���ƂƂ��Ẵh�D�t�F�[���̃X�^���X�́A�܂��Ɂu�_��v�ƕ]������̂��ӂ��킵���ł��낤�B�t�����X��l���a�����A���W�F���A���ɒ��ʂ��Ă������A�ނ́ASFIO���ŁA�A���W�F���A�̓��I��������F�߂Ă������Ƃ��闧����Ƃ��āA�M�E������̕��j�ƑΗ����Ă����B���ܔ��N�㌎�ɁA�A���W�F���A�̘a�����߂����ăh�S�[���Ɖ�k�����h�D�t�F�[���́A�����S�O���Ȃ��A�h�S�[�����R���x������B�S�[���Y���ɂ͔����Ȃ�����A�ނ́A�h�S�[�����\�z���������x�ɂ͔����Ȃ������B���Z�O�N�㌎�A���N�X�v���X���́A��N��ɍT�����哝�̑I���̍������҂Ƃ��āA�u���b�V���[X�v���ƃK�X�g���E�h�D�t�F�[���x���̃L�����y�[�����͂�A��q�̌����N���u�u�N���u�E�W�����E���[�����v���ނւ̎x����\�������B�ނ͂���������Ɠ����ɁA������@�ɁAMRP���܂ގЉ���`�I�ȁu��A���v�̐������͂��낤�ƍl����(�����A���H��)�B�������AMRP�́u�Љ��`�v�ɑ���A�����M�[�I������M�E�����̔��ɂ����āA���́u��A���v�\�z�͍��܂��A�h�D�t�F�[�������Z�ܔN�̑哝�̑I���������ނ��A�t�����\���E�~�b�e�����̎x���ɂ܂�����̂������B�h�S�[���̎��C�������Ď��{���ꂽ���Z��N�̑哝�̑I���ɁA�h�D�t�F�[���͎Љ�}�̌��҂Ƃ��ė���₵��(14)�B�������A�s�G�[���E�}���f�X�E�t�����X�̎x�����Ƃ���Ă����ɂ�������炸�A���[�ł̓��[���͌܁��Ɏ~�܂����B
��@�@�h�D�t�F�[���s���̓W�J
�@�@(1)�@�@�}���Z�C�������ɂ�����N���A���e���X���ƃf���A���X��
�@�@�T���}���R�ƃ������́A�}���Z�C�������V�X�e�����A���܂��܂Ȋ�@��Љ�I�ω����~�߁A���܂��܂ȃR���t���N�g(�s�s�v��Ɋւ��钷���I�œ��O�Ȍ���)���_��ɉ������A�K�͂̕ω�(�Z���{�ݐ����̑�K�̓v���O����)�ɑς������A�Љ�I�A��(�Љ�}��������)��傫�����W������ȂǁA�����ׂ��\�͂�g�ɂ����Əq�ׂĂ���(15)�B�����������V�X�e���̂��Ƃł́A�s�s�̊g��ɔ����l�X�̌Ǘ����╶���I�ޔp�ɑ��āA���邢�́A���Ɩ��ȂǗl�X�Ȍo�ϓI�����o�σV�X�e���̋@�\�s�S�ɑ��āA�u���W�̃l�b�g���[�N�v���d�v�Ȗ������ʂ������Ƃ���A�E�T����Z�܂��T���A���邢�͗l�X�ȓ���I�����̉����ȂǎЉ���̂Ȃ��ŁA���́u���W�v���ɂ߂ďd�v�Ȓn�ʂ��߂Ă���B�����A�Љ�I�}���̔��W�A�l�I���W�̏d�v���A�����I�N���A���e���X���A����ɂ͒n��I�����Ƃ��������Ƃ���ɂ���ē����Â�����A���́u�A�т̃V�X�e���v���ꎞ�I�ɂł����Ă����Ȃ�A�}���Z�C���͂���ɏd��Ȗ��ɒ��ʂ��Ă����ł��낤�B�������A�Ƃ�킯�A�����I�N���A���e���X���ɂ��ẮA���Ӑ[���݂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�m���ɁA�����̐l�X���s�s�ɗ������A�Z����ٗp�̖��̉������}�����Ƃ��A�n���c���������Z�������Ƃ̊Ԃɗ��v���^�̊W��z���グ�邱�Ƃ́A���̐�������L����ł��낤�B�������A���������������@���F�߂���̂́A�l���̊g��A���͂���o�ρA�����āA�Z���̍����������Ƃ��������������������ꍇ�݂̂ł����āA��㎵�Z�N�㒆�Ղɂ́A�V�����Љ�I�����̏o���ƂƂ��ɁA�����̏����͊��ɕ���Ă����̂ł���B
�@�@���n�挠�͂̎��Ԃ���݂Ă݂�ƁA�h�D�t�F�[���s�����̃}���Z�C�������V�X�e���́A�u�ꕔ�̎҂����ɂ�錠�͂Ƃ����l�̒j�̂��ƂɌ��W�������c�̂Ƃɂ�镡�G�ȃq�G�����q�[�v���Ȃ��Ă���A�u���̒��_�Ŏs�������̃V�X�e���̃o�����X���Ƃ�v�A���������G���[�g�������u�n���c���Ǝs���̐l�I�𗬂Ⓖ�ړI�W�v��������x���Ă����̂ł�����(16)�B���ꂪ�܂��ɁA�}���Z�C�������ɂ�����u�f���A���X���v�̖��ł���B����͈�㎵�Z�N��A�}���Z�C���s�s���̓�d�\���Ƃ����������ł�薾�m�Ɍ���Ă����B�u�s�s�v�掖����(l'Agence
d'urbanisme)�v(���Z��N�n��)�A�u�s�s�J��������(le Secre�Ltariat ge�Lne�Lral a�M l'Expansion)�v(��㎵��N�n��)�A�����āA�u�a���������Ɂv�Ƃ������s���ǂƒ����Ȓ��Ƃ̋����̃C�j�V�A�e�B���ɂ����đn�݂��ꂽ����̏��R�~���[���@�ւƂƂ��ɁA�}���Z�C���s���ǂ́A��K�͎��Ƃ̌v����肨��ю��{��S�����邳�܂��܂ȕ��ǂ�ݒu�����B���̌v�����E���{��S������V�ݕ���(�e�N�m�N���[�g�I�X��)�Ə]������̕���(�����`�I�X��)�Ƃ̊ԂɁA�l�ނ̃��N���[�g���@�A���Ƃ̐i�ߕ��Ȃǂ̑��ʂŁA���܂��܂ȑΗ���������ȂǁA�s�s�������ɁA��q�̓�d�\���f�������܂��܂ȑΗ��������N�����ꂽ�B
�@�@�����āA���̃V�X�e���̐����I�S����ł���}���Z�C���Љ�}�̊����Ƃ����́A�}������Ƃ���������̖��Ȗ��ɔY�܂���Ă����B
�@�@(2)�@�@�}���Z�C���̎Љ�}�Ɠ��������
�@�@�Љ�}�̑��݂��ɁA�}���Z�C���̐�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����̃t�����X�Љ�}�������ɑ傫�ȉe���͂�����قǂ̓}�����g�債�Ă����A���̏o���_�͊ԈႢ�Ȃ���㎵��N�̃G�s�l�[���ɂ���A�������h�D�t�F�[�����A���̑��ɂ����Ċm�F���ꂽ�V�����w����(�~�b�e����)�ƐV�����������j(����������)�����F�����B�������A������`������W�Ԃ���}���Z�C���̎Љ�}���₻�̃V���p�T�C�U�[�A����Ɂu�J���҂̗�(FO)�v�̑g�������Ƃ̑唼�ɂƂ��āA�h�D�t�F�[���̂��̍s���͎��ꂪ�������̂ł������B
�@�@��㎵��N�̃t�����X�Љ�}���b�c���܂ł̃u�V���E�f���E���[�k���A���ɂ́A���̂悤�ȓ�̒������������Ƃ�����B���Ȃ킿�A����ɂ́A��p�I�ϓ_���獑�����x���ɂ����鍶����������e�F���Ȃ�����A�}���Z�C���ɂ����邻�̓K�p�͋��ۂ��A�g�D�I�ɔ�����`�����H�Ɉڂ������h�ƁA�����ɂ́A�h�C�c�Љ��}�����f���ɁA���łȎЉ���`�̗��O�̂��ƁA���Y�}�Ƃ̈�̘A�g�����ۂ��鏭���h�ł���B���������}���̕��G�ȏ̂Ȃ��A�����h�𗠐邱�ƂȂ������h�Ɉˋ����邩�����Ńh�D�t�F�[�������َ҂Ƃ��Ă̖������ʂ����Ƃ����A�u�V���E�f���E���[�k���A���ɓƎ��̎�@�ɂ����ē��ꂪ�ێ�����Ă����B�ނ�͎Љ�}�S���g�D�̂Ȃ��ł͂����炩�ᒠ�̊O�ɂ�����A���Ƃ��w�����j�e(l'Unite�L)�x�Ƃ������Љ�}�@�֎��̍w�Ǘ����Ⴉ�����Ƃ�����B�}�{�����}���Z�C���ɂ����鏔���ɂ͉�������A���̉����������ς�h�D�t�F�[���ɂ䂾�˂��B
�@�@��㎵�l�N�̑哝�̑I���ȍ~�A���������}���Z�C���Љ�}���̏��A���X�ɍ����̓x��[�߂Ă����B�Ƃ����̂��A�h�D�t�F�[���ɂƂ��āA�������x���ɂ����Ă̓~�b�e�������x�����Ȃ���A�}���Z�C���ɂ����ẮA��̑I���ŃW�X�J�[���f�X�^�����x�������}�h�ƘA�g�����ނ��Ƃ́A�����Ɩ������͂�ނ��ƂɂȂ邩��ł���B�����������ɁA�Љ�}�̊����Ƃ����ɁA�ǂ������狤�Y�}�Ƃ̐ڋ߂����ꂳ����̂��Ƃ����ۑ���c����A����ɁA�哝�̑I���Ń~�b�e�����Ɏ^��������萔�̐l�X���A�Љ�}�̊O���獶���������̐헪�̗p�𔗂��Ă���Ƃ��������݂����B��㎵���N�̃R�~���[���c��I���܂œ�N�Ԃ̏������Ԃ����������A�h�D�t�F�[���̍s���͂���߂Ď����ł������B�܂��A��㎵�ܔN�A���N�̊Ԓ����h�̏����ɑ�����Ă����E�����~���邱�Ƃɂ����B���̎��_�ł́A���������������͑��݂��Ȃ��������A�����h�Ƃ̓�������͂����Ă����B�����Ŕނ́A��㎵��N�̑n�݈ȗ����炪�c���߂郌�W�I���]�c��ɂ����āA�����������̕��j�����H�Ɉڂ��B�}���Z�C���ɂ�����Љ�}�Ƌ��Y�}�̋����W�́A���̂悤�Ȃ������ō\�z���ꂽ�̂ł���B
�@�@(3)�@�@��㎵���N�̃R�~���[���c��I��
�@�@�Ƃ��낪�A��㎵���N�̃R�~���[���c��ɗՂނɂ�����A�ނ́A���Y�}�Ƃ̋������X�g���쐬���Ȃ����Ƃ����߂�B���Y�}�c���̂Ȃ����珕����C�����邱�Ƃ������ŁA�Љ�}�Ǝ��̌��҃��X�g���쐬�����̂ł���B���̓�N�Ԃ̏������Ԃ̂Ȃ��ō\�z����Ă��������W�����j�Z�ɂ���}���Z�C���s���̂��̌���ɁA���Y�}�͏Ռ����A�ނ�͂�������ۂ����B�ނ狤�Y�}�������ɂ́A�Љ�}�����Ƃ����ɍ���������������������Ƃ����h�D�t�F�[���̂��܂�ɂ�����ȉۑ�́A�����ł��Ȃ������̂ł���B������ɂ���A�h�D�t�F�[���ƃ}���Z�C���̎Љ�}�͋����W����ؒf�������B��㎵���N�Ƀh�D�t�F�[���������������f�������Ɏ������w�i���A�T���}���R�ƃ������́A�h�D�t�F�[�����ߋ��ꔪ�N�Ԃ̎s���^�c�ɂ����ĂƂ��Ă����u�C�����S�v�Ƃ�����@�������������̂ƁA�����Ă���(17)�B���Ȃ킿�A�s�s�v���o�ϐ���Ƃ������v����Ɂu��^�v���W�F�N�g�v�͒����h�ɔC���A�Љ�}�ɂ͏Z���Ƃ̑Θb��Љ���S��������Ƃ�����@�ł���B�������A����������@�̉��Ői�߂��Ă�������́A�s�s�����ɂ����Ĉ��̐��ʂ������Ȃ�����A�}���Z�C���n��Љ�ɍ��[���f��������炵�����A�Z��݂�s�s�̃C���t�������Ƃ������ڕW�͒B������Ȃ�����A���̂̂��ɂ͐[���ȎЉ�̉�̂Ɨl�X�Ȗ��̕��o�o�����Ă���̂ł͂Ȃ����B�V�����Љ���̏o����F�����A�h�D�t�F�[���́A�]���̐����@�{�I�Ɍ��������̂ł���B�����������n����U��Ԃ�Ȃ�A�u��㎵�ܔN�v�Ƃ����N�̓}���Z�C���s���j�ɂ������̓]���_�ł������ƌ����邩������Ȃ��B�����āA��㎵���N�R�~���[���c��I���ɂ����ă}���Z�C���̎Љ�}�͈��|�I���������߂�B���̏����́A����ł͍������x���ɂ����鍶�����͂̐L���ɂ����̂ł��������A�����ł͊e�E��\�҂����Ƃ̘A�g�ɂ��Ƃ��낪�傫�������B���������A�g���͂��邱�ƂŁA�E�����͂Ƌ��Y�}���͂̑o���ɑ��Č����������邱�Ƃ��ł����̂ł���B
�@�@�������āA�}���Z�C���ɂ�����Љ�}�̃w�Q���j�[�͊m�����ꂽ�B�������A�]���̃h�D�t�F�[���s���ɂ����āA�}�h�Ԃ̋��n���I������S���Ă����}���Z�C����GAM(18)�ɂ��Č��Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ����̂��A�����ƍ����ɂ���Ďx�����Ă�����㎵���N�܂ł̃h�D�t�F�[���s���̂��Ƃł́A�s�s�v���o�ϐ���Ȃǃn�[�h�ʂɊւ��s����GAM�ɐ������C����Ă���A�������������A�Љ�}���P�Ƃŗ^�}���`���\�ɂȂ������̃R�~���[���c��I���ȍ~���A�n�[�h�ʂɊւ��s����GAM�Ɍp�����ĔC���邱�Ƃ�]�ސ����������Ă�������ł���B�����āA��㎵���N�̑I���ȍ~���A���������s���^�c�̘g�g�݂��ێ����ꂽ���ʁA�]���͒����E�E�h�c�������̗͓Y���ɂ���Ď���̌v������{�Ɏ�������ł���GAM���A����́A�h�D�t�F�[���Љ�}�s���̂��ƂŁA����̐������萸�k���E���m�����邱�Ƃ����߂���悤�ɂȂ�B���̂悤�ɁAGAM�̌v�悪�s���̂Ȃ��Ŏ��グ����g�g�݂��m�ۂ��ꂽ���Ƃɂ���āA���x�͋t�ɁAGAM�̑�\�҂������e�N�m�N���[�g�Ƃ��ė�������A����ΐV�����O����܂Ƃ����N���A���e���X���̍ė��ƂȂ�댯�������܂�邱�ƂɂȂ�B��㎵���N�ȍ~�̃h�D�t�F�[���Љ�}�s���́A���̓����ɂ��܂��܂ȑΗ��I�v�����͂�݂Ȃ���A�o�����邱�ƂɂȂ����B
�@�@�������A���������Η��v�����A������`�I����̎��{�Ƃ�����v�_�̉��ŁA�������Ă������B�Љ�}�n���}�h�Ƃ������������S�ۂ��ꂽ�s���ǂ̉��ŁA�h�D�t�F�[���̓}���Z�C���ɐi�s�����邳�܂��܂ȗ̈�ł̕���ߒ��������~�߂�ׂ��A�V�����s�s����Ƃ�����v��E���{����s���^�c�̘g�g�݂��m�����悤�Ǝ��݂��B���Ȃ킿�A��ʖԂ��Č������A��ʗA��������Ă��A�s�k���ɂ���V���J���e�B�G�̎Љ�I������T�����A�ł��V�������������s�X�n�̕�C�������Ȃ����߁A�y�n���e�v��Ɋւ��A���P�[�g�����{����Ȃǂ̎�i���Ƃ��āA�ނ̓}���Z�C���s�̎{��Ɋւ���{�I�ȍl�����ƌv�扻���߂��̂ł���B����䂦�A�}���Z�C���s�̎{��́AGAM���n���̎��c�Ǝ҂����łȂ��A��ƉƂ�����������ɓ��ꂽ�K�w��I�Ȑ헪�̂Ȃ��ɑg�ݍ��܂�邱�ƂɂȂ�A�Љ�}�ƒ����h�̋��n���I������S����GAM�̂������������́A�Љ�}�ƒ����h�Ƃ̊Ԃɐ����Ă����Η����A����^�c��̘g�g�݂Ƃ��Ă�����������Ɏ���̂ł���B
�@�@��㎵���N�̃R�~���[���c��I������̓]���_�Ƃ��āA�h�D�t�F�[���́A���}�h�ɂ�鍇�c�^�����g�g�݂��������A�s���ǂ̌v����蕔��ɐV�����l�ނ�ϋɓI�ɓo�p���āA�u�����Ƃ��Ă̐V�����s�s����v��(19)�v�����肵�Ă������B
�@�@(4)�@�@�V�����s�s�s���^�c�̊�{�����|�}���Z�C���Љ�}�̓���|
�@�@��㎵���N�ȍ~�A�h�D�t�F�[�����Ƃ�������́A�Љ�I��҂ւ̋~�ς̎��_���悭�������Љ�}�c���Ƃ����������͂ɁA�傫���ˑ��������̂ł��������Ƃ���A�T���}���R�ƃ������́A����ɂ���āA��ƉƂ����Ƃ̃N���A���e���X���Ƃ����h�D�t�F�[���s���ᔻ�����Ȃ��Ƃ������I�ɂ͂��킷���Ƃ��\�ɂȂ����Ƃ݂Ă���B�܂��A���̐�����A�u�Љ��`�v�Ƃ������́u��O��`(massisme)�v�ł���Ɲ�������������������A��㎵�Z�N�㖖�̎��_�ł��d�v�Ȗ��́A�Љ�}�̒����{�������シ�鐭��ƃ}���Z�C���Ǝ��̐���Ƃ��ǂ̂悤�ɒ��a������̂��Ƃ����_�ɂ�����(20)�B�����̖��́A��㎵��N�Ƀ��b�c�ŊJ�Â��ꂽ�Љ�}�������������ɁA��茻���̂��̂ƂȂ�B���Ȃ킿�A���̑��ł́A�~�b�e�����h�ƃ��J�[���h�E���[�����h�Ƃ̘H�����Ɋւ���c�_���������킳��A�Љ�}�u�V���E�f���E���[�k���A���̂Ȃ��ŁA���̋c�_���d��Ȗ�����N���邱�ƂɂȂ����̂ł���B�Ƃ����̂��A��q�̂悤�ɁA�h�D�t�F�[���̓~�b�e�������x�����闧����Ƃ��Ă����ɂ�������炸�A�}���Z�C���ł�SFIO���ォ��̊����̑唼�⌻�������Ƃ̉ߔ������A���[�������x�����Ă�������ł���B����̓}���Z�C���Љ�}�̑g�D�f����댯�Ș_���ł������B�������A�厖�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B�ꕔ�������āA�قƂ�ǂ̊����Ƃ������A�S�����ɂ����鏑�L���I���̌��ʂɉ�����(�}���Z�C���Љ�}����)�|�X�g�z�������҂��āA�}���Z�C���ɂ�����s�тȘ_�����������Ƃ̈�v�_����A�h�D�t�F�[���x���ɂ܂��������ł���B�����āA�~�b�e�������Ăя��L���ɑI�o����A�}���Z�C���Љ�}�ɂ����Ă��~�b�e�����h���哱�������邱�ƂɂȂ����B
�@�@�}���Z�C���Љ�}��������́A�|�X�g�̔z���ɍۂ��āA���[�������x�������}��(��r�I�}���̒��������o�[)�ւ̐��ق����߂铮�����݂�ꂽ���A�}�g�D�̎狌�h�Ƌߑ�h�Ŋu�Ă�ꂽ����������Ƃ����ϓ_����A�h�D�t�F�[���͂��������[�u���Ƃ�Ȃ������B�h�D�t�F�[���������Ȃ����|�X�g�z���Ɋւ��邱�̕ϊv(�h���Ɋ�Â��Ȃ��l���z�u)���A���ʓI�ɁA�ނ������i�߂悤�Ƃ��Ă����V��������̎��s��e�Ղɂ��A�ߑ�h�}�������͂��̐���Ɏ^�������B�Љ�}�u�V���E�f���E���[�k���A���̏��L���ɑI�o���ꂽ�~�V�F���E�y�[(Michel
Pezet)�́A���̏A�C�̂������ɂ����āA�}���Z�C���s�̎{��ɐӔC���Ă���s���NJ����Ƌٖ��Ɋ�������Ȃ��Ń}���Z�C���̖��������A�Љ�}�̓�������Ȃ��œ}�����}�h�Ԃ̘a����i�����B�������āA��㎵��N�A�s���ǂƃ}���Z�C���Љ�}�Ƃ̊ԂɁA�����̓��ꂪ�}����̂ł���B
�@�@(5)�@�@�V�����s�s�s���̉^�c��@
�@�@���ɏq�ׂ��悤�ɁA�����h(�n�[�h�ʂɊւ��s��)�ƎЉ�}(�\�t�g�ʂɊւ��s��)�Ƃ̊Ԃ̔C�����S���A���O�N�����㎵���N�܂ł̃h�D�t�F�[���s��������Â��鎩���̍s���g�D�̉^�c�X�^�C���ł���A�����ɂ�GAM�Ƃ������n���I������S���c�̂����݂��Ă����B�������A�T���}���R�ƃ������́A��㎵���N�̎��_�ŁA���̎s���^�c�X�^�C���͍��܂��A���͂�@�\���Ȃ��Ȃ����Əq�ׂĂ���(21)�B�����x���҂̑����������Ƃ��b�܂�Ȃ��K�w����\������Ă��邱�Ƃ���A��㎵���N�܂ł̃h�D�t�F�[���s���́A����o���}�L�^�̐���ɂ���Đ�߂��Ă����B�h�D�t�F�[���̌��т́A���������]���^�s���^�c�X�^�C���̌��������͂������_�ɂ���B���̔w�i�Ƃ��āA�����ł͎O�̗v��(�@��㎵���N�R�~���[���c��I���œ��I�����V�����Љ�}�c�������̌o���̐A�A�����̂̊����S�̂�������Љ�I����A�B�R�~���[�������ɋ������f�����o�ϓI��@)���w�E����邪�A�����ɂ́u�^�̌o�ϐ���v�ɗ��r�����V�����s�s����ƐV�����s���^�c�X�^�C�����v������Ă����B����ɂ́A�c��Ȏ��ԂƁA����ȍ���ƁA�[����含���K�v�Ƃ���邪�A�����ɁA�����I�ɂ݂�ł����ʂ����҂����̂ł���B�������A��㎵���N�ȑO�̎s�����c��������O�ʂɂ��Ă��s���Ǘ��ł������Ƃ���A����ȍ~�̎s���́A�n���e�N�m�N���[�g��������v�ȒS����ƂȂ������߁A���ʂƂ��āA�s���I��含�̘_���Ɛ����̘_���Ƃ̊Ԃ̑Η������ݏo����邱�ƂɂȂ����B
�@�@���i�Ȑ���v��ɂ́A������x���鋭�łȍs���g�D���K�v�ƂȂ�B��㎵���N�܂ŁA�}���Z�C���s�������̑Η��\�}���I�悳��邱�Ƃ͂Ȃ��������A���܂₻�ꂪ���炩�ɂȂ�������B���Ȃ킿�A��^�v���W�F�N�g���\�z����҂����Ƃ��������{����҂����Ƃ̑Η��ł���B�}���Z�C���̏ꍇ�A����́A�v��̍\�z��S������s�s�v�掖������s�s�J�������ǂ̂�����Ă���u���@����(Valmer)�v�Ǝs�����Ƃ̑Η��Ƃ��ĕ\�����ꂽ�B�����Ă��̑Η��́A���̓�̌��ۂɂ���ė��t������B���̂܂����́A���@���������Ē����h�ɔC���z������Ă����s�s�v���o�ϐ���̍\�z��Ƃ�S���Ă������Ƃ���A���@�����������I�ɕΌ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����Љ�}�c���̊���ł���B�������A�������������I�Ό����́A���قǖ��ɂȂ�Ȃ������B�ނ����荪�{�I�Ȗ��́A���̌��ۂƊ֘A���Ă����B���Ȃ킿�A���@�����̐��Ƃ�������̓I�Ȍ����������狗����u���A�l�X�Ȃ��������Ƃ����N���A���e���X���ɑ��Đ��I�ȗ�����Βu���悤�Ƃ���Ƃ��ɐ�����A����Ƃ��a瀂ł���B��̓I�ɂ́A���s�Ґ�p���Ə��Ɠ��ʋ��̗����\����A�o�X��ʐ������Z���̃G�S�C�X�e�B�b�N�ȗv���∳�͂ɏ]�����邩�����Ői�߂��Ă����댯���Ȃǂ����Ƃ��ꂽ���A���������v���S��������Ƃƒn���c���Ƃ̑Η��́A�s�s�R�~���[���̎{��𐄂��i�߂Ă�����ŏ�Q�ƂȂ����B����䂦�A��㎵���N�ȍ~�A�s�s�J�������ǂɂ́A������̊���������������^����ꂽ�B���������������ʂ������߂ɂ́A�����S������l�X�ɁA�v��̍\�z��S������l�X�̊�{�I�Ȗ�����F�������Ȃ���Ȃ炸�A�����̖�����������C�����s�s�J�������ǂɈ�C����邱�ƂɂȂ����B��̓I�ɂ́A���̂悤�Ȏ��g�݂��w�E�����B���Ȃ킿�A�s�s�v��ɂ�����鏔�����̒��a���͂��邽�߂̍�����c�̊J�Â�A����ŏd�v�Ȗ�����S���e����Ԃ̒������̐ݒu�Ȃǂ�����ł���B����ɂ���Ă͌����Ɣǂƍ\�z��ƔǂƂ𐅕��I�ȋ@�\�ɍĕҐ�����K�v�����������B
�@�@�����̒�����Ƃ��s�����߂ɂ́A�s�s�J�������ǂɈ�萔�̎��Ƃ̐ӔC�ƁA���̎��������^�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���������s���g�D�����������[�u�́A�������̊ϓ_�����łȂ��A�����I�E�����I�Ȋϓ_������K�v�ł������B�����ɂ͓�̃��x�������݂���B���Ȃ킿�A�܂����ɁA�s���g�D���x���̖��ł��邪�A��㎵���N�܂ŁA�v��̍\�z��Ƃ̂̂��ɁA���̐��I���e��S���Ȃ݂Ȃ��n���c�������ɂ�錈���Ƃ��s��ꂽ���߁A�v��\�z��S������`�[���̎m�C�͍��܂�Ȃ��܂܂ɂ�����(�y�n���e�v��̎���)�B��������㎵���N�ȍ~�A��܂��Ȑ����I����̂̂��A���̌v��̋�̉���Ƃ��v��\�z�S���`�[���ɗ^������悤�ɂȂ������ƂŁA�ނ�s�s�v��̐��Ƃ����̓��e�B���F�[�V���������߂����Ƃ��ł����̂ł���B�����ő��ɁA�����ƃ��x���̖��ł���B���Ȃ킿�A��㎵���N�����㔪�O�N�܂ł̊ԂɁA�}���Z�C���̒n���c�������ɗ^�����Ă����R�~���[������Ɋ֗^���錠�͂́A�ߋ��ɗ���݂Ȃ������̂��̂������̂ł���B����̋�̉��͐��Ƃ��s���Ƃ͂����A���̌v��̊�{�I�ȍl������Ӗ��ɂ��Č��肷�邱�Ƃ��A�{���̈Ӗ��ł̌��͂ł���B�����āA��U��̉��i�K�ɓ��������̂ɑ��Ēn���c��������������͂���Ȃ����Ƃ��A���Ƒ��̂��C�������Ȃ��Ƃ����_�ŏd�v�ł���B���̂悤�ȓs�s�s���^�c�̍Đ�����Ƃ�ʂ��āA�}���Z�C���ł́A�]���A�s�̍s���g�D�ɑ��Ă������e�N�m�N���[�g�����ᔻ�@���A�g�D���ɂ݂�ꂽ����ԁE�S���ҊԂ̃R���t���N�g�̉������ڎw���ꂽ�B�s���g�D���܂߂��}���Z�C���̓�������邱�ƁB����̓h�D�t�F�[������㎵�Z�N�㔼�ɗ��Ă������ڕW�ł���A�}���Z�C���Ƃ����s�s�^�Љ�̍��{�I�ω����v���������̂ł�����(22)�B
�@�@�ȏ�̂悤�ɁA�h�D�t�F�[���s���́A��㎵�Z�N��㔼�A�V�����s�s�s���̉^�c��@���m�����Ă������̂ł��邪�A�s�s�R�~���[���̎����I�^�c�\�͂��ؖ����邱�������u�����^�����̐���v�̊J�����A���������Ƃ̑Η��\�}���яオ�点�A�ŏI�I�ɂ̓~�b�e�����������ɂ����镪���E�Q���@�����v�̎����ɋɂ߂đ傫�ȉe����^���Ă������̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B���̓_�𖾂炩�ɂ��邽�߁A��O�߂ł́A�n�����{�̉^�������ƋK�͂̑���v�ւƌ������Ă����_�C�i�~�b�N�ȃv���Z�X���X�P�b�`���Ă������Ƃɂ���B
��O�߁@�@�h�D�t�F�[���̒n���������v��
�@�@�n���������v�𐄂��i�߂�͂��n�����{�����瓭���A�s�s�^�Љ�̐�����w�i�Ƃ���s�������̊��������邢�͓s�s�R�~���[���̎������^�����A���̉��v�̎�v�Ȍ_�@�ɂȂ����Ƃ��Ă��A���������������^�����A���ځA��K�͂ȍ��Ɖ��v�����Ƃ͂��蓾�Ȃ��B�����ɂ͉��炩�̓��������ԐړI�U�������K�v�ƂȂ�ł��낤�B�]���āA�����́A�n�搭�����x���ɂ����邱�������^�����A���ۂɂ͂ǂ̂悤�ɂ��Ēn���������v�Ƃ����@���x���v�ւƌ������Ă����̂��A����������Ȃ�A�n���������v���߂��鉺����̉^���Ɩ@�����Ƃ��A�t�����X�̏ꍇ�ɂ͂ǂ̂悤�Ɍ��т���ꂽ�̂��Ƃ��������𖾂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�@���̓_�ɂ��Ă����́A����t�����X�ɂ�����n�����������A��㎵�Z�N��ɂ�����ʒn�����{�̎������^��(�����^�����̐���̌`��)�����㔪�Z�N��ɂ����鍑�ƋK�̖͂@���x���v�ւƑ傫���W�J���Ă����Ȃ��ŁA����߂ďd�v�Ȗ������ʂ�������l�̒���҂��������ƂɋC�Â��B����́A�}���Z�C���s���A������b�����Ēn��������b�Ƃ����O�̊���������K�X�g���E�h�D�t�F�[�����̐l�ł���B�h�D�t�F�[���́A����̓s�s�s���^�c�̌o������A�n���������v���ǂ̂悤�Ɉʒu�Â��A���̖@������Ƃɂ����ɂ��ėՂ�ł������̂��B�ȉ��A�����̓_�ɂ��Č�������B
��ꍀ�@�@�}���Z�C���s�̌o�ω������
�@�@(1)�@�@�D���C���Ƃ̊�@
�@�@���܋�N�����㎵���N�܂ł̊ԁA�D���C���Ƃ̓}���Z�C���̂����Ƃ���\�I�ȎY�ƕ���̈�ł������B���̕���́A�`�p�֘A����̒E�H�Ɖ��̗���ɋK�͊g��ł͂Ȃ��T�[���B�X�̎��I���P�őR���A�}���Z�C���̍`�p����̓`��������Ă����B�������A��������炷�邱�Ƃ̈Ӗ��́A�D���C���Ƃɒ��ړI�E�ԐړI�ɊW����ٗp�̈ێ������ɂƂǂ܂炸�A�}���Z�C���s���ǂɂƂ��Ă��̍`�p���L���鑶�݈Ӌ`�̓_�ɂ����Ă��A�ɂ߂đ傫�����̂��������B�D���̏C���́A�n��̊C��A���ƌ��т����}���Z�C���ɏ]�����炠��`���I�o�ϊ����ł���A�Ƃ�킯�^���J�[�ɂ��A�����g�傷��Ȃ��A�`�p��ʂ̔��W���t�����X�̂Ȃ��ł��Ƃ�킯�}���Z�C���̑D���C���Ƃɏd�v�Ȗ�����^���邱�ƂɂȂ���(��㎵�Z�N���_�Ńt�����X�����̎��Z�����̃V�F�A)�B
�@�@�����őD���C���Ƃ��L�������̓��ꐫ�ɂ��Ċm�F���Ă����ƁA�܂����́A���ꂪ��̍`�ł������B�����Ȃ��Ƃ����_�ł���B�]���āA�C�������́A���ꂪ�u����Ă���`�p�̗A�������ƁA����ɂ́A�T�[���B�X�̎��̌���ւ̘H���]���ɁA��{�I�ɂ͈ˑ����Ă���B�}���Z�C�����A���[���b�p�ɂ�����d�v�ȐΖ��A����n�ւƕϖe���Ƃ������Ƃ́A���Z�Z�N�ォ���㎵�Z�N��O���ɂ����āA�|���g�K���A�C�^���A�A�X�y�C���A�M���V�A�Ƃ��������̋�������ɑ��A�}���Z�C���̑D���C���Ƃ����Ȃ�D�ʂȏ����̉��ɒu�����B�����āA�}���Z�C���ɂ�����D���C���́A�C��A���ɋ��߂��鏔���������Ă����B�T�[���B�X�Ɛݔ�(���Z���g���܂ł̑�^�^���J�[������\)�̍������́A�Ɛт̌���݁A��㎵��N�ƈ�㎵��N�ɁA���ꂼ���Z�Z�ǂ��̃^���J�[���}���Z�C���Ń����e�i���X�����B
�@�@�������A���������}���Ȋg��́A�����̂̂��ɂ���Ă��鏔�����B�����邱�ƂɂȂ����B�}���Z�C��������ɂ������߂ɕK�v�ȑ�K�͂ȓ����́A�Ƒ��o�c���哱�I�Ŏ��ȓ����ɗ����Ă���}���Z�C���̑D���C���Ǝ҂����ɁA���͂Ȏ����͂�v������悤�ɂȂ����B���Ȃ킿�A�e�����E�O���[�v���N���]�E�����[���ƒʏ������������A�C�O�̌@�p�D����D���p���啔�i�ȂǏ��X�ɃT�[���B�X�Ώۂ𑽗l�����������A����ł͕s�\���ł������B�����̊�Ƃ́A�ۉ��Ȃ��ɍ��ۓI�����̂Ȃ��ւƈ������܂�Ă����B�����āA�s��̈ꕔ�ɕ����]���������炷�悤�ȋ������肪�A���X�ƌ��ꂽ�B�I�C���E�V���b�N�ɔ����^���J�[�A���Ƃ̊�@�́A�D���ƂɂƂ�킯��Ō���^�����B��㎵���N�A�e�����E�O���[�v�͂��ɔj�Y����B���̋���O���[�v�̏��łƑD���C���Ƃ̑�s���ƂƂ��ɁA�`�p�Ɋ֘A����o�ϊ����̐��ނ��A�}���Z�C���ɂ����Č����̂��̂ƂȂ����B���̏o�����́A�`�p�������̂��̂ւƔg�y���A���̓s�s�̒E�H�Ɖ��v���Z�X�������������̂�����(23)�B
�@�@(2)�@�@�}���Z�C���s�̋~�όv��
�@�@��㎵���N�㌎��l���A�Վ���Ƃ��ď��W���ꂽ�}���Z�C���s�c��́A�h�D�t�F�[���s�����c��ɕt�����Ă������c��S���v(�����[�������ܔ��[)�ō̑������B���̗Վ���́A�D���C���ƊE(�Ƃ�킯�A���̍ő���ƃe�����E�O���[�v)�̋~�ύ�ɂ��ĐR�c���邽�߂ɏ��W���ꂽ���̂ŁA���Y�}�c���c���܂ތܖ��̎s��c�������������B���E�����h��(��㎵���N�㌎��Z���t)�́A���̃j���[�X���u�}���Z�C���s�A�e�����E�O���[�v�̍Č��ɂ��Ď��ƉƂƌ��ցv�Ƃ̌��o����t���đ傫���Ă���(24)�B
�@�@�}���Z�C���s���������O�ɗ\�����Ă����u��̓I�{��v�̑S�e�́A���̗Վ���ɂ����Ė��炩�ɂ��ꂽ�킯�ł��邪�A���́u�~�όv��v�ɂ��A�e�����E�O���[�v���܂ޏ���Ƃɍ��Y�̐��Z���鍐���ꂽ�ꍇ�A���Y�����ɕK�v�ȍ��Y�E���Y�E�s���Y�̔����߂����}���Z�C���s�������Ȃ��A�����̊�Ƃ̊����ĊJ�ƊǗ�����Ȃ��������̎��ƉƂɈϑ�����Ƃ��Ă����B�}���Z�C���̑D���C���Ƃ͍ċN�s�\�Ǝv����قNJ�@�I�ȋǖʂɂ��������Ƃ���A�h�D�t�F�[������o�������̌v��́A�ċN���������Ō�̃`�����X�ł���Ƃ������B
�@�@�܂��A���̌v��ɂ��A�܃����ԑ��Ƃ��~���Ă����`�^���E�R�f�@�B���݃O���[�v�������ĊJ���\�ƂȂ����B���Ȃ킿�A���Z����邱�ƂɂȂ��Ă������Y(��Z�w�N�^�[���̓y�n�A���Y��i�A�s���Y)���A�}���Z�C���s���܁Z���ȏ�̊������L����u���X�s���Y�����o�ϊ������(SAIEMB)�ɂ���Ĕ����߂����̂ł���B���̂��ƁA�����̎��Y�́A�x�����B�������В��߂�T���E�}���Z������H�ƂɈϑ����ꂽ�B
�@�@�h�D�t�F�[�������̗Վ���̐R�c�Ŗ��炩�ɂ����Ƃ���ɂ��A���̐������̊ԂɁA�u�e�����������A���Y��l�ނ̊g�U��������邱�Ƃ̂ł�����ƉƂ��邢�͎Y�ƃO���[�v���A�D���C���ƊE�ɂ����Ċ��Ɏ��т��グ�Ă���Ƃ��납��A�܂����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�̂ł���A�}���Z�C���s���Ԃɓ��邱�ƂŁA���@�I�u�ו����v��j�~���邱�Ƃ��v������Ă����B�}���Z�C���s�́A���̂Ƃ��A���H��c���A�}���Z�C���`�p�g���A���̒n���o��@�ցA�����ċ��Z���ɂȂǂƋ��͂��āA�}���Z�C���o�ςɂƂ��Đ������ƂȂ��Ă���Y�ƕ���̋~�ς������Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B
��@�@�n�������̂ɂ��o�ω������̈Ӗ�
�@�@(1)�@�@�o�ϓI���_
�@�@�T���}���R�ƃ������́A��㎵���[���O�N�Ƀ}���Z�C���s���ǂ��Ƃ����o�ω��������u���Y��i�̋~��(sauver des outils)�v�Ƒ�����(25)�B���̐���Ɋւ���ނ�̂��������c���̎d�����肪����ɂ��Ȃ���A�h�D�t�F�[���s���̉��Ői�߂�ꂽ�o�ω������̌o��(����)�I�Ӗ��ɂ��Ė��炩�ɂ��Ă����B
�@�@�u���Y��i�̋~�ρv�Ƃ́A�����Ӗ�����̂��B�ނ�ɂ��A����͎��̂悤�ɐ��������B���Ȃ킿�A���Y��i���~�ς��邽�߂̎{��͋ɂ߂đ��l�ɑ��݂��邪�A�����͂��ׂāA�}���Z�C���ɋ��łȌo�ϓI�E�H�ƓI�l�b�g���[�N���ێ����悤�Ƃ���ӎv�ɂ���ē����Â�����A�ƁB����̓I�ɂ́A�`�^���E�R�f�Ђɑ��čs��ꂽ�悤�ɁA������~�ƂȂ��Ă����Ƃ̊����ĊJ����������B�������A���������{��͒����I�ɍs���Ȃ���ΈӖ��������Ȃ��B���̓_����A���̓�̗D��I���w�E�����B���Ȃ킿�A�܂����̗D��I����͊C�`�̖����Ɗ֘A���Ă���A�}���Z�C���ɂ����邠����o�ϐ헪�͊C�`�����ɂ͍l�����Ȃ����䂦�ɁA����ł̓��B�g���[���ɍ`�p�s�s�����݂��A�����ł́A���H��c���̈ӌ��ɓY���������ŁA�G�b�\�̏��L�n���^�d�ʕ��A����e�Ղɂ��邽�߂̕s���Y�Ƃ��ėp���邽�߁A���̓]�p�̍����~�߂����肳�ꂽ�̂ł���B�����đ��̗D��I����́A�}���Z�C���n��o�ς̊�Ղł��钆����Ƃ̖L�x�ȃl�b�g���[�N���ێ����邱�Ƃł���A�����ł͓y�n������I�Ȗ������ʂ����Ă����B�܂�A���ɂ́A����Ƃ��L����}���Z�C���O�|�Ƃ�킯�A�G�^���E�h�D�E�x�[���|�ւ̎u���Ɏ��~�߂�������ׂ��A�H�Ɖ�����Ă��Ȃ��y�n��y�n�̏����A����ɂ͔_����Ƃɑ���y�n���@�̗}�����K�v�ł������B�����āA�Y�Ɨp�n�����������A��ƗU�v�ɂ���Ă��̗p�n�����p���A�����̊�Ƃ��~�ς��邱�Ƃ́A�ߋ��ɂ����Ă����݂ɂ����Ă���̊�{�I�ڕW�ƂȂ��Ă���B���ɂ́A������Ƃɑ��������i��F�߂Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��Ƃ���������A��Ƃ��g�傷�邽�߂̌ܔN�ԕԊ҂��P�\�����Z���Ɋւ���f�N�����A�}���Z�C�������O���Ă������Ƃɂ��������悤�ɁA���̕���ɂ�������āA�~�b�e�����ȑO�̒������{�̓}���Z�C����S���Ƃ����Ă悢�قǖ������Ă����B����䂦�s���ǂ�DATAR�Ƃ̌��ɏ��o���A���ɐ��������߂�B�����āA�f�N�������\�����ƁA�}���Z�C���s�c��͑��������̕ԊҗP�\�Z�������F�����̂ł���B�܂��A�����̐��Y��i���v�V���邱�Ƃ��d�v�Ȑ헪�ł������B����䂦�A��㔪�Z�N��ɂ����镪���E�Q���@�����v�ȑO�̋ɂ߂Č��肳�ꂽ�����̂̊����͈͂̂Ȃ��ŁA��̐����肳�ꂽ�B�܂�����͍`�p�ɂ��������̂ł���A���Y�����ւ̓�����ʂ����D���C���Ƃւ̉����₻�̋ߑ㉻�Ƃ����n��o�ϐ���̂Ƃ�킯�d�v�Ȏ�i�Ƃ��Đ���������邱�ƂɂȂ�B�����ł́A�C�Ɋ֘A���邠���銈���ւ̉����ł���A�Ō�ɁA���Y������e�Ղɂ��邽�߂̃C���t���X�g���N�`���[�̐����ւ̉����ł���B�܂��ɂ�����������̘g�g�݂ɂ����āA���Ղɂ�����邷�ׂĂ̑�O���Y�Ƃ��ĕ҂��邽�߂́u�n���C���ی��ՃZ���^�[�v���J�݂��ꂽ�B�o�ϊ�������芪���ȏ�̂悤�Ȋ������Ȃ����āA�`�p�̔��W�͂��蓾�Ȃ������̂ł���B
�@�@(2)�@�@�����I���_
�@�@�n�����Ƃ̓|�Y�́A���Ɩ��Ƃ����`�Œn��Љ�̕s���艻���������̂ł��邾���ɁA�n���n�������̂ɂƂ��ẮA�����̊�Ƃ��ǂ̂悤�ɋ~�ς��Ă����̂����A����߂ďd�v�ȊS���ƂȂ�B��㎵�Z�N��ɂȂ�ƁA�敾���v���ȑΉ��̂ł��Ȃ����Ƃɑ����āA�s�s�R�~���[���A�s�s�����́A���A�����ă��W�I���܂ł����A�ٗp����邽�߂̂��������ɎQ�킷��悤�ɂȂ��Ă���B�S�[���X���̊�{����̈�ł��鍑�Ƃɂ��o�ω�������̌��E�ɒB���A�n�����{�̑�����łĂ��������̓����́A�]���̏W���I�����`�ɑ���A����u�����I�����`�v�ƌĂԂׂ����̂ł���(26)�B
�@�@�}���Z�C���s���ǂ��{�i�I�Ȍo�ω������ɏ��o���Ă������̍��A�u���^�[�j���n���̃u���X�g�s�s�����̂͑�K�͑D���̏C�����Ƃ����H��c���Ƃ̋����ŊJ�n���Ă������A�u�U���\���s�́A�����ƂɈ�Z�w�N�^�[���̓y�n��^���A���S���t������݂��t����Ƃ���v���W�F�N�g�ɁA���O�Z������|�̒�Ă����Ă����B�����̉������́A�m���ɊԐړI�Ȃ��̂ł͂��������A����I�ȈӋ`�������Ă����Ƃ����_�ł͒n���Z�������Ɏ��������̂ł������B�Ƃ����̂��A�ÓT�I�ȍ��L���Ƃ͈قȂ�A�n�������c�̂��s���ɑ��Ă����Ȃ��{��́A���Ƃ̂�������~���ŁA�����̂��͂����肵�Ă�������ł���B����ł��}���Z�C���̏ꍇ�A�~�όv��̑ΏۂƂȂ��Ă������D�Ƃ�D���C���Ƃ������Ƃ��Ă͂���߂Đ��Y���̒Ⴂ����ƂȂ��Ă���A������������ւ̌��I���������͐ŋ��̖��ʌ����ł���Ƃ̔ᔻ�����蓾���B�������A���琢�т��̉ƒ낪���������Ƃɂ������A�t�H�X�ՊC�H�ƒn�т̎Y�ƐU�������s�ɏI������ł́A���^���x�������߂ɒn���ł�s�̍����������{����J�n�������Ƃɂ��āA�h�D�t�F�[������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�܂�A�o�ς̐��Ƃ������l��������̏퓹���炷��A�}���Z�C���s�̎{��͔ᔻ�����ł��낤���A�[���Ȏ��Ɩ��ɒ��ʂ��������̐ӔC�҂������܂����ɖڎw���ׂ��́A�����ɍ���Ȃ������I�������d���邱�Ƃł͂Ȃ��āA�ނ���A���v���ɎЉ�����������邱�Ƃɂ������B�ꎞ�I�Ɋ��͂������Ă��鏔��Ƃ��ێ���������A���ƎґS���ɕ⏞�����x�����������A�n�������c�̂ɂƂ��Ĕ�p�����Ȃ��čςނȂǂƘ_�ł���҂́A��l�Ƃ��Ă��Ȃ������̂ł���B
�@�@�����̃}���Z�C���n��Љ���ʂ��Ă����ۑ�Ɋӂ݂�Ȃ�A�h�D�t�F�[���̑I���͑Ó��Ȃ��̂ł������ƕ]�������Ƃ��Ă��A�S����Q���Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B����́A�������{�A�Ƃ�킯�A�h�D�t�F�[�����̂��ɑ�b�߂邱�ƂɂȂ�����Ȃł������B�R�~���[���ɑ���㌩�ē������Ȃ��Ă��������Ȃ̒n���o��@�ւ́A�s�s�R�~���[����W�I�����A���ځA�o�ϊJ�������S�����Ă��邱�Ƃɕs�M�̖ڂ������Ă����B�H��ɉۂ���鎖�ƖƋ��ł��y��������A�ʋΓ��H��J���҂̂��߂̏h���{�݂����݂�����A��㐧�̍H��ɗZ�����邱�Ƃ͋�����Ă��A�n�������c�̂������ƂɎ��{�Q�����邱��(�}���Z�C���̃e�����E�O���[�v�̏ꍇ�A��O��)�͕ʂ̖��Ƃ��ꂽ�B�����̃R�~���[���c��ɂƂ��đ��ނׂ��́A�|�j�A�g�t�X�L�[����(����)�����m�����ɑ��t������㎵�Z�N�㌎��Z���̒ʒB�ɋL���ꂽ�A���̓��e�ɂ���B���̓����́A���̂悤�Ȏw�����o���Ă����B���Ȃ킿�A�u����Ƃ̊���������ւ̒n�������c�̂̒��ڊ֗^��F�߂�Ȃ�A���ʂ�������x�\�z����鋣�������シ�邱�ƂɂȂ�B�]���āA�T���ȃR�~���[���͂��T���ɂȂ�A�n���ȃR�~���[���͂��n���ɂȂ�ł��낤�B���̂��Ƃ͂܂��A���ʂ�������点����A�s��̎��s����������Ƃ������댯�ɁA�n�������c�̂Ə���Ƃ����炷���ƂɂȂ邵�A�[�Ŏ҂��������̋]���ƂȂ�ł��낤�B�]���č��̂Ƃ���́A�s�s�ĊJ���Ɋ֘A���鍬���o�ϊ�Ƃ̌����ɂ��Ă݂Ă��������ł悢�v�ƁB���̂悤�ȁA����(�����Ȓ�)�ɂ��o�ϐ���̓Ɛ�Ƃ������z�́A����t�����X�I������ттĂ��邪�A���̂��Ƃ́A��q����h�D�t�F�[���@�̋c��R�c�ߒ��ɂ����Ă�薾�m�Ɍ���邱�ƂɂȂ낤�B
��O���@�@�������n��������b
�@�@��㔪��N�Ƀ~�b�e�������哝�̑I���œ��I���ʂ����A�t���l�������ƂȂ����B���ǁA�̓��[���������߂邱�ƂɂȂ�A�h�D�t�F�[���͓������n��������b�ɔC�����ꂽ�B��㎵�l�N�̑哝�̑I���Ƀ~�b�e���������I���Ă�����A�h�D�t�F�[�����ɔC������Ƃ̖����Č���Ă����Ƃ����邪�A��㔪��N�̎��_�ŁA���̖͂��łɉߋ��̂��̂ƂȂ��Ă����̂ł���B�������A���̓앧���\����啨�����Ƃɂ́A������ʂ̖ڕW���������B����́A�ꌾ�ŏq�ׂ�Ȃ�A�}���Z�C���s���Ƃ��Ē����W�����ƂƑΌ����Ă������j�ɋ������A�����S���҂̈�l�Ƃ��Ď���̔O��ł���n���������v����������Ƃ������Ƃł������B
�@�@�W�����W���E�}���I���́A�h�D�t�F�[���̐��U��Ԃ����w�K�X�g���E�h�D�t�F�[���x�̂Ȃ��ŁA�h�D�t�F�[�����~�b�e���������̐V�����ɏA�C����ہA�n���������Ƃ����傫�ȗ��z�̎����ɕ��X�Ȃ�ʏ�M��R�₵�Ă������Ƃ��w�E���Ă���(27)�B�~�b�e��������㔪��N�̑哝�̑I���ɂ����ď����I���ʂ�������㔪��N�܌���Z������O����A�h�D�t�F�[���̓r�G�[�����ʂ�ɂ���~�b�e�����@��K�ˁA�g�t��Ƃɓ����Ă����V�哝�̂ɑ����̂悤�ɏq�ׂ��Ƃ����B
�@�@��㎵�l�N�̑哝�̑I���̍ہA���Ȃ��́A�����̋łɂ͎����Ɏw�����邨����ł���ƌ����A���͂�������������B���ꂩ�玵�N�ȏ�̔N�����߂����������A���͔N���Ƃ�A���܂�ɂ�����ł��B���́A���[�������Ɏw�����邱�Ƃ��Ă������B���́A������b�̃|�X�g������������Ώ\�������ł��B�����ɂȂ�A�n�������������{���邱�Ƃ��ł���̂�����A��(28)(�����͈��p�҂ɂ��)�B
�@�@�t�����X�ɂ�����n�������v�z�̗��j�͒����A���Ȃ��Ƃ���㐢�I�O���܂ł����̂ڂ邱�Ƃ��ł���ƌ�����(29)�B���������ɑ��͂ł݂Ă����悤�ɁA���Z�Z�N��ȍ~�l�X�Ȏ���I�����N���u�ɂ���Đςݏd�˂��Ă������c�̂Ȃ�����A�����I�Q���f���N���V�[�Ƃ����l�������A�t�����X�����̂Ȃ��Œ蒅���Ă����B�����āA�h�D�t�F�[�����g���������n�������_�҂̈�l�ł������B�������A�ނ��n�������_�̐M��҂Ƃ��āA�@���x���v�̃C�j�V�A�e�B�����Ƃ�Ɏ���w�i�ɂ́A������Ȏ���������ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿�A�}���I�����w�E���Ă���悤�ɁA��s�s�̍ō��ӔC�҂Ƃ��Ĕނ́A�}���Z�C���ɂ����Č��m�����ނɉۂ��Ă����s���I�E�����I�������ǂ����Ă��䖝�Ȃ�Ȃ������̂ł���B���������p������̊Ď��̑��݂��A�ނɂ͂ƂĂ��Ȃ��ߏd�Ȃ��̂Ɏv���邱�Ƃ��������B�����A�\�Z�A�����A�s�s�v��ȂǁA�ǂ��Ƃ��āA�s���̍ٗʂɂ����čs������̂͂Ȃ������̂ł���(30)�B
��l���@�@�h�D�t�F�[���@�̋c��R�c�|��̏d�v�_�_�|
�@�@�~�b�e�����������ɂ����镪���E�Q���@�����v�̊�{�@���锪��N�@�́A��㔪��N��������ɍ����c��܂����̖@�Ă��̑����A�����ŏ�@���C���̏�A��Z�����ɓ��@�Ă��̑����A���̌�A���c��Ԃł̏C�����킪�J��Ԃ���A�ŏI�I�ɂ́A������炨�悻�ブ����̈�㔪��N�O���ɐ�������B�����_���́A�h�D�t�F�[���̂��̐v���ȋc���^�c���u�d����(blitzkrieg(31))�v�ƌĂ�ł��邪�A����͒P�ɂ��̐v�����䂦�ł͂Ȃ��B�h�D�t�F�[���́A�O�����̂��ƂŁu�n�������c�̐ӔC�������i�@�āv���p�ĂɏI��������������̋��P�Ă����̂ł���B���āA���̖@�Ă�������ꂽ�ہA�Љ�}�͂���ɑΈĂ��o���A���̎�|�����ɂ͓������L���������t�����\���E�~�b�e�������������B�~�b�e�����́A�W�X�J�[���f�X�^���̉��v�̐i�ߕ���ᔻ���āA���̂悤�ɏq�ׂ��Ƃ����B���Ȃ킿�A�n���������v����������̂́A�����W���I�ȁu�V�X�e���S�̂̃o�����X�����f�B�J�����v���ɒf�₳����ꍇ�̂݁v�ł���A�u���Ƃ�������v���߂ɂ́A�u���̎�v�Ȏ�v�ҁA�Ƃ�킯�A�n���c���ƂȂ�ɈႢ�Ȃ��l�X�v��r�����邱�Ƃ͔����A�u�����W�����̗l�X�Ȍ����͂�j��v�Ɠ����ɁA�u�\�����v���ɓW�J����v���Ƃ����߂���A��(32)�B�v����ɁA�n�����x���v�ɂ������V�@��������c�������ɏ��F�����邽�߂ɂ́A�ނ�̑��������E���Ă���n�������̂̑�\��(�Ƃ�킯�A�s�s�R�~���[���̃��[��)�Ɏv�����āu�����Ǝ��R�v��^���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł���B�s�s���̖��]�Ƃ����̓������Ӑ}����A�ނ̋c��헪�́A�K�R�I�ɁA�_���R�~���[���������鏔���̉��������A�ނ���A�s�s�R�~���[���̒n�挠�͋����D�悳��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���(33)�B
�@�@�����_���ɂ��A���ǁA�c��R�c�̂Ȃ��ōŌ�܂ŗ��@(�哝�̗^�}���ߔ����𐪂��鍑���c��Ɖߔ����������Ă�����@)����v�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ������_�_����������B���Ȃ킿�A��͌��m���ɂ��㌩�ē��̔p�~�̖��ł���A������͊�Ƃɑ���n�������c�̂̎x���̖��ł���(34)�B�������čŌ�܂Ŏc���ꂽ�_�_�����A�h�D�t�F�[���������ď��邱�Ƃ̂Ȃ������A���̉��v�̍ŏd�v�ۑ�ł������ƍl������B�ȉ��A������̘_�_�ɂ��Ă݂Ă����B
�@�@(1)�@�@���m���ɂ��㌩�ē��̔p�~���
�@�@�㌩�ē��̔p�~���K�肵���h�D�t�F�[���@�Ăɑ��āA��@�́A�ŏI�i�K�܂Ŕ��̎p�����т����B�����S�ʓI�ɔp�~���邱�ƂɂȂ�A�_����A�n�������c�̂Ɏ��s���@�\�����F���邱�ƂɂȂ邽�߁A�㋉�@�ւɂ��㌩�ēƂ����P�̉��ɂ���Έ��Z���Ă����㏬�R�~���[���̃��[�������́A���̔p�~�ĂɌ��O������Ă����B�����āA���������㏬�R�~���[���̃��[�������̗�����\���Ă����̂��A�܂��ɁA��}�����̏�@�c�������ł������B���̂悤�Ȏ狌�I�E�`���I���͂̃m�X�^���W�[�́A�h�D�t�F�[���@�Ă̊�b�ɂ���u�ӔC�̌����v�Ɩ�������������Ȃ������B�������A���m���ɂ��㌩�ē��̔p�~�Ƃ����h�D�t�F�[���̂܂��ɐM�O�ɂ�������{���j�́A�Ō�܂Ŋт��ꂽ�B�Ȃ��Ȃ�A���Ɗ����ƒn�����]�Ƃ̑R���ɂ����Ēn���������������i�߂��Ă����ȏ�A���ꂪ�h�D�t�F�[���@�Ă̊j�S�����ɑ��Ȃ�Ȃ���������ł���B
�@�@�Ȃ��A��㔪��N�ꌎ���ɍ����c��ōŏI�I�ɍ̑����ꂽ���̖@���ɑ��A��}�c������(���a���A���̔��O���̍����c��c���ƁA�����h�����̋㔪���̏�@�c��)�́A���@�@�ւ̒�i�Ƃ����R��i�ɏo�邱�ƂɂȂ邪�A���@�@�́A���̖@�Ă̈ꕔ�ɂ��Ĉጛ�������o�������̂́A���̑S�̓I�̌n�ɂ��Ă͍����Ƃ���(35)�B
�@�@(2)�@�@��Ƃɑ���n�������c�̂̎x��
�@�@��q�̂悤�ɁA�h�D�t�F�[���ɂƂ��āA����͊��Ƀ}���Z�C���s���Ƃ��Ď��炪���s���Ă����R�~���[���̌o�ω�����A�����Ȃ̗l�X�Ȍ㌩�ēƂ̑R�̂Ȃ��ň�@�̋^��������Ƃ���Ă������Ƃ���A�����̍s�ׂ��A����N�@�̐����������č��@������_����������(36)�B�c��R�c�ߒ��ł́A����N�@�Ă̑�l��(�ŏI�I�ɂ́A����Ƃ��ĉ��E����)�̓��e���߂���A����߂Ċ����ȋc�_���������킳�ꂽ�B
�@�@����N�@�Ă̑�l���́A�w�s�����@�T�x�̈������Z���ƈꔪ����ꔪ���̈�l�Ɏ��̂悤�Ȉ�i����������������̂Ƃ���Ă����B���Ȃ킿�A�u�R�~���[���c��́A�R�~���[���Ɩ��̒T���Ƃ����ړI�������Ȃ��c����ړI�Ƃ���������Ђ⑼�̂������Ƃւ̂����鎑�{�Q���������A���Y�R�~���[���Z���̌o�ϓI�E�Љ�I�����v�̗i��ɕK�v�ȏ��[�u���Ƃ邱�Ƃ��ł���B�������A�����̉�����A���ƌv������F���闧�@�ɂ����Ē�߂�ꂽ���y�����Ɋւ�鏔�K���Ɉᔽ���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƁB�����āA�����́A���̂悤�ɒ�߂Ă���B���Ȃ킿�A�u�R�~���[���Z���̌o�ϓI�E�Љ�I�����v�̗i�삪�v����������ɂ����āA�R�~���[���́A����Ɋׂ�������ƂƂ̊Ԃɒ����������肪��߂�X���̂��߂̏��[�u�����{���ׂ��A���Y��Ƃɑ��钼�ړI�E�ԐړI�ȉ��������F���邱�Ƃ��ł���v�ƁB
�@�@�����c��(��㔪��N�Z����)�̐R�c�ŁA���̑�l���̓��e�Ɍ��O��\�������W���b�N�E�g�D�{��(Jacques Toubon)���}(���a���A���A�t�����X����A��)�̋c���ɑ��A�h�D�t�F�[���́A�}���Z�C���s�ɂ����鎩��̌o��(�`�^���E�R�f���@�B��A�e�����E�O���[�v�ȂǑD���C���ƊE�ɑ���~�ϑ[�u)��y��ɂ��Ȃ���A���̏ɑ���m��I�ȗ����ϋɓI�ɕ\�����Ă���(37)�B�܂��A��@�c���������A�o�c���s���l�܂�����Ƃɑ��ăR�~���[�����@�I�E�����I�{����Ƃ�Ƃ��邱�̑�l���̓��e�ɂ��āA�ɂ߂ď��ɓI�ł������B�ɓ��m�ꎁ�ɂ��A���̖����߂����Đ��{�E�����c��Ə�@�Ƃ�Η��������v���́A�u���v�̌��ʂɑ��錩�ʂ��̈Ⴂ�v�ɂ������Ƃ����B���Ȃ킿�A�����c�(���V���[�������c��@�ψ����)�́A�ߋ��̓s�s�R�~���[���ɂ�������тɊ�Â��A�ނ�R�~���[���c�������̃C�j�V�A�e�B���Ɂu���邢���ʂ��v���������̂ɑ��A��@��(�W���[��@���@�ψ����)�́A�ɂ߂ĈÂ����ʂ����������̂ł���B�u�n�������c�̂̌o�ω���v�ɑ���W���[�̔ᔻ�I���_�́A�ȉ��̂悤�ɗv���B���Ȃ킿�A�������ɃR�~���[���́A�n���̎���ɋ߂����A�������A�߂����āA�Ɛѕs�U��Ɖ��������߂�J���҂Ȃǂ̒n�搢�_�ɑ���\���ȓƗ����������������B�܂��A�R�~���[���ɂ͌o�ϓ����̕��́E�\���\�͂��Ȃ��A���������̉��������ʋ������ɂȂ�댯���傫���B�S���I�ȎY�Ɣz�u�v��ƒ��a���Ȃ��R�~���[���P�ʂł̉���́A�R�~���[���Ԋr�����g�傳�������ł���B���ǁA�n��̎���ɉ����炸�߂������A�n��Z����̐��_�̈��͂�����Ɨ����A����ѐ����鐭�����s�\�͂����L����n�������c�̂Ƃ��ẮA���W�I�����œK�ł���A��(38)�B
�@�@�ނ́A�u�h�D�t�F�[���@�āv�ƌĂ�邱�̐��{��o�@�āi�v���W�F�E�h�D�E�����j�̒�o��(�������n�������S����b)�Ƃ��āA��������̖����c���ł��낤�B����������ȏ�ɏd�v�Ȃ��Ƃ́A�ނ��A�}���Z�C���̐�s������c��ɓ`����u�`�B�ҁi�|���g�D�[���j�v�Ƃ��Ă̏d�v�Ȗ������ʂ������Ƃ����_�ł���A����ǓI���_�ɂ��ĂA�n�����{�̎������^�����W�J���ꂽ��㎵�Z�N��ƕ����E�Q���@�����v�����{���ꂽ��㔪�Z�N��Ƃ����т���u����ҁi���f�B�@�g�D�[���j�v�ł������Ƃ����_�ł��낤�B
(1)�@�@Philippe Sanmarco - Bernard Morel, Marseille�Fl'endroit
du decor, Edisud, 1985, p. 87.
(2)�@�@ibid., p. 87-130.
(3)�@�@ibid., p. 119.
(4)�@�@Philippe Sanmarco - Bernard Morel, Marseille�Fl'etat du futur, Edisud,
1988, p. 15-48.
(5)�@�@ibid., p. 19.
(6)�@�@ibid., p. 33-34.
(7)�@�@ibid., p. 34.
(8)�@�@ibid., p. 46.
(9)�@�@ibid., p. 46-47.
(10)�@�@Philippe Sanmarco - Bernard Morel, op. cit., 1985, p. 163.
(11)�@�@�����ł́A��ɁA���̂��̂��Q�Ƃ����BJean�|Francois Sirinelli, Dictionnaire historique
de la vie politique francaise au XXe siecle, PUF, 1995, p.
276-278.
(12)�@�@���̓����̃h�D�t�F�[���́ASFIO�Ƌ��Y�}�Ƃ����悤�Ƃ����Ăɂ������Ă����Ƃ����Bibid., p. 277. �������A��q����悤�ɁA��㎵��N�ɎЉ�}�̍��V��Ƃ̐擪�ɗ������~�b�e�������Ћ������H�����Ƃ������Ƃ���A�h�D�t�F�[���͂ނ���A�����I���y�̋��������}���Z�C���Љ�}�̊����Ƃ����ɁA���̐V�H�������F�����闧��ɗ��������̂ł������B
(13)�@�@�h�D�t�F�[����������E�Ƃ��ẮA��������(���l�Z�N)�A�C�^�S����b(���܁Z�[�܈�N)�A�M�E�������t�̊C�O�̓y�S����b(���ܘZ�[���N)�Ȃǂ�����Ƃ����B���̍Ō�̑�b�E�ɂ��������ܘZ�N�Z���A�ނ́A�u�A�t���J�ɑ��݂���t�����X�̐A���n�̑Q�i�I�����e�Ղɂ����{�@(loi�|cadre)�v�𐬗������Ă���Bibid.,
p. 277.
(14)�@�@�n粌[�M���ɂ��A���̂Ƃ��h�D�t�F�[���́A���Z�ܔN�I���̍ۂƓ��l�A�u�����A���H���v���咣�����Ƃ����B�������A�u�Љ�}�̒��V�M�E�����́A�h�S�[���h�ɑR����ɂ̓h�D�t�F�[���ȊO�̒����h�̌���i������K�v������Ƃ��āA���Ǐ�@�c���̃A�����E�|�G�[�������[�ł̍����̓��[��������Ŕ��h�S�[���h������`�̖��̉��Ɍ��҂ƂȂ����v�Ƃ����B�n粌[�M�w�t�����X�j�x(�����V���A���㔪�N)�A��Z�Z�ŁB
(15)�@�@Philippe Sanmarco - Bernard Morel, op. cit., 1985, p. 146.
(16)�@�@ibid., p. 148.
(17)�@�@ibid., p. 165.
(18)�@�@���̓����A�t�����X�S���Ŋ�����W�J���Ă���GAM�ł͂��邪�A�}�h�I�u�����͊e�n��ɂ���ĈقȂ��Ă����B�����āA�����Ɏ��グ��ꂽ�}���Z�C����GAM�ƁA�{�e��O�͂ɂ����Č�����������Ǘ��Љ��`���u������O���m�[�u��GAM�Ƃ̊Ԃɂ́A�����I����̓_�ł��Ȃ�̕����F�߂���B
(19)�@�@Philippe Sanmarco - Bernard Morel, op. cit., 1985, p. 167.
(20)�@�@ibid., p. 167.
(21)�@�@ibid., p. 168.
(22)�@�@ibid., p. 170-172.
(23)�@�@ibid., p. 78-79.
(24)�@�@Le Monde,�hLa ville de Marseille devra ne�Lgocier avec les industriels
la relance du groupe Terrin, Jean Contrucci, 16 Septembre 1978, p. 30.
(25)�@�@Philippe Sanmarco - Bernard Morel, op. cit., 1985, p. 139-141.
(26)�@�@��q�̃}���Z�C���s�c��̌��������E�����h���́A�����������������̂悤�ɕ��͂��Ă����B���Ȃ킿�A�u������n�������c�̂��A�c��^�}�̐����I�F�ʂɊւ��Ȃ��A���������ꂽ�����`���邢�͉����`�̕������ƌĂԂׂ������ɎQ�����Ă���v�ƁBLe
Monde,�hChances et me�Lcomptes de l'interventionnisme de�Lcentralise�L,
Francois Grosrichard, 16 Septembre 1978, p. 30.
(27)�@�@Georges Marion, Gaston Defferre, Albin Michel, 1989, p. 294.
(28)�@�@ibid., p. 296.
(29)�@�@���J�ҁw�ߑ�t�����X�̎��R�ƃi�V���i���Y���x(�@�������ЁA����Z�N)�A����ł��Q�ƁB
(30)�@�@Georges Marion, op. cit., p. 296.
(31)�@�@Jacques Rondin, op. cit., p. 53.
(32)�@�@Cite�L par Jean�|Marc Ohnet, op. cit., 1996, p. 164.
(33)�@�@���ꂱ���A�����_�����A�h�D�t�F�[���̂��̉��v���u���]�Ƃ����̐��ʎ��v�ƌĂԏ��Ȃł���B�������A�����_�����g���̉��v���s�s���]�Ƃ����̈�l�����ł������Ƃ͑����Ă��Ȃ��B�܂�A�����_���́A�s�s���]�ƂƔ_�����]�ƂƂ̋��d�I�Ë����������Ă����Ƃ݂Ă���̂ł���B���̓_�ɂ��Đ�������ƁA���@�Ă̂Ȃ��ł́A�R�~���[���̃��[�������́u�����Ǝ��R�v�ɂ��ċK�肷��Ɠ����ɁA�ނ�̐����̐ӔC(����)�ɂ��Ă��K�肵�Ă������Ƃ���A�]���㋉�@�ւ̌㌩�ēƂ����P�̉��Ɉ��Z���A�������Ĕ\�͂̓_�ŕs���������_���R�~���[���̃��[������������Ɍ��O��\�������B�����ŁA�_�������ߏ�ɑ�\���Ă���ƌ������@�̖�}�c���́A�哝�̗^�}����@���ł͉ߔ����������Ă���Ƃ��������̐��͔z�u��w�i�Ƃ��āA���̔����K��̍폜���������߁A�h�D�t�F�[��������ɑË������̂ł������BJacques
Rondin, op. cit., p. 49-90.
(34)�@�@ibid., p. 63-64.
(35)�@�@�n���������v�@�̌��m���ɂ��㌩�ē��Ɋւ���Ɉ�㔪��N��ܓ��̌��@�@�����Ɋւ��ẮA���̂��̂��Q�Ƃ����B�镔�͖�u���@�@(Conseil
constitutionel)��㔪��N��ܓ������v(�w���������x��ܔ����掵��)�A��{���q�A�O�f�_���A��㔪�l�N�A��Z�Z�ŁB��}�c���́A�@���Ƃ̑㗝�l�ɁA�n�����ǂ̈�@�ȍs�ׂɑ��āA���̊��Ԃ��o�߂��Ă���n���s���ٔ����ɒ�i���錠���ȊO�F�߂Ă��Ȃ����ƁA�A���̒�i�͑����̒�~���������Ȃ����ƁA�B���̌��ʁA���Ƃ̑㗝�l�͂��͂�s����̃R���g���[���̍s�g�A�@���̏���̊m�ہA�s���̎��R�̕ۑS���Ȃ����Ȃ��Ƃ����O�_�ɂ����āA���@�掵����Ɉᔽ����Ǝ咣�����B����ɑ��A���@�@�́A���̒n���������v�@����߂�Ƃ���́A�ٔ�����ʂ�������I�ȍ��@���R���g���[�����̂́A�u���@�掵�O���O���̒�߂�ړI�̈�̐���ڕW�Ƃ�����́v�ł����āA�����̌��͂𐧖���̂ł͂Ȃ��Ƃ��A���̓_�ňጛ�ƂȂ�|�̔������������B���Ȃ킿�A���ɁA�n�������c�̂̍s�ׂ��u���Ƃ̑㗝�l�ɑ��t�����O�̒i�K�ŁA�܂荑�Ƃ̑㗝�l�����̓��e��m�炸�A�]���čs���ٔ����ɑ��A�ꍇ�ɂ���Ă͎��s��~�̐\�����Ă�t�����đi�����N���邱�Ƃ��s�\�Ȓi�K�ŁA�����̍s�ׂ��@���㓖�R�Ɏ��s�͂����Ɛ錾����v�_�A���ɁA�u���Ƃ̑㗝�l���S��������Z���Ԃ̗\�����Ԃ̌o�ߑO�ɐ\�����Ă�ꂽ�i�����A�i�חv�����������̂Ƃ���v�_�ɂ����āA�u���Ƃ��ꎞ�I�ɂ���A���@�掵����O���ɂ���č��ɗ��ۂ���Ă�������̍s�g��i��������D�����̂ł���v�Ƃ����_�ł���B
�@�@�Ȃ��A���@�@�́A����ō̑����ꂽ�@���̂����ጛ�����������������͗L���ł���Ɛ錾�������A���͈̔͂ɂ��Ă̖��m�Ȓ�߂������Ă������߁A�ጛ�����̍폜�Ȃ����C���́A�R���������哝�̂Ɉς˂���Ƃ���ƂȂ�A�~�b�e�����́A��i�̗\���Ɋւ���K����폜���A�n�������c�̂̍s�ׂ��u���z�܂��͒ʒm�v�ɂ���Ď��s�͂����Ƃ���K����u�@���㓖�R�Ɂv���s�͂���������Ƃ���K��ɏC�����A�O������@�Ƃ��Đ����������B
(36)�@�@����N�@�ɑ���h�D�t�F�[���̂������������I�Ӑ}�́A�}�r���[�̎��̂悤�Ȏw�E�Ƌ����[����v�������Ă���B���Ȃ킿�A�}�r���[�͂��āA���̔���N�@���A�u�n�������c�̂ɑ�����̎�������F�߁v�A���̎�������ʂ��āu�n�����{�𐳓����v���A�u�n��V�X�e���̖@�@�@���@�@�x�@�@���i�A���X�e�B�e���V�H�i���U�V�H���j�𐳓����v�������I���@�ƕ]����(Albert
Mabileau, op. cit., 1994, p. 7-8.)�A���̏d�v�ȍ����Ƃ��Ă��̔���N�@�̑�����u�Z���̌o�ϓI�E�Љ�I�����Q�̗i��v��n�������c�̂ɔF�߂��_���w�E�����̂ł���B�]���t�����X�ł͔F�߂��Ă��Ȃ������n�������̂ɂ��o�ω�����A���̔���N�@����ɂ���Đ��������ꂽ�ȏ�A�}�r���[�ɂ��A�n���������v�́u�n��V�X�e���ɑ����ꂽ�Љ�I�����@�\����������v���̂Ƃ����B�������Ƃ̔��W�Ƃ��̌�̒����ɂ킽���@�̂Ȃ��ŁA�u�n��Z���̂��߂̕�����T�[���B�X�̒Ƃ������Ƃ̖����v�����債���ɂ�������炸�A�ނ��덑�Ƃ͂��������o�ρE�Љ�̈悩��̓P�ނ��J�n���Ă��邱�Ƃ���A�n��V�X�e��(�n�����@�ցE�n�����{)�ɂ́A���Y��Љ�I�����A����ɂ͒n��Z���̓���I�ȏ��v���ւ̉��Ȃǂ�ʂ����u�Љ�I�����@�\�v���v������Ă����Ƃ���(ibid.,
p. 134-135.)�B
(37)�@�@�g�D�{���c���́A����ȏ�ԂɊׂ�����Ƃւ̋~�ϑ[�u���A���[����R�~���[���c��ɑ��ėv������n���Z���̐��_�̈��͂ɍR�������̂��Ƃ����A�W���[��@���@�ψ�����Ɠ��l�̌��O��\�������B����ɑ��h�D�t�F�[���́A���̂悤�ɓ��ق����B���Ȃ킿�A���ɁA�R�~���[���̗\�Z�͋ύt�̂Ƃꂽ�Ґ��Ǝ��s���s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��邩��A�u�R�~���[���̗\�Z�̂��ƂŁA�����̍ی��Ȃ�������������邱�Ƃ͂Ȃ��v���A���ɁA�u�������g�̌o�����ɂ����āA�˔��I�ɂ���Ă��鈳�͂ɍR���邱�Ƃ́A��r�I�e�Ղł������v�ƁB�h�D�t�F�[���́A�}���Z�C���̑��ƃ`�^���E�R�f�Ђ̖��ƂȂ��ŁA�}���Z�C�����̑��ƃe�����Ђ̖��ɑ��A���̂悤�Ɍ��y���Ă���B���Ȃ킿�A�u�D���C���Ƃ̑���ƃe�����Ђ��x������~�̏�ԂɊׂ�A�����ٔ��������Y�̐��Z��鍐���邨���ꂪ�������B�����A�t�����X�⑼���̂������̊�Ƃ̑㗝�l�������A���̉�Ђ̒��ߑ�I�Ȑݔ��������Ŕ�����߂悤�ƁA�}���Z�C���ɏW�܂��Ă����B���̓R�~���[���c������W���A�e�����Ђ̎��Y������j�~���邽�߁A�}���Z�C���s�c����̐ݔ������|���^�������ŋc�������B���������Y�Ƃ��}���Z�C���Ɏc���Ă��ė~�����ƍl�����̂ł���B�Ƃ���ŁA���̌���́A�����̔P�o�������ɋ`���Â���킯�ł͂Ȃ����A���̌��O��̃`�����X�ɂƂ���ꂽ��ƉƂ������}���Z�C������ގU������ɂ́A���̌���ŏ\���ł���B���̂��ƁA���̏���Ƃ��e�����̍H���������̂��v�ƁBJournal
of officiel de la Republique francaise, Assemble�Le Nationale, Compte
rendu inte�Lgral, 3e Seance du 28 juillet 1981, p. 442-451.
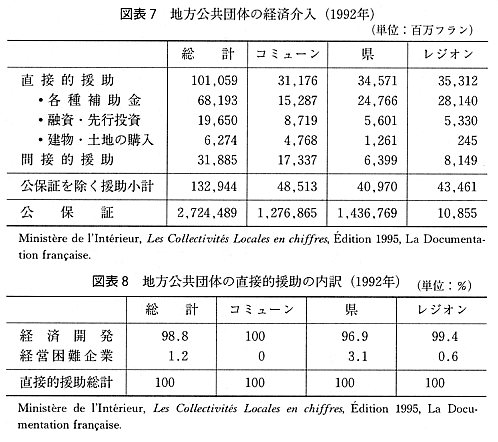
(38)�@�@�ɓ��m��u�t�����X�̒n�����x���v�Ɓw�s�����Љ��`�x�|�s�����̌o�ρE�Љ������K����߂����āv(�w�@������x���������A��㔪�l�N)�A��l�[��ܕł��Q�ƁB
�@�@���v�ȍ~�̒n�������c�̂̌o�ω���̎��ԂɊւ��ẮA�}�\7�E�}�\8���Q�ƁB�Ƃ�킯�A�}�\8�Ɏ������悤�ɁA�o�c����Ɋׂ�����Ƃւ̎x���́A�R�~���[���ł��A���W�I���ł��Ȃ��A�����ς猧���x���ōs���Ă���_���ڗ����Ă���B
�ށ@�@�@�@���@�@�@�@��
�@�@�ȏ�̂悤�ɁA�{�e�́A�~�b�e�����������ɂ����镪���E�Q���@�����v�̌�����T��ׂ��A�u�s�s�^�Љ�̐��n��w�i�ɂ��Ēn�����{�����������������̗v�������߂Ă����v�Ƃ��������̂��ƁA��㎵�Z�N��Ɋ�������������s�s�R�~���[���̕������v�����A��㔪�Z�N��ɂ�����@�����v�̎����ɋɂ߂đ傫�ȉe����^�����_�𖾂炩�ɂ��Ă����B�����ɁA����������㎵�Z�N��t�����X�ɂ�����s�s�R�~���[���̕������v�����n�����x���v�Ƃ��Ď��������ꍇ�A�������{�̓��������������Ȃ��K��v���ƂȂ�_�ɂ��Ă��w�E�����B�Ƃ����̂��A�����͂̔@���ɂ�����炸�A�n���������v�́A�{���������{���x���̒n�����x���v�Ƃ����̍ق��Ƃ炴��Ȃ�����ł���A�������{�ɂƂ��Ē����[�n���W�̂������n�搭���\���̎��Ԃ́A�Ȃ��헪�I�ʒu���߁A���������n��ɑ��鐭����Ջ����헪���n�����x���v�Ƃ����O�ς��Ƃ��Ď��s�Ɉڂ���邩��ł���B
�@�@�����ő��͂���ё��͂ł́A�������{(����)�̎��_����݂��A��萭���w�I�ɂ́A�����̎x����Ղ���������헪�I���_����݂��A�n�����x���v(���W�I�����v�ƃR�~���[�����v)�̈ʒu�ɂ��Č��������B����t�����X�ɂ�����n���������v�̒[�����Ȃ����̂́A�t�����X��܋��a������哝�̃V�������E�h�S�[���̃��W�I�����v�̎��g�݂ł���B�h�S�[�������̉��ň��Z�Z�N�����т��ĒNj�����Ă����n���s�����v�̎��g�݂��A�u�n���N�U���v�Ƃ�����̐����헪�Ƃ��đ����鎋�p�́A���ɂ킪���̐����w�����ɂ����Ē�o����Ă������A�{�e�ł́A���Z���N�̌܌������ȍ~�A�������x���ɂ����č��܂�������Ă����u�Q���v�v�����A��@�c��ƃ��W�I���]�c��̐E�\��\�����ɂ���Ď�荞�����Ǝ��݂�ނ̂�����ȁu�Q���v�_�����ӂ܂��A���Z��N�̍������[���ی�����A�ނ��ŏI�I�Ɏ��C����Ɏ���v���Z�X�ɂ��Č��������B���������h�S�[���̓����ɑR���邩�����ŁACJM���\�i�Ƃ��錤���N���u�^���́A�s����n��̂��܂��܂ȃC�j�V�A�e�B�������W���A�����W����`�I�Ŋ�����`�I�ȕ��Q�ɔY�܂���Ă��������̃t�����X���Ƃ������ɂɉ��v���Ă����̂��Ƃ����A�ɂ߂ďd�v�Ȗ��Ɏ��g��ł����B�����̉^���̂Ȃ�����A�����I�Q���f���N���V�[�̗��_�I���W���F�߂���킯�ł��邪�A�����������_�I�O�i�������}�̐����I���j�̃��x���ɐZ������ɂ͂����炩�̔N����v�����B����̑哝�̑I���ɂ����鏟��������ɓ���A�Љ�}�̍Č��E�����Ɏ��g��ł����~�b�e�������A���������s����n��̃G�l���M�[������̓}���ւƑg�ݍ���ł������ƂɂȂ�B���̓_�ŁA��㎵�Z�N��̌㔼�A�n���c��ɂ����鐭���I��Ղ̊m����ڎw�����Љ�}�ق����������͂��A�e��n���I���ŏ��������߂����Ƃ͌����ċ��R�ł͂Ȃ��������A���̂��ƂƁA��㔪��N�哝�̑I���ɂ�����W�X�J�[���f�X�^���̔s�k�ƃ~�b�e�����̏������A���W�ł͂Ȃ������Ǝv����B��㎵�l�N�̑哝�̑I���ɓ��I�����W�X�J�[���f�X�^���́A��܋��a�����ŏ��́u��S�[���X�g�v�哝�̂ƂȂ������A�c����ɂ����Ă͈ˑR�Ƃ��ď����h�Ɏ~�܂��Ă����哝�̗^�}����������K�v���ɔ�����B�ނɂƂ��Đ�����Ղ̋����A�Ƃ�킯�n�惌�x���̐�����Ջ����Ƃ́A�S���̒n���c��̑唼���߂�ƌ����関�g�D�����h�c������������̓}�h�֑g�D���邱�Ƃł������B�W�X�J�[���f�X�^���������_���R�~���[���̌����ŊJ���邽�߂̉��v�ɔz���������������������ɂ���B�������A����͖��������������ł������B���Ȃ킿�A��㎵�O�N�̃I�C���E�V���b�N�ȍ~�A�_���^�o�ύ\���̋ߑ㉻�E���Ē������}���̉ۑ�ƂȂ��Ă��������̐����ɂƂ��āA�o�ύ\�����v�́A�_���^�n��o�ςɈ��Z����n�����]�Ƃ���(�ނ炱�������g�D�����h�c���ł�����)�Ƃ̑Ό����Ӗ����Ă�������ł���B���ǁA�W�X�J�[���f�X�^�������̒n�����x���v�����u�ߑ��`�v�I���i�́A�_�����̎㏬�R�~���[�������ʂ��Ă����ۑ����������Ƃ����������Ŏ������Ɏ~�܂�A�s�s����o�ύ\���̋ߑ㉻�ɂƂ��ĕs���́u���W�I���n�݁v�Ƃ����ۑ�́A�������������́u�ꔄ�����v�I����ƂȂ�B�v����ɁA�W�X�J�[���f�X�^�������̒n�����x���v(�p��)�ƃ~�b�e���������̒n�����x���v�Ƃ��A�ő�̃|�C���g�́A���̉��v�̔w��ɑ��݂��鐨�͂��A�_���I�E�狌�I���]�Ɛ��͂ł��������A�s�s�I�E�V���s�����͂ł��������Ƃ����_�ɂ������B
�@�@��㎵�Z�N��t�����X�̓s�s�R�~���[���A�Ƃ�킯�A�Љ�}�n�̓s�s�R�~���[���̂Ȃ�����A�܂��ɒn�����{�̎����������߂铮�������������Ă������B�����ő�O�͂���ё�l�͂ł́A��㎵�Z�N��ɑ䓪�����s�s�R�~���[���̐V���������ꂽ�B�s�s�Ƃ��Ă̗��j���A�Y�ƍ\�����A�l�����Ԃ��A���O���x���̕����╗�y���قȂ��̓s�s(�O���m�[�u���ƃ}���Z�C��)�́A���炪���ʂ��鏔�����������鎎�s����̂Ȃ�����A�����^�����̐�������ꂼ��قȂ����������Ŋm�����Ă����B���Ȃ킿�A�O���m�[�u���ɂ����镪���^�����̐���́A�s�s�v��̃v���Z�X�ւ̎s���̎Q���𑣐i����ȂǁA�u�n�斯���`���n�挠�͂̕����v�𗝔O�Ƃ��鎩���̉��v�Ƃ����������Ŗ͍����ꂽ���A�}���Z�C���ɂ����镪���^�����̐���́A�}���Z�C���̊�Y�ƂƂ������鑢�D�E�D���C���Ƃ���@�Ɋׂ�Ȃ��ŁA�}���Z�C���s���A���ځA���̋~�ςɏ��o���ȂǁA�n�������̂ɂ��o�ω����`�Ƃ����������Ŗ͍����ꂽ�̂ł���B�������A������̓s�s�R�~���[���̎��g�݂́A�����Ȓ��ɂ�铝���ɔ����A�����������������u�����A�]���̊���E�W���^�̐�����Č������A�����E�����^�����V���ɊJ�����Ă������_�ł͋��ʂ��Ă���B�v����ɁA��㎵�Z�N��ɂ�����Љ�}�n�s�s�R�~���[���̂�������������ʂ��āA��㔪�Z�N��ɕ����E�Q���@�����v������������������肠����ꂽ���̂ƍl������̂ł���B���̂��Ƃ́A��㔪�Z�N��ɁA�~�b�e�����̍��������̂��ƂŎ��{���ꂽ��A�̒n�����x���v���A�Ȃ��A�����I�Ŏs���Q���I�Ȉꑤ�ʂ�L���Ă����̂������������̂ł���B�������A���������ʒn�����{�̎������^�������ƋK�͂̑���v���ɂ́A���炩�̓��������ԐړI�U�������K�v�ƂȂ�B���̓_�ŁA�t�����X�̏ꍇ�A�K�X�g���E�h�D�t�F�[���Ƃ�����l�̑啨�����Ƃ��d�v�Ȗ������ʂ��������Ƃ́A���ڂɒl����Ǝv����B�}���Z�C���s���Ƃ��ĕ����^�����̐���ƌĂԂׂ��V���Ȑ���������J�����A�t�����X�̓s�s�R�~���[�����A�n�����{�Ƃ��Ĉ��̎��������m�����Ă����\�������o���Ă����ނ́A�t�ɁA�������{���n�������̂̎{������钆���W���V�X�e���ւ̔ᔻ�I�Ȗ��ӎ����`������ɂ�����B���ꂪ���������ƂȂ��āA��㔪��N�Ƀ~�b�e�������哝�̑I���ɏ�������ƁA�h�D�t�F�[���͎|�X�g�ł͂Ȃ��A�������n��������b�̃|�X�g������~���A�n���������v�̎����ɏ�M��R�₵�Ă������ƂɂȂ����B�ނ́A��㔪��N�ɊJ�n�����n���������v�̋c��R�c�ߒ��̂Ȃ��ŁA�ɂ߂đ傫�Ȑ����w���I�������ʂ������̂ł���B
�@�@�Ō�ɁA�c���ꂽ�����ۑ���w�E���Ė{�e���ނ��Ԃ��Ƃɂ������B�{�e�́A��㔪�Z�N��̃t�����X�ɂ����Ēn���������v�Ƃ������ƋK�͂̑���v���������ꂽ�w�i�Ƃ��āA��㎵�Z�N��̓s�s�R�~���[���ɂ����镪�����v���^�����݂Ă����B����́A�s�s�E�V���s�����͂̉^���I�G�l���M�[�����Ƃ̓����̎d�g�݂�ϊv������̎���ł���B�������A����t�����X��f�ނƂ��邱�������^���_�����w�́A���肳�ꂽ����ł���B����́A��萸�k�ȓs�s����������ʂ��āA�ނ炪�W�]�����V�����Љ(�����I�Q���f���N���V�[�Љ�)���яオ�点�A����牺����̉^���ƍ��ƃ��x���̐����Ƃ̘A�ւɂ��āA���炩�ɂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A�{�e�́A�t�����X�ɂ�����n���������v�̖@�����v���Z�X�ɂ��Ę_���Ă���킯�ł��邪�A����A���{�ȂǏ]�����璆���W���I���ƍ\�����Ƃ��Ă���Ɩڂ���鍑�X�Ƃ̔�r�������K�v�Ƃ����Ǝv����B
�@
�@
|