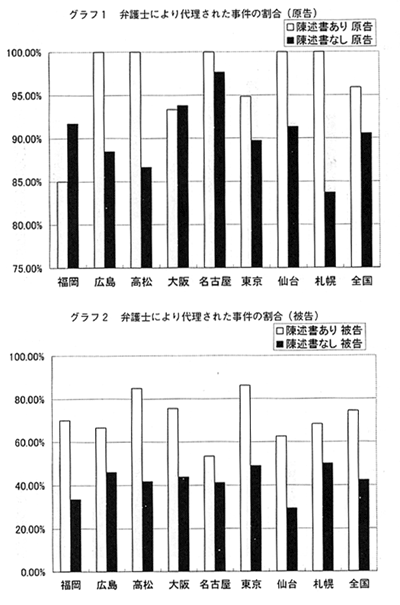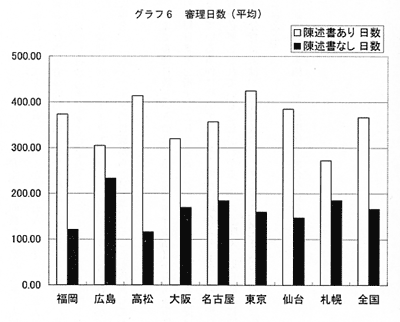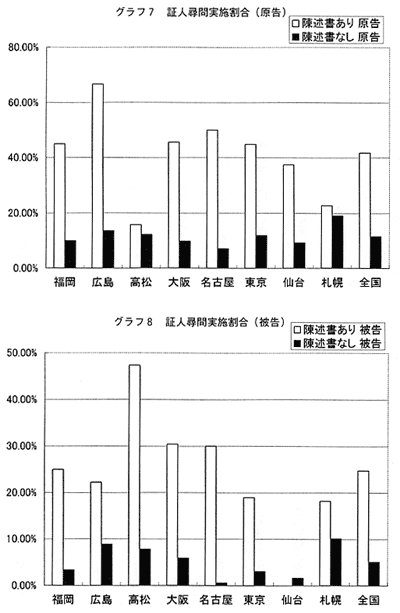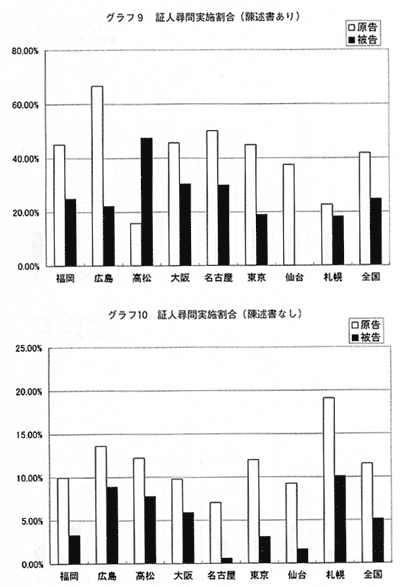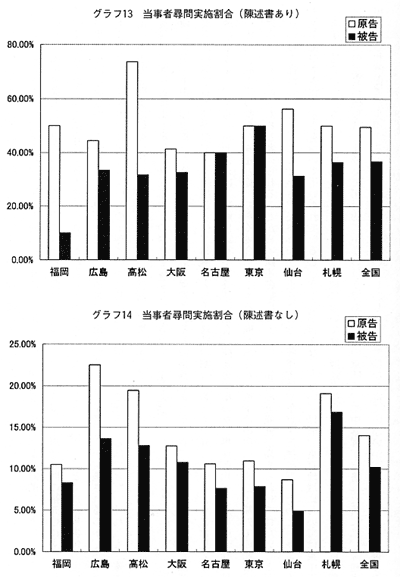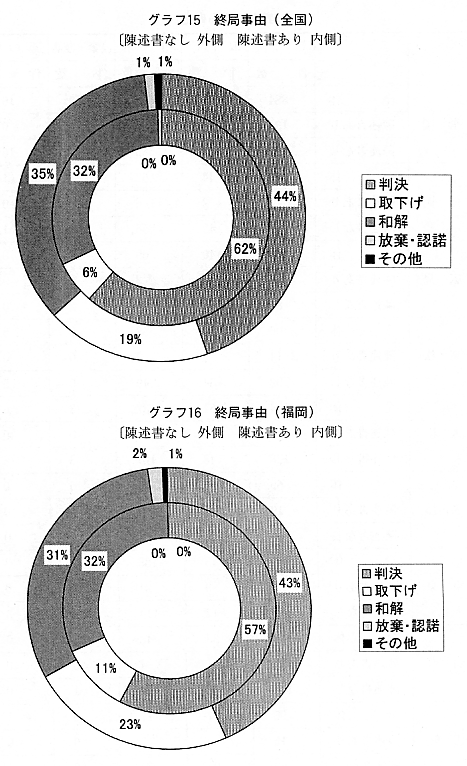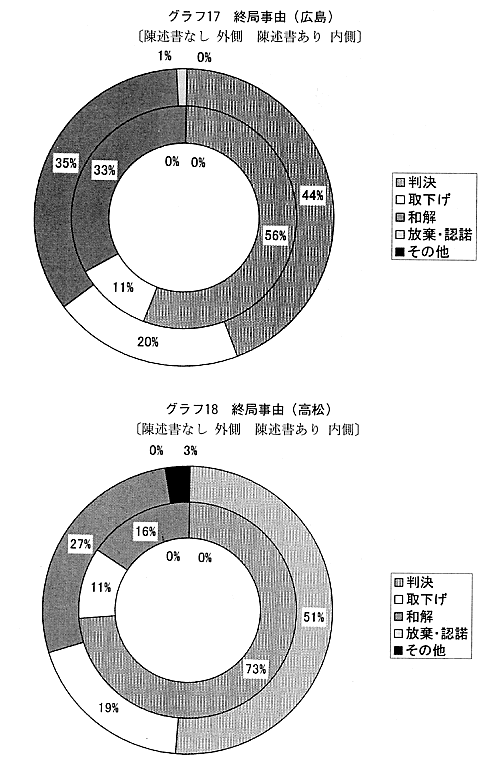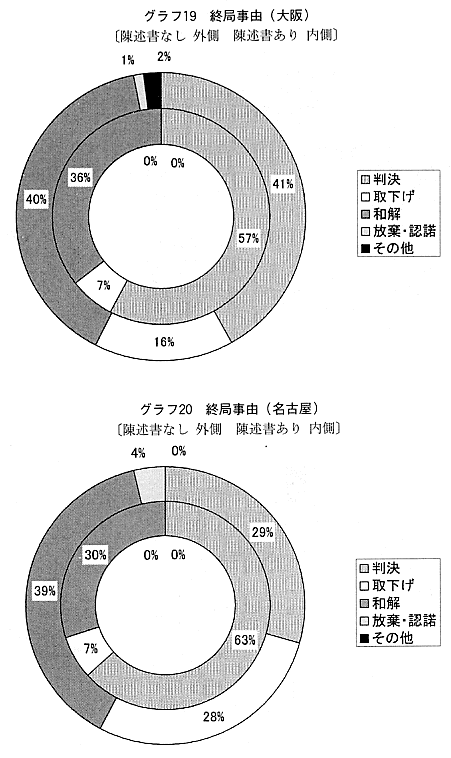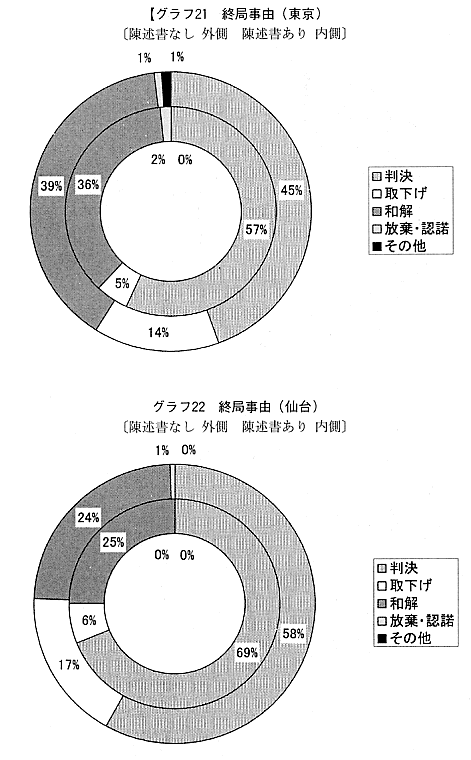|
かつて弁論兼和解という審理技法は、民事訴訟法上の明文がなく、諸外国の歴史を紐解いても直截的にこの技法の基礎となったものが見当たらないにもかかわらず、短期間で日本の民事裁判実務を席巻した(1)。弁論兼和解が持つ実務運営上の多くの利点はともかく、法律上明文の根拠が定かでないことと併せて、手続の非公開性や当事者対席の欠如等の点を中心に理論的批判は厳しく、全面的な民事訴訟法改正を経て、争点・証拠整理手続が整備された今日においては、もはやその存在意義に終止符が打たれたとも評価し得る。
他方で、弁論兼和解と同じような経緯で民事裁判実務に浸透しながら、先の民事訴訟法改正によってもなお存続が確実視され、その利用につき実務法曹のみでなく、理論研究者の関心を引くものとして、いわゆる陳述書がある(2)。旧法下において、一連の民事裁判実務改善運動を通して、この陳述書といった書面が活発に利用されるようになった。陳述書を一般に定義づけることは難しいようであるが、その輪郭として、事件に関する当事者や証人等の経験を時系列的にまとめられていること、書面の末尾にそれらの者の署名や押印がなされていること等が指摘されており(3)、作成主体、記載内容、および提出時期により、訴訟法上の性質は異なるとされる(4)。いずれにせよ、法律上明文の根拠を持たず、諸外国にその沿革を有しないため、理論研究者の側からはその輪郭を知ることすら困難であることには注意を要する。
しかしながら、弁論兼和解が充実した争点・証拠整理手続の整備により、その必要性を疑問視され、かつまたそれを利用すること自体が否定的に解されるのに対して、陳述書は今後も大いに活用される可能性が、実務の側だけでなく、理論の側からも示唆されている(5)。陳述書の活用に実務上の利益があるとしても、研究者の側からすればその実態が見えないため、弁論兼和解をめぐる論議がかつてそうであったように、陳述書について論じるべき点を見誤らないとも限らない(6)。
本稿は、かかる現状に鑑み、陳述書をめぐる種々の法的諸問題を考察する前提として、陳述書の利用実態をでき得る限り客観的に提示するための準備として、全国八地域の平成三年新受第一審民事通常訴訟事件一九〇〇件を対象に行われた民事訴訟事件記録の実態調査のデータをもとに、陳述書が提出された事件の特徴を明らかにすることを目的とする。その意味で、本稿は、陳述書に関する理論的提言を新たに示すものではないが、「ぬえ的」と評されながらも(7)、民事裁判実務においてその重要性を増している陳述書をめぐる考察への手がかりとして、その利用実態の一端を計量的に明らかにすることにも一定の意義はあるであろう。
以下においては、まず、陳述書をめぐる問題点をごく簡単に整理し、右に挙げたデータの分析方法の大枠を示した上で、個別的な検討を行いたい。
【付記】 本稿で用いるデータは、民事訴訟実態調査研究会(代表竹下守夫教授)により行われた調査データをもとにしている。この研究会による調査分析結果はすでに民事訴訟実態調査研究会(代表竹下守夫教授)編『民事訴訟の計量分析』(商事法務研究会、二〇〇〇年)により明らかにされている。本稿は、そこで扱えなかった分析を企図するものである。もちろん本分析における責任は著者一身にある。このデータの利用を快く承諾していただいた竹下先生をはじめ、研究会の構成員の各先生方にお礼申し上げる。本稿におけるデータ分析については、和歌山大学大学院経済研究科の中元祥人氏、濱田久美子氏にご協力いただいた。ここでお礼申し上げる。なお、本稿での分析により導かれた数値が右書におけるそれと異なる場合があるが、これは本稿で立てた分析項目の関係上、独自のデータ解釈により、個別データの取捨選択を行なったためである。
第一章 前 提
現在陳述書の利用は増加しているともいわれ、その積極的効用が次第に認識されつつあるようである。こうした陳述書をめぐる状況やその効用を理解する上でも、そもそも民事訴訟法改正前において、陳述書がどのように利用されていたかを知ることは重要である。本稿は、かかる分析を行なう準備として、陳述書利用事件の実態をさしあたり検討するものであるが、ここではもう少し視野を広げ、利用状況全般を検討する分析の枠組みを獲得するため、民事訴訟法改正に前後して公表された陳述書をめぐる諸文献を参考にしつつ、陳述書の有り様として指摘される諸々の点を確認しておきたい(8)。
陳述書は、そもそも、人事事件等において、婚姻破綻にいたる経緯等を当事者本人が明らかにするべく利用されていたとされ、そのため、その利用にあたっては、人証の経歴や計算書関係等の形式的事項等に限って使用されるべきものとされていた(9)。しかし、陳述書が準備書面等とは異なり、事案の概要を要件事実等に拘束されず、時系列に従い明らかにする形式を採ることから、次第に人事事件以外でも積極的に利用されるようになったとされる(10)。もっとも、こうした積極的利用については、裁判所・弁護士といった実務法曹の間でも評価が分かれるようである。裁判所の側では、証拠調べにおける主尋問の代用として陳述書を利用する方法が早くから認知されていたようであり(11)、その後、争点整理段階における「事案提示型陳述書」が「事案解明型準備書面」と併せて活用されるよう説かれている(12)。とりわけ、裁判所については争点整理ないし証拠開示といった後者の機能への積極的評価が窺える。これに対して、弁護士の中には、陳述書の利用自体を批判する向きもある(13)。こうした点から、裁判官の陳述書に対する嗜好性や代理人弁護士の陳述書提出への関与の仕方を検討することが必要となろう。
陳述書はさまざまな機能を有し、多様な取り扱いがなされていると指摘されている(14)。その中でもとくに、争点整理段階における証拠開示機能と証拠調べ段階における主尋問代替機能が注目に値しよう。とりわけ、前者については、「証拠」をもって「主張」を固定することにもつながり(15)、理論的にも検討すべき必要性は高いといえよう。しかし、そもそも、このような「争点整理と証拠調べの架橋」が生じた原因はどこにあるのであろうか。この点を考える上で、陳述書にこれらさまざまな役割が期待される前提として、どのような性質の事件で陳述書が用いられているかを確認しておくことが肝要と考える。陳述書の多様な機能を論じる前に、それが提出されている事件の特徴を把握しておくことにも意味はあろう。
陳述書の有するとされる種々の機能のなかで、右に挙げた機能に着目するとして、これらに関連するすべての事象について検討を行なうことは、取り扱うデータの性質等からきわめて困難である。そこで、さしあたり収集されたデータとの関係で検討されるべき点として、つぎの三つの点を示唆しておきたい。まず第一に、陳述書には「準備書面兼書証」という実態があるとされる点である(16)。準備書面との関連性につき、何らかの有意な傾向が見て取れるかは検討に値しよう。第二は、陳述書が人証実施において果たす役割である。これまで、陳述書の提出をもって人証の取り調べに代えることがあるとの指摘がなされてきた。また、主尋問を省略するために陳述書が用いられることがあるとされる。これらの点につき具体的なところまで完全に明らかにすることは困難であるが、人証実施と陳述書提出時期の関係を示すことである程度の示唆を得ることは可能であろう。最後は、陳述書という「証拠」には、「主張」固定機能があり、結果として、争点が早期に固定され、和解成立への気運が高まるとの点である(17)。証人の供述と準備書面が矛盾する場合と異なり、陳述書の場合は、代理人弁護士の言い訳ができないからである。その意味で、陳述書提出事件の終局事由を分析することが求められよう。
以上の俯瞰から、次の諸点に留意しつつ、陳述書利用状況把握のため、データ分析を行うことが有用であろう。まず、裁判官による、陳述書の利用状況を示す必要がある。現行法における陳述書の利用状況を考える上で、旧法下における裁判官による陳述書の利用率ないし頻度を明らかにしておくことが考えられる。次に、陳述書作成への代理人弁護士の関与が指摘されている関係で、代理人弁護士の有無による陳述書の利用状況を分析対象に加えることが求められる。また、陳述書が利用される事件について、その全体像を可能な限りの分析項目をもって明らかにしたい。陳述書が「準備書面兼書証」と言われている点で、準備書面との対応状況を示すことにもそれなりの意味はあろう。陳述書が提出された事件について、終局事由の状況を知ることは興味深い点である。すなわち、争点・証拠整理に陳述書が利用された場合、陳述書には「証拠」としての「主張」固定機能があり、それにより、争点が早期に固定され、場合によっては、和解成立への可能性が高まるかもしれないとの指摘があるからである。
しかしながら、本稿では、紙幅の関係から、これらすべてを取り扱うことはできない。そこで、まず、陳述書が利用されている事件の状況につき、データ分析の結果を明らかにしたい。
第二章 分析の方法
かつて筆者は、被告側からの答弁があり、かつ人証が実施された事件について、第一回口頭弁論期日から初回人証実施期日までの期間を便宜上「争点整理期間」と称し、この期間を中心として、人証の実施と準備書面や陳述書との関係について、本調査データをもとにした分析を行った(18)。本稿はこの業績を踏まえさらに分析を付加することを企図し、陳述書利用状況全般を理解する前提として、陳述書が提出された事件の特徴を収集された事件記録のデータから汲み上げることを目的とする。
まず、分析の対象となった民事訴訟実態調査の目的、データの収集方法、分析方法等については、民事訴訟実態調査研究会[代表竹下守夫]編『民事訴訟の計量分析』第一部に譲る。大づかみに言えば、本調査は、高等裁判所が存在する全国八地域の地方裁判所における平成三年新受第一審民事通常訴訟事件一九〇〇件を対象に行われた。本稿では、この民事訴訟事件記録の実態調査から得られたデータを前提にして、陳述書の提出があった事件につき、いくつかの項目を立て、主として地域を軸にしてデータ分析を行う。
分析の仕方は以下の通りである。まず、分析の対象となる事件数を各地域ごとに明らかにしたうえで、いくつかの分析項目を立て、検討を進める。そのさい、陳述書が提出された事件とされなかった事件のデータを示し、両者の差異を確認していくことを方法として採用する。
第一の項目として、訴訟当事者数の平均を明らかにする。当事者の多寡により、陳述書の利用状況が変化するかどうかを見るためである。つぎに、弁護士により代理されている事件の割合を確認する。すでに指摘しように、陳述書の利用には弁護士の関与が大きな意味を持つようであり、その点を確認する意味を持つ。訴額の平均値も検討に値しよう。陳述書が提出されている事件について、争いの対象となっている数額を知ることも一つの方法であろう。陳述書が提出されることによって、審理の期間がどのように変化しているかということも確認しておく。そのさい、弁論期日回数の平均値と第一回口頭弁論期日から終局にいたるまでの期間の平均値を併せて提示する。なお、証人尋問の実施率や当事者尋問の実施率も一般的な情報として提示されるべきであろう。とくに、陳述書作成者自身の人証実施を検討する前提として、一定の意義はあろう。最後に、終局事由の状況を挙げておく。民事訴訟法改正前において、陳述書が提出される場合に、和解率が高まるというようなことははたして生じていたのか。
なお、本来は、前章で指摘した諸問題を網羅的に分析すべきところであるが、本稿ではさしあたり、陳述書が提出された事件の特徴を提示するにとどめる。他の分析に先立ち、かかる点を検討することにも一定の意義はあると考える。
第三章 分 析
まず検討の対象となる事件数を以下に挙げる。(表1参照)
この表1から、陳述書提出事件の割合が全国的に見てそう高くないことと地域的な偏りのあることが窺える。三大都市圏とそれ以外の地域には若干の格差が見られる。この点を敷延して言えば、陳述書の利用は都市部を中心に拡大していく可能性があるとも考えられる。
つぎに陳述書の提出のある事件とそうでない事件に関する訴訟当事者の人数平均を示す。(表2参照)
ここから窺える傾向は、陳述書提出のある事件の訴訟当事者数のほうが提出のない事件のそれよりやや多いことである。たとえば、原告当事者について言えば、福岡、広島、高松、大阪、東京の各地域で、そのような傾向が示されている。とくに、被告当事者については、福岡、広島、大阪、名古屋、東京、仙台、札幌の7地域までがそうである。誤解を恐れずに言えば、陳述書は訴訟当事者の数が多い事案で用いられる傾向にあるということである。
表1 事件件数
|
全 体 |
陳述書あり |
陳述書なし |
陳述書あり |
| 件 数 |
件 数 |
件 数 |
割 合 |
| 福岡 |
200 |
19 |
181 |
9.50% |
| 広島 |
200 |
9 |
191 |
4.50% |
| 高松 |
199 |
19 |
180 |
9.55% |
| 大阪 |
351 |
45 |
306 |
12.82% |
| 名古屋 |
200 |
30 |
170 |
15.00% |
| 東京 |
350 |
58 |
292 |
16.57% |
| 仙台 |
200 |
16 |
184 |
8.00% |
| 札幌 |
200 |
22 |
178 |
11.00% |
| 全国 |
1,900 |
218 |
1,682 |
11.47% |
表2 訴訟当事者の平均人数
|
全 体 |
陳述書あり |
陳述書なし |
| 原 告 |
被 告 |
原 告 |
被 告 |
原 告 |
被 告 |
| 福岡 |
1.17 |
1.61 |
1.50 |
1.75 |
1.13 |
1.59 |
| 広島 |
1.24 |
1.81 |
1.33 |
2.00 |
1.23 |
1.80 |
| 高松 |
1.13 |
1.82 |
1.35 |
1.70 |
1.10 |
1.82 |
| 大阪 |
1.18 |
1.49 |
1.22 |
1.67 |
1.17 |
1.47 |
| 名古屋 |
1.14 |
1.65 |
1.03 |
1.80 |
1.16 |
1.62 |
| 東京 |
1.11 |
1.55 |
1.17 |
1.76 |
1.10 |
1.51 |
| 仙台 |
1.03 |
1.78 |
1.00 |
2.00 |
1.03 |
1.76 |
| 札幌 |
1.17 |
1.54 |
1.05 |
1.68 |
1.18 |
1.52 |
| 全国 |
1.14 |
1.63 |
1.19 |
1.77 |
1.14 |
1.61 |
弁護士により代理された事件の割合はどうであろうか。(表3参照)
この表の「全体」データから窺えるように、原告当事者のほとんどが弁護士に代理されているのに対し、被告当事者の代理されている割合は大きくない。このような傾向は、陳述書提出がない場合にも見られるが、他方で、陳述書提出がある場合には、被告側の代理人選任率が目に見えて上昇する。また、陳述書提出がある事件において、原告の弁護士に代理される割合はきわめて高い。これらのことから、陳述書の利用にあたっては、弁護士の関与が不可欠とも言い得る状況が存在していたことが指摘できよう。
表3 弁護士による代理の割合
|
全 体 |
陳述書あり |
陳述書なし |
| 原 告 |
被 告 |
原 告 |
被 告 |
原 告 |
被 告 |
| 福岡 |
91.00% |
37.37% |
85.00% |
70.00% |
91.71% |
33.52% |
| 広島 |
89.00% |
47.00% |
100.00% |
66.67 |
88.48% |
46.07% |
| 高松 |
87.94% |
46.23% |
100.00% |
85.00% |
86.67% |
41.67% |
| 大阪 |
93.73% |
47.86% |
93.33% |
75.56% |
93.79% |
43.79% |
| 名古屋 |
98.00% |
43.00% |
100.00% |
53.33 |
97.65% |
41.18% |
| 東京 |
90.57% |
55.14% |
94.83% |
86.21% |
89.73% |
48.97% |
| 仙台 |
92.00% |
32.00% |
100.00% |
62.50% |
91.30% |
29.35% |
| 札幌 |
85.50% |
52.00% |
100.00% |
68.18% |
83.71% |
50.00% |
| 全国 |
91.16% |
46.05% |
95.87% |
74.31% |
90.55% |
42.39% |
訴額の大きさによるデータの相違を見てみる。(表4参照)
訴額の平均値に関しても、多くの地域で、陳述書提出のある事件のほうがない事件よりも高額な値を示している。一般化して言うことは難しいかもしれないが、争う金額の多い場合に、陳述書を用いた訴訟運営がなされる傾向にあるのかも知れない。今後の運用において、低額な訴額の事件にも陳述書が利用されるようになれば、陳述書自身のあり方が変わったと言えるかも知れないし、あるいは、この調査の時点とは異なった目的ないし機能をもって陳述書が利用されているとも推測し得る。
表4 訴額の平均
|
全 体 |
陳述書あり |
陳述書なし |
| 金 額 |
金 額 |
金 額 |
| 福岡 |
¥9,797,605 |
¥9,316,693 |
¥6,481,723 |
| 広島 |
¥6,768,531 |
¥12,523,696 |
¥6,693,161 |
| 高松 |
¥14,786,399 |
¥12,988,126 |
¥14,889,169 |
| 大阪 |
¥9,716,244 |
¥15,031,513 |
¥8,916,288 |
| 名古屋 |
¥6,254,502 |
¥6,074,324 |
¥6,286,676 |
| 東京 |
¥31,328,240 |
¥35,754,820 |
¥30,455,178 |
| 仙台 |
¥11,220,769 |
¥15,455,864 |
¥10,873,630 |
| 札幌 |
¥10,193,768 |
¥11,266,538 |
¥10,067,206 |
| 全国 |
¥13,444,945 |
¥18,244,864 |
¥12,846,915 |
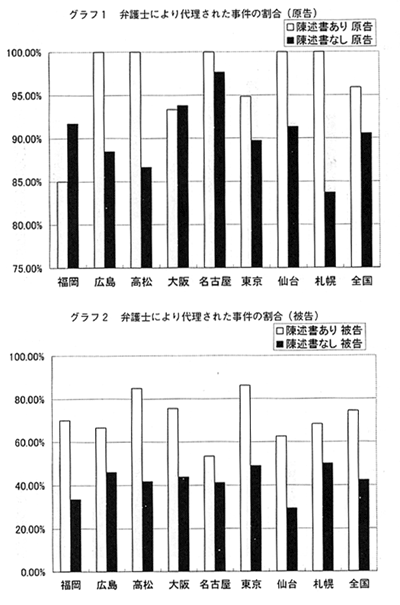

つづいて審理にかかる時間と陳述書の利用状況の関係を検討する。まずは、口頭弁論期日回数の表・グラフを示す。なお、ここでは、期日が一度も行われなかった場合、これをデータの母数から除外していることを指摘しておく。
これらの表・グラフから明らかなように、陳述書の提出されている事件は、そうでない事件と比較して、明らかに弁論期日回数が多い。この結果からごく単純に言えることは、陳述書提出のある事件は、そうでない場合と比較して、多数の審理期日を要するということである。このことは、判決ないし当該事件の終結までに多くの審理回数を必要とするような複雑な事件で利用されるということを意味しているとも考えられる。陳述書を人証実施の代わりとしたり、争点整理や証拠開示のために用い、事件全体の「ストーリー」を知るために利用しようということの意味はこのデータの結果から容易に窺える。すなわち、事件の複雑さから、一つには審理負担の軽減のためであり、また要件事実的な把握が困難に感じられることから、背景事情等を裁判所が知りたいという欲求が強くなるということである。
表5 弁論期日回数(平均)
|
全 体 |
陳述書あり |
陳述書なし |
| 回 数 |
回 数 |
回 数 |
| 福岡 |
4.27 |
8.63 |
3.74 |
| 広島 |
5.71 |
8.00 |
5.58 |
| 高松 |
5.39 |
8.90 |
4.86 |
| 大阪 |
5.06 |
8.69 |
4.47 |
| 名古屋 |
4.65 |
7.87 |
3.96 |
| 東京 |
5.83 |
10.98 |
4.72 |
| 仙台 |
4.54 |
9.38 |
4.08 |
| 札幌 |
5.92 |
7.86 |
5.67 |
| 全国 |
5.23 |
9.17 |
4.65 |

表6 審理日数(平均)
|
全 体 |
陳述書あり |
陳述書なし |
| 日 数 |
日 数 |
日 数 |
| 福岡 |
149.80 |
373.47 |
120.69 |
| 広島 |
237.02 |
304.89 |
233.21 |
| 高松 |
195.87 |
413.95 |
116.13 |
| 大阪 |
191.87 |
320.13 |
169.33 |
| 名古屋 |
217.37 |
356.70 |
184.72 |
| 東京 |
210.07 |
424.90 |
159.62 |
| 仙台 |
168.61 |
385.00 |
146.83 |
| 札幌 |
195.72 |
272.41 |
185.37 |
| 全国 |
192.88 |
367.01 |
166.15 |
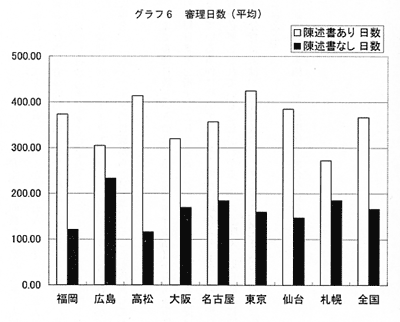
ところで、このような多くの弁論期日回数の結果は人証の実施の有無によって左右されているのかも知れない。そこで、証人尋問および当事者尋問の実施の有無を検討したいが、その前に、審理に要した日数のデータも見ておくことにする。(表6参照)なお、弁論期日回数のデータと同様に、期日が一度も行われなかった場合、これをデータの母数から除外していることを指摘しておく。
ここで審理日数というのは、第一回口頭弁論期日から当該事件の終局日までを指す。これらの表・グラフからも、陳述書が提出されている事件については、そうでない場合よりも多くの審理日数が必要とされていることがわかる。その意味で、期日回数に関する分析結果は、審理日数のデータにより否定されるものでないと言えよう。
証人尋問実施のあった事件の割合を見る。(表7参照)
表7 証人尋問実施割合
|
全 体 |
陳述書あり |
陳述書なし |
| 原 告 |
被 告 |
原 告 |
被 告 |
原 告 |
被 告 |
| 福岡 |
13.50% |
5.50% |
45.00% |
25.00% |
9.94% |
3.31% |
| 広島 |
16.00% |
9.50% |
66.67% |
22.22% |
13.61% |
8.90% |
| 高松 |
12.56% |
11.56% |
15.79% |
47.37% |
12.22% |
7.78% |
| 大阪 |
14.53% |
9.12% |
45.65% |
30.43% |
9.80% |
5.88% |
| 名古屋 |
13.50% |
5.00% |
50.00% |
30.00% |
7.06% |
0.59% |
| 東京 |
17.43% |
5.71% |
44.83% |
18.97% |
11.99% |
3.08% |
| 仙台 |
11.50% |
1.50% |
37.50% |
0.00% |
9.24% |
10.11% |
| 札幌 |
19.50% |
11.00% |
22.73% |
18.18% |
19.10% |
10.11% |
| 全国 |
15.20% |
7.63% |
41.74% |
24.77% |
11.53% |
5.11% |
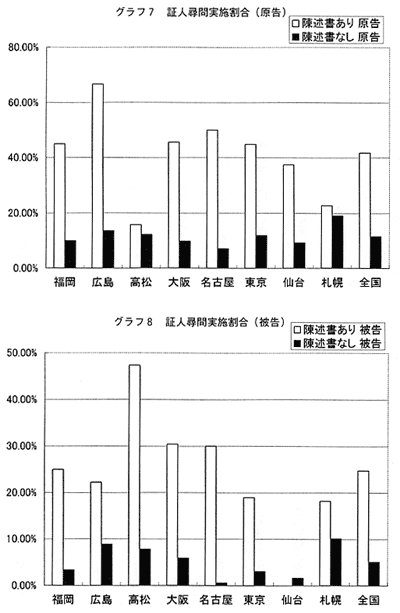
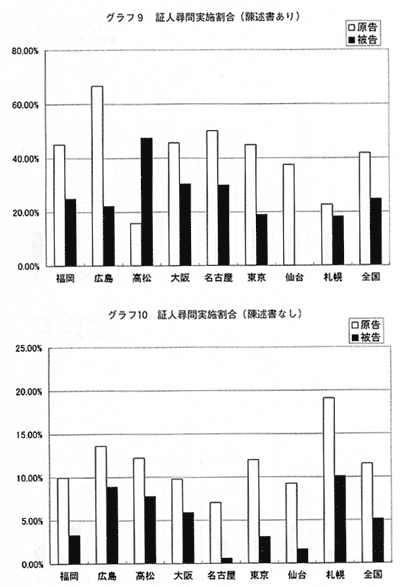
ここでは、証人尋問実施のあった事件の割合を原告・被告それぞれについて示している。これらの表・グラフを一瞥して言えることは、陳述書提出事件における証人尋問実施の割合が大きいということである。このことは、陳述書提出事件の口頭弁論期日回数の多さや審理期間の長さと関連付けて考え得る。証人尋問を行うためにはその準備のための時間が必要となるであろうし、尋問のための期日も設定しなければならない。事件終結のために証人を取り調べる割合が大きいということは、これまでも指摘してきたように、事件の複雑さ、当事者間の対立の根深さを示しているとも思われ、陳述書はこのような場合に機能するものであることがここでのデータからも明らかとなっている。また、原告と被告のそれぞれの割合は、概して原告側の実施割合が大きいことがわかる。このことは陳述書提出の有無に関係しないようである。いずれにせよ、陳述書は証人の取り調べと浅くない関係性を有することが窺え、この点について立ち入ったデータ分析が必要となろう。
つづいて、当事者尋問実施割合を見ておきたい。(表8参照)
表8 当事者尋問実施割合
|
全 体 |
陳述書あり |
陳述書なし |
| 原 告 |
被 告 |
原 告 |
被 告 |
原 告 |
被 告 |
| 福岡 |
14.50% |
8.50% |
50.00% |
10.00% |
10.50% |
8.29% |
| 広島 |
23.50% |
14.50% |
44.44% |
33.33% |
22.51% |
13.61% |
| 高松 |
24.62% |
14.57% |
73.68% |
31.58% |
19.44% |
12.78% |
| 大阪 |
16.52% |
13.68% |
41.30% |
32.61% |
12.75% |
10.78% |
| 名古屋 |
15.00% |
12.50% |
40.00% |
40.00% |
10.59% |
7.65% |
| 東京 |
17.43% |
14.86% |
50.00% |
50.00% |
10.96% |
7.88% |
| 仙台 |
12.50% |
7.00% |
56.25% |
31.25% |
8.70% |
4.89% |
| 札幌 |
22.50% |
19.00% |
50.00% |
36.36% |
19.10% |
16.85% |
| 全国 |
18.37% |
13.74% |
49.54% |
36.70% |
14.03% |
10.23% |

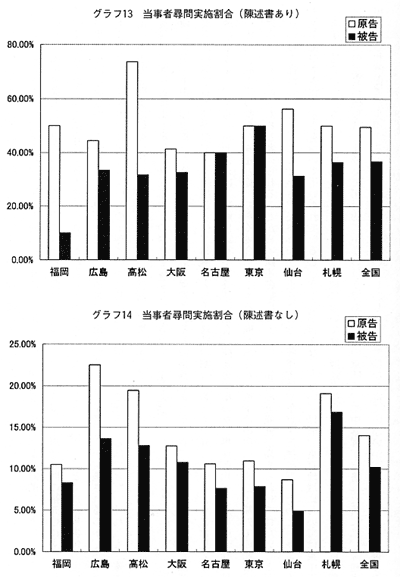
ここでも、当事者尋問実施のあった事件の割合を原告・被告それぞれについて示している。これらの表・グラフを俯瞰して言えることは、証人尋問実施率と同様に、陳述書提出事件の当事者尋問実施率が相対的に大きいということである。陳述書提出と当事者尋問実施の間には一定の関係性が窺える。ところで、当事者尋問の補充性にもかかわらず、陳述書提出事件の割合は、証人尋問実施のそれよりも小さくなっているとは言えない。とくに、被告側の実施率は当事者尋問の実施率の方が高いとも評価し得る。陳述書が提出されるから当事者尋問が実施されるのか、当事者尋問実施のために陳述書が利用されているのか等といった具体的な分析はここで行うことはできないけれども、陳述書提出と当事者尋問実施の関係性についても立ち入った検討が必要であろう。
最後に、陳述書提出と事件の終局事由との関係を確認しておきたい。(表9参照)
表9 終局事由
|
|
判決 |
取下げ |
和解 |
放棄・認諾 |
その他 |
| 件 数 |
件 数 |
件 数 |
件 数 |
件 数 |
| 全国 |
全 体 |
884 |
326 |
655 |
19 |
16 |
| 陳述書あり |
134 |
14 |
69 |
1 |
0 |
| 陳述書なし |
750 |
312 |
586 |
18 |
16 |
| 福岡 |
全 体 |
90 |
44 |
62 |
3 |
1 |
| 陳述書あり |
11 |
2 |
6 |
0 |
0 |
| 陳述書なし |
79 |
42 |
56 |
3 |
1 |
| 広島 |
全 体 |
89 |
40 |
69 |
2 |
0 |
| 陳述書あり |
5 |
1 |
3 |
0 |
0 |
| 陳述書なし |
84 |
39 |
66 |
2 |
0 |
| 高松 |
全 体 |
106 |
36 |
52 |
0 |
5 |
| 陳述書あり |
14 |
2 |
3 |
0 |
0 |
| 陳述書なし |
92 |
34 |
49 |
0 |
5 |
| 大阪 |
全 体 |
154 |
51 |
137 |
3 |
6 |
| 陳述書あり |
26 |
3 |
16 |
0 |
0 |
| 陳述書なし |
128 |
48 |
121 |
3 |
6 |
| 名古屋 |
全 体 |
69 |
50 |
75 |
6 |
0 |
| 陳述書あり |
19 |
2 |
9 |
0 |
0 |
| 陳述書なし |
50 |
48 |
66 |
6 |
0 |
| 東京 |
全 体 |
163 |
45 |
135 |
4 |
3 |
| 陳述書あり |
33 |
3 |
21 |
1 |
0 |
| 陳述書なし |
130 |
42 |
114 |
3 |
3 |
| 仙台 |
全 体 |
118 |
33 |
48 |
1 |
0 |
| 陳述書あり |
11 |
1 |
4 |
0 |
0 |
| 陳述書なし |
107 |
32 |
44 |
1 |
0 |
| 札幌 |
全 体 |
95 |
27 |
77 |
0 |
1 |
| 陳述書あり |
15 |
0 |
7 |
0 |
0 |
| 陳述書なし |
80 |
27 |
70 |
0 |
1 |
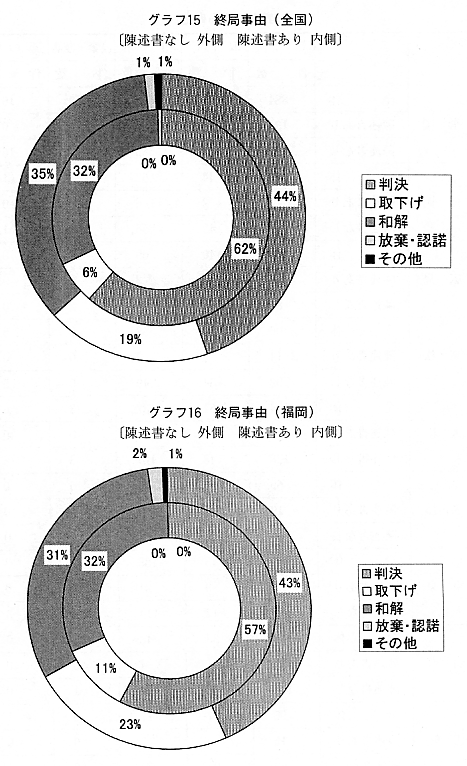
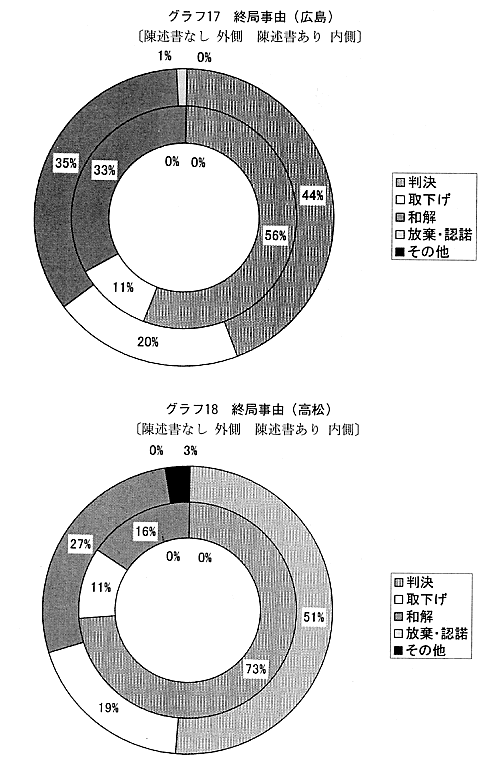
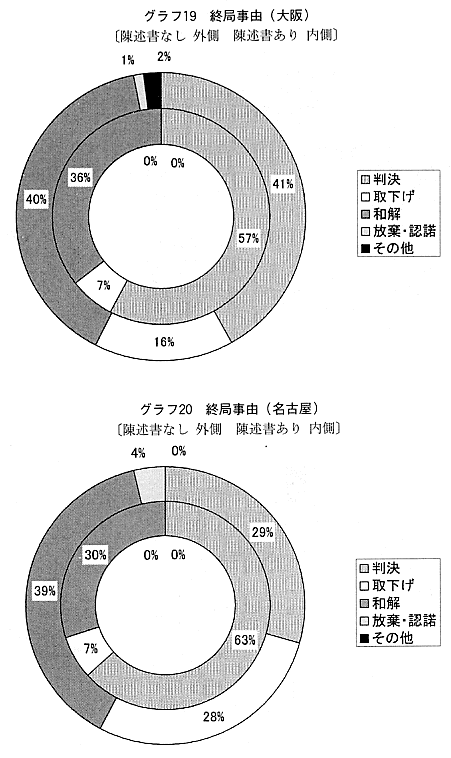
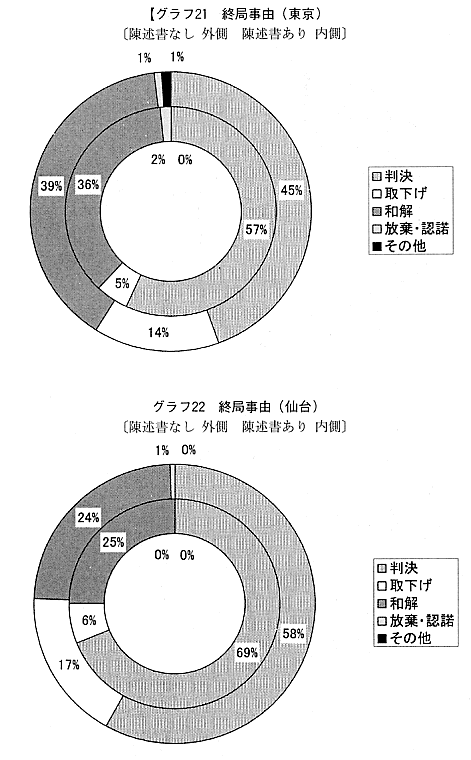

陳述書が「主張」固定機能を持ち、その結果和解が促進されるとの指摘があるが、右の表・グラフに示した陳述書提出事件に関する本調査のデータ結果からは、和解による手続終結の割合が著しく上昇しているようには見えない。地域にもよるが、どちらかと言えば、和解による手続終結の割合は陳述書提出のない事件と比べて小さいように見える。また、取下げの割合が陳述書提出のある場合に低下する傾向があるが、取下げの中には訴訟手続外での和解成立を理由とするものがあると考えられることから、陳述書提出によって、和解の可能性が高まるわけではないことがこの点からも推測し得る。このことから、民事訴訟法改正前における陳述書は、争点・証拠整理のためというよりも、人証実施の簡素化に重点をおいて用いられているということが言えなくもない。以前、東京地域においては集中審理の萌芽が見受けられることを指摘したが(18)、その東京地域においては、陳述書提出のある場合とない場合の和解の割合についての差異が他地域と比較して相対的に小さいほうである。その意味で、集中審理が定着した折には、陳述書利用による和解促進が実現する可能性は否定できない。しかし、本稿ではなし得ていないが、この点は、陳述書の提出状況と人証実施の関連性に関する分析結果と併せて検討されることが必要であろう。
他方で、陳述書提出事件の特徴は、そうでない場合と比較して、判決による手続終結の割合が大きくなり、取下げの割合が低下することである。その理由は一体何であろうか。これまでの分析においても見られたように、陳述書提出事件については訴額が大きく、審理期間も長く、人証実施の割合も大きいことが窺える。それゆえ、当事者が最後まで対立し、取下げによる手続終結を拒否し、裁判所の判決による決着を望むのかも知れない。現行法の集中審理方式が定着した場合に、このような傾向が変わる可能性については注意を向けるべきであろう。手続終結の状況に変化が見られた場合には、陳述書の利用形態、たとえば、争点・証拠整理段階における証拠提示等のために陳述書が利用される傾向が定着しているかも知れないからである。
結 び に か え て
陳述書は現行法のもとでの活用が必ずしも消極的には解されていない印象を受ける。その一方で、陳述書については法律の明文や外国法にその考察の手がかりを求めることができず、理論研究者の側は陳述書をめぐる諸問題に取り組む場合その考究の手がかりとなるものを持てない可能性がある。そこで、本稿では、陳述書に対する理論的検討の前提として、陳述書の利用実態を計量的に明らかにすることを企図した。ともすれば理論研究者の側はその実態を十分に認識せず、陳述書に関する論議を進めてしまう恐れがあるため、このような作業にも相当の意味はあると考えたからである。
このような意図から、本稿では、民事訴訟実態調査から得られたデータをもとに、陳述書が提出された事件とそうでない事件との比較を若干の項目につき行なった。そこから得られた分析結果はつぎのようなものである。まず、陳述書が利用された事件は、全国で見れば、全体の一割強であった。この割合が今後どう変わるかは興味深い点である。地域的に見れば、東京、大阪、名古屋の三大都市圏の利用率が他地域に比較して高いものとなっており、陳述書の利用は大都市部を中心に利用されていたことが分かる。弁護士により代理された事件の割合も陳述書提出事件では大きくなる。このことから、陳述書の提出にあたっては、代理人弁護士の関与が大きな意味を持つことがわかる。弁護士が裁判所によるいわゆる「頭越し」の情報収集を嫌い、ごく形式的な陳述書の提出しか認めないのであれば、陳述書の利用率は高まらないであろう。かかる意味からも、今後の民事訴訟実務における陳述書の利用状況を見極める必要がある。つぎに、陳述書提出事件の特徴は、提出のなかった事件と比較して、当該訴訟手続に関与する訴訟当事者の平均人数が多く、訴額も高めであった。これらのことから、陳述書提出事件は、そうでない事件よりも複雑なものであることが容易に推測され得る。このことは、口頭弁論期日回数や審理日数の長さから見ても、また証人尋問の実施率や当事者尋問の実施率の高さからも補強できる推測である。このような仮定を前提にすれば、主尋問の代替のために陳述書を用いたり、そもそも人証実施を省略するというような、いわば陳述書を人証実施の簡素化のために用いる実務が急速に普及したことも納得がいく。審理負担の軽減にこれらが結びつく可能性があるからである。さらに、事件の規模の大きさや複雑さからすれば、裁判所の側ができるだけ早期に事件全体の「ストーリー」を把握したいという欲求が強くなるのも首肯できる。日本には、ディスカヴァリーのような強力な証拠開示手段が今もってないわけであり、今回の改正により争点・証拠整理の手続が整備され、証拠収集手段が拡充されたとはいえ、訴訟の初期段階で要件事実的な枠組みを与えられた「紛争」の提示だけでは満足しない裁判官が将来存在するとしても不思議ではない。その意味で、民事訴訟実態調査データに関しても争点・証拠整理段階における陳述書の利用状況を確認しておく必要がある。陳述書の利用により、和解が促進される可能性が示唆されているが、民事訴訟法改正前におけるデータから、このことは窺えなかった。むしろ、判決による決着の割合が高く、当事者間の対決姿勢が垣間見えるとも言える。この点に関するデータの傾向につき、何らかの変化が見られた場合、陳述書の機能の転換、とくに争点・証拠整理を目的とした利用の拡大がなされているかも知れない。
もちろん、これまでの分析で陳述書の利用実態が明らかになったわけではないし、民事訴訟実態調査のデータが全国の陳述書利用状況を完全に体現していると言い切ることは困難であろう。しかしながら、なお、このデータを参照しつつ、検討すべき項目は残されているように思われる。第一章で指摘したように、陳述書の利用に関しては実務法曹の中でも評価の分かれるところがあるようであり、その意味で、たとえば、裁判官ごとの陳述書利用状況を考え、また陳述書の提出状況につき代理人弁護士の有無を基軸にした種々の分析を行なうことにも意味はあろう。また、陳述書の提出状況を他の書証や準備書面のそれと比較してみることも本稿では成し得ていない。さらに、人証実施の時期と陳述書提出時期につき、たとえば、陳述書作成名義人に対して人証取調べが実施されたような場合等につき、今少し立ち入った分析も必要であろう。陳述書の利用実態の特徴を明らかにするという本稿の目的から、検討すべき問題点がこれらに尽きるものでないことを自覚しつつも、ここで本稿を閉じたい。
(1) 弁論兼和解のはらむ諸問題を理解する文献として、高橋宏志「民事訴訟法改正と弁論兼和解」『新民事訴訟法論考』八二頁以下(一九九八年、初出一九九四年)が有用である。
(2) この問題点に関する理論の側の先行業績として、山本克己「人証の取調べの書面化−「陳述書」の利用を中心に−」自正四六巻八号五四頁以下、また同「陳述書問題につい−シンポジウム「新民事訴訟法のもとでの審理のあり方」を契機に−」判タ九三八号六九頁(一九九七年)。なお、陳述書をめぐる諸問題を俯瞰するための実務法曹による有益な文献として、・須弘平「争点整理における陳述書の機能」判タ九一九号一九頁以下(一九九六年)。大段亨「陳述書の活用」自正五二巻二号一〇二頁以下(二〇〇一年)。
(3) 小林秀之・田村陽子「第二編第三章第二節(六)陳述書」小室直人他編『別冊法学セミナー基本法コンメンタール新民事訴訟法2』一五五頁(一九九八年)
(4) 伊藤眞『民事訴訟法[補訂版]』三三九頁(有斐閣、二〇〇〇年)。
(5) 高橋宏志「陳述書−研究者の視点から」『新民事訴訟法論考』一二二頁(信山社、一九九八年、初出一九九六年)等。
(6) この点の問題意識について、高橋・前掲註(5)一二四頁参照。
(7) 山本克己(発言)「座談会/民事集中審理の実際」八八六号二〇頁(一九九五年)。
(8) 以下に示す分析の視点を得る上で、高橋・前掲註(5)論文に多くを負っている。
(9) 西口元「陳述書をめぐる諸問題−研究会の報告を兼ねて」判タ九一九号三六頁(一九九六年)、および同頁註(1)に挙げられる諸文献参照。
(10) 西口・前掲註(9)三六頁。
(11) 篠原勝美ほか「民事訴訟の新しい審理方法に関する研究」司法研究報告書四八巻一号一五五頁(一九九六年)。
(12) 篠原ほか・前掲註(11)七六頁以下。この場合、陳述書には、事実認定に重要な当事者の主観的あるいは感情的な動機・認識が記載される可能性があり、準備書面では担保しきれない効用があるとされる(同七七頁)。
(13) 弁護士の陳述書に対する当初の素朴な疑念として、那須・前掲註(2)一九頁参照。
(14) たとえば、北尾哲郎「陳述書の運用準則」判タ九三七号五八頁以下(一九九七年)参照。
(15) 高橋・前掲註(5)一一二頁。
(16) 高橋・前掲註(5)一〇九頁。
(17) 陳述書の早期提出により、争点の早期固定がなされ、早期に和解に入る可能性を示唆するものとして、高橋・前掲註(5)一一二頁ー一一三頁、一二七頁註(13)。
(18) この「争点整理期間」に関する分析については、拙稿「争点整理」民事訴訟実態調査研究会[代表竹下守夫]編『民事訴訟の計量分析』一六八頁ー二二〇頁(商事法務研究会、二〇〇〇年)参照。もちろん、旧法下においては、この期間は必ずしも争点整理のみに特化された審理が行なわれていたと評価することは困難であるかも知れない。しかしながら、弁論の準備の不十分さが指摘されてきた旧法下の審理において、そもそもこのような期間を設定し、その中で、あるいはその後にどのような審理がなされていたかに注目することは、争点・証拠整理手続が整備され、集中審理方式が採用される現行民事訴訟法の審理を実証的に理解する上でも大切である。また、今後行われる可能性のある類似の調査のためにも、かかる期間を取り巻く審理状況に関するデータを提示することにも意味がないわけではないと考えるからである。なお、証拠調べの枠組みから陳述書につき検討するものとして、岡田幸宏「第五章証拠調べ第二節書証・陳述書関係」同書二七八頁ー二九四頁参照。
(19) 拙稿・前掲註(17)一七二頁参照。
|