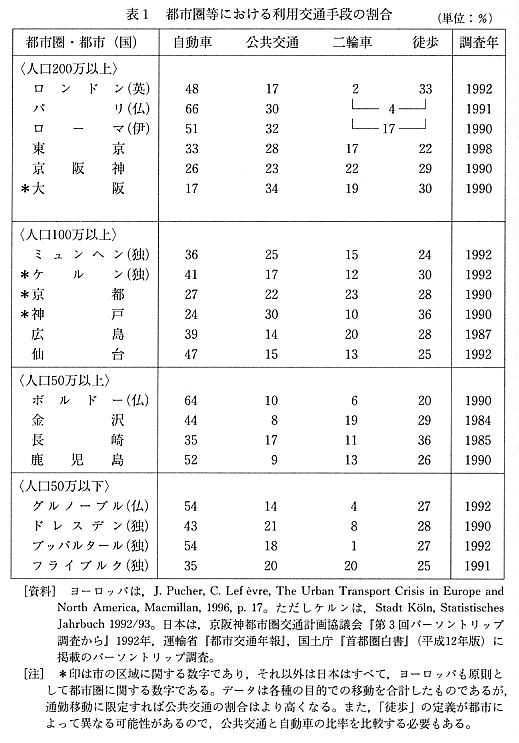|
一、は じ め に
二、日本の都市政策の手法と成果-西ヨーロッパとの比較
三、政策の特徴と政治行政過程
四、要約と展望
一、は じ め に
1960年代の高度経済成長のなかで、都市の成長がもたらす施設需要と弊害に公共政策と市場とは十分対応できず、都市問題が深刻化した。日本は公害の実験場と呼ばれ、「交通戦争」の犠牲者が増え、狭い住宅は欧米から「ウサギ小屋」とからかわれた。80年代には経済大国となった自信のなかで都市開発が進んだが、それが地価の急騰、バブル経済後の不況を生み、都市政策の根底を揺るがした。それでも、道路、鉄道、住宅、公園などのストックはしだいに増加し、アメニティ、人や環境にやさしいまちづくりなど新たな視点も導入されてきた。日本の都市は、高度成長期はカオスだったが、最近はかなりよくなったというのが、多くの人の実感だろう。
この論文は、日本の都市政策の全体像を描き、特徴を説明し、評価しようとしている。もちろん、都市交通、都市再開発などの個別分野だけでも十分すぎるほど複雑であり、それぞれに関して専門家が分析を積み重ねている。しかし、この論文は、マクロに都市政策の全体を対象とし、それを分野ごと、手法ごとに分けて検討し、かつ西ヨーロッパとの比較をおこなうことによって、次のような問題関心に答えようとするものである。
・都市政策の分野、目標によって達成水準や発展速度が違うか。それはなぜか。
・それぞれの分野において、適用される手法(政府の投資、市場メカニズムの利用、政府の規制)の選択に偏りがあるか。それはなぜか。好まれる手法の傾向には、分野を超えて共通性があるか。それぞれの手法には、どんな長所と短所があるか。
・これまでの日本の都市政策の成果、および今後の課題は何か。
以上の問いとともに、個別分野の分析においても多少の示唆が得られれば幸いである。
(1) 公共政策研究の方法
政策研究においてとくに着目すべきなのは、政策の内容(目標と手法)、政策過程(決定・執行過程)やそれへの参加者、そして政策の結果-政府の出力(output)およびそれによる社会的効果(outcome)-であろう(1)。
このうち政策過程には、政党、首相・大臣、中央省庁の官僚制、地方自治体、市民、企業、利益集団、専門家集団などのアクター(参加者)が、それぞれ固有の価値、情報、利害関心などをもち、それにもとづく意見をもって参加する。政策過程においては、アクターのあいだで議論、交渉、強制などの相互作用が繰り広げられる。ここでとくに関心の対象になるのは、アクター(やその同盟)間における影響力関係、そして相互作用である(2)。影響力関係とは、誰の意図が誰をどのように動かしたか、つまり「だれが支配するのか」という古典的な問いかけであり、これはたとえば政策過程のパターンを官僚優位型、政党優位型、自治体主導型、市民参加型などと分けて検討することにつながる。しかしアクターの勝ち負けと同じくらい重要なのは、政策立案や協力関係の質であろう。それを生み出すアクターの相互作用を分析する枠組みとしては、閉鎖的な政策共同体と開放的なイシューネットワークの対比(3)や、政策過程を流動的な参加者による政策と課題の偶然的な結び付けと見る「ゴミ缶モデル」などがある。もちろん、政策の内容の選択や決定・執行過程は、各種の制度や政策の伝統(「政策遺産」)によっても、規定される。
さて、分析のモデルはそうであっても、実証的に研究する場合には、2つの課題が生じる。第1に、個々の要因に関する事実の確定作業である。たとえばアクターが公式に表明している意見、価値や把握している情報は、文書(白書などの出版物、審議会議事録、議会での発言など)で確認できるが、アクターの抱く利害関心や動機に関してはそうした確認方法をとりにくい。アクターの影響力関係や相互関係のパターン(たとえば官僚と業界、族議員の同盟関係)も、表面に現れない場合がある。むしろ、結果としての政策内容(目標、手法)の選択状況を把握し、そこからさかのぼって、各アクターの意図やその背景、相互作用を推定するという方法も用いなければならない。第2の課題は、個々の要因間の因果関係である。たとえば、行政主導の政策過程はどのような政策選択につながりやすいか、どんなスタイルの住民参加が望ましい政策選択をもたらすか、といった因果関係の究明である。この作業のためには、変数(要因)の値が異なる複数のケースを比較することになる。時間軸に沿ってたとえば70年代と90年代の政策過程の違いを比べる研究や、あるいは政策間、自治体間、国家間での比較研究が手掛かりを与えてくれるだろう。
以上は1単位の意思決定過程であるが、実際にはそれが時間軸に沿って展開される。ひとつの政策の決定・執行過程は、アジェンダ(議題)設定↓企画立案↓決定↓執行↓評価↓フィードバックという経過をたどって進行するというモデルがあり、現実にそのまま当てはまるものでないとしても、現実の流れを記述し解釈するうえで便利である。さらに、一度導入された政策は、何年か経つうちに改善されたり、執行が怠られて衰退したり、他の政策と調整統合されたり、役割を終えて縮小・停止されたりする。こうした政策発展のメカニズムも研究のテーマとなるだろう(4)。
この論文では、以上の枠組みを厳密に適用するわけではないが、まず政策の目標、手法、効果について各分野間の比較、西ヨーロッパとの比較をおこない(二)、そうした政策選択の特徴からさかのぼって、背景にある政治行政その他の要因について考察する(三)ことにしたい。
(1) 政策研究の全体像については、宮川公男『政策科学入門』東洋経済新報社、1995年、草野厚『政策過程分析入門』東京大学出版会、1997年、T.R.
Dye, Understanding Public Policy, 8th ed., Prentice-Hall, 1995;W. Parsons,
Public Policy, Edward Elgar, 1995 などの本が参考になる。理論動向については、P.A. Sabatier
(ed.), Theories of the Policy Process, Westview Press, 1999.
(2) アクター間の影響力関係やネットワークに注目した研究として、たとえば、中野実『日本の政治力学』日本放送出版協会、1993年、草野厚『連立政権日本の政治1993-』文春新書、1999年、Parsons,
op. cit., p. 248-271;Y. Rydin, Urban aud Environmental Plannng in the
UK, Macmillan, 1998;R. Czada, Reformloser Wandel. Stabilita¨t und Anpassung
im politischen Akteursystem der Bundesrepublik, in:T. Ellwein, E. Holtmann
(Hrsg.), 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland, Westdeutscher Verlag,
1999.
(3) 伊藤光利ほか『政治過程論』有斐閣、2000年、11章、R. Hague et. al., Comparative Government
and Politics, 4th ed., Macmillan, 1998, p. 123-124.
(4) 村上弘「日本の地方自治と政策発展」水口憲人ほか編『変化をどう説明するか地方自治編』木鐸社、2000年。
二、日本の都市政策の手法と成果-西ヨーロッパとの比較
以下では、日本の都市政策(1)を10の分野に分けて、目標と手法、成果を概観し、ヨーロッパとの比較をまじえて特徴づけ評価する。なお、政府とは、国と地方自治体の総称である。またヨーロッパとは、イギリス、ドイツ、フランスなどの西ヨーロッパ先進工業国を指す。欧米の水準に追いつくことは都市政策の年来の目標であり、毎年の『建設白書』は資料編のなかで必ず、下水道、都市公園、住宅の床面積、道路延長、河川の氾濫防御率などの数字を比較する表を示して、日本が欧米諸国に及ばないことを訴えてきたのである。
政策手法を3つのタイプに分類し、それを念頭において各政策分野を検討することにしよう。
・政府投資-国または地方自治体が投資をおこなう(公共投資)。
・民間投資の誘導-企業や国民による投資その他の活動を、政府が財政援助、基準設定、情報提供等によって誘導する。
・政府による規制-企業や国民の活動を、政府が義務づけ、または制限する。
(1) 道路整備とTDM
日本の道路は、1953年の揮発油(ガソリン)税の特定財源化に支えられ、翌年、他の分野に先立ってスタートした5か年計画にもとづき、国と公団、都道府県、市町村の公共投資によって順調に整備されてきた。高規格幹線道路の延長は99年度には7548キロに達し、イギリス3303キロ、ドイツ1万1400キロ、フランス1万300キロと比べても、とくに国土面積・平地面積を計算に入れれば、遜色はない。2000年の『建設白書』は引き続き道路建設の必要を主張し、前記道路の21世紀初頭の目標を1万4000キロに置いている。しかし、その根拠を、従来の同白書のように欧米水準からの立ち遅れに求めることはほとんどせず、結局、道路渋滞の悪化と地域開発の必要性をおもな根拠としてそう主張しているという点は、注目に値する(2)。
日本の道路交通の特徴はトラックの多さにあるようだ。自動車による貨物輸送量(トンキロ換算)自体は英独仏の2倍程度なので、人口当たりでは同じレベルだが、それにしては驚くのが、トラック保有台数が日本2068万、イギリス330万、ドイツ318万、フランス364万という数字(1998年)である(3)。「道路を倉庫がわりに使う」と形容された材料・部品輸送やキメ細かにサービスするコンビニエンスストア、宅配便など、物流の効率の悪さを反映している可能性が大きい。このことが渋滞、騒音、排気ガスなどをいっそう深刻にしているのだろう。
さて、90年代、道路の量的拡大という目標に対する疑問が強まってきた。道路批判のおもな根拠は、環境・景観への影響と、建設費の大きさである。
自動車交通は、快適であり目的地まで直接行けるという利便性を持つために、旅客、貨物輸送ともにそのシェアを拡大してきた。反面、道路を利用した自動車交通は、たとえば鉄道と同じ数の乗客を運ぼうとすれば、より大きい占有面積と、約6倍のエネルギーを要する。それだけ、用地費も、環境や景観への負荷も、道路の方が大きい。ただし、鉄道の場合には車両費用や人件費も含めたものが、事業主体の負担となるのだが。
環境・景観に対する影響を抑えるための対策には、つぎのようなものがありうる。
① 自動車排気ガス、騒音の規制。1970年代以降、環境庁と運輸省は、排出ガス(黒煙、窒素酸化物など)、騒音の規制をしだいに強化してきたが、自動車数とくに排出量の大きいディーゼル車の増加によって、大都市の大気汚染状況は改善されていない(4)。国際比較をすると、窒素酸化物の排出総量(人口1人当たり)で見るかぎり、自動車メーカーが規制に対応し技術改良に努めてきたこともあって、日本は英独仏をかなり下回っている。しかし、局地的な大気汚染はひどく、また65dB以上の交通騒音にさらされている人口も日本では約3800万人に達し、イギリス570万人、ドイツ950万人、フランス940万人と大差がある(5)。トラックの多さや、幹線道路周辺に住宅地が密集するような土地利用のありかたが原因だろう。
② 道路の地下化。日本の都市高速道路は、短期間につくるために高架式が基本であり、大阪でのように運河を埋めたてて用地を確保することも多かった。地下高速道路は、東京(皇居の周辺)、横浜(都心部の分断を避けるため)、および計画中の京都(古都の景観保全)でみられるくらいである。それ以外の地域でも住民からトンネルまたは掘り割り方式を要望する声が多いが、おもに建設費の問題によってほとんど実現されていない。たとえば掘り割り方式でも、高架方式の2倍程度の費用がかかるといわれる。
ヨーロッパの都市では、ふつう周辺からの高速道路は都心部に入り込まない。ロンドンでは、都心部での建設計画が、住民の反対と地方選挙の結果をうけて中止された(6)。中心部での抑制とは違って、都市周辺部の高速道路はよく発達しており、自動車の利便を保障する政策をとっているようだが、ここでもパリ、ミュンヘン、デュッセルドルフなどでは一部を地下化している。さらに、都心部にあった幹線道路を地下トンネルに埋めて地上の跡地を公園化する事業が、ケルンやデュッセルドルフで完成している(7)。
③ さらに根本的な対策としては、交通需要を分散、縮小、他の交通手段への転換などによって抑制する「交通需要マネジメント」(Transportation
Demand Management:TDM)がある。これは、需要に対応した交通施設・サービスを供給することを目標にしてきた従来の政策からの発想の転換を、意味している。その場合、需要抑制のターゲットは自動車交通である。具体的には、パークアンドライド、公共交通の充実など投資的手法と、都心への自動車乗り入れの抑制、自動車利用への課税など規制的な手法とがある(8)。それによって道路建設を抑えることができるならば、予算を公共交通に振り向けることも期待できる。
しかし、道路抑制論に対して、建設省は全面的に反論してきた。『建設白書』によれば、道路整備は地方圏では経済振興につながり、都市部では渋滞緩和とそれによる排気ガスの減少を可能にする。
争点は、自動車交通需要は道路の整備によって新たに誘発されるか、あるいは道路を整備しなくとも増え続けるか、限られた財源を道路と公共交通とでどう配分するか、そして、限られた財源のなかで優先されるべき効果の高い道路は何か(たとえばバイパス)、の3つであろう。
(2) 歩行者空間
「交通戦争」とまで呼ばれた事故の激増に対して、ようやく1966年に交通安全3か年計画が、また70年に交通安全対策基本法がつくられた。さらに近年の『運輸白書』では、「都心の活性化や都市観光の振興」が、歩道整備の理由づけに加わっている。
政策手法の中心は、限られた道路空間の利用に関して自動車交通を規制するものとなる。弱い規制から強い規制へと順に並べると、路面表示による歩道、車道と物理的に区別した歩道、コミュニティ道路(歩道を拡幅し通過自動車交通を抑える)、トランジットモール(歩行者道路とし公共交通のみ乗り入れを認める)、歩行者専用道路である。日本では、歩道の整備に加えて、81年に国庫補助事業となったコミュニティ道路の整備が進み1000カ所を超えている。しかし、トランジットモールやまとまった歩行者専用道路は、三、で後述するような理由からほとんど設定されていない。
歩道等整備済み道路延長は12・8万キロで、舗装・簡易舗装された国・都道府県・市町村道の合計83・5万キロに対して約15%に過ぎない(95年(9))。整備の遅れを間接的に示すデータとして、歩行中の交通事故死者数を人口10万人当たりで見ると、日本2・8、アメリカ2・0、フランス1・7、ドイツ1・4である(97年(10))。しかし、歩道整備率は、『建設白書』でも道路延長や舗装率に比べてまれにしか登場しない。とくに、他の都市施設についてはしばしば示される自治体別の数字を、歩道についても広く公表することが、改善を促すだろう。
もちろん、区画整理等による幅の広い道路では、歩道も広くとられている。問題は、過去につくられ両側に建物が並ぶ狭い道路での歩道確保なのだが、コミュニティ道路化は一方通行化を伴うので条件のよい場所でしかできない。それ以外のうまい方法を研究しモデルを示す必要がある。
逆に、自動車を規制せず立体的に歩行者空間を確保する投資型の手法である、歩行者デッキや地下街(普通は商店街)は、日本ではヨーロッパに見られないほど普及している。
ヨーロッパでは、都心部に歩行者専用地区をつくることは常識になっている。ドイツでは1930年代から始まった歩行者地区が、60年代に全国の都市に広がった。イギリスでは、まず地方自治体のイニシアチブでこれが設置されたあと、71年の都市計画法が法的根拠を与えた。都心部への自動車乗り入れ規制は提唱されつつも実現に至っていないが、ヨークなどの都市では歩行者地区を拡大し、事実上の乗り入れ制限の効果を生み出している。イタリアでも60-70年代に、都市商業・観光振興の目的もあって、歩行者地区を設ける都市が増えていった(11)。また、トランジットモールも、ロンドン(オクスフォード通り)やチューリヒ、ストラスブール、フライブルク(ドイツ)など、各地に設けられている。
さらに、日本では大量の自転車の駐輪が歩道をふさいでしまう。都市自治体は、駐輪場を整備し、大型店等にスペース確保を要請し、禁止区域に停めた自転車を撤去し有料で返却するなどの対策を進めてきた。これはかなり強い規制的手法で、撤去の頻度が高ければ一定の成果はある。
ヨーロッパの都市でもやはり自転車は路上に置かざるをえないが、そもそも歩行者エリアが広く、さらにそこに自転車を効率的に並べるための設備が設けられていることも多いので、歩行者の妨げにはなりにくい(12)。日本は駐輪対策が遅れているというよりも、むしろ歩行者空間の狭さ、あるいは自転車利用者のモラルが問題なのである。同様に、歩道にはみ出す看板類(昔の写真を見るともっとひどいが)や歩きながらの喫煙(以前は駅や電車内で被害があった)も、歩行空間の快適さを損なっている。これら多数の行為者への規制は日本では困難であるが、たとえば神戸市の「ポイ捨て禁止条例」は、たばこの吸い殻の投げ捨てを禁止しており、間接的に歩きながらの喫煙を抑制できるかもしれない。
(3) 公共交通
公共交通とは、大量輸送機関(鉄道)、中量輸送機関(バス、路面電車、モノレールなど)を指す。公共交通の重要性はまずその輸送効率の高さにあり、とくに大都市では不可欠だろう。また、すべての市民への交通サービスの保障、環境汚染の軽減といった利点、さらに企業の立地条件の向上、中心市街地の活性化、郊外住宅地のスプロールの防止など都市形成上の利点もあげられる。公共交通はこうした効果をもち、他方で投下資本が巨大でかつ労働集約型産業でもあるために、日本のように民間企業によって広く担われる場合にも、政府による補助が望ましいとされる(13)。
まず、日本とヨーロッパの政策の成果を比べてみよう。
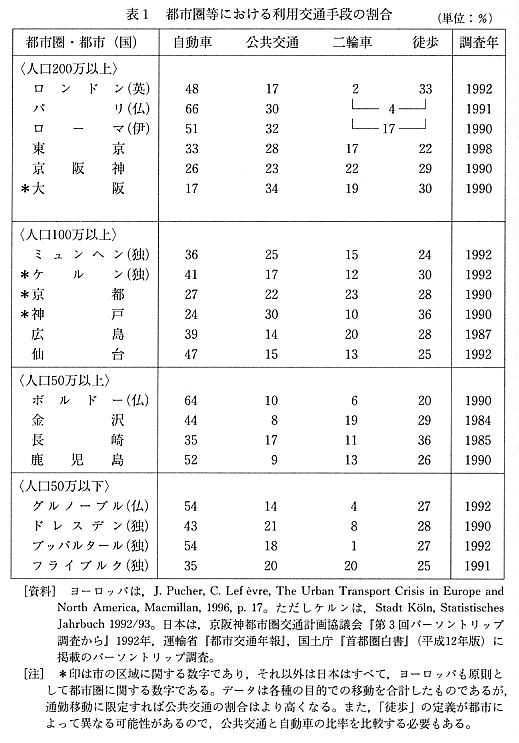
第一に、サービスの量と質について、ロンドン、パリ、ニューヨークとの比較調査によれば、東京の鉄道は駅数や路線などのネットワークが稠密で、遅れがほとんどなく定時性が高いが、しかし満員電車のひどさは「世界中で知られている(14)」。
第二に、公共交通の利用率については、とくに自動車交通(マイカー)との競争の結果が注目される。利用交通手段の割合(modal split)に関する調査結果を集めると(表1)、日本の大都市での公共交通のシェアは、パリ、ローマ、ミュンヘンと並んでいる。住宅の遠距離化と道路渋滞のゆえに鉄道を消極的に選ぶ側面があるとしても、大都市の高速鉄道の水準は高い。ところが逆に、中小都市では、公共交通の利用率はヨーロッパより低く、マイカーに圧倒されている。
公共交通の利用率は、ヨーロッパの大陸諸国で高く、イギリスやカナダがそれに次ぐが、アメリカではニューヨーク等を除いて極端に低い。ヨーロッパの都市でも70年代以降、公共交通のシェアが下がりつつあるが、フライブルク、ミュンヘン、チューリヒ、ウィーンなどではむしろ自動車の利用率を抑えることに成功しているという。こうした格差や変化は、国や自治体の政策-土地利用計画との連携、交通乗り換えの利便改善、自動車に対する課徴金・交通規制、公共交通の魅力向上-が市民の行動を変えうることを示している(15)。
日本の公共交通もかなり健闘しているが、多くの人が体験している問題として、①大都市での鉄道の非常な混雑、②道路を利用する「中量輸送機関」の苦戦、③地方都市での利用率の急減がある。そして、こうした弱点は、政策目標の設定の低さによるというよりも、政策手法の選択と関連しているようだ。
①は結局、大都市の規模や住宅の郊外化の問題であるとともに、建設投資の不足の問題になる。つまり、東京23区では、ロンドンやパリに比べて流入する鉄道利用者は3倍にのばっているのに、鉄道の路線密度はやや低い。1975-98年に東京圏では輸送力は1・6倍に改善されたが、乗客も1・35倍に伸びたので、ラッシュ時の混雑率は221%から186%に下がるにとどまった(16)。東京圏では、列車の編成の長大化と運転間隔の短縮は限界に達し、輸送力強化のためには複々線化か新線建設しかないという。
ヨーロッパや北米では、公共交通の料金収入は運営費用の3-7割をカバーするにとどまり、残りの運営費(および建設費)は公的資金によってまかなわれている(17)。これに対して日本では、建設費への補助は拡大されてきて、地下鉄では70%が国・地方自治体の一般会計から補助され、民鉄では資金融資や鉄道公団による建設・貸付を受けることができる。また、民鉄が大規模な輸送力増強工事のために運賃を上乗せすることも、政府は認めてきた(18)。しかし、運営(営業)費用については原則として補助はなく、独立採算に近い考え方がとられている。実際にも、大都市の民鉄や地下鉄では、鉄道営業収入が同営業費を上回っている。しかし、営業収入からは人件費に加えて、さらに減価償却費や過去の債務の支払い利息をも賄う制度になっており、こうした収支計算の結果、全国の自治体交通事業の経常収支は、地下鉄のすべて、バスの多くが赤字となっている(19)。民鉄も、鉄道部門の赤字を不動産開発などの関連事業収益で補填してきた。
②③について、大都市や地方都市の路面電車が60-70年代に衰退したのは、人口の郊外拡散に路線が対応できず、また自動車の増加による渋滞に巻き込まれたからであった。経営が①で述べた理由もあって苦しく、自治省は地方公営交通事業の財政再建策として市電の廃止を勧めた。警察は広島などの場合を除いて自動車を規制しえなかった。しかし、近年では高性能化した路面電車の便利さ、地下鉄の10分の1程度という建設費の小ささが見直されつつあり、建設省は95年から施設整備への補助を導入した(20)。路面電車の復活の条件は走行の保障と車両の連結であり、前者は専用軌道、自動車乗り入れ禁止といった規制的な手法によるか、あるいは渋滞の激しい都心部で一部地下化するかである。一部地下化でも本格的な地下鉄より安上がりで、ケルンやサンフランシスコに例がある。人件費を抑えて車両を連結するためにはドイツのような料金支払システムが良いが、これは一定の社会的モラルの存在を前提とする。
バスの場合、渋滞区間では短いバス専用レーンだけでも時間短縮効果が大きいが、警察の取締りでレーンへの自動車の侵入を防ぐことは困難だ。侵入車に警報する技術、道路脇やバスの先頭に設けたカメラで侵入車を撮影・摘発する技術が有望である(21)。なにしろ、停留所でバスの接近を表示する「ロケーションシステム」は、80年代から世界に先がけて整備されてきたのだから(22)。
(4) 住 宅
住宅状況のおもな指標は、量、質、都心からの距離、価格、建て方(一戸建てか共同住宅か)、および所有形態であろう。
所有形態からみると、日本の特徴は、持ち家が多く公共賃貸住宅が少ないことだ。1993年の全国データは、持ち家60%、公的借家(公営、公団)7%、民営借家26%、給与住宅(社宅)5%である。日本の持ち家率は、イギリス66%、フランス54%と並び、旧西ドイツ38%より高い。公共賃貸はスペイン2%、スイス4%などの例もあるが、オランダ36%、スウェーデン21%、フランス17%、旧西ドイツ15%など力を入れてきた国が多い(ドイツの「社会住宅(23)」などを含む)。イギリスは80年代に自治体の公共賃貸住宅を所有者に売却させる政策を取り、持ち家率が上がったが、公共賃貸の割合は33%(81年)から24%(92年)に下がったとはいえなお高いレベルにある(24)。もっとも、高層の公営賃貸の集中立地が地域環境の悪化を生む場合もあるが。
つまり、ヨーロッパでも持ち家への公的助成は盛んだが、同時に賃貸住宅にも公的投資をおこなってきた。ドイツのように持ち家と賃貸を同様に補助する政策は、所有形態に関して中立的(tenure
neutral)と言う(25)。これに対して、日本が1950年代以降「持ち家政策」を取ってきたといわれるのは、持ち家には所得税減税や住宅金融公庫の長期低利融資を通じた援助をする反面、賃貸の分野では低所得者向けの公営住宅(自治体が建設)とサラリーマン向けの公団住宅を限定的に供給し、それ以外は民営借家に委ねてきたからである。ただし、家賃高騰に対処して93年、ドイツの社会住宅にならった特定優良賃貸住宅が導入され、民間賃貸住宅に家賃や居住環境に関する条件付きで補助をおこないはじめた。
さて、日本の住宅政策では、まず量的充足つまり「1世帯1住宅」の目標が追及され、1968年ごろに一応達成された。この時期に全国の世帯数に対する住宅戸数の割合が100%に至ったが、この数字は98年には113%に達し、空き家が余っていることになっている。つぎに質的改善のためには、建設省は、住宅の床面積について、最低居住水準、誘導居住水準という2つの目標基準を設定している。全国平均の達成率は、それぞれ92%、41%であるが、たとえば東京圏では88%、30%と低い。建設省のこの基準には拘束力はないが、別に住宅金融公庫は融資の条件として、独自の建設基準(居住水準)を満たすことを求めている。
持ち家購入への融資と公共賃貸の少なさに促されて、民間の住宅建設が増え、民鉄会社や製造業が経営多角化のために参入することも多い。住宅建設5か年計画においても、計画戸数の大部分は民間による建設とする一方、公営・公団住宅は全体の1割以下を予定しかつその達成率は低い。宅地開発も、民間による供給が、公団や自治体による供給の3-4倍にのぼっている。60年代以降、国の公団および都道府県によって40程度の大規模な(300ヘクタール以上)ニュータウンが建設され、うち東京圏、大阪圏でそれぞれ11カ所を数える。民鉄等によるニュータウン開発も活発である(26)。ロンドン大都市圏で、戦後8つのニュータウン(合計目標人口は約65万人)が建設されてきたことにも匹敵する成果だといえよう。
質のうち、住宅性能はともかく住環境についてなお不満が高い。また、住宅地が郊外に拡大し、東京圏では都心への通勤に1時間以上を要する人が67%もある。原因は、都市人口の巨大さ、高地価、低層住宅の多さ、市内の未利用地・農地の多さなど多様だが、近年ではマンションの増加によって新たな都心近くでの居住も発生している。
価格については、国は91年の「生活大国5か年計画」のなかで無理のない価格として、サラリーマン世帯の平均年収の5倍という目標を設定している。当時は地価高騰によって、マンションですら東京圏で年収の10倍、大阪圏で8倍と手の届かない価格水準であったが、バブル経済崩壊後の地価下落とマンション建設ブームの結果、2000年には東京圏で5・4倍、大阪圏で4・4倍にまで下がってきている(27)。
住宅の価格を安定させる方法には、地価の安定の他に、①民間賃貸への家賃統制、②公共住宅の低家賃での供給、③民間住宅の家賃への補助、④公共住宅の大量供給による需要超過の解消、⑤民間住宅の供給増、集合住宅の増加による需要超過の解消、が考えられる。①の規制的手法は家賃急上昇への緊急対応としては必要な場合があるが、長期的には民間賃貸投資の減少、維持管理の不足による老朽化を招き、デメリットが多いとされる(28)。日本では地代家賃統制令(1939年)は50年に撤廃された。②は日本のように公共賃貸の戸数が限定されている場合、入居できた人とそれ以外との不平等を生む。③は特定優良賃貸のほか、人口減に悩む大阪市が新婚世帯を対象におこなっている例がある。日本では結局、おもに⑤の誘導を通じて価格をある程度安定化させてきたといえる。
(5) 都市計画
都市計画は、公共的な都市施設の整備計画と、民間を含む建設活動に関する土地利用規制とから成り立つ。都市施設のうち道路、公園などの整備は、自治体等が用地を買収するか、地元の負担においておこなうかになる。後者の代表的な手法である土地区画整理は「健全な市街地の造成」を目的とし、開発利益を得るものが負担をするという意味では適切な制度だが、土地の一部を提供し(減歩)また交換する(換地)ことには抵抗も多い。しかし、その成果は日本の市街地の30%に及んでいる。
土地利用規制は、ヨーロッパに比べてゆるやかである。戦後も、基本的には1919年の都市計画法が適用され、①スプロール(市街地の無秩序な拡大)、②住宅と工業地域との区分、③住宅と商業・オフィス地域の区分、④容積率、建ぺい率、高さ、⑤形態やデザイン、についてコントロールがないか弱かった。このうち、68年の法改正で、①を防ぐ市街化調整区域制度が導入された。用途地域区分の詳細化は、工場公害への対策として②について(70年)、地価高騰への対策として③について(92年、容積率規制を含む)、実現した。④の規制強化や⑤のコントロールは、選択メニューとしての地区計画(80年)や建築協定によって、実現可能になった(29a)。
日本の都市計画は、規制をさらに緩和することによって民間の投資意欲を高めるという方法にも転用されてきた。都心での住宅整備や公開空地の確保など特定の条件付きで容積率等を緩和し、民間による都市の整備を誘導する「総合設計制度」は有意義だろう。しかし、80年代の容積率等の規制緩和がバブル経済の引き金の1つとなってしまった(29b)のは、まだ記憶に残っているところである。
(6) 都市再開発
計画的な整備のなされていない、または建物が老朽化した市街地は多くあり、その改善を、政府投資よりも地元の企業・住民の負担を中心におこなうのが、市街地再開発事業である。この手法は、細分化した土地を統合して共同ビルを建設し、同時に道路、公園などを建設する。土地の所有権はビルの床に対する権利に変換される。公的な補助金に加えて、再開発ビルの床の一部(保留床)を大型店や自治体(公共施設用)に売却したり、住宅として販売することで、事業費を捻出することになっている。
5か年計画による目標値はないが、国は補助金を用意し、自治体が再開発方針をつくる。全国で643か所が完成または事業中であり、東京都で約100カ所、大阪府で約40カ所などと活発である。しかし、「駅前再開発」といわれるように、ビル建設の採算が取れない一般の商業・住宅地には適用できず、交通の要所以外の地域の改善は、基本的に個々の地権者か民間の開発業者に委ねられる。
再開発の成功のポイントは、地元の合意とビルの集客力だろう。前者については、権利状況や環境を激変させる再開発には地元の商店・住民から反対も強いため、自治体は説得作業と財政援助をおこなうのが普通である(30)。再開発ビルの魅力を高めるには、中核店舗の誘致、商店等の配置デザイン、公共施設の設置、建物のデザインなどが重要になる。
(7) 下水道
1965年の5カ年計画の導入以来、公共事業費の約1割を占める投資を、市町村等がおこない国が補助してきた。この政府投資に支えられて、下水道の全人口に対する普及率は8%(65年)から54%(95年)へと急速に伸び、イタリア(61%)、スペイン(59%)に迫っている。ちなみに、イギリス87%、ドイツ86%など、19世紀から整備が進んだヨーロッパでの普及率は一般に高い(31)。日本でも大都市では普及率が90%を超え、河川の水質汚濁(BOD)はかなり改善されてきた(32)。
一方、規制的な手法としては、工場・事業所に対する排出規制がある。また、滋賀県の琵琶湖富栄養化防止条例をはじめ、市民に生活排水の抑制を呼びかける啓発もなされており、下水道の未整備地域では有意義だが、それだけでは水質の改善に限界があるだろう。
(8) 公園緑地と自然保護
都市生活に不可欠なオープンスペースのうち、1人当たり公園面積(平方メートル)は、大都市の巨大さもあって、全国平均で7・7、東京23区3・0、大阪市3・3など、ロンドン27、パリ12より一ケタ小さい。それでも1969年の全国2・4、東京0・99、大阪1・37よりは改善され、建設省は、21世紀初頭において全国平均で1人約20平方メートルを目標としている。公園整備の手法において重要なのは、土地の確保と整備のデザインである。72年に公園整備5か年計画が始まったが、すでに膨張し地価が高い市街地での用地確保は難航した。デザインの面では、近年、専門家の技術(33)と市民の好みを反映して、人工的なものよりも自然保全・再生型の公園が増えている。
都市域の自然空間を保全する規制的手法も弱い。①市街化調整区域(68年導入)は、都市のスプロール(市街地の無秩序な拡大)を抑え郊外の自然や農地を守るための、一種のグリーンベルトである。しかし、土地所有者の反対で各自治体による調整区域の指定は狭くなり、また区域内でもゴルフ場、廃車の野積みなどは許されている。さらに、そもそも都市計画が策定されていない「白地区域」での乱開発が起こってきた。②都市緑地保全法(72年)にもとづく緑地保全地区では、開発が許可制により厳しく規制され、所有者は補償や土地の時価での買い取りを求めることができる。そのためもあって、自治体による指定は、所有者の同意を要しないにもかかわらず、神戸、横浜など以外では散発的で、鎌倉市では指定に反対する宅地開発業者が巨額の補償を求めている(34)。③土地所有者から賃借して自治体が緑地を管理する市民緑地制度(95年)も、99年現在全国で56か所にとどまっている。これらに対して、投資型の都市の緑化は5か年計画もありよく進んでいる。
東京湾や大阪湾では、活発な埋め立てによって自然海岸はほとんど残っていない。理由は、埋め立て地が高価格で売れること、自治体の用地不足と開発指向、環境庁による規制の弱さなどだろう。かわりに、数十億円かかる「人工なぎさ」が建設されている。
鉧 都市景観
景観も、戦争による破壊のあと急速に成長する日本の都市では後回しになった。緑地や水辺の場合と同じく、すでにあるものを守る手法と、新しく創造する手法とがある。前者はおもに規制的手法になるが、保全対象の規模、指定手続き、所有者への拘束力に関してヨーロッパとの違いは大きい。
都市景観政策の目的・対象を4つに分けて検討しよう。
① 歴史的景観の保全。1950年の文化財保存法(個々の建物を現状保存)、66年の古都保存法(京都、奈良、鎌倉の寺社周辺などの地区保全)、75年の伝統的建築物群保存制度(歴史的街並み地区を厳格に保全)、96年の文化財登録制度(おもに近代洋風建築向けで、改修は届け出制)と、国の制度面では発展してきた。66、75、96年の保全対象の拡大においては、自治体の先行的な試みの影響も大きかった。70年代ごろから、歴史的街並みは観光振興策としても重視されている。政策手法は、保全のための規制・指導と、財政・税制面での援助を組み合わせている。
しかし、指定される前に取り壊された貴重な近代建築も多い。東京駅や大阪の中央公会堂は、市民運動によってかろうじて破壊を免れた。制度の適用手続きも、文化財登録の指定をするには所有者の同意を要する。市町村が地元住民の大多数の同意のもとで選定する伝統的建築物群保存地区は、全国でようやく40カ所を超えたが、大・中都市では京都、神戸、長崎、倉敷くらいである(35)。
投資的手法では、昔の建物の復元が、以前から城・天守閣について、最近では町並みや洋風建築についておこなわれている。洋風建築の部分保存の例も増えている。
一方、イタリアでは、多くの自治体が指定する歴史的都心地域(67年法で導入)において、建物の修復、保存的改造、通常の維持と設備等の近代化のみが認められ、町並みは凍結保存される。イギリスの登録建造物(47年)は、イングランドで約45万件にのぼり、改変・解体は許可制で、所有者は買い取り・補償請求ができる。指定は国がおこない所有者の意見は聴取しない。保全地区(67年)は、イングランドで約8000を自治体が指定していて、建物の外観の改変が許可制になる(36)。保全制度の導入時期が日本より早くないのに、適用件数がはるかに多い理由は、地権者の同意によらない手続き、国・自治体の熱意、中層の様式建築群の残存、および高さ制限のゆえに建て替えのメリットが大きくないことだろう。
② 歴史的景観を取り巻く景観の保全。建物の高さやデザインの規制によって街の雰囲気を整える政策で、建物の高さ制限(京都、奈良など)、美観地区(1919年導入だが京都、大阪、皇居前など5都市のみ)は例外的だが、かなりの都市で条例によるコントロールがある。ヨーロッパでは、市街地での高さ制限は一般の都市計画においてすでに厳しい。
日本ではむしろ投資的手法を重視し、歴史的町並みに調和したデザインの建物、街路、河岸などのまちづくりに対しては、各省庁がさまざまな補助金・起債許可プログラムを用意している(37)。
③ 重要な建物や山などの眺望の保全。京都での鴨川東の美観地区や、盛岡・岩手公園からの岩手山の眺望保全、ロンドンでの国会議事堂やセントポール寺院の眺望保全などがある。
④ 新たな都市景観の形成。都市の「顔」となる地域で、民間の新しくつくられる建物にデザイン上の配慮等を求める制度は、神戸市の都市景観形成地域をはじめ、多くの都市が条例等で定めている。また、電線類の地中化計画が、86年より進んでいる。
(10) 中心市街地の活性化
都市の郊外への拡大は、都心部の衰退につながりうる。ヨーロッパの都市でも、インナーシティ(都心の周辺部)の環境悪化は深刻である(38)が、都心の魅力と集客力は政策的に維持されていることが多い。
日本ではまず、80年代に大都市インナーシティでの製造業と人口の衰退が政策課題になった。自治体の対策は、工場跡地への良質な住宅建設、駅前などの再開発、老朽住宅地を地元が建て替える場合の情報・財政援助などであり、都心部でのマンション建設もあって、人口はやや回復している(39)。
90年代になると地方都市の中心街の空洞化が、危機感をもって注目されるようになった。原因は、中心商店街の魅力の低下、人口の郊外分散、公共施設の郊外移転、公共交通シェアの小さい地方都市での自動車中心の買い物行動、大規模店舗法の商業調整を嫌った大型店の郊外展開などである。これに対して、98年に「まちづくり三法」が成立した。大規模店舗立地法は、大型店に対して従来の商業調整の代わりに環境面での配慮を求めるもので、自治体が運用する。中心市街地活性化法は、市街地の整備改善と商業活性化を一体的に推進する。都市計画法の改正は、自治体が大型店の立地を誘導する可能性を開く。
ようやく政策目標が認知された意味は大きいが、手法は投資的なものが中心で、「活性化法」は区画整理、再開発、道路・公園・駐車場の整備、商業基盤施設の整備、公共交通の改善などを列挙し、98年度の予算は関係11省庁で1兆円近い(40)。これらは中心街の魅力を高めるために必要だとしても、次の2つの規制的手法はほとんど予定されていない。
① 歩行者専用道路については、同法に関する関連省庁の方針のなかで「歩行空間」と表現されるにとどまる。しかし、大型店の魅力の一つは自動車や歩きながらの喫煙からの解放であり、これと競争するには商店街もヨーロッパのような快適な空間をつくる必要があろう。ヨーロッパの都市では、歩行者専用道化やトランジットモールが来訪客を増やしている(41)。
② 大型店の立地規制は、建設省の解釈によっても、都市計画法改正で導入された特定用途制限地域を指定すれば可能であるが、政府はそれを勧めているわけではない(42)。確かに競争原理によって商店街が奮起することは大切だが、郊外でのスーパーマーケットの林立を放置したままで、中心市街地の活性化が可能だろうか。都心商店街が魅力を高めて郊外の大店舗と競い合うというシナリオもありうるが、これまでのその衰退の速さから見るとむずかしい。
通産省関連の海外調査団の報告によれば、イギリス、フランス、ドイツでは中心市街地を整備するとともに、商業施設の郊外立地を都市計画等で規制している。イギリスでは、大型店は営業戦略として、中心市街地活性化のための組織に積極的に参加している(43)。イタリアでも、70年代以降、商店立地許可制と用途地域規制によって大店舗の出店はコントロールされている(44)。
(1) 日本の都市政策の現状については、建設省監修『日本の都市』平成10年度版、第一法規、全国市議会議長会『全国都市の特色ある施策集』各年、ぎょうせい、都市計画用語研究会『全訂都市計画用語事典』ぎょうせい、1999年、三船康道ほか『まちづくりキーワード事典』学芸出版社、1997年。分野ごとの変遷・発展については、東京市政調査会編『都市問題の軌跡と展望』ぎょうせい、1988年、土木学会海外活動委員会『社会基盤の整備システムー日本の経験』経済調査会、1995年を参照。最近のルポルタージュ・論説としては、日本経済新聞社編『都市・誰のためにあるか』1996年、五十嵐敬喜・小川明雄『都市計画・利権の構図を超えて』岩波新書、1993年。なお、この論文で統計数字のうち出典を注記していないものは、『日本の都市』または建設省『建設白書』2000年版によっている。各種制度について、法令の根拠条文を示すことは省略した。
(2) 『建設白書』2000年版、339-352頁。もっとも、日本の道路整備の遅れを示すデータとして、自動車台数当たり道路延長、道路の幅、大都市の道路面積率、大都市環状道路の未整備、ドイツの高速道路延長との比較を示すことはなお可能である。
(3) 運輸省『海外運輸統計』1999年度版、運輸振興協会。都市内の物流については、高田邦道「都市内物流と交通政策」『都市問題』2000年8月号。
(4) 『運輸白書』平成11年度版、46-47頁、環境庁『環境白書』。
(5) OECD, Environmental Performance in OECD Countries, 1996, p. 62-63.
(6) 1969年の大ロンドン発展計画(GLDP)が構想した都心部での高速道路網に対して、住民運動や専門家が反対していたが、73年の大ロンドン議会(GLC)選挙で「都心部の環境を破壊する高速道路計画の放棄」を公約に掲げた労働党が勝ち、その結果、計画は中止となった。J.
Simmie (ed.), Planning London, UCL Press, 1994, p. 83.
(7) ケルン(1982年完成、約600メートル、費用1・2億マルク)、デュッセルドルフ(1993年完成、約2キロ、費用4・5億マルク)の道路地下化事業は、いずれも都心のライン川沿いに公園と散歩道を生み出すための投資であった。後者については、春日井道彦『人と街を大切にするドイツのまちづくり』学芸出版社、1999年。アメリカのボストンでも、都心部の高架高速道路を地下化し跡地を公園にする事業が、建設中である。『建設白書』2000年版、169頁。
(8) 三船ほか、前掲書(注1)、130-131頁。『都市問題』1998年7月号・特集「都市内の道路交通」、橋本信之「TDMと行政組織」丸茂新編『都市交通のルネッサンス』御茶の水書房、2000年、交通と環境を考える会編『環境を考えたクルマ社会』技報堂出版、1995年。また、建設省監修『都市交通問題の処方箋』大成出版社、1995年、ブライアン・リチャーズ『トランスポート・イン・シティーズ』論創社、1992年が、TDMのための内外の諸方策を豊富に紹介・評価している。
(9) 建設省『道路ポケットブック』1996年版、全国道路利用者会議、10、12頁。都道府県別のデータは、建設省『道路統計年報』。
(10) 『運輸白書』平成11年度版、143頁より計算。逆に、自動車乗車中の交通事故死(人口10万人当たり人)は、日本では2・5と歩行者と同程度だが、アメリカ8・2、フランス9・2、ドイツ6・4と高くなっている。
(11) B. Cullingworth, British Planning. 50 years of Urban and Regional
Policy, 1999, The Athlone Press, P. 210-211. 宗田好史『にぎわいを呼ぶイタリアのまちづくり』学芸出版社、2000年、189-199頁。歩行者専用道路を表示した地図は、ヨーロッパ各国についての
Michelin 社の観光案内書で見ることができる。イギリスについては、Atlas of Town Plans, Bartholomew
など。ドイツの観光パンフレットや案内書は市街図のなかで歩行者専用道路を示すのが通例であり、それが都心の魅力をアピールする重要な手段であることがうかがえる。
(12) 川嶋敏正『世界の歩行者道』ぎょうせい、1986年。
(13) 『運輸白書』平成11年度版、54-56、71-76頁、藤井彌太郎・中条潮編『現代交通政策』東京大学出版会、1992年、154-155頁。
(14) 東京市政調査会編『メトロポリスの都市交通』日本評論社、1999年、180頁。東京の地下鉄の輸送人員は、パリ、ニューヨークの2・5倍、ロンドンの3倍にのぼるのに、保有車両数ではこれら3都市に及ばない(運輸省『海外運輸統計』19頁)ことも、混雑の原因だろうか。
(15) J. Pucher, C. Lefe`vre, The Urban Transport Crisis in Europe and
North America, Macmillan, 1996, p. 15-21, 206-209.
(16) 東京市政調査会、前掲書(注14)、168、212頁。混雑率については、『運輸白書』平成11年度版、49頁。180%とは「体が触れ合う(ぶつかるー筆者注記)が新聞は読める」ほどの混雑。
(17) J. Pucher et. al., op. cit., p. 34. 藤井ほか、前掲書(注13)、149頁。
(18) 交通協力会『交通年鑑』平成12年版、交通新聞社、100-107頁、土木学会海外活動委員会、前掲書(注1)、124-128頁。
(19) 自治省『地方財政白書』平成12年度版。
(20) RACDA『路面電車とまちづくり』学芸出版社、1999年、121-148頁。和久田康雄『路面電車』成山堂書店、1999年、95-98頁。
(21) 建設省、前掲書(注8)、243-244頁、秋山哲男・中村文彦編『バスはよみがえる』日本評論社、2000年、20、36頁。
(22) 岡並木『都市と交通』岩波新書、1981年、76-80頁。
(23) ドイツの社会住宅(Sozialwohnung)とは、おもに賃貸住宅に家賃、面積などの条件を義務づけて公的融資をおこなうもの。融資の返済後は義務づけがなくなるので、今後予想される戸数減への対応が課題である。小玉徹ほか編『欧米の住宅政策』ミネルヴァ書房、1999年、113頁、B.
Hintzsche, Kommunale Wohnungspolitik, in:H. Wollmann, R. Roth (Hrsg.),
Kommunalpolitik, Leske+Budrich, 1999.
(24) 日本については、総務庁『日本の住宅・平成5年住宅統計調査報告の解説』。ヨーロッパのデータは1990年前後のもので、G. McCrone,
M. Stephens, Housing Policy in Britain and Europe, UCL Press, 1995,
p. 18, 21, 142による。
(25) Ibid., p. 20, 51.
(26) 地域振興整備公団『地域統計要覧』1998年版、ぎょうせい、282-290頁。
(27) 都市開発協会の調査による(毎日新聞2000年8月19日)。
(28) G. McCrone, op. cit., p. 20-21, 151-152, 宮尾尊弘『現代都市経済学』第2版、日本評論社、1995年、113-114頁。
(29a) 村上弘「日本型都市計画と地価」山下健次編『都市の環境管理と財産権』法律文化社、1993年。制度とその変遷は、建設省『日本の都市』(注1)など。
(29b) 三船ほか、前掲書(注1)、14-15頁。バブル経済を分析した経済企画庁『経済白書』平成5年版、133頁も、「民間活力の活用等による再開発プロジェクト」を地価上昇の一因としている。
(30) 市街地再開発の制度については、建設省『建設白書』(注1)。分析として、林宜嗣『都市問題の経済学』日本経済新聞社、1993年、6章。批判的な論説として、区画整理対策全国連絡会議『再開発を考える』自治体研究社、1992年など。
(31) OECD, op. cit. (注5), p. 62. ヨーロッパの数字は1993年またはその直前。
(32) 『環境白書』および各自治体の環境関連報告書を参照。
(33) たとえば、武内和彦『まちの自然とつきあう』岩波書店、1997年。
(34) 地区のリストは、地域振興整備公団、前掲書(注26)、255-261頁。鎌倉の事例は、小早川光郎編『分権改革と地域空間管理』ぎょうせい、2000年、74-82頁。
(35) 三船ほか、前掲書(注1)、82-103頁、大河直躬『都市の歴史とまちづくり』学芸出版社、1995年(とくに41-60、141頁)。
(36) 宗田好史『にぎわいを呼ぶイタリアのまちづくり』学芸出版社、2000年、西村幸夫ほか『都市の風景計画欧米の景観コントロール』学芸出版社、2000年、24-38頁。
(37) 大河、前掲書(注35)、149-164頁。
(38) たとえば、H. Matthews, British Inner Cities, Oxford University Press,
1991.
(39) 都市居住シンポジウム開催委員会『都市居住の課題と展望』学芸出版社、1993年、49-90頁、小林重敬・山本正堯編『既成市街地の再構築と都市計画』ぎょうせい、1999年、1部3章。
(40) 法律の解説および関連省庁が告示した「基本的な方針」は、通産省・中小企業庁『中心市街地活性化対策の実務』ぎょうせい、1998年。
(41) 国際交通安全学会ほか『トランジットモールの計画』技報堂出版、1988年、2章、福島まちづくりセンター『街をよみがえらせた知恵と手法』ぎょうせい、1999年。もちろん、歩行者エリアだけでは活性化は保障されない。小林ほか、前掲書(注39)、319頁はアメリカでの失敗を指摘する。
(42) 建設省『平成12年改正・都市計画法・建築基準法の解説』大成出版社、2000年、92頁。
(43) 通産省・中小企業庁、前掲書(注40)、130-152頁。
(44) 宗田、前掲書(注36)、178-182頁。小林ほか、前掲書(注39)も、内外の活性化政策の事例(ヨーロッパでの大型店規制を含む)を紹介している。
三、政策の特徴と政治行政過程
つぎに、以上の分野ごとの国際比較から、日本の都市政策における目標と手法の選択の傾向をまとめ、原因を、都市化の様相と政治行政的要因のなかに探ってみよう。
(1) 日本の都市化の特徴
日本の都市化現象は欧米よりも遅れて、かつ急速に進んだ。欧米では産業革命の19世紀にすでに都市が成長し、20世紀初めにかけては、用途地域(ゾーニング)、地区詳細計画、田園都市、公園ネットワークなどの政策アイデアも実践されていった(1)。日本での本格的な都市化は1960年代の高度経済成長期のことで、市街地(DID)人口が全人口に占める比率は、60年の43・7%から80年の59・7%に急増し、95年には64・7%に達した。(もちろん発展途上国での「都市の爆発」は、いっそう深刻である。)
また、日本では東京圏(東京に10%以上通勤・通学している市町村)に全国人口の約22%が集中しているが、フランス、イギリスでも首都圏への集中度はそれぞれ16%、11%である(ドイツは4%)。非連邦制国家では首都の肥大化は避けにくいようだ。ただ東京圏の人口は、全国人口が英仏の約2倍あるために、2753万人(1990年)と世界最大級で、パリやロンドンの3倍以上の規模になっているのである。
こうした、「あとからの、急速かつ大規模な都市化」という厳しい条件を念頭において、日本の都市政策をバランスよく評価する必要がある。つまり、政府・民間投資については、毎年の建設速度(フロー)では努力が見られるのに、人口急増がその成果を相殺したり、開始後の年月が浅いために蓄積(ストック)ではヨーロッパに及ばない、ということもある。都市計画、景観保全、道路や公園用地の確保などでも、急速な都市化のあとを追って規制を強めたり土地を確保することの限界がある。
(2) 都市政策各分野での目標の設定
各分野での政策の本格的な導入を画するのは、多くの場合根拠法の制定と、さらに投資的手法による場合には5か年計画の開始である。
現在、公共事業関連で閣議決定による長期(おもに5か年)計画は16あり、計画を重ねることで政策を発展させてきた。都市政策に関係の深いものとしては、道路整備(第1次計画は1954年)、下水道整備(65年)、住宅建設、交通安全施設等整備(ともに66年)、都市公園等整備(72年)があり、すべて建設省(2)の所轄である。なお、運輸省担当の鉄道に関する5か年計画は存在しないが、大手民鉄輸送力増強計画(61年より)が続けられ、運輸政策審議会の答申による主要都市圏の鉄道整備計画もある。カッコ内に示した計画導入の年度を比べると、戦後日本での各政策分野の優先順位がうかがえるだろう。
これらは、建設省や運輸省の各部局において中心となる政策である。しかし、「縦割り行政」のはざまで取り残される政策目標もあるようだ。
たとえば、運輸省が担当する公共交通を優先させようとしても、なかなか道路重視の壁を破れなかった。建設省は従来、自動車交通と公共交通の関係について、「総合都市交通体系」をめざす、つまり「各種交通手段の適切な分担」を図るという表現をとってきた(3)。自動車の抑制を意味する「需要マネジメント」(TDM)を白書で用いるようになったのは最近である。具体的施策としても、建設省は80年代には都市モノレール、新交通システムなど道路の上空を利用する公共交通を補助してきたのであり、90年代になってようやく、路面電車やパークアンドライドの実験に支援を始めた。
中心市街地活性化という目標も、明確な設定は98年まで遅れた。大型店の郊外立地はすでに80年代から急増していた(4)にもかかわらずである。通産省も小売業者も、「大店法」のもとで問題を商店街保護・商業調整としてとらえていたため、大型店の郊外への展開には抵抗せず、また規制緩和の声に押されてきた(5)。建設省は問題を認識していたが、85年から実施した地方都市活性化計画は、再開発等、従来の基盤整備手法で対処するものだった。大規模店舗法の廃止の代償として、ようやくつくられた98年「活性化法」の意義は、商業調整からまちづくりへと視点を広げた点と、それに対応して、各省に細分化されていた補助事業を総合化し、また地元の推進主体(TMO:town
management organization)を育成しようとする点にある(6)。
(3) 政府の公共投資
ここからは、3種類の政策手法について順に検討する。日本の都市政策では、政府および民間の投資が目立つ反面、規制的手法は概して弱い。そして表2が示すように、政府と民間の投資の軽重は分野によって異なる。
まず、日本の国・地方自治体の公共投資(一般政府総固定資本形成)がGNPに占める比率は6・2%(98年)で、公団を含めると7・9%にのぼり、アメリカ1・9%、イギリス1・4%、ドイツ2・0%、フランス2・8%を圧倒している(7)。
表2 日本の建設投資の推計(1997年)
| |
総計 |
建築
(住宅) |
建築
(住宅以外) |
道路 |
鉄道 |
政府(国、自治体)
(住宅金融公庫の融資)
民間 |
346,768
417,873 |
17,546
(110,4000**)
220,479
|
40,680
93,754z*** |
108,957
- |
5,878*
7,643 |
| 総計 |
764,641 |
238,025 |
134,434*** |
108,957 |
13,521 |
[資料]『建設白書』2000年版,資料編18-19ページより筆者が作成。
[注] *『建設白書』に項目がないため,交通協力会『交通年鑑』平成12年度版,38ページによる。このうち1,457は新幹線,地方新線。
**計画額であり,また投資総計には含まない。出典は『図説日本の財政』。
***民間による鉱工業関連投資を除く。
巨額の投資の理由を、『建設白書』では、社会資本の欧米に比べての立ち遅れ、豪雨・豪雪・地震など自然災害の多さ、景気対策の必要性に求めている。しかし、原因として他の指摘もある。まず、建設業界の巨大さ(8)があるが、これはもちろん公共事業の結果でもある。政治的には、業界、建設省、建設族議員が「三角同盟」または「政策共同体」を形成していること、地方自治体レベルでも議会が保守主導でかつ建設業出身の議員が多いこと(9)などがある。予算制度の面でも、公共事業に充てる建設国債(これも実は財政赤字なのに)をそれ以外の経費に充てる「赤字」国債より優先してきたこと、国が自治体への補助金に加えて、地方自治体の「地方単独事業」を、そのための地方債の元利償還を後年度に地方交付税で補助する制度により促してきたこと、などが効いている。とくに90年代には、金額を各分野の必要から積み上げるのではなく、政府が不況対策として大型の公共投資構想を打ち上げることが一般化した。批判的な論者は、日本を「土建国家」と呼ぶほどだ。
こうした巨額の歳出は、都市政策の各分野にどのように配分されてきたのか。
前述の5か年計画は、期間内に達成すべき目標値を設定するとともに、前回の計画を超えた新たな政策目標の展開を打ち出す。そして目標の達成率は事業費で見る限り、一般にかなり高い(低いのは戸数レベルで見た公営・公共住宅など)。特徴的なのは、新しい5か年計画は前回の計画から事業費がほとんど常に増えるということだ。計画による認知が遅れた分野(たとえば公園、交通安全施設)でも、先行した分野(道路)と同じく一定の伸び率で予算が増えていく(10)。これを違った角度から見ると、有名な、国の公共投資の分野別配分率の固定化のグラフになる(11)。たとえば国の公共投資全体の約3割を占める道路予算を減らし、シェア約1%の鉄道関連予算に再配分することはできていない。しかし、いったん実績をつくると、地下鉄への補助金も公園整備費も、予算はふつう横ばいまたは微増で推移してきたのである。
単に予算が増えるだけでなく、政策の目標や技術も多様化し、進化してきた。規制的手法については後述するように一定の限界があるが、政府投資や民間への誘導の面では次々と新しい制度や補助金が登場する。こうした政策発展を促す要因は、都市の現状に対する批判が強いこと、毎年の予算編成で各省が新規事業を競って概算要求のなかに盛り込むこと、審議会が都市計画、住宅、道路、運輸政策など各分野ごとにおかれ、メンバーである官僚OB、学者・専門家、業界代表が意見交換すること(12)、地方自治体が国に先立って新たな政策実験を進めたり、政策を執行するなかで国への改善要求を繰り返してきたこと、などであろう。
ただし、道路の地下化・堀割り化や路面電車の地下化のための投資は、ヨーロッパに遅れている。今後の展開が待たれる。
(4) 民間投資と政府による誘導
民間企業が商業・オフィスビルをつくるのは当然だが、日本ではそれに加えて、公共交通のかなりの部分や多数の有料公園も民間によって供給されてきた。持ち家や賃貸住宅の大部分も個人や企業の資金で建設されてきた。もちろんこれらの施設はフリーライダーを許す純粋な公共財ではないから、需要が高ければ企業は採算が取れ、その投資意欲は政府の誘導なしでも生じる。したがって、政府の誘導が巧みだったかは判断がむずかしいが、ゆるやかな都市計画、市街化調整区域の限定的設定、鉄道整備への補助金、住宅金融公庫の融資、家賃統制の早期解除、さらに道路網の整備などは、民間の建設活動をいっそう促してきたといえる。
一定の経済成長のあとでは、民間企業や市民は競争やブームをつうじて短期間に大量の投資をおこなうことができた。ただし、規制のゆるさ故に乱開発に陥ったのも事実だ。また、政府は都市整備の一部を民間に依存し、効率的に進めたとも評価できる。しかし政府財政の再配分機能が小さい結果、住宅(や高等教育!)のように財の価格が高いか、鉄道のように欧米と同価格水準であるが混雑を伴う場合が起こる。
区画整理や市街地再開発も、受益者とみなしうる土地所有者が負担して進める方式で、自治体の都市整備の意欲がこれを主導してきた。
さらに、82年の臨時行政調査会答申以降、「民間活力の活用」が政府のスローガンとなった。都市政策に関連しては、都市計画での規制緩和や、民間の資金を導入し「官の公共性と民の効率性が相乗的に発揮される」第3セクターの活用が進められた(13)。容積率に関する規制緩和はビルやマンションの供給を増やしたが、一定の期間、激しく深刻な地価高騰を引き起こした。第3セクターは、自治体がオフィスビル(大都市)やリゾート施設(地方)など、かならずしも公共的でない民間の領域に進出したとも解釈できるが、経営見通しの甘さ等から赤字に陥る例も多い。
(5) 公的規制の弱さ
その背景にある政治行政過程を明らかにするために、二で述べたいくつかの事例をもう一度検討してみよう。日本では自治体が規制的政策を試行することが多いが、規制への国の法的・財政的支援が一般に弱いなかで、自治体の努力には限界があるといえそうだ。
① 規制が強くなったもの(自転車駐輪のほか、防災・日影規制等に関する建築基準法)。
自転車の駐車対策に関する1980年の法律にもとづいて自治体が対策を実施してきたが、「相当の期間放置されている」自転車しか撤去できないなどの欠点が深刻だったので、自治体の意見を入れつつ衆議院委員会を中心に93年、法改正をおこなった(14)。
② 規制が弱いが、少しずつ強化されてきたもの(都市計画、景観、歩道の確保)。
前述のとおり、都市計画法は問題の噴出ごとに、後追いではあるが関連する規制制度を建設省設置の審議会の検討を経て強化してきた。しかし自治体による規制の適用に対しては、議会を通じての土地所有者の抵抗が強い(15)。景観保全の場合は、景観紛争への対処や観光政策から自治体の取り組みが多く、それが国の制度に結実するが、そのあとも多くの自治体に広がっていくとは限らない。
③ 規制が弱いもの(歩行者専用道路、自然保護、大型店の郊外立地のほか、都心部での自動車交通規制、ガソリンへの環境税、広告看板規制)。
まとまった歩行者専用道路の設定について、建設省・運輸省はなお消極的である。日本での数少ない実現例である旭川では、市長が発案し、商店街も振興のためにまとまり、反対する警察や陸運事務所に精力的に働きかけた。しかし、通常は、商店街(の一部)が自動車での来訪者が減ると反対したり、交通規制を担当する府県公安委員会・警察が難色を示したりで進まない。抵抗の中心は、自動車利用者それ自体ではないのである(16)。商店街全体や買物客の利益を追求する主体が弱いといえよう。
ドイツでも商店主からは反対があるが、実験や部分区間での実施で効果を証明しつつ、最後は市長と議会が導入を決定するという過程をたどる(17)。つまり、歩行者エリアの実現のためには、自治体のリーダーシップと、政策効果に関する予測・研究の蓄積が必要だ。あるいは国の補助金、観光案内書での道の歩きやすさの表示などが促進要因になろう。
つぎに、自然保護のための厳しい規制は、土地所有者が現在の地価での補償を要求するならば、相当の政治的決断を要するだろう。
中心市街地の衰退原因の一つが郊外での大型店立地であることを、関係省庁は情報をもちながら公式には認めていない(18)。自治体は、新たな特定用途制限地域を指定する等で大型店を規制できるが、現実には消極的である。その理由は、市によってはすでに中心街が「ぼろぼろに」なっていること、市としても郊外での開発を進めていること、個別市域内だけでの対応に限界があることなどである(19)。ただし、京都市は独自の「商業集積ガイドプラン」で地区別に大型店の規模の上限を「目安」として設定した。
④ 最後に、道路の用地確保に関する建設省の考えを見よう。2000年の『建設白書』は、景観形成のための規制については世論調査を根拠に否定的であり、また郊外での大店舗の規制にも触れていない。しかし、規制的手法の必要を、「緊急整備が必要」なのに欧米に比べて「極端に整備のスピードの遅い」大都市の環状道路の用地取得に関して示唆している。白書は、計画初期段階からの住民参加や事業評価によるコンセンサスの形成とともに、「公共事業における公共の福祉の優先」、具体的には現行の土地収用制度の見直しを主張している(20)。これは自民党都市問題対策協議会の意向でもある。
ここで意見を述べる用意はない。ただし、白書で迅速に完成した例として紹介されているロンドンの環状道路M25は、実はすべてグリーンベルト地帯に建設され、市街地を通過する部分はきわめて少ない。パリの外環状線(Boulevard
Pe´riphe´rique)も、都市の防御壁の跡地を利用し、かつブーローニュの森その他でトンネルや掘割を多用しているのである(21)。
(1) 都市計画教育研究会編『都市計画教科書』彰国社、1987年、1、2章。
(2) 建設省の政策形成過程については、城山英明ほか『中央省庁の政策形成過程』中央大学出版部、1999年、五十嵐敬喜・小川明雄『都市計画・利権の構図を超えて』岩波新書、1993年、北原鉄也『現代日本の都市計画』成文堂、1998年、7章。
(3) たとえば、『日本の都市』平成6年度版、326頁。
(4) 『建設白書』平成7年版、50頁、矢作弘『地方都市再生の条件』岩波書店、1999年、15-17頁。
(5) 石原武政「出店調整政策の転換と地域商業の今後」『都市問題』1998年10月号。
(6) 通産省・中小企業庁編『中心市街地活性化対策の実務』ぎょうせい、1998年、52、56、75、87頁。
(7) 竹内洋編『図説日本の財政』平成12年版、東洋経済新報社、178-180頁。
(8) 金森良嗣『日本の建設産業』日本経済新聞社、1999年、2章。日本の建設業界は、業者数がアメリカに匹敵し、建設業従事者の全就業者に占める比率で欧米を上回る。労働組合の組織率が低いことも特徴で、建設業界は従業員を含めて保守の支持基盤となってきた。
(9) 村上弘「ドイツと日本の市町村議会」『立命館法学』245号、1996年。
(10) データは、国土庁『国土統計要覧』大成出版社、建設省監修『建設統計要覧』建設物価調査会。
(11) 竹内、前掲書(注7)、184頁。
(12) 委員の名簿は、総務庁『審議会総覧』。委員の職業別分類は、村上弘「日本型都市計画と地価」山下健次編『都市の環境管理と財産権』法律文化社、1993年。
(13) 井上源三「民間活力の活用」中川浩明編『新しい自治体活動と地方自治法』ぎょうせい、1990年。
(14) 諸岡昭二『改正自転車法の解説』東京経済、1994年。
(15) 伊藤滋『市民参加の都市計画』早稲田大学理工総研シリーズ、1996年、107-111頁。
(16) 『建設白書』2000年版の新「歩行空間ネットワーク事業」で想定されているのは「幅の広い歩道」である。『運輸白書』平成11年度、142-145頁も参照。旭川については、全国革新市長会編『資料革新自治体』日本評論社、1990年、412-413頁。歩行者エリア化への障害については、国際交通安全学会ほか『トランジットモールの計画』技報堂出版、1988年、30頁のアンケート結果も参照。
(17) C. Jochims, R. Monheim, Einkaufsausflugsverkehr in Stadtzentren
- ein zukunftstra¨chtiges Marktsegment, in:der Sta¨dtetag 11/1996, S.
730. 中村静夫『市民参加の大都市づくり・国際都市ミュンヒェン』集文社、1989年、97-104頁。ウィーンでも同様であったことについては、建設省監修『都市交通問題の処方箋』大成出版社、1995年、169頁。
(18) 通産省ほか、前掲書(注6)、34-35、132頁を参照。
(19) 『造景』16号、1998年の市長座談会から筆者がまとめた。矢作弘、前掲書(注4)、28-35頁は、都市計画法の不備を指摘する。
(20) 『建設白書』2000年版、12-15、63-66、141頁。
(21) ロンドンについては、Ordinance Survey 発行の5万分の1地図などを参照。パリは、『ヨーロッパのインフラストラクチャー』土木学会、1997年、115頁。
四、要約と展望
この論文は、日本の都市政策の10分野を検討し、政策目標と手法の選択の特徴を探った。目標については、道路整備から始まった5か年計画方式がその他の多様な政策分野に広がり成果をあげてきたが、省庁の管轄の「谷間」に位置する課題への取り組みが遅れたことを示した。また、手法の面では、3タイプへの分類が説明力をもっているようだ。つまり、中央・地方政府による公共投資(道路、下水道など)、および民間投資の誘導(都市再開発、鉄道、住宅など)において活発である反面で、公的規制は弱いながらもある程度発展してきたことを示した。政策目標は多様化するが、手法の選好は変わりにくいともいえそうだ。
政策過程の面での特徴は、十分扱えなかったが次のようなものだろう。①課題を先取りすることは少ないが、状況が深刻になり社会問題化した場合には、政党や市民運動などの政治過程を受けて、行政が欧米の先例を参考に新たな政策を導入する。②ひとたび導入された政策は、行政官僚制において業界や専門家の意見を入れつつ少しずつ改善される。③そうした過程が国においてだけではなく、地方自治体でも展開する。
さて、このように発展してきた日本の都市政策は、持続可能か、またモデルたりうるか。
ヨーロッパの都市政策は、政府による投資と規制に重点を置いてきた。日本は民間投資が政府投資を補完しているわけだが、やはりそれでは不足する部分もある(鉄道、住宅)。また、技術力を用いた政府・民間投資で公的規制の弱さを代替しようとしている。郊外大型店の規制の代わりに中心市街地の整備、歩行者エリアの代わりに地下街、自然保護の代わりに緑化や人工なぎさ、路面電車の代わりに地下鉄といった具合である。それも歓迎されるだろうが、効果に限界があり、また費用がかさむ。
都市政策における今後の課題は、①政府投資における分野間再配分と効率化、②民間投資の誘導・活用、③政府・民間投資に対する都市計画や環境面での必要な規制、④歩行者空間、自動車交通、公共交通の走行確保、自然保護、景観、大型店立地などに関する規制の強化、だろう。そうした新たな政策発展を支える政治行政面のしくみとしては、国レベルでの政党間競争、議員立法、中央省庁再編(とくに国土交通省、環境省の誕生)、地方分権、市民参加、住民投票、環境アセスメント、情報公開制度、政策(事前)評価、自治体の比較指標とランキングの発表など、最近の動向に期待できるかもしれない。とはいえ、巨大な建設業界と族議員、地方選挙での競争度の低さ、地方議会での保守・自営業議員の優位といった日本に特徴的な構造は、簡単には変わらないと思われる。
|