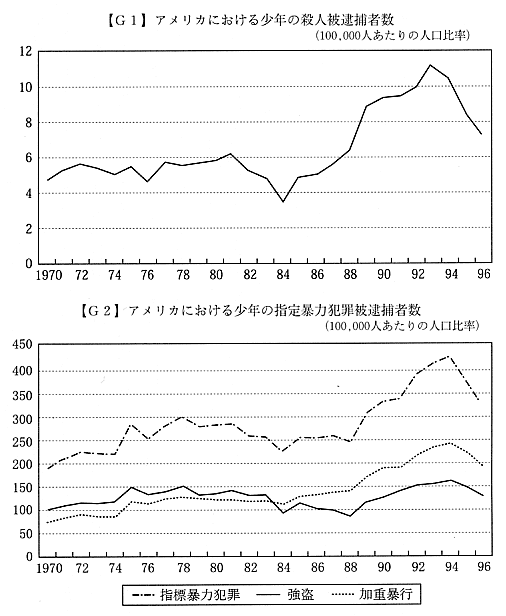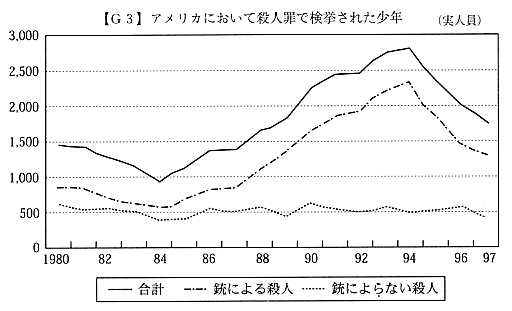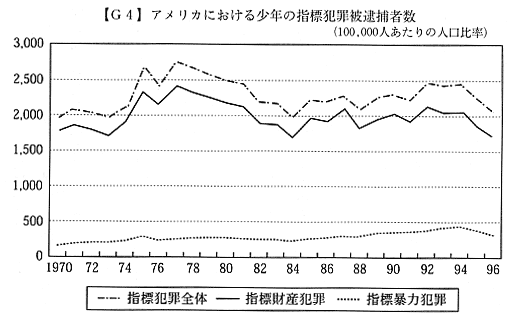|
丂
栚丂丂丂丂師
堦丂丂栤丂戣丂愝丂掕
擇丂丂朄揑敾抐偲宱尡壢妛
丂丂(1)丂丂朄揑敾抐偺峔憿
丂丂(2)丂丂朄揑敾抐偵偍偗傞帠幚擣幆
嶰丂丂瓟N朄夵惓乿朄埬傪傔偖偭偰
丂丂(1)丂丂朄埬偺撪梕
丂丂(2)丂丂彮擭旕峴偺乽嫢埆壔乿
丂丂(3)丂丂孻敱偺惓摉壔梫審偲偟偰偺斊嵾梷巭岠壥
丂丂(4)丂丂堦斒梷巭岠壥
丂丂(5)丂丂嵞斊棪傊偺塭嬁
丂丂(6)丂丂訑C偺帺妎乿偲墳曬揑惂嵸
丂丂(7)丂丂棫朄夁掱偺栤戣
巐丂丂峫丂丂丂丂嶡
丂丂(1)丂丂憱瘋虋鷳襾v偲孻帠棫朄
丂丂(2)丂丂孻帠棫朄夁掱偺揔惓庤懕
屲丂丂寢丂丂丂丂岅
堦丂丂栤丂丂戣丂丂愝丂丂掕
丂丂斊嵾幮夛妛幰偺尨揷朙偼丄傾儊儕僇斊嵾幮夛妛夛偺嵟嬤偺摦岦傪徯夘偟偨偆偊偱丄師偺傛偆偵弎傋偰偄傞丅乽崱擔丄傢偑崙偺斊嵾丒旕峴栤戣偵偮偄偰亀壗偐偑側偝傟側偗傟偽側傜側偄亁偲偄偆婥塣偑媫懍偵崅傑偭偰偄傞偲姶偠傜傟傞丅偟偐偟丄偨偲偊偽嶐崱偺彮擭朄夵惓栤戣偱擔乆旘傃岎偭偰偄傞媍榑偺偆偪丄妋偐側幚徹揑棤晅偗傪帩偭偰岅傜傟偨傕偺偑偳傟偩偗偁傞偩傠偆偐丅亀揔惓庤懕偒亁偵傛偭偰摼傜傟偨亀徹嫆亁埲奜偼抐屌偲偟偰媍榑偺慺嵽偐傜攔彍偡傞偲偄偆幚徹壢妛偺惛恄偑丄崱偙偦昁梫側偺偱偼側偄偐(1)乿丅
丂丂幚徹庡媊偺斊嵾幮夛妛幰偐傜偺尩偟偄巜揈偱偁傞丅孻帠朄妛幰偲偟偰丄偙傟傪偳偺傛偆偵庴偗巭傔傞傋偒偐丅
丂丂杮峞偵偍偄偰偼丄宱尡壢妛偲孻帠朄偺岎嶖丄偁傞偄偼孻帠棫朄偵偍偗傞宱尡壢妛偺埵抲偯偗偲偄偆帇揰偐傜丄乽崙柉偺婜懸乿傊偺墳摎偲偄偆宍偱恑傔傜傟偰偄傞崱夞偺乽彮擭朄夵惓乿偺斸敾揑専摙傪捠偠偰丄偙偺偙偲傪峫偊偰傒偨偄丅偙偺傛偆側宍偱孻帠棫朄偑恑傔傜傟傞偲偒丄偦偺宱尡壢妛揑婎斦偑幐傢傟丄壢妛揑丒棟惈揑懺搙偐傜棧傟偨丄湏堄揑偱偛搒崌庡媊揑棫朄偺婋尟偑崅傑傞偺偱偼側偐傠偆偐丅偙偺偙偲偼丄孻帠棫朄偺棫朄惌嶔偲偟偰偺懨摉惈丄偁傞偄偼寷朄偺庯巪丒惛恄偵傛傝揔崌偡傞傛偆側孻帠棫朄偺曐忈傪幐傢偣傞偺偱偼側偐傠偆偐丅
擇丂丂朄揑敾抐偲宱尡壢妛
(1)丂丂朄揑敾抐偺峔憿
丂丂孻帠朄偺応崌偵尷傜偢丄朄偺夝庍偼丄偐偮偰丄朄偺惓偟偄媞娤揑堄枴傪柧傜偐偵偡傞偙偲偱偁偭偰丄杮棃丄夝庍偡傞庡懱偺庡娤揑側傕偺偵偼塭嬁偝傟側偄丄偲棟夝偝傟偰偒偨丅尰嵼傕丄惓摉壔偺偨傔偺媄朄偲偟偰偦偺傛偆側憰偄傪傑偲偆偙偲偑偁傞偑丄朄夝庍傕丄夝庍偡傞庡懱偺壙抣敾抐偺寢壥偱偁傝丄偦偺慜採偵偼帠幚偺擣幆偑偁傞丄偲堦斒偵棟夝偝傟偰偄傞(2)丅偙偺傛偆側朄揑敾抐偺惈奿偼丄朄偺夝庍偺応崌偺傒側傜偢丄棫朄偵偐偐傢傞敾抐偵傕摉偰偼傑傞丅傓偟傠棫朄偺応崌偺曽偑丄朄婯掕偺暥尵偵峉懇偝傟側偄偑備偊偵丄傛傝嫮偔側傞偲偄偊傞丅
丂丂朄揑敾抐偼壙抣敾抐偱偁傞偲偄偭偰傕丄彑庤婥傑傑偵丄偳偺傛偆側壙抣偵棫偭偰傕峔傢側偄偲偄偆堄枴偱側偄偙偲偼丄傕偪傠傫偱偁傞丅寷朄偺梫惪傪堩扙偡傞朄揑敾抐偼丄摉慠丄嫋偝傟側偄丅偝傜偵丄屻弎偡傞傛偆偵丄朄夝庍偵偍偄偰傕丄棫朄偵偍偄偰傕丄寷朄偺庯巪丒惛恄偵傛傝揔崌偡傞傛偆側朄揑敾抐偑梫媮偝傟傞丅
(2)丂丂朄揑敾抐偵偍偗傞帠幚擣幆
丂丂栤戣偼丄壙抣敾抐偺慜採偲側傞帠幚偺擣幆偱偁傞丅惓妋側帠幚擣幆偑側偗傟偽丄偦傟偵懳偡傞壙抣敾抐偺寢壥偲偟偰帵偝傟傞朄揑敾抐偑丄湏堄揑側傕偺丄応摉偨傝揑偱偛搒崌庡媊揑側傕偺偲側傝丄寢壥偲偟偰丄寷朄偺庯巪丒惛恄偵偆傑偔揔崌偟側偄傕偺偵側傞婋尟偑偁傞偐傜偱偁傞丅
丂丂偟偐偟丄偙傟傑偱丄朄揑敾抐偵偍偗傞帠幚擣幆偵偮偄偰偼丄惓妋側帠幚擣幆偐偳偆偐傪廫暘偵嬦枴偡傞偙偲側偔丄偁傞偄偼丄昁梫偲偡傞寢榑傪摫偒弌偡偨傔偵搒崌傛偔丄堦掕偺乽帠幚乿傪嶌傝忋偘偰偟傑偆偙偲偝偊彮側偔側偐偭偨傛偆偵巚傢傟傞丅
丂丂惓妋側帠幚擣幆偑岞惓丒岞暯側朄揑敾抐偵偲偭偰晄壜寚偱偁傞側傜偽丄偦偺偨傔偵丄宱尡壢妛揑尋媶偺惉壥丄偦偙偵帵偝傟偨抦尒傪摜傑偊傞傋偒偱偁傞丅偦傟偑懚嵼偡傞偵傕偐偐傢傜偢丄偦傟傪廫暘偵摜傑偊偢偵丄偁傞偄偼丄偦傟傪柍帇傗榗嬋偟偰乽帠幚乿傪愝掕偟丄朄揑敾抐傪峴偆側傜偽丄偦偺傛偆側朄揑敾抐偼丄湏堄揑敾抐偺婋尟傪偼傜傓傕偺丄偁傞偄偼偛搒崌庡媊揑側敾抐偲偟偰丄斸敾偝傟傞傋偒偱偁傞丅
丂丂偟偐偟丄偙偺傛偆側堄枴偵偍偄偰斸敾偝傟傞傋偒朄揑敾抐偼丄偙傟傑偱丄昁偢偟傕彮側偔側偐偭偨傛偆偵巚傢傟傞丅孻帠朄偺応崌偵傕偦偆偱偁傞丅偦傟偼丄屄乆偺嬶懱揑側朄夝庍偵偲偳傑傜偢丄幚柋偺偁傝曽傪婯掕偟丄偦偺戝榞傪愝掕偡傞孻帠棫朄偺応崌偵傕傒傜傟傞丅傑偨丄屄乆偺尋媶幰偵偍偄偰傕丄朄棩幚柋壠丄嵸敾強丄棫朄幰偵偍偄偰傕傒傜傟傞丅
嶰丂丂瓟N朄夵惓乿朄埬傪傔偖偭偰
(1)丂丂朄埬偺撪梕
丂丂偦偺傛偆側斸敾偝傟傞傋偒孻帠棫朄偺椺偲偟偰丄擇乑乑乑擭嬨寧擇嬨擔丄媍堳採弌朄埬偲偟偰崙夛偵採弌偝傟偨乽彮擭朄夵惓乿朄埬偑偁傞(3)丅
丂丂崱夞偺乽彮擭朄夵惓乿朄埬偼丄戞堦偵丄彮擭朄偺尩敱壔偲偟偰丄嘆孻帠張暘揔梡擭楊偺尰峴堦榋嵨埲忋偐傜堦巐嵨埲忋傊偺堷偒壓偘丄嘇堦掕帠審偵偮偄偰偺尨懃孻帠張暘揔梡丄嘊崸愗偱側偛傗偐側怰敾偐傜尩惓側怰敾傊丄偲偄偆揰偺夵惓傪丄戞擇偵丄乽旕峴帠幚擣掕庤懕偺揔惓壔乿偺偨傔偺怰敾庤懕夵惓偲偟偰丄嘆嵸掕崌媍惂丄嘇専嶡姱娭梌丄嘊専嶡姱娭梌偺応崌偺曎岇巑晅揧恖娭梌丄嘋専嶡姱偺晄暈怽棫丄嘍娤岇慬抲婜娫偺尰峴嵟挿巐廡娫偐傜嵟挿敧廡娫傑偱偺墑挿丄嘐曐岇張暘廔椆屻偺媬嵪庤懕偺惍旛丄偲偄偆揰偺夵惓傪丄戞嶰偵丄旐奞幰摍偵懳偡傞攝椂偲偟偰丄嘆旐奞幰摍偺怽弌偵傛傞堄尒挳庢丄嘇旐奞幰摍傊偺怰敾寢壥摍偺捠抦丄嘊旐奞幰摍偺旕峴帠幚偵娭偡傞婰榐偺墈棗丒摚幨丄偲偄偆揰偺夵惓傪峴偍偆偲偡傞傕偺偱偁傞丅
丂丂杮峞偑栤戣偲偡傞偺偼丄偙偺偆偪丄彮擭朄偺尩敱壔偵偮偄偰偱偁傞丅
丂丂乽夵惓乿朄埬偼丄孻帠張暘揔梡擭楊傪尰峴偺堦榋嵨埲忋偐傜堦巐嵨埲忋傊偲堷偒壓偘丄嶦恖丄彎奞抳巰偦偺懠屘堄偺斊嵾偵傛傝恖傪巰朣偝偣偨堦榋嵨埲忋偺彮擭偺帠審偵偮偄偰偼丄尨懃偲偟偰孻帠張暘傪揔梡偡傞側偳丄彮擭傊偺孻帠張暘揔梡傪奼戝偟傛偆偲偟偰偄傞丅偙偺揰偵偍偄偰丄彮擭朄傪尩敱壔偟傛偆偲偡傞傕偺偱偁傝丄彮擭朄偺棟擮傗彮擭巌朄偺崻姴偵偐偐傢傞廳戝側乽夵惓乿朄埬偱偁傞丅
(2)丂丂彮擭旕峴偺乽嫢埆壔乿
丂丂偄傑偙偺傛偆側夵惓偑昁梫偲偝傟傞棟桼偵丄彮擭旕峴偺乽嫢埆壔乿偑偄傢傟傞丅偟偐偟丄偦偺傛偆側帠幚擣幆偵媈栤偺偁傞偙偲偼丄偙傟傑偱偵傕丄偄偔偮偐偺尋媶偑柧傜偐偵偟偰偒偨(4)丅堦斒偵丄斊嵾摑寁忋偺悢抣偵偼丄寈嶡偺斊嵾庢掲偺懺惃丄愊嬌惈側偳丄朄幏峴惌嶔偺偄偐傫偑堦掕偺塭嬁傪梌偊偆傞丅偲偔偵丄寈嶡摑寁偵偍偄偰彮擭偺嫮搻専嫇恖堳偑堦嬨嬨幍擭偵尠挊偵憹壛偟偰偄傞偙偲偺堄枴偵偮偄偰偼丄傂偭偨偔傝帠斊偵偍偄偰栤戣偲側傞嫮搻彎奞偲愞搻偍傛傃彎奞偺暪崌嵾偲偺嬫暿偵濨枂偝偑巆傞偙偲偐傜傕丄彮擭寈嶡偵偍偗傞旕峴庢掲偺愊嬌壔丒尩奿壔偺塭嬁傪怲廳偵峫椂偟側偗傟偽側傜側偄(5)丅
丂丂偲偙傠偑丄偄偔偮偐偺悽榑挷嵏偑帵偡傛偆偵丄崙柉偺懡偔偑乽嫢埆壔乿傪怣偠偰偍傝(6)丄棫朄幰傕偦傟傪慜採偵偟偰丄彮擭朄偺夵惓傪恑傔傛偆偲偟偰偄傞丅彮擭旕峴偺乽嫢埆壔乿偺妋怣偼丄暉巸丒嫵堢棟擮偵婎偯偔尰嵼偺彮擭朄偑偆傑偔婡擻偟偰偄側偄偲偺擣幆傪攠夘偲偟偰丄彮擭朄偺尩敱壔梫媮偵寢傃偮偔丅偙偙偵丄崱夞偺乽彮擭朄夵惓乿偑壢妛揑丒棟惈揑側懺搙傪幐偄丄湏堄揑偱偛搒崌庡媊揑偵峴傢傟傞婋尟偑偁傞丅
(3)丂丂孻敱偺惓摉壔梫審偲偟偰偺斊嵾梷巭岠壥
1丂丂孻敱傪惓摉壔偡傞梫審偵丄斊嵾梷巭岠壥偑偁傞丅偙傟偼丄堦斒梷巭岠壥偲摿暿梷巭岠壥偲偵暘偗傞偙偲偑偱偒傞丅
丂丂孻敱棟榑忋丄愨懳揑墳曬孻榑傪偲傜側偄尷傝丄斊嵾梷巭偺岠壥偑側偄側傜偽丄孻敱偼惓摉壔偝傟側偄丅傛傝尩偟偄孻敱傪惓摉壔偡傞偨傔偵偼丄偦偺昁梫忦審偲偟偰丄憡懳揑偵傛傝嫮偄梷巭岠壥偑側偗傟偽側傜側偄(7)丅崱夞偺乽彮擭朄夵惓乿傪傔偖偭偰偼丄孻帠庤懕偵傛傝孻敱傪壢偡偙偲偑丄彮擭怰敾偵傛傝曐岇張暘偱懳張偡傞傛傝傕嫮偄梷巭岠壥偑偁傞偐偳偆偐丄栤戣偵側傞丅
2丂丂寷朄傕偙偺偙偲傪梫惪偟偰偄傞傛偆偵巚傢傟傞丅恖尃偺嵟戝尷偺懜廳偲偄偆寷朄尨懃偐傜偡傟偽丄孻敱偵傛傞恖尃惂栺傕丄偦傟偵傛傞斊嵾梷巭傪捠偠偰恖尃怤奞傪杊巭偡傞偨傔偵昁梫嵟彫尷偺斖埻偵偍偄偰偺傒丄嫋梕偝傟傞偐傜偱偁傞(8)丅斊嵾梷巭岠壥偺懚嵼偟側偄偙偲偑柧傜偐偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄傛傝尩偟偄孻敱傪壢偡偙偲偼丄寷朄忋惓摉壔偝傟偢丄乽巆媠側孻敱乿(寷朄嶰榋忦)偲偟偰嬛巭偝傟傞丄偲棟夝偡傋偒偱偁傞(9)丅
丂丂傑偨丄柧傜偐偵斊嵾梷巭岠壥偑懚嵼偟側偄偲偼偄偊偢丄寷朄堘斀偲傑偱偼擣傔傜傟側偄応崌偱傕丄屻弎偺傛偆偵丄寷朄偺庯巪丒惛恄偵傛傝揔崌偡傞傛偆側孻帠棫朄偑昁梫偲偝傟傞側傜偽丄傛傝尩偟偄孻敱傪掕傔傞偨傔偵偼丄傛傝嫮偄斊嵾梷巭岠壥偺懚嵼偑丄憡摉掱搙偵傑偱妋幚偵擣傔傜傟側偗傟偽側傜側偄丅偙傟偑擣傔傜傟側偄偵傕偐偐傢傜偢丄傛傝尩偟偄孻敱傪偁偊偰掕傔傞偙偲偼丄恖尃偺嵟戝尷偺懜廳偲偄偆尨懃傪偲傞寷朄偺庯巪丒惛恄偵揔崌偟側偄丄偲偄偆傋偒偱偁傠偆丅
(4)丂丂堦斒梷巭岠壥
1丂丂傑偢丄堦斒梷巭岠壥偑栤戣偵側傞丅偙傟傑偱偺宱尡壢妛揑尋媶偵偍偄偰丄曐岇張暘偺応崌傛傝傕孻帠張暘偺応崌偺曽偑丄傛傝嫮偄梷巭岠壥傪桳偡傞偲偺強尒偼帵偝傟偰偄側偄丅傓偟傠丄傾儊儕僇偱夁嫀峴傢傟偨尋媶偼丄徚嬌揑強尒傪帵偟偰偒偨(10)丅
丂丂偟偐偟丄乽尩廳側張暘偼傛傝嫮偄梷巭岠壥傪傕偮乿偲偄偆嫮偄怣擮偑偁傞偨傔偐丄曐岇張暘傛傝孻敱偺曽偑傛傝嫮偄梷巭岠壥傪傕偮丄偲峀偔怣偠傜傟偰偄傞丅偨偲偊偽丄揙掙偟偨尩敱惌嶔傪偲偭偰偒偨傾儊儕僇偵偍偄偰丄堦嬨嬨乑擭戙敿偽埲崀偵嶦恖偵傛傞彮擭偺旐戇曔幰悢偺恖岥斾偑尭彮偟偰偄傞偙偲側偳傪丄尩敱偺梷巭岠壥偺尰傟偲偡傞尒曽傕帵偝傟偰偄傞丅偙偺傛偆側尒曽偼丄尩敱偵梷巭岠壥偁傝偲偺怣擮偵揔崌偡傞偩偗偵丄梕堈偵庴偗擖傟傜傟傗偡偄丅
2丂丂彮擭朄偺曣崙傾儊儕僇偼丄堦嬨幍乑擭戙枛偐傜丄嬌抂側尩敱壔傊偲孹幬傪恑傔偰偒偨丅廳戝斊嵾傪岠壥揑偵梷巭偡傞偨傔偲偟偰丄堦掕偺廳戝斊嵾偵偮偄偰偼丄嘆彮擭嵸敾強偐傜孻帠嵸敾強偵帠審傪峀偔梕堈偵堏憲(娗妽尃曻婞)偱偒傞傛偆偵偡傞丄嘇専嶡姱偑帠審傪彮擭嵸敾強偵憲傞偐丄孻帠嵸敾強偵婲慽偡傞偐傪嵸検揑偵敾抐偱偒傞応崌傪奼戝偡傞丄嘊偼偠傔偐傜彮擭嵸敾強偺娗妽偐傜彍奜偟偰丄孻帠嵸敾強偺杮棃揑娗妽壓偵抲偔丄偲偄偆曽朄偵傛傝丄孻帠張暘偺揔梡傪愊嬌揑偵奼戝偟偨(11)丅偙偺傛偆側孹岦偼丄堦嬨敧乑擭戙偐傜嬨乑擭戙傪捠偠偰恑峴偟丄尰嵼偵帄偭偰偄傞(12)丅
丂丂梷巭岠壥偑偁傞偲偄偆尒曽偼丄傾儊儕僇偺寈嶡摑寁偵偍偄偰丄嶦恖偵偮偄偰偺彮擭(堦乑嵨埲忋堦敧嵨枹枮)偺旐戇曔幰偺恖岥斾棪偑丄堦嬨嬨嶰擭傪僺乕僋偵堦嬨嬨巐擭埲崀尭彮傪懕偗偰偄傞偙偲傪丄崻嫆偲偡傞偙偲偑懡偄傛偆偵巚傢傟傞(側偍丄巜昗斊嵾偲偝傟偰偄傞朶椡斊嵾乲嶦恖丄嫮搻丄嫮姯丄壛廳朶峴乴慡懱偵偮偄偰傕堦嬨嬨巐擭傪僺乕僋偵堦嬨嬨屲擭埲崀尭彮偺孹岦偵偁傞)(G1丄G2嶲徠)丅偙偺帪婜偺尭彮偼彮擭朄偺尩敱壔偺岠壥偵堘偄側偄丄偲峫偊傞傢偗偱傞(13)丅
丂丂偟偐偟丄斊嵾偺憹尭偼丄彮擭朄偺尩敱壔偲偄偆偙偲埲奜偺偝傑偞傑側梫場偺塭嬁傪庴偗傞丅偦偆偱偁傞偑備偊偵丄傾儊儕僇偵偍偗傞夁嫀偺宱尡壢妛揑尋媶偼丄尩敱棫朄偑偱偒偨偙偲埲奜偺丄斊嵾偺憹尭偵塭嬁傪梌偊偦偆側梫場傪僐儞僩儘乕儖偟偨偆偊偱丄偡側傢偪嶖棎梫場傪彍奜偟偨偆偊偱丄尩敱棫朄偑斊嵾偺憹尭偵塭嬁傪梌偊偨偐偳偆偐丄妋擣偟偰偄傞丅偦偺寢壥丄尩敱棫朄偺堦斒梷巭岠壥偵偮偄偰偼丄徚嬌揑強尒偑帵偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄尩敱壔偑恑峴偟偰偄偨帪婜偵斊嵾偑尭彮傪帵偟偨偲偄偆偙偲傪傕偭偰丄偨偩偪偵尩敱壔偵梷巭岠壥偑偁傞偲寢榑偡傞偙偲偼丄抁棈揑偵夁偓傞偲偄傢偞傞傪偊側偄丅堦斒梷巭岠壥偵偮偄偰徚嬌揑強尒傪帵偟偰偄傞宱尡壢妛揑尋媶偑懚嵼偡傞偲偒丄偨傫偵寈嶡摑寁忋偺悢抣偵偍偄偰斊嵾尭彮偺孹岦偑偁傞偐傜偲偄偭偰丄偙傟傜偺強尒偑暍偝傟側偄偙偲偼摉慠偱偁傠偆丅
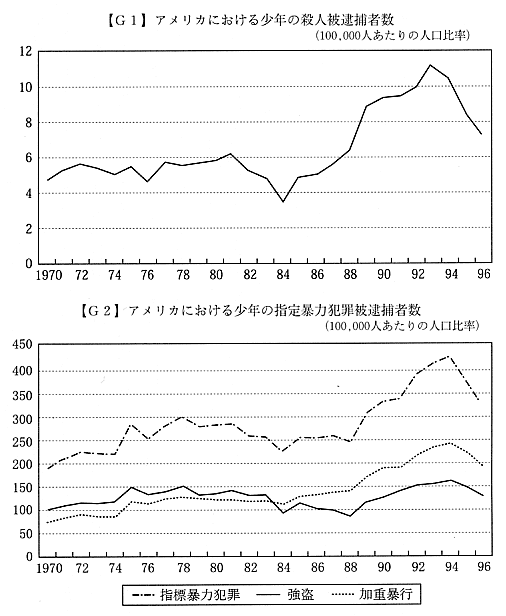
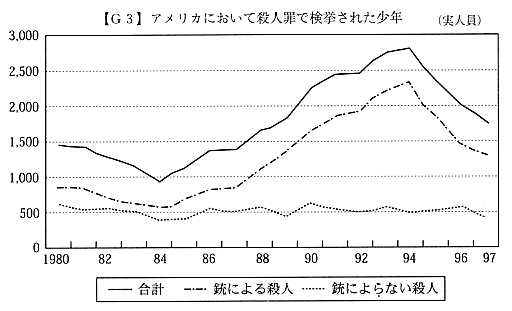
3丂丂傑偨丄寈嶡摑寁忋偺悢抣偺憹尭偩偗傪尒偰傕丄堦嬨敧乑擭戙敿偽崰偐傜堦嬨嬨乑擭戙敿偽偺僺乕僋偵帄傞傑偱丄朶椡斊嵾慡懱偵偮偄偰傕擇攞掱搙丄嶦恖偵偮偄偰偼嶰攞掱搙傕憹壛偟偰偄傞丅忋弎偺尭彮孹岦偼丄偙偺傛偆側尠挊側憹壛偺偁偲偵惗偠偨丅傾儊儕僇彮擭朄偺尩敱壔偼丄堦嬨幍乑擭戙枛偐傜巒傑傝丄堦嬨敧乑擭戙丄嬨乑擭戙傪捠偠偰恑傔傜傟偨丅堦嬨嬨乑擭戙敿偽埲崀偺尭彮偺帪婜偺傒側傜偢丄偦傟偵愭棫偮憹壛偺帪婜傕丄摨偠偔丄彮擭朄偺尩敱壔偑恑傔傜傟偰偄偨帪婜偵廳側傞偺偱偁傞丅
丂丂堦嬨嬨巐擭戙埲崀偵偍偗傞嶦恖偺旐戇曔幰悢偺尭彮傪傕偭偰丄尩敱壔偺梷巭岠壥偺尰傟偲傒傞側傜偽丄堦嬨敧乑擭戙敿偽偐傜偺堦乑擭偼尩敱壔偵梷巭岠壥偼側偐偭偨偗傟偳傕丄堦嬨嬨巐擭偐傜偼堦揮偟偰梷巭岠壥傪敪婗偟巒傔偨丄偲偄偆偙偲偵側偭偰丄偁傑傝偵晄崌棟偱偁傞丅尩敱壔偑恑峴偟偰偐傜堦屲擭傕宱偭偰媫偵丄斊嵾梷巭岠壥偑敪婗偝傟偨偙偲傪丄崌棟揑偵愢柧偡傞偙偲偼晄壜擻偱偁傠偆丅
4丂丂傾儊儕僇偺寈嶡摑寁忋偺旐戇曔幰悢傪尒傞偲丄堦嬨敧乑擭戙敿偽偐傜嬨乑擭戙敿偽偵偐偗偰丄彮擭偺嶦恖偼丄恖岥斾棪偱嶰攞掱搙偵傑偱憹偊偰偄傞(G1嶲徠)丅偙偺娫丄惉恖偺嶦恖偼埨掕偟丄彮擭偺嵿嶻斊傕憹壛偟偰偄側偄丅彮擭偺嶦恖偺憹壛偼偡傋偰廵偵傛傞傕偺偱偁傝(G3嶲徠)丄彮擭偺廵婯惂朄堘斀傕寖憹偟偨丅摨偠帪婜丄彮擭偺杻栻斊嵾傕丄偲偔偵儅僀僲儕僥傿偺偁偄偩偵憹壛偟偨丅
丂丂僽儖乕儉僔儏僞僀儞傜偺尋媶偵傛傟偽丄彮擭偺嶦恖偑憹壛偟偨偙偲偺峔恾偑丄師偺傛偆偵帵偝傟偰偄傞丅偡側傢偪丄杻栻偺枲墑偵傛傝丄斊嵾慻怐偑奼戝偟偰戝搒巗偺僗儔儉偵惗妶偡傞儅僀僲儕僥傿偺彮擭傪枛抂偺杻栻攧恖偲偟偰慻傒崬傒丄偙傟傜偺彮擭偑帺屓杊塹偺偨傔廵傪強帩偟丄偦傟偑偦偺廃曈偵傕峀偑偭偨寢壥丄杻栻庢堷偺僩儔僽儖側偳偺鎦偄偑廵偺巊梡偵傛傝嶦恖傗廳戝彎奞偵敪揥偡傞丄偲偄偆峔恾偱偁傞丅偦偟偰丄偙偺攚宨偵偼丄惌帯宱嵪揑丒暥壔揑悐戅偵傛傞幮夛揑崿棎傗柕弬偺側偐偱丄壠掚傗抧堟幮夛偑峳攑偟丄彮擭偨偪丄偲偔偵偦偺壵崜側塭嬁偑廤拞偡傞戝搒巗僗儔儉偺儅僀僲儕僥傿彮擭偑丄彨棃傊偺婓朷傗幮夛傊偺棟憐傪幐偭偰偟傑偭偨丄偲偄偆傾儊儕僇幮夛偺昦棟偑偁傞(14)丅
5丂丂偙偺傛偆偵丄彮擭偺嶦恖偺憹壛偵丄峔憿揑側幮夛揑梫場偑暋嶨偵嶌梡偟偰偄傞偙偲偐傜偡傞偲丄尩敱棫朄偑梷巭岠壥傪桳偟側偐偭偨偙偲傕丄摉慠偱偁傞傛偆偵巚傢傟傞丅尩敱棫朄偺梷巭岠壥偵婜懸偡傞棫応偼丄斊嵾峴堊偼崌棟揑側棙奞摼幐寁嶼偵傛偭偰寛掕偝傟傞偲偄偆崌棟揑慖戰儌僨儖偵埶嫆偟偰丄彮擭偺嶦恖偺憹壛偼彮擭偵懳偡傞張暘偺娒偝偑庡偨傞梫場偱偁傞偐傜丄尩敱壔偵傛偭偰偙傟傪梷偊崬傓偙偲偑偱偒傞丄偲壖掕偡傞丅偟偐偟丄偙偺傛偆側壖掕偑揑奜傟偱偁傞偙偲偼丄柧傜偐偱偁傠偆(15)丅
丂丂彮擭偺嶦恖偺憹壛偵偮偄偰丄忋弎偺峔恾偑偁偭偨偲偡傟偽丄堦嬨嬨巐擭埲崀偺尭彮偵偼丄廵偺婯惂偑堦掕偺惉壥傪廂傔偨偙偲丄偝傜偵偼丄宱嵪忬懺偑忋岦偒偲側傞側偐偱丄幮夛偑堦掕偺埨掕傪尒偣丄傑偨丄庒擭幐嬈棪偺掅壓偵帵偝傟傞傛偆偵丄彮擭偨偪偑幮夛嶲壛偡傞婡夛傕憹壛偟丄揔朄側宱嵪揑婡夛偺憹戝偵偲傕側偭偰丄堘朄側杻栻巗応偑弅彫偟偨偙偲側偳偑娭楢偟偰偄傞丄偲峫偊傜傟傞偱偁傠偆(16)丅
6丂丂傾儊儕僇偺乽孻朄斊嵾(嵓媆側偳傪彍偔)専嫇恖堳偺曄壔乿偵偍偄偰丄彮擭偵偮偄偰偼丄偦偺幚恖悢偑堦嬨幍乑擭戙枛偐傜敧乑擭戙敿偽偵偐偗偰尠挊偵尭彮偟丄敧乑擭戙敿偽埲崀偼庒姳偺憹壛孹岦傪尒偣側偑傜傕斾妑揑埨掕偟偰偄傞偙偲傪帵偡僌儔僼傪嶲徠偟側偑傜丄乽暷崙偱丄敧乑擭戙埲崀彮擭斊嵾偑捑惷壔偟偨帠幚傕廳梫偱偁傞丅亀暷崙偱偼尩敱壔惌嶔偼幐攕偟偨亁偲傕偲傟傞榑弎偑尒傜傟傞偑丄彮側偔偲傕丄彮擭尩敱壔偵傛傝彮擭斊嵾偺慡懱悢偑梷偊崬傑傟偨帠幚偼斲掕偟摼側偄乿偲偡傞尒夝偑偁傞(17)丅
丂丂偟偐偟丄偙偺傛偆側尒夝偵偼媈栤偑偁傞丅
丂丂尩敱棫朄偺堦斒梷巭岠壥偵徚嬌揑側強尒傪採帵偟偨宱尡壢妛揑尋媶偑偁傞偲偒丄偨偲偊尩敱壔偲彮擭斊嵾偺尭彮偑摨帪婜偵懚嵼偟偰偄偨偲偟偰傕丄偦偺偙偲偐傜偨偩偪偵丄尩敱壔偲偄偆尨場偵傛偭偰彮擭斊嵾偺尭彮偲偄偆寢壥偑惗偠偨偲擣傔傞偙偲偑偱偒側偄偺偼丄忋弎偺偲偍傝偱偁傞丅尩敱偵偼梷巭岠壥偑偁傞偼偢偩丄偲偄偆恖乆偺怣擮偑懚嵼偡傞偐傜偲偄偭偰丄摉慠側偑傜丄偦傟偩偗偱丄彮擭朄偺尩敱壔偵梷巭岠壥偑偁傞偙偲傪愢柧偟偨偙偲偵偼側傜側偄丅
7丂丂傾儊儕僇偺寈嶡摑寁偵偍偄偰偼丄廈偛偲偺斊嵾掕媊偺堘偄傪峫椂偟偰丄偳偺傛偆側廈偵偍偄偰傕斊嵾偲偝傟偰偄傞傛偆側斊嵾傪巜昗斊嵾偵巜掕偟偰偄傞丅偙偺巜昗斊嵾偼丄嶦恖丄嫮搻丄嫮姯丄壛廳朶峴偺巜昗朶椡斊嵾偲丄怤擖愞搻丄帺摦幵愞搻丄扨弮愞搻丄曻壩偺巜昗嵿嶻斊嵾偲偐傜惉傞丅乽孻朄斊嵾(嵓媆側偳傪彍偔)乿偲偼丄偙偺巜昗斊嵾偺偙偲偱偁傠偆丅
丂丂偨偟偐偵丄巜昗斊嵾慡懱偺旐戇曔幰偵偮偄偰丄堦嬨幍乑擭埲崀偺恖岥斾棪傪傒傞偲亅専嫇恖堳偺帪宯楍揑側憹尭傪栤戣偵偡傞偲偒偼丄幚恖悢傛傝傕丄恖岥斾棪偵傛傞曽偑揔愗偱偁傠偆亅丄堦嬨幍幍擭傑偱偼憹壛孹岦偑傒傜傟傞偑丄堦嬨敧巐擭傑偱偼尭彮孹岦偑傒傜傟丄偦偺屻丄堦嬨嬨巐擭傑偱偼備傞傗偐側憹壛孹岦丄偦偺屻偼傑偨尭彮孹岦偑傒傜傟傞(G4嶲徠)丅
丂丂偟偐偟丄摉慠偺偙偲側偑傜丄恖岥斾棪偱傒偨偲偒丄巜昗斊嵾慡懱偺偆偪戝晹暘傪愯傔偰偄傞偺偼巜昗嵿嶻斊嵾偱偁傞丅堦嬨幍乑擭偐傜堦嬨嬨榋擭偺偁偄偩偵丄巜昗嵿嶻斊嵾偑愯傔傞妱崌偼丄嵟崅偱嬨乑亾丄嵟掅偱傕敧嶰亾偵偺傏偭偰偄傞丅偟偨偑偭偰丄巜昗斊嵾慡懱偺憹尭偼丄巜昗嵿嶻斊嵾偺憹尭偵傛偭偰寛掕揑偵嵍塃偝傟傞偙偲偵側傞丅巜昗嵿嶻斊嵾偑尭傟偽巜昗斊嵾慡懱傕尭傝丄憹偊傟偽憹偊傞丄偲偄偆娭學偱偁傞丅帠幚丄巜昗斊嵾慡懱丄巜昗嵿嶻斊嵾丄巜昗朶椡斊嵾傪暲傋偰傒傞偲丄巜昗斊嵾慡懱偼丄巜昗朶椡斊嵾偺憹尭孹岦偲偐偐傢傝側偔丄巜昗嵿嶻斊嵾偺憹尭孹岦偲
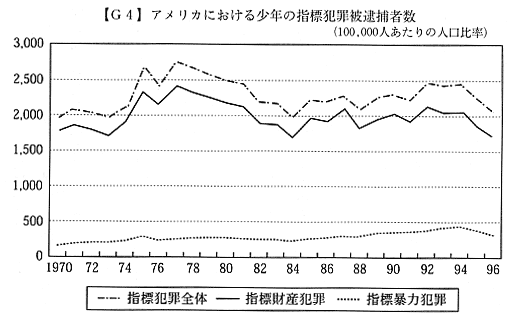
堦抳偟偰曄壔偟偰偄傞偙偲偑暘偐傞(G4嶲徠)丅偟偨偑偭偰丄堦嬨幍乑擭戙枛偐傜堦嬨敧乑擭戙敿偽偵偐偗偰丄巜昗斊嵾慡懱偑恖岥斾偵偍偄偰傕尭彮偟偨偲偄偆偙偲偼帠幚偱偁傞偑丄偦傟偼偁偔傑偱傕丄巜昗嵿嶻斊嵾偺尭彮偺寢壥偱偁傞丄偲峫偊傞傋偒偱偁傠偆丅
丂丂偙偺傛偆偵丄巜昗斊嵾慡懱偺憹尭偼丄巜昗嵿嶻斊嵾偺憹尭偵寛掕揑偵嵍塃偝傟傞傕偺偱偁傞偐傜丄尩敱壔偺梷巭岠壥傪妋擣偡傞巜昗偲偟偰揔愗偱偼側偄傛偆偵巚傢傟傞丅彮擭朄偺乽尩敱壔乿偲偄偆奣擮偼懡條側傕偺偱偁傝偆傞偑丄崱夞偺擔杮偺乽彮擭朄夵惓乿偲偺娭學偱偲偔偵栤戣偲側傞偺偼丄廳戝斊嵾傊偺孻帠張暘揔梡偺奼戝偲偄偆堄枴偺尩敱壔偱偁傞丅傾儊儕僇偺尩敱壔傕丄偙傟傪嵟戝偺徟揰偲偟偰偒偨丅偟偨偑偭偰丄尩敱壔偺梷巭岠壥傪栤戣偵偡傞応崌丄巜昗斊嵾慡懱傪巜昗偲偡傞偺偱偼側偔丄尩敱壔偺庡偨傞昗揑偲側偭偨巜昗朶椡斊嵾(嶦恖丄嫮搻丄嫮姯丄壛廳朶峴)傪巜昗偲偡傞傋偒偱偁傠偆丅偝傜偵丄巜昗朶椡斊嵾偺側偐偱傕丄嶦恖埲奜偺斊嵾偵偮偄偰偺埫悢偺戝偒偝丄尷奅偺濨枂偝偲娭楢偡傞庢掲偺偁傝曽偺梌偊傞塭嬁偺戝偒偝傪峫椂偡傞側傜偽丄嶦恖傪巜昗偲偡傞偙偲偑嵟傕揔愗偱偁傠偆丅
8丂丂堦斒梷巭岠壥偲娭楢偟偰丄彮擭朄偺尩敱壔側偄偟孻帠張暘偺揔梡奼戝偵傛傞乽婯斖堄幆乿偺妎惲偲偄偆偙偲偑偄傢傟傞丅彮擭旕峴偺憹壛丒怺崗壔偼丄彮擭偺偁偄偩偵乽婯斖堄幆乿偑悐戅偟偰偄傞偙偲偺尰傟偱偁傞偐傜丄乽婯斖堄幆乿偺妎惲偵傛傞斊嵾梷巭偺偨傔偵丄孻帠張暘偺揔梡奼戝偑昁梫偱偁傞丄偲偄偆偺偱偁傞丅
丂丂偨偟偐偵丄棟榑揑偵偼丄孻敱偺堦斒梷巭岠壥偼丄埿奷偵傛傞梷巭偩偗偱側偔丄婯斖堄幆偺妋擣丒嫮壔偵傛傞梷巭偵傛偭偰払惉偝傟偆傞丅嬤帪孻敱棟榑偲偟偰桳椡偲側偭偰偒偨愊嬌揑堦斒梊杊榑偼丄屻幰傪嫮挷偡傞傕偺偱偁傞丅偟偐偟丄婯斖堄幆偺妋擣丒嫮壔偵傛傞堦斒梊杊岠壥偼丄偦傟帺懱丄専徹偝傟偰偄側偄壖愢偱偁傞丅
丂丂忋弎偺傛偆偵丄尩敱壔偺堦斒梷巭岠壥偵偮偄偰徚嬌揑強尒傪帵偟偰偄傞宱尡壢妛揑尋媶偑偁傞側偐丄偙偺傛偆側枹専徹偺壖愢偲偟偰偺婯斖堄幆偺妋擣丒嫮壔偵傛傞堦斒梊杊岠壥傪丄孻敱慡懱側偄偟孻敱惂搙堦斒傪棟榑揑偵惓摉壔偡傞偨傔偺崻嫆偲偟偰梡偄傞偙偲傪挻偊偰丄偨偲偊偽嶦恖偵懳偡傞嵟崅孻傪柍婜孻偱偼側偔巰孻偲偡傋偒偐偲偄偆傛偆側丄斊嵾峴堊偵懳偡傞傛傝尩奿側嬶懱揑張暘傪惓摉壔偡傞崻嫆偲偟偰梡偄傞偙偲偼偱偒側偄傛偆偵巚傢傟傞(18)丅
(5)丂丂嵞斊棪傊偺塭嬁
1丂丂斊嵾梷巭岠壥偲偟偰師偵栤戣偲側傞偺偑丄嵞斊棪傊偺塭嬁偱偁傞丅
丂丂曐岇張暘偺応崌偺嵞斊棪偲孻敱偺応崌偺嵞斊棪傪斾妑偟偨宱尡壢妛揑尋媶偼丄擔杮偵偼偙傟傑偱偵側偄偑丄彮擭堾壖戅堾幰偑曐岇娤嶡拞偺嵞斊偵傛偭偰挦栶丒嬛屌偺孻敱傑偨偼彮擭堾憲抳偺曐岇張暘傪庴偗偨妱崌偵斾傋偰丄枮婜傑偨偼壖庍曻偵傛傝峴孻巤愝傪弌強偟偨幰偑峴孻巤愝偵嵞擖偡傞妱崌偺曽偑崅偄偙偲(19)傗丄傾儊儕僇偺宱尡壢妛揑尋媶偺帵偡強尒(20)偐傜偡傞偲丄孻敱偺応崌偺曽偑嵞斊棪偼崅偄傛偆偵悇應偝傟傞丅
丂丂偙偺偙偲偼丄孻敱偺応崌偵偼丄幮夛惗妶偐傜偺挿婜偺妘棧丄幮夛暅婣巟墖偺庛偝丄斲掕揑側幮夛揑鄝報偺嫮偝偑嵞斊棪偺崅偝偵偮側偑傞偲偄偆揰偵偍偄偰丄棟榑揑偵愢柧傕壜擻偱偁傞丅孻敱傪壢偝傟偨応崌偵偼丄埨掕偟偨廇怑側偳丄彨棃偺幚岠揑側幮夛嶲壛偺婡夛傪傛傝戝偒偔幐偆偙偲偵側傞丄偲偺愢柧傕壜擻偱偁傠偆丅彮側偔偲傕丄孻敱偺応崌偺曽偑嵞斊棪偑掅偄偲偡傞偙偲偼丄晄崌棟偱偁傞丅
2丂丂偙偺傛偆偵丄堦斒梷巭偺揰偱傕丄孻敱偺曽偑嫮偄梷巭岠壥傪桳偡傞偲偼峫偊傜傟側偄偟丄摿暿梷巭偺揰偱傕丄孻敱偺応崌偺曽偑傓偟傠嵞斊棪偑崅偄偲悇應偝傟傞丅
丂丂忋弎偺傛偆偵丄寷朄偺庯巪丒惛恄偵揔崌偡傞孻帠棫朄偱偁傞偨傔偵偼丄傛傝嫮偄斊嵾梷巭岠壥偺懚嵼偑丄憡摉掱搙偵傑偱妋幚偵擣傔傜傟側偄尷傝丄傛傝尩偟偄孻敱傪掕傔傞偙偲偼嫋偝傟側偄丅偦偆偱偁傞埲忋丄崱夞偺乽彮擭朄夵惓乿偼寷朄偺庯巪丒惛恄偵斀偟偰偄傞丄偲偄傢偞傞傪偊側偄丅傛傝嫮偄堦斒梷巭岠壥傪桳偡傞傢偗偱傕側偔丄嵞斊棪傪崅傔傞偙偲偝偊傕梊應偝傟傞傛偆側乽夵惓乿傪偁偊偰峴偆偙偲偼丄恖尃偺嵟戝尷偺懜廳偲偄偆寷朄尨懃偵柕弬偟嫋偝傟側偄丄偲偄偆傋偒偱偁傞丅
丂丂偦傟偵傕偐偐傢傜偢丄岠壥揑側斊嵾梷巭偺偨傔偵孻敱偑昁梫偱偁傞丄偲崙柉偺懡悢偑怣偠偰偄傞偲偄偆偙偲傪傕偭偰(21)丄斊嵾梷巭岠壥偺懚嵼傪慜採偵偟偰丄崱夞偺乽彮擭朄夵惓乿偑恑傔傜傟偰偄傞丅偙偺堄枴偺乽崙柉偺婜懸乿偵墳偊傞傕偺偱偁偭偨偲偟偰傕丄宱尡壢妛揑婎慴偵寚偗傞丄壢妛揑丒棟惈揑懺搙偐傜棧傟偨孻帠棫朄丄偁傞偄偼寷朄偺庯巪丒惛恄偵揔崌偟側偄傛偆側孻帠棫朄偑惓摉壔偝傟傞偼偢偼側偄丅
(6)丂丂訑C偺帺妎乿偲墳曬揑惂嵸
丂丂崱夞偺乽彮擭朄夵惓乿傪傔偖偭偰偼丄孻敱偵傛傞乽愑擟偺帺妎乿偲偄偆偙偲偑偄傢傟傞丅孻敱偵傛偭偰偦傟偑壜擻側偺偐丄偳偺傛偆側曽朄偑桳岠側偺偐丄偲偄偆揰偼宱尡壢妛揑尋媶偺壽戣偲側傝偆傞丅偟偐偟丄偙偺傛偆偵偄傢傟傞暥柆偼丄宱尡壢妛揑帇揰偐傜棧傟偰丄乽廳戝斊嵾偵偼尩偟偄孻敱偙偦偑摉慠偩丅彮擭偩偐傜偲偄偭偰曐岇張暘偱亀娒偔亁埖偆偺偼惓媊偵斀偡傞乿偲偄偆傛偆側墳曬揑惂嵸偺嫮壔傊偺梫媮偺尵偄姺偊偱偁傞傛偆偵巚傢傟傞丅偦偆偱偁傞偑備偊偵丄乽愑擟乿偺堄枴偑嬦枴偝傟傞偙偲傕丄偦傟偑幮夛暅婣偺揥朷偲娭楢偯偗傜傟偰丄偦偺撪梕偑幚柋忋偺張嬾栚昗偲偟偰愝掕壜擻側掱搙偵傑偱嬶懱壔偝傟傞偙偲傕側偄丅
丂丂寢嬊丄斊嵾梷巭岠壥偵偮偄偰偲摨條丄墳曬揑惂嵸偺嫮壔偲偄偆娤揰偐傜孻帠張暘偺揔梡奼戝傪梫媮偡傞偺偑尰嵼偺乽崙柉偺婜懸乿偱偁傞偲偺慜採偵棫偭偰丄偦偺乽崙柉偺婜懸乿傊偺墳摎偲偄偆棟桼偐傜丄乽彮擭朄夵惓乿偑恑傔傜傟偰偄傞丅
(7)丂丂棫朄夁掱偺栤戣
1丂丂愭偵攑埬偲側偭偨乽帠幚擣掕庤懕偺揔惓壔乿傪昗炘偡傞乽彮擭朄夵惓乿朄埬(22)偑丄朄惂怰媍夛偺怰媍傪宱偰丄惌晎採弌朄埬偲偟偰嶌惉偝傟偨偺偵懳偟偰丄崱夞偺戝偒側摿怓偼丄乽彮擭朄夵惓乿偑乽惌帯栤戣壔乿偟偰丄媍堳棫朄偲偄偆宍偱乽惌帯庡摫乿偵傛傝恑傔傜傟偨偙偲偱偁傞丅傕偭偲傕丄愭偵攑埬偲側偭偨乽彮擭朄夵惓朄埬乿傪傔偖偭偰傕丄幚偼丄媍堳棫朄偺埿奷偑朄惂怰媍夛偺怰媍傗惌晎偺朄埬嶌惉傪懀恑偟丄朄埬偺撪梕偵塭嬁傪梌偊偨偺偱偁偭偨偑(23)丄崱夞偼丄乽惌帯庡摫乿偑傛傝僗僩儗僀僩偵尠嵼壔偟偨丅
丂丂偙偺側偐偱丄嵟嬤偺拲栚偝傟偨旕峴帠審傪偳偺傛偆偵懆偊傞偐傪娷傔丄旕峴尨場傗幚柋偵偍偗傞彮擭朄偺塣梡忬嫷丄巕偳傕傪庢傝姫偔幮夛娐嫬側偳偵偮偄偰丄惓妋側帠幚擣幆傪摼傞偨傔偵廫暘側搘椡偑側偝傟偨偲偼偄偊側偄丅彮擭朄偺幚柋偵実傢傞壠掚嵸敾強嵸敾姱丄壠掚嵸敾強挷嵏姱傗彮擭堾怑堳丄曐岇娤嶡姱丄曐岇巌側偳偺堄尒偝偊傕丄廫暘偵暦偐傟偰偄側偄(24)丅帺柉搣撪偱偼丄崱夞偺乽夵惓乿朄埬採弌偵愭棫偭偰丄堦掕偺斖埻偱娭學幰偐傜偺暦偒庢傝偑峴傢傟偨傛偆偱偁傞偑丄偙傟傕旕岞奐偱抐曅揑側傕偺偱偟偐側偔丄帺柉搣埬傗乽夵惓乿朄埬偵偳偺傛偆偵斀塮偟偨偺偐丄柧傜偐偱偼側偄(25)丅
2丂丂傾儊儕僇偵偍偄偰傕丄彮擭朄偺揙掙偟偨尩敱壔偼丄彮擭巌朄夵妚偺乽惌帯栤戣壔乿偲偄偆暥柆偺側偐丄崙柉偺尩敱梫媮偲尩敱棫朄偵岦偗偨惌帯夁掱偲偺憡屳懀恑揑側娭學傪捠偠偰恑傔傜傟偨(26)丅
丂丂偨偲偊偽丄堦嬨幍敧擭偺僯儏乕丒儓乕僋彮擭斊嵾幰朄偼丄杁嶦偵偮偄偰偼堦嶰嵨埲忋偺彮擭傪丄嫮搻丄壛廳朶峴側偳偦偺懠堦掕偺朶椡斊嵾側偳偵偮偄偰偼堦巐嵨埲忋偺彮擭傪丄壠掚嵸敾強偺杮棃揑娗妽尃偐傜彍奜偟孻帠嵸敾強偺杮棃揑娗妽壓偵抲偄偰丄孻帠愑擟傪栤偄丄尩偟偄孻敱傪揔梡偡傞丄偲偄偆傕偺偱偁傝丄傾儊儕僇傪戙昞偡傞尩敱棫朄偱偁傞偲昡偝傟偨偑丄偙傟傕丄廈媍夛傗惌晎偑丄曐庣攈傪拞怱偵丄乽斊嵾晄埨乿偵嬱傜傟偰尩敱壔傪梫媮偡傞廈柉悽榑傪慀傝偮偮丄偦傟偵寎崌偡傞宍偱棫朄偝傟偨丅擇擭懕偗偰廈媍夛偑壜寛偟偨巰孻朄埬偵嫅斲尃傪峴巊偡傞側偳偵傛傝丄曐庣攈偐傜乽斊嵾偵庛崢乿偲斸敾偝傟懕偗丄惌帯揑捝庤傪旐偭偰偒偨儕儀儔儖攈廈抦帠偑丄廈抦帠丒廈媍夛慖嫇偵偁偨偭偰丄曐庣攈廈媍夛媍堳偺採埬傪庢傝崬傒斊嵾傊偺嫮埑揑巔惃傪帵偡偙偲偵傛傝丄桳尃幰偺巟帩傪峀偔妉摼偟傛偆偲偺惌帯揑巚榝偐傜丄彮擭堾傪戅堾偟偨捈屻偵偁傞彮擭偑抧壓揝偱悢恖傪幩嶦偡傞偲偄偆撍敪揑偵婲偒偨廳戝旕峴帠審傪偒偭偐偗偵丄撍慠偵棫応傪揮姺偟偨偙偲偵傛偭偰丄傎傫偺悢擔娫偱朄埬偑嶌惉偝傟壜寛偝傟偨丅廈媍夛媍堳偵朄埬偑庤搉偝傟偨偺偼丄怰媍丒嵦寛偺偨傔偵媍応擖傝偡傞偝偄偵偱偁偭偨丅
丂丂偙偺娫丄擇擭慜堦嬨幍榋擭偺彮擭巌朄夵妚朄偺惂掕偵偁偨偭偰峴傢傟偨傛偆偵丄愱栧挷嵏埾堳夛傪愝抲偟偰丄彮擭旕峴偺尨場傗彮擭朄偺塣梡忬嫷丄朄夵惓偺岠壥梊應側偳偵偮偄偰惓妋側帠幚擣幆傪摼傞偨傔偺挷嵏尋媶傪峴偆偙偲傕側偄傑傑丄彮擭朄偺塣梡偵実傢傞幚柋壠傗愱栧壠偺堄尒偝偊傕廫暘偵暦偐傟傞偙偲側偔丄傓偟傠偦傟傜偺斀懳傪墴偟愗傞宍偱丄嫮堷偵棫朄偑峴傢傟偨(27)丅
3丂丂崱夞丄擔杮偵偍偄偰傕丄乽彮擭朄夵惓乿傪悇恑偟偨崙夛媍堳偐傜偼丄乽朄惂怰媍夛偵偐偗偰偄偨偺偱偼帪娫偑偐偐傝偡偓傞丅亀崙柉偺婜懸亁偵恦懍丒揑妋偵墳摎偡傞偙偲偑惌帯壠偺愑擟偱偁傞偐傜丄崱夞偺夵惓偼惌帯庡摫偺媍堳棫朄偵傛偭偰峴偆乿巪昞柧偝傟偨(28)丅傑偨丄偙偺傛偆側宍偱乽崙柉偺婜懸乿偵墳偊傞偙偲偼丄崙柉偺偁偄偩偵峀偑偭偰偄傞乽晄埨姶乿傪夝徚偟偰乽埨怱偟偰曢傜偣傞擔杮乿傪嶌傞偙偲傪堄枴偡傞丄偲傕偄傢傟偨丅
丂丂偙偆偟偰丄乽彮擭朄夵惓乿偑丄旕峴懳嶔側偄偟巕偳傕偺暉巸丒嫵堢偵娭偡傞朄偺夵惓偲偄偆堄枴傪挻偊偰丄愊嬌揑側崙柉摑崌偺偨傔偺庤抜偲偟偰崙壠婋婡娗棟偺堦娐偵埵抲偯偗傜傟偨偲傕偄偊傛偆丅偙傟偼丄乽搻挳朄乿傗乽慻怐斊嵾懳嶔朄乿偵傕捠偠傞埵抲偯偗偱偁傞(29)丅偙偺傛偆側孻帠棫朄傪惓摉壔偡傞愗傝嶥偑丄乽崙柉偺婜懸乿傊偺墳摎偲偄偆偙偲偱偁傞(30)丅
巐丂丂峫丂丂丂丂丂丂嶡
(1)丂丂憱瘋虋鷳襾v偲孻帠棫朄
1丂丂崱夞偺乽彮擭朄夵惓乿偺悇恑椡偲偟偰埵抲偯偗傜傟傞傕偺偼丄乽崙柉偺婜懸乿偱偁傞(31)丅廳戝旕峴偵懳偡傞墳曬揑惂嵸偺嫮壔傊偺梫媮偑丄尩敱壔偺斊嵾梷巭岠壥傊偺怣擮偵傛偭偰巟偊傜傟偰丄尩敱壔傊偺乽崙柉偺婜懸乿偵墳摎偡傞偲偄偆宍偱丄崱夞偺乽彮擭朄夵惓乿偑恑傔傜傟偨丅偙偙偱偼丄儅僗丒儊僨傿傾側偳傪捠偠偰峀偔揱偊傜傟擣幆偝傟偨乽旐奞幰偺梫媮乿偵懳偡傞乽嫟姶乿偑廳梫側埵抲傪愯傔偰偄傞丅
2丂丂僠僃僓乕儗丒儀僢僇儕乕傾偑丄堦敧悽婭敿偽夁偓偵亀斊嵾偲孻敱(32)亁偵偍偄偰丄岟棙庡媊揑棫応偐傜丄孻敱偺惓摉壔崻嫆傪墳曬偱偼側偔斊嵾梷巭偵抲偔傋偒偙偲傪庡挘偟偰埲棃丄斊嵾梷巭岠壥傪孻敱偺惓摉壔梫審偲偡傞孻敱棟榑偑桪惃偲側偭偨丅
丂丂偙偆偟偰丄斊嵾梷巭岠壥傗嵞斊棪偼丄孻帠棫朄傪惓摉壔偡傞昁梫忦審偱偁傝丄偦偺桳岠惈傪寛傔傞巜昗偲偟偰埵抲偯偗傜傟偨丅孻帠朄偵娭偡傞宱尡壢妛揑尋媶偺庡偨傞娭怱傕丄偙傟偵岦偗傜傟偰偒偨丅偨偲偊偽丄巰孻懚攑傪傔偖傞媍榑偵偍偄偰傕丄傒傜傟傞偲偍傝偱偁傞丅偙偺偙偲偼丄乽斊嵾梷巭岠壥偑宱尡揑偵妋擣偝傟側偄孻敱傗丄嵞斊棪傪偐偊偭偰崅傔傞傛偆側孻帠棫朄偼惓摉壔偝傟側偄乿偲偄偆宍偱丄孻帠棫朄偑丄宱尡壢妛揑婎斦傪桳偡傞傕偺偲偟偰丄壢妛揑丒棟惈揑懺搙偺壓偵峴傢傟傞偙偲傪曐忈偟偨丅
丂丂偟偐偟丄崱夞偺乽彮擭朄夵惓乿偵傒傜傟傞傛偆偵丄孻帠棫朄偺乽惌帯栤戣壔乿偲偄偆暥柆偺側偐偱丄偦偺惓摉壔偺崻嫆傪僗僩儗僀僩偵乽崙柉偺婜懸乿傊偺墳摎偵抲偔傛偆偵側偭偨側傜偽丄棫朄傪婎慴偯偗傞帠幚偺擣幆偵偍偄偰宱尡壢妛揑婎斦偑幐傢傟丄孻帠棫朄偑壢妛揑丒棟惈揑懺搙偐傜槰棧偟偰偄偔婋尟偑惗偠傞丅尰嵼傑偱偵丄乽婯惂娚榓乕帺桼嫞憟乕帺屓寛掕丒帺屓愑擟乿傪宖偘傞怴帺桼庡媊揑夵妚偵傛傝慡柺揑側幮夛嵞曇偑恑傔傜傟傛偆偲偟偰偄傞偑丄偙傟偺慜採偲偡傞恖娫憸偼丄斊嵾峴堊偲偺娭楢偵偍偄偰偼丄崌棟揑側棙奞摼幐寁嶼偺寢壥偲偟偰斊嵾峴堊偵媦傇偐偳偆偐傪寛掕偡傞偲偄偆恖娫憸偱偁傠偆丅怴帺桼庡媊揑夵妚偑恑傔傜傟傞側偐偱丄偙偺傛偆側斊嵾峴堊偵娭偡傞崌棟揑慖戰儌僨儖偵埶嫆偟偨埿奷梷巭榑偵丄惌帯揑丒幮夛揑巟帩偑嫮傑傝丄偦傟偵偲傕側偄丄埿奷梷巭榑偵婎偯偔尩敱壔傊偺乽崙柉偺婜懸乿偵偍偄偰懚嵼偡傞偲偝傟傞孻斊嵾梷巭岠壥偼丄傕偼傗丄宱尡壢妛揑偵妋擣壜擻側帠幚偱偼側偔丄壢妛揑丒棟惈揑懺搙偺壓偱丄孻帠棫朄傪婎慴偯偗傞傕偺偲偼側傝偊側偄丅
丂丂孻帠棫朄偑壢妛揑丒棟惈揑懺搙傪幐偭偰峴傢傟傞偲偒丄斊嵾丒旕峴偵懳偡傞幮夛揑暜寖傪攚宨偵偟偰丄晄昁梫偵壵崜側丄夁搙偺恖尃惂栺傪傕偨傜偡婋尟偑嫮偔側傞丅傑偨丄斊嵾尨場傪惓妋偵夝柧偟偦傟傪夝徚偡傞偲偄偆娭怱偑幐傢傟傞偙偲偵側偭偰丄寢嬊丄斊嵾栤戣傪怺崗壔偝偣傞偙偲偵傕偮側偑傞丅忋弎偺傛偆偵丄寷朄偺庯巪丒惛恄偵揔崌偡傞傛偆側孻帠棫朄偱偁傞偨傔偵偼丄憡摉掱搙偵傑偱妋幚偵丄傛傝嫮偄斊嵾梷巭岠壥偺懚嵼偑妋擣偝傟側偗傟偽丄傛傝尩偟偄孻敱傪掕傔傞偙偲偼偱偒側偄丄偲偄偆傋偒偱偁傞丅宱尡壢妛揑婎斦偐傜棧傟丄壢妛揑丒棟惈揑懺搙偑幐傢傟偨偲偒丄寢壥偲偟偰孻帠棫朄偼丄恖尃偺嵟戝尷偺懜廳偲偄偆尨懃傪偲傞寷朄偺庯巪丒惛恄偐傜堩扙偟偨傕偺偲側偭偰偄偔丅
3丂丂憱瘋虋鷳襾v偵墳摎偡傞偙偲偙偦偑惌帯偺愑擟偱偁傞丄偲偺峫偊傕偁傞偐傕偟傟側偄丅偨偟偐偵丄堦尒傕偭偲傕偱偁傞丅
丂丂偟偐偟丄恖尃偺嵟戝尷偺懜廳偲偄偆寷朄尨懃偺壓丄孻帠棫朄偵偁偨偭偰偼丄棫朄幰偼丄偁傝偺傑傑偺乽崙柉偺婜懸乿偵丄偦偺撪梕傪嬦枴偡傞偙偲傕側偔柍斸敾偵廬偆偺偱偼側偔丄偁傞傋偒孻帠棫朄傪巗柉偵採帵偟偨偆偊偱丄偦傟偵偮偄偰偺崌堄傪宍惉偡傞傛偆搘椡偡傞惌帯揑愑擟傪晧偭偰偄傞丄偲偄偆傋偒偱偁傠偆(孻帠棫朄夁掱偺揔惓庤懕偵偮偄偰丄屻弎嶲徠)丅孻帠棫朄偑恖尃偺嫮惂揑攳扗偵娭偡傞傕偺偱偁傞埲忋丄偨偲偊懡悢攈偺乽崙柉偺婜懸乿偵崌抳偡傞偐傜偲偄偭偰丄偳偺傛偆側孻帠棫朄偱傕惓摉壔偝傟傞傢偗偱偼側偄偐傜偱偁傞丅偙偺傛偆側惌帯揑愑擟傪壥偨偡偙偲偙偦偑丄柉庡庡媊偵揔偆傕偺偱偁傞丅僼儔儞僗偵偍偗傞巰孻攑巭偼丄偦偺岲椺偱偁傞(33)丅
4丂丂傑偨丄尩敱壔側偄偟斊嵾摑惂偺嫮壔偺梫媮偲偄偆宍偱昞尰偝傟傞偙偲偺懡偄乽崙柉偺婜懸乿偵偮偄偰丄偦偺撪梕傪傛傝惛鉱偵夝柧偟丄偦傟偑偳偺傛偆偵宍惉偝傟傞偺偐丄偳偺傛偆側梫場偑偦傟偵嶌梡偟偰偄傞偺偐丄側偳傪栤戣偵偟側偗傟偽側傜側偄丅崱夞偺乽彮擭朄夵惓乿傪傔偖偭偰偼丄側偤尩敱壔偺梫媮偑嫮傑偭偨偺偐丄偳偺傛偆側帠幚擣幆傪婎慴偵偟偰偄傞偺偐丄偦偺傛偆側乽崙柉偺婜懸乿偑偳偺傛偆偵宍惉偝傟傞偺偐丄乽惌帯栤戣壔乿偺暥柆偑偳偺傛偆偵娭楢偟偰偄傞偐丄側偳偺揰偵偮偄偰偱偁傞(34)丅
丂丂偙偺偲偒丄尩敱壔偺梫媮傪堷偒婲偙偡乽斊嵾晄埨乿偑丄傛傝峀斖偱崻怺偄乽幮夛晄埨乿偺傂偲偮偺尰傟偱偼側偄偺偐丄偲偄偆帇揰偵傕棷堄偡傋偒偱偁傠偆(35)丅偦偆偱偁傞側傜偽丄乽斊嵾晄埨乿偺夝徚傪慱偭偨孻帠棫朄偵傛偭偰丄偨偲偊堦帪偺乽埨怱乿偑摼傜傟偨偲偟偰傕丄偦傟偼偮偐偺娫偺婾傝偵偟偐夁偓偢丄婎斦偵巆傞乽幮夛晄埨乿偑巄偔偟偰傑偨乽斊嵾晄埨乿偲側偭偰昞弌偟丄尩敱壔梫媮偑嵞傃惗偠傞偙偲偵側傞偐傜偱偁傞(36)丅
5丂丂尰嵼丄斊嵾偺戝婯柾壔丒慻怐壔丒暋嶨壔丄崙嵺壔側偳偑偄傢傟丄怺崗壔偡傞斊嵾偐傜巗柉偺埨慡傪妋幚偵庣傞昁梫偑偁傝丄幚懱丄庤懕偺椉柺偵傢偨傞斊嵾摑惂偺嫮壔偵懳偡傞乽崙柉偺婜懸乿偑偁傞偲偟偰丄偦傟傊偺墳摎偲偄偆宍偱丄憑嵏尃尷偺嫮壔丄斊嵾張棟偺岠棪壔側偳丄峀斖側孻帠巌朄夵妚偑採婲偝傟偰偄傞丅巌朄惂搙夵妚怰媍夛偵偍偄偰傕丄乽崙柉偺婜懸偵墳偊傞孻帠巌朄偺嵼傝曽乿傪傔偖偭偰丄偙偺傛偆側媍榑偑峴傢傟偰偄傞(37)丅
丂丂偟偐偟丄採婲偝傟偰偄傞嬶懱揑夵妚埬傪婎慴偯偗丄偦傟傪惓摉壔偡傞掱搙偵傑偱丄斊嵾偺怺崗壔偑尰幚偵偁傞偐偳偆偐丄昁偢偟傕柧傜偐偱偼側偄丅傑偨丄斊嵾梊杊傗斊嵾旐奞媬嵪偺庤抜偲偟偰孻帠巌朄偵偼寛掕揑側尷奅偑偁傝丄偦傟偵夁忚側婜懸傪婑偣傞偙偲偼丄斊嵾偐傜偺巗柉偺埨慡傪妋曐偡傞偨傔偵恀偵昁梫側丄峀斖側幮夛揑忦審偺曄妚傪傕帇栰偵擖傟偨惌嶔傪寢嬊偼曻抲偡傞偙偲偵傕偮側偑傞丅
丂丂傕偲傕偲丄孻帠巌朄偼崙偺壵楏側嫮惂揑尃椡偲偟偰偺孻敱尃偑峴巊偝傟傞夁掱偱偁傝丄巌朄偺杮棃揑婡擻偑巗柉偺恖尃曐忈偵偙偦偁傞埲忋丄嵟廳梫偺壽戣偲偝傟傞傋偒偙偲偼傗偼傝丄尃椡峴巊偺湏堄丒愱抐偐傜偺恖尃曐忈偱偁傞丅愴慜丒愴拞婜偺怺崗側恖尃怤奞傊偺斀徣偵棫偪丄恖尃曐忈偵怺偔攝椂偟偰丄庤岤偄揔惓庤懕傪掕傔偨偺偑寷朄偱偁傞丅恖尃偺嵟戝尷偺懜廳傪尨懃偲偡傞寷朄偺壓偱偼丄恖尃曐忈偙偦偑孻帠巌朄偺僥乕儅偱偁傝丄乽崙柉偺婜懸乿偼尃椡揑側斊嵾摑惂偺嫮壔偵偱偼側偔丄幚懱揑丒庤懕揑偵揔惓側孻帠巌朄偵傛傞恖尃曐忈偵岦偗傜傟偰偄傞丄偲棟夝偡傋偒偱偁傠偆(38)丅
(2)丂丂孻帠棫朄夁掱偺揔惓庤懕
1丂丂寷朄嶰堦忦偼丄乽壗恖傕丄朄棩偺掕傔傞庤懕偵傛傜側偗傟偽丄乧乧孻敱傪壢偣偝傟側偄乿偲掕傔偰偍傝丄偙偺婯掕偼丄揔惓庤懕側偄偟揔惓庤懕偺曐忈偲偟偰丄孻帠幚懱朄偲孻帠庤懕朄偺揔惓偝傪梫媮偟偰偄傞丄偲棟夝偝傟偰偄傞丅偝傜偵丄孻敱幏峴夁掱偺揔惓庤懕傕梫媮偝傟偰偄傞丄偲偺棟夝傕偁傞(39)丅巗柉偺恖尃曐忈偺偨傔偵丄孻帠朄偺揔惓偝偑偙傟傜偺揰偵偍偄偰梫媮偝傟傞偺偱偁傟偽丄孻帠棫朄偺夁掱偵偮偄偰傕丄揔惓庤懕偑栤戣偲側傝偆傞偺偱偼側偐傠偆偐丅
丂丂偨偟偐偵丄孻帠棫朄偼寷朄偺梫惪傪枮偨偡傕偺偱側偗傟偽側傜偢丄寷朄堘斀偺朄椷偱偁傟偽丄嵸敾強偵傛偭偰偦偺揔梡偼攔彍偝傟傞丅偟偐偟丄孻帠棫朄偵偮偄偰偼丄寷朄偺梫惪傪枮偨偡偲偄偆堄枴偺崌寷惈偺梫媮傪挻偊偰丄棫朄惌嶔偲偟偰偺懨摉惈傪傕栤戣偲偟側偗傟偽側傜側偄丅偙偺揰偵偮偄偰丄懞堜晀朚偼丄孻帠棫朄偺棫朄惌嶔揑懨摉惈傪栤戣偲偡傞偙偲偺堄媊傪採婲偟丄妋幚側棫朄帠幚偺懚嵼丄偦傟偲孻帠棫朄偺娭楢惈偑昁梫偱偁傞偙偲傪榑偠傞偲偲傕偵丄婎杮揑恖尃偺懜廳偲偄偆棫媟揰偐傜丄孻帠棫朄偺懨摉惈敾抐偺儊儖僋儅乕儖傪偁偘偰偄傞(40)丅傑偨丄寷朄妛幰偺巗愳惓恖偼丄乽寷朄偺庯巪丒惛恄偵傛傝揔崌偡傞傛偆側朄夝庍丄棫朄惌嶔偺採帵傕寷朄妛偺壽戣偱偁傞乿偲偺栤戣傪採婲偟丄乽寷朄偺棟擮傪尰幚壔偝偣偰偄偔丄寷朄偺掕棫偟偨壙抣傪慡朄懱宯偵幚嵺偵娧揙偝偣偰偄偔乿偨傔偵丄乽棫朄惌嶔偺摉斲偵偮偄偰偺媍榑偺搚昒丄婎弨傪愝掕偡傞傕偺乿偲偟偰丄乽偁傞惌嶔偑亀寷朄忋朷傑偟偄亁亀寷朄忋朷傑偟偔側偄亁偲偄偆媍榑乿傪峴偆傋偒偱偁傞丄偲榑偠偰偄傞(41)丅偲偔偵丄忋弎偺傛偆偵丄寷朄偺庯巪丒惛恄偵揔崌偟偨孻帠棫朄偱偁傞偨傔偵偼丄摿暿側斊嵾梷巭岠壥偺懚嵼偑憡摉掱搙偵傑偱妋幚偵擣傔傜傟側偄尷傝丄傛傝尩偟偄孻敱傪掕傔傞偙偲偼偱偒側偄丄偲偄偆傋偒偱偁傞丅
丂丂偙偺傛偆偵丄孻帠棫朄偵偮偄偰丄棫朄惌嶔偲偟偰偺懨摉惈丄偁傞偄偼寷朄偺庯巪丒惛恄偵傛傝揔崌偡傞傛偆側孻帠棫朄偑昁梫偲偝傟傞偺偱偁傟偽丄偦傟傪妋曐偡傞偨傔偺庤懕曐忈偲偟偰丄孻帠棫朄夁掱偵偮偄偰傕婯斖揑側庤懕婎弨偑愝掕偝傟傞傋偒偱偼側偐傠偆偐丅偄傢偽丄孻帠棫朄夁掱偺揔惓庤懕偑梫媮偝傟傞偺偱偁傞丅
2丂丂孻帠棫朄夁掱偺揔惓庤懕偲偄偭偰傕丄偦偺撪梕偼柧傜偐偱偼側偄丅偙傟傪峫偊傞庤偑偐傝偲側傞偺偼丄楌巎揑偵揔惓庤懕偺杮幙揑梫慺偲偟偰丄乽崘抦乿偲乽挳暦乿偺曐忈偑娤擮偝傟偰偒偨偙偲偱偁傞(42)丅孻帠棫朄夁掱偺揔惓庤懕傪峔憐偡傞偲偒丄孻帠棫朄偵傛傝恖尃傪惂栺偝傟偆傞巗柉偵懳偟偰乽崘抦乿偲乽挳暦乿傪幚幙揑偵曐忈偟丄孻帠棫朄夁掱傊偺巗柉偺幚岠揑嶲壛傪妋曐偡傞偙偲偑昁梫偲偝傟傞偱偁傠偆丅
丂丂孻帠棫朄夁掱偵偍偗傞乽崘抦乿偲乽挳暦乿偺曐忈偲偄偆娤揰偐傜偼丄棫朄幰偼丄傑偢丄棫朄偺慜採偲側傞帠幚傪惓妋偵擣幆偡傞偨傔偵昁梫側忣曬傪廂廤偟丄偦傟傪峀偔巗柉偵採嫙偟側偗傟偽側傜側偄丅偙偙偱丄宱尡壢妛揑抦尒傪摜傑偊傞偙偲丄娭學偡傞幚柋壠丒愱栧壠偺堄尒傪揔愗偵挳庢偡傞偙偲偑梫惪偝傟傞丅偦偺偆偊偱丄孻帠棫朄夁掱傊偺巗柉偺幚岠揑嶲壛傪妋曐偡傞偨傔偵丄奐偐傟偨帺桼側摙榑偺応偲婡夛傪梡堄偡傞昁梫偑偁傞丅偙傟偼丄慜採偲側傞帠幚擣幆傪怺傔丄偦傟傪峀偔嫟桳偟丄壢妛揑丒棟惈揑懺搙偺壓偱丄孻帠棫朄偺偁傝曽偵偮偄偰帺桼偐偮恀潟偵摙媍偡傞偲偄偆偙偲偱偁偭偰丄偁傝偺傑傑偺乽崙柉偺婜懸乿偵抁棈揑偵墳摎偡傞偲偄偆偙偲傪堄枴偡傞傕偺偱側偄偙偲偼丄傕偪傠傫偱偁傞丅
3丂丂孻帠棫朄夁掱偺揔惓庤懕偵偮偄偰丄偦偺寷朄婯掕忋偺崻嫆偼偳偆偐丅寷朄嶰堦忦偼丄揔惓側孻帠幚懱朄丒庤懕朄偵傛傞孻敱偺幚尰傪梫媮偟偰偄傞偑丄偙偺栚揑偺壓偱丄孻帠棫朄偑寷朄偺庯巪丒惛恄偵傛傝揔崌偡傞傛偆側傕偺偱偁傞偙偲傪妋曐偡傞偨傔偵丄孻帠棫朄夁掱偵偮偄偰傕揔惓庤懕傪梫媮偟偰偄傞丄偲棟夝偡傞偙偲偑偱偒傞偱偁傠偆丅
丂丂傑偨丄寷朄屲幍忦堦崁偼丄乽椉媍堾偺夛媍偼丄偙傟傪岞奐偡傞乿偲掕傔偰偄傞丅乽媍夛偱偺帺桼側摙榑偑岞奐偝傟丄昞尰偺帺桼偺曐忈偺傕偲偱丄崙柉偺斸敾偵偝傜偝傟傞偙偲偵傛偭偰丄懡尦揑側棙奞偲壙抣傪斀塮偟偨怰媍偑壜擻偲側傝丄偦偺偙偲偵傛偭偰丄偦偺偲偒偳偒偺媍夛彮悢攈(栰搣)傕丄偦偺帪揰偱偺昞寛偱偼攕傟偰傕丄崙夛怰媍偺応偱丄偝傑偞傑側憟揰傪採婲偡傞偙偲傪捠偠偰丄師偺慖嫇偺婡夛偵丄桳尃幰偺巟帩傪摼傞偙偲傪婜懸偱偒傞丄偲偄偆偲偙傠偵丄尰戙媍夛惂柉庡庡媊偺恾幃偑惉傝棫偮乿偺偱偁傝丄偙偺堄枴偵偍偄偰丄乽崱擔偺媍夛惂柉庡庡媊偺崪奿傪側偡傕偺乿偱偁傞丄偲偝傟偰偄傞(43)丅
丂丂偙偺夛媍偺岞奐偺堄媊偵偮偄偰丄孻帠棫朄夁掱偺揔惓庤懕偲偄偆帇揰偐傜偼丄揔惓庤懕偵揔偭偨棫朄夁掱偑幚尰偡傞偙偲傪丄夛媍偺岞奐傪捠偠偰丄巗柉偺娔帇偲斸敾偵傛偭偰曐忈偟偰偄傞丄偲棟夝偡傞偙偲偑偱偒傞丅嵸敾偺岞奐偑丄孻帠庤懕偺揔惓庤懕偺杮幙揑梫慺偱偁傞偺偲摨偠傛偆偵丄夛媍偺岞奐偼丄孻帠棫朄夁掱偺揔惓庤懕偺杮幙揑梫慺偲偟偰埵抲偯偗傜傟傞丅
屲丂丂寢丂丂丂丂丂丂岅
丂丂偐偮偰乽朄夝庍榑憟乿偵偍偄偰丄棃惒嶰榊偼丄朄夝庍偺杮幙偑壙抣敾抐偱偁偭偰丄夝庍幰偼帺屓偺朄夝庍偵偮偄偰惌帯揑愑擟傪柶傟偊側偄偙偲傪榑偠偨(44)丅懞堜晀朚偼丄搻挳朄偺惂掕傪傔偖偭偰丄乽朄棩妛幰偑丄帪偺巟攝揑側惌帯尃椡偲丄偦傟偺悇恑偡傞惌嶔偵懳偡傞斸敾揑惛恄傪幐偄丄傓偟傠偦偺惌嶔傪幚尰偡傞愊嬌揑栶妱傪壥偨偡偲偒丄妛栤尋媶偵偲偭偰廳梫側壙抣偱偁傞惌帯偐傜偺帺桼傪傒偢偐傜幪偰嫀傞偙偲偵側傞丅乧乧朄棩偺惈奿傪曄偊丄恖乆偺婎杮揑恖尃偵懡戝側傞怤奞揑塭嬁傪梌偊傞偲偄偆偙偲偵側傞偲丄扨偵妛幰屄恖偺栤戣偱偼嵪傑偝傟側偄丅亀偁側偨偼偦傟偑彽棃偡傞寢壥偵懳偟偰丄惌帯揑愑擟傪偳偆偲傝傑偡偐亁偲栤偄妡偗傜傟傞偙偲偵側傞丅亀巹偼丄惌帯壠偱偼側偄亁偲偄偆摎偊偱偼摝偘傜傟側偄乿偲榑偠偰偄傞(45)丅
丂丂棫朄幰偺惌帯揑愑擟偲偼丄偁傝偺傑傑偺乽崙柉偺婜懸乿偺抁棈揑偵墳摎偡傞偙偲偱偼側偄丅棫朄幰偼丄寷朄偺梫惪傪枮偨偡偙偲偼傕偪傠傫丄寷朄偺庯巪丒惛恄偵傛傝揔崌偡傞傛偆側孻帠棫朄傪峴偆偲偄偆惌帯揑愑擟傪晧偭偰偄傞(46)丅偙偺惌帯揑愑擟傪壥偨偡偨傔偵偼丄宱尡壢妛揑尋媶偺抦尒傪摜傑偊偨惓妋側帠幚擣幆偵婎偯偒丄巗柉偵奐偐傟偨帺桼側摙榑傪宱偰丄壢妛揑丒棟惈揑懺搙偺壓偱孻帠棫朄傪峴傢側偗傟偽側傜側偄丅恖尃偺嵟戝尷偺懜廳偲偄偆寷朄尨懃偺壓丄斊嵾梷巭岠壥偑憡摉掱搙偵傑偱妋幚側傕偺偲偟偰擣傔傜傟側偄偵傕偐偐傢傜偢丄傛傝尩偟偄孻敱傪掕傔傞偙偲偼丄寷朄偺庯巪丒惛恄偵斀偡傞傕偺偱偁傞丅乽崙柉偺婜懸乿傊偺墳摎偱偁傞偲偺棟桼偵傛偭偰惓摉壔偝傟傞偙偲偼側偄丅棫朄幰偑偙偺傛偆側堄枴偺惌帯揑愑擟傪壥偨偝側偄偲偒丄乽巹偼朄棩壠偱偼側偄丅崙柉偐傜慖嫇偝傟偨惌帯壠偱偁傞乿偲偄偆尵偄栿偼捠傜側偄偺偱偁傞丅
(1)丂丂尨揷朙乽斊嵾尋媶摦岦傾儊儕僇斊嵾妛夛偵偍偗傞亀宲懕偲曄壔亁乿斊嵾幮夛妛尋媶擇屲崋(擇乑乑乑擭)丅傑偨丄捗晉岹乽EBP(僄價僨儞僗丒儀僀僗僩丒僾儔僋僥傿僗)傊偺摴亅崻嫆偵婎偯偄偨幚柋傪峴偆偨傔偵亅乿斊嵾偲旕峴堦擇巐崋(擇乑乑乑擭)偼丄嵞斊棪掅壓偺幚徹揑崻嫆偵婎偯偄偨張嬾幚柋傪峔抸偡傞傋偒偙偲傪嬶懱揑偵採婲偟偰偄傞丅
(2)丂丂孻朄棟榑尋媶夛亀尰戙孻朄妛尨榑丒憤榑(戞嶰斉)亁(嶰徣摪丒堦嬨嬨榋擭)擇暸埲壓丅
(3)丂丂抍摗廳岝亖懞堜晀朚亖惸摗朙帯傎偐亀乽夵惓乿彮擭朄斸敾亁(擔杮昡榑幮丒擇乑乑乑擭)嶲徠丅
(4)丂丂栰揷惓恖乽嵟嬤偺彮擭旕峴(帠審)偺摿挜乿朄棩帪曬幍乑姫敧崋(堦嬨嬨敧擭)丄愇捤怢堦乽彮擭旕峴亀怺崗壔亁偺恄榖乿棿扟朄妛嶰擇姫巐崋(擇乑乑乑擭)丄摨乽彮擭斊嵾偺嫢埆壔偲孻敱偺梷巭岠壥乿抍摗廳岝傎偐丒拹(3)彂側偳丅側偍丄William
J. Chambliss, Power, Politics, 仌 Crime 50-54 (2001) 偼丄傾儊儕僇偵偍偄偰傕丄塃攈斊嵾幮夛妛幰傗惌晎婡娭曬崘彂側偳偺堦晹偑丄壢妛揑懨摉惈傪寚偔摑寁揑崻嫆偵婎偯偄偰丄嬤偄彨棃偵偍偗傞彮擭偺朶椡斊嵾偺寑揑憹壛傪梊應偟丄偦傟偵傛偭偰岞廜偺乽斊嵾晄埨乿傪慀傝丄尩敱惌嶔傊偲曽岦偯偗偰偄傞忬嫷偑偁傞偙偲傪斸敾揑偵専摙偟偰偄傞丅
(5)丂丂妺栰恞擵乽尩敱巜岦偺彮擭朄夵惓埬丒斸敾乿斊嵾偲孻敱堦巐崋榋榋暸埲壓丅
(6)丂丂撉攧怴暦偑堦嬨嬨幍擭幍寧偵幚巤偟偨悽榑挷嵏偵傛傞偲丄乽崱屻丄嫢埆側彮擭斊嵾偑憹偊偰偄偔偺偱偼側偄偐偲偄偆晄埨乿傪乽偍偍偄偵姶偠偰偄傞乿偲偺夞摎偑榋擇Z亾丄乽懡彮偼姶偠偰偄傞乿偑擇嬨軄搨艂爞鑱A彮擭朄偵偮偄偰丄乽斊嵾杊巭偺棫応偐傜丄嫢埆斊嵾偵尷偭偰偼丄堦榋嵨枹枮偺彮擭偱傕孻帠敱傪揔梡偱偒傞傛偆偵丄偙偺朄棩傪夵惓偡傋偒乿偐偲偺幙栤偵懳偟偰丄幍榋O亾偑乽夵惓偡傋偒偩乿偲夞摎偟丄乽偦偆偼巚傢側偄乿偼敧l亾偱偁偭偨(撉攧怴暦堦嬨嬨幍擭幍寧嶰堦擔)丅堦嬨嬨敧擭擇寧偺撉攧怴暦悽榑挷嵏偵偍偄偰傕丄偙傟偲傎傏摨條偺寢壥偑帵偝傟偨丅偨偩偟丄偄偢傟偺悽榑挷嵏偵偮偄偰傕丄乽彮擭帠審偑嫢埆壔偟偰偄傑偡偑乿偲偺堦愡傪暿偺幙栤拞偵憓擖偡傞側偳丄挷嵏曽朄忋偺懨摉惈偵媈傢偟偝偑巆傞丅憤棟晎偑堦嬨敧敧擭巐寧偵峴偭偨悽榑挷嵏乽惵彮擭偺旕峴摍栤戣峴摦偵娭偡傞悽榑挷嵏乿偵傛傟偽丄乽嵟嬤丄惵彮擭偵傛傞旕峴摍偑栤戣偲側偭偰偄傑偡偑丄偁側偨偼丄幚姶偲偟偰丄偙偆偟偨惵彮擭偵傛傞廳戝側帠審側偳偑埲慜偵斾傋憹偊偰偄傞偲巚偄傑偡偐丅偦傟偲傕偦偆偼巚偄傑偣傫偐乿偲偺幙栤偵懳偟偰丄乽偐側傝憹偊偰偄傞乿偲偺夞摎偑丄擇乑嵨枹枮偱屲幍Z亾丄擇乑嵨埲忋偱榋嬨銇搧A乽偁傞掱搙憹偊偰偄傞乿偲偺夞摎偑丄摨偠偔嶰屲銇搧A擇巐l亾偵偺傏偭偨(http丗//www.sorifu.go.jp/survey/seishonen.html)丅幙栤偵乽嵟嬤丄惵彮擭偵傛傞旕峴摍偑栤戣偲側偭偰偄傑偡偑乿偲偺堦愡傪擖傟偨偙偲偼晄揔摉偱偁傠偆丅
(7)丂丂妺栰恞擵乽巰孻惂搙偲斊嵾梷巭岠壥乿嵅攲愮樋亖抍摗廳岝亖暯応埨帯曇亀巰孻攑巭傪媮傔傞亁(擔杮昡榑幮丒堦嬨嬨巐擭)嶲徠丅偙偺榑暥偑丄乽枹専徹偺壖愢側偄偟庡娤揑怣擮偵偡偓側偄斊嵾梷巭岠壥偵傛傝巰孻傪惓摉壔偡傞偙偲偼丄惗柦偺懜廳偲偄偆尰戙幮夛偺嵟崅壙抣偵偁傑傝偵傕斀偟丄崌棟揑偱側偄丅斊嵾梷巭岠壥偑妋偨傞壢妛揑徹嫆偵傛偭偰帵偝傟傞偙偲偑丄偦傟偵傛偭偰巰孻傪惓摉壔偡傞偨傔偺昁梫忦審偱偁傞乿偲偟偨偙偲偵偮偄偰丄強堦旻乽斊嵾偺梷巭偲巰孻乿朄棩帪曬榋嬨姫堦乑崋(堦嬨嬨幍擭)偼丄幮夛壢妛揑帠幚偵偮偄偰偺幚徹偺惈幙偲偄偆帇揰偐傜斸敾偡傞丅
(8)丂丂悪尨懽梇乽恖恎偺帺桼乿埌曈怣婌曇亀寷朄(4)丒恖尃(2)亁(桳斻妕丒堦嬨敧堦擭)堦堦屲偐傜堦堦榋暸偼丄乽恖尃曐忈傪崙惃偺栚揑偲偟偰宖偘偐偮岞尃椡傪偦偺庤抜偲婯掕偡傞巗柉寷朄(擔杮崙寷朄)乿偵偍偄偰偼丄乽屄恖庡媊偺娤揰偐傜恖尃偺嵟戝尷偺懜廳偑媊柋偯偗傜傟傞偐傜丄孻敱尃偺敪摦傕懠偺崙柉偵恖尃偺暯摍偺嫕庴傪曐忈偡傞偆偊偱昁梫傗傓傪偊側偄応崌偵偮偄偰擣傔傜傟傞偙偲偵側傞偼偢偱偁傞乿偲榑偠偰偄傞丅傑偨丄摨榑暥擇屲榋暸偼丄偙偺傛偆側堄枴偺乽帺桼崙壠揑岞嫟偺暉巸(撪嵼揑惂栺)乿偲偟偰偺孻敱尃偺幚懱揑僨儏乕丒僾儘僙僗偺梫惪偲偟偰丄乽恖尃偵偮偄偰偺昁梫嵟彫尷偺婯惂尨懃偐傜偡傟偽丄孻敱尃偺敪摦偼丄堦掕偺峴堊傪嬛巭偡傞偙偲偵偮偄偰傕丄傑偨嬛巭堘斀偵懳偟偰惂嵸傪壽偡偙偲偵偍偄偰傕丄昁梫嵟彫尷偺傕偺偱側偗傟偽側傜側偄乿偲榑偠丄嵾孻嬒峵偺尨懃丄乽傛傝惂尷揑偱側偄懠偺慖傃偆傞庤抜乿尨懃(LRA尨懃)偵尵媦偟偰偄傞丅
(9)丂丂悪尨懽梇丒拹(8)榑暥擇幍乑暸偼丄乽嶰榋忦偺亀巆媠側孻敱亁偺嬛巭偑嶰堦忦偺梫媮偡傞幚懱揑揔惓偺堦撪梕傪側偟丄偐偮嶰堦忦偺幚懱揑揔惓帺懱偑堦嶰忦偺恖尃偺嵟戝尷偺懜廳亅恖尃婯惂偺昁梫嵟彫尷亅偺尨懃偵婎慴偯偗傜傟偰偄傞偲偙傠偐傜偡傟偽丄嶰榋忦偺巆媠孻偑堦嶰忦偍傛傃嶰堦忦偵傛偭偰婯掕偝傟傞孻敱栚揑傪払惉偡傞偆偊偱晄昁梫夁戝側孻敱傪堄枴偡傞偺偼摉慠偺偙偲偱偁傠偆丅尨懃偲偟偰丄懠偺恖尃偵懳偡傞怤奞傪慾巭偡傞偨傔偵晄昁梫側夁戝側孻敱偺偙偲偱偁傞乿偲榑偠偰偄傞丅偦偺偆偊偱丄摨榑暥擇幍擇偐傜擇幍嶰暸偼丄乽巰孻偑巆媠偐斲偐偑晄柧妋側崙柉姶忣偵傛偭偰憡懳揑偵寛掕偝傟傞偲偡傞偙偲偵傕栤戣偑偁傞丅偡偱偵巜揈偟偰偍偄偨傛偆側巆媠孻偺棟夝偺巇曽偐傜偡傟偽丄巰孻偑巆媠偐斲偐偼丄巰孻偺埿奷椡丒攔奞椡傪傕偭偰偟側偗傟偽丄恖尃偵懳偡傞怤奞傪怘偄巭傔傜傟側偄偐偳偆偐偵傛偭偰偒傑傞丅攔奞椡偺揰偵偍偄偰偼丄柍婜孻偑廫暘偵戙懼惈傪傕偭偰偄傞偙偲偐傜丄尰幚偵偼斊嵾梷巭偺埿奷椡偑柍婜孻偱偼晄廫暘偐斲偐偵傛偭偰寛傑傞偙偲偵側傞丅偙偺揰偱柍婜孻偑巰孻偵戙懼偟偆傞偺偱偁傟偽丄巰孻偼尰忬偵偍偄偰傕巆媠孻偲側傞乿偲榑偠偰偄傞丅
(10)丂丂堦嬨幍敧擭偺僯儏乕丒儓乕僋廈彮擭斊嵾幰朄偵偮偄偰丄Singer 仌 McDowall, Criminalizing Delinquency丗The
Deterrent Effects of New York Juvenile Offender Law, 22 Law and Society
Review 521 (1988). 偙傟偵偮偄偰丄妺栰恞擵乽僯儏乕丒儓乕僋彮擭斊嵾幰朄偺斊嵾梷巭岠壥亅嫮埑揑側彮擭斊嵾摑惂棫朄偼惉岟偟偨偺偐?亅乿朄宱榑廤榋嬨亖幍乑崋(堦嬨嬨嶰擭)嶲徠丅堦嬨敧堦擭偺傾僀僟儂廈朄偵偮偄偰丄Jensen
仌 Metsger, A Test of Legislative Waiver on Violent Juvenile Crime, 40
Crime and Delinquency 96 (1994). 彮擭斊嵾傊偺孻敱揔梡偑桳偡傞堦斒梷巭岠壥偍傛傃摿暿梷巭岠壥偵娭偡傞嵟怴偺儗價儏乕偲偟偰丄Bishop
仌 Frazier, Consequences of Transfer, in Jeffry Fagan 仌 Franklin E. Zimring,
The Changing Borders of Juvenile Justice丗Transfer of Adolescents to
the Criminal Court 227 (2000).
(11)丂丂妺栰恞擵乽傾儊儕僇/彮擭巌朄偺楌巎偲夵妚偺摦岦乿郪搊弐梇曇挊亀悽奅彅崙偺彮擭朄惂亁(惉暥摪丒堦嬨嬨嶰擭)丄摨乽傾儊儕僇彮擭巌朄夵妚偲幮夛暅婣棟擮乿朄惌尋媶堦姫堦崋(堦嬨嬨榋擭)丄摨乽彮擭巌朄偵偍偗傞亀曐岇亁棟擮偺嵞峔抸偵岦偗偰亅傾儊儕僇彮擭巌朄夵妚偺嫵孭偐傜亅乿孻朄嶨帍嶰榋姫嶰崋(堦嬨嬨幍擭)嶲徠丅傎偐偵丄嵅攲恗巙乽傾儊儕僇偵偍偗傞彮擭巌朄惂搙偺摦岦乿僕儏儕僗僩堦乑敧幍崋(堦嬨嬨榋擭)丄惸摗朙帯乽傾儊儕僇偺彮擭巌朄乿婫姧孻帠曎岇堦乑崋(堦嬨嬨幍擭)側偳嶲徠丅
(12)丂丂孻帠張暘揔梡傪奼戝偝偣傞孹岦偼丄堦嬨嬨乑擭戙偵擖偭偰傕丄宲懕偟偰偄傞丅Howard N. Snyder 仌 Melissa
Shickmund, Juvenile Offenders and Victims丗1999 National Report, National
Center for Juvenile Justice 103 (1999) 偵傛傟偽丄堦嬨嬨擇擭偐傜堦嬨嬨幍擭偺偁偄偩偵丄孻帠張暘揔梡奼戝偺曽岦傊偺朄夵惓傪峴偭偨廈偼丄僐儘儞價傾摿暿嬫傪娷傔偰巐屲廈偵傕偺傏傝丄偙偺傛偆側棫朄傪峴傢側偐偭偨偺偼丄榋廈偵夁偓側偄丅傑偨丄傑偡傑偡懡偔偺廈偑丄朄棩偵傛傝堦掕斊嵾偵偮偄偰孻帠嵸敾強偺杮棃揑娗妽壓偵抲偔偙偲傪掕傔傞偲偄偆曽朄傪嵦梡偡傞傛偆偵側偭偰偄傞丅
(13)丂丂偨偲偊偽丄崱夞偺乽彮擭朄夵惓乿朄埬傪傔偖傞廜媍堾朄柋埾堳夛擇乑乑乑擭堦乑寧堦乑擔偵偍偗傞墶撪惓柧埾堳(帺桼柉庡搣)偺敪尵(戞昐屲廫夞崙夛廜媍堾朄柋埾堳夛媍榐戞擇崋)丅傾儊儕僇彮擭旕峴偵娭偡傞庡梫側寈嶡摑寁偵偮偄偰偼丄埨搶旤榓巕亖徏揷旤抭巕亖棫扟棽巌乽傾儊儕僇偵偍偗傞彮擭旕峴偺摦岦偲彮擭巌朄惂搙乿朄柋憤崌尋媶強尋媶晹曬崘堦嬨嬨嬨擭屲崋傪嶲徠丅杮峞偺僌儔僼(G1丄G2丄G4)偼丄偙傟偵帵偝傟偨悢抣傪婎偵嶌惉偟偨丅傑偨丄巌朄徣偺彮擭巌朄旕峴杊巭嬊偺僀儞僞乕僱僢僩丒儂乕儉儁乕僕(http://ojjdp.ncjrs.org/ojstatbb/index.html)偐傜丄梕堈偵傾僋僙僗偡傞偙偲偑偱偒傞丅杮峞偺僌儔僼G3偼偙傟偵傛傞丅
(14)丂丂Blumstein, Young Violence, Guns, and the Illicit亅Drug Industry,
86 Journal of Criminal Law and Criminology 10 (1995)丟Blumstein 仌 Cork,
Gun Availavility to Youth Gun Violence, 59 Law and Contemporary Problem
5 (1996). 桳椡側彮擭嵸敾強攑巭榑幰偱傕偁傞僼僃儖僪偼丄乽彮擭斊嵾偵捈愙娭楢偟偰偄傞傕偺偼丄僐儈儏僯僥傿偵偍偗傞惗妶偺幙偱偁偭偰丄惌晎偺梌偊傞張敱偺掱搙偱偼側偄丅乧乧壠掚丄廆嫵丄曐寬娗棟丄嫵堢丄廧戭丄屬梡丄僐儈儏僯僥傿偺壙抣丄偦偟偰斊嵾偑憡屳偵娭楢偟偰偄傞偺偱偁傞偐傜丄彮擭旕峴偵恀寱偵懳張偡傞偨傔偵偼丄僐儈儏僯僥傿偺偁傜備傞峔惉晹暘偑愊嬌揑栶妱傪壥偨偝側偗傟偽側傜側偄偺偱偁傞乿偲偄偆帺傜偑埾堳挿傪柋傔偨儈僱僜僞廈彮擭巌朄摿暿埾堳夛偺曬崘彂偺堦愡傪堷梡偟偨偆偊偱丄乽偄偐偵巚椂怺偄朄夵惓偱偁偭偰傕丄彮擭巌朄丒孻帠巌朄偵娭偡傞棫朄偑彮擭偲惉恖偲偺嫬奅慄傪曄峏偟偨偲偙傠偱丄僐儈儏僯僥傿偵惗偠傞斊嵾検傪尭彮偝偣傞偙偲傕丄斊嵾峴堊幰偺嵞斊壜擻惈傪掅尭偝偣傞偙偲傕丄堦斒巗柉偺埨慡傪憹戝偝偣傞偙偲傕偱偒傞偼偢偑側偄乿偲弎傋偰偄傞(Feld,
Violent Youth and Public Policy, 79 Minnesota Law Review 965, 1128 [1995])丅
(15)丂丂Franklin E. Zimring, American Youth Violence 128-129 (1998) 偼丄師偺傛偆偵榑偠偰偄傞丅偡側傢偪丄彮擭偺朶椡斊嵾傊偺惌帯揑暜寖偵嬱傜傟偰恑傔傜傟偰偒偨尩敱棫朄偼丄尰嵼偺堏憲惂搙傪側偵偐嬶懱揑偵夵慞偡傞偨傔偲偄偆傢偗偱偼側偔丄彮擭偺朶椡斊嵾棪偺崅偝偼乽尰峴惌嶔偵側偵偐栤戣偑偁傞乿偙偲傪帵偡偵廫暘側徹嫆偱偁傝丄乽尩敱壔偙偦偑枩擻偺夝寛嶔偱偁傞乿偲偄偆抁棈揑側峫偊偐傜丄堏憲惂搙傪夵惓偡傞棫朄偑懕偄偨丅尰峴惂搙偺塣梡幚懺偺昡壙偐傜夵慞偡傋偒栤戣傪柧傜偐偵偡傞偺偱偼側偔丄乽彮擭偺朶椡斊嵾敪惗棪偺崅偝偼孻敱偺尩奿偝晄懌偵尨場偑偁傞偺偱偁傝丄偟偨偑偭偰丄朶椡斊嵾偵偼孻帠張暘傪揔梡偡傞曽偑摉慠偵揔偟偰偄傞乿偲偄偆抁棈揑側峫偊偵婎偯偄偰惂搙夵妚傪峴偭偨偲偟偰傕丄偦傟偵偼昁慠揑偵戝偒側尷奅偑偲傕側偄丄幚柋偺夵慞偵偼寛偟偰婑梌偟側偄丅廫暘偐偮惓妋側忣曬偵婎偯偐側偄棫朄偼丄棫朄夁掱偺偁傝曽偲偟偰湏堄偵棳傟丄棟惈揑側傕偺偱側偔側傞婋尟傪偲傕側偆偟丄傑偨丄幚柋偺尰忬傗栤戣揰傪摜傑偊側偄棫朄偼丄寢嬊偼堄恾偟偨幚柋偺曄壔傪惗偠偝偣傞偙偲傕側偔丄朄偺暥柺偲幚柋偺槰棧傪峀偘傞偙偲偵側傞丅偙傟偵偮偄偰丄妺栰恞擵乽(徯夘)彮擭偺朶椡斊嵾傪傔偖傞尩敱惌嶔偵懳偡傞曪妵揑斸敾亅Franklin
E. Zimring, American Youth Violence, Oxford University Press, 1998亅乿傾儊儕僇朄擇乑乑乑擭擇崋嶲徠丅
(16)丂丂Blumstein, Disaggregating the Violence Trends, in Alfred Blumstein
and Joel Wallman, The Crime Drop in America 39-40 (2000).
(17)丂丂慜揷夒塸乽彮擭嫢埆斊嵾丄怺崗偝擣幆傪乿擔杮宱嵪怴暦擇乑乑乑擭嬨寧嬨擔丅杮峞枛偺晅婰仏仏仏傪嶲徠丅
(18)丂丂棟榑揑偵傕丄彮擭朄偵婎偯偔曐岇張暘偑丄彮擭偺帺桼傪嫮惂揑偵攳扗偡傞偲偄偆揰偵偍偄偰晄棙塿張暘偱偁傝丄尰峴彮擭朄忋傕丄寛掕帪堦榋嵨埲忋偺彮擭偵偮偄偰堦掕偺応崌偵偼孻帠張暘偺揔梡偑擣傔傜傟偰偄傞偙偲偐傜偡傞偲丄孻帠張暘偺揔梡傪奼戝偡傞偙偲偵傛傝丄婯斖堄幆偺妋擣丒嫮壔偺婡擻偑偳傟傎偳崅傑傞偙偲偵側傞偺偐丄昁偢偟傕柧傜偐偱偼側偄傛偆偵巚傢傟傞丅
(19)丂丂亀斊嵾敀彂(暯惉堦擇擭斉)亁榋嶰暸丄堦嬨敧偐傜擇乑乑暸丅
(20)丂丂堦嬨敧幍擭僼儘儕僟廈朄偺壓偱偺抁婜娫偺嵞斊棪偵娭偡傞 Bishop et al., The Transfer of Juveniles
to Criminal Court丗Does It Make a Difference?, 42 Crime 仌 Delinquency
171 (1996)丄摨偠偔傛傝挿婜娫偺嵞斊棪偵娭偡傞 Winner et al., The Transfer of Juveniles
to Criminal Court丗Reexamiing Recidivism Over the Long Term, 43 Crime
仌 Delinquency 548 (1997)丅Fagan, Separating the Men from the Boys, in
James C. Howell et al. (ed.), A Sourcebook丗Serious, Violent and Chronic
Juvenile Offenders (1995) 238 偼丄僯儏乕丒儓乕僋廈偺孻帠嵸敾強偵偍偄偰帠審傪埖傢傟偨彮擭偲丄僯儏乕丒僕儍乕僕廈偺彮擭嵸敾強偵偍偄偰帠審傪埖傢傟偨彮擭偲傪斾妑偟偨偲偙傠丄惂嵸偺妋幚惈丒尩奿惈偵偍偄偰孻帠嵸敾強偺応崌偺曽偑崅偄傢偗偱偼側偔丄嵞斊棪偼孻帠嵸敾強偺応崌偺曽偑崅偄孹岦偵偁傞偙偲傪柧傜偐偵偟偨丅
(21)丂丂杮峞丒拹(6)嶲徠丅
(22)丂丂妺栰恞擵乽旕峴帠幚擣掕傪傔偖傞巌朄偲暉巸乿孻朄嶨帍嶰嬨姫堦崋(堦嬨嬨嬨擭)嶲徠丅
(23)丂丂妺栰恞擵丒拹(5)榑暥榋擇偐傜榋嶰暸丅
(24)丂丂擇乑乑乑擭嬨寧敧擔嫟摨捠怣幮攝怣僯儏乕僗偵傛傟偽丄乽亀旕峴偵憱傞擭彮偺巕嫙偼憡摉備偑傫偱偄偰丄峏惗偝偣傞偵偼丄孻敱傪壢偡偲偟偰傕彮擭堾偱懕偗偰偄傞傛偆側屄恖偵崌偭偨張嬾偑昁梫偩亁丅曐壀嫽帯朄憡偲彮擭堾偺嫵姱傜偺崸択夛偑敧擔丄朄柋徣撪偱奐偐傟丄嫵姱傜偐傜偼尩敱壔偵岦偐偆彮擭朄偺夵惓偵媈栤傪搳偘妡偗傞堄尒偑憡師偄偩丅嫵姱傜偼旕峴彮擭偺敧妱埲忋偑亀彮擭朄偑寉偄偲抦偭偰偄傞偐傜旕峴傪偟偨傢偗偱偼側偄亁偲摎偊偨傾儞働乕僩寢壥傪帵偟偨傎偐丄旕峴彮擭偲岦偒崌偭偨宱尡偐傜丄嵟嬤偺彮擭偺摿挜傗旕峴偺尨場側偳傕棪捈偵岅偭偨乿偲偄偆丅偙偺傛偆側彮擭堾朄柋嫵姱偨偪偺堄尒偑丄崱夞偺乽夵惓乿朄埬傪嶌惉偡傞偆偊偱惗偐偝傟偨偲偼偄偊側偄丅堜奯峃峅亖憪応桾擵亖嵅摗妛亖栰揷惓恖亖妺栰恞擵乽(嵗択夛)彮擭朄偺尩敱壔偑堄枴偡傞傕偺乿抍摗廳岝傎偐丒拹(3)彂榋堦暸(嵅摗妛敪尵)偼丄彮擭堾嫵姱偑彮擭堾張嬾偺岠壥丄偙傟傑偱偺惉壥丄梊憐偝傟傞孻敱偺斲掕揑岠壥側偳偵偮偄偰丄巗柉偵岦偗偰丄帺桼偵敪尵偱偒傞傛偆曐忈偡傋偒偱偁傞偲偡傞丅
(25)丂丂帺桼柉庡搣惌柋挷嵏夛朄柋晹夛彮擭朄偵娭偡傞彫埾堳夛乽彮擭朄偵娭偡傞拞娫庢傝傑偲傔乿(堦嬨嬨敧擭巐寧)丄帺桼柉庡搣惌柋挷嵏夛朄柋晹夛彮擭朄偵娭偡傞彫埾堳夛乽曬崘彂乿(堦嬨嬨嬨擭堦寧)擔杮曎岇巑楢崌夛曇亀捛偄偮傔傜傟傞巕偳傕偨偪亁(尰戙恖暥幮丒堦嬨嬨嬨擭)強廂丅挬擔怴暦堦嬨嬨敧擭堦擇寧擇擇擔偵傛傟偽丄帺柉搣彮擭朄彫埾堳夛偑堦嬨嬨敧擭乽廫寧埲崀偵僸傾儕儞僌偟偨愱栧壠傜偺堄尒偱偼丄幚嵺偵廫巐丄屲嵨偵孻帠敱傪壢偟偨応崌偺尰応偺懳墳傗丄嵞旕峴杊巭岠壥傊偺媈栤傕弌偰偄偨丅偩偑丄彫埾偱偺媍榑偺拞怱偼丄偁偔傑偱亀梷巭椡亁丅幚嵺偵廫巐嵨偐傜彮擭孻柋強偵擖傟偨応崌偺懳墳偵偮偄偰偺媗傔偺媍榑偼側偄傑傑偩偭偨乿偲偄偆丅
(26)丂丂Zimring, supra note 15, at 129 偼丄傾儊儕僇偺尩敱棫朄偑堦斒偵丄廫暘側忣曬偵傛傞惓妋側帠幚擣幆偵婎偯偔傕偺偱偼側偄揰偵偍偄偰丄棫朄夁掱偵偍偗傞寚娮傪桳偡傞偲巜揈偟偰偄傞丅傾儊儕僇偺尩敱棫朄偲乽惌帯栤戣壔乿偵偮偄偰丄Stuart
A. Schneingold, The Politics of Street Crime丗Criminal Process and Cultural
Obsession (1991) 嶲徠丅傾儊儕僇揑側屄恖庡媊丄帺屓愑擟側偳丄斊嵾摑惂傪傔偖傞暥壔揑梫場傪傕廳帇偟偰偄傞丅傑偨丄杮峞丒拹(36)嶲徠丅
(27)丂丂Edmund F. McGarrell, Juvenile Correctional Reform丗Two Decades
of Policy and Procedural Change 105-115 (1988). 妺栰恞擵丒拹(10)榑暥嶲徠丅
(28)丂丂偨偲偊偽丄崱夞偺乽彮擭朄夵惓乿朄埬嶌惉丒採弌偵偍偄偰庡摫揑栶妱傪壥偨偟偨帺桼柉庡搣丒悪塝惓寬廜媍堾媍堳偼丄挬擔怴暦偺僀儞僞價儏乕偵懳偟偰丄乽慖嫇塣摦傪捠偠偰丄桳尃幰偼彮擭朄夵惓傪朷傫偱偄傞偙偲偑傛偔暘偐偭偨丅朄惂怰偵偐偗傞偲丄揘妛揑側媍榑偐傜巒傔傞偙偲偵側傝丄壗擭傕偐偐傞丅孻帠張暘懳徾擭楊偺堷偒壓偘偼丄愱栧壠傛傝傕惌帯壠偑寛傔傞傋偒栤戣丅偩偐傜丄媍堳棫朄偵偟偨乿偲摎偊偰偄傞丅
(29)丂丂懞堜晀朚乽慻怐揑斊嵾懳嶔朄偺攚屻偵偁傞傕偺乿朄棩帪曬幍堦姫堦擇崋(堦嬨嬨嬨擭)丅傑偨丄彫揷拞汔庽乽尰戙帯埨惌嶔偲搻挳朄(忋丒壓)乿朄棩帪曬幍堦姫堦擇崋丒幍堦姫堦嶰崋(堦嬨嬨嬨擭)傕嶲徠丅
(30)丂丂乽巗柉揑埨慡乿偺梫媮偵墳摎偡傞宍偱幚懱揑丒庤懕揑偵斊嵾摑惂傪嫮壔偟傛偆偲偡傞摦偒偑丄堦嬨嬨乑擭戙枛偵偼丄慻怐斊嵾懳嶔朄丄搻挳朄側偳偺惂掕偲偟偰嬶懱壔偟偨丅彫揷拞汔庽亀恖恎偺帠桼偺懚嵼峔憿亁(怣嶳幮丒堦嬨嬨嬨擭)堦嶰暸埲壓偼丄堦嬨嬨乑擭戙埲崀丄婯惂娚榓丄巗応尨棟丄帺屓愑擟側偳傪宖偘傞堦楢偺怴帺桼庡媊揑夵妚偵傛偭偰慡柺揑側崙壠揑丒幮夛揑嵞曇偑恑傔傜傟傞側偐偱丄乽寈嶡偵傛傞巗柉巟攝偺恑峴傪拞幉偲偡傞亀尰戙揑亁帯埨朄乿偑丄乽巗柉偺埨慡梫媮偵棫媟偡傞媅帡揑亀巗柉庡媊亁揑側僀僨僆儘僊乕揑奜憰傪偲傝乿偮偮揥奐偝傟偰偄傞偙偲傪丄恖尃曐忈偺嫮壔偲乽巗柉庡媊乿揑帯埨朄偺杮幙揑柕弬偲偄偆帇揰偐傜丄斸敾揑偵暘愅偟偰偄傞丅
(31)丂丂惣尨弔晇亀孻朄偺崻掙偵偁傞傕偺亁(堦棻幮丒堦嬨幍嬨擭)偼丄孻朄偺崻掙偵偼乽崙柉偺梸媮乿偑偁傞偲偡傞丅偨偩偟丄偙偺乽崙柉偺梸媮乿偼丄偁傝偺傑傑偺傕偺偱偼側偔丄乽傕偟暯嬒揑崙柉偑旕峴偺忬嫷偲偦傟偵懳偡傞孻朄惂掕偺堄媊偵偮偄偰惓妋側擣幆傪帩偭偨側傜偽書偄偨偱偁傠偆梸媮乿傪堄枴偡傞丄偲偡傞丅偙傟偵偮偄偰丄懞堜晀朚乽孻帠棫朄偺懨摉惈亅搻挳偺朄惂壔栤戣傪戣嵽偵偟偰亅乿亀惣尨弔晇愭惗屆婬廽夑榑暥廤丒戞巐姫亁(惉暥摪丒堦嬨嬨敧擭)嶰敧暸埲壓嶲徠丅
(32)丂丂儀僢僇儕乕傾(晽憗敧廫擇亖晽憗擇梩栿)亀斊嵾偲孻敱(夵斉)亁(娾攇彂揦丒堦嬨屲嬨擭)丅
(33)丂丂僼儔儞僗偺巰孻攑巭偵偍偗傞崙柉悽榑偲惌帯揑儕乕僟乕僔僢僾偲偺娭學偵偮偄偰丄埳摗岞梇亖栘壓惤曇亀偙偆偡傟偽偱偒傞巰孻攑巭亅僼儔儞僗偺嫵孭亅亁(僀儞僷僋僩弌斉夛丒堦嬨嬨擇擭)嶲徠丅
(34)丂丂戝掚奊棦乽彮擭帠審偲儅僗丒儊僨傿傾乿屻摗峅巕曇亀彮擭旕峴偲巕偳傕偨偪亁(柧愇彂朳丒堦嬨嬨嬨擭)偼丄儌儔儖丒僷僯僢僋偲偦傟偵懳偡傞儅僗丒儊僨傿傾曬摴偺塭嬁傪巜揈偟偰偄傞丅
(35)丂丂乽斊嵾晄埨乿偵偮偄偰丄Furstenburg, Public Reaction to Crime in the Street,
40 American Scholar 601 (1971)丟LaGrange, Ferraro and Spanicic, Perceived
Risk and Fear of Crime丗Role of Social and Physical Incivilities, 29
Journal of Research on Crime and Delinquency 311 (1992)丟Perkins 仌 Taylor,
Ecological Assessments of Community Disorder丗Their Relationships to
Fear of Crime and Theoretical Implications, 24 American Journal of Community
Psychology 601 (1996)丟McGarrell, Giacomazzi 仌 Thurman, Neighborhood
Disorder, Integration, and the Fear of Crime, 14 Justice Quarterly 479
(1997). 儌儔儖丒僷僯僢僋偵偮偄偰丄抾懞揟椙乽儌儔儖丒僷僯僢僋乿摗杮揘栫曇亀尰戙傾儊儕僇斊嵾妛帠揟亁(櫎憪彂朳丒堦嬨嬨堦擭)嶰嬨暸嶲徠丅
(36)丂丂儅僢僋僊儍儗儖偲僉儍僗僥儔乕僲偺堦楢偺尋媶偼丄嫮埑揑斊嵾摑惂朄偺惂掕偵偮偄偰暘愅偡傞偨傔偵丄乽懡尦揑僐儞僼儕僋僩儌僨儖乿傪採帵偟偰偄傞丅McGarrell
仌 Castellano, An Integrative Conflict Model of the Criminal Law Foundation
Process, 28 Journal of Research in Crime 仌 Delinquency 174 (1991)丟Castellano
仌 McGarrell, The Politics of Law and Order, 28 Journal of Research in
Crime 仌 Delinquency 304 (1991)丟McGarrell 仌 Castellano, Social Structure,
Crime and Politics, in William J. Chambliss 仌 Marjorie S. Zatz (eds.),
Making Law (1993). 偙傟偵偮偄偰丄妺栰恞擵丒拹(11)榑暥(孻朄嶨帍)嶰嬨暸埲壓嶲徠丅
(37)丂丂偨偲偊偽丄巌朄惂搙夵妚怰媍夛戞擇屲夞(擇乑乑乑擭幍寧堦堦擔)偵偍偗傞嶳杮埾堳(搶嫗揹椡暃幮挿)偺儕億乕僩偼丄乽惛枾巌朄乿偲偄傢傟傞尰忬傪婎杮揑偵峬掕偟丄偙傟傪曄妚偡傋偒偱側偄偲偄偆婎杮揑棫応偺偆偊偱丄乽僐儈儏僯僥傿乕偺夝懱丄宱嵪晄埨偝傜偵偼奜崙恖偺憹壛丄忣曬媄弍偺敪払側偳傪攚宨偵偟偨斊嵾偺嫢埆壔丄崙嵺壔丄慻怐壔丄崅搙忣曬壔摍乿偵懳墳偟偰丄乽幮夛拋彉偺堐帩乿偲偄偆乽崙柉偺婜懸乿偵墳偊傞偨傔丄怴偨側憑嵏曽朄丒岞敾庤懕(偍偲傝憑嵏丄巌朄庢堷丄孻帠柶愑側偳)丄徹恖曐岇偺嫮壔丄乽惓媊姶偺梙傜偓乿偺側偐偱崙柉偺乽堘榓姶乿傪夝徚偡傞傛偆側帠審偺廳戝惈偵懳墳偟偨揔惓側張暘(廔恎孻偺摫擖丄彮擭朄偺尒捈偟)側偳傪採婲偡傞傕偺偱偁偭偨丅偙傟偵懳偟偰丄摨擔偺崅栘埾堳(楢崌暃埾堳挿)偺儕億乕僩偼丄乽寷朄丒孻慽朄偑憐掕偟偨悽奅偼丄偁偔傑偱傕亀揔惓庤懕偺曐忈亁偺忋偱偺亀恀幚偺敪尒亁偱偁傝乿丄乽嫮戝側尃尷傪梌偊傜傟偨憑嵏丒慽捛婡娭偵傛傞恖尃怤奞傪杊巭偡傞偲偄偆娤揰偐傜尒偨帪丄恀幚敪尒偵廳揰傪偍偄偨傝丄夁搙偵僶儔儞僗榑偵埶嫆偟偨応崌偼丄椡偺庛偄旐媈幰丒旐崘恖偺恖尃怤奞傪堷偒婲偙偡偲偄偆偺偑楌巎偺嫵孭偱偁傝丄寷朄嶰堦忦偼偦偺楌巎揑側嫵孭傪摜傑偊偨傕偺偱偁傞乿偲偄偆婎杮揑帇揰偵棫偮傕偺偱丄旐媈幰丒旐崘恖偺恎懱峉懇(恖幙巌朄)丄戙梡娔崠丄挷彂嵸敾丄帺敀曃廳側偳偵偮偄偰尰忬偺栤戣揰傪塻偔巜揈偟丄恖尃曐忈偺偨傔偺揔惓庤懕偺嫮壔偲檒嵾杊巭偵岦偗偰偺偝傑偞傑側夵妚壽戣傪採婲偟偨丅
(38)丂丂妺栰恞擵乽巌朄夵妚怰媍夛僂僅僢僠儞僌嘔亀崙柉偺婜懸偵墳偊傞孻帠巌朄偺嵼傝曽亁傪傔偖偭偰乿朄棩帪曬幍擇姫堦堦崋(擇乑乑乑擭)丅側偍丄巗柉偺尃棙偲孻帠恖尃偺娭學偵偮偄偰丄妺栰恞擵乽斊嵾曬摴偺岞嫟惈偲彮擭帠審曬摴乿亀棫柦娰戝妛朄妛晹憂棫堦乑乑廃擭婰擮榑暥廤(忋)亁(擇乑乑堦擭)嶲徠丅
(39)丂丂暉揷夒復乽庴孻幰偺朄揑抧埵乿郪搊弐梇懠曇亀怴丒孻帠惌嶔亁(擔杮昡榑幮丒堦嬨嬨嶰擭)丅
(40)丂丂懞堜晀朚丒拹(31)榑暥丅
(41)丂丂巗愳惓恖乽寷朄榑偺偁傝曽偵偮偄偰偺妎偊彂偒亅寷朄偺庯巪丒惛恄偺墖梡傪傔偖偭偰亅乿亀棫柦娰戝妛朄妛晹憂棫堦乑乑廃擭婰擮榑暥廤(忋)亁(擇乑乑堦擭)丅
(42)丂丂悪尨懽梇丒拹(8)榑暥嬨榋暸埲壓丅
(43)丂丂旙岥梲堦懠亀拹庍丒擔杮崙寷朄(壓)亁(惵椦彂堾丒堦嬨敧敧擭)嬨屲屲暸(旙岥梲堦)丅
(44)丂丂棃惒嶰榊乽朄偺夝庍偲朄棩壠乿巹朄堦堦崋(堦嬨屲巐擭)丅
(45)丂丂懞堜晀朚丒拹(29)榑暥巐敧暸丅
(46)丂丂巗愳惓恖丒拹(41)榑暥幍嶰偐傜幍巐暸丅
丂丂仏丂丂杮峞偼丄擇乑乑乑擭堦乑寧擇擇擔偵峴傢傟偨擔杮斊嵾幮夛妛夛戝夛(廼摽戝妛)偺儈僯僔儞億僕僂儉乽幚徹揑傾僾儘乕僠傪幚柋偵偳偆惗偐偡偐乿偵偍偗傞曬崘尨峞偵丄廋惓傪壛偊偨傕偺偱偁傞丅
丂丂仏仏丂丂巹偼丄擇乑乑乑擭堦乑寧擇榋擔丄廜媍堾朄柋埾堳夛偵嶲峫恖偲偟偰弌惾偟丄壢妛揑丒棟惈揑側懺搙偺壓偱偺彮擭朄夵惓偲偄偆帇揰偐傜丄嘆彮擭朄夵惓傪榑偠傞偵偁偨偭偰偼丄偲偔偵尩敱壔偺傕偨傜偡偱偁傠偆岠壥傪専摙偡傞昁梫偑偁傞偙偲丄嘇尩敱壔偵偼堦斒梷巭岠壥偑婜懸偱偒側偄偙偲丄嘊尩敱壔偵傛傝彮擭偺幮夛揑嵞摑崌偑崲擄偵側偭偰嵞斊棪偑崅傑傝丄偐偊偭偰幮夛偺埨慡偑懝側傢傟丄彨棃偺斊嵾旐奞偑憹偊傞寢壥偲側傞偍偦傟偑偁傞偙偲丄嘋彮擭怰敾丄彮擭張嬾丄孻帠嵸敾丄孻敱幏峴側偳偵偍偄偰丄偙傟傑偱偺埨掕偟偨幚柋偑崿棎偡傞偱偁傠偆偙偲丄嘍旕峴尨場偺壢妛揑夝柧偲偦偺夝寛偲偄偆傾僾儘乕僠偐傜棧傟傞偙偲偵傛傝丄栤戣傪傑偡傑偡怺崗壔偝偣傞寢壥偲側傝丄尩敱壔偵傛偭偰崙柉偑偨偲偊堦帪偺乽埨怱姶乿傪摼傜傟偨偲偟偰傕丄偦傟偼乽偮偐偺娫偺婾傝乿偵夁偓側偄偙偲丄嘐壢妛揑丒棟惈揑懺搙偺壓偵彮擭朄夵惓傪恑傔傞偨傔偵丄旕峴尨場丄彮擭朄偺塣梡忬嫷丄彮擭傪庢傝姫偔幮夛娐嫬側偳偵偮偄偰偺惓妋側帠幚擣幆偑昁梫偱偁傝丄偦偺帠幚傪岞奐偟偨偆偊偱丄彮擭朄偺塣梡傗嫵堢偵実傢傞愱栧壠偺堄尒傪暦偔偙偲傪傕娷傔丄奐偐傟偨帺桼側摙榑傪峴傢側偗傟偽側傜側偄偙偲丄傪巜揈偟偨丅偙傟偵偮偄偰偼丄亀戞昐屲廫夞崙夛廜媍堾朄柋埾堳夛媍椢戞幍崋(暯惉廫擇擭廫寧擇廫幍擔)亁丅偦偺屻丄擇乑乑乑擭堦堦寧擇敧擔丄崙夛偵偍偄偰丄乽彮擭朄夵惓乿朄埬偼壜寛丒惉棫偟偨丅孻帠張暘揔梡傪尨懃偲掕傔傞乽夵惓乿彮擭朄擇擇忦擇崁傪夝庍丒塣梡偡傞偵偁偨偭偰丄壠掚嵸敾強偼丄寷朄偺庯巪丒惛恄偵揔崌偟偨朄偺夝庍丒塣梡偱偁傞偨傔偵偼丄朄偺暥尵偵偐偐傢傜偢丄孻帠張暘偺偨傔偺専嶡姱憲抳偺寛掕傪梷惂偡傋偒偱偁傞丅
仏仏仏丂丂扙峞屻丄慜揷夒塸亀彮擭斊嵾亁(搶嫗戝妛弌斉夛丒擇乑乑乑擭)偵愙偟偨丅摨彂堦嬨乑暸埲壓偼丄傾儊儕僇偵偍偄偰堦嬨幍乑擭戙枛偐傜堦嬨敧巐擭傑偱偺偁偄偩彮擭偺巜昗斊嵾専嫇恖堳偑尭彮偟偨偙偲偼丄偙偺帪婜偵恑傔傜傟偨彮擭朄偺尩敱壔偺岠壥偱偁傝丄堦嬨敧屲擭偐傜偺憹壛偼丄尩敱壔偺斊嵾梷巭岠壥偑帪娫偺宱夁偵傛偭偰愗傟偨偐傜偱偁傞丄偲偺尒曽傪採帵偟偰偄傞丅杮暥偵弎傋偨傛偆偵丄寈嶡摑寁忋丄巜昗斊嵾(巜昗朶椡斊嵾偲巜昗嵿嶻斊嵾偐傜側傝丄巜昗嵿嶻斊嵾偑慡懱偺嬨乑亾嬤偔傪愯傔傞丅G4嶲徠)偺旐戇曔幰悢偺尭彮偑偁偭偨偲偟偰傕丄偦傟傪傕偭偰丄偨偩偪偵尩敱壔偺斊嵾梷巭岠壥偑帵偝傟偨傕偺偲偟偰棟夝偡傋偒偱偼側偄傛偆偵巚傢傟傞丅傑偨丄彮擭朄偺尩敱壔偼偨偟偐偵堦嬨幍乑擭戙枛偵巒傑偭偨偑丄杮暥偵弎傋偨傛偆偵丄堦嬨敧乑擭戙偐傜嬨乑擭戙傪捠偠偰丄奺廈偼尩敱棫朄偺惂掕傪宲懕偟丄尩敱壔傊偺孹幬傪怺傔偰偄偭偨偺偱偁傞偐傜丄堦嬨敧屲擭埲崀丄彮擭偺巜昗斊嵾専嫇恖堳偑憹壛偟偰偄傞偺偼丄尩敱壔偺斊嵾梷巭岠壥偑帪娫偺宱夁偵傛偭偰愗傟偨偐傜偱偁傞丄偲偺尒曽偵偼媈栤偑巆傞丅
仏仏仏仏丂丂惸摗朙帯乽偙偙偑偍偐偟偄丄彮擭朄亀夵惓亁乿抍摗廳岝傎偐丒拹(3)彂擇榋暸偼丄乽堦楢偺廳戝側彮擭帠審傪宱尡偟偰丄擔杮幮夛偱儌儔儖丒僷僯僢僋偑惗偠乿傞側偐丄乽彮擭朄亀夵惓亁偵偮偒丄偁偨偐傕崙柉揑崌堄偑惉棫偟偰偄傞偐偺傛偆側晽挭偑傒傜傟偨丅偟偐偟丄柉庡庡媊幮夛偵偍偗傞崙柉揑崌堄偼丄惓妋側忣曬傪婎慴偵偟偰宍惉偝傟側偗傟偽側傜側偄乿偲榑偠丄崱夞偼丄惓妋側忣曬偵婎偯偔偙偲側偔丄乽彮擭朄偺尩敱壔亀夵惓亁偼嫊峔偺崙柉揑摨堄乿偱偟偐側偐偭偨偲巜揈偡傞丅傑偨丄摨榑暥擇幍暸偼丄崱夞偺彮擭朄乽夵惓偑乿丄媍堳棫朄偺宍偱丄乽斀懳偡傟偽丄媍惾傪尭傜偡乿偲偺巚榝偐傜丄乽嵟弶偵寢榑偁傝偒乿乽栤摎柍梡乿偱嫮峴偝傟偨偙偲偼堚姸偱偁傞偲偡傞丅
丂
丂
|