|
棫柦娰朄妛丂丂堦嬨嬨榋擭堦崋乮擇巐屲崋乯 搶僪僀僣偺曵夡偲僴乕僔儏儅儞棟榑 嶳愳丂梇枻 |
丂丂儀儖儕儞偺暻曵夡屻侾擭宱偭偨1990擭10寧俁擔丄搶惣椉僪僀僣偺摑堦偑幚尰偟偨丅搶僪僀僣丄偡側傢偪僪僀僣柉庡嫟榓崙乮俢倕倳倲倱們倛倕 俢倕倣倧倠倰倎倲倝倱倛倕 俼倕倫倳倐倢倝倠乯偼崙壠偲偟偰偼徚柵偟丄偦偺俆偮偺儔儞僩偼僪僀僣楢朚嫟榓崙偵曇擖偝傟偰丄惣僪僀僣偺惓幃柤徧僪僀僣楢朚嫟榓崙乮俛倳値倓倕倱倰倕倫倳倐倢倝倠 俢倕倳倲倱們倛倢倎値倓乯偑摑堦僪僀僣偺崙柤偲側偭偨偺偱偁傞丅 丂丂搶僪僀僣偑惣僪僀僣偵媧廂崌暪偝傟偨夁掱偼丄崙壠偺巰柵偺侾偮偺働乕僗偲偟偰嫽枴怺偄傕偺偱偁傞偑丄傾儊儕僇偺惌帯宱嵪妛幰俙丒俷丒僴乕僔儏儅儞偼偦偺戅弌丒峈媍乮倕倶倝倲-倴倧倝們倕乯棟榑傪梡偄偰丄偙偺夁掱傪尋媶偟偰偄傞(侾)丅 丂丂杮峞偼丄僴乕僔儏儅儞偺偙偺尋媶傪徯夘偡傞偲偲傕偵丄僔僗僥儉擖弌椡榑偺妏搙偐傜丄偐傟偺戅弌丒峈媍棟榑偺堄媊傪専摙偟傛偆偲偡傞傕偺偱偁傞丅 (侾)丂丂俙倢倐倕倰倲 俷丏 俫倝倰倱們倛倣倎値丆乭俤倶倝倲丆 倁倧倝們倕丆 倎値倓 倲倛倕 俥倎倲倕 倧倖 倲倛倕 俧倕倰倣倎値 俢倕倣倧們倰倎倲倝們 俼倕倫倳倐倢倝們丆 倝値 俫倝倰倱們倛倣倎値丆 俙 俹倰倧倫倕値倱倝倲倷 倲倧 俽倕倢倖-俽倳倐倴倕倰倱倝倧値丆 俠倎倣倐倰倝倓倗倕丗 俵倎倱倱丏丗 俫倎倰倴倎倰倓 倀値倝倴倕倰倱倝倲倷 俹倰倕倱倱丆 侾俋俋俆丆 倫倫丏 俋-係係丏 乮俥倝倰倱倲 倫倳倐倢倝倱倛倕倓 倝値 倂倧倰倢倓 俹倧倢倝倲倝們倱丆 倁倧倢丏 係俆丆 侾俋俋俁丆 倫倫丏 侾俈俁-俀侽俀丏乯 埲壓丄堷梡儁乕僕晅偗偼丄俙 俹倰倧倫倕値倱倝倲倷 倲倧 俽倕倢倖-俽倳倐倴倕倰倱倝倧値 偵傛傞丅 堦丂丂側偤僴乕僔儏儅儞偼搶僪僀僣偵娭怱傪傕偭偨偐 丂丂僴乕僔儏儅儞偼偙傟傑偱奐敪搑忋崙偺宱嵪暘愅偱抦傜傟偨尋媶幰偱偁傞丅偐傟偼側偤搶僪僀僣偲僪僀僣摑堦偵娭怱傪傕偭偨偺偱偁傠偆偐丅偙傟傪棟夝偡傞偨傔偵偼丄偐傟偺宱楌偵傆傟偰偍偔昁梫偑偁傞偱偁傠偆丅 丂丂嵟嬤姧峴偝傟偨偐傟偺榑暥廤 俙 俹倰倧倫倕値倱倝倲倷 倲倧 俽倕倢倖-俽倳倐倴倕倰倱倝倧値丆 侾俋俋俆 偼丄僴乕僔儏儅儞偺宱楌傗僷乕僜僫儕僥傿傪棟夝偡傞偆偊偱栶棫偮丅 丂丂偙偺榑暥廤偺戣偼丄捈栿偡傟偽亀帺屓揮暍偺孹岦惈亁偲偄偆偙偲偵側傞偱偁傠偆偑丄摿堎側僞僀僩儖偱偁傞丅慡懱偺彉榑偱丄偐傟偑尵偭偰偄傞偲偙傠偵傛傟偽丄嵟嬤偐傟偼帺暘帺恎偺巇帠傪斸敾揑偵嵞専摙偟傛偆偲偟偰偄傞丅偩偐傜榑暥廤偺戣傕乻倱倕倢倖-們倰倝倲倝們倝倱倝倣乮乽帺屓斸敾乿乼偲偄偆偺偵偟傛偆偐偲巚偭偨偑丄偙偺尵梩偼丄偡偱偵僗億僀儖偝傟偰偄傞偺偱丄乻倱倕倢倖-倱倳倐倴倕倰倱倝倧値乼偲偄偆尵梩傪慖傫偩偺偩偲偄偆乮俫倝倰倱們倛倣倎値丆 俙 俹倰倧倫倕値倱倝倲倷 倲倧 俽倕倢倖-俽倳倐倴倕倰倱倝倧値丆 侾俋俋俆丆 倫丏 侾乯丅 丂丂撪梕偼妛弍榑暥偲僄僢僙僀偺崿崌偱偁傞丅嶰晹偐傜惉偭偰偄偰丄戞堦晹偼乽帺屓揮暍乿偲偄偆戣偑偮偗傜傟丄傢傟傢傟偑偙偙偱偲偔偵娭怱傪傕偮榑暥乭俤倶倝倲丆 倁倧倝們倕丆 倎値倓 倲倛倕 俥倎倲倕 倧倖 倲倛倕 俧倕倰倣倎値 俢倕倣倧們倰倎倲倝們 俼倕倫倳倐倢倝們 偼丄偦偺戞堦復偵埵抲偡傞丅戞擇晹偼丄惵擭帪戙傪夞屭偟偨敧曆偺僄僢僙僀傪廂傔傞丅偨偲偊偽乭俥倧倳倰 俼倕倕値們倧倳値倲倕倰 偲戣偝傟偨復偼丄僴乕僔儏儅儞偑儀儖儕儞偺暻曵夡偺慜擭1988擭偵儓乕儘僢僷偲僪僀僣傪朘栤偟偰丄43擭側偄偟56擭傇傝偵嵞夛偟偨係恖偺抦恖乮宱嵪妛幰儐儖僎儞丒僋僠儞僗僉乕傪娷傓乯偺偙偲傪婰偟偨傕偺偱偁傞丅戞嶰晹乽怴偟偄恑弌乿偵偼丄偙偙10擭傎偳偺偁偄偩偵彂偄偨妛弍榑暥偑廂傔傜傟偰偄傞丅 丂丂僴乕僔儏儅儞偼丄柤慜偐傜暘偐傞傛偆偵丄儐僟儎宯偺恖偱偁傞丅戞擇晹偺奺復偱偼丄揋懳揑側夦暔偲壔偟偨崙壠偺娽偲庤傪偐偄偔偖偭偰摝朣偟偨惵擭帪戙偺堦枊堦枊偑昤偐傟偰偄傞丅偐傟偑懱尡偟偨掞峈偲摝朣偺怱棟偼丄偍偦傜偔晛捠偺擔杮恖偺憐憸傪愨偡傞偱偁傠偆丅 丂丂偐傟偼1915擭係寧俈擔丄儀儖儕儞偵惗傑傟偨丅晝偼桳柤側奜壢堛偱偁偭偨丅俫倝倰倱們倛倣倎値 偲偄偆惄偺杮棃偺捲傝偼乭俫倝倰倱們倛倣倎値値 偱丄柤慜偺偆偪乭俷丏 偼乭俷倲倲倧 偺棯偱偁傞丅惗傑傟偨帪偺惄柤偼乭俷倲倲倧-俙倢倐倕倰倲 俫倝倰倱們倛倣倎値値 偱偁偭偨乮俫倝倰倱們倛倣倎値丆 侾俋俋俆丆 倫丏 侾侽俋乯丅傾儊儕僇偵搉偭偰偐傜丄俙倢倐倕倰倲 俷丏 俫倝倰倱們倛倣倎値 偲偄偆柤慜偵曄偊偨偺偱偁傞丅懡暘丄僪僀僣揑側柤慜偲偟偰栚棫偮乭俷倲倲倧 偲偄偆柤慜傪塀偦偆偲偡傞怱棟偲丄傾僀僨儞僥傿僥傿傪曐帩偟偨偄偲偄偆怱棟偺妺摗偺懨嫤偺嶻暔偱偁傠偆丅僼儔儞僗偱朣柦惗妶傪偟偰偄偨偙傠偼丄俙倢倐倕倰倲 俫倕倰倣倎値倲 偲偄偆壖柤傪巊偭偰偄偨乮倫倫丏 俋俈-俋俋乯丅 丂丂偙偆偄偆宱楌偐傜帵嵈偝傟傞傛偆偵丄偐傟偼丄傾儊儕僇偵棊偪拝偄偰偐傜傕僪僀僣栤戣偵偼嫮偄娭怱傪傕偪偮偯偗偰偒偨偟丄僫僀僕僃儕傾偱偺宱嵪僐儞僒儖僞儞僩偲偟偰偺宱尡偐傜惗傑傟偨偲偝傟傞丄偐傟偺戅弌丒峈媍棟榑偵偟偰傕丄偦偺傛傝怺偄崻偼丄偐傟帺恎偺崙壠偐傜偺摝朣偲偄偆懱尡偵偁偭偨傢偗偱偁傞(俀)丅搶僪僀僣暘愅偵偮偄偰尵偊偽丄僴乕僔儏儅儞偼丄搶僪僀僣偐傜偺摝朣幰偨偪傪丄偐偮偰僸僩儔乕丒僪僀僣偺庤偐傜摝傟傛偆偲偟偨帺暘偺巔偲偺僟僽儖儊乕僕偵偍偄偰懆偊偰偄偨偺偱偁傞丅 丂丂僴乕僔儏儅儞偑惓柺偐傜搶僪僀僣暘愅傪帋傒傞偵偄偨偭偨嬶懱揑側帠忣偵偮偄偰偼丄僴乕僔儏儅儞帺恎偑丄榑暥乭俤倶倝倲丆 倁倧倝們倕丆 倎値倓 倲倛倕 俥倎倲倕 倧倖 倲倛倕 俧倕倰倣倎値 俢倕倣倧們倰倎倲倝們 俼倕倫倳倐倢倝們 偺彉榑偵偍偄偰師偺傛偆偵愢柧偟偰偄傞乮倫倫丏 侾侽-侾俀乯丅 丂丂偐傟偼尵偆丅搶僪僀僣偺曵夡偵偮偄偰榑偠偨傕偺偼懡偄偑丄偙偺嫄戝側惌帯揑幮夛揑曄壔傪棟榑揑偵愢柧偟偨椺偼埬奜偵偲傏偟偄丅偟偐傞偵丄嵟嬤丄帺暘偺戅弌丒峈媍棟榑偼丄僪僀僣偱偦偆偟偨棟榑揑愢柧偺偨傔偺奣擮梡嬶偲偟偰寎偊傜傟傛偆偲偟偰偄傞丅傕偲傕偲帺暘偺戅弌丒峈媍棟榑偼傾儊儕僇偱1970擭偵敪昞偝傟偨傕偺偱丄僪僀僣岅栿偼1974擭偵弌偨偺偱偁傞偑(俁)丄1989擭10寧偺儀儖儕儞偺暻曵夡偺偁偲丄僿僯儞僌丒儕僢僞乕偑丄僪僀僣偺尃埿偁傞怴暦 俥倰倎値倠倖倳倰倲倕倰 俙倢倢倗倕倣倕倝値倕 倅倕倝倲倳値倗 偵宖嵹偝傟偨乭俙倐倵倎値倓倕倰値丆 倂倝倓倕倰倱倫倰倕們倛倕値丗 倅倳倰 倎倠倲倳倕倢倢倕値 俛倕倓倕倳倲倳値倗 倕倝値倕倰 俿倛倕倧倰倝倕 倴倧値 俙丏 俷丏 俫倝倰倱們倛倣倎値 偲偄偆榑愢偵偍偄偰丄嵟嬤偺搶僪僀僣偺曵夡偼丄僴乕僔儏儅儞偺1970擭偵敪昞偝傟偨棟榑偺惓偟偝傪丄戝婯柾側宍偱幚徹偟偨傕偺偱偁傞偲榑偠偨偙偲傪宊婡偲偟偰丄偐側傝懡偔偺幮夛壢妛幰偑帺暘偺棟榑傪1989擭偺揮姺偺暘愅偺偨傔偵揔梡偡傞孹岦偑栚偩偮傛偆偵側偭偨丅傑偨丄俢倕倳倲倱們倛倕 俥倧倰倱們倛倳値倗倗倕倣倕倝値倱們倛倎倖倲 傕丄偦傟偑巟媼偡傞尋媶曗彆嬥偺懳徾偲側傞尋媶偺暘椶崁栚偲偟偰乽戅弌丒峈媍傾僾儘乕僠乿(倕倶倝倲-倴倧倝們倕 倎倫倫倰倧倎們倛乯傪愝掕偡傞傛偆偵側偭偰偄傞乮倫丏 侾侾乯丅 丂丂僴乕僔儏儅儞帺恎偼丄偙偆偟偨僪僀僣偵偍偗傞尋媶摦岦偺偙偲傪丄1990擭偐傜1991擭偵偐偗偰儀儖儕儞帺桼戝妛偵懾嵼偡傞婡夛偵宐傑傟偨偙偲偵傛偭偰弉抦偡傞傛偆偵側偭偨偺偱偁傞偑丄偦偺偙偲傪偲偍偟偰丄搶僪僀僣偺曵夡夁掱偺暘愅偵偍偄偰戅弌丒峈媍棟榑偑偳傟傎偳桳岠偱偁傞偐傪帺暘帺恎偱専徹偟偰傒偨偄丄偲峫偊傞傛偆偵側偭偨偺偱偁偭偨丅 (俀)丂丂偙偙偱丄僴乕僔儏儅儞偺庡梫側嬈愌傪楍嫇偟偰偍偙偆乮偡偱偵偁偘偨傕偺傪彍偔乯丅 俙丏 俷丏 俫倝倰倱們倛倣倎値丆 俿倛倕 俽倲倰倎倲倕倗倷 倧倖 俢倕倴倕倢倧倫倣倕値倲丆 侾俋俇侽丏亀宱嵪妛敪揥偺愴棯亁丄彫搰惔娔廋丒杻揷巐榊栿丄涇徏摪弌斉丄堦嬨榋堦丅 亅丆 倕倓丏丆 俴倎倲倝値 俙倣倕倰倝們倎値 俬倱倱倳倕倱丆 俶倕倵 倄倧倰倠丗 俿倵倕値倲倝倕倲倛 俠倕値倲倳倰倷 俥倳値倓丆 侾俋俇侾丏 亅丆 俰倧倳倰値倕倷倱 俿倧倵倎倰倓 俹倰倧倗倰倕倱倱丗 俽倲倳倓倝倕倱 倧倖 俤們倧値倧倣倝們 俹倧倢倝們倷 俵倎倠倝値倗 倝値 俴倎倲倝値 俙倣倕倰倝們倎丆 俶倕倵 倄倧倰倠丗 俿倵倕値倲倝倕倲倛 俠倕値倲倳倰倷 俥倳値倓丆 侾俋俇俁丏 亅丆 俢倕倴倕倢倧倫倣倕値倲 俹倰倧倞倕們倲倱 俷倐倱倕倰倴倕倓丆 倂倎倱倛倝値倗倲倧値丆 俢丏 俠丏丗 俛倰倧倧倠倝値倗倱 俬値倱倲倝倲倳倲倝倧値丆 侾俋俇俈丏亀奐敪寁夋偺恌抐亁丄杻揷巐榊丒強揘栫栿丄涇徏摪弌斉丄 丂丂丂丂侾俋俈俁丅 亅丆 俤倶倝倲丆 倁倧倝們倕丆 倎値倓 俴倧倷倎倢倲倷丗 俼倕倱倫倧値倱倕倱 倲倧 俢倕們倢倝値倕 倝値 俥倝倰倣倱丆 俷倰倗倎値倝倸倎倲倝倧値倱丆 倎値倓 俽倲倎倲倕倱丆 俠倎倣倐倰倝倓倗倕丆 俵倎倱倱丏丗 俫倎倰倴倎倰倓 倀値倝倴倕倰倱倝倲倷 俹倰倕倱倱丆 侾俋俈侽丏 丂丂丂丂亀慻怐幮夛偺榑棟峔憿亁丄嶰塝棽擵栿丄儈僱儖償傽彂朳丄侾俋俈俆丅 亅丆 俙 俛倝倎倱 倖倧倰 俫倧倫倕丗 俤倱倱倎倷倱 倧値 俢倕倴倕倢倧倫倣倕値倲 倎値倓 俴倎倲倝値 俙倣倕倰倝們倎丆 俶倕倵 俫倎倴倕値丗 倄倎倢倕 倀値倝倴倕倰倱倝倲倷 俹倰倕倱倱丆 侾俋俈侾丏窕 亅丆 俿倛倕 俹倎倱倱倝倧値倱 倎値倓 倲倛倕 俬値倲倕倰倕倱倲倱丗 俹倧倢倝倲倝們倎倢 俙倰倗倳倣倕値倲倱 倖倧倰 俠倎倫倝倲倎倢倝倱倣 倐倕倖倧倰倕 俬倲倱 俿倰倝倎倣倫倛丆 俹倰倝値們倕倲倧値丗 俹倰倝倣們倕倲倧値 倀値倝倴倕倰倱倝倲倷 俹倰倕倱倱丆 侾俋俈俈丏 亀忣 丂丂丂丂擮偺惌帯宱嵪妛亁丄嵅乆栘婤丒扷桽夘栿丄朄惌戝妛弌斉嬊丄侾俋俉俆丅 亅丆 俤倱倱倎倷倱 倝値 俿倰倕倫倎倱倱倝値倗丆 侾俋俉侾丏 亅丆 俼倝倴倎倢 倁倝倕倵倱 倧倖 俵倎倰倠倕倲 俽倧們倝倕倲倷 倎値倓 俷倲倛倕倰 俼倕們倕値倲 俤倱倱倎倷倱丆 俶倕倵 倄倧倰倠丗 倁倝倠倝値倗丆 侾俋俉俇丏 (俁)丂丂俙丏 俷丏 俫倝倰倱們倛倣倎値丆 俙倐倵倎値倓倕倰倳値倗 倳値倓 倂倝倓倕倰倱倫倰倳們倛丆 倲倰丏 倐倷 俴倕倧値倎倰倓 倂倎倢倕値們倠丆 俿倳丯倐倝値倗倕値丗 俰丏 俠丏 俛丏 俵倧倛倰丆 侾俋俈係丏 擇丂丂戅弌丒峈媍棟榑偵偮偄偰 丂丂偝偰丄搶僪僀僣暘愅偵揔梡偝傟偨戅弌丒峈媍棟榑偺偙偲偱偁傞偑丄偙傟偵偮偄偰偼摉慠丄偐傟偺 俤倶倝倲丆 倁倧倝們倕丆 倎値倓 俴倧倷倎倢倲倷丗 俼倕倱倫倧値倱倕倱 倲倧 俢倕們倢倝値倕 倝値 俥倝倰倣倱丆 俷倰倗倎値倝倸倎倲倝倧値倱丆 倎値倓 俽倲倎倲倕倱丆 侾俋俈侽 傪嶲徠偡傋偒偱偁傞偑丄偦偺僄僢僙儞僗偼丄僴乕僔儏儅儞帺恎偵傛偭偰丄慜婰偺榑暥乭俤倶倝倲丆 倁倧倝們倕丆 倎値倓 倲倛倕 俥倎倲倕 倧倖 倲倛倕 俧倕倰倣倎値 俢倕倣倧們倰倎倲倝們 俼倕倫倳倐倢倝們 偺朻摢偵偍偄偰梫栺偝傟偰偄傞乮倫倫丏 侾俀-侾係乯丅 丂丂偙偺棟榑偼丄傕偲傕偲慻怐偺惉挿丒悐戅偵娭偡傞棟榑偲偟偰峔惉偝傟偨傕偺偱偁偭偰丄慻怐偲偦偺屭媞偲偺娭學傪栤戣偵偡傞傕偺偱偁傞丅偦偺偝偄僴乕僔儏儅儞偼丄偲偔偵慻怐偑屭媞偵採嫙偡傞嶻弌暔乮弌椡乯偺幙偺掅壓偵偮偄偰偺屭媞偺斀墳傪栤戣偵偡傞丅 丂丂乻俤倶倝倲乼偲偼丄扨弮偵嫀傞峴堊偺偙偲傪堄枴偡傞丅偁傞恖偑偙傟傑偱偁傞婇嬈偺惢昳傪攦偭偰偄偨偲偟偰丄傕偟偦偺婇嬈偑丄埲慜傎偳幙偺傛偄惢昳傪偦偺恖偵採嫙偟側偔側偭偨偲偡傟偽丄偐傟偺斀墳偼擇偮偵暘偐傟傞偱偁傠偆丅堦偮偺斀墳偼偦偺婇嬈偺惢昳傪攦傢側偔側傞偙偲偱偁傞丅偍偦傜偔偐傟偼暿偺婇嬈偺惢昳傪攦偆傛偆偵側傞偱偁傠偆丅偮傑傝慜偺婇嬈偺屭媞廤抍偐傜棧扙偟偰丄怴偟偄婇嬈偺屭媞廤抍偵擖傞偺偱偁傞丅偙傟偑戅弌偱偁傞丅 丂丂乻倁倧倝們倕乼偼丄栤戣揰傪巜揈偟暥嬪傪偮偗傞峴堊偱偁傞丅婇嬈偺採嫙偡傞惢昳偺幙偑棊偪偰偒偨偲偒丄偙傟傑偱偺屭媞偼晄枮傪傕偮偑丄応崌偵傛傞偲丄偨傫偵攦傢側偄偲偄偆峴堊偵傛偭偰偦偺婇嬈偐傜棧傟傞偺偱偼側偔丄棧傟傞棧傟側偄偼暿偲偟偰丄晄枮側惢昳傪攧傝偮偗偨婇嬈偵峈媍偟丄僴僢僉儕暥嬪傪偮偗傞峴堊偵弌傞偙偲偑偁傞丅僴乕僔儏儅儞偺尵偆乻倁倧倝們倕乼偼丄偙偺傛偆側峈媍峴堊偺偙偲偱偁傞丅 丂丂戅弌偲峈媍偑丄婇嬈宱塩偵偲偭偰偒傢傔偰廳梫側丄偨偊偢拲堄傪偼傜偭偰偍偐側偗傟偽側傜側偄婎杮忣曬偱偁傞偙偲偼忢幆揑側帠暱偱偁傠偆丅偨偲偊偽戅弌幰偑懕弌偡傞傛偆側婇嬈偼偄偢傟搢嶻偲偄偆攋嬊偵尒晳傢傟傞偱偁傠偆丅偟偐偟丄僴乕僔儏儅儞偼丄偙偺忢幆揑側帠暱偑埬奜偵寉帇偝傟傞孹岦偑偁傞偙偲偵寈崘傪敪偡傞偺偱偁傞丅偙偆偟偨寉帇偑偲偔偵婲偙傝傗偡偄偺偼岞婇嬈傗惌晎偵偍偄偰偱偁傞丅1970擭偺挊彂偱僴乕僔儏儅儞偼丄偙偆偟偨寉帇偵傛偭偰惗偠偨婋婡偵偮偄偰偄偔偮偐偺働乕僗傪椺帵偟丄戅弌偲峈媍偑偳偺傛偆側娭學偵偁傝丄偳偺傛偆側忦審偺傕偲偵偦傟偧傟偑尰傢傟傞偺偐傪栤戣偵偟偨丅 丂丂戅弌傕峈媍傕丄屭媞偺晄枮偲娭學偡傞偑丄偙傟傑偱宱嵪妛偼丄峈媍偵偮偄偰偼偁傑傝娭怱傪暐傢側偐偭偨丅屭媞偼彜昳偺壙奿偑晄摉偵崅偄偲敾抐偟偨偲偒偵偼偦偺彜昳傪攦傢側偔側傞偱偁傠偆丅偦偆偄偆徚旓幰峴摦偺儌僨儖傪壖掕偟偰嵪傑偣偰偒偨偺偱偁傞丅婇嬈偵偟偰傕丄徚旓幰塣摦偑崅傑傞傑偱偼丄庡偲偟偰戅弌忣曬偵斀墳偟偰偒偨丅 丂丂偟偐偟丄偨偲偊偽岞婇嬈偺応崌丄戅弌忣曬偼嬈愌掅壓傪杊偖偨傔偺婎杮忣曬偲偟偰偼偁傑傝栶偵棫偨側偄丅慻怐偲偟偰偺惈幙忋丄屭媞偺戅弌偑栤戣偵側傜側偄偙偲偑懡偄偐傜偱偁傞丅偦偙偱丄偙偆偟偨慻怐偺応崌丄峈媍偑拲栚偝傟傞偙偲偵側傞丅惌帯妛偑丄戅弌傛傝峈媍偺傎偆偵娭怱傪傕偭偰偒偨偺偼丄偙偺偨傔偱偁傞丅偟偐偟丄峈媍偺僠儍僱儖偱偺晄枮偺昞弌偼僄僱儖僊乕偲帪娫傪梫偟丄旓梡偺揰偱崅偔偮偔偙偲偑懡偄丅偝傜偵懠幰偺嫤椡傪媮傔傞昁梫偑偁傞偙偲傕偟偽偟偽偱偁傞丅 丂丂偙傟偵懳偟偰丄戅弌偼娙扨偱僀乕僕僀偱偁傞丅乽晄枮側傜攦傢側偗傟偽傛偄乿偲偄偆傢偗偱偁傞丅偐傝偵乽晄枮偩偐傜峈媍偟偨偄乿偲巚偭偨偲偟偰傕丄峈媍峴堊偼恖偺拲堄傪傂偔栚棫偮峴堊偱偁傞偨傔偵丄旔偗傜傟傞偙偲偵側傝傗偡偄丅傕偟晄枮僄僱儖僊乕偺埑椡偑丄戅弌僠儍僱儖傪捠偭偰敪嶶偝傟傞偙偲偵側傞偲偡傟偽丄峈媍偺偨傔偵棙梡偝傟傞僄僱儖僊乕偼偁傑傝巆偝傟偰偄側偄偲偄偆偙偲偵側傞丅偙偺傛偆偵偟偰乽戅弌僆僾僔儑儞偺懚嵼偼丄峈媍媄弍偺奐敪傪杻醿偝偣傞乿寢壥偵側傞偱偁傠偆丅 丂丂僴乕僔儏儅儞偼丄1970擭摉帪丄偙偺傛偆偵丄戅弌偲峈媍偺娭學偵偮偄偰丄晄枮僄僱儖僊乕偺懚嵼傪慜採偲偟偰丄椉幰偺偁偄偩偵僔乕僜乕揑娭學傑偨偼乽憡屳攚斀揑乿側娭學偑偁傞偲憐掕偟偰偄偨丅偙偺憐掕偺偙偲傪僴乕僔儏儅儞偼乽悈椡妛揑儌僨儖乿偲傕屇傫偱偄傞偑丄偙偺儌僨儖偑丄搶僪僀僣偺曵夡夁掱偺暘愅傪偲偍偟偰廋惓偝傟丄儕僼傽僀儞偝傟傞偙偲偵側傞丅 丂丂偦偺撪梕偵偮偄偰偼師愡埲壓偱徻偟偔尒傞偙偲偲偟偰丄偙偙偱拲堄偟偰偍偄偰傛偄偙偲偼丄戞堦偵丄偙傟傑偱戅弌峴堊傪暘愅偺拞怱偵偟偰偒偨宱嵪妛偲丄峈媍峴堊傪暘愅偺拞怱偵偟偰偒偨惌帯妛偑曕傒婑偭偰丄戅弌偲峈媍偲偄偆擇偮偺暘愅僇僥僑儕乕傪傕偭偨惌帯宱嵪妛傪敪揥偝偣傞傋偒偩偲僴乕僔儏儅儞偑採埬偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅戞擇偵丄偐傟偼丄宱嵪懱宯偲惌帯懱宯偲傪棟榑揑偵摑崌偡傞偲偄偭偨偙偲傪採埬偟偰偄傞偺偱偼側偔偰丄傓偟傠僔僗僥儉偺擖弌椡僇僥僑儕乕傪尒捈偡偙偲偵傛偭偰摑崌偟傛偆偲採埬偟偰偄傞偺偩偲偄偆偙偲偱偁傞丅偨偩偟丄偦偺偝偄丄偐傟偼儊儞僶乕僔僢僾丒僔僗僥儉傪廳帇偡傞棫応偵棫偭偰偄傞丅偙偺揰偵偮偄偰偼丄偁偲偱傆傟傞偙偲偵側傞偱偁傠偆丅 嶰丂丂侾俋係俋擭偐傜侾俋俉俉擭偵偄偨傞帪婜偺搶僪僀僣 丂丂偝偰丄搶僪僀僣偺暘愅偱偁傞丅偙偺崙偼丄愴屻悽奅偵偍偄偰丄億乕儔儞僪丄僠僃僐僗儘償傽僉傾丄僴儞僈儕乕側偳偲偲傕偵丄僜楢寳塹惎崙壠偺堦偮偱偁偭偨丅僜楢偼儚儖僔儍儚忦栺婡峔側偳偺惌帯宱嵪揑巟攝懱惂偺榞偺側偐偵偙傟傜偺崙壠傪埵抲偯偗掲傔晅偗偰偄偨丅偟偐偟丄偙偺幮夛庡媊揑丒掗崙庡媊揑懱惂傕摦梙傪傑偸偑傟側偐偭偨丅 丂丂億乕儔儞僪丄僠僃僐僗儘償傽僉傾丄僴儞僈儕乕偱偼嫟嶻搣惌尃偵懳偡傞摤憟偑尠嵼壔偟偨偙偲偑偁傞丅1956擭偺僴儞僈儕乕摦棎丄1968擭偺僾儔乕僌偺弔丄1980擭偺億乕儔儞僪偵偍偗傞楢懷偺妶摦側偳偑偦傟偱偁傞丅搶僪僀僣偺応崌丄1953擭偺俇寧偵儀儖儕儞偱楯摥幰偺朶摦偑偁偭偨偑丄偦傟埲屻丄搶僪僀僣偼僜楢寳塹惎彅崙壠偺偆偪偺桪摍惗偱偁傝懕偗傞傛偆偵尒偊偨丅偟偐偟丄帠懺偼偦偆娙扨側傕偺偱偼側偐偭偨丅 丂丂僴乕僔儏儅儞偑傒傞偲偙傠偵傛傟偽丄億乕儔儞僪丄僠僃僐僗儘償傽僉傾丄僴儞僈儕乕偼峈媍妶摦偵傛偭偰摿挜偯偗傜傟傞崙壠偱偁偭偰丄戅弌尰徾偑偁傑傝尠挊偱偼側偄丅偦偺戝偒側梫場偲偟偰偼丄僜楢偲搶僪僀僣偵埻傑傟偨抧棟揑埵抲丄嬤悽埲崀偺掞峈妶摦偺揱摑偑偁偘傜傟傛偆丅偙傟傜偺彅崙偲懳徠揑偵丄搶僪僀僣偱偼丄尠嵼揑側峈媍妶摦偼偁傑傝尒傜傟偢丄戅弌尰徾偑尠挊偱偁偭偨丅 丂丂昞侾偼丄惣僪僀僣偍傛傃搶僪僀僣偑寶崙偝傟偨1949擭偐傜1989擭傑偱偺朣柦幰丄摉嬊偺嫋壜傪摼偨堏廧幰丄恎戙嬥偲偺岎姺偱嫋壜偝傟偨堏廧幰側偳偺堏廧幰摑寁傪帵偡乮們倖丏 倫倫丏 侾俇-侾俈乯丅 丂丂偙偺昞偑帵偡傛偆偵丄搶僪僀僣偑寶崙偝傟偨1949擭偐傜1961擭傑偱丄朣柦幰偼枅擭10枩恖傪墇偊丄偲偔偵儀儖儕儞朶摦偺1953擭偵偼33枩恖偵払偟偨丅偙傟偼憤恖岥1679枩恖乮1976擭擭墰乯僋儔僗偱丄楯摥椡晄懌偵擸傑偝傟偰偄偨崙壠偵偲偭偰偼丄廳戝側弌寣偲偄偆傋偒偱偁傞丅偐偔偟偰丄偮偄偵搶僪僀僣偼丄1961擭俉寧丄搶惣儀儖儕儞偺嫬奅偵揝嬝僐儞僋儕乕僩惢偺暻傪抸偒偼偠傔偨丅偙傟偑偄傢備傞儀儖儕儞偺暻偱偁傞丅偦偺憤墑挿偼160噏埲忋偵払偟偨丅 丂丂昞侾偵傛傞偲丄1962擭偺朣柦幰偺悢偼侾枩6741恖偱丄慜擭偺栺21枩恖偐傜寖尭偟偰偄傞丅暻偺岠壥偑尰傢傟偨偺偱偁傞丅傕偭偲傕朣柦幰偺悢偼僛儘偵側偭偨傢偗偱偼側偄丅1966擭埲崀1988擭偵偄偨傞傑偱朣柦幰偺悢偼侾枩恖儗儀儖傪愗偭偰偄傞偑丄尩廳側娔帇偺傕偲惗柦偺婋尟傪偲傕側偆扙弌傪偼偐傝丄惉岟偟偨恖乆偑枅擭俁愮恖傪挻偊偰偄偨偺偱偁傞(係)丅 丂丂偙偆偟偨摝朣摑寁偼搶僪僀僣偺恖乆偺惣懁悽奅傊偺偁偙偑傟偑偄偐偵嫮楏偱偁偭偨偐傪帵偟偰偄傞丅惣儀儖儕儞帺懱偑乽惣懁偺忺傝憢乿偲偄傢傟偨帪婜偑偁偭偨偑丄扙弌傪摦婡偯偗傞梫場偲偟偰廳梫側摥偒傪偟偨偺偑柍慄曻憲偲偔偵僥儗價偱偁偭偨偙偲偼傛偔抦傜傟偰偄傞丅 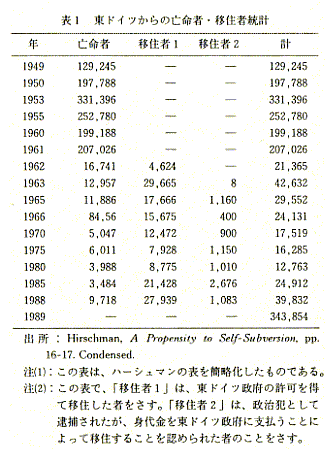
丂丂昞侾偼丄1962擭埲崀丄搶僪僀僣摉嬊偑崌朄揑側堏廧幰傪擣傔傞傛偆偵側偭偨偙偲丄恎戙嬥偲偺岎姺乮係枩儅儖僋偵払偟偨偙偲傕偁偭偨偲偄傢傟傞乯偵傛傞堏廧幰傕1963擭埲崀擣傔傜傟丄偦偺悢傕師戞偵憹偊偰偒偨偙偲傪帵偟偰偄傞丅 丂丂偙傟偼傕偪傠傫搶僪僀僣偺堄幆揑側惌嶔偵傛傞傕偺偱偁偭偨丅搶僪僀僣摉嬊偼擭侾枩恖側偄偟俀枩恖掱搙偺堏廧偼巇曽側偄偲擣傔偰偄偨傆偟偑偁傞丅恎戙嬥偼婱廳側奜壿傪壱偖堦偮偺曽曋偱傕偁偭偨丅 丂丂堏廧偼丄応崌偵傛傞偲丄搶僪僀僣惌晎偵傛偭偰丄懱惂偺埨慡曎偲偟偰桳岠偩偲棟夝偝傟偨丅乽埆幙側乿斀懱惂揑暘巕偑惣僪僀僣偵堏摦偡傟偽丄偐傟傜偺乽幮夛揑埆塭嬁乿偑側偔側傞偐傜偱偁傞丅偙偺偨傔惌晎偼丄1976擭偺帊恖償僅儖僼丒價乕儖儅儞傪傔偖傞帠審偑椺帵偡傞傛偆偵丄斀懱惂揑恖暔偑惣僪僀僣偵椃峴偵弌偨偲偒丄搶僪僀僣傊偺婣崙傪擣傔側偄偲偄偆傛偆側峴堊偵弌偨偙偲偝偊偁傞丅 丂丂僴乕僔儏儅儞棟榑偵傛傟偽丄戅弌僆僾僔儑儞偑嶌梡偡傞応崌丄峈媍妶摦偼晄妶敪偵側傞偼偢偱偁傞偑丄偨偟偐偵搶僪僀僣偱偼丄1949擭偐傜1988擭偵偄偨傞帪婜偵偍偗傞峈媍妶摦偼妶敪偱側偐偭偨丅搶僪僀僣偱偼億乕儔儞僪偺乽楢懷乿偺傛偆側妶摦偺揥奐偼傒傜傟側偐偭偨偺偱偁傞丅 丂丂偟偐偟丄搶僪僀僣偱峈媍峴堊偑妶敪偵側傝偊側偐偭偨捈愙揑棟桼偲偟偰偼丄師偺嶰偮偺梫場偑偁偘傜傟傞偲僴乕僔儏儅儞偼尵偆丅 丂丂戞堦偵丄搶僪僀僣偱偼惌晎傗嫟嶻搣偺椡偐傜偺旔擄強傪採嫙偡傞傛偆側斾妑揑撈棫偟偨帺棩揑側幮夛慻怐偑側偐偭偨乮偙傟偵偼搶僪僀僣偑僫僠偺乽僌儔僀僸僔儍儖僩僁儞僌乿傪宱偰偄傞偙偲偑戝偒偔塭嬁偟偰偄傞偱偁傠偆乯丅億乕儔儞僪丄僠僃僐丄僴儞僈儕乕偱偼丄傑偩傑偟偱偁偭偨丅偨偲偊偽億乕儔儞僪偱偼拞悽偐傜偺揱摑傪傕偭偨僇僩儕僢僋嫵夛偑偁偭偨丅 丂丂戞擇偵丄搶僪僀僣偺懱惂僀僨僆儘僊乕偺栤戣偑偁傞丅僪僀僣偵偲偭偰僫僠僘儉偼埆柌偱偁偭偨偑丄偙傟偵偲偭偰戙傢偭偨儅儖僋僗丒儗乕僯儞庡媊偼僫僠僘儉偺僀僨僆儘僊乕傪朰傟偝偣傞岠擻傪傕偭偰偄偰丄恖乆偼偙傟傪怣偠傛偆偲偡傞孹岦偑偁偭偨偲偄偆丅 丂丂戞嶰偵丄搶僪僀僣偼僜楢寳偺嵟慜慄傪宍惉偟偰偄偰丄僜楢偺嫮椡側孯帠揑巟攝偺傕偲偵偍偐傟偰偄偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅僜楢偼搶僪僀僣偵廳憰旛偺惛塻晹戉傪挀撛偝偣丄懡悢偺妀儈僒僀儖傪攝旛偟偰偄偨丅搶僪僀僣惌晎偵偟偰傕丄僜楢偲偺偒傢傔偰枾愙側嫤椡娭學偺傕偲偵巟攝懱惂傪尩廳偵屌傔偰偄偨丅峈媍妶摦傗偦偺慻怐壔偼梷埑偺嫮戝側僾儗僢僔儍乕偺傕偲偵偍偐傟丄婋尟惈傕戝偒偐偭偨偺偱偁傞丅 丂丂偙偺傛偆偵偟偰丄搶僪僀僣偱偼丄峈媍峴摦偺惉岟壜擻惈偼偒傢傔偰掅偄丄偳偆偟偰傕偄傗側傜扙弌偡傞傛傝側偄丄偦偆怣偠傜傟偨偺偱偁偭偨丅偦偟偰丄扙弌愭偼斾妑揑嬤偄偲偙傠偵埵抲偟偰偄偨偺偱偁傞丅 丂丂僴乕僔儏儅儞偺昞偵傕偲偯偄偰寁嶼偡傞偲丄1949擭10寧偐傜1961擭枛偵偄偨傞婜娫偵偍偗傞搶僪僀僣偐傜偺戅弌幰偺椵寁偼273枩8572恖偱丄擭暯嬒22枩5082恖丅1962擭偐傜1988擭偵偄偨傞27擭娫偺戅弌幰偺椵寁偼丄56枩4436恖偱丄擭暯嬒俀枩905恖偱偁傞丅1989擭偩偗偱34枩恖埲忋偺恖偑扙弌偟偰偄傞偑丄偙傟傪擖傟偰愊嶼偡傞偲丄搶僪僀僣偐傜偺戅弌幰偼丄椵寁364枩6862恖偵払偡傞丅1976擭墰偺恖岥摑寁偺恖岥1679枩恖偺21丒7亾偑庡偲偟偰惣僪僀僣傊偲徚偊偨偙偲偵側傞丅 丂丂偙偺傛偆側扙弌偼丄搶僪僀僣偵偲偭偰宱嵪揑偵旕忢側捝庤偱偁偭偨偼偢偩偑丄惌帯揑偵偼偳偺傛偆側塭嬁偑偁偭偨偱偁傠偆偐丅 丂丂偙傟偼丄億乕儔儞僪側偳偺旕扙弌揑丒峈媍揑側彅崙偲搶僪僀僣偲偺懳斾偵傛偭偰傛偔棟夝偝傟傞偱偁傠偆丅億乕儔儞僪側偳偱偼斀懱惂揑僄儕乕僩偑扙弌偣偢崙偵偲偳傑偭偨偨傔偵丄惌帯揑側僀僨僆儘僊乕偺懡嵤側僗儁僋僩儖偑懚嵼偡傞偙偲偵側偭偨丅惌帯揑尵榑妶摦偑斾妑揑妶敪偱偁傝丄幮夛庡媊偺榞偺側偐偱丄幚幙揑偵懡尦庡媊揑側昞弌峔憿偑宍惉偝傟傞偙偲偵側偭偨丅偙偺偨傔丄嫟嶻搣懱惂偑曵夡偟偨偁偲傕丄偦傟偵庢偭偰戙傢傞儕乕僟乕僔僢僾偵寚偗傞偙偲偑側偐偭偨偺偱偁傞丅 丂丂搶僪僀僣偼偦偺斀懳偱偁傞丅搶僪僀僣偱偼丄懱惂曵夡屻丄岅傜傟偨偺偼偣偄偤偄偺偲偙傠乽恀惓儅儖僋僗庡媊偺嵞惗乿偲偄偭偨偙偲偵偡偓側偐偭偨丅偦偟偰丄惌帯揑偵桳擻側恖嵽偑惣僪僀僣偵朣柦偟偰偟傑偭偰偄偨偨傔丄儕乕僟乕僔僢僾傪偲傞恖嵽偑屚妷偟偰偄偨丅偙偺偙偲偑丄搶僪僀僣偑惣僪僀僣偵媧廂偝傟偞傞傪偊側偐偭偨堦偮偺戝偒側尨場偲側偭偰偄傞丅 丂丂昞侾偼丄1989擭偺搶僪僀僣偐傜偺扙弌幰偑幚偵34枩恖埲忋偵払偟丄儀儖儕儞偺暻埲慜偺嵟崅婰榐偱偁傞1953擭偺悢帤傪墇偊偨偙偲傪帵偟偰偄傞丅偙傟偼丄扙弌幰偨偪偑丄戝偒偔塈夞偟偰僴儞僈儕乕丄億乕儔儞僪丄僠僃僐偐傜僆乕僗僩儕傾傪宱桼偟偰惣懁偵堏摦偡傞偲偄偆宱楬偺戝偒側曄壔偑婲偙偭偨偨傔偱偁傞丅搶僪僀僣惌晎偼丄偙傟傪岠壥揑偵庢掲傑傞偙偲偑偱偒側偐偭偨丅 丂丂偙偙偱偼1989擭偺寧暿偺摑寁傪帵偡昞偼徣棯偡傞偑丄扙弌幰偺悢偼1989擭俆寧偵偼侾枩恖戜傪偙偊丄搤偑杮奿壔偡傞慜偺11寧偵偼13枩恖傪墇偊偨丅俆寧偐傜媫寖偵憹偊偨偺偼丄僴儞僈儕乕惌晎偑俆寧俀擔偵僆乕僗僩儕傾偲偺崙嫬慄偵愝抲偝傟偨揝忦栐傪揚嫀偟偨偨傔偱偁傞丅搶僪僀僣惌晎偼崙柉偵僴儞僈儕乕側偳偺僜楢寳桭岲彅崙偵帺桼偵椃峴偡傞偙偲傪擣傔偰偄偨偨傔丄僴儞僈儕乕傊偺椃峴偵弌偐偗偨恖乆偼僴儞僈儕乕偐傜僆乕僗僩儕傾傊弌丄偝傜偵惣僪僀僣偵擖傞偙偲偑梕堈偵側偭偨偺偱偁傞丅 丂丂僴儞僈儕乕惌晎偼偝傜偵俋寧丄僴儞僈儕乕偐傜僆乕僗僩儕傾偵弌崙偟傛偆偲偡傞搶僪僀僣恖偵偙傟傪岞幃偵擣傔傞偙偲偲偟偨丅戅弌偵攺幵偑偐偐偭偨偙偲偼偄偆傑偱傕側偄丅偙偆偟偨僴儞僈儕乕惌晎偺慬抲偺攚宨偵偼丄暷僜嫤挷偵傛傞懳搶僪僀僣丒懳僪僀僣惌嶔偺揮姺乮搶僪僀僣偺帺慠巰偲僪僀僣摑堦偺梕擣乯偑偁偭偨偙偲偼妋偐偱偁傞偑丄僴乕僔儏儅儞偼丄偦偆偟偨僌儘乕僶儖丒億儕僥傿僋僗偵偼傆傟偰偄側偄丅 丂丂1989擭10寧俈擔丄搶僪僀僣偼僑儖僶僠儑僼傪寎偊偰寶崙40廃擭傪廽偭偨偑丄偦偺捈慜偺10寧侾丄係丄俆擔偵丄億乕儔儞僪丄僠僃僐偐傜僆乕僗僩儕傾傊偲岦偐偆搶僪僀僣偺乭俙倳倱倰倕倝倱倕倰乮弌崙幰乯侾枩4000恖傪忔偣偨晻報楍幵偑搶僪僀僣傪捠夁偟偰偄偭偨丅搶僪僀僣惌晎偼丄偙偆偟偨孅怞揑側弌棃帠傪慾巭偡傞偙偲偑偱偒側偐偭偨偺偱偁傞丅 (係)丂丂僴乕僔儏儅儞偼丄扙弌偵幐攕偟偨恖乆偺偙偲偵傆傟偰偄側偄偑丄偙偺揰丄晄廫暘偱偁傞丅偐傟傜偼応崌偵傛傞偲幩嶦偝傟丄懡偔偼搳崠偝傟偨丅朣柦偵幐攕偟偨恖偺悢偼擭偵傛偭偰堎側傞偑丄堦愢偵傛傞偲丄擭5000恖掱搙偱偁偭偨偲偄傢傟傞丅仭嶳朏榊曇亀嵟怴悽奅尰惃亁丄暯杴幮丄1979擭丄191儁乕僕丅 丂丂巹偼1988擭偵億僀儞僩丒僠儍乕儕乕偺専栤強傪宱偰搶儀儖儕儞傪朘傟偨偙偲偑偁傞偑丄専栤偼旕忢偵尩偟偔丄戝偒側嬀傪巊偭偰僶僗偺壓晹傪専帇偟偰偄偨丅扙弌幰偺側偐偵偼丄僶僗偺壓晹傪棙梡偟偨幰傑偱偄偨偺偐傕偟傟側偄丅 巐丂丂侾俋俉俋擭偵偍偗傞戅弌偺岞慠壔偲峈媍妶摦偺暚弌 丂丂1988擭傑偱偺偲偙傠戅弌偲峈媍偼憡屳攚斀揑側宍偱嶌梡偟偨傛偆偵巚傢傟傞偺偱偁傞偑丄嫟嶻搣惌尃偑曵夡偟偨1989擭偵偼丄搶僪僀僣偱峈媍妶摦偑尠嵼壔偟丄戅弌偲峈媍偑嫤摨偟偰懱惂偺曟孈傝嶌嬈傪偟偨丅僴乕僔儏儅儞偼師偵偙傟傪専摙偡傞乮倫倫丏 俀係-俁俁乯丅 丂丂偐傟偼峈媍妶摦偺暚弌偵娭偡傞偄偔偮偐偺廳梫側帠椺傪徯夘偟偰偄傞丅 丂丂傑偢丄儔僀僾僠僢僸偱偺弌棃帠偵偮偄偰丅儔僀僾僠僢僸偺僯僐儔僀嫵夛偼丄1980擭戙偺弶傔偐傜枅廡寧梛擔屵屻偵乽暯榓婩婅幰乿偺廤夛偑傕偨傟傞傛偆偵側偭偰偄偨偑丄1988擭偵偼丄偦偙偑乻俙倳倱倰倕倝倱倕倰乮弌崙幰乯乼側偄偟乻俙倳倱倰倕倝倱倕倵倝倢倢倝倗倕乮弌崙婓朷幰乯乼偺廤傑傞応強偵側偭偰偄偨丅1989擭侾寧15擔亅偙偺擔偼僇乕儖丒儕乕僾僋僱僸僩偲儘乕僓丒儖僋僙儞僽儖僌偺埫嶦70廃擭偺擔偵摉偨偭偰偄偨偑亅丄偙偺嫵夛偐傜帺慠敪惗揑偵僨儌偑巒傑傝丄儔僀僾僠僢僸偺奨傪峴恑偟偨丅寈嶡偼150恖傪戇曔偟偨丅 丂丂埲屻丄偙偺嫵夛偺峀応偼斀懱惂攈偺僙儞僞乕偲側傞丅乭俙倳倱倰倕倝倱倕倰乭 傗乭俙倳倱倰倕倝倱倕倵倝倢倢倝倗倕乭 偼丄乭倂倝倰 倵倧倢倢倕値 倰倎倳倱両"乮乽偙偺崙偐傜弌偰偄偔偧両乿乯偲嫨傇偺傪忢偲偡傞傛偆偵側偭偨偑丄89擭俋寧係擔丄乭倂倝倰 倵倧倢倢倕値 倰倎倳倱両乭 偲嫨傇懡偔偺恖乆偵懳偟偰丄弶傔偰丄偁傞幰偑乭俬們倛 倐倢倕倝倐倕 倛倝倕倰両乭乮乽偙偺崙偵棷傑傞偧両乿乯偲嫨傇惡偑暦偙偊偨丅偦偟偰丄堦廡娫屻偺11擔偵偼丄暋悢偺恖乆偑乭倂倝倰 倐倢倕倝倐倕値 倛倝倕倰両乭 偲嫨傇傛偆偵側偭偨丅僴乕僔儏儅儞偼丄偐傟傜偼懱惂偐傜摝偘傞偺偱偼側偔偰丄懱惂偵懳偟偰峈媍偟懳寛偡傞摴傪慖傫偩恖乆偱偁偭偨偲夝庍偡傞丅 丂丂摉弶丄偙傟傜擇偮偺僌儖乕僾偼懳棫揑偱揋懳揑偱偁偭偨偑丄傗偑偰偐傟傜偼乭倂倝倰 倱倝値倓 倓倎倱 倁倧倢倠丏乭乮乽傢傟傢傟偼恖柉偩乿乯偲偄偆僗儘乕僈儞偺傕偲偵楢懷姶傪昞柧偡傞傛偆偵側偭偨偲偝傟傞丅 丂丂師偵僪儗僗僨儞偺応崌偱偁傞丅僪儗僗僨儞偼搶墷傊偺楍幵岎捠偺梫徴偱偁傞偑丄偙偙偱丄89擭偺10寧偵偒傢傔偰拲栚偡傋偒弌棃帠偑婲偙偭偨丅 丂丂1989擭俋寧偐傜10寧偵偐偗偰丄僪儗僗僨儞墂偼乭俙倳倱倰倕倝倱倕倰乭 偱堦攖偵側偭偰偄偨偑丄10寧俁擔偵丄搶僪僀僣惌晎偼丄偦傟傑偱偼帺桼偵峴偒棃偱偒偨偺傪夵傔偰丄僠僃僐偲偺崙嫬傪晻嵔偟丄僷僗億乕僩偲價僓傪帩偨側偄幰偼弌崙偱偒側偄偙偲偵偡傞偲揱偊傜傟偨丅墂偱懌巭傔傪偔偭偰丄弌崙婓朷幰偺悢偼傑偡傑偡朿傟偁偑傞偙偲偵側偭偨偑丄10寧係擔丄偝偒偵弎傋偨晻報楍幵偑僪儗僗僨儞傪捠夁偡傞偲偄偆塡偑峀偑傝丄恖乆偼昁巰偵側偭偰偙傟偵忔偣偰傕傜偍偆偲嶦摓偟偨丅寈嶡偼寈崘傪敪偟丄乭俙倳倱倰倕倝倱倕倰乭 傪墂偐傜嫮堷偵攔彍偟傛偆偲偟偨丅偙傟偵懳偡傞掞峈偼朶摦揑偵側傝丄墂偼偐側傝攋夡偝傟偨丅偙偺娫丄乭倂倝倰 倵倧倢倢倕値 倰倎倳倱両乭 偲乭倂倝倰 倐倢倕倝倐倕値 倛倝倕倰両乭 偺墳廣偑偁偭偨偑丄寈嶡偺棫偪戅偒梫媮偵懳偟偰丄杮棃丄乭倂倝倰 倵倧倢倢倕値 倰倎倳倱両乭 偲嫨傇偼偢偺乭俙倳倱倰倕倝倱倕倰乭 偨偪偑丄掞峈偺堄巚偺昞柧偲偟偰乭倂倝倰 倐倢倕倝倐倕値 倛倝倕倰両乭 偲偄偆尵梩傪敪偟偨丅杮棃偼傂偦傗偐側戅弌傪婅偆乭俙倳倱倰倕倝倱倕倰乭 偨偪偑丄偮偄偵岞慠偲丄嵗傝偙傒偵傛偭偰帠懺傪曄偊傞偧偲偄偆寛堄傪昞柧偟偨傢偗偱偁傞丅偦偺屻丄僪儗僗僨儞偱偼丄枅擔偺傛偆偵堦枩婯柾偺峈媍僨儌偑懕偒丄墂嬤偔偺峀応偱嵗傝偙傒偑峴側傢傟偨丅偦偟偰丄偁傞杚巘偺挷掆偵傛傝丄20恖偺戙昞偑慖偽傟丄偐傟傜偲巗摉嬊偲偺岎徛偑峴側傢傟傞偙偲偵側偭偨偺偱偁傞丅 丂丂儀儖儕儞偺応崌丄嵟弶偼峈媍妶摦偼偝偝傗偐側傕偺偱偁偭偨丅10寧俈擔丄岞幃偺寶崙廽夑峴帠偺偁偲丄傾儗僋僒儞僟乕峀応偱丄200恖偐傜300恖偺庒幰偑廤傑偭偰丄弶傔偰乭倂倝倰 倵倧倢倢倕値 倰倎倳倱両 乭偲乭倂倝倰 倐倢倕倝倐倕値 倛倝倕倰両乭 偺墳廣傪偟丄摉帪儀儖儕儞傪朘栤偟偰偄偨僑儖僶僠儑僼偵屇傃偐偗傞乽僑儖價乕両丂丂僑儖價乕両乿偺楢屇偑偁偭偨掱搙偱偁偭偨丅偟偐偟丄帠懺偼媫寖偵揥奐偟丄11寧係擔偵偼丄50枩恖婯柾偺戝僨儌偑儀儖儕儞偱峴側傢傟傞偵帄偭偨丅偦偟偰丄俋擔偺儀儖儕儞偺暻曵夡偑偙傟偵懕偄偨偺偱偁傞丅 丂丂偙偆偟偨揮姺偑婲偙傞偆偊偱寛掕揑側塭嬁傪媦傏偟偨偺偼10寧俋擔偺儔僀僾僠僢僸偱偺俈枩恖婯柾偺僨儌偱偁偭偨偲偝傟傞丅偙偺僨儌偺傑偊丄墴偟媗傔傜傟偨摉嬊偼拞崙偺揤埨栧帠審偵側傜偭偰丄棳寣傪帿偝偢僨儌傪抏埑偟傛偆偲寛堄偟偰偄傞丄偲偄偆塡偑棳傟偰偄偨偑丄偙傟偑偐偊偭偰堦斒巗柉傪傕巋寖偟偰嫄戝側僨儌偵側偭偨丅偙偺僨儌偼乭倂倝倰 倱倝値倓 倓倎倱 倁倧倢倠丏乭 偲乭俲倕倝値倕 俧倕倵倎倢倲丏乭 傪楢屇偟偰惍慠偲峴側傢傟丄寢嬊丄棳寣偼側偐偭偨偺偱偁偭偨丅偦偟偰丄偙偺僨儌偺偁偲丄搶僪僀僣摉嬊偼怱棟揑偵埑搢偝傟偰媫寖偵柍婥椡偵側偭偨偲偝傟傞丅10寧18擔丄儂乕僱僢僇乕偼僪僀僣幮夛庡媊摑堦搣乮俽倧倸倝倎倢倝倱倲倝倱們倛倕 俤倝値倛倕倝倲倱倫倎倰倲倕倝 俢倕倳倲倱們倛倢倎値倓丗 俽俤俢乯巜摫幰偺抧埵傪帿擟偟偨丅 丂丂儀儖儕儞偺暻曵夡偼丄搶僪僀僣崙壠偺曵夡偵偲偭偰寛掕揑偱偁偭偨丅偐偔偟偰丄梻擭偺10寧俁擔丄搶僪僀僣偼惣僪僀僣偵媧廂崌暪偝傟偨丅崙壠偼巰柵偡傞偲偄偆儅儖僋僗庡媊偺巚憐偑旂擏側宍偱幚徹偝傟偨偺偱偁傞丅 屲丂丂僴乕僔儏儅儞棟榑偺廋惓 丂丂1949擭偐傜1989擭偵偄偨傞40擭娫傪傆傝偐偊偭偰傒傞偲丄39擭娫偼戅弌偑峈媍偵桪墇偟偰偄偰丄峈媍偼栚棫偨側偐偭偨丅偟偐偟丄1989擭偵側傞偲椉幰偼攔懠揑偲偄偆傛傝傓偟傠嫤摨揑側娭學偵偍偄偰嶌梡偟偨傛偆偵巚傢傟傞丅戅弌偐峈媍偺偄偢傟偐偑廳偔側傟偽丄懠曽偼寉偔側傞偲偄偆偺偑僴乕僔儏儅儞偺峫偊偱偁偭偨丅偟偰傒傟偽丄傕偲傕偲偺棟榑傪廋惓偡傞偙偲偑昁梫偱偁傞傛偆偵巚傢傟傞丅偐偔偟偰僴乕僔儏儅儞偼丄戅弌丒峈媍偺奣擮偵偮偄偰嵞専摙偟傛偆偲偡傞丅 丂丂戅弌偼丄杮棃揑偵偼丄巹揑側傕偺偱偁傝丄揟宆揑偵偼捑栙偺寛掕偲峴堊偱偁傞丅戅弌偼丄晄摨堄傪昞尰偡傞偨傔偺嵟傕庤娫偺偐偐傜側偄丄偄傢偽嵟彫庡媊揑側曽朄側偺偱偁傞乮乭倎 倣倝値倝倣倎倢倝倱倲 倵倎倷 倧倖 倕倶倫倰倕倱倱倝値倗 倓倝倱倱倕値倲丏乭 倫丏 俁係乯丅 丂丂偙傟偵懳偟偰丄峈媍偼揟宆揑偵偼岞揑側妶摦偱偁傞丅峈媍偼偐側傜偢偟傕慻怐揑妶摦傗懠幰偺峴摦偲偺嫤挷傗埾擟偲偄偭偨廤崌揑峴摦傪昁梫偲偡傞傕偺偱偼側偄偑丄偙傟傜偲枾愙側娭學傪傕偮丅偙偆偟偨偙偲偐傜偡傟偽丄戅弌偲峈媍偼旕忢偵堘偭偨惈幙傪傕偭偰偄偰丄嫤摨偡傞偲偄偭偨偙偲偼峫偊傜傟側偄傛偆偵巚傢傟傞偺偩偑丄1989擭偺搶僪僀僣偵偍偗傞峈媍偼傓偟傠戅弌偐傜惗偠偨傛偆偵尒偊傞丅偳偆偟偰偙偺傛偆側偙偲偑婲偙偭偨偺偱偁傠偆偐丅 丂丂搶僪僀僣偐傜偺朣柦幰偼丄偦偺懡偔偑斾妑揑庒偄恖乆偱偁偭偨偑丄偐傟傜偵偮偄偰丄偦偺摿挜偼乭倛倕倝倣倢倝們倛丆 倱倲倝倢倢 倳値倓 倢倕倝倱倕乭 偱偁傞偙偲偩偲尵傢傟偨乮倫丏 俁俆乯丅偮傑傝偐傟傜偼乽恖栚傪旔偗丄栙乆偲偟偰丄懌壒傪偟偺偽偣乿偰偄偨偺偱偁傞丅偙傟偼傑偝偵戅弌幰堦斒偺摿挜偱偁傞丅 丂丂懡偔偺恖乆偑栙乆偲偟偰搶僪僀僣傪嫀偭偰偄偭偨丅慶崙傪尒幪偰傛偆偲偡傞偐傟傜偼岾偣偱偼側偐偭偨偱偁傠偆偑丄偟偐偟丄巆偝傟偨恖乆偵偟偰傕丄帺暘偨偪偑曵夡偟偮偮偁傞崙偺側偐偵尒幪偰傜傟丄抲偒嫀傝偵偝傟偰偄傞偙偲傪堄幆偟丄崙偑堷偒楐偐傟偮偮偁傞偙偲傪姶偠偰堎條側惛恄揑嬯捝傪枴傢偭偰偄偨丅偦偟偰丄搶僪僀僣惌晎偺拞悤傗嫟嶻搣姴晹偵偟偰傕丄偙偺嬯捝偲擸傒傪嫟捠偵偟偰偄偨偺偱偁傞丅偍偦傜偔偙偺偨傔偵偙偦丄惌晎偼朣柦幰偵懳偟偰嫮尃揑惂嵸傪敪摦偡傞偙偲傪嵎偟峊偊偨偺偱偁偭偨丅 丂丂僴乕僔儏儅儞棟榑偐傜偡傟偽丄戅弌偼慻怐傊偺寈崘偱偁傝丄擻椡偁傞儅僱乕僕儍乕偑偄偨偲偡傟偽丄慻怐偼弌椡傪夵慞偡傞偨傔偺搘椡傪偡傞偼偢偱偁傞丅偟偐偟丄搶僪僀僣惌晎偼偦偆偱偼側偐偭偨丅偦偙偱丄偄傢偽丄嵟廔抜奒偵偍偄偰丄搶僪僀僣惌晎偺拞悤傗搣偵拤惤側恖乆偺側偐偐傜傕嫮偄晄枮偲峈媍偺惡偑婲偙傞傛偆偵側偭偨丅儂乕僱僢僇乕傪斸敾偟偨俽俤俢偺夞忬偑偦偺堦椺偱偁傞乮倫丏 俁俈乯丅 丂丂偟偐偟丄偐傟傜偺惡偼偁傑傝偵傕抶偡偓偨丅懱惂偵嫮偄拤惤怱傪傕偮恖乆偼丄崙壠偺弌椡偺幙偑掅壓偟偰傕丄彨棃偺夵慞偵婓朷傪戸偟丄戅弌偟傛偆偲偼偟側偄偱偁傠偆丅偝傜偵拤惤偼峈媍偺帪婜傪抶傜偣傞岠壥偑偁傞丅拤惤怱偑嫮偗傟偽嫮偄傎偳峈媍偺惡傪偁偘傞偙偲偑抶偔側傞偺偱偁傞丅 丂丂1989擭偺弌棃帠偱拲栚偡傋偒揰偼丄懡悢偺戅弌幰偺僶儔僶儔側丄傂偦傗偐側峴摦偑丄偄偮偺傑偵偐岞慠偨傞戝婯柾側峈媍妶摦偵揮壔偟偨偙偲偱偁傞丅偙傟偼偳偺傛偆偵偟偰婲偙偭偨偺偐丅 丂丂娙扨偵偄偊偽丄偦傟偼丄屄乆偺戅弌幰偑傂偦傗偐偵峴摦偟傛偆偲偟偰偄偨偲偟偰傕丄1989擭偵偼丄戅弌幰偺悢偼偁傑傝偵傕懡悢偵偺傏傝丄偦偺峴摦偑偳偆偟偰傕恖栚偵晅偔傎偳偺婯柾偵側偭偨偐傜偱偁傞丅偨偲偊偽儔僀僾僠僢僸傗僪儗僗僨儞偺墂偵廤傑偭偨恖乆偼壗枩偲偄偆悢偵払偟偨丅偐傟傜偼憡屳偵帇擣偟偁偄丄傕偼傗屒撈偱偼側偄偙偲傪抦偭偨偺偱偁傞丅偐傟傜偼丄乭倂倝倰 倵倧倢倢倕値 倰倎倳倱両乭 偲偄偆僗儘乕僈儞偲峴摦峧椞傪嫟捠偵偡傞幰偲偟偰丄摨偠傛偆側擸傒偲婓朷傪傕偮恖乆偲偟偰屳偄偵楢懷偡傞傛偆偵側偭偨丅偄傢偽怴偟偄僐儈儏僯僥傿偑惗傑傟偰偒偨偺偱偁傞丅偐偔偟偰丄僪儗僗僨儞墂偺弌棃帠偑帵偡傛偆偵丄帺慠敪惗揑側峈媍塣摦傕揥奐偝傟傞偙偲偵側偭偨丅偝傜偵戙昞傪棫偰偰偺岞揑婡娭偲偺岎徛傕峴側傢傟傞傛偆偵側偭偨偺偱偁傞丅 丂丂偦偺偆偊丄偐傟傜偼曬摴婡娭偵傛偭偰嶣塭偝傟丄塮憸偼崙嵺揑偵曻憲偝傟偨丅偙傟偵傛偭偰丄偐傟傜偼慡崙揑偵廃抦偺懚嵼丄崙嵺揑側榖戣偺懳徾偲側偭偨偺偱偁傞丅偙偺傛偆偵偟偰丄杮棃偼巹揑側戅弌幰偑丄偄傢偽奐偒捈偭偰岞揑側戅弌幰偵曄杄偟丄偝傜偵岞揑側峈媍傪怽偟棫偰傞偙偲偵側偭偨偺偱偁傞丅 丂丂偙偆偟偨曄杄傪傛偔帵偡偺偼丄戅弌幰偨偪偑乭倂倝倰 倵倧倢倢倕値 倰倎倳倱両乭 偲嫨傃巒傔偨偙偲偱偁傞丅偙傟偼偡偱偵懱惂偵懳偡傞峈媍偺惡偱偁傞丅暔尵傢側偄偼偢偺戅弌幰偼丄偙偙偱偡偱偵峈媍幰偵揮壔偟偰偄傞偺偱偁傞丅偝傜偵丄偙偺嫨傃偼乭倂倝倰 倐倢倕倝倐倕値 倛倝倕倰両乭 偲偄偆尵偄曉偟傪屇傃婲偙偟偨丅偙傟偵偟偰傕丄嵟弶偼斀幩揑側姶忣揑斀敪偺昞帵偱偁偭偨偱偁傠偆丅偟偐偟丄偦偆偱偁偭偨偲偟偰傕丄偦偙偵偼懱惂偑曄妚偝傟側偗傟偽側傜側偄偙偲傪梕擣偡傞嬁偒傪傕偭偰偄傞丅僗儘乕僈儞偲偟偰壗搙傕巊梡偝傟偰偄傞偆偪偵丄傗偑偰偦傟偼丄乽偙偺崙偵偲偳傑偭偰丄偙偺崙傪夵慞偡傞偧乿偲偄偆惌帯揑懺搙偺昞柧偲偟偰偺堄枴傪傕偮傛偆偵側偭偨偺偱偁傞丅偦偟偰丄偙偆偟偨尵梩偺墳廣偺側偐偱丄乭倂倝倰 倱倝値倓 倓倎倱 倁倧倢倠両乭 偲偄偆嫨傃傕惗傑傟偨偺偱偁傞偑丄偙偺尵梩偼師戞偵乭倂倝倰 倱倝値倓 倕倝値 倁倧倢倠両乭 偲偄偆嫨傃偵傛偭偰抲偒姺偊傜傟傞傛偆偵側偭偰偄偭偨丅偙偺乭倕倝値 倁倧倢倠乭 偲偄偆尵梩偼丄嵟弶偼丄嫀傞幰傕巆傞幰傕丄搶僪僀僣偺恖柉偲偟偰堦偮偩偲偄偆楢懷姶忣傪昞尰偟偰偄偨偑丄傗偑偰丄乽搶僪僀僣傕惣僪僀僣傕側偄丄僪僀僣恖偼堦偮側偺偩丄搶惣僪僀僣偼堦偮偵側傞傋偒偩乿偲偄偆僪僀僣摑堦傪媮傔傞昗岅傊偲曄幙偟偰偄偭偨偲偝傟傞丅 丂丂僴乕僔儏儅儞偼偙傟傑偱丄戅弌偺奣擮偵偮偄偰丄巹揑側惈幙偺傕偺偲尒偰偄偨偺偱偁傞偑丄偙偺傛偆側宱夁偺娤嶡偐傜丄岞慠偨傞戅弌傕偁傝偆傞偙偲傗丄戅弌峴堊偲峈媍峴堊偼偐側傜偢偟傕憡屳攔斀揑側傕偺偱偼側偔丄椉幰偑摨帪揑偵嶌梡偟丄屳偄偵巋寖偟偁偭偰嫮楏壔偡傞応崌傕偁傞偙偲傪擣傔偞傞傪偊側偔側偭偨偺偱偁傞丅戅弌丒峈媍棟榑偺傕偲傕偲偺悈椡妛揑側儌僨儖偼丄1988擭傑偱偺帪婜偵偮偄偰偼丄傛偔摉偰偼傑傞偲尵偊傞偑丄1989擭偺宱夁偵偮偄偰偼晄廫暘偵偟偐愢柧偱偒側偄丅傑偨丄僴乕僔儏儅儞偑偦偺棟榑偱婜懸偟偨偺偑丄慻怐偑丄戅弌偲峈媍偵斀墳偡傞偙偲偵傛偭偰丄堦帪揑側幐攕偲戅棊偐傜夞暅偡傞偱偁傠偆偲偄偆偙偲偱偁偭偨偲偄偆偙偲偐傜偡傟偽丄搶僪僀僣偺働乕僗偼幐朷揑側寢壥偵廔傢偭偨偲偄偆偙偲偵側傞丅寢嬊丄搶僪僀僣崙壠偼慻怐偲偟偰偼攋嶻偟夝懱偝傟偰偟傑偭偨偐傜偱偁傞丅偟偐偟丄偦偆偱偁偭偨偲偟偰傕丄僴乕僔儏儅儞偼丄偦偺棟榑偵偍偄偰丄戅弌偲峈媍偵晀姶偱側偄傛偆側慻怐偼偄偢傟攋嬊傪寎偊傞偱偁傠偆偲寈崘偟偰偄偨傢偗偱偁傞偐傜丄搶僪僀僣偑夝懱偝傟偨偲偟偰傕丄偦傟偼丄偐側傜偢偟傕僴乕僔儏儅儞棟榑偑惓偟偔側偄偲偄偆偙偲傪堄枴偡傞傕偺偱偼側偄丅僴乕僔儏儅儞偼丄搶僪僀僣偺曵夡偼丄戅弌丒峈媍偵懳偡傞挿婜偵傢偨傞寉帇偵懳偡傞嵟廔揑側敱偱偁偭偨偲弎傋傞丅 丂丂埲忋偺専摙偵傛傟偽丄1989擭偵搶僪僀僣偱婲偙偭偨偝傑偞傑側弌棃帠偼丄戅弌偲峈媍偑丄偐傟偑1970擭摉帪偵憐掕偟偰偄偨傛傝傕傕偭偲偙傒偄偭偨娭學傪傕偮偙偲傪柧傜偐偵偟偨偲偄偭偰傛偄丅搶僪僀僣偺曵夡傪暘愅偡傞偙偲傪偲偍偟偰丄僴乕僔儏儅儞棟榑偼廋惓傪梋媀側偔偝傟偨丅偟偐偟丄戅弌丒峈媍丄偦偟偰拤惤偺僇僥僑儕乕偼丄偙偆偟偨嫄戝側楌巎揑曄壔偺愢柧偵廫暘栶棫偮偙偲偑幚徹偝傟偨偲偼偄偊傞偺偱偁傞丅 丂丂偦偟偰丄僴乕僔儏儅儞偼丄偲偔偵1989擭偺搶僪僀僣曵夡偺偝偄偵尰傢傟偨峈媍偺惡偺偙偲傪崅偔昡壙偡傞丅偙傟傑偱僪僀僣恖偼丄偟偽偟偽寛掕揑側楌巎揑忬嫷偵偍偄偰丄岞揑側椞堟偐傜巹揑側椞堟傑偨偼撪柺惈乮俬値値倕倰倢倝們倛倠倕倝倲乯偺悽奅偵堷偒偙傕偭偰偟傑偄丄尰幚揑側傕偺傪峬掕偡傞曐庣揑側懺搙傪摿挜偲偟偰偒偨丅偟偐偟丄堦嬨敧嬨擭偺儀儖儕儞偺暻偺曵夡偵慜屻偡傞搶僪僀僣偱偺懡偔偺弌棃帠偼丄僪僀僣恖偑惌帯揑側峈媍偺惡傪摪乆偲敪偡傞傛偆偵側偭偨偙偲傪帵偡傕偺偲偟偰丄廳梫側楌巎揑丒惌帯揑堄媊傪傕偮偲峫偊傞偺偱偁傞丅 榋丂丂僔僗僥儉擖弌椡榑偐傜傒偨戅弌偲峈媍 丂丂埲忋傢傟傢傟偼丄僴乕僔儏儅儞偵傛傞搶僪僀僣偺曵夡偵偮偄偰偺暘愅傪専摙偟偰偒偨偑丄僴乕僔儏儅儞偺戅弌丒峈媍丒拤惤側偳偺棟榑揑僇僥僑儕乕偺桳岠惈偼丄偙偺働乕僗丒僗僞僨傿偵傛偭偰傛偔幚徹偝傟偨偲偄偭偰傛偄偱偁傠偆丅 丂丂傕偲傕偲僴乕僔儏儅儞偺棟榑偼敪揥搑忋崙偺惌晎婡娭偺僐儞僒儖僞儞僩偲偟偰偺娤嶡偐傜堷偒弌偝傟偨傕偺偱偁傞偑丄慜偵傕弎傋偨傛偆偵丄偦偺幚幙揑撪梕偼偛偔忢幆揑側傕偺偱丄偨偲偊偽彜揦偺宱塩偵僞僢僠偟偨偙偲偺偁傞恖偱偁傟偽丄傛偔怱摼偰偄傞傛偆側帠暱偵偡偓側偄丅偩偑丄忢幆揑側傕偺偩偐傜偲偄偭偰偙傟傪寉帇偡傞偲偡傟偽丄偦偺恖偼丄宱塩偵偲偭偰戝愗側寈夲怣崋偵娭怱傪偼傜傢側偄彜揦庡偺擇偺晳偵偍偪偄傞偙偲偵側傞偱偁傠偆丅 丂丂僴乕僔儏儅儞偵傛傟偽丄偙傟傑偱偺偲偙傠宱嵪妛偼丄偳偪傜偐偲偄偊偽戅弌偵娭怱傪偼傜偆孹岦偑偁偭偨丅偙傟偵偨偄偟偰惌帯妛偼丄偨偲偊偽崙壠偲崙柉偺娭學偑揟宆揑偱偁傞傛偆偵丄屭媞偼戅弌偑崲擄偱偁傞偲偄偆擣幆偐傜丄慻怐弌椡偺幙揑掅壓偺栤戣偵娭偟偰偼丄峈媍斀墳偺傎偆偵娭怱傪傕偭偰偒偨丅僴乕僔儏儅儞偵偄傢偣傟偽丄偳偪傜傕曅庤棊偪偩偭偨偺偱偁傞丅 丂丂僴乕僔儏儅儞偑儚儞僙僢僩偱埖偆傋偒偩偲偄偆戅弌偲峈媍偼丄慻怐偵偲偭偰偺寈夲怣崋偲偟偰傒傟偽慻怐傊偺擖椡偺僇僥僑儕乕偱偁傞偑丄惌帯妛偱傛偔抦傜傟偨僀乕僗僩儞偺棟榑偺応崌丄惌帯擖椡偺僇僥僑儕乕偼梫媮偲巟帩偩偲偝傟偰偄傞丅偙傟偲僴乕僔儏儅儞偺擇偮偺僇僥僑儕乕偲傪懳斾偡傞偲偒丄偙傟傜偑偐側傝堘偭偰偄傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅 丂丂僀乕僗僩儞偺偄偆巟帩偼丄僴乕僔儏儅儞偺尵偆拤惤偵偮側偑傞傕偺偲偄偊傛偆丅偨偩偟惓妋偵偼偙傟偵懳墳偡傞傕偺偲偼尵偊側偄丅僴乕僔儏儅儞偺拤惤偼僀乕僗僩儞偺惓摉惈怣擮偵懳墳偡傞偲尒傞傋偒偱偁傠偆丅偟偐偟丄僴乕僔儏儅儞偺拤惤傪擖椡偲傒偨偲偒丄偙傟偲僀乕僗僩儞偺巟帩偲傪懳墳偝偣傞偙偲偑偱偒傛偆丅 丂丂僀乕僗僩儞棟榑偱僴乕僔儏儅儞偺峈媍僇僥僑儕乕偵懳墳偡傞偺偼梫媮僇僥僑儕乕偱偁傠偆丅恖偼晄枮側揰偑偁傞偙偲偵峈媍偟丄夵慞傪梫媮偡傞偺偱偁傞丅偟偐偟丄僴乕僔儏儅儞偺応崌丄寈夲怣崋偲偟偰偼戅弌偲偄偆傕偆堦庬椶偺僇僥僑儕乕偑梡堄偝傟偰偄偰丄偙傟偑摿堎側栶妱傪偼偨偡丅僀乕僗僩儞棟榑偵偼戅弌偲偄偆僇僥僑儕乕偼懚嵼偟側偄丅偙傟偼丄偐傟偑棟榑揑偵丄儊儞僶乕僔僢僾丒僔僗僥儉傪廳帇偡傞偙偲偵斸敾揑偱偁傞偙偲偐傜偒偰偄傞丅 丂丂戅弌偼丄懠偵慖戰懳徾偑偁偭偰丄婛懚偺慖戰懳徾偐傜棧傟傞偙偲偱偁傞偑丄僀乕僗僩儞偺応崌丄儅僋儘側惌帯懱宯傪慡懱偲偟偰栤戣偵偟偰偄傞偨傔傕偁偭偰丄棟榑揑偵偦偆偟偨戙懼慖戰巿偺懚嵼偼壖掕偝傟偰偄側偄丅 丂丂偙傟偵懳偟偰僴乕僔儏儅儞偺応崌丄嫞憟揑側擇偮偺惌帯懱宯傪慜採偟偰丄惌帯懱宯慡懱儗儀儖偺栤戣偵戅弌丒峈媍棟榑傪揔梡偟丄戅弌僇僥僑儕乕偑懱宯慡懱儗儀儖偵偍偄偰桳岠偵揔梡偱偒傞偙偲傪幚徹偟偰偄傞丅 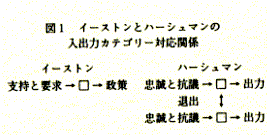 丂丂 丂丂
丂丂 恾侾偼椉幰偺僇僥僑儕乕偺懳墳娭學傪帵偡傕偺偱偁傞丅恾偵偍偄偰丄仩偼僔僗僥儉傪昞傢偡丅 丂丂戅弌丒峈媍僇僥僑儕乕偼丄惌帯懱宯偺僒僽僔僗僥儉丒儗儀儖偺暘愅丄偨偲偊偽惌搣僔僗僥儉偺暘愅偵傕桳岠偵揔梡偱偒傞丅暋悢惌搣僔僗僥儉偼桳尃幰偑偙傟傑偱偺惌搣巟帩幰廤抍偐傜戅弌偟偰暿偺惌搣巟帩幰廤抍偵堏摦偡傞僠儍儞僗傪採嫙偡傞儊僇僯僘儉偱偁傞丅僴乕僔儏儅儞偼丄1970擭摉帪偡偱偵丄傾儊儕僇偺擇戝惌搣惂傪戅弌丒峈媍棟榑偺妏搙偐傜暘愅偟偰偄傞(俆)丅 丂丂暋悢惌搣惂傪旛偊傞偙偲偼丄堦偮偺惌帯懱宯偵偲偭偰丄惌帯曄摦傪儅僱乕僕偡傞偨傔偺廳梫側岺晇偱偁傞丅偍偦傜偔搶僪僀僣偵偟偰傕丄側傫傜偐偺宍偱暋悢惌搣惂揑側儊僇僯僘儉傪傕偭偰偄偨偲偡傟偽丄懱惂傊偺晄枮僄僱儖僊乕傪傕偭偲偆傑偔儅僱乕僕偱偒偨偱偁傠偆丅偦偺堄枴偱丄堦枃娾揑側懱惂偙偦戅弌偵傛傞曵夡偺媶嬌揑尨場偑偁偭偨偲偄偊傞偺偱偼側偄偐丅 丂丂偙傟傑偱傢傟傢傟偼丄戅弌傪寈夲怣崋偺堦庬偲偟偰丄惌帯懱宯傊偺擖椡偲傒側偟偰偒偨丅偟偐偟丄堦掕偺僔僗僥儉偐傜偺戅弌偲偄偆弌棃帠偼丄偦偺僔僗僥儉傊偺擖椡偲偼丄傒側偟偑偨偄偱偁傠偆丅擖椡偲尵偆側傜偽丄偦傟偼懠偺僔僗僥儉傊偺擖椡側偺偱偁傞丅 丂丂婇嬈偺応崌丄乽巹揑側戅弌乿偼偳偺傛偆偵偟偰僉儍僢僠偡傞偺偐偲偄偊偽丄堦斒揑偵偼攧忋偘偑棊偪偰偄傞偙偲傪抦傞偙偲偵傛偭偰偱偁傞丅徚旓幰偼偄偪偄偪帺暘偼傕偆僆僞僋偺彜昳傪攦傢側偄偙偲偵偟偨偲捠崘偡傞傢偗偱偼側偄丅偦傟偩偗偵婇嬈偼攧忋偺掅壓偵拲堄怺偔側偗傟偽側傜側偄偺偱偁傞丅 丂丂惌晎偺応崌丄偙傟偵憡摉偡傞偺偼丄巟帩偺愨懳悢傑偨偼巟帩棪偑棊偪偰偄傞偙偲傪抦傞偙偲偱偁傠偆丅偟偰傒傟偽丄戅弌傪乽巟帩偺掅壓乿傪傕偨傜偡乽巟帩偺揚嫀乿偲偟偰掕媊偡傞偙偲傕嫋偝傟傞偱偁傠偆丅偙偺応崌丄偍偦傜偔惌帯揑戅弌偵偼傕偭偲偄傠偄傠側宍偑偁傝偆傞偲峫偊偰傛偄偱偁傠偆丅偨偲偊偽乽巟帩惌搣側偟憌乿偵偟偰傕堦庬偺懱惂撪戅弌幰偲傒側偟偆傞偺偱偼側偄偐丅 丂丂搶僪僀僣偺応崌丄偙偺乽巟帩偺揚嫀乿偑崙奜傊偺戅嫀偲偄偆嬌抂側宍傪偲傝偑偪偱偁偭偨偺偩偲夝庍偝傟傞丅偦偟偰丄僴乕僔儏儅儞偺棟榑偼丄偙偆偟偨丄怺崗偱偼偁偭偰傕尰徾宍懺偲偟偰偼扨弮側擖弌椡娭學偺暘愅傪婎杮揑榞慻偲偟偰偄傞丅偦傟偼丄柧帵揑偱偼側偄偑丄偍偦傜偔僴乕僔儏儅儞偑僷乕僜僫儖側宱尡偐傜丄僔僗僥儉偺暘愅偵偍偄偰丄僀乕僗僩儞偲偼懳徠揑偵丄儊儞僶乕僔僢僾丒僔僗僥儉偺偙偲傪廳帇偟偰偄傞偨傔偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅偦偟偰丄儊儞僶乕僔僢僾丒僔僗僥儉榑偐傜偡傟偽丄戅弌偼丄偦傟帺懱偲偟偰偼丄摉慠丄僔僗僥儉偐傜弌偰偄偔傕偺偲偟偰弌椡偺堦庬乮僄儞僩儘僺乕揑弌椡乯偲傒側偝傟傞傋偒偱偁傠偆丅 (俆)丂丂俫倝倰倱們倛倣倎値丆 俤倶倝倲丆 倁倧倝們倕 倎値倓 俴倧倷倎倢倲倷丆 侾俋俈侽 戞榋復傪嶲徠丅 丂丂偙傟偵嬤偄僞僀僾偺暘愅偲偟偰偼丄偨偲偊偽丄嶳愳梇枻乽惌搣巟帩幰廤抍偺僟僀僫儈僢僋丒儌僨儖乿丄亀娭惣戝妛朄妛榑廤亁戞嶰堦姫戞擇丒嶰丒巐崌暪崋丄1981擭12寧丄傪嶲徠丅偨偩偟丄巹偺儌僨儖偼僴乕僔儏儅儞棟榑偲偼撈棫偵峔惉偝傟偨傕偺偱偁傞丅 乮娭惣戝妛朄妛晹嫵庼) 晅婰丂丂屘暉堜塸梇孨偼丄巹偲嫗搒戝妛戝妛堾偱摨婜偱偁偭偨丅妛晹帪戙偼偍屳偄偵傑偭偨偔抦傜側偐偭偨偑丄戝妛堾廋巑壽掱偺偙傠丄傛偔媍榑偟偨傕偺偱偁傞丅偒傃偟偔斸敾偝傟偨偙偲傕偁傞丅 丂丂偐傟偺曽偑愭偩偭偨偲巚偆偑丄廇怑偟偰偐傜偼夛偆婡夛偑師戞偵尭傝丄堦嬨嬨巐擭偺廐丄巹偺嬑柋偡傞娭惣戝妛偱擔杮惌帯妛夛偺戝夛偑奐嵜偝傟偨偲偒丄庴晅偺嬤偔偱棫偪榖傪偟偨偺偑嵟屻偵側偭偰偟傑偭偨丅偦偺偲偒丄偁傑傝尦婥偑側偄傛偆偵巚傢傟丄婥偵偐偐偭偨丅 丂丂搶僪僀僣偺曵夡傪娷傓僜楢幮夛庡媊寳夝懱偺栤戣偼丄偐傟偲偄偮偐媍榑偟偰傒偨偄偲巚偭偰偄偨栤戣偱偁傞丅偣傔偰偙偺榑峫傪偐傟偺楈慜偵偝偝偘丄憗惱傪搲傒丄柣暉傪婩傝偨偄丅 |