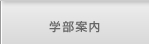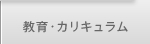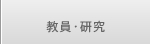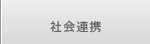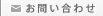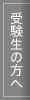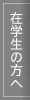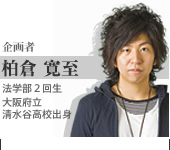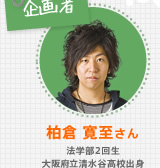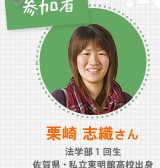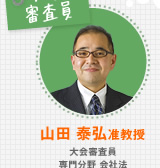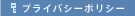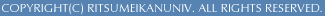- 現在表示しているページの位置
-
- HOME
- 進路・キャンパスライフindex
- 課外自主活動
- 法学部ゼミナール大会

法学部ゼミナール大会は、学生が主体となって企画・運営している法学プレゼンテーションの場。2008年に第1回目を開催したばかりの新しい取り組みです。本大会は、学生一人ひとりが自主的に学ぶ姿勢を持ち、仲間と議論を交わし、学習内容を公の場で発表する絶好の機会。学びの楽しさや奥深さを実感することで、より積極的な学問探究心を育成することが狙いです。
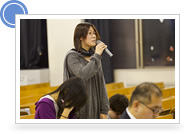
本大会は、必修や選択制の授業ではなく、法学部生なら誰もが出場できる自由参加型のコンテストです。(1回生は1クラス1チーム参加が必須)各チームが自由に研究テーマを設定し、それぞれの見解・主張を皆の前でプレゼンテーション。専門教員・学生による審査を経て入賞者を決定します。受付や司会はもちろん、審査基準の設定など運営の全てを学生主体で行います。
チームごとに研究テーマを設定し、メンバーそれぞれが担当項目の資料を収集。互いの意見を交換し合い、方向性を決めていく。

プレゼン用資料作成と平行して、聴講者に配布するためのレジュメを作成。1回生はオリター等にチェックしてもらい、ブラッシュアップしていく。

いよいよ発表のとき。大講義室の舞台上で代表者が研究成果をプレゼンし、聴講者や審査員らの質疑に答える。優秀チームには表彰と賞金の授与が。

- 自主的に学ぶ姿勢
- 文章・資料作成能力
- 研究能力(問題発見・解決能力)
- ディスカッション能力
- プレゼンテーション能力
|
|
|
| 開催頻度 | 年1回 |
|---|---|
| 参加規模 | 約50チーム(2回生以上は自由参加) |
| 発表テーマ例 |
|