【壁紙プレゼント】てこちゃんと中国古典の名句を合わせた壁紙を作りました。設定方法:サイズを選択してクリックすると画像が表示されるので、画像の上で右クリックして「背景に設定」を選んでください。 1920×1080(アスペクト比16:9)、 1680×1050(8:5)、1280×1024(5:4)、1024×768(4:3)の四種類を用意しました。 |
|
 |
その1 黄庭堅「戲れに王定國の門に題するに答ふ兩絶句」その二 頗る歌舞を知るに竅鑿すること無かれ 我が心は塊然として帝江のごとし 花裏の雄蜂 雌蛺蝶 時を同じくするも本より自ら雙を作さず (そのままで)歌舞に熟知しているのであるから目鼻耳の穴をあけてくれようとするな(無理やりおせっかいなことはしないでくれ)。私の心は無心の土くれのように素朴でそんな帝江のような境地である。花の中のオスの蜂とメスの蝶とは、同じ時を過ごしても本来(種が異なるから)魅かれあってつがいになることは無いのだ。 任淵の注によれば、塊然は『荘子』応帝王篇にある言葉。“花裏雄蜂雌蛺蝶、同時本自不作雙”は李商隠「柳枝詞」の“花房與蜜脾、蜂雄蛺蝶雌、同時不同類、那復更相思”句をふまえています。 |
| 1920×1080 1680×1050 1280×1024 1024×768 |
|
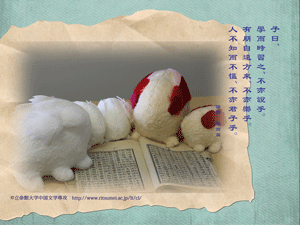 |
その2 『論語』學而篇 子曰く、學びて時にこれを習ふ、亦た説(よろこ)ばしからずや。 朋有り遠方より来(きた)る、亦た樂しからずや。 人知らずして慍(うら)みず、亦た君子ならずや。 先生はおっしゃった、学んで適切な時にこれを実修する、なんとも悦ばしいことだ。(学問を通じて)遠くからも友達が来る、なんとも楽しいことだ。人に自分のことを知ってもらえなくとも恨まない、なんとも立派な人物だ。 『論語』冒頭の有名な文。学ぶことが好きな孔子らしい言葉です。立命館の衣笠キャンパスにある学而館はこの句から名をとっています。 ちなみに写真でてこちゃんたちが熱心に読んでいるのは『七書正義』です。 |
| 1920×1080 1680×1050 1280×1024 1024×768 |
|
 |
その3 孟浩然「春曉」 春眠 曉(あかつき)を覺えず 處處 啼鳥を聞く 夜來 風雨の聲 花落つること知る多少 春の眠りのここちよさに夜明けに気付かず(布団の中でうとうとしていると)、あちらこちらから鳥の声が聞こえる。昨夜は雨風の音がしていたが、花はどれくらい落ちただろうか。 春先、寝坊の言い訳によく使われる句(私だけ?)。最後の「花落知多少」は訳者によって様々な読み方があるので、その違いを楽しんでみるのも良いと思います。 写真は寝床の中のてこちゃん。春の句なのでピンク系にしてみました。 |
| 1920×1080 1680×1050 1280×1024 1024×768 |
|
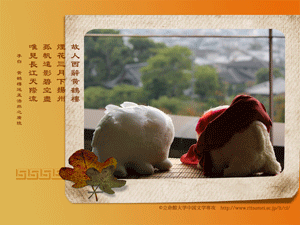 |
その4 李白「黃鶴樓にて孟浩然の廣陵に之くを送る」 故人 西のかた黃鶴樓を辭し 煙花三月 揚州に下る 孤帆の遠影 碧空に盡き 唯見る 長江の天際に流るるを 古くからの友人が西の方で黄鶴楼を後にし、花かすみが立ちこめる三月に揚州に下ってゆく。(君がゆく様を想像してみるに)ぽつんと一つ遠くに浮かぶ船はやがて青空のかなたに見えなくなり、ただ長江が天の果てまで流れているのを見つめるばかりだ。 図らずも上の詩の作者孟浩然を送るという内容になっています。 写真ではてこちゃん(黄)を去ってゆく友人(一応旅支度)に見立て、高いところから遠くを見ながら別れに際し感慨にふける様子を表現してみました。 |
| 1920×1080 1680×1050 1280×1024 1024×768 |
|
 |
その5 陶淵明「子を責む」 白髮は兩鬢を被い 肌膚 復た實(ゆたか)ならず 五男兒有りと雖も 總べて紙筆を好まず 阿舒は已に二八なるに 懶惰なること故(まこと)に匹(たぐい)無し 阿宣は行(ゆく)ゆく志學なるも 而も文術を愛さず 雍と端とは年十三なるも 六と七を識らず 通子は九齡に垂(なんな)んとするに 但だ梨と栗とを覓(もと)む 天運 苟しくも此の如くんば 且(しばら)く杯中の物を進めん (私の)白髪は左右の鬢をおおい、肌のハリツヤも無くなった。男の子五人がいるが、皆勉強を好まない。(長男の)阿舒は十六歳になるが、無類の怠け者だ。(次男の)阿宣はもうすぐ十五歳をむかえるというのに、(志学という言い方に反して)文章学問の道に興味がない。(その下の)雍と端はふたりとも十三歳だが、六と七の区別もつかない。(末っ子の)通子も九歳になろうというのに、ただ梨とか栗とかいうものをねだるだけだ。まあ運命がこうであるというのなら、とりあえず(それはいいとして)酒を飲もう。 作者が「うちのせがれどもは不出来でね…」とか言いつつ酒を飲む姿が目に浮かびます。解釈には意見が分かれるところですが、口ではどうのこうの言いながら子供たちへの愛情が感じられる詩ではないでしょうか。 写真はちびてこちゃんをやんちゃな子供に見立ててみました。 |
| 1920×1080 1680×1050 1280×1024 1024×768 |
|
 |
その6 孟郊「游子吟」 慈母 手中の線(いと) 游子 身上の衣 行に臨んで密密に縫い 意は恐る 遲遲として歸らんことを 誰か言ふ 寸草の心 三春の暉(ひかり)に報い得んと 慈悲深い母が旅に出る息子のために手づから服を縫ってくれた。出発にあたって縫い目を細かくしっかり仕立てつつ、息子の帰りが遅くなりはしないかと心配してくれる。誰が言うのだろうか、かぼそい草のような子の心が、春の暖かい日差しのような大きな親の恩に報いることができると。 作者の孟郊は若い頃から苦労して五十歳近くになってようやく科挙に合格した人。この詩は、やっと地方の低い役人の職を得て老いた母親を呼び寄せたときの作品だといわれています。 写真はちびてこちゃんのために何かを編んであげているてこちゃん。ちょっとサイズが合わないみたいですが。 |
| 1920×1080 1680×1050 1280×1024 1024×768 |
|
 |
その7 袁枚「意に得るところ有り數絶句を雜書す」 説ふ莫(なか)れ 光陰は去って還らずと 少年の情景 詩篇に在り 燈痕 酒影 春宵の夢 一度(ひとたび) 謳吟すれば 一に宛然たり 言わないでくれ、光陰は去れば二度と戻ってこないものだなどと。若い頃の情景は詩篇の中にしっかりと残っているではないか。灯のあとも、酒の色も、春の夜の夢も、ひとたび詩を吟ずれば、その場にいるかのように眼前に浮かんでくる。 袁枚は清代の学者。詩については感情のありのままを発露する性霊説を唱えました。この詩は乾隆42年(1777)の作で、九首の一です。 写真は訪ねてきた刑天と旧交を温めるてこちゃんたち。上半身が寒そうな刑天に自分が編んだマフラー(?)をそっと差し出すてこちゃん。 |
| 1920×1080 1680×1050 1280×1024 1024×768 |
|
 |
その8 王安石「初夏即事」 石梁 茅屋(ぼうおく) 彎碕(わんき)あり 流水 濺濺(せんせん)として 兩陂(りょうひ)を度(わた)る 晴日 暖風 麥氣を生じ 緑陰 幽草 花時に勝れり 石の橋、かやぶきの家、そして曲がりくねった堤の岸。水はさらさらと二つの堤のあいだを流れている。晴れた日差しと暖かい風のなかに麦の香がただよう。新緑の木陰、ひそやかに茂った草は、花の季節よりもはるかに美しい。 王安石は北宋の政治家・思想家・文章家。神宗の信任を受けて宰相となり、新法をかかげて政治改革を行ったものの、保守派の反対などにより数年で頓挫、のち南京で隠栖しました。すぐれた詩文を多く残しており、特に文は唐宋八大家の一人に数えられています。 写真は初めて日光のもとで撮影してみました。夏らしく涼しげな青てこちゃんと白てこちゃんがお茶を飲みながら(飲める!?)森羅万象について語り合っています。無言ですが。 |
| 1920×1080 1680×1050 1280×1024 1024×768 |
|
 |
その9 『論語』學而篇 子曰く、人の己を知らざるを患へず、人を知らざるを患ふなり。 先生はおっしゃった、人が自分を知ってくれないことを気にするのではなく、自分が人のことを知らないことを気にするのである。 その2と同じく『論語』の文。人は自分が他人にどう評価されているのかということばかり気にしがちですが、その前に他人を理解することに努めよう、という言葉です。 写真は入学式期間にトップページにも使用した全員集合。刑天は鉛筆を持っているのですが、こうしてみると指揮棒のようです。 |
| 1920×1080 1680×1050 1280×1024 1024×768 |
|
|
|
|