| 『湖北省三國關係遺跡』 |
| 沙市市・江陵縣地圖 |
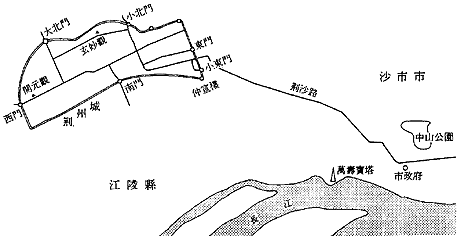 |
宜昌からバスで3時間餘り。沙市市と江陵縣は隣接した街である。私が泊まったのは沙市。沙市の長江沿いに萬壽寶塔という明代の七層の石塔がある。各層には半數はつぶれていたが見事な佛像があり、塔の内部は寄進された石板が貼ってあるが、上の層に行くほど身分の高い人が寄進したもので、なかなか興味深い塔であった。また沙市市の中心部に中山公園という大きな公園があり市民の憩いの場となっているが、この中に春秋閣がある。關羽が春秋を讀んでいる像があることから名づけられたという春秋閣だが、昔は別の場所にあったものをここに移し、さらにそれを建てかえてから二年しかたっておらず、中には關羽の像はなく、繪があるだけだった。沙市の他にも當陽の關陵、洛陽の關林、許昌の關帝廟などにも春秋閣、あるいは春秋樓というものがある。
沙市市と江陵縣の境界はよく分からなかった。ホテルで借りた自轉車で沙市の中心部からわずかに30分。江陵、いや荊州城の城壁にたどり着く。西安、南京、そして襄陽など城壁の殘っている所は多いが、ここ江陵の城壁のように一角の崩れもなく完璧に殘っているものは珍しい。城壁は大體明代のもの。清代から現在に至るまで修復を重ねてきたものであり、東門、大北門のあたりなど大變美しい。關羽が守り、後に呉軍によって奪われた荊州城はここなのである。
先主西定益州,拜羽董督荊州事。(『三國志・關羽傳』)
【日本語訳】先主は西の益州を平定すると、關羽を荊州の總督に任命した。
| 荊州城 |
 |
城内には開元觀、玄妙觀という道觀があり、開元觀の中に荊州博物館がある。ここには荊州城の北から發掘された前漢の男性の遺體が展示されていた。また地圖によれば城壁の東南の角が仲宣樓だとのこと。しかし基礎部分だけで樓自體は殘っていない。王粲(字が仲宣)は後漢末の人。『三國志』にも傳があり(卷二十一)、劉表の息子琮に曹操に降ることを勸めた人だが(『演義』では毛本第四十回)、この王粲が「登樓賦」(『文選』卷十一)を殘しており、『王粲登樓』という元雜劇もある。ここ仲宣樓がその王粲が登った樓だということらしいが、「登樓賦」の内容からはどこの町かは判斷できかね、當陽城、襄陽城、麥城などいろいろな説があるようだ。
江陵には、これと言って三國に關する遺跡は無いが、觀光客目當てに最近作られたものがあるよりはかえって氣持ちよく、城壁に登って街の賑いを、そして城外の田園風景を眺めながら、三國時代の荊州に思いを馳せることができた。
豫定では沙市・江陵の後、最後に赤壁を訪ね、湖北三國遺跡めぐりの旅のしめくくりをするつもりだったのだが、宜昌・沙市と激しい胃痛に苦しみ、ついに沙市から涙をのんで武漢へ、そして南京へ戻ったのである。
私は湖北省以外にも洛陽・成都などの三國關係の遺跡をいくつか訪れたが、最も觀光地化されておらず、最も収穫の大きかったのはここ湖北省のものであったように思う。これら遺跡の作られた時代や背景はまちまちであったけれども、『三國志』『三國演義』というものが、三國六朝時代から現在に至るまで人々の心にしっかりと根づいていることが感じられた。また中國を訪れる機會があれば、他の地域の三國關係の遺跡も見てみたいし、湖北でもさらに詳しく調査をしたいと思う。
※なお、日本語譯の作成にあたっては、今鷹眞・小南一郎・井波律子譯『三國志・II』(1982年・筑摩書房・世界古典文學全集24b)、小川環樹・金田純一郎譯『完譯三國志』(1988年・岩波文庫)を參照した。