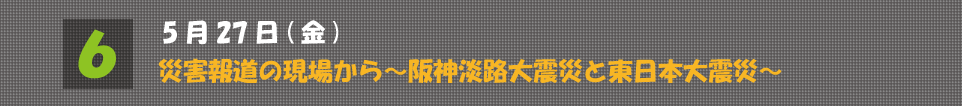
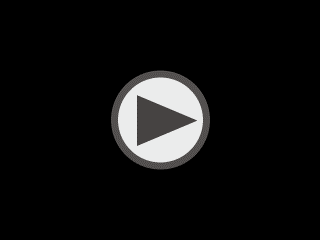
第6回NHK講座は、「災害報道の現場から~阪神淡路大震災と東日本大震災~」と題し、NHK大阪放送局チーフアナウンサー住田功一さんにお話を伺った。
住田さんは、1995年1月17日、故郷・神戸に帰省中に阪神淡路大震災に遭遇し、実家から第一報を伝えた経験を持つ。「災害時に何を伝えるか?」その難しさを自身の体験からも実感している住田さんから、東日本大震災の地震発生時から、震災をNHKがどのように報道したのか、実際に放送されたVTRを見ながら解説された。
地震が起こった午後2時46分、NHK総合テレビは「国会中継」を放映中だった。まず、緊急地震速報が伝えられ、その自動音声の終わる約18秒後には国会中継のアナウンサーが地震の際の呼びかけ文をコメントした。約50秒後には国会でも揺れが伝わり始めたのがわかる。約1分28秒後に画面が渋谷のニュースセンターに切り替わり、アナウンサーが地震情報、大津波警報など、次々に入ってくる最新情報を伝えていった。未曾有の大地震で複数の情報が重なる中で、伝える側は何が一番大切なのか、瞬時に取捨選択していかなければならない。
住田さんは、災害報道の初動で一番大切なのは、「命を救うための情報は何なのか」を見極めることだという。そして命を救うために、誰に何を伝えるべきかを、次々に入ってくるデータや映像から読み取って、的確に知らせていくことが大切だと指摘する。結果論だが、東日本大震災では命を救うための最も大切な情報のひとつは「津波から逃げろ!」だった。
しかし、NHKスペシャル『巨大津波 “いのち”をどう守るのか』(5月7日放送)によると、被災地の多くは地震後に停電し、メディアからの情報源はラジオと携帯のワンセグだけという状況だった。住民の多くは「命を救う」情報にアクセスしづらい状況にいたのだ。
津波の危険が住民に十分に伝わらなかった宮城県名取市の閖上(ゆりあげ)地区では、多くの住民が津波の犠牲となった。住民たちは、沿岸から1キロ以上離れた内陸部に津波が押し寄せるとは予想だにしていなかった。
住田さんは、「今までは来なかった」という経験や、「ここまでは来なかった」という記憶が避難を妨げてしまった場合もあると指摘する。そして、津波は上空から見えても水平からでは見にくいこと、そして津波の「高さ予想」や「到達予想時刻」、「観測結果」など多くのデータと、深刻な中継映像が重なりながら伝えられて、情報が断片化してしまい、沿岸住民にとって何が重要な情報かが伝わりにくかったことも、逃げ遅れに繋がった可能性が指摘されているという。
住田さんが経験した阪神淡路大震災の報道現場でも、「何が大切な情報か?」判断を問われる瞬間が幾度もあったという。
東日本大震災では津波避難の呼びかけが「命を救う」情報だったが、直下型地震に襲われた阪神淡路大震災では、倒壊した家屋に生き埋めとなった人が多数いるということを伝えることが重要だった。「生き埋め多数」は、地震発生からおよそ2時間後に、倒壊した自宅の屋根の上から何かを叫ぶ少年の映像から伝えるチャンスがあったのだという。少年は、逃げ遅れて瓦礫に埋もれていた祖母に向かって「ばあちゃん!」と呼びかけていたのだった。しかしこの場面を最初に放送した時は、ビデオの現場音声は消されていて、放送ではアナウンサーがJRの運休情報を伝えるコメントがかぶせられた。あの時点で、送出スタジオでは少年の叫び声が重要な意味を持つと瞬時に気づくことは難しかったのかもしれない。(叫ぶ少年の映像は音声付きで後ほど放送された。)
住田さんが16年前、被災地に居合わせて思ったことは、被災地の状況がなぜ放送に流れないのかということだった。東京のスタッフに現場の状況が理解してもらえないばかりか、大阪のスタッフですら温度差を感じたそうだ。
自分の経験も踏まえて、住田さんは被災地向けと全国向けの放送は、視点や内容が違うのではないかと感じている。被災地向けの放送では、広いエリアでは救い上げられない生活情報の伝達手段として、住田さんはコミュニティFMの役割を指摘した。
住田さんは、メディアは「ゆたかな生活」を送るための指針となるためにあるとし、究極的には生き延びるための情報を伝えるためにあると考えている。次に同じことが起こったときに、一人でも多くの「救えるはずの命」を救うことに繋がるからだ。東日本大震災をNHKがどう伝えたかを住田さんに振り返っていただき、人の命を左右するかもしれない災害報道の難しさ、そして大切さを実感した講座だった。


住田功一(すみだこういち)
NHK大阪放送局チーフアナウンサー
1983年入局。1995年1月、自身の出身地である神戸市で阪神淡路大震災の第一報を伝えたほか、同年3月の地下鉄サリン事件霞が関中継、警察庁長官狙撃事件東京医大前中継なども務めた。 2011年4月から「関西ラジオワイド」キャスターを務めている。
☆『関西ラジオワイド』
NHKラジオ第1放送 666khz 月~木 16:05~18:00
サイトはこちら
ツイッターフォローお願いします! @nhk_kansairadio
