

NHK解説委員室解説主幹。1993年にNHKへ第1期キャリア採用で入局。その後、NHKスペシャル「人体・脳と心」のアートディレクション、NHKロゴマークデザインなどに携わる。1999年にはNHK解説委員(芸術文化・デジタル関連担当)に就任。一方で、メディアリテラシー教育や、Gマーク(グッドデザイン賞)の審査委員などにも取り組む。
第8回のテーマは「プレゼンテーションの極意」。大学生にとっては、講義やゼミなどでプレゼンテーションに苦しめられている人も少なくないだろう。今回は、NHK解説委員室解説主幹の中谷日出さんをお迎えした。数々の仕事を手掛け、成功を遂げてきた“仕掛人“にプレゼンテーションとは、そして、人にモノを伝え、ひきつけるための術をお話しいただいた。
講義は中谷さんが現職に至るまでの経緯と自身が手掛けられた事業に関する話を中心に展開された。中谷さんは一番はじめに「プレゼンテーションで最も大切なのは、アイデンティティ(主体性)です」と述べた。中谷さんの言う“アイデンティティ”とは、「自らがどう思い、どう考えているのか。軸足立ててモノを考え、発言する」ことであるそうだ。アイデンティティさえ、プレゼンテーションの中に内包されていれば、自分自体は、その場にいなくても支障はない。そのような考え方を裏付けるものとして、中谷さんは現在、インターフェース(=二つのものの間に立って、情報のやり取りを仲介するもの、また、その規格のことを指す)をNHKで研究されている。「アバター」と呼ばれる、自分の分身となるキャラクターが、自分の声色を認識して動くという仕組みを開発されている。「現在の役職でもある、解説委員も、ニュースや出来事をわかりやすく視聴者に向けて説明するという仕事。これもひとつのインターフェースのような役割だ」と中谷さんは言う。
中谷さんは、1989年にNHKのキャリア採用の一期生として入局した。中谷さんは一つのキーワードを挙げた。それが、“造注”である。ビジネスの世界では本来、“受注”と言われる。しかし、中谷さんは自らクライアントに発案し、注文を受けたものを自らで制作し、クライアントに還元するという仕組みを取り入れている。この“造注”が中谷さんの仕事上のコンセプトになっているという。デザイナー時代のことだけではなく、NHK入局後もこのスタイルを貫いているそうだ。「造注は心にも体にもいい。なぜなら、すべての責任は自分に降りかかってくるけども、発案から制作まですべて自分の思うままにすることができるから」と述べていた。
企業やブランドのイメージの構築や転換を行う仕事のことをCorporate Identity(以下、CI)という。デザイナー時代に中谷さんはCIに関わることが多かったそうだ。70周年記念事業局の扉を叩くまで、NHKにはCIという概念が存在しなかったという。そこで中谷さんはA3横15枚ほどの企画書を手にして、記念事業局へ。そして、当時の会長に向けてプレゼンを行うことになり、その結果、70周年記念事業局は「ネクストテン」と改称された。そして、中谷さんの功績のひとつ、あの“三つのたまご”のロゴマークが誕生するきっかけとなった。
ここにも中谷さんのワークコンセプトである造注の要素が含まれている。この70周年記念事業に関しても、当初は広告代理店に発注するという案もあった。しかし、「NHKのことを一番わかっているのは自分たちであり、変わるのも自分たちだ」という考えのもと、NHK局内でCIを実現するという方向へと導いたのだ。そして、CIの仕事として誕生したのが、“三つのたまご”のロゴマーク。しかし、ロゴマークだけを変えるだけでは、NHKのイメージが大きくは変わらない。大きな変化を得るためには、「商品=番組の変化」が必要であると考え、新しいNHKを打ち出すようなPR番組やミニ番組の制作にも自ら着手した。中谷さんは次のように述べた。「物事をうまく成功に導くためには、成功に落とし込むまでのシナリオが必要です。そして、そのシナリオ通りに成功へと導くために、誰もがわかりやすいようなアプローチの方法を具現化・実体化させることが重要です。これがプレゼンのコンセプトにもつながってきます」。これを中谷さんは「完全ビジュアル仮説主義」と呼んでいる。ビジュアルで見せることが何よりも重要だという。さらに、中谷さんは続けて述べた。「プレゼンとは、新しいものを提案する際に行います。ですので、基本的に先行事例がないものも少なくありません。先行事例がないものに対して、組織は壁を作り拒否反応を示します。徹底的に叩いてきます。」それでも、中谷さんは、思いを伝えるために、造注を実現するために何度も何度もプレゼンを重ねている。
最後に中谷さんは自らのアイデア創出・発案方法を私たちに伝授してくださった。それは、自らの提案におけるあらゆる周辺状況をマップ化するというものだった。「あらゆる情報を手書きで書くことで自分の頭の中でもそのマップを描くことができる、つまり、想起することが可能になる」と中谷さんは言う。そして、もう一つ、私たちにプレゼンテーションの極意を教えてくださった。それは、「図解をすること」である。「プレゼンはスピードが大事。かつてはA4用紙100枚の企画書を提出したりしていたが、今は1枚でもいける。それは図解によって可能になりました。図解は要約する力を最大限に発揮し、かつ、いろんな場面で応用が可能です。これにより、想いを強めて相手に伝えることがより一層可能になると思います」と述べ、中谷さんは講義を締めた。
![]()
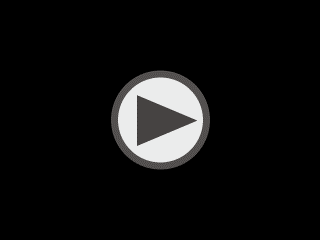


大学におけるプレゼンテーションというと、ゼミや授業での研究発表が一番初めに思い出される。このプレゼンテーションには、もしかしたら、想いを強める要素はないのかもしれない。ただ、いかにすごい研究なのか、面白い題材なのかという点で人をひきつけることはできる。素晴らしいと言われる全てのプレゼンテーションにはこの、人をひきつける力があるのではないかと講義を通じて感じた。紙一枚だけではなく、言葉や表情、姿勢などあらゆる表現体を駆使することができる。“あらゆる角度からから想いを相手に伝える”これがプレゼンテーションなのだと強く感じた。(山田裕規)

