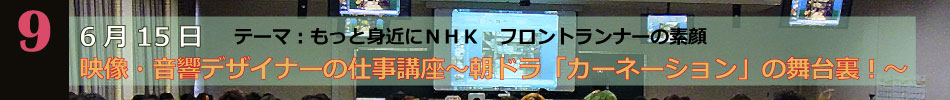
NHK講座第9回は、映像デザイナーの西村薫さん、音響デザイナーの嶋野聡さんを講師に迎え、ドラマを彩るデザイナーの仕事について、朝の連続テレビ小説「カーネーション」を事例に講義して頂いた。
まず始めに、西村さんに映像デザインについてのお話を伺った。
ドラマを制作している現場には、制作・技術・美術という三つの部署がある。西村さんは美術部署でセットや看板のデザイン、ロケ現場での撮影プランを考えるなど、ドラマの世界観を映像で作り上げる仕事に取り組んでいる。
朝の連続テレビ小説は、約1年のスパンで制作されている。「カーネーション」は、ファッションデザイナーの小篠綾子さんをモデルとするヒロインの、大正から平成までの生涯を描いた作品だ。映像デザイナーの仕事は、このドラマの世界観を描く映像を考えることから始まる。例えば、ロケ地の選定、セットのデザイン、時代考証などだ。「カーネーション」でもっとも重要だったのは、時代考証だ。大正から平成と幅広く移り変わる時代に合わせて、世界観を変えていかなければならなかったからだ。例えば、建物はもちろんだが、看板の文字の書体や電線の張り方、そういった細かい物のディティールにこだわってセットを制作した。なぜ、これほどまでにこだわるのか?それは、完璧な世界観をつくらなければ、視聴者をドラマの世界に引きこむことが出来ないからだ。確かに、看板や電線はストーリーには関係のない部分だ。しかし、これらによってドラマの厚みが増すことで、より視聴者にドラマを楽しんでもらうことが出来る。一つ一つのセットにこだわりを持ってシーンを作る。それが美術スタッフの仕事なのだ。
このようにセットや装飾を手がけるにあたり、意外なことで困ったことがあったそうだ。それは、大正や昭和の古い家電や小道具よりも、平成初期のケータイ電話やテレビなどの小道具を集める方が苦労したことだ。大量消費社会となり、物の入れ替わりが激しい現代では、ある特定の時期の世界観を表現することがとても難しい。このように様々な時代の移り変わりを表現する作品に関われたことは、これまでの経験を活かすことができ、とても燃えたと西村さんは振り返った。
ドラマを作り上げるのは映像だけではない。続いて嶋野さんからドラマを彩る「音」についてお話を伺った。嶋野さんは、ドラマで重要な役割を果たす音をデザインする音響デザイナーとして活躍されている。
音響デザイナーとはどのような仕事なのだろうか?ドラマで流れてくる音は、セリフやBGMなど様々だ。この音を担当する仕事は、実は2種類に分かれている。音声と音響効果だ。音声とは、撮影現場に存在する音を収録する仕事で、セリフや足音などをより鮮明に収録することに命を懸けている。音響効果とは、現場では撮ることの出来ない音を作ったり、探したりする仕事で、どんな音がドラマを盛り上げるか、視聴者を引き込むか、そんな音作りに情熱を燃やしている。こうした生の音と架空の音を組み合わせて、ドラマ全体を盛り上げる音の構成をプランニングするのだ。
では、実際どのような仕事をしているのだろうか?「カーネーション」を事例に音響デザインの仕事について伺った。音響デザインは、ただ出来た映像を見て音をつけていくだけではない。ドラマが制作された背景、何を描くのか、登場人物のカラーやイメージ、そういったドラマコンセプトの共有から仕事が始まる。そうした情報から、時代や地域、当時の風俗、社会、自然についてあらゆることを調べる。一見これらは、音と関係ないように感じられるが、時代や土地によって使える音、流れている音は全く違う。こうして得た知識からドラマに必要な音を考え、音ロケを行い収録する。映像と同じ土地、違う土地。様々な場所に行き必要な音を集める。このようにリアルな音を再現することで、ドラマの世界観を「音」で構築していくのである。
ドラマの世界観を作る音は、環境音だけではない。作品を盛り上げる音楽、BGMなどの作曲コーディネイトも音響デザイナーが担当する。「カーネーション」では、作曲家の選定から携わったそうだ。こうして選んだ作曲家と、ドラマの世界観を共有した上で、どのような楽曲が必要かを考える。どういうシチュエーションで使う曲を何曲作るかといった点まで打ち合わせる。つまり、音による作品の総合プロデュースを音響デザイナーは担っているのだ。
これだけの下準備を経てようやく、撮影された映像に音を当てる仕事に入る。ここが音響デザイナーの腕の見せ所だ。いかにして視聴者にドラマの世界に入り込んでもらうか、そのための工夫が音によって行われている。そのポイントが、リアリティ、強調、心理描写だ。VTRであがってきた音では、臨場感に欠ける。例えば、その場所の環境や主人公の出す足音などを、別に収録した音で重ね、リアリティを表現している。これらの音は、実際その状況で録られた音を合わせているだけではない。例えば、芝生の上を歩く音は、廃テープの山を歩いて収録するそうだ。こうして収録された音によって、よりドラマの深みは増していく。また、BGMや効果音によって主人公の心理状態を表現し、間接的に感情を表現することも出来る。こうした狙いをもって音声と効果を組み合わせ、ドラマの世界を音で作り上げる。それが音響デザイナーの仕事だ。
質疑応答では、NHKが受信料によって運営されていることを踏まえて、制作費に関する質問があった。多くのこだわりを持って制作されているセットや音楽も、受信料を無駄にしないよう様々な工夫がなされている。プロのデザイナーはただ良い作品を作り上げれば良い訳ではない、そうしたシビアな世界も感じることが出来た講義だった。
フリーで映画やゲームソフトなどの美術を担当したのち、1997年、番組制作局映像デザイン部に入局。2008年、大阪局編成部映像デザイン専任ディレクターに就任し、現在に至る。「オードリー」「ほんまもん」「ウェルかめ」「カーネーション」など多くの”朝の連続テレビ小説”制作に関わった。
![]()
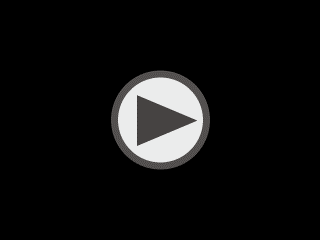

今回の講義では、映像、音響デザイナーの仕事から、ドラマの世界観を作り上げるまでの技術、こだわり、熱意を知ることが出来た。ドラマといえば役者やシナリオにばかり注目が集まるが、どんな良い俳優、脚本家がいても、それだけでは良いドラマにはならない。こうしたデザイナー達の創意工夫によって私たち視聴者はドラマの世界観を120%楽しむことが出来ていると感じた。目につかない、耳につかないところの大切さを知ることが出来た講義だった。(島田嶺央)

