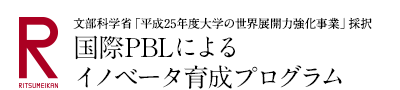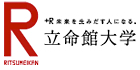参加学生によるプログラム・レポート
アクティビティレポート⑥(2017年派遣:バンドン工科大学)
Bandung | 2018年04月06日
経営学部 大槻 光平さん(3回生)
Selamat Siang!
経営学部国際経営学科3回生の大槻光平です。僕は国際PBLプログラムを通じて、バンドン工科大学のビジネスマネジメント学部・アントレプレナー学科に留学しました。このプログラムを志望した理由として、「成長しかない」と言われる新興国のインドネシアでビジネスを学びたい、アジアが好きで、しばらくの間生活してみたいという単純な好奇心があったという背景がありました。このレポートでは、この留学を通して学び、得たことについて紹介したいと思います。
◆ビジネスの楽しさ、難しさを学んだ
僕が留学したアントレプレナー学科は少し特殊で、起業について学ぶため、生徒は全員何かしらのビジネスを持つことが義務付けられます。しかし、起業といっても日本でイメージされるようなハードルの高いものとは異なり、飲食(レストラン・カフェなど)やファッション、インテリア、化粧品など、衣食住の生活に寄り添ったものが多く、インドネシアが発展に向けて拡がっていく段階なのだと実感したことは印象的でした。それでも、ビジネスモデルを一から落とし込み、実際に店やホームページを構え、商品・サービスを客に届けるまでを自らで手掛けることは非常に興味深く、それに一員として携われたのは貴重な経験でした。僕は鉄板焼き×インドネシア料理のレストランを経営しているチームに参加し、マーケティング業務を務めたのですが、生活基盤が異なる国ということもあり、実際に集客をする事は思っていたより難しく、ビジネスの難しさを知りました。また、自分がしたいと思ったことがあれば、それを拡げていける機会・ステージが大いにあるということを体感したのも大きな学びです。
レストラン「RasaKhano」のメンバー(イベントの為、露店販売)
◆“sabar”の精神
“Tidak apa-apa”(大丈夫)は少し有名かもしれませんが、それに似た、僕の好きなインドネシア語の一つに、”sabar”という言葉があります。この言葉が、明るく、何とかなる精神のインドネシア人の性格をうまく表しているように感じるからです。直訳すると「辛抱強く」という意味ですが、友人と会話の中で話すときには「まあぼちぼちいこう」ほどの感覚で使います。
前提として、インドネシアという国では、日本での常識はほとんど通用しません。トイレ、時間感覚、宗教観、食べ物・食べ方、交通手段など、あらゆるものが異なるので、慣れない最初の一か月は驚きの連続で、生きているだけで精いっぱいでした。ですが、人懐っこいインドネシア人と生活するうちに、彼らと同じような価値観を持つようになり、気付けば毎日が楽しいと思えるようになったのです。
渋滞がひどくても、動くのが嫌になるくらい暑くても、友達が待ち合わせに1時間遅れても、電気・水道やwi-fiが急に止まっても、部屋にヤモリやゴキブリが発生しても、出したはずの洗濯物が返ってこなくても、インドネシア語だけの会話にまざれなくても、”sabar ya”と心で一言いえば、「まあいいか、ぼちぼちいこう」という気持ちになります。
これから就職活動も本格化し、卒業後進んでいく道を決めなければいけませんが、思い詰めすぎず、”sabar”の精神を大事に自分のペースで歩んでいこうと思います。
お風呂がない集落に泊まった際の、自然のシャワー
家庭料理。手で食べることも多い