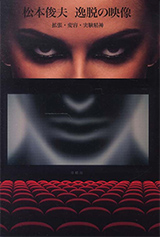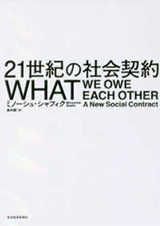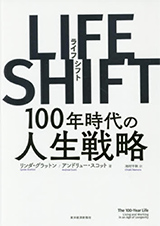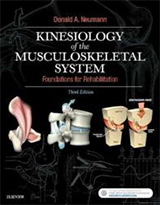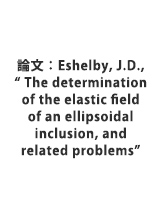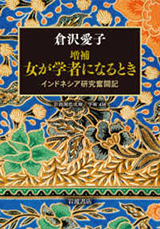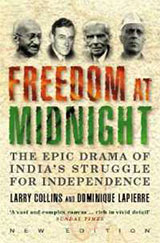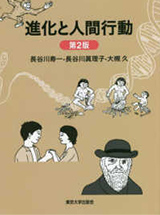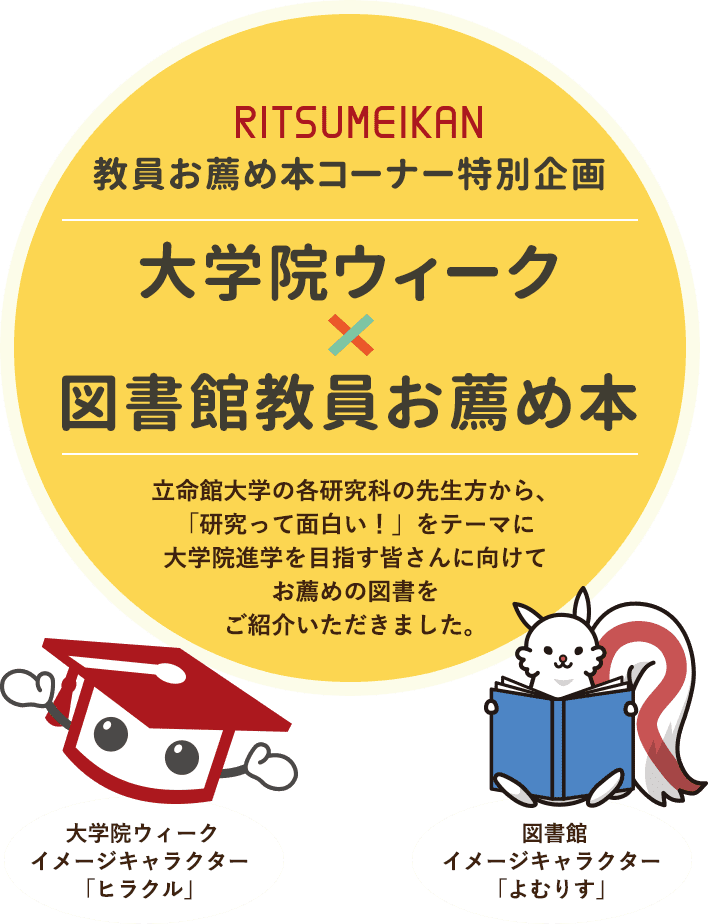
- ALL
- 衣笠
・朱雀 - BKC
- OIC
※掲載のない研究科もありますのでご了承ください。
推薦教員

小松 浩(教授)
法学研究科
『議会制民主主義の現在-日本・イギリス』
小松 浩著/2020年/日本評論社
- 推薦の言葉
- 自著で恐縮です。学部学生時代から関心があった選挙制度の問題に40年以上いまだに取り組んでいます。選挙制度の問題から議会制民主主義、レファレンダムなどの問題へと関心は広がってきましたが、中心はいまだに選挙制度です。生涯取り組んでいきたいと思います。研究は辛いなと思うときもありますが、わからないことを知ることは楽しいことです。
- 先生の
研究キーワード - 選挙制度、憲法、民主主義
RUNNERS

三笘 利幸(教授)
社会学研究科
『民衆暴力:一揆・暴動・虐殺の日本近代』
藤野 裕子著/2020年/中央公論新社
- 推薦の言葉
- 江戸時代の一揆や明治初期の秩父事件。日比谷焼き討ち事件や関東大震災時の朝鮮人虐殺。こうした歴史上の「民衆暴力」については、高校の頃から名称は知っているだろうが、実際、どうして民衆は「暴力」に向かったのか、それはどういう「暴力」だったのか。単純なイメージで知ったつもりになっているところに、一歩踏み込んでみること。これがまさしく研究の第一歩である。その一歩を踏み込むと、そこには自分の知らない広大な世界があることが見えてくる。本書は、その内容の素晴らしさだけでなく、研究へ踏み込んでいくことで視界が開けていくおもしろさを伝えてくれる良書である。
- 先生の
研究キーワード - マックス・ヴェーバー、客観性、価値自由、沖縄、ナショナリズム、帝国主義、植民地主義、包摂/排除
RUNNERS

ダヌシュマン
イドリス(准教授)
国際関係研究科
『Global Religions:An Introduction』
Mark Juergensmeyer (ed.)/2003/Oxford University Press
- 推薦の言葉
- 日本も含む先進国の若者の間では、伝統的な宗教への関心が薄いというのは周知のことである。しかし、宗教は、世界の多くの地域で、少なからず人々の生活や文化に影響を与え続けている。そのような現象を、ローカルとグローバルの両方の観点から論じる英語の論文集である本書は、宗教の「再興」とグローバル化について理解を深めたい方が必読の一冊でもある。
- 先生の
研究キーワード - 宗教と国際関係、イスラーム思想、トルコ研究、中東地域研究、多文化共存・共生
RUNNERS

萩原 正樹(教授)
文学研究科
『宋詞の世界:中国近世の抒情歌曲』
村上 哲見著/2002年/大修館書店
- 推薦の言葉
- 詞という中国の韻文は、漢詩ほどには日本で普及しなかった。その詞の発展の歴史や特徴が過不足無く説かれる本書は、私の研究の出発点となった。詩と詞とはどこが違うのか。なぜ詞は日本で流行しなかったのか。それを著者はさまざまな側面から解き明かそうとする。その試みはたまらなくスリリングで面白い。
- 先生の
研究キーワード - 中国文学、日本の詞学、森川竹磎、明治大正期の詩詞、唐宋詞、詞牌、詞律、欽定詞譜、萬樹、詞譜
RUNNERS
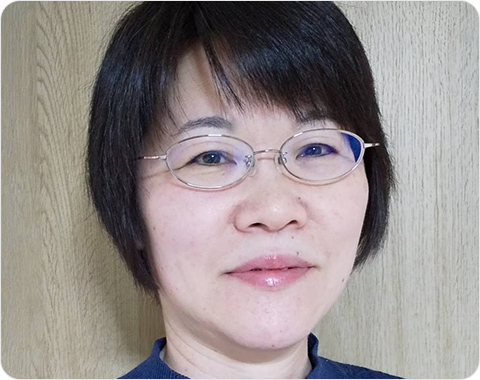
小川 真和子(教授)
文学研究科
『津田梅子:科学への道、大学の夢』
古川 安著/2022年/東京大学出版会
- 推薦の言葉
- 本書は、「科学者」としての津田梅子の姿に迫ります。アメリカの大学で生物学の研究に没頭した彼女が、帰国後、女性科学者の受け皿を欠く日本で苦悩しつつ女子高等教育の拡充に努めたことについて、読みやすい筆致で描いています。注釈も充実しており、研究者にとっても読み応えのある書です。
- 先生の
研究キーワード - ハワイ、日米関係、太平洋史、民間交流・外交史、ジェンダー
RUNNERS

川村 健一郎(教授)
映像研究科
『逸脱の映像:拡張・変容・実験精神』
松本 俊夫著/2013年/月曜社
- 推薦の言葉
- 戦後を代表する映像作家である松本俊夫の第6評論集。映像体験の特性を「述語の前景化」として規定しながら、S・ブラッケージ、J・メカスらの難解な実験映画を明快に読み解いていく。第1評論集『映像の発見』から通貫する松本の思想に接近するための格好の一冊。
- 先生の
研究キーワード - 映画史、映画研究
RUNNERS

クルソン デビッド(教授)
言語教育情報研究科
『外国語を話せるようになるしくみ:シャドーイングが言語習得を促進するメカニズム』
門田 修平著/2013年/SBクリエイティブ
- 推薦の言葉
- 語学習得に必要なプロセスのヒントが詰まった1冊です。シャドーイングで繰り返し発話練習をしていく中で、単なる音を確認する段階から、自動化が進み、意味レベルでの理解が可能になります。言語習得の障壁を簡単に取り払うアプローチがシャドーイングだと考えます。(現在在籍の院生もこのテーマを研究しています!)
- 先生の
研究キーワード - Foreign language education, Second Language Acquisition Measurement, Task-Based Learning

滝沢 直宏(教授)
言語教育情報研究科
『ことばの実際2 コーパスと英文法』
滝沢 直宏著/2017年/研究社
- 推薦の言葉
- コーパス(コンピュータに載っている大量の言語資料)を使うことで初めて見えてくる(語法と文法に関わる)英語の姿の一端を、コーパス利用の方法論と共に示したものです。研究ということだけではなく、英語の学習面にも役立つ点があります。
- 先生の
研究キーワード - 英語学・英語語法文法研究・コーパス研究
RUNNERS

北出 慶子(教授)
言語教育情報研究科
『ともに生きるために』
尾辻 恵美・熊谷 由理・佐藤 慎司著/2021年/春風社
- 推薦の言葉
- 翻訳アプリの性能も良くなり、正確に情報をやりとりすることだけが外国語学習の意味ではなくなってきました。そんな中で「外国語教育は、何を目指していくのか?」という問いに対し、本書は一つの糸口を示しています。言語教育情報研究科でこの問いへの答えを一緒に考えませんか。
- 先生の
研究キーワード - 応用言語学・言語教育、日本語教育
RUNNERS

阿部 朋恒(准教授)
先端総合学術研究科
『マツタケ:不確定な時代を生きる術』
アナ・チン著/2019年/みすず書房
- 推薦の言葉
- 先行きが見えない人生に、あるいは世界に不安を覚えることはないだろうか。そんなときこそマツタケの出番だ、と著者は言う。栽培を拒否するこの菌類の気まぐれは、世界各地で大小さまざまな騒動を巻き起こす。本書は、学問分野を超えた協働のもとでそれら悲喜劇をつなぎ合わせ、不確実な時代の希望の物語として読ませてくれる。
- 先生の
研究キーワード - 文化人類学、中国少数民族、山間集落
RUNNERS

森田 真樹(教授)
教職研究科
『国際理解教育を問い直す』
日本国際理解教育学会編著/2019年/明石書店
- 推薦の言葉
- 子どもたちが生きるのは、さらにグローバル化した社会ですから、国際理解教育を実践する力を獲得することは、これからの教師に不可欠です。国際理解教育は、英語学習や留学だけではなく、どの教科・領域でも様々な方法で実践できる教育です。国内で唯一「国際教育コース」を置く本学教職大学院で国際理解教育を学べば、これからの学び、授業、学校、そして教師の姿が見えてきます。
- 先生の
研究キーワード - 国際教育、教師教育、社会科教育
RUNNERS

神藤 貴昭(教授)
教職研究科
『「9歳の壁」を越えるために』
脇中 起余子/2013年/北大路書房
- 推薦の言葉
- 子どもたちが、様々なことを学び、深め、探究していくためには、生活言語から学習言語への移行が必要になります。しかし、移行は、必ずしもスムーズにはなされません。なぜか。本書には、教科教育を実践するにあたって、知っておくべき大前提が書かれています。
- 先生の
研究キーワード - 教育心理学
RUNNERS

荒木 寿友(教授)
教職研究科
『多様性の科学』
マシュー・サイド著/2021年/ディスカバー・トゥエンティワン
- 推薦の言葉
- 多様性は近年脚光を浴びており、人種、性的指向、国籍といった多様性だけではなく、考え方の違いといった認知的多様性が集合知を生み出すということが、本書では論じられている。人権感覚としての多様性の尊重とともに、集合知を生み出すシステムとしての多様性の尊重は興味深い。
- 先生の
研究キーワード - 教育方法学、道徳教育、ワークショップ
RUNNERS

大橋 陽(教授)
経済学研究科
『壁の向こうの住人たち』
A・R・ホックシールド著/2018年/岩波書店
- 推薦の言葉
- ルイジアナ州に暮らす貧しい白人。彼らは連邦の援助を拒絶する。石油産業に自然環境は汚染されているが、環境保護に反対し企業批判もしない。温暖化も信じない。生活保護や福祉にも反対だ。この理解しがたい心情、トランプ支持が根強い理由が解き明かされている。
- 先生の
研究キーワード - 現代アメリカ経済史、アメリカ経済論、政治経済学
RUNNERS

桒田 但馬(教授)
経済学研究科
『21世紀の社会契約』
ミノーシュ・シャフィク/2022年/東洋経済新報社
- 推薦の言葉
- 本書が問う「人間が社会の中でいかに共生するか」は日本の経済社会のあり方に強いインパクトを与える。本書は学部生には社会保障を大局的に考える素材を提供するが、それを超えるテーマに向き合う。院生が意識すべき研究スタンスへの示唆もみられる最適の書である。
- 先生の
研究キーワード - 国と地方自治体の財政、都市と農山漁村の経済
RUNNERS

大友 智(教授)
スポーツ健康科学研究科
『体育科教育学研究ハンドブック』
日本体育科教育学会編/2021年/大修館書店
- 推薦の言葉
- 我が国の体育科教育学・スポーツ教育学を牽引する日本体育科教育学会が編集した研究の手引書。執筆者は、学会を代表する研究者である。各国の研究動向を踏まえ、構図(歴史、目的・性格、研究領域、研究課題・対象他)、研究方法、研究の典型事例等が豊富に盛り込まれている。
- 先生の
研究キーワード - 体育科教育学、スポーツ教育学
RUNNERS

真田 樹義(教授)
スポーツ健康科学研究科
『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)』
リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット著/2016年/東洋経済新報社
- 推薦の言葉
- 平均寿命は200年増加し続けており、今の大学生の平均寿命はおよそ105歳に到達すると考えられる。そのため70代、さらには80代まで働かなくてはならない可能性が大きい。これからは新しい職種が登場し、手持ちのスキルだけでは生き残れず、教育→仕事→引退という3ステージの人生が崩壊する。仕事のステージが多様化することで、実験→変身→変貌を生涯に何度もくりかえす必要がある。この本は、若年者のライフプランについても詳しく提示されており是非将来のキャリアプランの参考にしてほしい。
- 先生の
研究キーワード - 高齢者、介護予防、運動処方
RUNNERS

篠原 靖司(教授)
スポーツ健康科学研究科
『Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation』
Donald A. Neumann/2016/Mosby
- 推薦の言葉
- 身体に関する研究で最も基礎となる大事な知識は解剖です。しかし、解剖は単なる構造を知るだけでなく、その機能を理解しなければいけません。この本は運動器の機能解剖に関することが詳細に書かれています。「なぜ背骨(脊椎)はこのような形や並びをしているのか?」、「なぜふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)はこのような形状や走行をしているのか?」など、この本を読めば人体における機能解剖が理解できます。翻訳版もあるので読み易いと思います。
- 先生の
研究キーワード - 整形外科学、スポーツ医学
RUNNERS
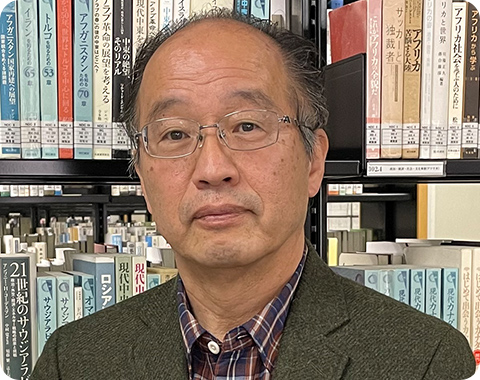
谷垣 和則(教授)
食マネジメント研究科
『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために』
渡邊淳司, ドミニク・チェン(監修・編著)/2020年/ビー・エヌ・エヌ新社
- 推薦の言葉
- 最近注目されるようになった幸せの上位概念であるwell-being、本書では食への直接の記載は少ないが、食との関係性は、人とのつながりを重視する共食、創造性のある調理、社会的貢献、多様な価値観・異文化理解、などなど、考えると多様である。研究や生き方に少なくとも間接的には役立つであろう。
- 先生の
研究キーワード - 国際貿易論、文化と国際貿易論、国際比較、卸中間業者と国際貿易、家庭の経済学
RUNNERS

鳥山 寿之(教授)
理工学研究科
論文:Eshelby, J.D., “ The determination of the elastic field of an ellipsoidal inclusion, and related problems”
Proceedings of the Royal Society of London, Series A, Vol.241, No.1226, 1957, pp.376-396 所収
- 推薦の言葉
- 20世紀の新しい固体力学分野であるマイクロメカニックスの原点となる歴史的論文である。Eshelbyは母材に含まれる介在物や不均質相などの欠陥が楕円体形状の場合に、欠陥に作用する非弾性ひずみと母材に作用する弾性ひずみの関係が、楕円体の幾何学形状とポアソン比で表現できることを発見した。PoincareやRouthといった先人たちの業績を土台にエレガントな理論を組み立てた過程を楽しんでほしい(正直に申し上げると初めて読んだときはさっぱり分かりませんでしたが、その後理解して研究に利用しています)。
- 先生の
研究キーワード - マイクロメカニックス
Cambridge Core

島川 博光(教授)
情報理工学研究科
『ファスト&スロー』上・下
ダニエル・カーネマン著/2014年/早川書房
- 推薦の言葉
- ヒトが使いやすいと感じる製品をつくるためには、ヒトがどのように意思決定しているかを知ることは重要である。本書は、ヒトの思考を2つの仕組みに分けて考えることで、意思決定の仕組みを明らかにしている。多くの人を望ましい行動に導く行動経済学の礎となった名著である。
- 先生の
研究キーワード - データサイエンス、ユーザビリティー工学
RUNNERS

杉山 圭吉(客員教授)
生命科学研究科
『WHAT IS LIFE? 生命とは何か』
ポール・ナース著/2021年/ダイヤモンド社
- 推薦の言葉
- 細胞周期を調節する機構の解明で2001年ノーベル生理学・医学賞を受賞した著者が、「生命とは何か」という誰もが感じる疑問に最新の知見に基づきわかりやすく答えた啓発書である。中でも「今日地球上にある生命の始まりは『たった1回だけだった』との結論は感動的である。専攻の如何に関わらず、「生命とは何か」を考えることの大切さを学んでほしい。
- 先生の
研究キーワード - 研究マネジメント、応用生命科学、食品生理機能
RUNNERS
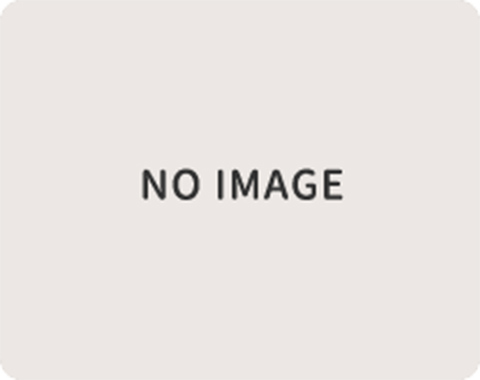
稲津 哲也(教授)
薬学研究科
『ネアンデルタール人は私たちと交配した』
スヴァンテ・ペーボ著/2015年/文藝春秋
- 推薦の言葉
- 著者らは、古代のDNAを復元するという困難な研究に、衝撃的な新技術「次世代シーケンサー」で、約4万年前のネアンデルタール人のDNAの増幅に成功した。そのDNAは、現生人類に、数パーセント共有されており、約5万年前にアフリカを出た現生人類は、ネアンデルタール人の遺伝子を、交配後に取り込んで世界中に広がっていった。
- 先生の
研究キーワード - 旧人類、現生人類、遺伝学、ミトコンドリア・ゲノムDNA、次世代シークエンシング
RUNNERS

植田 展大(准教授)
経営学研究科
『サラ金の歴史 :消費者金融と日本社会』
小島 庸平著/2021年/中央公論新社
- 推薦の言葉
- サラ金や消費者金融に良いイメージを持つ人は少ないだろう。確かに高金利や厳しい取り立てなどダークサイドとしての面もあるが、同時に暮らしを支えるセーフティーネットでもある。そして、実は私たちの多くが無意識にその存在を支えている。通読すれば分かるように、本書はサラ金を通して中長期的に日本の経済成長を捉え直す壮大な試みである。対象を絞り込み、実証的に事実を積み上げ、時期区分を行い中長期的な視野で全体像を作り上げていく。歴史的な分析のお手本としてもおすすめである。
- 先生の
研究キーワード - 経営史・経済史、地域経済、農林水産業
RUNNERS

岸田 未来(教授)
経営学研究科
『増補・女が学者になるとき』
倉沢 愛子著/2021年/岩波書店
- 推薦の言葉
- 大学院生時に1998年版を読みました。増補版が2021年に出版され、改めて読み直しましたが、長期フィールド調査の困難や出産・子育て・介護と研究との両立など、けっしてきれい事だけではないリアルな研究者人生が描かれており、いまでも面白く、研究者を目指す皆さんにも参考になると思います。
- 先生の
研究キーワード - 比較企業研究、人事労務管理、労使関係、スウェーデン・モデル
RUNNERS
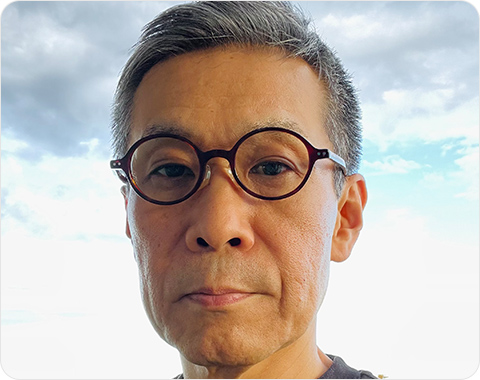
小田 尚也(教授)
政策科学研究科
『Freedom at Midnight』
Larry Collins and Dominique Lapierre/1977/Vikas Publishing House
- 推薦の言葉
- 本書はインド・パキスタンの独立に至る過程と独立前後の混沌を詳細な調査に基づき叙述したノンフィクションの傑作です。今も対立する両国の歴史的背景やヒンドゥー・イスラームの宗教間の争い、宗主国英国との関係など教科書や専門書では学べない貴重な情報が満載。国家の独立という一大イベントの熱気がむんむんと伝わってくる名著です。
- 先生の
研究キーワード - 開発経済、南アジア地域研究(インド、パキスタン)
RUNNERS
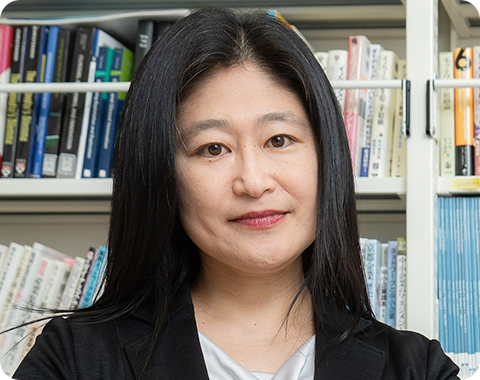
水野 由香里(教授)
経営管理研究科
『エビデンスから考えるマネジメント入門』
中本 龍市・水野 由香里著/2022年/中央経済社
- 推薦の言葉
-
論文1)は、研究(学術界)と実務(実業界)のギャップ・埋められない溝について、ビジネススクールの教員らしい視点で書かれています。書籍は、偉大な経営学研究者の研究スタイルから、「研究するとはどういうことか」を学ぶことができる構成となっています。
(注1)Markides, Costas, “In search of ambidextrous professors”, Academy of Management Journal,2007,Vol.50,No.4,pp.762—768
(本大学図書館定期購読の電子ジャーナル、冊子体はOICライブラリーで所蔵)
- 先生の
研究キーワード - イノベーション論、組織論、戦略論、組織間関係、中小企業、産業集積、産学連携
RUNNERS

谷 晋二(教授)
人間科学研究科
『進化と人間行動』第2版
長谷川 寿一・長谷川 眞理子・大槻 久著/2022年/東京大学出版会
- 推薦の言葉
- 「あの人はなぜあのように行動するのだろうか」この問いは人間の行動を研究するすべての研究者の基礎的な問いである。進化学のアイデアは、異なる領域の研究者の考えを統合していく時に有用なものとなる。この本は、進化学や現代の生物学と心理学や社会学をつなぐアイデアのヒントを提供してくれる。
- 先生の
研究キーワード - 発達障がい、応用行動分析、対人援助、ACT
RUNNERS