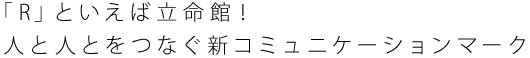| |
2007年10月10日、立命館学園のコミュニケーションマークが発表されました。このアルファベット一文字で表されたコミュニケーションマークには、実に様々な思いが込められています。
今回は、コミュニケーションマークをデザインされたアートディレクターの秋山具義さんに、「R」に織り込まれたメッセージについてお伺いしました。 |
| |
|
| |
|
| Q_ |
最初にコミュニケーションマーク「R」のコンセプトをお聞かせください。 |
| |
|
| 秋山_ |
まず一番大切にしたかったことは、「シンプルである」ということです。在学生、生徒、児童や教職員、校友、受験生や保護者など、立命館と関わる人全てが、このコミュニケーションマークを見ることで同じイメージを共有できるかどうかを大切にしようと考えました。
色味も同様で、立命館のスクールカラーのえんじ色以外を用いた場合、どうしても違和感が出てしまいますよね。「R」と言えば立命館、誰が見てもそうイメージできるようなマークであることを重視しました。シンプルな「R」ロゴですが、これが人と人との心をつなぐツールとなってほしいですね。 |
| |
|
| Q_ |
このコミュニケーションマークにより、みんなの立命館へのイメージが共有されるのですね。では次にコミュニケーションマーク「R」の特徴を教えてください。 |
| |
|
| 秋山_ |
大学のコミュニケーションマークであるからには、「知性」や「品位」を感じることのできるようなものにしたいという思いを持っていました。そのなかで、このコミュニケーションマークの最も大きな特徴と言えるものは、黄金比です。黄金比とは、人間がもっとも美しいと感じる割合、5:8の事を言います。ギリシャのパルテノン神殿やオウムガイの殻など、人類が美しいと共通して感じられるものは、5:8との割合で生み出されていることが多いのです。コミュニケーションマークが長い時間、飽きずに使用され続けるために、人々に自然に受け入れられるよう「設計」しました。また、フォントはオリジナルのものを制作しました。よく見ると一般的なゴシック体とはちょっと違うんです。さっぱりと綺麗なフォントを使用することで、大学としてのインテリジェンスを表現しました。 |
| |
|