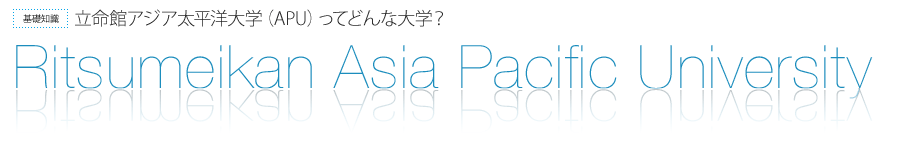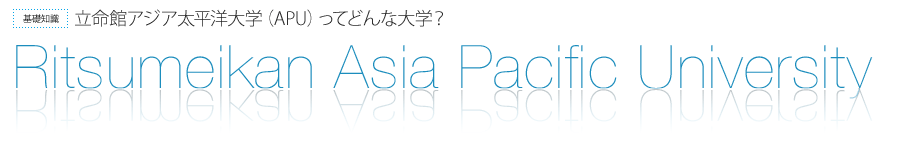アジア太平洋学部、アジア太平洋マネジメント学部の2つの学部があります。両学部では講義を通じて、アジア太平洋地域を意識した教学内容のもと、日本語基準で入学した学生に対しては英語を習得することが求められます。また、アジア太平洋地域の言語(中国語、韓国語、マレー・インドネシア語、スペイン語、タイ語、ベトナム語)を任意で習得することもできます。2006 年度にはインスティテュートとして両学部にまたがる学際的なコースとして、クロスオーバー・アドヴァンスト・プログラム(CAP)[→リンク]が設置されました。
国内外問わず春季と秋季の年2回、学生を受け入れている点も立命館大学のシステムと異なるところ。秋に入学式と卒業式があることも、珍しいですね。また、立命館大学との間で、相互に半年または1年の交換留学プログラムがあります。
APUには、英語か日本語のどちらかができれば入学でき、国際学生の70%が英語基準で入学しているそうです。英語で入れば第1外国語が日本語に、日本語で入ればその逆となるそうです。APUでは、開学時に第2外国語として中国や韓国などのアジア太平洋言語を学び始める動機付けのために、各言語の文化的背景を紹介するイベントとして「言語ウィーク」をスタートしましたが、今やアジア太平洋言語に限らず、各国の出身者や興味を持つ学生が、それぞれの国の文化を紹介する「マルチカルチュラル・ウィーク」として発展しています。 |