今月のキーワード 「文化庁が映画振興支援策の検討へ」 |
●文学部 冨田 美香 助教授に聞く
昨今の映画を取り巻く環境と課題
日本映画製作者連盟の全国映画概要によると、平成13年のスクリーン数はピーク時の昭和30年代に比べて約3割、入場者数は約1割にまで減少している。文化庁では「映画振興に関する懇談会」を設立し、欧米の例を参考に今年度中に具体策をまとめるという。
そこで今回は、映画監督兼プロデューサーとして草創期の日本映画界をリードし、「日本映画の父」と呼ばれる牧野省三研究の第一人者であるとともに、映画村のインターンシップなどにも取り組まれている文学部の冨田美香助教授にインタビュー。近年の映画を取り巻く環境と課題についてお話を伺った。 |
Q
文化庁が「映画振興に関する懇談会」を設立するなど、映画界の活性化を目指す動きが起こっていますが。A
文化庁の支援策がこの時期に動き出した最大の理由は、メディア時代における「コンテンツ」の核となる部分として「映画」を強化するためです。しかし、この問題を克服するためには映画界全体を活性化させることが必要であり、そのためにも日本の文化政策を見直すべきだと思います。映画の先進国である欧米諸国では、文化振興策の基本として、「制作者」と「鑑賞者」の生産・育成が最重要課題であると位置付けており、さらに映画の場合は、物質でもある「フィルム(=作品)保存」も行っています。ハリウッドの膝元にあるUCLAでは、映画人との深い交流のもとに蓄積したフィルムや資料などの膨大なコレクションをもつ世界有数のアーカイヴを有し、その人的・物質的資産を駆使することで、制作・研究・文化政策の総てにわたってトップレベルの教育を施し、世界中に優秀な映像制作者、教育者、研究者、学芸員を送り出しているのです。これらのいずれのレベルにおいても日本は文化政策の後進国であり、「日本のハリウッド」といわれる京都の大学で、映画をまともに取り上げることが近年までなかった、という事実はその無理解ぶりを物語ってると思います。
Q
日本の映画政策を考える上で、見直すべき課題とは?A
まず、制作者の視点から捉えると、媒体の変化や制作形態の多様化によって、表現媒体の基本であったフィルムの特質を知り尽くした上で積み上げられた実験的な技術や表現手段、その創造性が、世代間継承されにくくなっています。例えば、「闇夜に飛ぶカラス」を表現するのが時代劇映画の照明の粋ですが、ビデオでは映らないためそういう照明は使用されず、後継者に受け継がれる機会もありません。また、鑑賞者の視点から捉えると、まず、ロードショー以外のスクリーンが減少しています。シネ・コンでロードショー作品を上映するスクリーンは増えましたが名画座の減少により、見逃した作品を「フィルム映写」で見る機会が減っています。次に、映写技師の減少。自動映写が増え、映写技術と映像の質にこだわる技師が減っています。最後に、真正なる映画の普及不足。ビデオやテレビで見る作品は映像の質が異なる複製物であり、現在も尚最高の解像度であるフィルムの映像表現は、そのフィルムを映写しなければ、その表現は再現できないもの、という認識が観客に低い。その結果、原型としての「映画」を体験する場がなくなりつつあり、今後は、フィルムで撮られた「映画」をビデオ映像でしか見た事のない世代が中心になるでしょう。「映画」の原点であるフィルムでの映画体験無しで、つまり本来の映像や表現の質を知らないうえに、新しい映像作りや映画を思考することが出来るのだろうか、というのは最大の疑問です。こうした問題を打開する鍵となるのは、教育現場だと思っています。
Q
それではどのような教育が必要だとお考えですか?A
映画そのものに対する教育、もしくは映画を活用した文化教育がもっと必要です。音楽や絵画などは小学校から教育を行う環境が整っているのに対し、映画はどうでしょうか。圧倒的に少ない。大学で正式に教育しているところも数えられるほどです。立命館の教壇に立つことになって、私の授業では映画人をお招きして直接お話をいただいたり、近くにある「映画の聖地」を訪れたりと、映画を通した様々な教育を行っています。職人としての生き様を伝えることは、人間性の教育にもつながりますし、こうした活動や教育が「日本のハリウッド」京都を中心に広がっていけばと思います。
Q
今後の研究活動について。A
確かに、映画館などの数は減っていますが、映像自体に携わりたい人は増えています。そうした人たちのために、私自身も映画の普及活動と研究を進めていきたいと思っています。しかし、研究の素材となるべき過去の映画、とりわけ戦前の映画はほとんど残っていません。素材の発掘を進めることはもちろん、社会の動きに対する映画の変遷や、映画人の思いと技術を伝承するパイプ役になりたいと考えています。
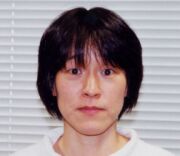 |
冨田 美香 助教授 専門分野:映画史 ■主な著書・論文 ●『映画読本千恵プロ時代』 (編著、'97年フィルムアート社) ●「場」への回帰―『三朝小唄』という装置― ('02年『アート・リサーチ』2号) ●セルゲイ・パラジャーノフの〈知的映画〉『火の馬』 ('90年『映画学』第4号) |