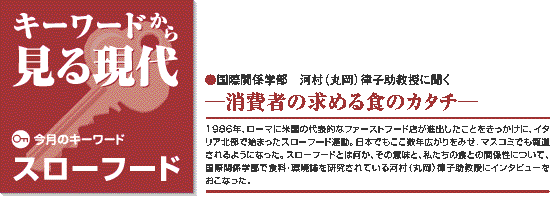
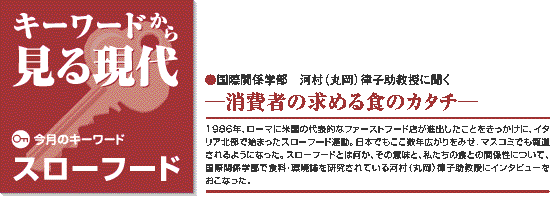 |
Q 現在、「ファーストフード」に対抗して、「スローフード」運動が世界中で広まりつつあると聞きますが、先生は「スローフード」にどのようなお考えをお持ちですか。A ファーストフードは、食の大量生産によって安価な食べ物を提供してきました。しかし同時にファーストフードは食の画一化をもたらし、食べ物を生産の現場から離れたものとしました。スローフードは、こうした動きへの危機意識に基づいて、本物を食べる、本来のものを食べる、作り手とのつながりを求める、また、文化として食を見直すものだと思います。 Q この運動が日本で脚光を浴びたのは、一連のBSE(牛海綿状脳症)や乳製品での事件などからくる「食に対する不信」も関係があるように思いますが。A そう思います。こんなものを食べさせられていたのか、といった恐怖心と怒りから来る食に対する不信と無関係ではないでしょう。食に関心を持ち、その安全性を考える中で、本物の食べ物を求める方向が注目され、食べ物の「出自」を知ろうという動きにつながったと言えます。 Q 京都では伝統野菜の生産が盛んで、全国的にも人気がありますが、「スローフード」との関わりではどのように考えられますか。A 京都府の農業生産は、数年前から野菜の生産額が米よりも多くなりました。「都」文化との関係で培われた伝統的で特殊な野菜(例えば、賀茂ナス)のなかで農薬使用などの規制を設定して「京の伝統野菜」というブランドを確立しており、首都圏を中心に大きな需要があります。生産者シールを貼ることは、消費者と生産者との距離感を縮めると同時に、生産者の責任感を高める役割を果たしています。 Q 「食」は、今後どういう方向に向かうとお考えですか。A いつの時代でも消費者は、好みにあった食を求めるというのが現実でしょう。そういう意味で、スローフードは消費者の好みを見直す運動だと言えます。野菜や肉、魚というのは大地や海といった地球環境で育まれた命で、生きるために食べるということは、他の命を貰うことなのです。そうした命を貰って生きているということを感じることが大切で、そうした方向性は出てきていると思います。しかし、スローフード的な農作物を大量生産することは難しいことです。生産規模を容易に拡大できないからです。この点でスローフードは一部の人々の贅沢なのかという批判も一部にはあります。
|
| Copyright(c) Ritsumeikan univ. All rights reserved. |