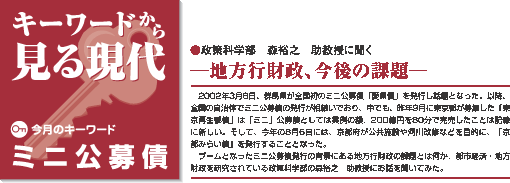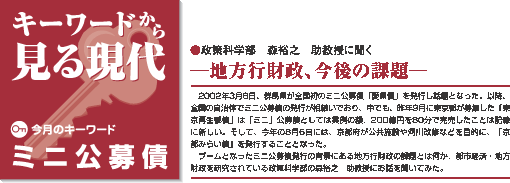Q 現在、全国の自治体でミニ公募債の発行が
相次いでいます。
そもそもミニ公募債とは何ですか。
A 自治体が公共事業の資金を調達する手段のひとつとして地方債があります。地方債の引受け先は政府と民間があり、民間引受けの中に非公募債(縁故債)と公募債の2種類があります。今話題の「ミニ公募債」というのは公募債の一種で、一般個人を対象として募集されるのが特徴です。そのため、購入価格も1万円ぐらいからと金額も手頃で満期期間も短いため買いやすくなっています。今までの公募債は単位が大きく、また財政規模の大きな自治体に発行が限られていました。しかし、国の後押しによって、起債の許可があれば小さな市町村でも公募債を発行できるようになりました。また、対象をその地域の住民や企業で働く人に限定しており、出来るだけ多くの地元関係者に持ってもらおうとする意図が伺えます。そのため今かなり多くの自治体で「ミニ公募債」が発行され、これからも増えていくと思います。
Q 小泉内閣が進める三位一体の改革との関係で、
自治体のミニ公募債発行が示す意味は何でしょうか。
A 三位一体の改革は、自治体における地方税、国庫補助負担金、地方交付税を一体として地方財政制度を改革するというものです。そこには自治体は自らの税金収入でもって行政を行うべきだという地方自治の理念が伺えます。しかし、現実に目を向けると、国の財政は未曾有の危機ですし、国からの財政移転がなければやっていけない小規模市町村はかなりの数に上ります。そのため、この改革を進めても、自治体の財政全体が豊かになるというのは考えられません。「ミニ公募債」はこのような財政状況の底流に位置づけられるのだと思うのです。すなわち、「必要なお金は自分で集めなさい」という考え方です。自治体は、住民の支持を得やすいミニ公募債を発行して公共施設等をつくるべきかどうかをこれまで以上に真剣に考えなければなりません。国の方針もあって「ミニ公募債」の発行は今後も増えると思いますが、自治体には従来以上に起債責任が重くなってくるのです。
Q 自治体がミニ公募債を発行することの
メリットとデメリットは何でしょうか。
A メリットは、自治体にとっては資金調達先の選択肢が増えたこと、住民にとっては出資することによって行政に参加しているという自覚が出るということです。財務的なところでは、「ミニ公募債」は一般に金利を国債にあわせているため、今のような時代には安全で有利な資産運用という側面もあるでしょう。そして自治体の裁量によって、国債に比べて償還期間を短く細かい設定ができるため、住民にとっては買いやすいと思います。反対にデメリットとしては、この人気にのって「ミニ公募債」が乱発されることが挙げられます。公募債に当てられるものは「ハコ物」が多く、これらの建造物ができることによって後年にわたり維持費などがかさみます。ですから、それが本当に住民にとって必要なものなのかを吟味することが自治体に求められ、もし自治体にそのようなコスト感覚が弛緩していれば、財政危機に拍車をかけかねない懸念があります。
Q 地方分権の推進、および地方財政健全化の
進むべき方向性とはどのようなものでしょうか。
A 日本は今まで道路など公共事業に投資してきたため、福祉や教育が遅れています。世界の中には、北欧のような福祉、医療、教育といった対人社会サービスに財政を投入してきた国や、一方でアメリカのようにそれらを基本的に市場にまかせている国もあります。今日本はアメリカ型へ進んでいるといえますが、今後は北欧型福祉社会の優れたところを摂取しなければならないでしょう。その時に、中心的役割を担うのは自治体です。というのは、福祉や教育は極めて地域に密着したものだからです。実際に北欧諸国でも地方分権を非常に重要視しています。日本でもそのような方向性を見据えて、各自治体が地域に即したサービスを充実させるために、自治体が自律的に活用できる資金を得なければならないのです。しかし今の改革は、地方分権の名を借りた国の財政再建策に過ぎません。このままいけば地方は疲弊します。その中で、各地域の知事や市長会、町村会などが国の改革に批判の声を挙げる動きは今までにない状況と言えます。このように地方、地域が団結し行動することは、国の財政再建策として使われている地方分権を本来の方向へと進めていくための力となり、地方財政健全化に向けた第一歩となると思います。
 |
|
森 裕之
政策科学部 政策科学科助教授
|
|
専門分野:財政学、都市経済論、地方財政論
|
| ■主な著書・論文 |
●『ピッツバーグ市の都市開発政策の評価をめぐって』
(1999年、大阪教育大学紀要)
●『土地開発公社をめぐる自治体行財政の課題』
(2001年、日本地方財政学会編『環境と開発の地方財政』勁草書房)
●『サイモンズ『個人所得税』―包括的所得税の確立―』
(2001年、宮本憲一・鶴田廣巳編『所得税の理論と思想』 税務経理協会) |
|