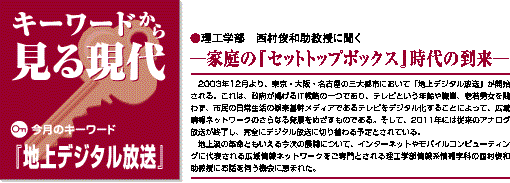Q まずは、現在のテレビ放送のしくみについて、
お聞かせください。
A 現在のテレビの放送は、「地上アナログ放送」が日本では主流です。「アナログ放送」というのは、テレビ画面の明るさを電気信号の強弱で表し、画面信号の強弱をそのまま電波にのせて送信する方法をいいます。この電波は一つの周波数だけでは通信できず、その送信信号の強弱によって中心周波数から上下に少し広がりを見せます。この広がりを電波帯域といいます。この電波帯域を重ねますと混信しますので、例えばラジオの周波数は、9キロヘルツの間隔を空けて放送局を設定しています。ですから、ラジオの周波数は「9」で割り切れる数字なのです。ラジオとは違ってカラーテレビの場合、音ではなく画像を通信するために、大変幅広い電波帯域を使います。色は光の三原色といわれるように3色の色を使いますから、単純に考えますと白黒放送の3倍の電波帯域を必要とするわけです。人類共通の限りある電波資源を有効に利用するために、人間の視覚の性質を利用して映像情報を1/3に圧縮させることで電波帯域をなるべく狭くして通信しているのがNTSCカラーという方法による現在の「アナログ放送」になるのです。
Q 従来の放送と比較した『地上デジタル放送』
の長所とは何でしょうか。
A この「アナログ放送」だけでも特に問題はないのですが、「デジタル放送」にすることによって、その人類共通の限り有る資源でもある電波帯域を節約し有効利用できることはもっとも大きな長所だといえると思います。「デジタル放送」というのは画面信号の強弱をデジタルデータ化して送信するもので、より高い圧縮、狭い帯域で通信することができます。LSI(超高集積回路)とデジタル信号処理技術の発達に伴い、「アナログ放送」での圧縮方法と違って、より高い圧縮の実現が容易になりました。圧縮によって電波帯域の節約になります。結果としてより高品質画像で通信でき、皆さんご存知のデジタルハイビジョンのような映像を楽しむことができるのです。視聴者からみたメリットとしては、周波数の間隔を狭めることで今までよりもよりチャンネルを増やすことでき、色々な放送を楽しむことができることがあげられます。そして、画像以外の大量の情報などもデータ放送でき、ご家庭の機器で便利に利用できます。その他にも電話回線等を接続して双方向通信を追加しますと、これまでインターネット等で提供されていたネットワークサービスのテレビへの統合も可能となり、単にテレビの置き換えではない、より身近なパソコンのようなものになるかもしれません。
Q 日本の国家戦略としてのIT戦略との関わりで、
地上デジタル放送に期待される積極的な役割を
ご紹介ください。
A 地上デジタル放送によって、単にテレビだけではなく、パソコンや端末利用としての一面も持たせることで、これまでの固定概念を超えた広がりが期待できると思います。例えば、デジタル放送によって料理のレシピを入手し、その調理方法をそのままレンジに転送すれば簡単に料理をつくることもできます。まさに、テレビとレンジのコラボレーションが実現するわけです。既存のBS放送あるいはデジタル放送用チューナーのように、既存のテレビに追加機能を持たせる機械を『セットトップボックス』と呼びますが、特にデジタル放送用チューナーにはデジタル信号制御用の計算素子がはいっていますし、家庭の電気機器の多くも制御用の計算素子が入っていますので、ソフトウェアの機能の追加によっては、家庭の電気機器をすべてこの『セットトップボックス』によって連携させることは、技術的にはそんなに難しいことではありません。デジタル放送用チューナーやテレビの導入によって、生活が便利になるデジタル化が知らず知らずの間に進行するでしょう。全ての電気機器がデジタル化されることで電気機器を子どもから大人、そして高齢者の方々もやや取り付きにくい既存の情報通信技術を意識せずにでき、生活の質を向上させていく夢の空間と成り得ると思います。
 |
西村 俊和
理工学部 情報系情報学科助教授 |
専門分野:社会情報学、モバイルコンピューティング、
計算機ネットワーク、ヒューマンコンピュータ
インタラクション |
| ■主な著書・論文 |
●『デスクトップ会議における3次元仮想空間の効果』
(共著、1998年、情報処理学会論文誌)
●『コンピュータネットワーク』
(共著、2001年、オーム社)
●『情報社会とデジタルコミュニティ』
(共著、2002年、東京電機大学出版局)
|
|