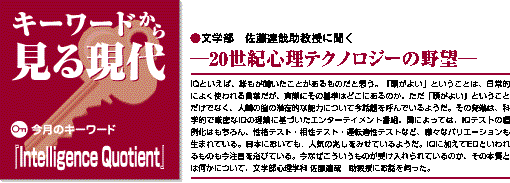
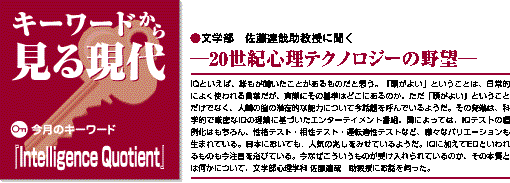 |
Q IQのしくみについてお聞かせ下さい。A 何かを計るときは、体温計のように計測するものを作らなければなりません。そこで、推理能力や知識の量などを「頭の良さ」のようなものとして仮定し、それを知能検査で調べます。その結果を同年齢の集団で比較して指標化したのがIQです。もともと、知能検査は学校に適応できるかを見るために作られました。歴史的にみると、1890年アメリカで「メンタルテスト」という論文が出されました。それから、1905年にフランスで初めてビネが知能検査を行います。この知能検査は児童が障害児である場合に特殊教育を必要とするかどうかをできるだけ客観的に判断する目的で行われました。その後、1916年にはIQという概念が出され1939年から現在のIQになります。IQを一言で言うと、単純に人の頭の良さを一次元で表そうとする野望の現れで、まさしく「20世紀的なテクノロジー」だと思います。それまでは身分によって職業や出世が決まっていたから知能を考える必要はありませんでした。しかし、近代社会になって客観的に人の能力をとらえようとしたことが知能検査を必要としたのです。
Q IQが表す脳のメカニズムについて、
A 生物学や脳科学が発展すると、「頭の良さ」には何か基礎となるべきものがあるのではないかという思いがでてきます。しかし、現在のIQと脳のメカニズムには何も関係がないと考えています。なぜならば、脳を何らかの形で計測してみても、それは生活の本質には何も関係していないからです。たとえば、夢をみることを脳波や他の手段で計測できたとしても、夢の内容までわからないのです。動物の脳とヒトの脳を比べてヒトの脳の方が大きいから脳には意味があるのではないかと考えたりもしますが、そのような比較自体が恣意的であり、本質的に違うもの同士の比較や人間が最上位であると仮定した考えは論理的に問題があると思います。
|
 |
|
佐藤 達哉
文学部 心理学科助教授 |
|
専門分野:社会心理学・心理学史
|
| ■主な著書・論文 |
| ●『心理学論の誕生(Psychology Studies)』
(共著、2000年、北大路書房) ●『知能指数(Intelligence Quotient)』 (単著、1997年、講談社) ●『通史 日本の心理学 (The History of Japanese Psychology)』 (共編著、1997年、北大路書房) |
| Copyright(c) Ritsumeikan univ. All rights reserved. |