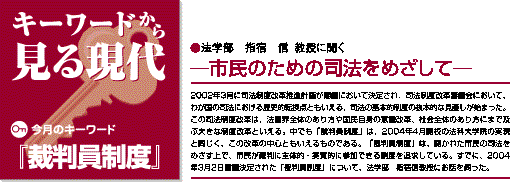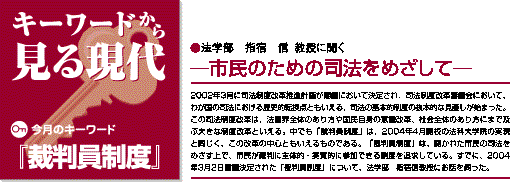Q 裁判員制度とは何ですか。
現在の制度と比較してお聞かせください。
A 現在の日本の裁判は、司法試験に合格した職業裁判官だけが判決を下します。そこには市民の参加はありません。しかし、今回導入される「裁判員制度」というのは、職業裁判官と裁判員となる市民が一緒になって有罪か無罪かを決めます。これは、民主主義のもと、立法・行政・司法の三権分立それぞれにおいて国民が主権であることを示すものといえます。特に、死刑や無期懲役を科すような殺人事件や重大な凶悪事件の刑事裁判は、国民の声をもっと尊重するために市民が参加する裁判員制度に限定して裁かれます。また、裁判員は国民の義務とされ、選挙の投票に用いられる当該市町村の選挙人名簿に登録された中から無作為にクジで選定されます。選定されれば特別な理由なしに拒否することはできません。そして、裁判員は1個の事件について出頭し、裁判上知り得た情報は裁判後も守秘義務を負い、違反した場合は懲役または罰金など厳しい懲罰が科せられます。
Q 裁判員制度導入の背景には
どのようなことが挙げられますか。
A 裁判の制度については戦後ずっと議論されてきました。日本において市民参加の制度は決して新しいものではありません。立命館大学の陪審法廷からも伺えるように、戦前、わが国は陪審制度を行なっていた時期があります。大正デモクラシーの中、自由民権運動が活発化し、普通選挙法が施行され、同時に陪審制度が導入されたのです。今も裁判所法第3条に実施できると明記されています。ところが、太平洋戦争中に陪審裁判は行なわれなくなりました。その理由として、陪審裁判を行なうには陪審員の宿泊や食事の用意なども必要だったために、裁判所に宿泊施設等を完備したりと大変お金がかかったこと、しかも、陪審裁判では陪審員の判断に不服な場合、裁判官は陪審を交代させる事ができ、裁判官の思うように判決が下されたことです。その後、陪審制度は停止されたままです。このような中、1990年代頃から被害者の心情を汲み取った裁判をおこなうべきだという声や陪審制を復活させるべきとの意見から、もう一度、陪審制度を視野にいれ、世界に例を見ない日本独自の制度を検討しはじめたのです。
Q 諸外国における裁判はどのようなものですか。
A 世界的にみて、裁判に一般市民が参加するのは当然の事とされています。日本のように職業裁判官だけが審理するのは大変珍しく、先進国では他にオランダのみです。世界の裁判制度には、主に陪審制度と参審制度の二つに分けられます。陪審制度は、義務として事件毎に選ばれた市民の陪審員だけで有罪か無罪かを決めます。職業裁判官は、法廷で進行役を務め、もっぱら量刑を決めます。つまり分業化されています。このような陪審制度は、英国や英国の植民地であった国などで導入されています。一方、参審制度は、職業裁判官と市民から選ばれた参審員が一緒になって審理します。この参審員は、主に政党などの推薦によって選ばれ、一年間といった任期を持って比較的長期間その職につきます。ですから、陪審制度と違って、参審員には義務はないけれども、推薦によって決められるので、一定の階層や職業に偏ってしまいます。このような参審制度は、ドイツなどで導入されています。また、北欧は、その両制度を導入しています。日本の裁判員制度は、参審制度に近い制度ですが、二つの制度の折衷型ともいえます。
Q 裁判員制度を導入することについて
問題点はありますか。
A 5年間の周知期間に議論すべき事はたくさんあります。中でも裁判員制度が導入される刑事裁判は、事件そのものが殺人事件であったり、重大な凶悪事件であるために、審理の中で目を背けたくなるような残酷なものを目にしたり、聞くに堪えない証言等を聞かなければなりません。そのために、裁判員自身が精神的苦痛によりPTSD(心的外傷後ストレス障害)に陥る可能性が想定され、市民に対する事後的ケアも必要となります。また、裁判後も守秘義務を負うこと、マスメディアの裁判員との接触の規制や報道の自由、表現の自由にも議論の余地は十分にあります。集中的な審理が予定されているので、裁判前に被告人側に十分な準備、特に検察官が持っている情報へのアクセスを認めることも必要でしょう。そして、国民の義務を果たすという意味においても、司法教育というものを充実させていく必要があります。国民主権のもと、司法においても裁判に係っていかなければならないという国民の意識改革を図る必要があります。大正時代に陪審制度を導入するにあたり、全国で千回以上も啓蒙映画を上映したと聞きます。裁くということは、国家権力で裁かれるということです。この国家権力は、市民の意思を反映した力です。裁判では、その力は人の命をも奪う事ができるほど恐ろしい力となります。だからこそ、市民は司法に参加し、真の民主国家をめざしていかなければならないと思います。
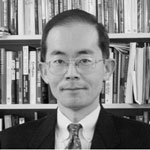 |
|
指宿 信
法学部教授 |
|
専門分野:刑事手続法・サイバー法・法情報学・
刑事訴訟法 |
| ■主な著書・論文 |
●『刑事手続打切りの研究』
(1995年 日本評論社)
●『サイバースペース法』
(2000年 日本評論社)
●『法律学のためのインターネット』
(2000年 日本評論社)
| |