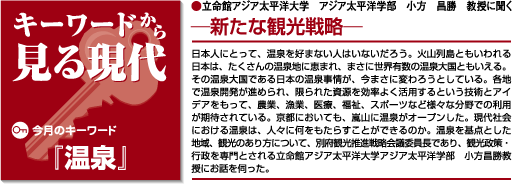
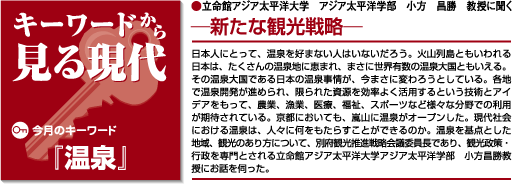
Q 日本の温泉の歴史についてお聞かせください。A 我が国において「温泉」が何時始まったかについては地域によって諸説があり、正確に述べることは難しいと言えます。 例えば、京大の地球熱学研究施設によると、別府の温泉は5万年前にさかのぼると言われています。しかし、「温泉地」という観点から見ますと、「古事記」や 「日本書紀」などの歴史的文献に温泉に関する記述が多く見られ、その中に日本三大古湯と呼ばれる『伊予の湯(道後温泉)』、『牟婁の湯(白浜温泉)』、 『有間の湯(有馬温泉)』が読み取れます。また、鎌倉時代に武士や僧侶が熱海温泉や伊豆山温泉で湯治を行ったことや、珍しいところでは、戦国時代に治療の ために温泉を利用し、また蒙古軍との戦いで傷ついた兵士が別府温泉で治療を行っています。江戸時代には、大名たちが湯治する温泉地が整備され、庶民でも特 別の許可を得て湯治を行なうようになりました。明治には、「日本の温泉医学の父」であるベルツ博士によるドイツの温泉医学や温泉地開発の指導が行われ、温 泉は従来の「湯治場」から「保養地」へと大きく変化します。大正、昭和には、温泉別荘地としての開発や鉄道網の充実を背景に、都市部から温泉地に人々が訪 ねるようになり、さらに近年にはレジャーランドやクアハウスを模した温泉地が現われ利用者層の多様化が生じています。障害者や老齢者に配慮した施設整備や 成人病対策等を含めた「温泉福祉」の分野への取り組みも進められています。 Q 温泉の条件についてお話しください。A 日本温泉協会によりますと、我が国には3千ヵ所を越える温泉地があり、多くの人々が利用しています。「温泉」の基準 については1948年に制定された「温泉法」があり、温泉とは「地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除 く)、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」とされています。この場合、温度は25℃以上(温泉源から採取された時の温度)であり、物質の方は遊離炭 酸、水素イオン、フッ素など計19種の内のいずれか1つを含んでいれば温泉としての条件を満たすことになっています。この幅の広い条件のために、どうして も「温泉」が多種多様なものとなってしまい、玉石混交の様相を呈することになっています。入浴用としての温度不足に対応する加熱、湧出量不足を補う加水、 温泉の循環利用などの問題発生は、この条件の性格によるところが高いように思われます。 Q 昨今のように都心部に掘削して作られる
|
 |
|
小方 昌勝
立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部 教授 |
|
専門分野:エコツーリズム論・アジア太平洋観光論・
観光政策行政論・観光システム論 |
| ■主な著書・論文 |
|
●『国際観光とエコツーリズム』 (2004年3月第2刷文理閣) ●『アジア太平洋における観光振興と課題』 (2003年6月国際観光サービスセンター) ●『都市間ネットワーキングの課題と展望』 (2003年9月アジア太平洋都市間観光振興機構) ●『観光振興による町づくりの諸問題』 (2004年2月都市問題研究会) |
| Copyright(c) Ritsumeikan univ. All rights reserved. |