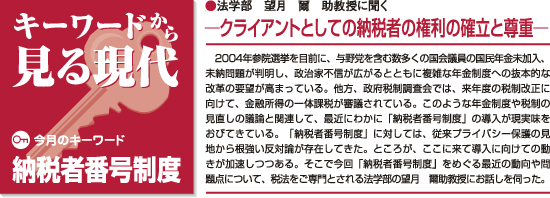Q 最初に「納税者番号制度」について、お聞かせ
ください。
A 「納税者番号制度」とは、納税者に広く番号を付与し、納税者や金融機関等の取引の相手方の税務当局に提出すべき課税資料にその番号を記入することを義務付けて、その番号を照合することにより、納税者に関する課税情報を集中的に整理し管理する仕組みのことをいいます。金融取引等から生じる納税者の所得捕捉の正確化が図られ、徴税の効率化や脱税の防止につながるなどの利点があるとして、政府税調を中心に長年導入が検討されてきました。1980年には、類似の制度として「少額貯蓄等利用者カード(グリーンカード)」を導入する法案が成立しましたが、金融機関等からの強い反対にあって実施が見送られました。それ以降も最近に至るまで、政府税調は答申や報告のなかで度々導入を提言してきましたが、結局今日まで実現していません。その一方で、納税者番号制度の導入につながる動きとして、基礎年金番号や住民基本台帳法に基づく住民票コードといった番号制度がすでに導入されています。
Q 世界主要国の状況はどうですか。
A 先進各国の納税者番号制度には、大きく3つの方式があります。まず第1に、「アメリカ方式」があります。これは、社会保険の受給管理を目的とする社会保障番号の仕組みを、税務をはじめ幅広い行政分野に利用する方式で、アメリカやカナダで導入されています。わが国では、基礎年金番号の利用を拡大する案がこれに当たるといえます。第2に、「北欧方式」があります。これは、北欧各国をはじめ、韓国、シンガポールで導入され、出生や国内居住を機会に強制的に付番する住民登録番号を利用するものです。共通番号制として、税務だけでなくあらゆる行政分野に利用されています。わが国の場合でいえば、住民票コードの利用を拡大する案がこれに該当します。第3に、「イタリア・オーストラリア方式」があります。これは、イタリア、オーストラリアで導入され、税務当局が納税者に付番し利用目的も基本的に税務に限定されています。ただし、いずれの国も、導入当初は番号の利用目的が限られていましたが、それぞれの事情に合わせて民間による利用も含め、番号の使用範囲が拡大しています。それに伴い、実際に個人情報の濫用やプライバシーの侵害などの問題が発生しています。これに対し、各国とも、プライバシー法や情報公開法、納税者権利憲章の制定やデータ照合の規制、オンブズマン(行政監察官)の設置などの対策をとっています。
Q 今次、制度導入の背景には、どのようなものが
ありますか。
A 大きく3つの要因が挙げられます。第1に、「年金の一元化」に代表される年金改革の動きが関係しています。今話題の年金問題を解決する一つの道筋として、年金制度を一元化することで負担と受給の公平化を徹底するという案があります。そのために、基礎年金番号を利用した納番制を導入して所得捕捉の正確化を図り、保険料の適正な徴収と負担を確保するという声が与野党の国会議員から聞かれます。第2に、「金融所得の一体課税」が挙げられます。近年、政府税調を中心に、金融取引から生じる利子、配当、株式譲渡益等の課税の一体化が議論されています。これを進めるために、選択的に納番制を導入して税務当局による金融所得の捕捉の正確性を確保する一方、納税者に異なる金融取引による損益の通算を認めるという案が有力となっています。第3に、「税務行政の情報化の推進」が挙げられます。国税庁では、課税事務の総合的な情報システム化を進める目的から、「国税総合管理システム(KSK)」の開発、整備を進めてきました。また、今春からは、「電子申告(E-TAX)」の導入が本格化しています。そのような税務行政の情報化を、より一層推進するための制度的基盤の一つが納番制といえます。特に、最近の政府税調での議論によると、当面は金融所得の損益通算を認める条件として、希望者に独自番号を付与する「選択的納税者番号制度」の導入が有力視されています。
Q 納税者番号制度を導入するに当たっての問題点
は、どこにありますか。
A 納税者番号制度の導入には、プライバシーや知る権利の保障など人権面での十分な配慮と行政内部の情報管理体制の整備が必要不可欠です。わが国でも、2001年4月の情報公開法の施行に続き、来年度からは個人情報保護法が完全施行されますが、プライバシーや知る権利の保護については、いまだに多くの課題が残る現状があります。また、わが国では納税者権利憲章が制定されておらず、納税者の権利が十分に確立し、尊重されているとはいえません。納番制を導入している先進国では、納税者権利憲章を制定して、プライバシーの保護をはじめ、納税者の「クライアントとしての権利」が明確な形で保障されています。他方、電子政府化推進の方針のもと、税務行政の情報化が進められていますが、情報システムやその管理体制の面での問題も少なくありません。事実、電子申告や国税庁の申告書作成システムでの技術的なミスやKSKの情報セキュリティ上の問題点が指摘されています。さらに、情報の流出や漏洩、目的外利用などを防止する内部の管理体制も十分に機能しているとはいえません。当面の議論は、金融所得の一体課税を目的とする選択的導入ということですが、納税者番号制の導入は、「国民総背番号制」へつながる恐れもあり、今後の動向をよく注視していく必要があると思います。
 |
望月 爾
法学部助教授 |
専門分野:税法 |
| ■主な著書・論文 |
●『アメリカにおける納税者の権利保護』
(単著、2002年、中小商工業研究所・「世界の納税者
権利憲章」所収)
●『アメリカ内国歳入庁の抜本改革と納税者の権利』
(単著、2001年、静岡大学法政研究)
●『OECDによる納税者の権利憲章の指針』
(単著、2003年、税制研究)
|
|