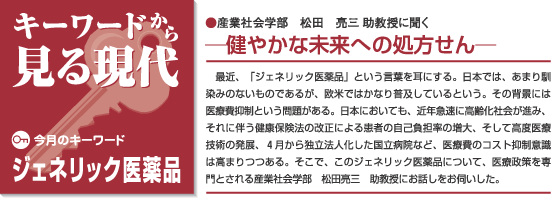Q ジェネリック医薬品とは、どのようなもの
ですか。
A 医薬品の種類には、医療機関で処方される薬と薬局で売られている薬(オーバーザカウンタードラッグ)とがあります。ジェネリック医薬品とは、その処方薬の中で新薬の特許が切れている薬のことをいいます。新薬の市場や開発は、今では国際的規模でおこなわれていて、世界の製薬会社上位数社で占められ、日本ではわずかな製薬会社でしかおこなわれていません。その背景には、新薬の開発には大変なお金がかかるということです。その費用は、数百億円以上ともいわれ、また開発に要する期間も10年20年という長い月日が必要です。こうしたコストを薄めるために資本力を増強することを目的に製薬業界は世界的規模で大々的に再編がおこなわれているほどです。それに比べてジェネリック医薬品は、特許が切れていることに加えて、すでに効果も成分もわかっているため、新薬開発のような巨額な開発費も必要がないので、その分安価に作ることができ患者への経済的負担も減らすことができます。また、新薬の場合、ブランド薬ともいわれるようにメーカーの商品名で称されますが、ジェネリック医薬品は一般的な薬品名(化学物質名)で処方されることが多いので『一般的な』という言葉の意味を表しています。
Q 海外の状況についてお聞かせください。
A 海外でのジェネリック医薬品が占める量的な市場シェアは、欧米主要国では約50%に達しているのに対して、日本はわずか10%程度に過ぎません。海外でジェネリック医薬品が多く使われている背景には、経済的政策の中で医療費抑制という問題から、ジェネリック医薬品の使用が強く促されたことが挙げられます。例えば、ドイツでは、医療保険から支払われる金額が一番安い薬に設定されています。そのために、新薬のような価格の高い薬を処方されても、その差額は個人で負担しなければならず、安価なジェネリック医薬品が処方されることが多いのです。また、アメリカでは、日本の医療保険制度と違い、医療保険は民間保険会社が基盤となっているのですが、なるべく薬も安いものを処方するような指導がおこなわれています。それに加えて、『代替処方』というものがあります。これは、医師が処方した薬を薬剤師が成分の同じ薬に変更することができるしくみのことです。このようにアメリカでは、医薬分業というシステムから地域の薬局が発達し、医師とではなく薬剤師と相談することがあたりまえとなっているのです。
Q 日本で今まで使われなかった理由は何ですか。
A 日本では、ジェネリック医薬品を使う政策誘導がなかったということです。また、どのような薬を使うべきかということは、医師の特権領域ではありますが、医師のなかにはジェネリック医薬品を処方することへの不安もあります。ジェネリック医薬品は、確かに薬の成分については新薬と同じですが、新薬の特許が切れた後、別の製薬会社で製造されるために薬の製造方法が違ってきます。そのために、病気の人に対する効果が実際に評価されていないということは、医師にとって不安に感じる理由のひとつだといえます。しかしながら、最近の厳しい経済状況で医療費の抑制が叫ばれる中、安価なジェネリック医薬品が注目され、「安くて同じ薬ならなぜ使わないのか」と議論されるのも当然のことだと思います。
Q 今後どのように進展するとお考えですか。
A 日本においてジェネリック医薬品を普及させるためには、まだまだ議論すべきことはあります。特に医薬品の場合、医師の理解がなければ進まないのが現状だと思います。その観点から、まず、ジェネリック医薬品メーカーの体制が挙げられます。ジェネリック医薬品メーカーの多くは中小企業のため、生産量が少なく、在庫が少ない傾向にあるので、薬を常に調達してもらえる体制をつくる必要があります。また、薬がマーケットに出たあとの副作用に関する情報収集体制を十分にすることも大切です。さらに、アメリカのように、より医薬分業を促進させることで、地域の薬局の役割が広がり、医師ではなく薬局と相談した上で『代替処方』できる制度が法的に可能になれば広がっていくと思います。そして、その中で製薬企業・医師・患者間の信頼関係が築き上げられることが重要でしょう。現在、独立法人化した国立病院などで導入の検討ははじまっています。しかし、医療費問題についてはジェネリック医薬品の導入だけで解決するような簡単なものではありません。ただ、現代社会に多くみられる生活習慣病などの慢性疾患に対応する新薬の特許が切れはじめている今、ジェネリック医薬品のマーケットは広がっていく可能性は大いにあると思います。
 |
| 松田 亮三 |
産業社会学部 人間福祉学科助教授 |
|
専門分野:比較保健・医療政策、地域保健・健康づくり |
| ■主な著書・論文 |
●『欧州の医療財政の経験から何を学びうるか』
(単著、2003年、日本医療経済学会会報)
●『医療制度改革におけるケース・ミックス分類の導入−スウェーデンと英国の経験』
(単著、2003年、月間国民医療)
●『グローバリゼーションと“下から”の保健医療政策
(共同、2003年、国民医療研究所編『21世紀の医療政策づくり』本の泉社)
|
|
Copyright(c) Ritsumeikan univ. All rights reserved.
|
|