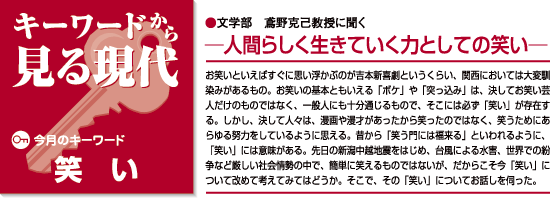
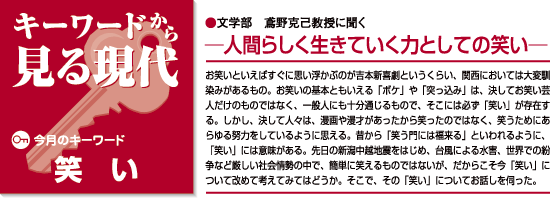
Q 笑いについて、どのようにお考えですか。A 笑いは、人間が人間らしく生きていく上でもっとも重要な生きるワザや術だと考えています。笑うという能力は、生まれながらにして誰もが持っているものです。でも笑う能力を上手に引き出し、活かし、そして花開かせるためには、それなりに笑いについてのセンスを磨いたり、育てたり、あるいは刺激を与えてより活性化するような努力が必要です。生まれつき持っていても、環境や状況によってその能力が妨げられたり、抑えつけられたりすることは、笑いについてもあてはまると思います。例えば、笑うことをすごく前向きに捉えられる環境で育ってきた場合と、笑いが専ら不謹慎や失礼と見なされ、笑うことを戒められる環境で育ってきた場合とでは、その人の笑いに対する構えや振る舞いは大きく違ってくるのです。 Q 笑いにはどんな力がありますか。A 私たちは通常、真面目に、ひたむきに努力し、目標に向かってまっすぐに進んでいく生き方こそ好ましいと思っています。そして、笑うことは、ふざけや茶化しと結びつく不真面目さとして、一見悪いイメージを抱かれがちです。確かに私たちは目標によって行動に方向性を与えられますが、同時にそれは目標に行動が縛られることでもあります。とすれば、目標を掲げてひたすら努力することだけが、人間の人間らしい生き方として、ただひとつの目指すべき姿なのかどうかと反省してみる必要があります。笑いを、ただ単に不真面目なものと捉えるのは誤りです。笑いは、「真面目―不真面目」といった図式を突き破った意味の次元を、私たちの生き方にもたらします。まっすぐに目標を持って生きていけている時はそれでいいのですが、その目標が失われたり、色あせたりした時、目標を拠り所とする生き方は大きく崩れてしまいます。そんな時、笑いは、どんな高遠崇高な目標であれ、私たちがひとつのものを絶対視して、それにすべてを注ぎ込んで身動きがとれないでいる状態を緩め解き放つ力を持っています。 Q 厳しい社会情勢の中「笑い」の活用法について
| ||||||||
 |
|
| 鳶野 克己 | |
|
文学部人文学科教育人間学専攻
|
|
|
専門分野/教育哲学、人間形成論、人間関係論
|
|
| ■主な著書・論文 | |
| ●『先生は眠らない―生の誘惑としての教育―』 (単著、2003年、皇紀夫編『臨床教育学の生成』 玉川大学出版部) ●『生の冒険としての語り―物語のもう一つの扉―』 (単著、2003年、矢野智司・鳶野克己編『物語の 臨界―物語ることの教育学―』世織書房) ●『笑いのスタンス―「笑いの人間形成論」ノート―』 (単著、1996年、光華女子大学人間関係学科編 『人間関係のプリズム』ナカニシヤ出版) |
|
| Copyright(c) Ritsumeikan univ. All rights reserved. |