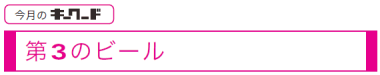|
|

|
|
経営学部 齋藤 雅通 教授に聞く 酒税格差から生まれた新しいビール 「第3 のビール」と呼ばれるビール風炭酸アルコール飲料が、今年に入りビール市場でシェアを拡大している。ビールと同じような風味があるが、酒税法上の分類はビールでも発泡酒でもないため、低い価格設定で販売されている。今回は、ビール・発泡酒を含めたビール関連市場の中で、出荷量が2 割に迫る勢いで消費者の支持を広げている「第3 のビール」の市場動向について、経営学部 齋藤雅通先生にお話をうかがった。 |
|
|
|
第3のビールとは?
「第3 のビール」は税率が高くなる要因である麦芽の代わりに、大豆やえんどうを原料とするビール風アルコール飲料のことです。すでにビール(350ml 缶あたり約78 円)よりも税率が低い発泡酒(同、約47 円)がありますが、酒税引き上げによる発泡酒の「うまみ」である安さのメリットが少なくなったところに、雑酒ビールとして更に低い税率(同、約24 円)の「第3 のビール」が登場しました。 日本の場合は、ドイツなどと違ってビールの原料にこだわるような伝統がないため、税率の低い雑酒類でビール風味を打ち出すことに対してそれほど戸惑いが無かったということが、第3のビールが大きく売り上げを伸ばしてきている理由の一つにあげられます。また高度な食品加工技術で、麦芽を使わずにビール風味を出せたことも要因といえます。他の国ではちょっと考えられないでしょう。 消費者がこれまでビールと発泡酒を飲むシーンを考えた時に、晴れの日にはビール、普段は発泡酒を飲むというように「飲みわけ」が行われています。第3 のビールも価格が安く、家で気軽に飲めるという点が支持されているのでしょう。ビールよりもすっきりした味わいが人々に受けている面もあります。清涼飲料水と同じくらいの値段で、自動販売機で気軽に買える点も、大きな特徴です。 | |||
|
|
|||
|
シェアが激化するビール業界についてお聞かせください。
業界1 ・2 位のアサヒ(2003 年度市場シェア39.9 %)・キリン(35.7%)の2 社よりずっとシェアの低いサントリー(10.4 %)とサッポロ(13.2 %)が、発泡酒や第3 のビールを生み出しました。これは下位メーカーが起死回生を賭けて、発泡酒や第3 のビールを出すことで業界の市場構造を変えるような戦略を取ろうとしたものです。 しかし消費者から低価格のビール風飲料に強い要望があったのだろうかと考えると必ずしもそうではなく、市場シェアをめぐる競争の結果として新しい味わいのビールが誕生したといえるでしょう。 | |||
|
|
|||
|
海外のビール市場についてお聞かせください
国内でのビール出荷量は第3 のビールを含めても年々減少しているので、成長しようとすれば総合飲料メーカーとして展開することや、海外への進出が重要となります。 ビールの海外での展開は、自動車やデジカメ、家電製品などとは異なる方法となります。家電製品や自動車などの製品分野では世界を股にかけて競争が行われ、アメリカでマーケットシェアが大きいことは、ヨーロッパで成功するための一つの取っ掛かりになっています。しかしビールの競争は世界規模では行われていません。ビールをはじめとする、加工食品や、シャンプー・洗剤などは、それぞれの国ごとに競争が行われています。これは生活文化の違いが大きく影響するためです。ですから世界1 位や3 位のバドワイザーやハイネケンが本格的に日本に参入しても、世界的なブランドだからといってアサヒやキリンのシェアを簡単に奪えるかというとそういう競争にはならないのです。 したがって国際的成長を見ていく上では、ビールメーカーは日本のビールを輸出するのでなく、例えばサントリーが中国の上海に進出し、日本で発売しているものと全く異なるテイストの大衆向けビールを発売することで、圧倒的シェアをとり、大成功した例があるように、それぞれの国ごとに戦略を考える必要があります。
|
|||
|