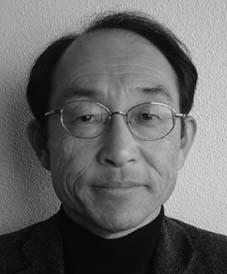|
|

|
|
経済学部 佐藤善治 教授 に聞く ストレスマネジメントのスキル いよいよ2006年2月から14日間に渡りイタリア・トリノにおいて冬季オリンピックが開催される。日本勢はスピードスケート、フィギュアスケートなど各種目でメダルの期待がかかっている。大きなプレッシャーの中、選手が最高のパフォーマンスを発揮するにはフィジカルの充実とともに大舞台でも揺らぐことのない強靭なメンタルが不可欠である。今回のキーワードでは「メンタルトレーニング」に焦点を当て、ストレスに対するメンタルのマネジメントについてスポーツ心理学を専門とされる佐藤善治経済学部教授にお話を伺った。 |
|
|
|
メンタルトレーニングとは
運動のパフォーマンスを最大限に引き出すために身体の各部の筋力や持久力を鍛えたり、筋肉をスムーズに動かすためのスキルを身につけるトレーニングを「フィジカルトレーニング」と呼ぶのに対し、緊張による神経の興奮や不安・懸念といった不愉快な思考など、一般に「あがり」と呼ばれる精神的ストレスをコントロールし平常心を保ったり、自分のモチベーションを常に高いレベルで維持させていく「心理的なスキル」を鍛えるトレーニングを「メンタルトレーニング」と呼んでいます。 | |||
|
|
|||
|
メンタルトレーニングが重要視される背景
オリンピックを例に取った場合、選手は大きなストレスの中に身を置いています。その原因のひとつはスポーツの高度化です。さまざまな近代技術がフィジカルトレーニングに導入され、競技レベルは回を増すごとに高くなっています。しかし、どれだけ激しいトレーニングを重ねても選手にとって完璧ということはありません。人間は何らかの原因で思いもよらないミスを起こします。トレーニングを重ねれば重ねるほど選手は失敗を恐れる心理的ストレスと戦わなければなりません。 また競技の結果に対する付加価値が非常に高くなってきたことも挙げられます。今やスポーツの商業化は進み、オリンピックも例外ではありません。成績次第では地位や名誉とともに大きな経済価値を手にすることが可能です。代表選手に選ばれるか否かでその後の生活にも大きな変化をもたらします。またトレーニングに多額の資金、膨大な時間と労力を投入している例が多くある中、選手は国民やスポンサー企業の期待を一身に背負い、期待に応えなければならないというストレスにさらされます。 1964年の東京オリンピックでは既にソ連やイタリアなどが心理学の分野の研究者を同行させ神経的な症候を示している選手のケアに当たっていますが、オリンピックの発展とともにメンタルトレーニングの重要性も増してきたと言って過言ではありません。 | |||
|
|
|||
|
メンタルトレーニングはどのように進化を遂げてきたのでしょうか
これまでの研究の中でスポーツ選手に必要な「心理的スキル」が確立されてきました。大きく①イメージのスキル、②心理的エネルギーの管理、③ストレスの管理、④注意のスキル、⑤目標設定のスキル、に分けられますが、これらのスキルは互いに密接な関係にあり、それぞれのスキルを強化することで、選手は総合的なメンタルの強さを手に入れることが可能です。例えばイメージのスキルを伸ばすトレーニングは自分自身の競技での成功のイメージを何度も頭の中で繰り返すため、注意集中の焦点をより明確化し、無理のない力を高め、リラックス状態をもたらし、ストレスをマネジメントする力を伸ばすことに繋がります。またストレスのマネジメントスキルを養うことによって、より大きなストレスを心理的エネルギーに変えプラスに作用させることができるようになり、今以上に挑戦的でかつ現実離れしていない目標を自ら設定し、達成するための内発的モチベーションを持続させることが可能になります。映像と瞑想に呼吸法などのリラクゼーションを取り入れたイメージトレーニングをはじめ、各競技の性質に合わせて各々の心理的スキルを伸ばしていく方法が開発されています。トレーニングの過程ではコーチが適切な指導やアドバイスで選手の心理的スキルを高めていくことが重要です。大舞台で結果を残す選手はコーチの指導により「心理的スキル」を磨き、最終的に自らの力でモチベーションを高め続けていくサイクルを作り出すことに成功しています。 | |||
|
|
|||
|
メンタルトレーニングはビジネスにも有効でしょうか ここ数年で「コーチング」という言葉がビジネスでも定着してきました。スポーツにおけるコーチングとビジネスでのコーチングには共通する点が数多くあると思います。スポーツ界で実績を上げた監督やコーチにビジネスセミナーでの講演依頼が多いことはそのことを物語っています。例えば営業マンを選手と置き換えた場合、彼らはどうすれば売り上げが上がるかを課題に直面する運動選手と同じような複雑な心境で考えています。このとき彼らに「心理的スキル」に関してある程度の知識と経験があれば業務に対してもそれが有効に働くと思います。消費者が喜んでいるイメージを高めてセールストークに変えていったり、どこに顧客が喜ぶポイントがあるか会話の中で注意を払ったり等々。適度な目標設定を行い、それをクリアすることで自信を持たせ最終的には自分でストレスをマネジメントしモチベーションを持続する力を身に付けさせる。個人の心理的スキルに対する意識と指導者のコーチングがうまくマッチすれば選手、すなわち社員のパフォーマンスは継続的に上昇していくことに成功するでしょう。
|
|||
|