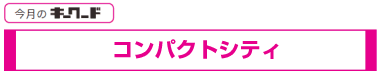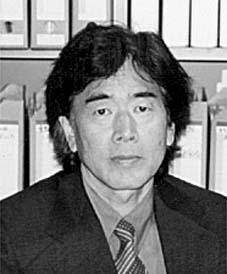|
|

|
|
政策科学部 高田 昇 教授に聞く 持続可能な都市づくりへの新たな潮流 行政・商業機能や住民を街の中心部に集める「コンパクトシティ」づくりが地方で加速している。人口減や高齢化、自治体の財政難に対応し、インフラなどを中心部に集中して中心商店街などの活性化や公共投資の効率化を図る狙いだ。コンパクトシティの普及してきた背景や各地域の代表的な取り組み、人々のライフスタイルの変化などについて政策科学部の高田昇教授に伺った。 |
|
|
|
コンパクトシティとはどのような町のことを言うのでしょうか
昔の城下町やヨーロッパの中世都市を思い浮かべると、コンパクトシティのイメージが描きやすいでしょう。それは寺院や広場が町の重要な位置にあり、住まい、仕事場、学校、公共施設などが身近なところに一通りそろっている情景です。広がりすぎた現代都市の歪みを正していくのに、歴史都市から学びつつ、公共交通の見直しや都市に住みよい生活環境を再生する動きが世界的に強まっています。 コンパクトシティとは何か?という問いに、決まった定義が確立している訳ではありませんが、ほぼ共通した考えが定着しつつあります。そこには、分散せず集約させる居住・就業、複合的な土地利用、明確な都市の境界、自動車だけに依存しない交通、日常生活の自足性、地域運営の自立性、といった要素が含まれます。特に大切なのは、都市の成長をコントロールして、環境と共生し、都市が空洞化したり、肥大化することなく持続させることです。 | |||
|
|
|||
|
コンパクトシティが採用されている背景について教えてください
住宅やショッピングセンターをつくるのに市場原理に委ね、自動車の普及にまかせた流れの中で、病院や福祉・文化施設までが、ロードサイド型の店と並ぶ状況が普通のようになっています。しかし都市の拡散、郊外化のもたらした弊害は、多方面にまたがって表面化しています。一見合理的とされた土地利用を分ける方法は、結果として通勤時間を長くし、自動車の量と移動距離を大きくし、郊外開発による環境問題を多発させ、画一的な景観を生み出したのです。 このような流れに歯止めをかけようと、1990年代に入ってコンパクトシティはEUが提唱し、イギリス、ドイツ、オランダ、そしてアメリカでも都市政策のキーワードとして重視されるようになってきました。 | |||
|
|
|||
|
各地での取り組みについて代表的なものやユニークなものについて教えてください
たとえばドイツの中小都市には、伝統的にその見本となるようなところが多くみられますが、これこそコンパクトシティ、という実物は世界のどこにもまだ存在しません。私はイタリアのフィレンツェで、コンパクトなまちの良さを実感したことがあります。駅から歩けるところに、住宅とオフィスやレストラン、ホテルが近接してあり、フェラガモ本社のようなブランドショップと庶民が楽しめる店や青果・肉屋さんが並び、観光客が訪れるドオーモ、シアター、カフェがあります。ドイツのデュッセルドルフでは、LRTを走らせ、市街地はオシャレで緑あふれるオープンモールに生まれかわり、古いビルはリニューアルされて幼稚園や高齢者のサロンに再生されている光景がみられます。都市のセンターが生き生きとしているのです。 日本でも、10年程前に青森市が「コンパクトシティ宣言」をして、活気がみられない中心部に、分散した都市機能を集めよう、との試みがはじまっています。神戸市では、大都市型のモデルをめざしています。しかし現実には、全国的にみてもまだまだこれからのプロジェクトとして、出発点に立ったばかりといえるでしょう。 | |||
|
|
|||
|
コンパクトシティの未来像について教えてください 超高層ビルが林立し、その間を高速道路が自在に走る、そして郊外には、大規模な住宅団地が広がる・・・そんな都市イメージに代表される見かけの立派さを追う都市建設の弱点を見据え、市民にとってより豊かな暮らしと、より望ましい都市のあり方を求めるという原点に立とう、というのがコンパクトシティのねらいです。 コンパクトシティは、まだ多くの未知の面を残していますが、それに近い都市が実現することにより、期待できる効果が少なくありません。自動車交通を減らすことによるCO2削減、郊外開発抑制による農村・自然環境の保全・活用、市街地の活性化、公共投資の効率化、生活の利便性向上、コミュニティ形成による地域社会の安定、いずれも現代都市の深い悩みへの答えとなりえるでしょう。 2006年5月には都市計画法と中心市街地活性化法の抜本的改正が国会で成立しました。そのねらいは都市計画により、郊外での大規模集客施設立地や新たな開発を抑えること、同時に古くからの中心市街地のにぎわいを回復させることです。ようやく日本でも、もうこれまでの無秩序で不効率な都市拡張はやめよう、との理念をはっきりさせ、コンパクトシティへの取り組みが始動したことになります。
|
|||
|