| |
 |
| (1)確かな基礎学力形成を目指す教学システム構築に向けて |
|

 |
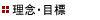 |
 |
| 学生に確かな基礎学力を形成させ、社会に送り出していく課題は、大学教育に求められる基本的な課題であり、本学ではこの課題について総合的な検討を行い、体系的な施策を推進してきている。その内容は、カリキュラムのありようから日常的な個々の授業の改善に関わる問題まで、多岐にわたって展開されてきた。 |
|
 |

 |
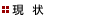 |
 |
| 今年度の具体的な取組みとしては、まずTA予算を大幅に増額し、それにより特に導入期教育の強化と、大規模講義の教学条件の緩和を図った。また先進的教育実践支援制度を新設し、様々なレベルでの授業改善の取組みの経費補助をスタートさせた。更に2002年度からは、各曜日に15回の授業週を確保し、教育の量的保障を行うとともに、質の保障として成績表示を従来の4段階から5段階に変更し、また大学としてGPAを導入する等、学生の到達度をより正確に測れる仕組みをスタートさせる。また従来の講義概要を全面的にオンラインシラバスに移行させ、合わせて内容の改善を図っていっている。 |
|
 |

 |
 |
 |
| 教育の内容を改善・改革する取組みは非常に多側面に及び、この間経年的に取組みを進めてきたが、2002年度をもって1つの段階を迎えたと評価できる。 |
|
 |

 |
 |
 |
| 今後の課題としては、これまでの積み重ねの上にたちつつ、個々の教育内容の改善を図っていくことが必要である。具体的には、2002年度のところで教養教育の在り方の検討、外国語改革の実施等を進めていきたい。 |
|
 |

 |
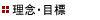 |
 |
| 急速に展開する情報化に対応し、大学教育においてもそれを生かした様々な取組みによる教育改善、学生サービスの改善が望まれている。大学教育においては大きく分けて、学生の情報スキル自体を向上させる教育の展開と、ネットワーク等を活用した教育方法の改善の2つの課題がある。また学生への諸情報の提供におけるネットワークの活用も、サービス向上の視点から要請されている課題である。 |
|
 |

 |
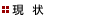 |
 |
本学では2002年度よりコースツールとしてのWebCTをすべての授業で導入するとともに、全ての授業についてシラバスがオンライン化される。またWebCTを活用した双方向型の授業展開も期待されている。情報スキルの向上の面では、全ての学部で1回生時に情報リテラシー科目を設置し、全1回生が受講する条件を整備した。学生サービスの面では今年度より試験的に試験時間割などをメールで配信するサービスも開始し、今後順次拡大していく予定である。
また教育IT化をサポートする組織として「教育IT化支援室」が設置され、日常的教育実践におけるIT化を支援することとなる。 |
|
 |

 |
 |
 |
| 全体としては、本学の豊富な情報資源を活用しつつ、教育分野でのIT化を試行段階から本格的な実施段階へと移行させる状況に至っていると評価できる。 |
|
 |

 |
 |
 |
| 2001年度に検討した教育分野のIT化の基本的な枠組みに基づき、今後順次IT化を推進していくこととなる。特に、教育実践における先進的な事例や、教材開発を進めることと、全学的なIT化の水準(ミニマム)を向上させるという2つの側面で積極的な取組みを行なうことが大きな課題である。 |
|
 |

 |
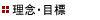 |
 |
| 大学教育において、従来型の座学だけではなく、インターンシップや海外実習、あるいは自主ゼミなどを通じて実社会を体験し、また自らが課題設定を行なって学びを深めていくことは、学生の学びの動機付けを強化し、自ら学ぶスタイルを築き上げていく上で重要な要素となっている。本学ではこれら体験型の学習を広く正課に取り入れ、積極的な展開を図っている。 |
|
 |

 |
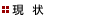 |
 |
インターンシップについては、全学インターンシップ教育推進委員会を設置し、各学部での正課のインターンシップ科目の設置を進めてきた。その結果来年度からは全ての学部で正課のインターンシップ科目が設置されることとなる。また、キャリアセンターにインターンシップオフィスを設置し、正課外でのインターンシップ先の開拓にも取り組んできた。これらにより、今年度は全学で800名以上の学生がインターンシップを体験するに至っている。また、学生が自らインターンシップ先を開拓し、正課に登録するインデンペンデントスタディ型のインターンシップ科目の設置も進んでいる。
海外実習科目についても年々拡充し、今年度で約220名の学生が、単なる語学研修型ではない海外実習科目に参加している。また、文学部、産業社会学部などで学生が自ら課題設定をして学びを進めて行くステューデント・イニシアチブ科目や経済学部、文理総合インスティテュートでは「プロジェクト研究」の設置が行なわれるなど、自主的な学びの正課への導入が進められている。 |
|
 |

 |
 |
 |
| この間のインターンシップを推進する取組みは全国の大学でもトップ水準に到達している。また多様な学びを正課につなげていくうえで、様々な試みが積極的に推進されてきていると評価できる。 |
|
 |

 |
 |
 |
| 今後の課題としては、インターンシップについては一層量的な拡大を図るとともに、欧米型のコーオプ教育をモデルにした長期のインターンシッププログラムの開発や、海外でのインターンシッププログラムの開拓など、質的にも異なった段階のプログラム開発が求められている。また長期にわたる体験型学習に対応できる単位認定や学籍のあり方の検討も課題となっている。 |
|
 |
|