| |

 |
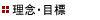 |
 |
| 現在社会的にも後期中等教育と大学教育との接続が課題となっており、また社会の高度化に対応するために大学院教育重視の流れの中で、従来にも増して多くの学生が大学院に進学しており、その中で学部教育と大学院教育のあり方が問われている。総合学園としての本学が、附属校や大学院との有機的な連携をもちつつ大学教育を進めること、また、本学に入学してくる学生がスムーズに大学の学習に入れるように、入学前教育を進めることが重要な課題となっている。 |
|
 |

 |
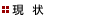 |
 |
本学では今年度、高校生に大学教育を体験させる「立命館サマーカレッジ」を実施した。また早期に本学に合格している生徒を対象に入学前教育を勧める「プレエントランスデー」を実施し、同時にWEBによる入学前教育も試行的に実施した。
大学院と学部教育との関係では、アドバンストプログラムとして多くの学部で大学院科目を受講できる制度を実施しており、また逆に大学院への進学層が多様化する中で、院生の基礎学力を補う目的で大学院生の学部科目受講の制度もいくつかの学部で実施されている。 |
|
 |

 |
 |
 |
| 高大連携については特に近年社会的にも注目される中で、大学として先進的な取り組みを進めてきていると評価できる。また、大学院との連携も経年的に強化をされている。 |
|
 |

 |
 |
 |
| 高大連携については、2002年度より高大連携推進室を設置し、一層積極的な展開を図る予定である。また、大学院との連携についても、今後新たな大学院が相次いで開設されていく中で、一層柔軟な連携のあり方を検討する必要がある。 |
|
 |
 |
| (2)立命館大学・立命館アジア太平洋大学への学内進学の状況 |
|

 |
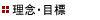 |
 |
| 立命館大学および立命館アジア太平洋大学へ、優れた能力と豊かな個性をもち、学園のあらゆる分野において中核となり、リーダーシップを発揮できる学生を輩出する。立命館大学の入試政策上、附属校からの学内進学の目標値を入学者比20%としている。 |
|
 |

 |
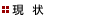 |
 |
| 2001年度において、附属3高校(立命館高、立命館宇治高、立命館慶祥高)から立命館大学へ944人、立命館アジア太平洋大学へ25人進学している。新入生に占める附属校出身者比率は、立命館大学12.76%、立命館アジア太平洋大学3.4%である。立命館大学の学部別にみると最高で17.8%、最低で6.1%となっている。 |
|
 |

 |
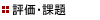 |
 |
| 現在の附属3高校の生徒数からみると、附属校出身者比率はほぼ横ばいで推移すると見込まれる。少子化にともなう各地域の私立高校生徒募集数の自主規制等により、附属高校の生徒数に影響を受けることも予想される。 |
|
 |

 |
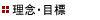 |
 |
| 総合学園の附属校として、その優位性を発揮して中学校、高等学校および立命館大学、立命館アジア太平洋大学の学部、大学院との連携を強め、教育内容を充実させ、社会に有為な人材を育成する。 |
|
 |

 |
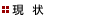 |
 |
特色ある高大一貫教育プログラムとして、2001年度から法学部と附属校の連携講座「附属高校法学講座」(高2・高3対象)および「法学基礎講義」(大学入学後要卒2単位認定、高3対象)を開講し、後者の講座では66人の法学部進学者が単位認定を受けた。毎年6月に附属高校3年生対象オープンキャンパスを開催している。衣笠・BKC両キャンパスで同日開催し、約1,000人の附属高校3年生が、学部等のガイダンス、模擬授業に参加した。本企画は、学部・学科選択の最大の動機づけとなっている。なお今後は、進路選択の早期化にともない、2年生対象オープンキャンパス実施に移行する。
毎年2月に、大学入学前の接続教育として附属校からの進学予定者を対象にブリッジ講座を開講している。2001年度において全ての学部において講座が開講された。
その他、附属校教員による適性を考えた進路指導や大学教員による進路講座・教養講座、初修外国語の附属校における履修者を対象とする既修者クラスの開講等を実施している。 |
|
 |

 |
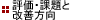 |
 |
| 従来、大学への進路指導を中心に中高大の協力を強めてきたが、全国的な高大連携の進展をふまえて、2003年度学習指導要領改訂を具体化する附属校の改革では、中高大(院)の教育連携を強化する方向を打ち出している。とくに、立命館高校ではスーパー・サイエンス・ハイスクール、立命館宇治高校ではスーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクールの指定をうけるための準備をすすめており、特色ある一貫教育をすすめるために、大学・附属校間の連携を一層強化する。 |
|
 |
|