| |
 |
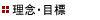 |
 |
| 産業社会学部では社会学としてのディシプリンを共通の基礎として重視しつつも、それを強くうちだすのではなく、その多様性、総合性、現代性という点に学部教学理念の特徴がある。なぜならば、複雑化する現代の人間と社会を理解し、新たな学問のパラダイムを作り上げていくためには、学際的なアプローチが強く求められていると判断するからである。さらに、社会の変化に対応しながら現代的な課題に応えていける優れた学生を社会に輩出していくために、大学での基礎的、系統的な学修に加え、それを社会のなかで実践的かつ再帰的に検証しうるようなアクティブ・ラーニング(自分の足で現場に出かけ、自分で問題を見つけ、解明する学び)も重視している。 |
|
 |

 |
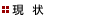 |
 |
2001年度は、1994年度改革以来の抜本的な教学改革(新カリキュラム)の初年度に当たる。以下、その要点のみ記す。
第1に、旧発達・福祉コースを拡充し、人間福祉学科(人間福祉学系:福祉環境プログラム、福祉マネジメントプログラム、発達臨床プログラム)を開設した。人間福祉学科では「人間がより人間らしく生きられる社会」、ならびにそれを持続的に発展させるための諸条件について、社会科学領域全般はもとより、自然科学や人間科学とも連携を深め、総合的社会福祉学の創造を進めていくことを目指している。
この点と関連して、学部のみならず全学における障害をもつ学生・大学院生のために教育支援プログラムの開発に向けて、今年度具体的な手だてと検討を開始した。
第2に、既存産業社会学科の再編を行った。すなわち、従前の6コース制から3学系6プログラム(現代社会学系:社会形成プログラム、環境社会プログラム、情報メディア学系:メディアリテラシープログラム、メディア社会プログラム、人間文化学系:人間文化プログラム、スポーツ・表現プログラム)、1コース(総合社会特修コース)制へと移行した。とりわけ情報メディア学系の新設に関しては、高度情報社会に対応したメディアスタディズの重要性を考慮に入れている。
第3に、学部における基礎基本の学修と系統履修などを重視する観点から、各学科・学系に対応した5つのコア科目(現代と社会、現代とメディア、人間と文化、現代と福祉、基礎社会学)とプログラム選択、ならびに2回生後期セメスターからの専門演習を開設した。
第4に、いわゆるアクティブ・ラーニングを促す教学上の仕組みを拡充した。具体的には従前の社会調査士プログラム、調査実習ゼミに加え、企画研究Ⅰ(自主学習型)、企画研究Ⅱ(インターンシップ)、ボランティア・コーディネーター養成プログラムなどを新たに開設、設置した。また、様々な社会的資源を利用するために、たとえば読売テレビ、NHKと連携した講座を開設し、また朝日新聞とのNIEプロジェクト、医療生協との共同研究などを実施している。
第5に、生涯学習を重視する観点から、総合社会特修コースをはじめとする社会人学生のために教育プログラムの充実について検討を加えた。
第6に、全学の外国語教育改革議論と連携し、英語学部副専攻の2004年度開設に向けて具体的準備に入った。
第7に、学部教学と大学院教学との連携を強化した。拡充された社会学研究科および応用人間科学研究科と学部教学との連携は、アドバンス科目群の再編や学内進学者の増大にみられるように促進されつつある。
|
|
 |

 |
 |
 |
新カリキュラム初年度の今年、産業社会学部では様々な面で教学の新たな進展が見られ、また同時に幾つかの問題点も浮き彫りとなった。
第1に、1999年度全学協議会で確認されたコア化議論を学部教学の中身に反映させ、その仕組みを精緻化したことである。前述したコア科目の開設に伴い、企画委員会のもとにコア科目検討小委員会を設置したが、コア科目の内容、講義方式、到達度検証、授業評価アンケートの活用などについて、コア科目担当教員のみならず学部全体での共通理解が深まったといえる。
しかし、コア科目に相応しい受講規模(300名程度)が必ずしも確保出来なかったこと、評価、試験などにおけるコア科目相互のばらつきが生じたことなどの問題点も浮上している。また、学部のコアである以上、講義以外の場で学生自らが科目と関連した学習を進んで行えるような工夫も必要となっている。
第2に、アクティブ・ラーニングの場が整備・拡充されつつある点である。今年度から開始された企画研究Ⅰには16グループ・個人がエントリーしたが、たとえば「東大阪の中小企業から学ぶ」「春日の高齢者福祉体制から学ぶ」という地域を限定した学習から、「発展途上国にいる子どもを取り巻く状況を考える」「ポルトガルの民衆文化研究」といった国際的な課題を扱ったものまでテーマは多彩である。また企画研究Ⅱの受け皿として、今年度新たに学部における3つのインターンシップ先が開拓され、講義や演習以外の自主的な学びの場が広がっている。この点は、学生のキャリア形成という意味においても積極面をもっており、今後それを一層充実させていく必要がある。
なお、本学部と京都醍醐ライオンズクラブならびに京都市社会福祉協議会とが学術協定を結び、21世紀のボランティア社会を担うボランティアコーディネーター養成プログラムの継続が確認された。今年度、当プログラムには63名の学生と社会人が参加し、合計2500頁にも及ぶ『ボランティア社会学研究紀要』(Vol.1-3)がすでに刊行されている。
第3に、全学のTA予算の拡充にともない、学部が政策的にTAを配置して授業内容の改善などに貢献している点である。今年度学部TA予算590万を活用し、政策枠としてはコア科目と基礎演習ⅡにTAを配置した。これにより、たとえば個々の授業内容に関する学生の感想や疑問をTAが整理して次回の講義に活用するといった取り組みがコア科目で生まれたり、また今年度ゼミナール大会へのエントリー(82グループ・個人)の半数が基礎演習のグループであったことなどの成果があがっている。ただし、TAの役割の範囲をめぐるクラス間格差問題も浮き彫りになってきており、この点を早急に解決しておかねばならない。
第4に、社会福祉士課程と精神保健福祉士課程の履修のあり方をはじめ、新設の人間福祉学科における学修の仕組みが整えられてきたことである。なお、今年度の人間福祉学科1回生のうち約8割が社会福祉士課程の受講を決めている。こうした高い水準を確認しつつも、残り2割の学生による学びの成果についても同様に評価していくことが必要である。
第5に、社会人学生の学びの要求に対し、真摯に応対してきたことである。社会人学生の大学教育に対する要望は非常に強く、産業社会学部では働きつつ学ぶ社会人学生の充実した学びを支援する立場から、総合社会特修コースのカリキュラム内容に関する議論を進めてきた。今年度の夜間時間帯における法、文両学部との共同化をめぐる議論においても、この立場は貫かれている。 |
|
 |

 |
 |
 |
ここでは、以下の3点のみ指摘しておく。
第1に、コア科目をはじめとする講義規模の縮小に向けた手だてを具体化させることである。とりわけ、コア5科目は300名程度という全学合意があることから、講義分割を含めた手だてが早急に求められる。また、これと関連して、今日の学力問題から必然化するであろうきめ細かな教育という課題からすれば、500名を超えるような大規模講義を放置しておくことは問題が大きい。教室条件、時間割などの点を含め、この課題を学部のみならず全学的にも議論すべきであろう。
第2に、学生が学部の基礎を自主的に学ぶことによって講義内容の理解を深められるように、コア科目の共通テキストを学部の責任において作成する必要がある。共通テキストは、各学系の教学の体系をあらわすとともに、それによって学生が学習の到達度を自分から検証できる手段ともなりうるものである。
第3に、国際インターンシップを含むインターンシップ先の開拓をさらに進め、アクティブ・ラーニングの内実を豊富化するとともに、企画研究プログラムの内容をこれまで以上に充実させていくことである。 |
|
 |
|