| |
 |
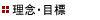 |
 |
| 政策科学部は、2001年度に設置8年目に入り、定着と飛躍のための第2フェーズを迎えようとしている。政策科学部の設置は、政治と経済の大きな変化を見通したものであったが、実際のところ、この間の日本社会の変化は顕著なものがあった。これまで一部の行政エリートの独占物であった政策が、民間企業であれ、地方自治体であれ、あるいはNPOであれ、市民社会にその発動の基盤を移行させつつある。インターディシプリナリーな(そして最終的にはトランスディシプリナリーな)政策科学を構築しつつ、同時に政策提起能力を備えた確かな人材を育成していくという、学部が自らに課した易しくはないが重要な課題は、ますますその意義を高めていると言えよう。学部の設立以後も、いわゆる政策系の学部や大学院が陸続と誕生し、相互のネットワークを形成しつつあることは、政策科学部設立時の見通しの確かさを示している。その一方で、この移行は必ずしもスムーズにすすんでいるとはいえず、旧来の構造とのさまざまな軋轢があり、また新しい仕組みがまだ定着するに至っていないために、見ようによっては新しい可能性の相よりも停滞の相が目につくことも多い。このようななかで政策科学部が、その先駆性を堅持しつつ、同時に現実の変化のスピードとも歩調をあわせつつ、学部の力をいっそうの高みに引き上げていく必要がある。 |
|
 |

 |
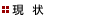 |
 |
| しかし、政策科学部の学部教学と現実の社会的変化のかみ合い方を点検すると、必ずしも当初の意図どおりではない、さまざまの食い違いや見込み違いもまた生まれており、学部教学の達成には、学部構成員を心から満足させない面も現れている。たとえば、学部志願者の推移をみるならば、学部設立直後こそ期待をはるかに超えた高い倍率を記録したが、その後は漸減傾向が続いた。2000年度入試以降は安定してきたが、志望者減は偏差値の低下に結びついている側面もあるので楽観はできない。また、前述のように政策科学部はその活発な学生組織と気風によって注目を集めてきたが、他方において、学生たちがその活発な活動を、堅実な学力と「政策提起能力」形成に効果的に結びつけているかというと、そのエネルギーを活かしきれていない面も否めない。
|
|
 |

 |
 |
 |
これまで政策科学部のカリキュラムは、学際的な教学内容に求心力をもたせる構造とくに政策過程科目を機軸とする編成や専門基礎科目の配置、学生のグループワークを中心とした小集団授業、海外調査プロジェクトなど、各方面からも注目される多くの新機軸を伴ってきた。そして、教学の実態としても、個々の講義に関していう限りは、学生の講義への満足度は決して悪くはなかった。さらに、2001年度からは、社系学部でありながら「情報科」教職課程が認定され、この点でも新境地を切り開いた。
しかし、学部の教学の達成は、教員の個別の努力に起因する場合が少なくなく、カリキュラムとしての総合性や整合性という点については、必ずしも当初の見込みどおりの連携が生まれていなかった。また、学部教学の基本目標である「政策提起能力」の涵養についても、その具体的内容をつめるべき段階に来ている。 |
|
 |

 |
 |
 |
以上のような認識に立って、2002年度実施カリキュラム改革案を2000年度末の教授会で確認を行った。改革の重点は、
| ① |
社会経営・国際環境(旧環境開発)・公共情報の3専攻に対応した3つの系を置く |
| ② |
各系に導入的科目を置く |
| ③ |
3つの系に並行して政策過程科目を発展させた争点課題科目群を置く |
| ④ |
各回生小集団科目におけるアウトプットの質をチェックするシステムを構築する |
などである。2001年度はこのカリキュラム改革案を具体的実施計画に移行する作業を行なった。 |
|
 |
|