| |
 |
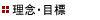 |
 |
国際インスティテュートは、2000年度より衣笠キャンパスの法学部、産業社会学部、国際関係学部、文学部、政策科学部においてグローバルな諸問題の解決と国際的コミュニケーション能力の獲得に向けた学習を行ない、現代の国際社会が求める人材を養成することを目標に設置した。
所属学部の教学を前提としつつ目標進路別に法学、経済学の素養を備えた国際的企業人の養成をめざす国際法務プログラム(法学部国際比較法専攻)、環境、開発、福祉など国際的諸問題の解明と解決をはかる分野でリーダーとして活躍する人材の養成をめざす国際社会プログラム(産業社会学部、文学部)、国際機関や国際援助機関で活躍する人材の養成をめざす国際公務プログラム(法学部、国際関係学部、政策科学部)を設置している。 |
|
 |

 |
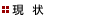 |
 |
国際インスティテュートは、1回生時は所属学部の基礎教育に専念し、2、3回生に授業を配置して卒業に必要な単位の内30単位を取得する。教学の中心を専門科目、専門外国語科目、海外研修科目に置き相互に関連して実施する。
(1)専門科目は各プログラムの教学に即して配置し、新たに開講する独自科目と各学部との合同開講科目がある。この内、特殊講義はプログラム共通で開講する。
(2)専門外国語は専門英語を中心として教学の内容を重視した専門外国語科目を配置する。専門英語の各クラスは習熟度別にグレード制で編成する。
(3)国内における教学を実践に移す場として海外研修を実施する。
協定校において英語で専門科目を受講するアカデミック・ラーニング、指導者について調査・実習活動を行なうフィールドワーク、目標とする進路で就業体験を実施するインターンシップの3つのタイプを配置している。 |
|
 |

 |
 |
 |
1回生の基礎クラスは各学部とも国際インスティテュート学生で独自クラスを編成して、授業内容や教材に工夫する他、新入生合宿を実施するなど、アイデンティティの醸成とともに2回生からの国際インスティテュートの学習に備える。また、専門英語の学習に備えた英語学習における1回生終了時の共通到達目標を設定した。
また、1年間の学習成果発表の場として12月には国際インスティテュート学生全体を対象としてゼミナール大会を開催した。運営の中心は1回生の委員が担い、有志によるプレゼンテーションを実施して多数の参加と学生相互のまとまりを得た。
(1)専門科目は各プログラムの教育内容に即した科目とプログラム共通の特殊講義を配置した。特殊講義においては、外国人教員による英語の専門科目、海外の大学とのネットワークを介した授業、立命館アジア太平洋大学との遠隔講義、留学生と学ぶ科目などの目標を設置して開講した。
(2)専門英語クラスは、前年度の学内における学内のTOEFL・ITP試験をもとにグレード制によるクラスを編成した。各学生は定期的に上記の試験により到達度をはかる習慣を構築した。
(3)専門科目、専門外国語科目の実践の場として実施した海外研修は国際インスティテュートの開設とともに具体化した独自の研修とUBCジョイントプログラムなどの全学プログラムとも積極的に連携して海外での実践的な学習を奨励した。
国際インスティテュートの学生も国際関係学部の学習自習施設(恒心館5階)を開放し、日常的に学習できる体制を構築した。
国際関係学部の演習募集について国際インスティテュート枠を設置して発展学習の場を設定した。これにより国際インスティテュート学生は所属学部の演習選択に加えて国際関係学部のゼミが選択できる構造を構築した。 |
|
 |

 |
 |
 |
国際インスティテュートの学生募集は入学試験時におこない、広報活動は事務局が入学センターと連携して実施しているが、学生確保は各学部の学生募集の枠内で行なわれており、国際インスティテュート教学委員会の学生募集の意図を各学部とより連携しながら実施する必要がある。2001年度は特別入試における学生採用の指針について教学委員会より各学部へ依頼した。
国際インスティテュートは学問分野の異なる学生が共通の進路目標を設定して学ぶことにより、その課題解決へのアプローチを互いに学びあうこともひとつの目標にしているが、教員との相互交流におけるゼミ形式で運営する科目を設置しているプログラムと講義系科目を中心に設置しているプログラムでは学習構造の目標に差が出てきている。
国際インスティテュートのさらなる発展学習として大学院進学指導および目標としてかかげた進路・就職の指導に力を入れる必要がある。 |
|
 |
|