| |
 |
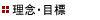 |
 |
| 国際関係研究科は、国際関係の諸理論や原理的研究を中心とした国際関係コース,国際協力に関わる理論的実証的研究能力の養成をはかる国際協力コース、留学生を中心に日本研究の高度な専門家を育成することをめざした日本研究コースの3コースで構成されている。
しかし時代の変化を受け2003年度より、冷戦後のグローバル社会の望ましい姿について研究するグローバル・ガバナンス、冷戦後の南北協力のあり方について考える国際協力開発、多様な文化の共存について考える多文化共生の三プログラムに改編する。また、本研究科は、国際機関職員、外交官、国際交流機関職員、国際的ビジネスマン、国際分野の研究者、NGO活動の担い手など21世紀の国際社会で活躍し、日本の国際化をリードする国際的な高度専門職業人と研究者の養成を目標としている。 |
|
 |

 |
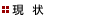 |
 |
(1)これまでの修了生の進路としては国連諸専門機関、日本外務省、日本の国際協力機関、マスコミ、研究者、NGO等に輩出している。(詳しくは研究科ホームページ参照)
(2)現行プログラムが国際環境の変容に対応できなくなっていること等のため受験者数が減少する傾向にあった(とりわけ日本研究コースにその傾向があった)ため、上記のように大幅にプログラムを改編することになった。(なお、受験者数はホームページを通じての広報等により増加傾向に転じた)
(3)長年力を入れてきたインターンシップについて2001年度も10名以上の学生を派遣した。インターンシップ協定先としては、現在の10数機関に加え、2001年度は新たに国連世界食糧計画日本事務所が加わった。
(4)研究・教育面での国際提携としては、アメリカン大学を中心とするこれまでの諸機関に加え、2001年度にはボルドー大学との学生交換、ISS(ハーグ)とのDMDP、ピアソン平和維持センター(カナダ)とのインターンシップ、客員教授派遣等の話し合いを開始した。 |
|
 |

 |
 |
 |
(1)受験者数の回復により、学力の面でも上昇傾向が見られるが、高い進路目標との間には依然開きが見られる。
(2)世界的に国際関係系大学院では教育の国際化が著しく進みつつあるが、本研究科に関しても、インターンシップ、客員教授の招聘、DMDPや協定校への学生派遣等で進展を見てきている。しかし、日本人学生の留学割合、研究科の留学生数、英語で行われる専門授業数等について充分とはいえない。
(3)修了者の進路先については学生により大きな開きが見られる。 |
|
 |
 |
 |
 |
(1)学力のアップに関しては、国際関係学部出身者を増加させる努力をする。また、受験に際しての基本学習図書を明示し、入学前ガイダンスを通じて学力向上の努力を促す。
(2)英語による専門授業履修のみで修士課程を修了できるプログラムを立ち上げ、留学生を増加させるとともに日本人学生による海外留学の垣根を低くする。
(3)国際機関、メデイア、外務省等への進路ルートを教育や諸機関との提携を通じて築く。 |
|
 |
|