| |
 |
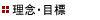 |
 |
| 学部で学修してきた人文科学の諸分野をさらに深く研究し、伝統的な学問成果を学ぶとともに、新たな方法や領域を自ら開拓する高度線専門職および研究職を養成する。 |
|
 |

 |
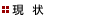 |
 |
哲学・文学・史学・地理の4学科10の専攻・専修相当で構成され、それぞれの伝統的な学問分野の研究を深めると同時に、人文科学総合科目を配して学際的で先端的な分野の学修・研究をする仕組としている。こうした中で、今年度は前期課程修了者58名、課程博士取得者は2000年度申請・2001年度授与7名、2001年度申請・授与者2名 計9名、他に論文博士6名を輩出した。
2001年度において文学研究科において実施した主な制度変更や改革は以下の諸点である。
| 1、 インスティテュート後期プログラムの立ち上げ(言語・表象文化と地域文化の2領域)。これは、既に前期課程修了生を2000年度に出しており、後期課程のプログラムが必要とされていたことに応えたものである。 |

| 2、 「特に優秀と認められる」学生が博士課程前期・後期課程をそれぞれ規定の就学年度に達しなくとも修了できるとする大学院規則に対応する文学研究科内規の整備。それぞれの課程で同大学院規則にもとづく修了希望者があり、今後も「特に優秀と認められる学生が輩出する事態を予測し、これを判断する基準と手続きを内規として定めた。 |

| 3、 インスティテュート所属であった認知領域を心理学専攻に移し、心理学専攻のカリキュラムを改訂した。 |

| 4、 入試の公正さを一層明らかにするための改善をおこなった。客観テストの答案採点は氏名を伏せることとし、関連して面接その他の選考システムを工夫した。この点は今後も継続して検討・改善を行っていく予定である。 |

| 5、 助手制度のあり方について検討をおこなった。大学院学生の研究ならびに課程博士取得を援助する研究奨励制度としての側面と、学部教育に不可欠な教育補助業務や実験実習準備等を行う助手の必要性について検討し、この2つの機能を区分して検討するよう助手制度検討委員会に意見を具申した。 |

| 6、 その他 インターンシップの開拓に努め、また学部共同開講科目が設置できるよう制度を整えた。
|
全学的な事柄としては、2001年度より課程博士取得にかかわって、博士課程4年まで在学延長が認められた者について、退学後2年以内であれば再入学を認め課程博士の申請を可能とする制度が実現した。この制度は、学位取得前に一定期間の調査・訓練を必要とされる文学研究科の学生にとって稗益するところ大である。 |
|
 |

 |
 |
 |
| 上記1・3は前からの予定を実現させたもの、2は修了希望者が出るに及んで、それに答える形で基準づくりをしたものであるが、文学研究科のシステム整備として成果があつた。その過程で、1は近く設置が予定されている新構想大学院(仮称)との区別が明確となり、2は修了認定のためのレベルの議論が深まった。4はさらに検討を要するが、この機会に選考基準や方法を含めて検討し、招来にそなえる。5は助手制度検討委員会における今後の検討結果に委ねることとなる。 |
|
 |

 |
 |
 |
当面の課題は、学生の進路・就職に関する問題である。この点については、前期課程を経て就職する高度職業人志向の学生に、実際的な専門技能科目やインターンシップによる実務教育などを増やすこと、研究者を目指す後期課程の学生には、課題別プロジェクト研究の設置とそれへの参加、また学位取得を一層推進する環境づくりをめざすことによる改善案が構想されている。併せて院生論集の発行や院生向け就職ガイダンスの実施も検討している。
研究科が社会的要請に応える課題では、専修免許取得などでの現場教員などの専門職従事者を社会人入学させる案もある。この案の概要は、年度末の全学的なレビューに文学部より提出した文書に関説した。 |
|
 |
|