
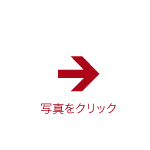


一人にできることは小さいけれど、現地で生まれも育ちも違う人がたくさんいる。みんなが集まれば、より近づけるのでは。その中の一人になれればと。
野村和秀さん(政策科学部3回生)


向こうの人もボランティア活動を喜んでくれた。
「ありがたがった」と言ってくれてうれしかったので。岡本翔平さん(政策科学部2回生)


日常に戻れることが一番というか、忘れ去られるということではなく。そのために祭りが実際に行われたりしている。日常の普通の出来事が行われるように。
小寺勇蔵さん(政策科学部3回生)


今生きている人もいる、亡くなった人がいる、それが被災地。生き残った人だけではなく、亡くなった人も人の心の中に生きている。忘れてはいけない。その思いを大切にしていきたい。
山枡美波さん(文学部4回生)


報告会の参加者の声から、本当に活動に行った意味があったのかとネガティブに捉えていた部分も感じた。でも、自分のやったことはもっとポジティブに捉えてもいいと思う。現地の人々にも、自分たちのこれからに自信を持ってもらいたい。
袴田有紀さん(産業社会学部4回生)


阪神・淡路大震災のときの記憶を忘れたくない。編集されていない、偽物ではなく現地を見たほうがいい。
塩田理紗さん(経済学部3回生)


行って帰ってきて、被災地とこちらでの震災に対する思いの温度差が大きい。行って終わりではなく、向こうの話をこちらで広げて輪を広げたい。そして「支えなあかんな」と思ってもらえるように。行ったからこそできること、僕の言葉にどれだけ力があるのかわからないけど。
北畠知幸さん(関西大学法学部2回生/ボランティアセンター学生スタッフ)


ボランティアを経験して、コミュニティを作るには長期的に、そして地域に密着することが必要だと思った。遠くの立命館ではそのむずかしさも感じた。関西からでもできることは、忘れかけられていることを、私たちが話して伝えることで、ちょっとでも「いってみるのもいいかな」という輪が広がって、思いやモノや人が集まって東北を支えられたら。多くの人を巻き込んでいきたい。
山根早由里さん(国際関係学部3回生)


まだ、もやもやしています。
震災で失ったものよりも、人のあたたかさや絆を。長谷奈央子さん(文学部4回生)


被災地の支援活動を通じて、こどもたちに夢を与えられることが自分の夢の第一歩になれば。
佐野 匠さん(情報理工学部2回生)


状況が刻々と変わる中で、できることは限られている。
行って、帰って、今何ができるか、何をするのか。西野 肇さん(文学部4回生)


復興支援活動は、考えることが大事だと思う。
この作業が誰のために、何ゆえ行うのか、今後どんな意味を持つのか。阿部辰樹さん(政策科学部3回生)


東北の人のため、私たち自身のために今活動している。
国や地域だけでなく、生きとし生けるもの、すべてのことにつながっている。上田 寛(立命館総長特別補佐)


いろんな人が関わったり、つながることで生きること、築いていけること。起こったことは消せないけど、希望を持てば夢や未来に必ずつながるはず。
河田のどかさん(NPO法人さくらネット)


自分が感じたことを誰かに発信することが、風化を防ぐことにつながるかもしれない。可能性は低くても、動くことが大切。
武藤笙太さん(政策科学部3回生)


東日本で終わらせたくない。京都でできること。防災とか、避難グッズの用意などに取り組んでいる。学園祭でも地域の人と語り合う取り組みをすすめている。
池内亮太さん(龍谷大学 法学部3回生)


交流のあった岩手県立大学、岩手とこれからもつながっていきたい。心理学を専攻しているので、専門性を深めることもやっていきたい。
児玉大樹さん(文学部1回生)


たどり着く場所。自分たちが笑顔でやらなければ、お互いが笑顔にはなれない。
藤澤千紘さん(文学部3回生)


関西と東北の距離を学生のパワーで縮めたい。可能な限り何度でも現地にいきたい。
大野千聡さん(国際関係学部3回生)


東北の実態を知らない人が多すぎる。知ること、興味を持つことで、自分たちができることが見えてくるはず。
小野友里代さん(法学部3回生)


自分自身に対しても人に対しても、何かをする。動くことで、相手から得るものも大きい。人と関わることで、世界が変わる。
田村 望さん(経済学部3回生)


ボランティアでやさしさに触れ、5日間の活動を乗り切れた。小さなやさしさを、日常の生活でも日々見出せれば。
原 雄太郎さん(法学部2011年9月卒業)
