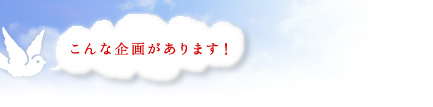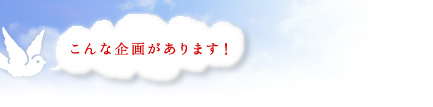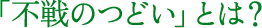 |
「平和と民主主義」を教学理念に掲げている立命館大学ですが、戦時中、多くの学生が徴兵や勤労奉仕に駆り出され、多くの尊い命を失いました。
「不戦のつどい」は、戦場で命を失った多くの学生を偲び、今を生きる人々が不戦について考え、「不戦の誓い」を新たにする場です。
1953年の「わだつみ像(*右コラム参照)」建立以来、毎年欠かさず開かれています。
|
 |
3月11日の東日本大震災では、地震・津波という自然から、また原子力という科学から、私たちの生活が脅かされる事態となりました。
いま、「平和」を単に「戦争のない状態」として捉えるのではなく、「生きること」が脅かされない状態をいかに作り出し、取り戻し、維持し、発展させるのか、ということについて考えなければならないのではないでしょうか。
そこで、11月30日(水)から12月9日(金)にかけて行われる、さまざまな企画を通して、平和について考えてみませんか? |
|
 |
 |
「わだつみ」とは、「わたのかみ」と同義で「海をつかさどる神」を意味します。
1949年10月20日、東京大学協同組合出版部から『きけわだつみのこえ』という戦没学生の手記が刊行され、広く普及されました。「わだつみ像」はこの刊行収入をもとに戦没学生記念会(通称「わだつみ会」)が計画したもので、本郷新氏の作品です。当初、東京大学構内に設置する予定でしたが、評議員会が拒否。「わだつみ像設置拒否反対集会」が開かれましたが、結局、設置場所は定まらず、本郷氏のアトリエに置かれることになりました。1953年、立命館大学の末川博総長が、反戦と平和のシンボルである「わだつみ像」を引き受ける意思を表明し、学内外からの強い支持も寄せられ、その年の12月8日、太平洋戦争開戦の記念日に立命館大学での建立除幕式を迎えるに至りました。現在は、立命館大学国際平和ミュージアムに設置されています。 |
|