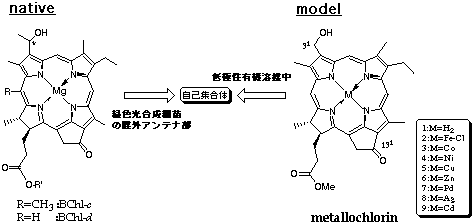私の研究について
研究テーマ
「メタロクロリン類の合成とその会合体の物性」
生物有機化学研究室
尼川 雅章
自然界ではバクテリオクロロフィル (BChl)-cやd(下図の左)などが緑色光合成細菌の膜外アンテナ部で蛋白質の支えなしでも自己集合体を形成していることがわかりつつある。この自己集合体の超分子構造は光合成の際、光エネルギーを集めるのに重要な働きをするが、BChlは生体外では容易に光や熱によって壊れるため、超分子構造の解明のために用いることが困難である。
そこでモデル化合物として現在までにzinc-chlorin(下図の右の6)の低極性有機溶媒中での自己集合体が提唱されてきた。
ここで自己会合体の形成のための必須因子をあげると
A)中心金属 M、 B)31位のOH基、 C)131位のCO基、
D)クロリン環
を有するということの4つがあげられ、B〜Dについては現在までにさまざまな実験が行なわれてきている。そこで本研究では中心金属
M として種々の金属を有するメタロクロリン(下図の右)を合成し、低極性有機溶媒中での自己会合能、ならびに光集合アンテナ色素モデルとしての可能性を検討した1)。
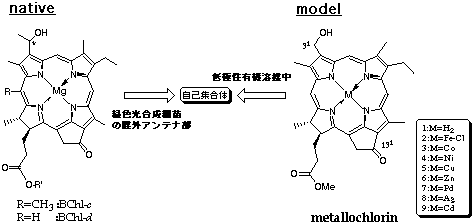
金属錯体としてFe-Cl, Co, Ni, Cu, Zn, Pd, Ag, Cdの8種を合成した。UV-VisスペクトルにおいてCoおよびCd錯体の場合、Zn錯体同様に低極性有機溶媒(1%THF-n-hexane)中で、モノマーの状態(極性溶媒中)のピークにくらべて各ピ−クがブロードで長波長側にシフトし、Soret/Qy比の低下がみられた。このことは低極性有機溶媒中でこれらの錯体が自己会合体を形成していることを強く示唆している。CDスペクトルについてもZn錯体同様、この長波長シフトした極大吸収波長付近に大きなコットン効果を示しておりCoあるいはCd錯体が自己会合することによって励起子相互作用が生じてQy
帯が長波長シフトしていることが判明した。
また、これらの会合体の結合様式について検討するため高感度反射式IRスペクトルによる測定を行なったところCo,
Zn, Cd錯体のそれぞれの会合体のSolid FilmにおいてBChl-c等の天然系Mgクロリン会合体と同様のC=O…H(X)O…M形の結合様式が存在することがわかった。
以上のことからCo, Zn, Cdの3種の金属錯体はBChlの膜外アンテナ部の超分子構造を調べる良いモデルになることが明らかになった。
1) H. Tamiaki, M. Amakawa, et al., Photochem. Photobiol., 63, 92 (1996).