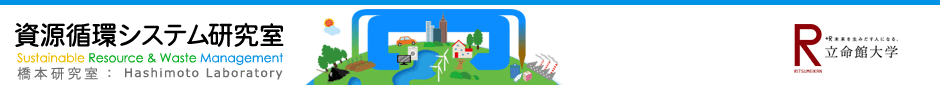
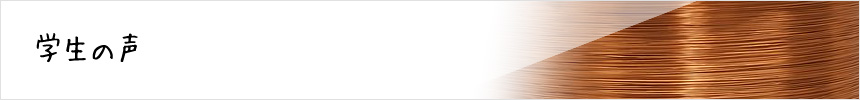
2023年度

- 全力で楽しんだ3年間
- 板垣 翔太(修士卒)
橋本研での3年間を振り返ると、本当に様々なことを経験することができたなと思います。
仮配属された当初は院生になるつもりはありませんでしたが、一生に一度しかないであろう研究室生活を、コロナで規制され続ける1年で「楽しめなかったらいやだなぁという」限りなく不純な動機で大学院に進学しました。結果として、研究室での何気ない日常での会話、学会発表や他大学との合同ゼミなどでの発表する機会など、どの瞬間を切り取っても楽しかったですし、貴重な経験ができた3年間を過ごすことができたと心から思います。
このように思えるのは、誰とでもコミュニケーションをとり、自分自身のやりたいことをしっかり言うことができたからだと思いますし、やりたいことを言えば一緒にやってくれる橋本先生をはじめとした研究室の仲間がいたからです。
学部生のころから研究室に行くと誰かは研究室にいる環境で、誰彼構わずその場にいる人と話をしていました。話す内容はもちろん(?)研究のこともあれば些細なこともあり、多くのことを話しました。また、橋本研はゼミの前後で先生を含め一緒にランチを食べるので、自然に会話をすることになり、他の研究室よりもメンバー同士の仲がいいですし、特に長くともに過ごした同期とは何でも言える関係になれ、自分のいいところ、ダメなところを認識させてもらいました。
合同ゼミは、橋本研のメンバーとより仲良くなる機会でもあると同時に、他大学の人達と関わる機会でもあり、多くの人と話しました。特に院生での2年間は対面で行われ、多くの人と仲良くなれたと思います。合同ゼミに参加している人達は似たような研究をしていることもあり、参加した学会に知っている人が誰かはいる状態になり、最後の1年間に参加した学会は遊びに行くような気持ちで参加することができました(笑)。もちろん研究発表もしっかり行いましたよ?(笑)
橋本研はゼミが多かったりイベントが多かったりと忙しくも楽しい日々を過ごすことができました。先生には気軽に相談できる環境があり、先輩後輩関係なく気軽に話せる環境があり、ここで伝えられること以上に研究室生活は充実したものとなりました。これはコミュニケーションから研究まで、自主的・能動的に動くことが求められる橋本研だったからこそと思いますし、だからこそ3年間で大きく成長することができたと思います。
最後になりますが、大学院進学を認めてくれた父をはじめ、3年間ご指導いただいた橋本先生、谷口さん、先輩方、同期、後輩、研究に関わって下さった皆様、感謝しかありません。本当にありがとうございました。

- 自分の道に出会える場所
- 渡邊 一史(修士卒)
ここでの日々は、間違いなく、私の人生において最もかけがえのない瞬間の一つです。そう感じさせてくれるのは、橋本先生をはじめとした研究室のメンバーと過ごした毎日や、時には他大学と、また時には企業や研究機関の方と交流する機会があったからです。
私が学部3年生の時、新型コロナウイルスが蔓延し、それによって授業・サークル・バイトなど、全ての機会が失われました。時間だけがただ過ぎていくような2020年の中で、研究室配属もちょうどその時期に始まりました。当時は対面で交流することはほとんどなく、必要最低限が全てオンラインで行われるような状況でした。この先の研究室生活にモヤモヤとした影を感じつつ、若干の諦めのような気持ちのまま迎えた4年時の研究生活では、慣れない環境と内向的になっていた気持ちから、ほとんど研究室に顔を出すことはありませんでした。
修士1年の春、このままじゃダメだと心機一転し、研究室に足を運び積極的に行動を起こすようにしました。そんな身勝手ともみれる私の振る舞いに、この研究室は温かく迎え入れてくれたのを今でも感謝しています。修士2年の夏、全てを投げ出そうかと本気で悩み、何も見えなくなっていた就職活動の時には、励ましと助けをいただきました。おかげで良い企業に就職でき、やりたいことにも挑戦できそうです。
本当に色んな人と知り合いました。表彰もされました。学会の学生幹事もやりました。研究室紹介ビデオも、研究室でカレーも作りました。飲み会とカラオケ楽しかったです。橋本研に居たおかげで、たくさん、たくさんの縁に恵まれ、今の自分がいると実感しています。
この縁は一生大切にしたいと思います。
最後になりますが、もし、また道に迷ったり、悩んだり、苦労し疲れた時があったら、研究室に顔を出しに行くかもしれません、もちろん美味しい手土産を持ってです。その時は、また暖かく迎え入れて下さると嬉しく思います。本当に、ありがとうございました。

- チャーミングな温かい人が集まる場所
- 南部 結香(学部卒)
配属当初は研究室紹介の時に足を運べていなかったので(^^;)、どんな人がいて何をする研究室なのかよく分からない状態で4年生を迎えました。最初は人見知りもあり、先輩や研究室メンバーと上手くコミュニケーションが取れていないなと感じていました。さらに就職先が決まっていたこともあり「1年しかこの研究室に居ることが出来ないし、そんなに仲良くなれなくてもいいかな」とも思っていましたが、先輩が話しかけて下さり研究のアドバイスを頂くにつれて徐々に話せるようになりました。沢山お話するようになってからは、研究室に来る目的は研究をすることはもちろんですが、「みんながいるし、話せて楽しい!」ということも1つの理由になっていたように思います。
研究面では多くの方に関わって頂きました。私の研究では、「リリパック」というプラスチック製弁当容器に対するデポジット制度試験導入の企画から実施、加えてアンケート調査も行うという、1人で全てを行うには大変な研究でした。デポジット制度試験導入開始直前にトラブルが起きた時は、夜遅くに橋本先生に相談させて頂き、アンケート調査では研究室メンバーが回答者集めに協力して下さいました。この研究をやり遂げられたのは橋本先生並びに研究室の皆さんのおかげだと思っています。本当に感謝しています。
私の研究対象でもあったリサイクル弁当容器の回収ボックスを学内施設の工作センターで作製したり、研究室メンバーのゴミの組成調査をお手伝いしたりと、パソコンと向き合う時間だけではなく、みんなで助け合って研究を行った1年だったと思います(特にB4の研究内容は(*^^*))。今思えば研究途中で上手くいかないことや失敗しても、笑いあっていた日々がとても楽しかったです。有難いことに橋本先生や谷口さん、個性的で魅力的な先輩や同期に恵まれ、橋本研を選んで後悔はしていません。実際、1年間を通して何度も人の温かさに触れ「橋本研で良かったぁ」と思うことが沢山ありました。
こんなに充実した研究室生活をおくれたのは橋本先生並びに関わってくださった全ての方のお力添えあってのことです。本当にありがとうございました!
2022年度

- 橋本研での貴重な経験
- 湯川 力(修士卒)
橋本研での生活を振り返ってみると、たくさんの良い経験を積み、社会人になる心構えができたと思います。私は、学部生の時にやりたい仕事を見つけらなかったことと、まだ社会人になりたくないという不純な気持ちから、大学院に進学しました。研究を行う中で、橋本先生には学会発表や論文投稿など多くの機会を頂きました。多くの人の前での発表や、論理立った文章の執筆などは良い経験になり、今後の社会人生活でも必ず役立つと思っています。
また、やりたいことがなかった私は、研究を行う中で、今まで学んできた環境分野の仕事に携わりたいと思うようになりました。就職活動を行う中でも、研究室の先輩や橋本先生は親身になって相談に乗ってくれるし、就職に関するラッキーな情報もたくさんありました。私は橋本研で大学院に進まなかったら、今の会社を知ることもなかったし、絶対に行けなかったと思います。研究室選びで悩んでいる学生は、ぜひ橋本研に来て下さい! いい経験が必ずできます!
最後に、たくさんの良い経験ができたのも、橋本先生、秘書の谷口さん、研究室のメンバーの皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。

- 充実していた日本留学生活
- Yingyin DU(修士卒)
橋本研の三年間を振り返ると、研究室に入って自分が予想できない自分に成長でき、充実した研究室生活を過ごしたと思います。
橋本研究室では、廃棄物・エネルギーや災害対応など幅広い研究分野を自由に選べ、研究課題を自分で設定し、計画的に進めます。これにより、自己管理能力を高めると同時に、論文を読んで実験や調査の方法を学び、研究に必要なスキルを身に付けました。また、定期的に進捗報告を行い、先生からフィードバックをもらえるため、研究が進めやすかったです。研究室ゼミや合同ゼミ・学会など、発表する機会が多く設けてられており、プレゼン力も高まりました。
橋本研では学生同士の交流を促進するためのイベントや活動が行われます。例えば、ボウリング大会、散策や他大学との合同ゼミなどがあります。様々な活動を通じて、研究室の雰囲気が良く、学生同士が助け合い、協力して研究に取り組む雰囲気があり、研究が楽しく進められます。さらに、研究室の先輩との交流も、貴重な経験になりました。先輩から研究や就職に関するアドバイスをもらい、自分が将来どのような道を進むかイメージすることができました。
橋本研のもう一つの特徴として、国際的な交流環境があります。英語や他の言語で交流するチャンスがあり、刺激的で充実した研究環境が期待できると思います。外国人として、先生と学生の皆さまにいろいろお世話になり、楽しく学生生活を過ごすことができました。コロナの禍で、最初の合同ゼミはオンラインで行われましたが、その後、制限されながらも、皆さまと下関および九州に行けて、とても楽しかったです。

- 成長の1年!!
- 濱地 泰周(学部卒)
私の大学生活の中で間違いなく一番成長できたのは橋本研に所属した最後の1年でした。人より遅れて4回生になった私は、「正直どこの研究室に入っても変わらないだろう」と思いながら、何となく人々の行動と環境負荷の関係について研究をしたいと考え橋本研を選びました。当初は、不安な事の方が多かったです。研究室ゼミ、個別ゼミ、他大学との合同ゼミ・学会発表など他の研究室と比較するとかなり忙しいことに加えて、資料作成・プレゼンも要求されているレベルには全く手が届いていなかったからです。橋本先生から「研究に費やす時間が足りていない」とお叱りを受けた事も印象に残っています。
しかしその不安だった要素の全てが、実りのある1年に繋がったと今では思っています。研究室内のゼミや対外的なゼミなど客観的に自身の研究を人に見てもらう機会が多く、様々なアドバイスや質問を通して疑問点が生まれ、自分自身の研究について考える時間が自然に増えていきました。また先輩や同級生、他大学の学生の発表を通して何かを吸収していく事ができる、そんな環境が橋本研には常にありました。卒業後、研究室配属当初に作成したプレゼン資料を見返していると、「ひっどい資料だなぁ」と笑えてくると同時に、1年を通して「少しは成長できたのかな??」と思ったりしていました (笑)。
今振り返ると、「能動的に動く」という事が橋本研では一番求められていたのではないかと思います。「自分で考え、行動する」、研究はその積み重ねで少しずつ進んでいくもの。そしてその様な能力を養う環境がどの研究室よりも確実に整っていたと思います。社会人という次のステージでも、この研究室で学んだ事を活かし、更に成長していきたいです。
3月のLCA学会発表会では、橋本先生や先輩方のサポートもあって、ポスター発表部門の優秀賞を受賞する事が出来ました。皆さんには、迷惑をかけてばかりだったのですがこの様な結果を学生生活の最後に橋本研の一員として残す事が出来て本当に嬉しかったです。
最後に、研究室に行けばプレゼン資料や研究方法など、嫌な顔一つする事なく相談に乗って頂いた先輩方、研究室の活動を裏から支えて頂いた谷口さん、そして、テーマ選択から論文の執筆まで、どんな時も常に親身に指導してくださった橋本先生、本当に感謝してもしきれません。本当に1年間ありがとうございました。
2021年度
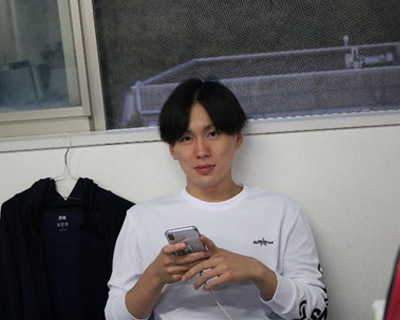
- 研究室での何気ない日常
- 岡本 宗一郎(修士卒)
橋本研での3年間を振り返って一番に思い出すこと、それは「研究室での何気ない日常」です。
学会発表や論文執筆で成果をあげる、専門的な知識やスキルを身につけるなど研究室での活動を通して得られるものは人それぞれだと思います。私自身も橋本先生に機会を設けていただき、学会発表や論文執筆を経験しました。また、他大学との合同ゼミなどもあり、橋本研はイベントの多い研究室です。それでも私が橋本研での3年間を振り返って一番に思い出すことは「研究室での何気ない日常」です。研究室の雰囲気が良く、周囲の人たちに恵まれていたからこそ、「研究室での何気ない日常」が良い思い出として心に残っているのだと思います。
橋本研の特徴の一つが「研究室の雰囲気の良さ」です。橋本研はゼミが多く忙しいというイメージがあったり?なかったり?(笑)しますが、そのゼミのおかげでコミュニケーションをとる機会が多くあり、先輩後輩関係なく学生同士の仲が良い、とても雰囲気の良い研究室です。研究について丁寧に指導をしてくれる橋本先生、研究や就活について親身になって相談に乗ってくれる先輩方、切磋琢磨し合う同期、イベントなどを積極的に企画してくれる後輩、周囲の人たちに恵まれた私の橋本研での3年間はとても充実したものであり、大きな財産となりました。
研究について橋本先生と立ち話をする、学生同士で冗談を言い合いながらそれぞれの研究に取り組むなど、「研究室での何気ない日常」があったからこそ、3年間を通して研究をやり切ることができたと感じています。
3年間ご指導いただいた橋本先生をはじめ、先輩方、同期、後輩、研究に関わって下さった皆様、本当にありがとうございました。

- 積み重ねの大切さ
- 堀部 翔(学部卒)
私は、2021年4月から橋本研に参加しました。2020年度中の仮配属の期間には、シミュレーションモデルを扱う研究室に配属されていました。研究室が変わると聞いた時は若干の不安を感じていましたが、学生生活の最後を橋本研で過ごせたことは、すごくよかったと思います。
自分にとってこの一年は、将来に対する悩みや不安の多い一年でした。そんな中、橋本研のスローガンの一つである「毎日研究室に来る」は、悩みや不安を和らげてくれました。研究室の人の顔を見るだけでも、落ち着かない気持ちが楽になり、穏やかに過ごすことが出来ました。これまで以上に将来のことを考える時期に、研究室に必ず誰かがいるというのは、それだけで支えになるものでした。
卒論については、順調に進めることができたのではないかと思います。「あの時こうすれば良かったな」等の小さい後悔はいくつかありますが、最終的には卒論提出・LCA学会でのポスター発表を満足のいく形で行うことが出来ました。これらに取り組んだことで文章力・イメージで伝える力を以前よりも向上させることができました。また、一年間、橋本研で卒論に取り組んだことで学んだのは「積み重ねの大切さ」です。後から発表資料や提出資料を見返すと、「手を抜いているな」と感じたり、「いい資料を作れたな」と感じたりします。時間をかけたものは、見返したときに「納得する資料が作れたな」と思うものが多く、良いものを作るにはある程度の時間を積み重ねる必要があるということを改めて学びました。
繰り返しになりますが、学生生活の最後を橋本研で過ごせたことは、すごくよかったです。部活感がありながら、どこかゆるさのある、大学生感のある研究室での生活は楽しかったです。おかげさまで精神的に穏やかにかつ健やかに過ごすことができました。橋本研の皆様には感謝いたします。ありがとうございました。
2020年度

- Find what you like and do your best
- Jian Zhang(修士卒)
Two years ago, I set foot in this charming country alone and began to study abroad with great expectation. Due to the fact that I can hardly speak Japanese, I was a little worried about whether it would become an obstacle to my life in Japan. However, the considerate and thoughtful help from the administrative staff and laboratory seniors made me realize that I was thinking too much. The Japanese language courses offered by the university and the various activities in the laboratory let me learn more about Japanese culture, which made my extracurricular life very fulfilling and interesting.
Before I came to Hashimoto Laboratory, I had always believed that studying was a mechanical behavior with a strong purpose. But Professor Hashimoto gave us plenty of freedom to choose our own research direction and constantly helped us inspire our self-learning ability. For me, studying was no longer a task goal but a process of challenging myself, and there would be a steady flow of motivation. In the laboratory, we were encouraged to participate in various academic conferences, which not only enriched our academic knowledge but also improved our speech and expression abilities. Moreover, we had the opportunities to visit factories and join the communication meetings with enterprises to obtain job hunting experience. Compared with when I entered the university I only hoped to graduate on time, now I would like to work hard at the research and publish it. Hereby, I would like to thank Professor Hashimoto, Sebastien, Paolo as well as my colleagues for their support. Without their selfless guidance and assistance, it would have been a dream that I could not have realized.
Japan is a very beautiful country with a wide variety of natural landscapes and historical heritages. Lots of wonderful memories were left when I was traveling in this country. I am extremely grateful to Professor Hashimoto for the positive learning environment provided me with, and I wholeheartedly thank all the laboratory members for everything you have done for me. The experience of studying and living in Japan is the most precious treasure of my life, and it also inspires me to step into a bright future.

- “機会”に恵まれた3年間
- 青木 一将(修士卒)
橋本研に入っての3年間は発表や議論の機会に恵まれた3年間でした。私はこれらの機会を通じて自分のプレゼンや論理的思考能力を向上させることができたと感じています。
特に印象深いのは修士2年のはじめから参加させて頂いた水俣条約の有効性評価のためのプロジェクトです。ここでは分野の第一線を走る研究者の方々が参加されており、定期的に開かれる会合で各々が行っている研究に関して意見交換を行う事が出来ました。大学教授や国立研究所の研究者、コンサルの方など錚々たる面子の中に学生が参加するのは緊張しましたが、自分より年上の方ばかりの場での会議は貴重な経験となりました。
こういった学外の方と関わる機会が多いのは橋本研ならではだと思います。年に3回ある他大学との合同ゼミや様々な学会での発表やその所属学生との交流、また先生に誘っていただいた水俣条約に関する講演会など様々な議論の場がありました。このような場では日々の研究やゼミとは異なった視点からの意見が頂けたり、普段の議論で見落としていた問題点が明らかになったりし、自分の研究の精度がより高まるきっかけになったと思います。
2020年度はコロナの影響で何かと大変なことが多い一年間でしたが、そんな状況下でも最後まで充実した研究生活を送ることが出来たのは橋本先生をはじめ研究室の皆様のおかげです。本当にありがとうございました。

- この1年間は確実に自分の成長を実感できた
- 出羽 加奈美(学部卒)
橋本研に入った理由として、年に数回多くの人の前で発表する機会があること、自分の興味がある環境分野に特化して研究を行うことができること、という2つの決め手がありました。
私はもともと人前で話すことが非常に苦手でした。しかし、橋本研では月に数回あるゼミでの発表、2回の合同ゼミでの中間発表、卒論発表、学会発表などと様々な人を相手にプレゼンテーションをする機会があり、自分のプレゼン力を高めることができる環境が整っていました。このおかげで、あまり緊張することもなくなり、常にどのようにしたら相手に伝わりやすいかを考える癖をつけることができました。私の人生の中で、この経験は自分の大きな成長に繋がったと思っています。
また、私は地球温暖化などの環境問題に興味を持っていました。橋本研では、様々な環境問題に関する研究をすることができると聞いていましたし、自分のやりたいことを先生も積極的に応援してくれました。私は、近年の身近な環境対策について詳しく調べたかったので、身近なものを題材にした研究テーマを設定しました。現在、ゴミ問題やCO?排出量の抑制のためにプラスチックを他の素材に代替しようとする動きがあります。ここで、私はスターバックスのストローが紙になっていることやキットカットやミルキーのパッケージが紙素材になっていることに気付き、それらの対策はどのような環境影響をもたらすのかを研究しました。この研究を通して、身近なテーマだからこそ様々な観点から環境問題について客観視することができて、見方を変えて考えるきっかけをつくることができました。これは社会人になっても生かせる知識だと思うので、非常に良い経験をすることができたと感じています。
最後に、この1年間研究のご指導をして下さった先生、先輩方、同期には本当に感謝しています。私はエクセルやパソコンの知識が乏しかったりして、沢山迷惑をかけてしまいましたが、橋本研の人はアットホームな感じで相談にのってくれたり、分からないことは優しく教えてくれました。改めて、研究に関わって下さった皆様本当にありがとうございました。
2019年度
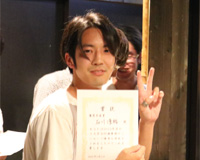
- すべきこととやりたいことの両立
- 石川 湧裕(修士卒)
橋本研での3年間は自分の生き方へ良い影響を貰えた3年間でした。大学院への進学の理由は自分のしたい研究があるから、プレゼンテーション能力を身につけられるから等、人それぞれであります。
自分の進学理由において、研究の内容はそれほど重要ではなく、大学院での研究生活の中で、研究は私にとっては大学院生としてやらなければならないことの一つでしかありませんでした。しかし、私生活や就職活動を行う中で、大学院生としての義務である研究は第一に考えていました。他にやりたいことがある中で、すべきことである「研究」を第一に考えながら、やりたいことをするには、どのように計画を立てるかということが、この3年間で身についた大きな能力です。このメリハリによって、すべきことである「研究」も計画的に進めることができ、やりたいことも効率良く行うことができました。
社会にでると、自分のやりたいことが仕事に直結しないことが多くあると思います。その中で、趣味などの自分がやりたいことと仕事の両立が、橋本研で身につけたこの能力によってできると思います。このような能力を身につけたいという理由も、大学院進学のきっかけとして悪くないと思います(笑)。
最後に、研究生活を充実したものにできたのも橋本先生、秘書の谷口さん、研究室のメンバー、皆さんのおかげです。この環境の中で、研究生活を送ることができたこと自体が大きな財産になりました。ありがとうございました。

- 物事を体系的に捉え、論理立てて考えること
- 上鶴 喜貴(修士卒)
大学院を含め3年間を過ごした橋本研を選択して最も良かったことは「論理的思考力」を身につけることができたことです。橋本研は木材や金属、廃棄物、情報通信技術等と選択できる分野が幅広く、興味のある分野を自らの意思で広げていけることが魅力な研究室です。「幅広くなんでもできる」と言えば響きはいいですが、逆にいうと自ら仮説を立て検証し続けていく難しさがあります。
でも、そこがまさにこの研究室に入って良かった「論理的思考力」が身についたポイントです。僕はInternet of Thingsという情報通信技術を使って、廃棄物処理の効率化を検討するというこれまで研究室では誰もやったことがない分野を先生と二人三脚で取り組んできました。未知の領域であり、学生では到底立ち会うことができない会議や企業間での打ち合わせなどにも数多く同席させて頂き、貴重な経験を積むことができました。
これまでに解決できていない課題に取り組んでいくことが研究の醍醐味です。その過程では、考えもつかないような課題や一長一夕には導けない解がたくさん存在します。そんな時にその課題の本質を問い、全体像を把握した上でどこに具体的課題点が存在するのか、そしてどのようにして解決し結論に結びつけるのかという力を、研究を通して身につけることができました。
最後に、研究を通した様々な経験は、研究だけに止まらず、これからの不安定な世の中を生きていく上で重要な力になったと思います。橋本先生をはじめ、研究室の皆様や研究協力者の皆様のお力無くしては得られない経験であり、心から感謝しています。

- 循環型社会研究室やったから…
- 隅谷 太陽(学部卒)
橋本研に所属した1年間は、不真面目だった私が大学生活の4年間を通して最も変化し成長できた1年間であったと確信しています。所属してすぐ、橋本研のゼミに対する学生の意識が高いことに驚きました。「発表に疑問を持たないことがおかしい」「質問はして当たり前」。入った当初はもっと楽な研究室があったのでは…と思いましたが、今振り返ると社会人で必要とされる、自分で考えて行動する「自主性」を持った人間になるという道が橋本研にはあったと感じています。研究テーマを決める際にも、大きな枠組みから研究内容、研究方法などを全て自分で考えてゼミで発表するという流れの中、多くの論文を読み込みました。そこで、興味がある研究テーマを見つけるために論文講読を怠らなかったことが、実りある1年になった要因の1つであると今では感じています。また、前述したようにゼミでは先輩や同級生、先生から必ずと言っていいほど、質問・アドバイスを頂ける環境が整っていました。人から何かを吸収する、そのような雰囲気を橋本研では自然と作ることができていて、人としても組織としても非常に高いレベルにあると思うと同時に、その一員になれたことを誇りに思います。
研究を進めていく中でGISやデータの収集等で行き詰まった時、気軽に相談できる先輩がいました。丁寧な助言をしてくれる先生がいました。「卒業研究」というのは決して1人でできるものではない、この橋本研だから味わえた最高の環境で1年間研究できたことを非常に嬉しく思います。全ての方々の協力のおかげで、こんな私が卒業研究発表会では優秀賞を勝ち取ることができました。この1年間はこれからの長い人生における大きな分岐点になったと感じています。関わってくださった全ての方々に感謝しています。本当にありがとうございました。
2018年度

- 3年間で築いた財産
- 佐々木 貴央(修士卒)
橋本研での3年間を振り返って、本当に修士課程に進んで良かったと改めて思います。学部生の頃は、研究の取りかかりが遅かったこともあり、思うように進まずに苦労しました。同じ失敗を繰り返したくないという思いから、大学院に進学してからの2年間は自身の研究に真摯に向き合い、大きく飛躍することが出来ました。これもひとえに橋本先生の丁寧なご指導や、切磋琢磨しあう研究室の雰囲気があってこそだと思います。
研究に付随して、得られたことも沢山あります。それは人との出会いです。橋本研では年に複数回、他大との合同ゼミがあり、そこで同じ研究分野の同世代の人たちと出会うことが出来ました。学会で会うたびに気さくに話をするだけでなく、時には研究の相談に乗ってもらうなど心強い味方となりました。また、私の場合は他の研究機関の方々と共同研究をしていたこともあり、その道の一線で活躍される研究者の方々と出会うことが出来ました。学内だけにとどまらず、学外でも多くの繋がりをもてたことは橋本研ならではのことです。人との出会いは財産だと思うので、この3年間で数多くの財産を築くことが出来ました。
最後に、充実した3年間を過ごすことが出来たのも、橋本先生や研究室のみんなのおかげです。本当にありがとうございました。今後はそれぞれの道に進みますが、自分が信じた道を自分らしく突き進んでいきます。

- 大学生活の分岐点
- 福谷 大樹(修士卒)
「橋本研に入って人生が変わった!」 少し大袈裟かもしれませんが、私はそう思えるくらい橋本研での3年間で大きく成長したと感じています。
研究室に入るまでの私は(どちらかというと)不真面目な大学生でした。しばしば授業で居眠りしたり、、、なんとなく単位さえ取れればと過ごした学部時代の3年間でした。そんな中、4回生始めの頃に橋本研に入り、当初は先輩の優秀さに圧倒されたことを今でも憶えています。そんなこともあり、4回生の頃は周りについていくことに必死で、学部時代の勉強負債を返す思いで研究に取り組みました。しかし、いつしか「ゼロから何かを明らかにする」という研究の面白さに魅了されていて、正に自らの意思で研究をしていた気がします。大学院に進学すると、できることには全て挑戦しようと決め、国内外での学会発表やアメリカの大学への研究留学、論文投稿など様々なことに積極的に挑戦しました。今振り返っても学部時代の私からは想像もつかないことです。
こんなにも私が成長できたのは、間違いなく橋本研の環境があってこそのことです。何にでもチャレンジできる環境を与えてくださった橋本先生、秘書さんには心から感謝しています。また、丁寧に相談に乗ってくださった先輩や切磋琢磨できる同期といったように、本当に恵まれた環境で研究が出来たと感じています。
最後に、どこかで「橋本研=優秀」といった噂を耳にしました。しかし、私のように決して優秀でなくとも必ず成長できる環境が橋本研には用意されています。寧ろ個人的には「研究室配属を機に自分を変えたい!」なんていう学生さんには最高の研究室だと思います。これを読まれた同じような境遇の学生さんの研究室選びの一助となれば幸いです。
- 「自分で考えたことが結果になる」研究の楽しさ
- 大平 菜央(学部卒)
橋本研に入って驚いたことは、研究が学生主体で進んでいくということです。研究室に入る前は、講義で教えられたことを頭にインプットする、出された課題をこなす、というように、自分から主体的に何かをするということはありませんでした。研究室を選ぶときも、特にこれがやりたいという希望もなく、雰囲気で橋本研を選びました。流されるまま研究がはじまり、最初に行き詰まったのは、研究のテーマ決めでした。テーマは先生が決めるものだと思っていたので、とりあえず既存論文を読む日々を送っていたら、橋本先生に「そろそろ何がやりたいか言って」と言われ、テーマも自分で考えるのかと驚きました。研究は、今まで誰もやっていないことをやる"新規性"が求められます。そのため、テーマを決める際にはその分野の既存研究について把握し、その上で新しいことを考えなければならず、かなり苦労しました。
なんとかテーマが決まりましたが、8月の合同ゼミでの発表が終わったあたりで、今の研究内容だと物事の一部分しか捉えられておらず、全体を分析できていないと感じました。しかし、研究ができる期間は残り半年もなかったので、研究内容を変えるべきか、また変えたところで卒業までに結果を出せるのか、と色々悩みました。結局、このまま研究を続けても納得する結果は得られないと思い、橋本先生に相談をして研究内容を少し変えることにしました。
その後は、試行錯誤を繰り返しながらも順調に研究が進んでいきました。自分で考えたこと、やりたかったことが研究結果として形になっていくのはとても楽しく、私は研究を通じて、自分が主体となって物事を成し遂げるという新たな経験ができました。そして、最後の最後まで私の意見に寄り添いながら、親身にご指導してくださった橋本先生には本当に感謝しています。苦労すること、悩むことなどもありましたが、自分なりにたくさん考え、新たな経験を得られた実りの多い一年でした。
2017年度

- この会議で飛び交う言葉や内容が理解できれば、確実に自分の財産になる!
- 田中 大介(修士卒)
この3年間で様々な経験をしましたが、橋本研に所属しなければ絶対に経験できなかったと思うことがあります。
それは「研究」です。
なに当たり前のことを言っているんだと思われるかもしれませんが、修士生にとっては一番大切なことだと思っています。この研究の質がどこまでも高められるのが橋本研の強みです。
橋本研に所属する学部生や院生のうち数名は、他大学や研究機関の方々と共同研究を行っています。例に漏れず、私もこのうちの1人でした。4回生の夏ごろに初めて会議に参加させていただき、実際の論文の著者の方々が目の前にいるという異常事態に「ここにいて良いのか」と何回も思ったことを今でも覚えています。しかし、会議が終わった後にあることに気が付きました。それが表題の言葉です。
それを機に修了まで研究を続けた結果、専攻分野に関する知識や留学で培った英語能力など、大きく成長できたと思います。ただ、この成長は橋本先生の丁寧なご指導はもちろん、橋本研の環境があってこそです。文献を読んでも分からないことがあれば先生が教えてくださいましたし、先生でも分からないことがあれば関連する研究機関に出張までさせていただきました。「研究」のサポートでは橋本研は群を抜いていますし、個人的にも貴重な経験をさせていただきました。
私の場合は卒業後も研究に近しい仕事をしますが、この仕事に興味を持ったのも、内定をいただいたのも、ここでの経験がなければあり得ませんでした。この3年間に、研究でご指導いただいた橋本先生や共同研究者の方々に、そして橋本研に本当に感謝しています。ありがとうございました。これからもよろしくお願い致します。

- 能動力を磨いた大学院生活
- 野木 茜(修士卒)
循環型社会研究室で過ごした3年間、特に修士課程の2年間では、研究活動を通じて大きく成長することができました。なかでも最も身についた力は、"能動力"だと感じています。私の研究では、「資源を対象とした環境効率指標」の検討を行っていました。分野の中でも着手され始めたばかりの研究テーマということもあり、新規性がある点ではやりがいを感じていたものの、先行研究がないために、どのように研究を進めていけばいいのか分からず、研究活動へのモチベーションが上がらないことが多々ありました。
そんな私が研究に積極的に取り組むようになったきっかけは、ドイツでの2ヶ月間の研究留学です。私が滞在した研究室では、循環型社会研究室と違って定期的なゼミが設定されておらず、そのままでは黙々と一人で研究を進めなければならない環境でした。そこで私は、せっかくの研究留学を実りあるものにするため、指導教員に依頼して自身の研究紹介や研究の進捗報告の機会を作るよう行動しました。発表では、循環型社会研究室の人たちとは違った視点のコメントをいただくことができ、改めて自身の研究内容について考え直すようになりました。また発表を重ねるごとに、英語で適切に意見を伝えられるようになり、研究について議論するのが楽しくなりました。
留学後の橋本先生との個別ゼミでも、分からないなりに自ら考えたアイディアを提示することで、先生とより深く議論できるようになり、研究も軌道に乗っていきました。同時に「このような研究がしたい」という展望もどんどん出てきて、研究に楽しんで取り組めるようになりました。それは、"悩みぬいて自分なりの答えを導き出すおもしろさ"を知ったからだと感じています。
循環型社会研究室でなかったら、こんなにも成長した自分はいなかったと思います。貴重な経験の機会をたくさんくださった橋本先生、研究活動もイベントも全力で取り組む研究室メンバーのおかげで充実した大学院生活を送ることができました。本当にありがとうございました!

- 興味と向き合えた1年
- 戸高 和彦(学部卒)
循環型社会研究室での1年間の学習・生活は、私にとって、学部3年生までのそれとは大きく異なるものでした。
学部3年生までは、興味のある分野と正課の授業を別のものとして考え、前者を諦めるか悩んだ時期もありました。しかし、循環型社会研究室に所属し、自分の興味をどのように研究に落とし込むかを考え、議論する時間を多くいただいた結果、今の自分ができることを浮き彫りにすることができました。私の場合はそれが「景観」であり、研究室の色にどのようにして近づけるのかを検討し、その方針を、橋本先生は共に考えてくださいました。
また、研究を進めるにあたり、ゼミでのプレゼンや様々な会社・学校法人への訪問を重ねることで、自分の興味・熱意を内部だけでなく学外の方々に伝える機会を多く経験でき、伝えることの難しさを学び、資料作成に対する意識を向上させることができました。
自分の未熟さ故に、すべてを順風満帆に進めることができた訳ではありませんが、興味に向き合い、挑戦し、失敗をも経験することができた循環型社会研究室での1年間の生活は、私の財産です。人により形は異なりますが、得られるものはとても大きい、そんな循環型社会研究室が今後も素晴らしいものであり続けることを願っています。
不安を抱えながら始めた研究でしたが、最後まで面倒を見てくださった橋本先生に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。学ぶ場所は変わりますが、循環型社会研究室での経験を基に今後も精進します。
2016年度

- こんな経験、今までにない!!!
- 髙栁 達(修士卒)
循環型社会研究室では、普通に研究をしているだけではなかなか体験することのできない、国内の学会や国際学会への参加、研究論文の執筆等の多くの貴重な経験が出来ました。特に、私にとって、最も貴重だと感じた経験は、Northeastern University, Bostonでの3ヵ月間の研究留学です。私の場合は、日本で行っていた研究内容とは異なる内容を留学先で研究していたため、この留学を通して他分野における幅広い知見を習得することが出来、研究方法においても新たな考え方を学ぶことが出来ました。さらに、留学先は英語が共通語であることから、研究のみならず、英語を用いたコミュニケーション能力も向上させて帰国することが出来たと思っています(帰国の際のフライトで日本語を3か月ぶりに聞き、なんだか気持ち悪くなったことを今でも覚えています。笑)。この経験を機に、私は良い意味で変われたと感じました。その理由は、帰国後から研究室の留学生と日ごろから英語で話すようになったからです(これは、国際色豊かな循環型社会研究室だったから出来たことでもありますが)。
英語でコミュニケーションをとれるようになったことで、留学生とも積極的に話すことが出来、研究に関する会話にとどまらず、談笑して冗談を言い合うことができたり相談相手になってくれたりと、言葉の壁を越えた仲になり、日本語よりも英語を話す回数の方が多い日もありました(すこぶる楽しい人たちばかりで。。。笑)。
こんなにも充実した学生生活を送ることが出来たのは、この研究室だったからだと思います。絶大に尊敬のできる教授やとても可愛らしく面白い秘書さん、いろんなことを分かち合える研究室メンバーに囲まれて研究ができ、様々な面で成長することが出来ました。
これからもとても楽しい研究室であることを期待しています!!

- やりたいことをやる
- 長井 翔太朗(修士卒)
橋本研究室は一人一人がそれぞれの研究テーマを持っており、その研究テーマの選択にとても自由が利くのが特徴です。そのおかげで、自分の好きなこと・やりたいことをじっくり考え、それに沿った研究テーマに打ち込むことが出来ました。また、パソコンの前に座るだけでなく実際に現場でのデータ収集・ヒアリング調査に関心があったため、建設現場や企業を訪れる機会も多く作っていただきました。やりたいことをやるというのはとても楽しくモチベーションが上がることで、やりたいことをやれる環境が整っていた橋本研究室にはとても感謝しています。研究内容を発表する機会も多く、研究室の普段のゼミはもちろん、他大学との合同ゼミ、学会での口頭・ポスター発表などなど、たくさん経験させていただきました。どうすれば分かりやすく、伝えたいことを伝えられるかを深く考えることができ、その難しさと面白さに気づくことができました。何を言ったかではなく、どう伝わったかが大切で、そのための工夫をこれからも考えていきます。
また、研究テーマが異なっていても、研究室の仲間として普段から研究内容について意見を交わすことも多く、チーム橋本研といった雰囲気がありました。誕生日会やボーリング大会、歓送迎会などのイベントも定期的に開催され、年齢・国籍関係なく楽しんだ思い出がたくさんあります。3年間、いろんなメンバーで楽しく充実した学びを得ることのできた研究室生活でした。やりたいことをやるというのはこれからもずっと続けていきたいと思います。本当にありがとうございました!

- 橋本研=チャレンジできる環境!
- 八柳 有紗(修士卒)
橋本研での3年間を振り返ったとき、一番最初に出てきた感想は、「本当に色んなことを経験したな!」でした。まず、4回生の時は、橋本先生の終始丁寧なプレゼン指導や先輩の華麗なプレゼンに刺激を受け、プレゼン能力の向上に尽力した一年でした。先生や研究室の皆さんにアドバイスを貰ったり、練習に付き合ってもらったりしているうちに、少しずつ納得できるプレゼンができるようになっていった嬉しさを今でも覚えています。M1に進学した頃は、だんだんと周りの留学生とも仲良くなり、英語で雑談や研究の相談もするようになりました(お陰で、3年間でTOEICの点数が150点上がりました(笑))。M1後半には、ノルウェーに2か月間留学に行き、慣れない環境で過ごす大変さとそれを乗り越える楽しさを学びました。さらにM2になると、研究がますます楽しくなり、国際学会の口頭発表に志願したり、先生と1対1で行う個別ゼミの回数を増やして頂いたりなんてことも…。この頃から、「次はこんな研究してみたいな!」というのも出てきて、楽しかったのを覚えています。また、橋本研は夏の合同ゼミやLCA学会の学生部会によるワークショップ等、他大学と交流する機会が多いため、他大学の方の研究への姿勢を見て、自分の足りない部分を考えさせられることが多かったのも印象的な経験でした。
研究、国際学会も含めた学会、英語、留学、プレゼン、外部との交流…。外部機関との研究打ちあわせや研究室運営など、ここには書ききれないことも経験させて頂きました。これだけ色々なことができたというのは、やはり橋本研が「チャレンジできる環境」であったためだと思います。これから橋本研に入る方、そして今橋本研にいる方は、橋本先生が整備してくださっているこの環境を最大限活用していってほしいですし、橋本研のチャレンジする風土をもっともっと盛り上げていってほしいなと思います。
最後に、こんな面白く、成長できた3年間にしてくださった橋本先生に感謝して終えたいと思います。橋本先生、本当にありがとうございました!これからも宜しくお願いします!
2015年度

- 3年間を振り返って…「悔いなし!」
- 田村 賢人(修士卒)
研究室での3年間の生活を振り返って、橋本研究室で生活ができて本当によかったと思います。
そう思える理由はたくさんありますが、まず、研究を通して多くの経験ができました。学会や普段のゼミなどでの発表はよい経験でした。国際学会では英語で発表する機会もいただきました。アブストラクトや論文等の文章を執筆する機会も多く、その際には毎回橋本先生に内容を細かくチェックしていただき、文章を書くスキルが向上したと思います。そんなこともあり、最後に修士論文を書く際には、文章を書くことにそれほど苦労しませんでした。
次に、研究室の国際色が豊かであることです。研究室に留学生や外国人の研究員が多く在籍しているので、海外に留学に行く以外にも英語に触れる機会に恵まれていました。日本語でも理解が難しい書類を作成する手伝いをし、英語で説明することもありました。その環境のおかげで、英語で話すことに抵抗はなくなりました。
そしてなにより、研究室でのイベントが多く、楽しく過ごせたことです、歓迎会や忘年会をはじめ、橋本杯や、先生や研究室のメンバーの誕生会等さまざまなイベントが開催されました。研究は個々にテーマを持っており、研究室に来なくてもできる作業が多いですが、研究室に来たくなるような雰囲気でした。毎年OBOG会も開催されているのでこれからも参加できればと思います。
3年間充実した楽しい研究室生活をありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

- 研究室初のごみ組成調査
- 佐々木 雄哉(学部卒)
2015年度、循環型社会研究室では大学内のごみ組成調査を実施しました。ごみ組成調査とは、捨てられたごみの中身を手作業で分類し、その組成を明らかにするというものです。
2015年度の調査は、ごみ分別行動の研究に興味があった私が主動となり進めていきました。といっても、この調査は研究室として初めての試みであった為、ゼロからのスタートでした。そのため、調査に必要な道具の調達、ごみの分類項目や調査手順の考案、実施場所や実施日程の調整等、やらなければならないことがたくさんありました。何よりいざ調査を実施すると、それは大変な作業でした。調査に用いるサンプルを毎朝早くから集めに行き、山積みとなった1週間分のごみ袋の中身を細かく分類して、重量や容積を測定します。最初に分類作業を実施した日は、朝から開始したのですが、夕方になっても全ての分類を終えることができず、後日に持ち越しとなったほどです。
このように大変な調査ではあったのですが、研究室メンバーの、忙しいながらも積極的な協力を頂けたおかげで、無事にやり遂げることができました。その達成感は、それまでの学生生活では得たことのないものでした。また、大変な作業を協力して進めていく中で、研究室メンバーの結束が強まったようにも感じました。
個々の研究テーマが異なる中、研究室総出で1つのことに取り組むというのは、なかなかないことだと思います。また、収集した数値データ等を扱って研究を進めることが多い中、研究対象に直に触れることができるというのも、この調査の良い点だと思います。このような経験ができるのも循環型社会研究室ならではだと思いますし、これからこの研究室で活動される皆さんには是非経験してほしいと思います。皆さんに調査を継続して頂き、今年度新調したばかりの作業着が、味のあるものになっていくことを期待しています!

- 外国人研究員との共同研究を通じて
- 村上 真理(学部卒)
私は研究室の外国人研究員の方と一緒に卒業研究を行いました。ひとつのテーマを二人で分担していたので、お互いの進捗状況や推計方法、データの扱いなどについて相手に説明する必要があり、何度も話し合う機会がありました。私は英語が得意な方ではないので、最初は上手く説明することができず、相手の方に長い間私の話を聞いていただくという状況でした。相手にわかりやすく伝えることの難しさを痛感しました。
研究を進めていく中で、いかに伝わりやすい説明をするかという点についても考えるようになり、事前に紙などに英語で重要な内容をまとめるといった準備をした上で説明を行うようにしていきました。そのようにしてからは短い時間で理解していただけるようになり、また自分でも研究の内容や考えを整理できるいい機会になったと思います。研究話の合間にお互いの国の文化や家族のことといったプライベートな会話も交わすことができ、色々な意味で新しい発見や驚きがたくさんあった卒業研究でした。日本人以外の方と一緒に研究できたのは、国際色豊かな橋本研究室だったからこそだと思いますし、自身の成長の糧になったと感じています。
橋本研究室はとにかく学べることが多くあたたかい雰囲気で、とても充実した時を過ごせました。社会へ出てからも、この一年間で学んだこと・得たことを胸に励んでいきたいと思います。本当にありがとうございました。
2014年度

- はじめての院生 ~かわいい子には旅をさせよ編~
- 伊藤 新(修士卒)
橋本研究室の初めての院生ということで、私自身は自由にやらせていただいたという印象があります。そして、この3年間は、自分自身非常に成長した期間だったと思います。特に修士課程では様々な経験をさせていただきました。
その中で特に成長した機会は、学会発表とオーストラリアおよび国立環境研究所でのインターンシップです。合計10回の学会発表をさせていただき、プレゼンテーションスキルを向上させることができました。オーストラリアでのインターンシップは、3週間という短い期間ではありましたが、研究から私生活まで全てが英語で、現在では、苦手であった英語もほとんど抵抗がなくなりました。また、私は大学入学時、将来国立環境研究所で働きたいと思っていたのですが、その夢をインターンシップという形ではありますが、橋本先生のおかげで叶えることができました。
これらの機会では、自分から行動を起こさなければ何も始まらず、積極的に行動を起こすことが大切であることを学び、行動するように心がけました。そして、普段なかなかお話しする機会のない研究者の方と議論を行うことによって、さらに研究を推し進めていくことができました。これらを通じて、橋本研究室の運営方針にもある「3つの力」を身につけることができたのではないのかと思っています。
これもすべて、橋本研究室ではなければ経験することができなかったと思います。ありがとうございました。

- 部活と研究室の両立
- 水上 瑞樹(学部卒)
私は循環型社会研究室初となる体育会所属の卒研生でした。よく「体育会に所属しているから忙しくて、研究大変じゃないの?」と、こんな質問をされましたが、私は部活も研究室も全力投球と決めていたので、どちらも手を抜くことをしませんでした。
私はゼミ係のリーダーを務め、主に合同ゼミの運営を担当しました。運営をするにあたって、他大学と連絡を取り、タイムテーブルを作成し、会場を確保しました。合同ゼミ当日は部活の合宿を途中で抜けて、合同ゼミに参加・進行し、終わり次第、また合宿に合流しました。なかなかできない経験だったと思います(笑)。
研究室での生活も部活と一緒でみんなとコミュニケーションを取り、円滑に運営するにはどのようにマネジメントするかなど、共通点が多く、非常に参考になりました。部活は部活、研究室は研究室と分けて考えるのではなく、共通点を見つけて経験を積むことで自分を最大限成長させることが出来ます。どちらも中途半端では何も身に付きません。これから研究に励む方々には何事にも全力で向き合ってほしいと思います。

- プレゼンに賭ける思い
- 梁田 雄太(学部卒)
この研究室を選んだ理由のひとつとして、学生生活の中でプレゼンテーションスキルを学びたいことがありました。しかし、研究室の先輩方の専門的な研究内容とレベルの高い発表で賞を取る姿を見て、ふつふつと「ただ学ぶだけでなく、先輩たちのように賞を取りたい!」と言う気持ちが湧いて来ました。
橋本研には、普段のゼミ発表だけでなく、他大学との合同ゼミや学会で発表できる機会等の数多くの機会がありました。これはたくさんの経験値を積めるのと同時に、先生や専門分野の方からの意見を頂き、日々勉強する機会でもありました。
この日々学んだ成果を示す最初の機会として、計画系グループ卒業研究発表会がありましたが、己の力量不足で勝ち取りたかった賞を取れず、すごく悔しい経験をしました。「このままでは終わりたくない」と思った私は、先生からのフィードバックを直接頂き、先輩方からのアドバイス、さらに同期からのコメントをもらって環境システム工学科卒業研究発表会に活かそうと努めました。結果、優秀発表賞を頂くことができました。
この賞は、先生、研究室の先輩、同期の後押しがあって得た賞だと感じています。まだまだ未熟者ですが、この研究室で学んだ多くの事を思い出しながら、精進していきたいです。

- 研究室での生活
- 矢野 夏美(学部卒)
理系の研究室といえば、実験やデータ収集ばかりで個人活動がメインというイメージを持っていませんか。循環型社会研究室はそんな私の考え方を変えてくれました。
循環型社会研究室では四回生は研究室を自主的に運営するために「ゼミ係」「イベント係」「研究室係」のいずれかの担当となります。私は「研究室係」として学生研究室の物品管理や環境改善などを担当しました。初めはわからないことが多く、先生や院生の方々に様々なサポートをしていただきました。
また、研究室には四人の留学生がおり、毎日様々な言語が飛び交っています。彼らは私たち学生に研究の専門家としての的確な指摘や刺激を与えてくれます。英語をはじめとした言語力を身に付けることができたのはもちろんのこと、彼らと接することでそれぞれの文化が持つ様々な価値観や意見に触れることができたことは、今後社会に出る身として大変貴重な経験となりました。
私はこの一年間で研究というものが如何に多くの人々に支えられながら成り立っているものであるということを学ぶことができました。そして学んだことを活かして、社会の一員として多くの人を支えられる人へなりたいと思います。
2013年度
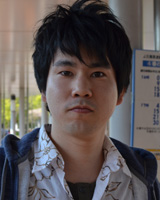
- インセンティブに関する研究を通して
- 川西 博貴(学部卒)
私は「温室効果ガスインベントリにおける廃棄物燃焼起源排出量の報告オプション」という題目で卒業研究を行いました。これは、日本国で排出された廃棄物燃焼起源のGHGを廃棄物分野とエネルギー分野にどのように配分するのが良いのか、その報告オプションを検討する研究でした。ここで重要だったのは、両分野にどのようにインセンティブを与えるかということです。インセンティブとは、モチベーションを誘因するものという意味です。両分野においてよりよいインセンティブを与えることにより、GHG排出量削減に向けての対策努力を促進していこうというモチベーションを高めることができます。しかし、研究を進めていく上で、両分野に等しくインセンティブを与えるということは難しく、双方が納得のいくインセンティブのバランスを考えることが大変だと感じました。
卒業後、私は行政で働きますが、行政は卒業研究で考えたインセンティブが直接必要になる仕事だと思います。住民の皆様にとって、また企業にとって、また行政を含めた国家にとって、など様々な事柄の相互関係を考えた上で、互いによいインセンティブをもたらす政策を考えていかなければなりません。一年間という短い期間でしたが、インセンティブについて考えた卒業研究は今後の私の仕事に大いに役立つものとなりました。
最後に、私は橋本研究室での一年間を通して、研究室が掲げる3つの力のうちの1つである「様々な事柄の相互関係を考慮できるシステム思考力」の重要性を実感し、少しは身につけることができたのではないかと思います。

- 廃棄物処理施設の現場見学
- 木船 敬太(学部卒)
2013年の夏、廃棄物処理業者を見学するため大阪に行きました。バスで行ったこともあり、最初は遠足気分でしたが、いざ見学が始まると非常に大切な経験ができたと思います。
見学会は、最終処分場のフェニックス埋立地、産業廃棄物リサイクル業者の田中企画、廃棄物の中間処理を行う京都環境保全公社に行きました。その中でも私はフェニックス埋立地が特に印象に残っています。フェニックス埋立地は大阪湾にある埋立処分場で、大阪湾圏域で発生した廃棄物を集めて埋立しているところでした。埋立地はそのほとんどが満杯状態で、平成39年度までしか受け入れを計画していないということを知りました。陸地での最終処分が困難になり、海上で埋立を行っているフェニックス計画への依存が増大するためです。
私はフェニックスで学んだことが2つあります。1つは、少しでもゴミを減らそうという意識、もう1つは現場を知ることの大切さ、です。さまざまな環境問題があることは知っていましたし、個人個人が小さな努力をしないといけないということもわかっていました。しかし行動に移すことができていませんでした。今回、現場を知ったことにより私自身の意識が変化したのだと思います。「事件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ!」の大切さを身に染みて感じました。

- 研究の楽しさ
- 堀 まつ梨(学部卒)
私にとって「研究の楽しさ」とは、人との繋がりを実感できることです。
研究室では夏の合同ゼミや共同研究、研究発表など多くの方と接する機会を頂きました。研究を通してこれまで繋がりのなかった方や専門分野の方と話す機会が増え、自分の研究に興味を持ってくださることが嬉しかったです。私の未熟さから、伝えたいことが伝わらず悔しい思いもしました。しかし、それがより研究を深くまで考えるきっかけになりました。
楽しいからこそ研究に真剣になって取り組め、真剣に取り組むことで周りの方も力になって下さいました。橋本先生をはじめとする研究室の仲間、環境システム工学科の先生・先輩方、誰にでも頼れ相談できる環境が作れたことは研究をするうえで大切なことだったと思います。楽しく研究ができたことが私の1番の強みになりました。
卒論発表はこれまでで一番楽しい発表でした。「楽しそうに話すから聞いてて楽しかったよ。」と声を掛けて頂き相手にも伝わったことが嬉しかったです。
研究を終えて、自分が楽しむためにしていた行動が最終的に自分の成長に繋がったと実感しています。これから研究に取り組む人にも自分の楽しさを見つけて研究に取り組んでほしいと思います。
2012年度
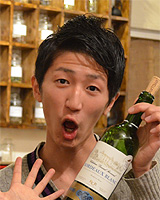
- 合同ゼミでの運営と発表を通じて
- 伊藤 新(学部卒)
2012年度は、名古屋大学谷川研究室と香川県琴平市で、九州大学加河研究室、北海道大学藤井研究室とBKCで計2回、他大学との合同ゼミを行いました。
合同ゼミを行うにあたって、各大学の幹事とメールでやり取りを行い、お互いが納得いく形となるように作り上げていきました。また、BKCで行った合同ゼミでは、他大学を迎えるということで、ゼミ係の力を合わせて、合同ゼミの内容を考え、会場の確保、タイムテーブルの調整、しおりの作成等の準備を行いました。合同ゼミ本番では、長いようで短い3日間の運営を行い、タイムテーブル通りに運営出来たところ、出来なかったところを含め、自分にとって貴重な経験となりました。合同ゼミ終了後、他大学の先生方から「Excellent!!」との一言を頂き、今回の合同ゼミは成功に終わったのではないかなと考えられ、運営を行ってきて良かったと思える瞬間でした。
参加してみて、合同ゼミのメインである研究発表会では、初めて発表を聞く人たちの前での発表のため、初めて聞いてもわかりやすいプレゼンテーションが求められます。そのため、プレゼンを作る際にどのようにしたら伝わりやすいかなどを試行錯誤していく作業の中で、自分の研究を見直すいい機会になりました。普段研究室で行われているゼミでは得ることのできない意見をいただくことができ、卒業研究に生かすことができました。
最後に合同ゼミの全体を通して、「能動力・コミュニケーション力」が大切であるということを実感し、少し力をつける事が出来たのではないかと思いました。

- 家庭ごみ組成調査のススメ
- 木下 三加(学部卒)
先生に紹介されたアルバイトで、家庭ごみの組成調査に参加しました。興味本意での参加でしたが、実際やってみるととにかく大変な作業でした。
組成調査はごみの中身を細かく分類し、どのような組成かを調べるもので、自治体が定期的に行っているものです。その対象は可燃ごみ、資源ごみ、小型家電等で、私は可燃ごみしかやりませんでしたが、恐らくこれが1番大変だったと思います。ごみ袋を開けるところから始まり、まず大まかに分類、さらにそこから細かく分類し、ひとつひとつを計量し記録する・・・ごみの量が半端なく多いうえに分類が数十種類とかなり細かく、初参加で右も左もわからない自分には本当に大変な作業でした。しかし、作業をしていて考えさせられたこともありました。ごみが多いのは資源が循環せず廃棄されているということ、分類が大変なのはごみを出す時に分別ができていないということ、そこから普段の自分の生活についても考えるきっかけとなりました。
個人的な感想を言うと正直辛かったです。あの真夏の暑い日に虫や悪臭と戦いながらの作業は体力的にも精神的にも本当に過酷そのものでした。けれども辛かったばかりでなく、前にも述べたように得たものもあったと思います。橋本先生のもとで、この研究室で、循環型社会について研究する際にはぜひとも一度はして欲しい経験です。この経験が自分の卒論や研究室の他の人の卒論の参考になるのは間違いないです。まさしく研究室の運営方針の一つである「事件は会議室で起きてるんじゃない。現場でおきてるんだ!」だと思います。実際に自分の目で見て体験すること、非常に大切なことだと感じた経験でした。

- 京都府の方と進めた卒業研究
- 細川 大地(学部卒)
私は京都府の方のご協力を得ながら木製治山ダムのライフサイクル評価について研究を行いました。
はじめに京都府の森林保全課に伺ったときには、計画中の土木構造物について論議されていたり、林務事務所との連絡をとられていて、職場にとても真剣な雰囲気を感じました。その後、林務事務所に連れて行っていただき、木製治山ダムの施工計画書の中身について紹介していただきました。実際に木製ダムの施工計画書をいただいた後は、メールで連絡を取り合い、それでもわからないところは府庁に直接伺って疑問を解消しました。文面だけでなく、直接の対話でなければ理解できない点が多くあると感じました。
亀岡市にある木製ダムの見学に伺った時には、木製ダムの補修方法やダム周辺の環境など、計画書だけではわからないことを多く学びました。特に、木製ダムと周辺環境が作り出す景観を実際に見ることで、数字だけでは分からない木製ダムの素晴らしさを体感しました。
卒業研究を進める中で、計画書やデータだけを参考にするのではなく、対象とするものを直に見ることで、その物に対する理解度は大きく高まると思います。研究は机に向かって進めるだけではなく、体を動かすことも意識して進めるものだと思いました。
2011年度
- 循環型社会研究室 第一期生
- 古賀 楓子(学部卒)
循環型社会研究室は、2011年4月にスタートした新しい研究室でした。橋本先生、Tao Wangさん、そして4人の4回生の合計6人と少ない人数ではありましたが、その分フットワークも軽く、イベントもたくさん行ってきました。それは、私が想像していた、できて1年目の研究室の活動頻度とはかけ離れていました。
まず、4月は全員の歓迎会をしました。先生も私達学生も互いに歓迎し合いました。そして、短期留学生と一緒に7名で、9月は名古屋大学へ行きました。ちょうど台風と重なり、悪天候ではありましたが、名古屋大学との発表・交流も、名古屋観光も楽しむことができました。帰りは、下道で様々なところに寄り道をしながら南草津まで帰ってきて、ボーリング大会をしました。優勝はもちろん橋本先生です。この頃には、4回生の卒業テーマが決まっていたように思います。
第一期生のテーマは、資源系と都市系の2つに分かれました。先生の専門分野は、循環型社会、資源・廃棄物管理です。私達は、それぞれ異なるテーマではありますが、循環型社会の形成を目指すための一要素について深く考えることができたのではないかと思います。私達の研究室には、院生や先輩はいませんでした。その分、毎週のゼミでは全員が発表し、先生が手厚いフォローをして下さいました。そうでなければ、数々の合同ゼミを乗り越えることはできなかっただろうと思います。本当にありがとうございました。
4月からは、それぞれ別の道を歩んでいきますが、この1年間で学んだことを糧に様々なことに挑戦していきたいと思います。
(立命館大学建設会学生部会会報「RITSUMEIKAN CONSTRUCTION」Vol.20(2012)に掲載された記事をもとにしています)