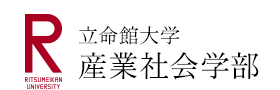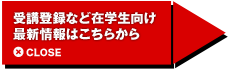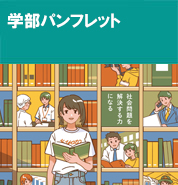教員紹介
現代社会専攻
| 氏名 | 専門分野 | 研究テーマ | 関連サイト |
|---|---|---|---|
| 江口 友朗 | 経済学の思考方法(経済学史)と理論・分析(制度の経済学) | タイなど東南アジア諸国の人々での間での金銭的な違い(例えば、貧困や所得格差など)に関する調査と、世界中の人々が物質的に豊かかつ幸せに暮らしていくために必要な持続可能な社会経済システムの検討:各国の制度や政策をてがかりにして |
|
| 大野 威 | 労働社会学、労使関係論、労働経済論 | 日米英を中心とした働き方の変遷の国際比較、女性役員登用の国際比較、育児と仕事の両立 | 個人HP |
| 加藤 潤三 | コミュニティの社会心理学 | 社会心理学から地域コミュニティにおける人間の行動と心理の探求(地域環境問題、地方への移住、沖縄に関する研究など) | |
| 加藤 雅俊 | 現代政治学、比較政治学 | 公共政策が国々によって異なる理由・背景に関して政治的な要因に注目して分析する(とくに、日本とオーストラリアに注目して)、紛争処理と合意形成のあり方を多角的に検討する、政治学という学問が可能になるための条件を検討する | |
| 金澤 悠介 | 計量社会学・数理社会学 | 大規模アンケート調査で人々の政治についての新たな価値観を探る、大規模アンケート調査で社会的孤立の実態と原因を探る | |
| 斎藤 真緒 | 家族社会学、ジェンダー論 | ヤングケアラー・若者ケアラーおよび男性ケアラーを中心とする家族ケアに関する理論的実証的研究と当事者参画に基づく社会資源の開発、今日の若者の恋愛の動向の把握とデートDV 予防プログラムの開発 |
|
| 崎山 治男 | 感情社会学 心理主義化と自己形成 | 感情の社会学、サービス産業下でのストレスに関する感情労働論、コミュニケーション能力が求められる社会の心理主義という視点からの分析 |
|
| 櫻井 純理 | 社会政策論、労働社会学 | 市町村と企業・NPO 等が提供している就業困難者への支援政策、日本とデンマークの比較研究 |
|
| 杉本 通百則 | 環境論 | EU・ドイツの環境政策の歴史、リサイクルや循環経済の研究、大量生産・大量消費社会の国際比較 | |
| 住家 正芳 | 宗教社会学 | 宗教学、宗教社会学。 宗教や宗教的なもの(聖地、霊的なもの、占いetc.)をめぐるさまざまな思想の研究 |
|
| 孫 片田 晶 | 社会学 | 在日コリアンの歴史や思い、多文化共生社会、人種主義の問題 | |
| 武岡 暢 | 社会学 | 歌舞伎町の都市社会学、商店街、職業のネットワーク:ホストクラブ、キャバクラ、性風俗、客引き、スカウト等 | |
| 竹濱 朝美 | 環境教育 | 再生可能エネルギー電源(風力、太陽光、バイオマスなど)の拡大政策、脱原発のエネルギー政策、再エネ100%を目指す企業・自治体の事例分析、電気自動車EV 拡大に関する国際比較 | |
| 趙 相宇 | 韓国社会のナショナリズムとメディア文化、日韓における植民地支配をめぐる感情や記憶の歴史社会学的研究。 | ||
| 富永 京子 | 国際社会学、社会運動論、グローバル化論 | ・政治に対して意見を言うことや批判をすることはなぜ日本社会では嫌がられてしまうのか ・「旅行」と「暮らし」を社会・政治とつなげて研究する |
|
| 中井 美樹 | 社会学(含社会福祉関係)、社会階層論 | 生活や仕事での男女間不平等の研究、ジェンダー格差・性別役割分業、等の研究 |
|
| 中西 典子 | 地域社会学、福祉社会学 | 地域社会と公共性(公共空間)、地域政策(地方分権、地域振興)に関する比較社会研究、京都学研究 | |
| 永島 昂 | 産業論 | 日本経済・産業の歴史、モノづくりにおける中小企業の研究 | |
| 永野 聡 | 学習支援システム、教育工学、都市計画・建築計画、まちづくり・まちおこし、復興まちづくり、観光地域づくり、プロセスデザイン | 観光と健康を融合したまちづくり、身近なところからの環境対策(SDGs)、アート活動で地域おこし?!、震災復興と国際交流の実践、UberやAirbnbが身近な社会を創るには?、高齢者に優しい社会をみんなで創るにはどうすれば良いか(海外にもトビ出そう)? |
|
| 永橋 爲介 | 環境デザイン | 参加型まちづくりの実践、ファシリテーション・スキル(対話と熟議を円滑に進める技法)の獲得と展開、合意形成の作法と技術 |
|
| 原尻 英樹 | エスニシティ論、文化人類学、世界のコリアン、東シナ海域研究、武道的身体論 | グローバリゼーション、世界のコリアン、東シナ海域研究、身体論 |
|
| 樋口 耕一 | 経験社会学・社会調査法 | ネットやマスメディアを飛びかう言葉から「社会の心」を探る研究、テキストマイニングの方法とツールの開発 | |
| 平井 秀幸 | 社会学、批判的犯罪学、アボリショニズム | 刑務所のフィールドワーク、薬物依存症とその支援、セルフヘルプ・グループと当事者活動、社会批判と社会調査 | |
| 三笘 利幸 | 社会学、社会思想史 | マックス・ヴェーバーの思想、近現代の沖縄をめぐる思想 | |
| 柳原 恵 | ジェンダー研究、女性史・ジェンダー史、地域女性史、女性運動、フェミニズム運動、ライフストーリー | ジェンダー研究。女性史。インタビューとミニコミ(自主制作雑誌)から見る女性運動 |
|
| 山口 歩 | 産業技術論 | 再生可能エネルギーの拡充政策 系統拡充の考察 電力自由化時代の系統接続ルール 電力消費生活のデザイン 公共空間の拡充 音響デバイスの発展過程 |
|
| 吉田 誠 | 産業社会学、人事労務管理論、労使関係論 | 戦後日本の企業と労働組合の歴史 | 個人HP |
| リム ボン | 都市再生、公共事業、市民参加 | 歴史都市・京都における都市政策課題の探求 |
メディア社会専攻
| 氏名 | 専門分野 | 研究テーマ | 関連サイト |
|---|---|---|---|
| 飯田 豊 | メディア論、メディア技術史、文化社会学 | メディア論、メディア技術史、文化社会学。とくにテレビ、ビデオ、万博などに関する研究 | 個人HP |
| 瓜生 吉則 | メディア論、文化社会学 | マンガの読者論・メディア論、メディア文化としての競馬の歴史社会学、戦後日本社会におけるテレビの文化研究 | |
| 川口 晋一 | 社会学(余暇・スポーツ) | メディアの発達と観覧スポーツ文化の変容:米国レクリエーションの歴史と政治 |
|
| 坂田 謙司 | ローカル・メディア論、音声放送メディア論 | 社会における音と声の存在を、理論とラジオ番組制作を通じてもう一度考える。特に、ジェンダーや災害、AIなどの日常生活との関わりについて、歴史を遡って考察する | |
| 住田 翔子 | 社会学 | 戦後日本の廃墟イメージの研究、アートと都市空間・都市イメージ、視覚文化論、感性文化論 |
|
| 高橋 顕也 | シンボリック・メディアを焦点とした社会理論の構築、社会学的システム理論の公理論化 | コミュニケーション・メディア、メディア文化、ソーシャル・メディア、社会理論 | |
| 筒井 淳也 | 社会学、社会的ネットワーク、ワーク・ライフ・バランス | 社会的ネットワーク(家族・友人関係)、仕事と家庭の両立、国による生活や価値観の違い | BLOG |
| 長澤 克重 | 経済統計学、社会学、経済理論 | 情報化・サービス化経済の統計的研究 |
|
| 浪田 陽子 | メディア学、教育社会学、カリキュラム研究 | メディア・リテラシー(メディアの特性を理解し、読み解き、発信する力)の獲得と学校におけるその教育実践、日本と北米の映画・テレビ番組・広告に描かれるジェンダーやエスニシティの比較分析、カナダのメディア研究 | |
| 根津 朝彦 |
日本近現代のジャーナリズム史、思想史 | 戦後日本のジャーナリズムの歴史、新聞記者・報道・ニュース研究、テレビのドキュメンタリーが迫る社会問題 | |
| 日高 勝之 | メディア学、文化社会学 | ①「物語(narrative)」としてのメディア・映画研究 ②記憶、ノスタルジアのメディア・映画研究 ③コロナ禍・東日本大震災などの大災害・カタストロフィ後のメディア・映画研究 |
|
| 福間 良明 | 歴史社会学、メディア史 | ①戦争観の変容とその社会背景に関する戦後メディア史 ②教養文化と格差・労働をめぐる歴史社会学 |
|
| 藤嶋 陽子 | 文化社会学、ファッション産業史、消費社会論 | 日本のファッション産業の歴史、ファッションメディア、SNSやECサイト(商品を売買できるウェブサイト)の登場が消費に与えた影響、ファッションとテクノロジー | |
| 増田 幸子 | 言語文化学 | 映像メディアにヒーロー・ヒロイン・マイノリティはどう描かれているか、日本のテレビドラマ研究 | |
| 柳澤 伸司 | ジャーナリズム論、マス・コミュニケーション論 | 新聞活用の教育(NIE:Newspaper in Education)、メディア・リテラシー、ジャーナリズムとメディアの諸問題 |
スポーツ社会専攻
| 氏名 | 専門分野 | 研究テーマ | 関連サイト |
|---|---|---|---|
| 市井 吉興 | スポーツ社会学、レジャー社会学 | 新しいスポーツ=ニュースポーツを創ってみよう!そして、スポーツの魅力を探求してみよう!!でも、「新しいスポーツ」ってなんだ?? | |
| 漆原 良 | 神経生理学、運動生理学 | スポーツのパフォーマンスを含む人の運動・行動能力の潜在的可能性を引き出す方法を学際的視点から考える | |
| 岡田 桂 | スポーツ科学、ジェンダー | スポーツとジェンダー(性役割)をめぐる歴史と現状、スポーツとセクシュアリティ(LGBTQ+)の関係性、文化としてのスポーツが社会で果たす役割 | |
| 金山 千広 | アダプテッド・スポーツ | ①障害者スポーツの普及・振興に関する研究 ②学校体育・生涯スポーツにおける「場」のインクルージョン ③ 対象者の状況に応じて、スポーツを工夫・展開するためのマネジメント(アダプテッドスポーツのマネジメント) |
|
| 金子 史弥 | スポーツ社会学、スポーツ政策論 | ①スポーツ社会学、スポーツ政策論 ② 戦後のイギリスにおけるスポーツ政策(スポーツとナショナリズム/社会的包摂) に関する研究 ③ オリンピック・パラリンピックをはじめとした国際的なスポーツイベントに関する社会学的研究(特にその<レガシー>(遺産)に関する研究) |
|
| 権 学俊 | 現代日本社会論、スポーツ政策 | 近現代日本の天皇制( 皇室)とスポーツの歴史 スポーツとナショナリズムに関する研究 スポーツと人種差別、排外主義に関する研究 |
|
| 中西 純司 | 体育・スポーツ経営学,地域スポーツ経営論,スポーツマーケティング論 | ①価値共創とスポーツサービソロジー(スポーツサービス学) ②地域スポーツと市民(志民)社会の形成 ③スポーツという「不便益」文化論の研究 ④スポーツ経営学の理論開発 |
|
| 松島 剛史 |
スポーツ社会学 |
①スポーツがなぜ世界に広まったのかを探る ② ラグビーの魅力や発展がいかに社会(政治、経済、科学技術など)に支えられているかを探求する ③レジャー・スポーツを使って理想的なコミュニティや社会をデザインする |
子ども社会専攻
| 氏名 | 専門分野 | 研究テーマ | 関連サイト |
|---|---|---|---|
| 石田 智巳 | 体育科教育学 | 体育と認識、ナラティブ・アプローチ、体育実践記録論 | |
| 大谷 いづみ | 生命倫理学 | 「いのち/生・老・病・死」の語り方・語られ方の分析と再考 |
|
| 大谷 哲弘 |
臨床心理学、教科教育学、特別支援教育 | 高校生の学校生活への適応やキャリア発達、児童生徒の大規模自然災害後のトラウマ反応 | |
| 岡本 尚子 | 数学教育学、教育工学 | 算数科の子どものつまずき、脈拍や視線などを用いた思考の分析 | |
| 御旅屋 達 | 教育社会学、福祉社会学 |
ひきこもり経験を有するなど、生活や就労において難しさを抱えた若者を支える仕組みについての研究 現代社会における「居場所」についての研究 |
|
| 角田 将士 |
社会科教育学 | 社会科(地理歴史科・公民科)カリキュラム編成論、社会科(地理歴史科・公民科)授業構成論 | |
| 景井 充 | 自我論、社会学理論 | ①フランス社会学を誕生させた問題意識と理論構成の解明 ②日本的近代社会の特質を炭鉱の歴史に探る研究 ③条件不利地域の社会経済的サステナビリティを実現するソーシャルデザインの探求 |
|
| 柏木 智子 | 教育学、教育経営学、地域教育学 | 子どもの貧困、外国ルーツの子ども、子ども食堂、学習支援活動、探究学習、ケアする学校・授業づくり、学校とICT活用、学校との連携によるコミュニティづくり | |
| 中西 仁 | 社会科、教職論、同和教育 | ①小・中学校における社会科授業の教材、方法の研究 ②京都の祭礼、年中行事、地域の歴史研究 |
|
| 野原 博人 | 教育学 | 理科教授・学習論、理科評価論、学習環境のデザイン | |
| 春木 憂 | 国語科教育学 | 国語科授業づくり、カリキュラム開発 |
人間福祉専攻
| 氏名 | 専門分野 | 研究テーマ | 関連サイト |
|---|---|---|---|
| 秋葉 武 | NPO・NGO論(非営利組織論)、社会的企業論 | NPO・NGOの経営学(NPOがより社会的成果を挙げるためのガバナンス・クラウドファンディング・広報・人材開発・コンサルティングなど) | |
| 石田 賀奈子 | ソーシャルワーク(社会福祉学)、子ども家庭福祉、社会的養護 | 児童福祉・特に虐待を受けた子どもの回復に向けた支援に関する研究、児童養護施設や里親による子どもの養育、子どもの権利擁護(アドボカシー) | |
| 呉 世雄 | 人間福祉 | 高齢者の地域生活を支える仕組みと実践、社会福祉施設の運営管理、ビジネス手法を用いた社会問題の解決、新たな福祉サービスの開発 | |
| 岡田 まり | ソーシャルワーク(社会福祉学)、ヘルスプロモーション(健康教育学) | 病気・障害・介護・貧困・差別などに直面している人の生活支援や環境改善、福祉専門職の養成や研修 | |
| 川﨑 聡大 | 障害児者心理学 | 発達障害や知的障害・言語障害の背景や支援法を心理学・脳科学の観点から検証するディスレクシア(発達性読み書き障害)の支援法やインクルーシブ教育実践を可能とする評価法の研究 | |
| 黒田 学 | 地域福祉、障害児福祉 | 障害のある子どもと家族の地域生活支援、特別ニーズ教育および障害児福祉に関する国際比較研究(ベトナムなどの東南アジア、ポーランドなどのEU諸国) | |
| 桜井 啓太 | 社会学、社会福祉学 | 現代日本の貧困問題。社会福祉、特に生活保護制度に関する研究 | |
| 鎮目 真人 | 社会保障論 | 社会保障、労働、家族などに関する社会問題と日本の福祉国家に関する研究、高齢期の貧困問題と年金制度の研究 | |
| 田尾 直樹 | 地域福祉 | 社会的孤立に関する地域福祉の役割、社会福祉施設の建設をめぐる地域住民との紛争事態に関する地域福祉の課題 | |
| 竹内 謙彰 | 発達心理学 | 発達心理学(発達障害児・者の特性理解と支援、発達のアセスメント、認知の発達と個人差) | |
| 田村 和宏 | 障害児者福祉 | 障害のある子ども・人たちの発達と生活・教育・労働の支援について、障害のある人の権利の侵害と保障について、家族やきょうだい支援について | |
| 丹波 史紀 | 社会福祉政策、公的扶助、災害復興研究 | 貧困や災害などのリスクにさらされた個人や家族が、尊厳を保ち地域での暮らしを実現する社会政策の研究 | |
| 中村 正 | 社会病理学・臨床社会学 | DV、虐待、いじめ、ハラスメント、性加害、ストーキング行為等の対人暴力をなくすための臨床社会学・社会病理学の研究、ジェンダーと男性性の研究等 | |
| 長谷川 千春 | 社会政策、財政・社会保障 | 日本やアメリカを中心とした、医療保険や医療サービスの提供に関する医療保障システムについての研究、また医療保障システムが抱える問題についての研究 | |
| 前田 信彦 | 社会学、ライフコース論(労働生活、職業キャリア、ワーク・ライフ・バランス研究)、エイジング研究 | 教育と職業キャリアに関する社会学的研究、学校から職業への移行とキャリア教育(大学生の就職活動など)、ワークライフ・バランス研究 | |
| 松田 亮三 | 比較福祉・医療政策、健康と医療の社会学 | 医療と福祉の仕組みと政府の役割、いろいろな国の福祉の仕組みの比較、誰もが必要な医療・福祉を利用できるために何をすればよいか | |
| 三木 裕和 | 障害児教育学 | 障害児教育における教育目標・教育評価論 | |
| 村田 観弥 | 教育学 | インクルーシブな社会に向けた教育のあり方についての研究 |
言語・国際教育
| 氏名 | 専門分野 | 研究テーマ | 関連サイト |
|---|---|---|---|
| Ian Hosack | 英語教育、シティズンシップ教育 | 日本の中等教育におけるシティズンシップ教育(市民教育)と英語教育との関連性とその取り組み。現代社会に市民として参加するため必要な意識、スキル、価値観など、英語教育を通してどのように育成されるかについての研究 | |
| 伊東 寿泰 | 言語学(語用論)、英語教育学、新約聖書学 | 言語学(語用論)を用いた英語教育研究、ヨハネ福音書を中心とした新約聖書の文学的・言語学的研究 | |
| 上原 徳子 | 中国文学 | 中国古典小説とそのパロディ・スピンオフ・映像化作品と読者や観客の受けとめ方についての研究 | |
| 下條 正純 | 日本語、日本語教育 | 日本語における表現とその効果、物語(少女小説やライトノベル)に見られる発話表現と人物描写の関わりなど | |
| 武田 淳 |
国際移動、移民、観光、オーストラリア | 留学や就職などで国境をこえて移動する人たちについての研究 | |
| 仲井 邦佳 | 言語学(スペイン語文法、ロマンス語比較研究、日本語・スペイン語対照研究、外国語教授法) | スペイン語文法構造の研究、ロマンス語(イタリア語、フランス語、等)との比較研究、スペイン語と日本語の対照研究 | |
| 盧 載玉 | 美術史、韓国美術史、日韓絵画交流史 | 韓国・朝鮮語教育(言語の機能「読む」「書く」「話す」「聞く」)を楽しく学べる教材開発、文化的背景に基づいて機能する言語力を身につけるための教材開発) | |
| 松島 綾 | コミュニケーション学(レトリック)、ビジュアル・カルチュラル・スタディーズ | ポピュラー・カルチャー研究、視覚文化と認識、主体の関係性、視覚的コミュニケーションの研究 | |
| 宮尾 万理 | 言語学(心理言語学)、英語教育 | 第二言語学習者による文の理解と産出、思考力の育成 |
嘱託講師
| 氏名 | 職位 |
担当授業科目 | 教育活動 | |
|---|---|---|---|---|
| 柳田 典子 | 初等教職課程支援担当嘱託講師 | 初等教育実習事前指導、初等教育実習Ⅰ、初等教育実習Ⅱ(事後指導を含む)、教職実践演習(小学校) | ・小学校研究発表会、校内授業研修会での指導助言(全国学校図書館スーパーバイザー/NPO法人学校図書館実践活動研究会理事) ・学校図書館を活用したワークショップ、教材研究会 |
|
| 山田 文乃 | 初等教職課程支援担当嘱託講師 | 初等教育実習事前指導、初等教育実習Ⅰ、初等教育実習Ⅱ(事後指導を含む)、教職実践演習(小学校) | 多文化共生教育、国際理解教育、地域学習、外国につながる子どもへの教育的支援、困難を抱えた子どもを学校で支える仕組みの構築、小学校外国語教育実践、日本語指導 |