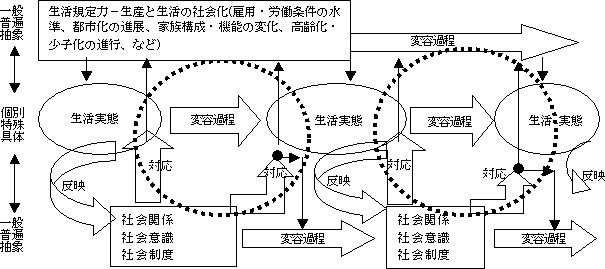地域福祉とは、制度政策としての一面と共に、他方では市民の暮らしの基盤としての地域社会の変容からその再生に向けた人々の意思的能動的なプログラムである。本研究では、地域において発生する生活問題状況やそれに対応した実践活動として現実に展開されている人々の意思的な相互支援活動について、臨床的研究方法を確立しつつその方法論をもって分析研究し蓄積していく。そして、福祉的機能をビルトインした地域社会の形成方向、すなわち地域社会の現実に即し市民生活に密着した新たな地域福祉活動プログラム開発を想定しながら研究するものである。
地域福祉における臨床的研究方法については事例研究的な方法は従来からもあるが、我々はこれに留まらずに、そのフレームを次のように考えている。それは、地域福祉の問題現象の発生現場あるいは地域福祉活動の実践現場さらには地域福祉運動の展開現場としての地域社会に、自らが直接足を運び関係者との共同作業を行いつつ、先行研究に依拠しつつ社会科学的分析を行いながらその歴史的あるいは社会的存在としての地域社会あるいはそこに住み暮らす人々の抱える諸問題の実態の把握に努め、問題状況を抱えた人々の生活保障や地域社会の福祉的機能の形成に必要な条件とその実現に向けてのプログラムを明らかにし、実践と運動の発展に寄与しつつ、自らの研究内容をさらに深めていくということである。
本研究での臨床研究場面は上記の図による。現実の生活実態と、社会関係・社会意識・制度政策との対応関係の齟齬が生じるいわば社会と生活の変化の最先端分野(・・・・・● )の実態をそこでの問題や地域福祉活動プログラムを臨床的研究方法によって浮き彫りにする研究である。
医療・教育・心理・福祉など臨床を標榜する諸科学が対人援助への関わりを重点にしたものであることに比して、我々の臨床現場は地域社会というシステムであり、そこで発生する様々な問題・病理現象である。ある意味で、ソーシャルマネジメントといわれる領域かもしれない。こうした問題や活動、運動の発生現場に研究者自らが臨んで、関係者と共に望むべき方向を探り出していくというような臨床的研究の蓄積と精査こそが、隆盛に見えるがサービス供給システム化に収斂し、ある種出口の見えないかのような閉塞感が漂う今日の地域福祉研究に活性化をもたらしていくリアリティある研究方法だとも考えるからである。このことはまた、市場原理に立脚したサービス供給システム型地域福祉ともいえるような社会福祉改革をリードしていく操作概念としての地域福祉ではなく、我々の生活に根ざし地域社会の福祉的機能を切り開いていく実践概念としての地域福祉に捉えなおしていく視点でもあろう。地域福祉一般理論からの各プログラム提起ではなく、多様な具体的プログラム開発からの地域福祉論への接近といってもよい。地域福祉研究の研究方法論としての臨床的研究方法を提起したいのである。
1.このプロジェクトは毎月一回第Ⅱ土曜日に定例的に開催する。 2.定例会には、各地での実践(社会変化の先端部門で取り組まれている、または取り組まれてきた様々なプログラム)の報告と討議を中心に進める。 3.そこでの報告及び討議内容のうち必要なものは活字化していく。 4.当面の報告予定は次の通りである。
|
||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C)2002 Tsudome Masatoshi. All Rights Reserved.