*例
失業者対策=雇用保険制度の失業給付は最長でも約1年であり、その期間が終了した後に収入が絶えたからといってすぐに補足性の原理を徹底させるのはかえって自立を困難にさせている特に若年層は失業給付の期間が短い。(最短90日)
補足性の原理を徹底させて公的扶助の入り口を狭くすることは、若年層の新しい産業へ の挑戦を遠ざけることにもなり、また不景気の中でいつ生活していくのが困難な状況に陥 るか分からない現代において、公的扶助のいわば“生活の保険”としての機能を果たしにくい状態にすることになる。
<改善案>
・原則、ストック(資産)ではなくフロー(収入)
→生活扶助基準により保護されるものは、日常の生活保護基盤にあたるフローの経費だけなのだから、これまでの生活を営むための基盤としての資産の保有は認めるべきである。
・保有限度ではなく生活基盤整備である
→売却しなくてもよい資産を列挙するのではなく、原則保有を認め処分を例外とする。
つまり社会通念からみて売却した方がよい資産の範囲を法定化し、列挙すべきである。
資産=生活基盤+社会通念上売却した方がよい資産
*生活基盤の具体例
現金:保護額の6か月分まで保有を認める。
現行は保護額の半分以下が限度であるが、保護額の半分になったらすぐに保護が開始されるわけではないのに半分の額では生活が不安定である。また、半年分の手持金を持っていた方が自立を促しやすく、自立した後の生活も安定する。
土地・家屋:原則認める。ローン付きのものについても1年間の立替えも可能とするが
立替えるかはケースワーカーとの話し合いによる。1年経っても自立の目 処が立たない場合は打ち切り、保護費からの返済も検討する。
ただし、現に使用されていないもので、著しく交換価植の高額なものはー旦保有を認め保護を開始してから賃貸、処分の途を検討。
事業用品:原則認める。ただし、将来全く利用予定のないものは処分の対象となる
車:原則認める。高級車などで買い換えた方がコストのかからない場合は買い替えを検討する。
その他の生活用品:生活に必要か、生活基盤を揺るがすものでないかという基準により
処分するか検討する。
Ⅱ 不当な保護廃止の抑制
|
増永訴訟 ●事実の概要・・・平成5年10月1日、生活保護を受給していた増永さんは、福祉事務所を訪れた帰途、担当ケースワーカーから自動車運転を目撃され、以前受けていた自動車の所有、借用及び仕事以外での使用を禁止する旨の指示に違反したとして平成5年11月1日をもって保護を廃止された。増永さんは体調の悪い娘を病院に連れて行くため、弟の車を借用して運転していたという事情があったにもかかわらず、福祉事務所はその事情を配慮することなく、保護廃止決定を行なった。これを不服として訴訟を提起した。 |
1.保護の廃止理由ⅰ)肯定的廃止…収入安定、傷病治癒など
〈資料7〉 ⅱ)被保護者の権利享受不能による廃止…死亡・失踪
ⅲ)不当な保護の廃止
2.不当な保護の廃止を可能とする現行制度の問題点
①行政の指導・指示に対する弁明の機会を徹底するシステムの欠如
②ケースワーカーの専門性を担保するシステムの欠如
3.行政の指導・指示に対する弁明の機会を徹底するシステムの構築
①行政の指導・指示に関する規定
■法27条 1項「被保護者に対して指導・指示ができる」
2項「指導・指示は被保護者の自由を尊重した最小限度のもの」
3項「指導・指示は強制できない」
■法62条 1項「指導・指示には従わなければならない」
3項「従わなければ、保護の変更・停止・廃止ができる」
4項「保護の変更・停止・廃止をする場合には、被保護者に弁明の機
会を与えなければならない」
法27条と62条との関係➡指導・指示は行政上の強制執行によって強制することはできないけれども、従うのが嫌だったら抜ければいいし、どっちみち従わなければ停止・廃止する。
②指導・指示による廃止への過程
◆法の形式的解釈 指導・指示➞拒否➞弁明➞変更・停止・廃止
◆実務(石川県のあるケースワーカーの例)
![]() 口頭指示➞口頭指示➞呼出(文書指示)➞呼出 ➞ 停止➞廃止
口頭指示➞口頭指示➞呼出(文書指示)➞呼出 ➞ 停止➞廃止
誓約書
![]() 法の解釈上、廃止処分への弁明はある。実務の一例はさらに指導・指示への弁明も行っている。
法の解釈上、廃止処分への弁明はある。実務の一例はさらに指導・指示への弁明も行っている。
③実務の一例を参考にした新しいシステムの提案
口頭指示➞口頭指示➞呼出(文書指示)➞呼出(文書指示)➞停止➞廃止
[弁明] [弁明]
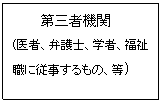
![]()
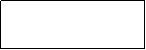
![]()
◆指導・指示から廃止に至る過程を手続きとして法定化
◆第三者機関の設置; 《介護保険について》
設置理由;本人だけでは行政に反論することができない。そこで、弁明の機会に第三者を参加させることにより、弁明の機会の客観性・公平性を確実にする。
4.ケースワーカーの専門性を担保するシステムの構築
①石川県のあるケースワーカーの話
現在の担当件数:80件 〈資料8〉
ケースワーカーの現状ⅰ)生活保護制度の知識がないまま、着任当初から何十件もケースを抱える。さらに、3~4年に1回異動があるために、専門性が備わらない。
ⅱ)形式的な研修はあるものの、新人育成という観点からみた研修はおこなわれていない。
②ケースワーカーの専門職化
●要件:社会福祉士の資格をもつ者または福祉職に従事した経験がある者
●新人研修
研修期間:着任から6ヶ月間
研修内容:生活保護制度の学習によりケースワークの基礎を身につけると共に、ベテランケースワーカーに付いて適切な対応の仕方を学び実践力を養う。