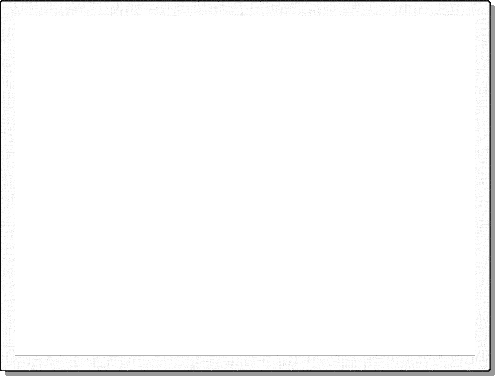講師:笹路 正徳(ささじ・まさのり)先生
| 第6回 2008年11月1日 「音楽プロデュースの変遷」 |
講師:笹路 正徳(ささじ・まさのり)先生
プロデューサー、アレンジャー、プレイヤー
4才の時からピアノを始め、小学生で「THE VENTURES」「THE BEATLES」等に憧れギターを手にする。中学時代は「CREAM」「JIMI
HENDRIX」に傾倒するが、高校入学後自分よりうまいギタリストに出逢いキーボードに回帰。慶応義塾大学在学中の1977年、「鈴木勲グループ」に参加しJAZZピアニストとしてプロ活動をスタートさせる。その後様々なグループで活動を続ける一方、コンポーザーやアレンジャーとしての活動も平行して行うようになる。
1979年、清水靖晃、土方隆行、山木秀夫と「MARIAH」を結成し、5枚のアルバムを発表する。それと並行し渡辺香津美の「KAZUMI
BAND」に参加、アレンジャーとしての活動が活発化する。1983年、「MARIAH」解散と同時に、土方隆行とロックバンド「NAZCA」を結成し、3枚のアルバムを発表する。この頃より、アレンジャー・プロデューサーとしての活動が注目され始め、以後「マリーン」「阿川泰子」
「ラウドネス」「チューブ」「ラフィンノーズ」「杉山清貴」「プリンセス プリンセス」「ユニコーン」「松田聖子」「THE YELLOW MONKEY」「スピッツ」「コブクロ」「小沼ようすけ」「南佳孝」「平川地一丁目」「HY」等数多くのアーティストを手掛けてきた。
また自身の活動も引き続きおこなっており1991年には、土方隆行、青山純、坂井紀雄と共に、ハードロックバンド「SASAJIE'S」を結成、ライヴバンドとしても好評を博す。2000年、しばらく遠ざかっていたJAZZのビッグバンドに挑戦し「M.Sasaji
& L.A.Allstars」をCD及びSACDでリリース。翌年にはそのセカンドアルバムをLiveレコーディングした。2003年には自身がプロデュースするインディーズレーベル“K's
TRACKS”を立ち上げ、「森山威男 & 杉本喜代志 / Battery's not included」「音川英二 ウィズ 森山威男 / 存在 New
& Old Wonder」の2枚を2003年8月27日全国同時発売した。2005年には伊東たけし、村田陽一、土方隆行、カルロス菅野、櫻井哲夫、則竹裕之からなる7人編成のBAND“CAST”を結成。東京・北海道でLiveを行った。2006年から森山直太朗のCDプロデュースを始める一方全国45都道府県Live
Tourの音楽監督を務めるなど今後も意欲的に活動していく予定。
「音楽プロデュースの変遷」
今日はプロデューサーの話ですが、僕は本当にレコーディングというか録音というのが好きでこういう仕事に就きました。人前でいろいろ演奏して目立ちたいとか拍手喝采を浴びたいというような欲求よりは、録音したいという欲求の方がもともと強かったので、何となく職人的なこういう仕事に就くようになってしまったのです。プロになって30年、かれこれ25年はレコーディングスタジオに入りびたりの生活なので、今日は何か工場見学のような感じで話を聞いていただければいいかなと思います。
1.プロデューサーとは何をする人か(録音物の話)
まずプロデューサーとは何をする人か。これが今日の一番重要な話ですのでお話したいと思います。先ほど反畑先生が昔はディレクターという人が全権を持って音楽をつくっていたと話されました。映画でいうとプロデューサーというのは、資金を調達して企画を立てて、どの監督にしようか、どういう脚本で誰に書かせようかということを決めると思います。そして現場監督というのはディレクターです。だから当時全権を握っていたプロデューサーというのも、そういう意味では映画に近かったのかもしれませんが、現在はプロデューサーというと、やはり映画に例えるならば監督、現場監督です。映画だと呼び名が逆になってしまいがちですが、ディレクターというのも権限を失ったというわけではなく、金銭面を管理したり、僕なんかは外部のプロデューサーという立場でレコード会社といろいろ話し合って、CDなどの録音作業をします。そういう意味で呼び名がちょっと逆になってきたような感じがします。
ではちょっとだけ古いことを話します。まず音楽というのは、1800年代とかもっと前、それこそベートーベンやモーツァルトなどの時代はライブ演奏しかなかった。けれどもその後レコーディング・録音物というのができたことで、演奏会場に行かなくてもいろんなところで聴けるようになり、音楽が世界的に普及しました。レコードの発明は音楽が普及するための画期的な出来事だったのです。エジソンが円筒型のものに録音することを発明しました。溝を掘って針のようなもので読んで音声信号にするという方式は別の人が考えたようですが、エジソンが実用化したのは1877年ごろです。
フルトヴェングラーという有名な指揮者がいました。ベルリン・フィルオーケストラの音楽監督で、1954年に亡くなりました。だから20世紀の前半に一番活動のピークであった人で、この人はレコーディングがものすごく大嫌いだったのです。
そのフルトヴェングラーの死後、次に有名なのはカラヤン。カラヤンは皆さんも知っていると思いますが、このカラヤンはものすごくレコーディングが好きだった。今でもレコーディングが嫌いなアーティストとすごく好きなアーティストがいるので、性格的なものかなと思っていたのですが、面白いことに大きな転機が1950年ぐらいにあるんです。1950年以前のフルトヴェングラーは録音嫌いで、そのあとのカラヤンは好きになった、この理由は何かというと、テープレコーダーの発達です。テープレコーダーに1回録音して、それからアナログのレコード盤を作るのですが、このテープレコーダーが1950年ごろから飛躍的に発達しました。音が良くなったのです。おそらくフルトヴェングラーは音が悪いからレコーディングというものが大嫌いだった。でもカラヤン以降になると、こんな良い音で記録されるのであれば、例えばミスがないテイクを選んだりできる。カラヤンは非常に完璧主義みたいなところがあるので、そういうものに飛びついたのだと思います。
それからその頃に似ているアーティストが2人います。まずグレン・グールドというピアニスト。カナダ人で1932年に生まれて82年に亡くなった、ものすごく個性的な演奏をするので有名な非常に格好いいピアニストです。このグレン・グールドは、64年ごろからコンサートを一切やらなくなりました。32歳からもうコンサートをやらなくなり、朝から晩まで録音をしていました。もう1人はビートルズです。ビートルズは業績の割には活動していた時期は意外と短くて7、8年で、これも1966年以降ライブ活動を中止しています。一切ライブ活動をやらなくなってレコーディングばかりになりました。
この2組のミュージシャンはものすごく録音というものに傾倒した珍しいアーティストだと思います。グレン・グールドの映像を見ると、彼の家にはテープレコーダーがあって、編集作業をしている場面もあります。自分で譜面にチェックをして、ここからここはテイク1、ここからここはテイクいくつというふうに自分で決める。そしてハサミを入れていってテープをつなげる。僕たちがレコーディングで歌手の歌を録るのと同じようなことを、グレン・グールドはピアノを弾いて自分でやっているんです。もちろんピアニストですから、あとで違う楽器を被せたりダビングするということはなく、テープレコーダーは2トラックのものでした。
だけどビートルズになると話が若干変わってきます。最初にレコーディングするときは4トラックとか8トラックで、それを最後に2つにまとめるのですが、トラックがいくつかあるのであとからいろんな音を被せることができる。でもライブではこのレコーディングのサウンドは実現できません。ビートルズがライブをやらなくなった大きな原因はここにあると思います。
このようにレコーディングにとても傾倒するアーティストが出てきて、そこからレコードを中心にして世界的に音楽が発展してきたのです。特にイギリス、アメリカを中心に、それも軽音楽界。軽音楽というのは本当にヒットしなければ意味がないような部分があるので、レコードが売れてからどういう活動をしようかとか、どうやって売れるものをつくるのだというふうに、音楽がマーケットと非常に関わるようになったのはレコードが出てきたからだと思います。
そこでプロデューサーというものが必要になってくるわけです。では話は戻って何をするかということですが、本来プロデューサーというのはアーティストの才能を引き出して、クオリティの高い作品をつくることが仕事です。もちろんコンサートやイベントのプロデュースもありますが、録音物に関するプロデュースという意味では、アーティストの才能を引き出して、なお且つクオリティの高い作品をつくる。しかもそれが売れる可能性の高いものでなければいけない。そういうことが何といっても一番重要な仕事です。だからこれらのことを見極めるセンスや経験などが必要になります。
皆さんの中には音楽を目指されている方もいるでしょう。1つ僕が思うことで才能ということについて考えてみたいと思います。ミュージシャンをやろうかなと思っていて、「あなたは才能があるんですか?」と聞かれたときに、「才能があるんですかと言われても、ないような、あるような…」と大概の人は思うのではないでしょうか。僕は才能がありますと言い切ってしまう人もいるかもしれませんが、内心どうかなあ…みたいな感じで、「譜面もあまり読むのは好きじゃないし、音大に行ってる人とかはもっといろんなことを知ってるし…」というような思いもあるかもしれない。僕もアーティストの才能を見極めないといけないので、才能というのはどういうことかといろいろ考えて、いま思っていることは、人間の才能とは才能という1つの塊をポンと持っているか持っていないかではないということ。もちろん口で項目を付けるようなものではないのですが、100項目、1,000項目あるとすると、それの33番目は89点とか、45番目は22点とかそんなようなものがいろいろデコボコしていて、まとめて何点かというものがその人のポテンシャルだと思うんです。だから音楽的に限っても、音楽を志そうなんて人は何か人に比べて音楽的にすごく優れている点、誰にも負けない点というのがある。だけどやっぱりプロの水準に比べると水準以下の要素だとかそういうものもある。
プロデューサーとしては、だいたい才能の高いところは放っておいていいんです。やはり人間というのはセンスのあるところというのは楽しいから、放っておいてもやる。けれどもここはちょっと底上げした方がいいなという要素は、何となくやるのは楽しくない。だからそういうところをプロデューサーは底上げしなければいけない。そして総合点の高い才能・タレントというものをつくることがすごく重要なセンスだと思います。
だから皆さんも「自分を知ること」というのは、音楽のみならず何でもやる上では重要なことだと思います。それからもっと言えば、音楽というのはやはり最終的には個性が出てこないと意味がないものです。例えば作品をつくるのでも、この人の個性をどうやって反映するのか、では個性はどうやって出るか。これは一言でいうと、自分ができないことの隣にあるのです。個性というのは自分のできないことの隣にある。できるところに個性があるように思いがちですが、実はそうではなくて、できないところの隣に個性というのはあるんです。
僕が好きなモーリス・ラベルというフランスの19世紀末の作曲家は、なにしろモーツァルトはすごいと言う。それで自分が書いている音楽はモーツァルトとは似ても似つかない音楽をやっている。それからジャズでは、ナンバーワンの巨匠のマイルス・デイヴィスというトランペッター。もう亡くなっていますが、さらにその前にデイズイカレスピーというすごいテクニックの天才的トランペッターがいて、まずそういうふうに吹けなかったからマイルス・デイヴィスは自分のサウンドというのをつくった。だから、何かができないから新しいものを生む、それの繰り返しなんですね。芸術というのはそういうもので、絵画であってもどんな巨匠でも若い頃の時代というのは誰か風であったり、そういう絵を描いているが、だんだん余分なものを削ぎ落として自分なりのエッセンスが残ってくると、やっぱり自分のスタイルというものを確立するようになってきます。というのは、やはり自分ができないこと、不器用なところを大切にした人間が、それをうまい具合に利用して個性を出していると言えると思います。
例えば、小学校での運動会で順位をつけない学校もあるという話を聞きますが、言ってみれば走るのが遅いのだって重要な個性。だからそういうのを大切にする、その視点がプロデューサーとしては非常に大切だと思います。僕がやっていたスピッツというバンドも、そういうところが何しろ長けているバンドでした。自分たちは演奏があまり上手ではないというような、B級意識というか一流のミュージシャンではないという意識がある。じゃあ何ができるだろうかという意味で、すごくバンドとしてのいろんなバランスがいいし、そうするといい作品を生む。だからいろんなことにバランスを取るということ、そういうアーティストのイメージをすることがプロデューサーの視点としては重要だと思います。
そのほかにプロデューサーは何をするかと言うと、レコーディングに入る前の作品管理や、レコーディングのときには細かい現場監督です。OKかOKでないかNGか、どうやって歌えとか、そういうふうに歌わない方がいいのではないかとか、そういうことを万事にわたって歌手に指示します。そしてレコーディングをしていいテイクを録音して、さらにミックスダウンやマスタリングを経て、工場に送るマスターを作るまでがサウンドプロデューサーの仕事です。
ですからプロデューサーに要求される能力とは、やはりリーダーシップです。それとその時点その時点での的確な早い判断、さらには作業上においての問題点の発見。そういうことの能力が要求されます。音楽をつくっている途中というのは、枝分かれの瞬間がいっぱいあります。これはこっちだろうか、こっちだろうか…。これが違う方向に行ってしまうとレコードは失敗する。だから最終的なことなどを総合的に判断して正しい道筋に行くということ、これが重要です。
昔ドラム合戦という、4人ぐらいドラマーが出てきてそれぞれ順番にソロで演奏し、そして誰が勝ったか競争することが流行った時代がありました。これで勝つのはだいたい手が多く動いて音が大きくて派手なことをやるドラマーが、あいつはすごいなという判断になって勝ちました。でも僕が言いたいのは、ドラム合戦で勝つタイプが適切なプレーなのか、いいミュージシャンなのだろうかということです。つまりレコーディングになると、一番適切なプレーのそれ以上のことをやらないで、必要なことはしっかりやるというのがいいプレーであったりします。だからちょっと見たところ派手であったりそういうことに惑わされないで、正しいプレー、正しい方向性を示すというのが大事なことです。
選択肢が2つあって、こっちに行こうといった場合に、こっち対こっちのどちらがいいかという割合が100対0ということはありません。こっちの要素から見たらこっちがいいし、こっちの要素から見たらこっちがいいし…というようなことは、皆さんも生活の中でいろいろあるでしょう。どちらを買おうかなとか。そうすると51対49であった場合、当然総合点が高い51点の方を選ばなければいけません。だからそちらに行くのですが、51の方向に行こうと決めた途端に49の方を見てしまう。やっぱりあっちの方がいいんじゃないかと。それはそうです、49はこちらの方が優れているのだから。だけどそこでしっかり49というのを捨てなければいけない。そちらの方向に行ってしまうと道筋を間違ったということになります。だから総合点の高い方向に行くということが一番のポイントです。
2.日本と欧米における音楽の在り方の違い(グラミー賞とレコード大賞)
次に日本と欧米における音楽の在り方の違いについてお話します。グラミー賞は日本でもテレビ中継をしていますが、詳細についてはそんなにご存知ないかもしれません。日本レコード大賞はもちろん知ってますよね。ちょっと比べてみました。
レコード大賞は1959年に発足しました。グラミー賞はいわゆるアメリカの音楽に対する年間の賞で、発足したのは1958年です。だからレコード大賞はその次の年、グラミー賞をヒントにして発足しました。先ほど反畑先生から伺ったのですが、58年に古賀政男さんや服部良一さんがアメリカに赴いてグラミー賞を見て、日本でもこのような賞を設けて音楽振興をしなければいけないのではないかと思って、もうその次の年からレコード大賞を開催したということです。
第1回にレコード大賞を取った水原弘が泣きながらステージで歌った映像を、僕は子ども心に覚えています。テレビ中継は3、4年後からだったそうですので数年後に映したのでしょうけれど、その『黒い花びら』という曲は子どもでも歌っていました。そのほうの女の方が捨てられたみたいな話ですが、それを子どもが歌っているんです。「♪あの人は帰らない」と歌っていた時代でした。だからその頃はアメリカに追いつけというような感じで発足したのでしょうか。
では2007年のレコード大賞の受賞者を見てみましょう。大賞はコブクロが取っています。そして最優秀歌唱賞、これは金賞に選ばれた作品の中から選ばれるもので、EXILE。そして金賞に選ばれたのが倖田來未や川中美幸など10作品。そして作曲賞、作詩賞、新人賞。それから特別賞、企画賞。企画賞というのは音楽的な企画に対するもので、そういう意味ではCDが売れなければ賞は取れないということでもない。編曲賞はここにも来た亀田さんが取っています。このレコード大賞の賞の部門は、初年度は6部門で、今は13部門です。
次にグラミー賞を見てみましょう。部門はとても多くて、当初は25部門だったのが、現在は110部門だそうです。Record Of The YearがAmy Winehouseで、2007年はこのAmy
Winehouseが総なめしたという印象です。そしてAlbum Of The Year、Song Of The Yearなど、この辺はレコード大賞にも似たようなものがあります。さらにはBest
Pop Vocal PerformanceとかBest Pop Instrumental Performance、それからInstrumental Album、Rock
Vocal、そしてHard Rock…と続いて、R&Bが出てきて、Princeが取っています。それからContemporary R&Bというのがまた別になっていて、Ne-Yoが取っています。Countryというのも出てきます。Country
& Westernというとテンガロンハットを被って演奏しているイメージが強い、あのカントリー音楽。Bluegrass というのはカントリーですが、また別の部門になっています。それからNew
Age、Contemporary Jazz Vocal…とジャンルが多岐にわたり、Gospelでも、Rock Or Rap GospelやPop/Contemporary
Gospel…と分かれています。ゴスペルというと教会で黒人の方を中心に大きな人たちが歌っているようなイメージですが、いろんなゴスペルがあるようです。それからBest
Latin Pop、Latin Urban Albumとか、Polka。ポルカというのは僕たちはあまりよく知りませんし、クラシック音楽でのジャンルのような感覚ですが、今でもポップスでポルカのアルバムが毎年出ているのでポルカというジャンルもある。
このぐらいにしておきますが、要するに日本では、演歌はちょっと別にして、ヒットというのが割と一本線のような感じがあります。だから今はR&Bだといえば、よしR&Bのアーティストを発掘して出そう、R&Bが売れるのだと。もう少し前では、バンドだといえばバンドばかりいっぱい出てくる。そういうふうにちょっとブームというか、流行というか、ヒットするのが似たような傾向の一本線です。しかしアメリカやイギリスでは、いろんなジャンルがそれぞれ独立してしっかりと根ざしているので、その中でしっかりとアーティストは活動できる。だからR&Bがブームだからとロックの人間がR&Bみたいな音楽をやり始めることはない。ハードロックはハードロックでしっかりあるし、R&Bはあるし、ポルカだってある。だから文化的に考えて、やはり成熟度という意味では、日本はもっと成熟して、いろんな音楽がジャンル的に捉えてもそれぞれ成り立って活動ができるようになるといいなと思います。
もちろんアメリカなどはポップスの歴史が長いという違いはあります。日本はいわゆる歌謡曲といわれるものが昔は売れる音楽であって、シンガー・ソングライターみたいなものが出てきてニューミュージックと呼ばれたようなそういう音楽を若者が買うようになったのはここ数十年、30年か40年ぐらいの話ですから、アメリカに比べると歴史はまだないと思います。それからマーケットの広さ。アメリカでは南部では南部の音楽をやっているし、東海岸、西海岸でもそれぞれ音楽のテイストというのは違います。ラップだとニューヨークあたり、LAだとハードロックをまだしっかりやっている。そのようなマーケットの広さがあることと、人種の多様性ということもあります。黒人の音楽がしっかりあるし、ラテン民族の音楽だってあるのです。そういう意味では、日本人としての音楽というのがない。でもないのも無理はなくて、日本のポップスの話に戻ると、日本は欧米から来た音楽をやってポップスというのをやっているわけです。だから日本で生まれたものではなくて、日本人としていかに洋楽をやるかというふうに思って間違いはないと思いますが、アメリカの真似をしているうちは、やはり成熟した作品はできません。
これは何でも同じで、例えば自動車も昔はどこの国の何とかという車にそっくりでした。だから日本人というのはゼロから生み出すということはあまりうまくないのかもしれませんが、海外の優れたものを取り入れて日本流にアレンジするということがうまい。だから音楽でも、何とかに似ているというのが褒め言葉だった時代がありました。「和製プレスリー」とか。「すごいね、何とかにそっくりだね」みたいなことを言って、似ていればそれでOKだった。もう似てたら最高。似ているだけで日本のトップになれた時代です。30年ぐらい前、20年ぐらい前まではそうでした。
しかしそこで、やはりそれではいけないと。自分たちなりのものをつくろうとしたのは、ある意味シンガー・ソングライターとかそういう人たちであったかもしれません。日本人なりの洋楽をやろうというふうに思った。だからといって日本語を英語みたいに発音して何を言ってるのか分からなくなってしまったということではないと思うのですが、そういう芸風の人もいます。
武満徹さんも生前、日本人としていかにヨーロッパの音楽をやるかと言っていました。だから琵琶を入れたり尺八を入れて、ヨーロッパの音楽を日本人なりにやった。日本の楽器を入れれば日本的かということでもないのですが、やはり海外から来たものを日本人なりにどうやるかということはポイントで、これが軽音楽をやる上での一番のポイントです。活動を長く続けられるミュージシャンは、そういう問題意識がすごくあると思います。ただ売れるものをつくろうというのではなくて、自分なりの洋楽をどのようにやるか、どのように表現していくかということを意識している。でも日本では、「流行」と「時代性」が混ざってしまうという難しさがあります。
3.有名プロデューサーの仕事ぶり
では次にプロデューサーにどんな人がいるかというお話をします。まずはジョージ・マーティン。ビートルズのプロデューサーです。この人は何をしたか。要するにジョージ・マーティンだけでビートルズというバンドがつくれたかというと、そんなことはなく、やはりあの4人がすごくて、そしてそこにジョージ・マーティンというプロデューサーが合体して、すばらしい作品を生み出したのです。ビートルズのすごさは、芸術性と大衆性のバランスというのが半分半分だと言っていいと思います。芸術と大衆性の両方を同時に実現した数少ない成功例です。だからビートルズみたいな成功例があるからその後ポップスはいろいろできる。売れるだけではなく、自分の表現をすることもできる。だから60年代にこういう成功例があったというのは非常に世界的な財産で、今でもビートルズ、ビートルズと言われる理由だと思います。
そのほかジョージ・マーティンの仕事ぶりとしては実験的な音づくり。『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』というアルバムがあります。これは20世紀最高のアルバムだと言われているのでぜひ聴いてください。ジョージ・マーティンはもともとエンジニア(録音技師)なので、そういうノウハウが非常にあった。しかもマルチトラックになってきて、レコーディングが4つあるいは8つのトラックになり、サージェントペパーズのときは8チャンネルだったという話ですが、8つのトラックにいろんな音が重ねられた。それでジョージ・マーティンは逆回転の音を入れてしまったりするんです。シンバルをジャ~ンと叩いて、それをひっくり返して「シャッ」という音を入れる。今では市民権を得た音なのでどこかで聞いたことがあると思いますが、そういうのをやり始めたのがジョージ・マーティンです。そんなふうにいろんな実験的なことをやり始めて、そこですばらしい楽曲と実験的な音というのが相乗効果になって、非常にメリハリのついたすごく作品力の高い作品を生み出しました。
それからこの人は楽器の演奏もできてチェンバロを弾いたり、アレンジの素養もありました。『The Beatles Anthology』というアルバムが出ていて、元々はこういう録音で重ねるとこうなったみたいな作る過程のCDが出ていますから、興味があれば聴いてみてください。
次にアルフレッド・ライオン。ジャズのプロデューサーで、ブルー・ノートという有名なジャズのレコード会社を立ち上げた人です。つまり外部プロデューサーではなくて社長そのもの。だから全権を持っていて、資金繰りから何から何まで全部自分で決めている。そのブルー・ノートには、ブルー・ノートのサウンド、ブルー・ノートっぽい音というものがあるんです。いろんな違う人が演奏しているのに、ブルー・ノートの音がする。ではなぜ「ブルー・ノートの音」があるのか。
ルディ・ヴァン・ゲルダーという世界的に有名なエンジニアがブルー・ノートのほとんどの音を録音しています。彼は他のレコード会社でも録音していますが、ブルー・ノートの音とは全然違うのです。つまりブルー・ノートの音というのはルディ・ヴァン・ゲルダーの音ではなく、アルフレッド・ライオンの音なんです。だからプロデューサーというのがものすごく録音に関しても指示をしていたということが分かるわけです。
そしてブルー・ノートのレコードのもう1つの特徴は、ジャケットがすごくいい。写真からデザインのレイアウトまですごくいいんです。だからアルフレッド・ライオンというのは、ジャケットからサウンド、そしてもちろん内容までをパッケージングとしてつくりあげた最初の人なのではないかと思います。
レコーディングではスタジオにメンバーを集めて、しかもほとんどがコンボバンドなので多くて6、7人で、いきなり「せえの!」で演奏します。1日に5、6曲録るので、1日か2日ぐらいでアルバムが1枚できてしまう。だからすごく低予算でできて、低予算である分パッケージングとして優れたものをつくって、しかも内容的にも優れているという意味ではとても優れたプロデューサーであったと思います。
あとはCTIのクリード・テーラー。この人はジャズにオーケストラを入れたり大きな演奏をいっぱいやりました。ストリングスを入れたりビッグバンドを入れたり。そしてすごくポップなジャズのレコードを世界的にヒットさせました。でもオーケストラやビッグバンドを入れるには、譜面を書くアレンジャーが必要です。そのアレンジャーの起用が、いい作品を生んだ要因だったと思います。ドン・セベスキーとかクラウス・オーガマンという有名なアレンジャーを起用して作品をつくっていった。
それはいいのですが、クリード・テーラーはとてもシャイだったらしいのです。先ほどプロデューサーというのはリーダーシップを発揮しなければいけないと言いましたが、彼は何かしてくれという要求を現場で言えなくて、エンジニアを呼んで「ちょっとこれ、悪いけれどベースの奴に言ってくれないか」と言ってたらしい。だからそういう人間でもそれなりの自分のやり方でプロデューサーができるということ。つまりリーダーシップをとるような人間が適するような仕事でもこのようなこともあるので、この人こそ先ほど言ったように自分のできないことを個性に変えたのかもしれません。
それからクインシー・ジョーンズ。これは黒人のプロデューサーとして有名で、アメリカのちょっと前のポップス界のドンみたいになっていました。もともとアレンジャーで、その前はトランペッターでしたがトランペッターとしてはあまり活動せずに、譜面を書いてビッグバンドのアレンジャーとして有名になった人ですが、プロデューサーになってからはアレンジャーをやらなくなりました。アレンジャーでありながら他のアレンジャーを起用して作品を全部やっていくので、野球でいえばゼネラル・マネージャーみたいな人です。この人の作品で一番有名なのがマイケル・ジャクソンの『スリラー』です。自分の作品でもなかなか優れたものを何枚も出していますし、それからアメリカ中の新旧の大歌手ばかりを集めてチャリティーをしました。『We Are The World』を全員で歌わせたというのは有名です。これは映像にもなっていますが、非常にアメリカ的なものです。
これを機会にジャズとかクラシックを聴いてみるといいですよ。やはりジャズとクラシックというのは、音楽のスタイルとして一番成熟したところまでいっています。そして崩壊していますから。クラシックは現代音楽みたいになって、ジャズはフリー・ジャズみたいになったり、山下洋輔さんみたいな人がいるでしょう。だから崩壊前夜までしっかりいっています。方法論から作品のスタイルにおいても。ぜひジャズ、クラシックを聴いて、大人になってジャズクラブへ行ったら素敵ですし、たまにクラシックコンサートに行くのもいいと思うので、興味があったらぜひ聴いてください。
4.機材と音楽の関係とプロデューサーの変遷
では次に、機材と音楽の関係、そしてそれによりプロデュースがどのように変わってきたかお話しします。先ほどフルトヴェングラーとカラヤンの違いや、ビートルズの実験的な音づくりの話をしました。だから録音する機械が変わると、音楽も変わってきてしまうということです。
これは別に不健全なことではないと思います。昔はジャズでも一発録音でしたが、今では「すいません、ちょっとギターだけ間違えちゃったので直させてください」と言って、ギターの部分だけを編集して直すことができます。でも当時は、“テープ編集の妙”というのをプロデューサーができるかできないかが重要なことでした。マイルス・デイヴィスのプロデューサーであったテオ・マセロは、マイルス・デイヴィスの音楽でハサミを入れてないものはほとんどないと言っています。
アナログ盤のレコードは片面20分ぐらいです。入れようとすれば30分ぐらい入りますが、そうすると溝が細かくなって音が小さくなったり低音が出なくなるので、だいたい20分に抑えます。しかしジャズの演奏者は収録時間を考えて演奏はしないので、長い演奏をすると入りきらなくなる。だからテープ編集をして要らないところを捨ててしまいます。しかもつながるような編集をしなければいけない。だからそういうテープ編集というのが重要です。僕も学生の頃は、そういうのを聴いてもどこでハサミを入れているのかなど分かりませんでしたが、大人になってこの仕事に就いたからかなり分かるようになりました。
それからいわゆるマルチチャンネルの時代になりました。昔のステレオの2チャンネルの時代では、オーケストラなどは全員一同に広い部屋に集まって演奏しました。でもマルチトラックになってからは、まずドラムとベースとピアノとギターだけ入れて、あとでストリングスを入れたり、歌を入れたりとか、違う日に違う場所でもレコーディングができるようになったのです。
ビートルズの『Strawberry
Fields Forever』という曲は、まずビートルズが最初に演奏しているのですが、そのあとにストリングスカルテットをダビングして、さらにあとでジョージ・マーティンがビートルズのリズムの音を全部抜いてしまっています。あったものをなくしてしまい、ほとんど歌とストリングスだけになっている。そういうこともできるようになったのはマルチトラックになってからです。
その後いよいよデジタル化します。まずCDというのができました。音楽がデジタル化する試みというのはかなり前からありましたが、CDになって決定的に聴く音というのがデジタルになった。もちろん最後はスピーカーが振動して空気の振動で音が出るということでアナログですが、レコードプレーヤーからデジタルのCDになったというのは大きな変化でした。
ただ、CDというのは当初はものすごく音が悪かったのです。いま考えるとデジタル技術というのが進んでいなかったからです。もう1つ、音の大きさみたいなものを16桁の符号で表す16ビットタイナミックレンジ。それから低い音から高い音までの周波数レンジというのを、1秒間を44,000分割してグラフでサンプリングするという
PCM方式、それがCDなのです。ゲーム機だと例えば24ビットだったのが64になったりして、次世代機が出るとどんどん買い替えられるものなのでデジタルが進んでいきます。けれどもCDというのはプレーヤーをいちいち買い替えられないでしょう。そんなに安いものでもないし。だからフォーマットCDとして規格を決めてしまったら今日まで変わっていない。今のデジタルの世の中から見るともう化石のようなデジタルのものなのです。16ビットのものをいま聴いているということは。思い起こせば、ソニーとフィリップスが共同開発して作ったのですが、若干時期尚早ではありました。だから当初のCDの音が悪かったというのは、いま思えば平面的だったり、すごく冷たかったり、温度感が低かったりするのですが、これは情報量が欠落していたのです。つまりアナログをデジタルにするときにものすごく情報が減っていた、記録されなかったということがあったからです。でも技術の進歩によってCDの音は極限まで搾り取るぐらいまで良くなりました。ただ、音色(おんしょく)が良くなるかどうかということではもう限界です。そこは限界が来ていると思います。
プロの現場でもテープレコーダーはずっとアナログでありましたが、1970年代から80年代ぐらいになるとデジタル化されて、そして今やハードディスク時代になりました。ほとんど音楽制作というのはハードディスクやパソコンで録音して編集しています。ですから昔のデジタルのテープレコーダーの時代は最大48チャンネルまで使えたのですが、ハードディスクの時代になってチャンネルという概念は無制限で、いくらでも使える。もちろん最終的に全部同時に音が出せるかという問題はありますが、チャンネルでは無制限。
それから面白いのは、僕が30年前にプロになった頃は、16チャンネルのテープレコーダーでした。それが24チャンネルになりましたが、24チャンネルでも最後に歌手が歌を入れるとなると、そんなにチャンネルが残っていないので3チャンネルぐらいしか歌は歌えません。だから3つ歌ってもう1回歌いたいとなると、どこかを消さなければいけない。だから昔の人は歌がうまくなるわけです。
その後 48チャンネルになって6本か7本ぐらい歌を録って、いいところを編集するようになりました。そして今に至ってはいくらでも歌が録れます。しかもいろんなエディット機能というのが出てきて編集ができます。例えば昔であれば「アタックがある・かきくけこ」とか「たちつてと」とか、「さしすせそ」みたいに「S」が前から出るところはタイミングが合うので編集しやすい。でも「あ」とか「あいう」みたいに母音がつながるとアタックがないので、そういう持続した部分は編集がしにくくて、テープレコーダーの時代はほとんど編集できませんでした。けれどもそういうところでもつながりやすくなってきた。しかもピッチも直せるソフトがあるので、歌が下手でも歌手になれるような時代になってきました。全くそういうことはないのですが、そんなことまでできるようになったというわけです。
5.プロデュースの実践及びエピソード
あとは実践的なことをお話ししたいと思います。まずレコーディングが進むにあたってプロデューサーの重要なポイントは、理想的なサウンドが出ているかどうかということです。これが一番重要なことです。サウンドというのを音色という意味だけではなくて、その瞬間のサウンドも、全体のイメージのサウンドもあるでしょう、そのサウンドに身を委ねることができる場所で思い描いたサウンドになっているかどうかということです。演奏がうまくいっているかどうか、ミスがないかどうかということよりも、サウンドの方がプライオリティとしては上だと思っていいと思います。
聴く人というのは、この曲が好きだというような判断を、どこかで判断します。イントロから始まって1拍で「よし、この曲を買おうという」人はいないでしょうが、歌が始まって1フレーズ、2フレーズで、「ああ、これはいいと」OKを出す人がいるかもしれない。例えばビートルズの『Yesterday』を「Yesterday,
oh my trouble seems so…」で、「あっ、買っちゃおう」と。あるいは1番のサビに行ったとき、「あっこれはいい作品だ」と。でも1番では思わなくて、2番のところで「ああこれはいいなあ」というふうに思うかもしれない。あるいは聴き終わったときに「よし、マル」と出すかもしれないし、次の日に出すかもしれない。何かよかったなあ…と。それはイメージを持ち帰って自分で反芻しているからです。あとは3回、4回聴いて、「よし、マル」というふうに出す。要するにリスナーというのは、どこかでこの曲が好きだ、自分に対してマルだと判断することがあります。だからいろんな人がいるにせよ、プロデューサーというのはこの曲はここでこういうふうな心持ちにさせたいという青写真・設計図を描く必要があるんです。これがヒットするという意味、多くの支持を得るという意味では、結構大事なことだと思います。
音楽の展開というのは時間芸術ですから、途中から聴くというようなへそ曲がりな人もいるかもしれませんが、だいたいは最初から最後まで聴くものです。そうすると聴いている人は、「ここでこの楽器がこのように聴こえてこういう展開になって…」という心持ちになる。だからそのような展開をしっかり感じさせるように曲に出ているかどうかが重要なポイントです。
では、どういうふうにして聴いている人がそのように思うか。アレンジの際などに一番重要なことなので覚えておいて欲しいのですが、それは「フォーカス」ということです。フォーカス=焦点です。例えばこういう曲があるとします。ドラムから出てきた→ベースが入ってきた→ギターとピアノが入ってきた→歌が入ってきた、このような順番で楽器が出てくる曲があるとします。ドラムから出てきたときは、フォーカスは100パーセントドラムにいきます。ドラム以外聴くものはないから。そしてベースが出てくると、人間は新しいものに耳がいくので、ベースに60、ドラムに40、あるいはベースに70、ドラムに30というふうになります。ギターとピアノが出てくると、ギターとピアノに50から60、そして全体を聴き出す。ドラムは20ぐらいになって、ベースも20とか30になる。歌が出てくると、歌というのは主旋律なので、歌って声が出ているときはずっと一番のフォーカスを取り続ける。だから歌で60、70になり、ピアノに10か20、ドラムに5、ベースに5というふうになる。けれども歌がここで3拍空いて、そこに他の楽器がメロディーをやれば、フォーカスは一気にそちらにいきます。そしてドラムがサビにいく前に格好よくやれば、ドラムにフォーカスがパッといく。そうすると、どこのどういう楽器に何パーセント耳がいくか、どこにフォーカスがあるかということが音楽の展開を生みます。だからちゃんとしたつくりができるかというのは、このフォーカスによるものです。
オーケストラでは指揮者が、「そこの楽器、強く」とか「ここではトランペットがうるさいから、ちょっと弱く吹け」と、フォーカスを調整しているのです。だから指揮者やオーケストラによって、演奏や表現にとても違いが出る。
よくレコーディングで歌手の歌入れをすると、実力のある人ほどテイク1がいいんです。演奏でもそうで、一発目はいい。なぜかというと、自分が聴いているフォーカスが正しいからです。でも人間はどうしてもちゃんと歌おう、ちゃんと演奏しようと思うと、自分の出している楽器の音、自分が歌っている声にフォーカスがどんどん多くなる。一番正しいときには、自分の声に50から60のフォーカスがあったとします。でもちゃんと歌おう、音程を取ろうと思うと、自分の声に60、70、80とどんどんフォーカスが多くなって、それで正しくなくなってくる。そうすると音程は良くなってもダイナミックスが崩れ、表現が崩れ、抑揚がなくなってくる。そうするとそれはいいテイクではありません。だからやっぱりテイク1というのが一番正しい聴き方です。
だから僕がよくアドバイスするのは、もっと楽器を聴こうと。自分の声はあまり聴かなくていいと。レコーディングに使うヘッドホンでは音のバランスを調整できるので、自分の声だけを上げたりすることもできます。だけど自分の声を必要以上に大きくしてしまうと、まず歌は悪くなり、ピッチも悪くなります。よく聞こえるからピッチが良くなるように思うかもしれませんが、歌の上手な人というのは自分の声は必ず小さいんです。そして体から来る骨伝導や体のバランスで音程を取る方法がどうやら音程の良い人の音程の取り方のようです。だから何回やっても、正しいバランス・正しいフォーカスで耳で聴いて体感して演奏する、歌う、というのがいいテイクを生み出す秘けつです。先ほど言ったように、このようなサウンドのダイナミックスというのが一番大事です。
それからあとは、マルチチャンネルでレコーディングすると、ミックスダウンをしなければいけません。これは要するに、昔であれば48ですが、何十個も録った音を2チャンネルにまとめる作業です。家庭であればスピーカーは右と左なので、2チャンネルにまとめる必要があります。最近では5.1チャンネルもあるので、5、6チャンネルに振り分けるのですが、これが非常に重要になります。そのときでもやはりフォーカスが正しいか、サウンドがちゃんと出ているかということが一番大事で、エンジニアの力はすごく大きい。
今はハードディスクの時代になって、自宅のレコーディング機材がスタジオと変わらなくなっています。昔であれば数千万円から1億、2億という値段だったので、お金持ちで山下達郎みたいな人は持っていましたが、そういうことはなかなか叶うものではないので、レコーディングはレコーディングスタジオでするものでした。でも今は100万円前後で同じような機材が揃ってしまう時代になりました。今の新しいプロデューサーというのは自宅で音をつくって編集もできて、そしてスタジオでやらなければいけない作業はそこにファイルごと持っていけば同じ作業ができる。だからプロデューサーがエンジニアのような仕事も自分でやるようになっています。
でもここには危険性もあります。エンジニアの仕事とは完全に専門職なので、プロデューサーがいくら機械の使い方が分かっていても、やはりエンジニアにしかできないことがあると思います。自宅とかそういうハードディスクを多用してやるプロデュースというのは、何しろ打率を高くすることが必要です。自宅録音というのは変わったことがやりやすいので、ホームランを打つような個性的な音はつくりやすいですが、いつもいつもクオリティの高いことをやるというのが難しい。だからやはりエンジニアというのはこれからもなくならないし、非常に重要な仕事です。
最後にマスタリングという工程があります。マスタリングエンジニアというのは、アナログからCDへデジタル化するには、補正しなければ元のものと同じようにならないという意味合いがありました。現在では、マスタリングエンジニアによって変わるのならそこでもっと音を良くしてしまおうということです。マスタリングエンジニアの新たな客観性というのが入るので、ここ10数年はマスタリングエンジニアがいい作品をつくるポイントになり、非常に脚光を浴びてきました。
―以下、質疑応答―
Q.バンドをしていて、オリジナリティを出すためにどういうことが必要かいつも考える。ライブで生演奏をするときのアドバイスをききたい。
A.まずオリジナリティというのは自ずと出てくるもの。だから先ほど言ったように、それぞれの問題意識の中で音楽をやるということしかない。それから人の真似をしないこと、何か変わったことをやってやろうというのはいつも懐に持っていないといけない。ただ、それが不自然になったり無理やりやっているようになるといけないので、やっぱりしっかりと根拠のある変わったことであれば素敵だなと思う。
ライブパフォーマンスを最近見ていると、必ず手を回さなければいけないとかジャンプしなければいけないとか…そういうものでもないと思う。何か佇まいとして非常に個性的な、自分たちなりの方法を一生懸命考えるのもいい。例えば照明1つにしても何となくやってしまわないで。でもやはり音楽をしっかりやることが重要。レコーディングの場合だと、やっぱり細かいことに終始している。なぜ細かいことをやるかというと、細かいことをちゃんとするというのは、でき上がったときにじわじわと効いてくるから。細かいことをないがしろにしていると、最後にはつまんないものができてしまう。だから細かいところをしっかりとやることが意外と早道。あとは先ほど言ったように自分がやりたくないことに努力することが大事。
Q.作品を生み出すときは、考えて考えて生み出すのか、または「天から降ってくる」のか。
A.亀田さんは考えて考えて…と言っていたらしいが、僕は両方。ずっと考える。これは具体的なことは一切考えずにずっとモヤモヤしていて、そのモヤモヤしているというのはおそらくイメージを固めている。だからそこに時間をかけて何時間もモヤモヤしている。そしてモヤモヤが一段落して具体的なことを考えると、すぐ5分でできてしまうこともあり、そのときは天から降ってくる感じ。だから両方。
作品をつくる人間にも「モヤモヤしてイメージをつくることに一番時間をかけろ」とよく言う。そこが一番重要な過程だから。いきなり楽器を鳴らす、いきなり具体的なことをやる、というのはいきなり最後のところに行ってしまい、一番重要なところを飛び越してしまうので、それでは個性的な作品は生まれないような気がする。
Q.ミュージシャンとしてヒットする人材の見極め方は。
A.3つある。①その人間に音楽のポテンシャルがあること。音感がいいかどうか、歌がうまいかどうか。②考える人間かということ。先ほど言ったようにできないことを個性に変えたり、自分がやったことを客観的に見ることができるか。これが達成できたら次はどういうことをやってみようかとか、そういうふうに考えられるか。またはどういう活動を自分でイメージできるかということも含めて。③やはり人を引き付ける雰囲気を持っているかどうかということ。容姿も含めて何か魅力的な佇まいを持っているかどうかというのが重要だと思う。
Q.学生時代に経験しておいてよかったと思うことは。
A.その年齢に応じた経験をしっかりすること。まず僕がいま音楽をやっている上でよかったなと思うのは、受験勉強。受験勉強をしたことで、物事を考える考え方がそのとき分かった。だから受験勉強をしたことがいま音楽をする上ですごく生きていると思う。あとは運転免許を取りに行ったときのこと。なぜかというと、車庫入れをするときに後ろを振り返って、「この角がドアのヒンジのところに来たときに、ハンドルをいっぱい切れ」と習ったそのときに、音楽はこういうふうにやった方がいいとピンときたから。もともとはモヤモヤしたイメージ・フィーリングだけで音楽をやっていたが、こういうふうにする方が自分のフィーリングを生かせると思った。だから非常に数学的に音楽をやるということにピンときて、そのときから僕は音楽のやり方が変わった。そういうふうに数学的にやり出したというのがとても印象に残っているので、受験勉強と運転免許。
以上