講師:斉藤正明(さいとう・まさあき)氏
1947年生まれ。中央大学法学部卒業。
1970年、東芝EMI株式会社入社。洋楽制作本部長、EMI本部長、Virgin本部長などを経て、1997年に代表取締役社長に就任。
2005年には代表取締役会長兼CEOに就任。
会長退任後、2006年、株式会社M-siteを設立、M-site代表取締約社長就任。
そのほか、㈱ジャパン・ディストリビューションシステム 代表取締役会長、㈱日本レコード普及 取締役会長なども務める。
「世界と日本の音楽レコードビジネス」
 東芝EMIは1994年までは、EMIと東芝で50:50の資本比率イコールの関係であったわけですが、私が社長に就任したときにはすでに55:45になっていました。いってみれば私は、「外資が選んだ社長」だったわけです。そのような移り変わりのなかで私が感じたことも含めて、今日はお話をしたいと思っています。
東芝EMIは1994年までは、EMIと東芝で50:50の資本比率イコールの関係であったわけですが、私が社長に就任したときにはすでに55:45になっていました。いってみれば私は、「外資が選んだ社長」だったわけです。そのような移り変わりのなかで私が感じたことも含めて、今日はお話をしたいと思っています。
音楽ビジネスのなかには、いろいろなビジネスがあります。最近の例でいえばパチンコ店でいろいろな音楽が使われていたりして、あれも音楽ビジネスのひとつです。今日、私がお話しようと思っているのは、専門分野でもありました「音楽レコード会社がつくっているビジネス」についてです。世界のマーケットはたいへん大きなものですが、その中で日本のマーケットというのは、独自の発展を遂げてきた結果日本固有の特徴がたくさんあります。外資がもともとどういう形で日本に入ってきたのかというと、日本は洋楽音源の安定的な確保のために海外の会社とライセンス契約を結んできたのですが、このライセンスがだんだんパートナーシップに変わり、資本参加に変わったというのが今日の結果になっています。つまり、外資側が海外から日本へ入ってきたのではなくて、むしろ「洋楽」という音源の確保のために、日本側が取り入れてきたという形で発展をしてきました。日本マーケットには海外からみると不思議な、グローバル・スタンダードにははまらない例がいくつもあります。そういった特殊性や、海外と日本のレコード会社、グローバル・スタンダードとジャパニーズ・スタンダードの違いと、その経営の難しさをお話できればと思っています。
1. 世界の音楽レコードビジネス
(1)世界の音楽レコードマーケット
世界の音楽レコードマーケットの推移は、2004年の段階では売り上げが2兆3590億円、これが2005年には2兆2880億円。相対的な流れとしては、世界のマーケットも日本のマーケットと同様にだんだんシュリンクし、小さくなってきています。そんな世界のなかで日本の位置はどのあたりかといいますと、売り上げの結果を見てみますと、圧倒的にアメリカが世界第一位のマーケット(7,715億円)で、世界の34%を占めています。日本は2位で18%(4,091億円)です。ほかの国々と比べてみると、日本のマーケットはたいへん大きいということがわかると思います。それに続いて3位がUK(10%)、4位がドイツ(7%)、5位がフランス(6%)・・・となっています。世界で2桁のシェアを持っているのは上位3国だけです。以下20位までを見てみても、アジアでは日本だけですので、アジアのなかでは日本は突出した音楽マーケットを持っていることになります。
(2)レコード会社のマーケットシェア
世界のレコード産業は、4大メジャーと呼ばれる4つの企業(Sony/BMG、Universal、EMI、Warner)による寡占状態となっています。一方日本では市場の7割以上が邦楽です。この「邦楽マーケット」がきわめて大きな割合を形成しているため、日本ではメジャーといえどもそう簡単に寡占状態にはなりません(日本ではSonyとBMGが合併していないため5大メジャー)。
(3)世界の音楽配信マーケット
携帯の「着うた」、「着メロ」、また「i-tunes」などを経由して買う音楽配信は、レコード会社にとってこれからもっとも成長すると思われる分野です。しかし2005年の世界のデジタルセールスは、まだ約1,144億円程度です。音楽配信が伸びているとはいえども、まだまだCDやDVDなどの「パッケージ」を買ってくださる方が多いのが現状です。これも、日本はアメリカに次ぐ2位です。
ここで特徴的なのは、日本の配信マーケットは圧倒的に携帯経由だということです。アメリカは、PC経由のダウンロードが68%、携帯経由は32%ですが、それに比べて日本の音楽配信マーケットで、携帯経由の割合は実に91%にも昇ります。世界の音楽配信状況と比べてみてこれは著しい特徴です。しかし、携帯電話を使って着うた等をダウンロードするのは、10~20代の人がほとんどです。つまり、若い人が聴く音楽に強いレコード会社は携帯経由の売り上げがものすごく大きい。一方、若い人たちに向けた音楽の開発が遅れている会社では、携帯経由で入ってくるインカムが少ないということになります。要するに、日本ではPC経由の音楽配信が強くならないと、幅広く音楽を聴いてもらえないと言えるかもしれません。
ではどうして日本でこんなに携帯電話が流行って、携帯経由の音楽配信が発達してきたのかというと、それにはauさんをはじめとした携帯電話会社が若者をターゲットにした戦略をいち早く進めてきたという事実や、日本において携帯端末機能の向上が著しかったことが挙げられます。
(4)メジャーレーベルの日本進出の歩み
●ユニバーサルミュージック
1996年に親会社のMCAが傘下のユニバーサル映画に合わせて社名をユニヴァーサルと変更した際、音楽部門であるMCAレコードもユニヴァーサル・ミュージック・グループと改名した。1998年にポリグラムと合併したことによって世界最大のレコード会社となった。
外資100%。
●Sony/BMG
ソニーミュージックエンターテインメントとBMGが合併し、また双方の50%ずつの出資によって2004年8月に発足。この合弁はソニー・アメリカとベルテルスマンとの間のものであるのに対し、日本のソニーミュージックエンタテインメントは日本のソニー株式会社の100%子会社である事とBMG
JAPANの販売元が松下グループの日本ビクター(2007年中に松下グループから離脱予定)の子会社であるビクターエンタテインメントが関わっているため等の理由から日本における合併の動きは現時点では見られない。
●東芝EMI
1994年まではながらく東芝/EMIの50:50の資本比率であったが、同年10月にEMI55%、東芝45%に資本比率が変更されEMIが経営の主導権を握った。さらに、東芝は半導体事業や原子力事業と言った同社の主力事業への経営資源投入強化による関連事業見直しの一環として、保有する東芝EMIの全株を2007年度中に英EMIへの売却を決定し、その結果EMI100%の子会社となる予定。
●ワーナー・ミュージック・ジャパン
ワーナー・コミュニケーションズ(現タイム・ワーナー)傘下のワーナーブラザーズ、エレクトラ、アトランティックの3つのレコード会社の配給網として、主要レーベルの頭文字を取った“WEA”が設立されたことから、当初ワーナー・コミュニケーションズの音楽部門全体のこともWEAと呼んでいた。そしてタイム・ワーナーはAOLとの合併以降、財務体質改善のため2004年にワーナー・ミュージック・グループを投資家グループに売却した。従って、現在はワーナー・ミュージック・グループとタイム・ワーナーとの間に資本関係はない。日本では1970年に米国ワーナー・ブラザーズとパイオニア、渡辺プロダクションの合併で「ワーナーブラザーズパイオニア(→ワーナー・パイオニア)」が設立された。1990年にワーナーブラザーズグループの100%子会社となり、現在に至る。

(注)上は斉藤氏が講義で使用したグラフ「日本のマーケットシェア」
1994年、EMIが経営の主導権をにぎったちょうどそのころ、私はそのさなかにいたのですが、日本の会社である東芝はどちらかというと経営的にハード指向の傾向が強く、エンタテインメント産業に向いているかたちのシステムとは必ずしも言えませんでした。ところが外資になって、いきなりEMI流グローバル・スタンダードが流入してきたわけです。そのときの会社の混乱ぶりは想像にお任せしますが、明治維新のような時代を経験したのだろうと、今になって思います。
2. 日本の音楽レコードビジネス
(1)
日本の音楽マーケット推移
過去5年間の日本の音楽マーケットの売り上げ推移を見てみると、1998年をピークに年々、右肩下がりになってきています。その理由として挙げられるのが、ひとつめは音楽に向かう消費が弱くなったということ。ふたつめは違法ダウンロードの増加です。そして消費が弱くなった一番の理由が携帯電話の利用ですね。若い人たちの可処分所得(=お小遣いなど自由に使えるお金)が携帯電話に使われるようになると、それまで消費対象の上位だった音楽の順位がだんだん下がってきます。このように、可処分所得の使い道の分散が大きな理由のひとつにあるのではないかと考えられます。ピーク時の98年から比べると、今ではその6割になってしまいました。マーケットの規模が10年も経たないうちに4割も減るというのは、他の産業でもあまりない現象だと思います。そういう意味では、レコード会社が合理化・統一化を進めなければ生き残っていけないという時代をいかに過ごしてきたか、そして今も過ごしているかということを理解していただけると思います。
日本の音楽マーケットで「邦楽」と「洋楽」のシェアをみてみますと、最近は邦楽でミリオンを越すほどのヒット曲があまり生まれていないということからも、洋楽の割合が徐々に増えてきている状況になっています。しかし海外のマーケットを見てみますと、ドイツなんかは9割方が輸入音楽です。日本はこれだけ海外の音楽が入ってきていながらも、洋楽は依然として25%くらいしかマーケットの中でシェアし得ないというのは、日本の音楽マーケットの強さともいえますし、日本の邦楽と音楽ファンとの密着度の強さともいえるかもしれません。
(2)
ミリオンセラーの推移
「ミリオン」というのは100万枚のことです。92年からミリオンセラーはずっと伸び続けてきて、99年にはミリオンセラーのアルバムが30枚、シングルでも10枚も出ました。これがピークです。この年の前後も20枚以上のミリオンが毎年ありました。ところが2003年あたりから、どうもミリオンセラーが生まれにくくなってきています。ひとつのアルバムに集中して売り上げが伸びるという現象が起きにくくなってきています。とくにシングルがこれだけ減ってきているということは、レコード会社にとっては危機的ともいえるかもしれません。
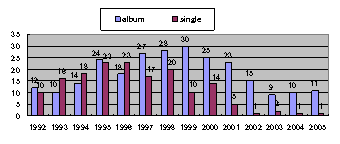 ※レ協HPより
※レ協HPより
(注)上のグラフは「ミリオンセラーの推移」。ミリオンセラーの著しい減少がわかる
(3)年代別のマーケット推移
年代別のマーケットシェアを見てみても、若年層(中学生~20代)の売り上げが減っているのが特徴的です。最近ではついに、30~40代の人たちの売り上げに抜かれてしまいました。50~60代の人たちについてはマーケットとしての潜在能力はあると思うのですが、どうしたら需要が高まるのか、なかなか決めてがありません。そこで年齢別で非訪店頻度(過去半年にCD店を一度も訪店していない)を調べてみると、その割合は高年齢ほど高く、50代では60%の人が一度も店に足を運んでいません。CD店に行かなくてもCDが手に入るようになるということを考えていくことが、こういった世代に向けての戦略のひとつなのだろうと思います。
(4)レンタル
レンタルは世界中でも日本にしかない制度です。ビデオのレンタルは海外にもありますが、CDレンタルは海外の人たちから見ると、きわめて信じがたいものであると思います。これは日本のレコード会社にとって無視できない制度です。日本レコード協会とレンタル商業組合は長い間交渉をしてきて、レコード会社は「レンタルの制度があるために私たちはビジネスの機会を失っている、世界に類を見ないこの制度に日本のレコード会社は苦しんでいるんだ」と主張、一方でレンタル側は「これはリーガルな制度だ」と主張してきました。協調もしてきましたが、どこかでせめぎあいをしてきたような関係が続いてきたのです。そして今朝(2007年4月23日現在)の新聞によると、レンタル側がレコード会社にトータルで10億円の追加使用料を払うことが発表されました。レコード会社にとっては悪い話ではないのですが、日本のレコード会社がレンタルによって失っている機会はこんなものではなく、もっと大きな額の被害を受けているというのがレコード会社の主張かもしれません。
全国のレンタル店の数は、1980年の時点では全国に34店しかありませんでした。1990年あたりのピーク時には6200件になりましたが、その後どんどん減少傾向が続き、3225件というのが直近のレンタル店の数です。町のレンタル店は大型店に吸収されたことで、店の数自体は少なくなりました。しかし店のスペースは減っていないのではないかと思っています。小型店が消えて大型店が増えたということに、レコード会社は決して胸をなでおろすことはできないんですね。レンタル店はむしろ大型化し、セルとレンタルの両方で、どんどんスペースを広げてきているのが現状です。
3.外資と日本の経営
日本は独特の音楽と経営のスタイルを持っていて、これが海外からは非常に不可解で理解しがたいものであると捉えられることがしばしばあります。最後にこの面から、ジャパニーズ・スタンダードとグローバル・スタンダードの相違点をお話したいと思います。
①アーティストの発掘と育成(投資と利益追求)
アーティストがライブ活動を重ねながら知名度を上げていくためには3~5年、インディーの時代から数えると5年以上かかるのが通常です。そのころから、レコード会社はアーティストに投資をしていくわけですが、この3~5年という期間は一方的な投資ですから、ほとんどリターンがない中でお金だけが出ていきます。レコードビジネスの最も大きな投資分野はこのアーティスト投資です。この投資と回収のバランスがとれている場合はいいのですが、必ずしもバランスがとれるとは限りません。ですから海外の株主に対して、この投資と回収のバランスがとれていないと説得が難しいんですね。一方でアーティストは、常に投資をしてあげて活動を続けていかないと成長できませんから、投資は際限なく、間断なく続きます。これが、一年ごとに利益を追求するという海外のスタイルからはなかなか理解されにくいんです。
②アーティスト契約(長期・短期)
海外のアーティストは、アルバム10枚とか15枚というたいへん長期な契約ですが、日本のスタンダードは2~3枚で、非常にショートタームな契約です。失敗したときには撤退が簡単ではありますが、成功したときにこのアーティストと契約を更新しようとしても、アーティストがノーといえば、ほかのレコード会社へ行ってしまうというリスクを常に抱えていることになります。ですから、海外からは「日本もロングタームの契約にすればいいじゃないか」といわれることがあります。しかし海外の契約というのはレコード会社に有利につくられていますので、例えばオプション付きでアルバム10枚で契約し、売れなければたちどころにレコード会社側から契約を切ることができます。成功したときは10枚出せて、失敗したときには1枚でお払い箱になるような契約です。
このような、海外の「ドライ」な契約ではなく、日本はもっと人間関係を重視した「ウェット」な関係が底辺にあるのではないかと思います。日本はアーティストたちと本当に親密なパートナーシップを築いてきましたので、なかなか海外のやりかたをそのまま取り入れるというふうにはいきません。たとえば、海外ではアーティストとの契約時には弁護士しか出てきませんが、日本では弁護士なんかが出てくるとかえって契約が難しくなる、あるいは難しい局面での交渉に入っていると見られがちです。信頼関係で解決していくというのは、日本の文化や風土の根底にあるんだと思います。
③従業員雇用形態(長期・短期)
最近は終身雇用制がくずれてきているとはいいますが、それでもやはり日本人は「この会社で一生やっていこう」と思う人が多い。これは、海外の雇用形態とは著しく違います。海外では能力がないと思われるとすぐに契約解除といわれてしまいますが、日本はそんなことは簡単にできないようなかたちになっています。
④原版権の保有
アーティストのアルバムをつくるとき、その制作したアルバムの権利がどこに帰属するか、ということが「原版権」です。海外はレコード会社が一方的に原版の保有権を持っています。日本は、マネージメントとの「共同原版」や、マネージメントが100%保有してレコード会社は供給されるだけというように、海外と日本は原版権の保有状況が異なります。日本では音楽配信の際にもアーティストに許諾をとったりしなければなりませんが、海外の場合はほとんどの権利をレコード会社が持っているので、そんな必要はありません。日本は昔から、持ちつ持たれつ、利益をシェアしましょうという考えでやってきましたし、それは今も底辺に脈々と流れているわけです。
⑤日本マーケットの特殊性との対立(アーティスト・マネージメント、流通ルール、etc)
日本の音楽レコードビジネスは戦前から独特な発達をしてきました。世界の中でも2番目の規模になるほどですから、それだけでたいへんなビジネスモデルができあがっています。海外の資本というのは、そのできあがっているところに入ってきたわけですから、グローバルと日本のスタンダードが対立するというのはやむを得ないことかもしれません。
流通ルールについても同じことが言えます。「再販売価格維持制度」というものがありますね。これは、全国どこで買っても価格が同じであるという制度です。現在この制度が認められているものは、新聞・雑誌・CDなどです。かつては薬や化粧品なんかもこの制度のなかに入っていましたが、公正取引委員会がこの制度は消費者のためにならないことを理由にどんどん対象を減らしてきているんですね。われわれレコード会社側としては、音楽は文化著作物ですから、日本の国民があまねく平等な機会を受ける権利があるという意味でも、再販制度をぜひ存続してほしいと思っています。この「再販制度」があるのは、世界で唯一日本だけです。そして「CDレンタル」。これも世界で日本だけにしかありません。
このように海外とは異なる、日本が独自に形成してきた商習慣を「ジャパニーズ・スタンダード」と呼んでよいかと思います。外資系のレコード会社などでは、つねに海外向けの「顔」と国内のマネージメントや従業員に向けた「顔」とで、ダブルフェイスにならざるを得ない場合があります。この折り合いをつけながらやっていくのが、私が経験してきた限りの、日本の外資系会社のトップの持つ苦労なのだと思います。
最後に、斉藤氏は受講生の質問に対し、ひとつひとつ丁寧に答えられた。
Q、これからの日本の音楽産業が発展するには、何が必要だと考えているか?
A、やはりメディアの問題がある。音楽にとって一番有効なメディアはテレビ。しかし音楽番組自体が減ってきている。これからは、高年齢層の人たちが見ても楽しめるような音楽番組、だからといって演歌のようなものだけではなく、幅広い層に聴いてもらえるような音楽番組を作っていくことが大切だと思う。私たちレコード会社側は、もう少し音楽のバラエティを持たせることが必要。主要なマーケットだけに絞るのではなくて、つねに幅広い層に向けて音楽を発信していくことも重要だと思う。
Q、携帯電話などのデジタル配信を使うと、いろんな人に興味を持ってもらえる?