

|
今回の講師は青山学院大学名誉教授(同大学前学長)であり、著作権の第一人者である半田正夫氏。本講座は著作権について学ぶことをテーマの1つとしているが、今回の講義では特に著作権に関するエッセンスを得ることができた。 著作権について学ぶとき、最初にひっかかるのが貸しレコードの問題だろう。CDをレンタルし、コピーする行為が違法かどうかを自信を持って説明できる人は少ない。著作物を複製するには、著作者の許諾が必要であり、レンタルCDのコピーは複製権の侵害であると考える人も多いだろう。これについて半田氏は「著作権には『私的使用のための複製』という例外規定があり、一定の条件を満たせばレンタルCDのコピーは法律に違反するものではない」と解説した。また、貸しレコード店の始まりから、レコード会社の運動により貸与権が作られたことなど、貸しレコードを貸与権にまつわる歴史も詳しく紹介した。 録音機器を購入する際、機器本来の価格に上乗せして、「私的録音補償金」というものを支払っていることを知っているだろうか。著作物の複製代金は直接利用者に請求するのが本来の姿だろうが、これは現実的な話ではない。そのため、録音機器購入の際に、私的録音補償金を上乗せしてメーカーに支払い、録音機器メーカーを通して著作者に複製代金を支払う仕組みができている。だがこの仕組みについて「クラシックなど著作権の切れているものを録音したり、英会話の勉強のため自分の発音をチェックするなど、著作権のかかるものを録音しない場合も録音代を支払うことになる」と指摘。そして「著作物を複製しない場合は返還請求もできるが、現実的でなく、実際に請求した人は誰もいない」と問題も含んでいるシステムであることを語った。 最後に著作権の将来について、「これからはネットワークでの著作物利用が増えてくる。ネットワーク型の配信は利用動向を把握できる。またパッケージ型の流通でも、パッケージにICチップを埋め込んで、利用動向を把握できるようになる。こうして利用動向が把握できるようになれば、水道やガスのように、エンドユーザーに対して著作者は権利を主張し、利用量によって課金するシステムになるのでは」と将来の著作権法の動向を予測した。 |
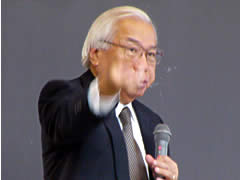 法律ができた時はアナログ時代だった。現在は完全にデジタル時代です。時代が大きく変わった以上は、権利者に対してもう少し目配せの聞いた法改正が必要ではないか。 (スターデジオ問題は)許諾権としての公衆送信権が認められていないことに起因する。  |
| Copyright(C) Ritsumeikan Univ. All reserved. |