

講義の冒頭、功刀教授はもず唱平氏を「東京以外に拠点を置く、唯一の専業作詞家」と紹介した。この紹介に多くの受講生は違和感を感じたに違いない。作詞家という職業の人間は日本中どこにでもいると思っていた人がほとんどだったろう。この詳細について、もず唱平氏は講義の中で次のように説明した。 現在、大衆音楽の送出はメディアなしには成り立たない状況になっている。大衆音楽はメディアと相まって発信しないといけないが、地方には発信機能がほとんどなく、東京に一元集中している。それを現す端的な事例として、著作権料の分配を地方別に見ると、関西対首都圏で1:350ぐらいである。関西にも首都圏に負けないぐらいの才能があるが、関西での活躍は現実的に不可能に近い。確かに一元集中することで効率は良くなるが、効率だけを追求すると、コンテンツの平準化が進み、面白みがなくなる。 次にもず唱平氏は知的財産に関する国家戦略について言及した。アメリカが法律を改定してディズニーの著作権をいつまでも開放しないことを例に出しながら、「アメリカは知的財産権を国家戦略の柱にしている。知的財産権は個人の権利であると同時に、国家の資源でもある」と知的財産が国家にとっても重要なものであり、それを守ることの必要性を示した。 現在、日本の音楽はアジア各国でも利用されているが、アジアから著作権料が入ってこないことが関係者の悩みの種となっている。これについてもず唱平氏は「アジアの音楽が欧米で売れていないので、アジア各国が欧米に著作権料を支払っても、著作権料をもらうことはほとんどない。そんな状況下では著作権料を払いたくないのがアジア各国の本音であり、私が担当大臣だったとしても著作権料は払わないだろう。だからアジアでの著作権に関する啓蒙活動は意味がない」と問題の構造を説明した。その上で「アジア各国での著作権料のマイナス分を、ODAで負担してはどうか」と斬新なアイデアを提案した。 |
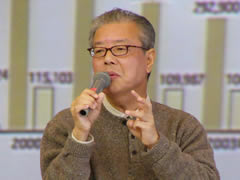 「多様性がつまっているのが大衆音楽。Hybridでいろんな音楽が混じっている」 「他との違いが文化における最初の玄関口である」 「地方の時代と言われているが、地方からの発信がほとんどなされていない」 「有形の資源はいずれ尽きるが、無形の資源は永遠に国を利する」 |
| Copyright(C) Ritsumeikan Univ. All reserved. |