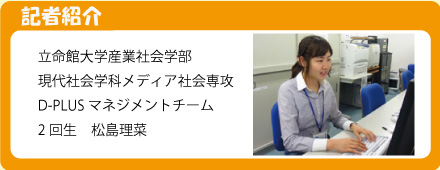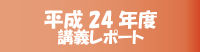
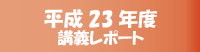
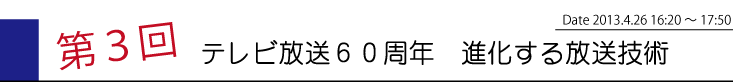
![]()
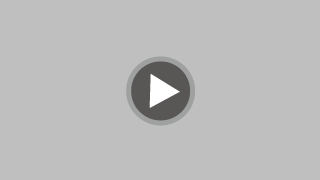
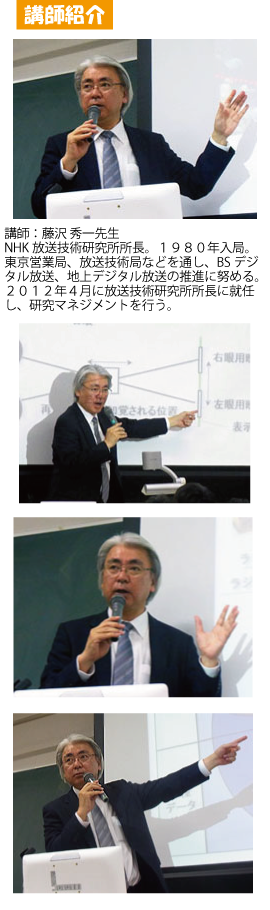 2013年。テレビ放送開始から今年で60年。白黒からカラーへ、アナログからデジタルへ。テレビは確実に進化をとげてきた。第3回のNHK講座ではそんなテレビ技術の向上のために日々研究しているNHK放送技術研究所より、所長の藤沢秀一さんをお迎えして、これまでの、そしてこれからの技術開発についてお話しいただいた。
2013年。テレビ放送開始から今年で60年。白黒からカラーへ、アナログからデジタルへ。テレビは確実に進化をとげてきた。第3回のNHK講座ではそんなテレビ技術の向上のために日々研究しているNHK放送技術研究所より、所長の藤沢秀一さんをお迎えして、これまでの、そしてこれからの技術開発についてお話しいただいた。
<講義概要>
「放送技術研究所の存在を知っている人!」そんな問いかけから講義は幕を開けた。藤沢さんは放送技術研究所、略して「技研」がどんなところかという紹介をしたあと、テレビ技術の歴史をさかのぼった。
そしてこれから実用化が考えられているという3つの研究開発について詳しくお話ししてくださった。
まず一つ目は、2013年、つまりまさに年内に実用化予定の「Hybridcast」である。これは、放送と通信の利点を最大限に活用した、身近で新しい放送サービスだ。テレビとタブレットを連携させ、クイズ番組などの視聴者参加型番組や、スポーツ中継番組などがより充実すると予想される。
二つ目は「SUPER Hi-VISION」である。ハイビジョンの16倍もの超高精細映像と22.2chのマルチチャンネル音響を合わせ持ち、スポーツなど動きの多い映像も今まで以上に楽しめる。昨年行われたロンドン五輪では、東京と福島のほか、イギリス、アメリカにおいてパブリックビューイングが行われ、成功を収めた。現在は2016年のリオデジャネイロ五輪までの一般家庭実用化を目指し、さらに研究が進んでいる。
そして三つ目は「空間像再生型立体テレビ」だ。専用メガネをかけることなく、より自然な3D映像が楽しめる。2030年頃実用化予定と少し先の話ではあるが、遠い未来の話ではない。
最後に、人にやさしい放送技術として、高齢者や障害者を含む全ての方々にむけたサービスを紹介した後、「若者のテレビ離れが叫ばれているが、今日の講義で興味を持ったところがあればうれしい。様々な形でテレビを楽しんでほしい」と講義を閉じた。
<感想>
地上デジタル放送が始まり、リモコンのdボタンを押すと多くのデータを取得できるようになった。私が以前驚いたのは、フィギュアスケートのデータ放送である。各選手の情報だけではなく、演技の予定プログラムがタイムラインになっていた。選手が現在どの演技をしていて次に何をするのか、また全プログラムのどのあたりなのかが、演技と連動してわかるというのがとても新鮮だった。アナウンサーが実況する技の名前も文字化されるとより頭に入りやすく、「地デジすごい!」とその日はいつもよりテレビに熱中した記憶がある。
しかし、技術はまだまだ進化していて、スポーツ観戦をはじめ、多くの番組が今とは違った形で楽しめるようになりそうだ。
私が一番面白いと思った新機能は、サッカーの試合中、選手にタグ付けができるというものである。自分がお気に入りの選手を登録すると試合中どこにいるのかすぐにわかる。さらに各選手の走行距離やボールキープ時間の算出ができるようになるという。これらに加え、複数設置してあるカメラの中から自分の見たい視点を選び、視聴することも可能になるそうだ。これらの機能は「Hybrid Cast」の応用形で、アプリができれば実用化可能ということだった。より詳しく知りたい人には細かな情報を。アナウンサーや解説者だけでは補えない、テレビでスポーツをより楽しく見る工夫がちりばめられている。
私自身、録画機能に頼りがちな今日この頃。リアルタイムだから面白い。そんな番組が増える予感を抱き、今から番組表をチェックする癖をつけなくてはと、「これからのテレビ」に楽しみが広がる講義だった。
NHK放送技術研究所
http://www.nhk.or.jp/strl/